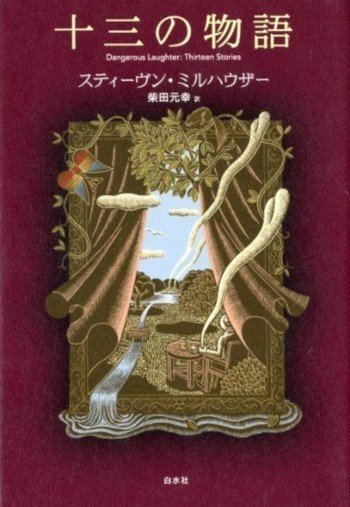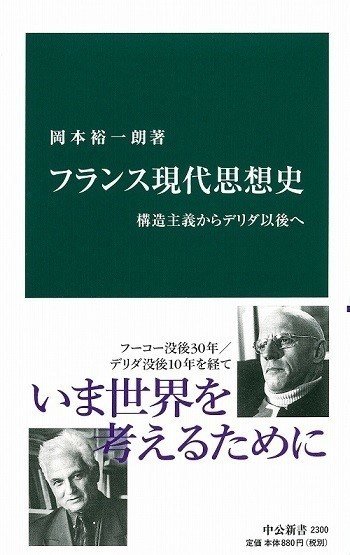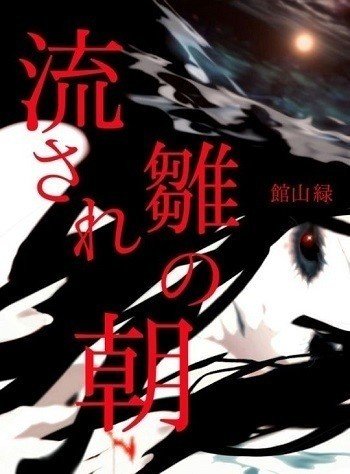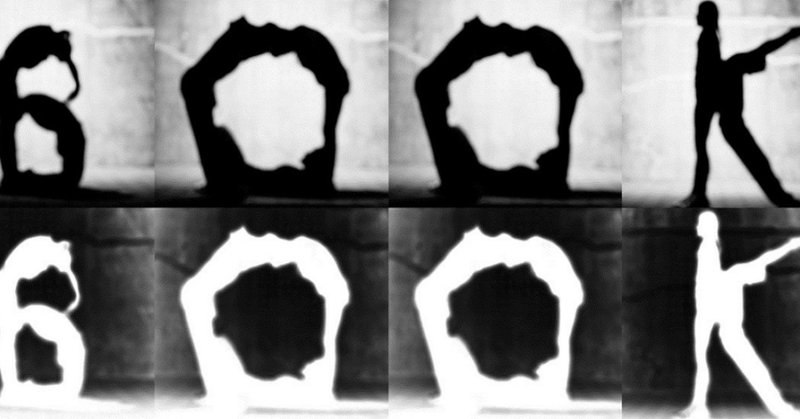
【読書備忘録】奪われた家/天国の扉から流され雛の朝まで
日本といえば自然災害と認識されそうですし、実際その見方は正鵠を射ていると痛感するこの頃。近畿地方を中心とする台風被害、北海道で発生した大地震。それらの続報を見聞しながらこの文章を書いています。複雑な気持ちですけれどもバタバタしたところで事態は好転しませんし、せめて暗闇に灯る一点の光になれることを願い、平常運転で日々をすごす所存です。東日本大震災では筆者の地元も少なからず影響を受けました。余震や飲食問題が心配される中、精神状態を保つのに本は大きな力になりました。それを思い起こしながらお送りします。
* * * * *
奪われた家/天国の扉 動物寓話集
*光文社古典新訳文庫(2018)
*フリオ・コルタサル(著)
*寺尾隆吉(訳)
光文社古典新訳文庫の近刊情報で知ったとき「もしかして『奪われた家』は『占拠された屋敷』ではないか」と期待した。曾祖父母から受け継がれてきた屋敷で暮らす兄妹の災難を描いた小説であり、生物かもわからない謎の物音に居場所を奪われていく過程が不気味で、岩波文庫『悪魔の涎/追い求める男』収録版を読了したときは恐怖で肌が粟立ったものだ。もっとも期待する最大の理由は新訳版『奪われた家』を読むことだけではなく、大元である短編小説集が翻訳されることにあった。本書『動物寓話集』には表題通り動物に焦点をあてた作品が複数おさめられている。けれどもフリオ・コルタサルがただもふもふの子を出演させて幕をおろすわけがない(それはそれで素敵な物語なのは言うまでもない)。『パリへ発った婦人宛ての手紙』では「時々小ウサギを吐き出す」現象で暗澹たる日常を、『偏頭痛』では架空生物マンクスピアの世話に奔走する奇妙な情景を表現したように、本を開けば底の見えない比喩の泉がたたえられている。期待を超える絶品。
十三の物語
*白水社(2018)
*スティーヴン・ミルハウザー(著)
*柴田元幸(訳)
短編小説の名手たるスティーヴン・ミルハウザー氏が世に送りだした魔術的な物語の箱、それが『十三の物語』に抱いた率直な感想だ。縦横無尽に作風を変貌させる引きだしの多さには舌を巻き、事物に立体感を与える細密な文体は眺めているだけで恍惚に至る。オープニングを飾る『猫と鼠』では細密を極めたアニメーションの台本のような描写を披露し、エンディングに選ばれた『ウェストオレンジの魔術師』では皮膚感覚を利用する機材の実験模様が被験者の日記で語られる。最初と最後を読み比べると作風の違いに驚かさせる。また随所に史実と虚構を混合した独自の表現・設定が織り交ぜられていて、ポストモダン小説のような遊び心を見出せる点も特色だろう。それだけ多彩なのにときおり別作品の影を垣間見せて(柴田元幸氏は呼応と絶妙な喩えをされている)虚を突いたりするのだからニクいことをする。寓意を仄めかし、それでいて生々しい構造。ミルハウザー作品は幻想文学として語られる節があるが、この頃はマジックリアリズムの一形態に属するのではないかと感じている。
冬将軍が来た夏
*白水社(2018)
*甘耀明(著)
*白水紀子(訳)
現代台湾文学を牽引する甘耀明氏の新作、それも二〇一七年に刊行されたばかりの長編小説が一年後に邦訳されたのは画期的であり、積極的に日本語訳を進めてくださった関係者の方々には感謝の言葉もない。というのも『神秘列車』以来甘耀明氏を追いかけていて、かの傑作『鬼殺し』は日本翻訳大賞にも推薦したほどなのだ。私事はさておき、主人公黃莉樺のレイプ被害告白から始まる本作品、冒頭の端的な言葉は重く、古代より繰り返されてきた暴力に言及するテーマだけに小生は息詰まることを覚悟してページをめくった。ところが予想に反して物語は祖母を中心とする老女の集団〈死道友〉の登場により、絶望に打ちひしがれる被害者に活力を与え、また読者にも笑い(ときには爆笑)をもたらし、裏組織とのアクションまで交えた超能動的な展開を見せたのである。随所に現実と超自然的な、マジカルな能力や現象を織り交ぜる著者の手法も生かされており、どこか夢見心地のままどんどん物語に引き込まれていく。個性の強い老女たち。彼女たちとの出会った夏は、忘れられない思い出になるだろう。
バロック協奏曲
*水声社(2017)
*アレホ・カルペンティエール(著)
*鼓直(訳)
アレホ・カルペンティエル(本書ではカルペンティエール表記)は小説家であると同時に音楽評論家でもあり、音楽を根幹とする小説をいくつも書き残している。本作『バロック協奏曲』も表題通りバロック音楽を主題としている。その構成は特殊だ。メキシコ生まれの主人と従者の物語と思えば、舞台は謝肉祭に移り変わり、アントニオ・ヴィヴァルディたちの音楽談義に展開する。架空人物と実在人物が混在するだけではなく、時系列を超越することもあるので、どこまで現実でどこまで幻想なのかわからなくなり演劇の舞台に突然引っ張りあげられたような心地になる。何しろヴィヴァルディがストラヴィンスキーを語る場面があるのだ。混乱せずにいられない。しかし、こうした時間を縦横無尽に操作する姿勢はカルペンティエルの特徴で、読了後に回顧すると目のあたりにしてきた奇妙な事象が緻密な楽曲であることに気付かされ、思わず感嘆の息を漏らすのである。余談ながら本書は発売当時に読んだ。端的に魅力を語る術を考えあぐねている内に一年もの歳月が経過してしまった。
物語 哲学の歴史 自分と世界を考えるために
*中公新書(2012)
*伊藤邦武(著)
中公新書の〈物語〉シリーズは哲学の分野にも焦点をあてている。本書は哲学の歴史を物語として概観しており、古くはソクラテスやプラトンやアリストテレスの古代ギリシア哲学、さらにデカルト登場に端を発する近代哲学の発展、プラグマティズムや言語哲学・分析哲学の勃興を経て、ペシミズムとニヒリズムの関係に論題は移行する。最後を飾るのはジル・ドゥルーズの「差異と反復」に関わる思想だ。おおまかな哲学の潮流をまとめるだけではなく、各人が提起する思想内容に踏み込み、後世の人物が踏襲あるいは批判するかたちで新たな思想を展開する変遷ぶりを詳細に記述している点にも好感を持てる。浅学な小生にはありがたい構成だった。もっとも彼らが提唱する哲学は非常に難解だけに一読二読で理解するのは難しく、今後も頻繁に本書にはお世話になると思われる。
フランス現代思想史 構造主義からデリダ以後へ
*中公新書(2015)
*岡本裕一朗(著)
構造主義と聞けば実存主義で一世を風靡したジャン=ポール・サルトルに挑戦状を叩き付けたクロード・レヴィ=ストロースを始め、ミシェル・フーコー、ジャック・ラカン、ロラン・バルト、ルイ・アルチュセールといった多分野の識者を想起する。しかし彼らの共通点は意外にもフェルディナン・ド・ソシュールを背景とする点のみであり、それぞれ提唱する思想体系は異なる。本書ではまず構造主義者の四銃士というレッテルを剥がす。またフランス現代思想を語る上で避けられぬポストモダニズムとアラン・ソーカルの歴史的悪戯、ときに批判対象にもなる難解なエクリチュール、そうした負の印象をあえてとりあげ、なるべく平易な言葉で解釈を試みる。あるときは誤解や曲解を正し、あるときは課題点と反省を示す構成はわかりやすいだけではなく、哲学(フランス現代思想)に対する真摯な姿勢がうかがえて好感を抱いた。哲学の仕事は概念を創造することであり、その概念を今までと違った風景を見る「思想のメガネ」に喩えた記述はよい意味で哲学の堅苦しいイメージをほぐしてくれる。
ロラン・バルト 言語を愛し恐れつづけた批評家
*中公新書(2015)
*石川美子(著)
一口にフランス現代思想と言っても分野はさまざまで、一人の名前をあげれば全体を網羅できるほど事情は単純ではない。当然だけれども分野に対する興味次第で各思想家に対する関心には差が生じる。自分の場合ロラン・バルトに関心を抱いている。ロラン・バルトは批評家ながら批評対象が非常に幅広く、古今東西の文化を論じることもあれば音楽や絵画に耽溺することもあり、記号論を唱えることもあれば愛を語ることもある。写真にこめられたテーマに言及することもある。彼が日本文化に親しんでいたのは有名だが、訪日を繰り返す内に俳句の技法にも影響されたという。一見一貫性に欠ける印象を持ちそうではある。しかしロラン・バルトのまなざしは常に原理の解明を楽しむ輝きに満ちており、あらゆる事物にテクストの要素を見出し、エクリチュールの可能性を模索している。本書はそうしたエクリチュールの意味・意義や「作者の死」を、その生涯を通して丁寧に解説する絶好の入門書だ。当人の人生と思想を強引にくっつけない書き方もリスペクト精神に富んでいて好感を持てた。
最初の物語
*水声社(2018)
*ジョアン・ギマランイス・ホーザ(著)
*高橋都彦(訳)
水声社〈ブラジル現代文学コレクション〉シリーズも四巻目。ジョアン・ギマランイス・ホーザはブラジル文学史に名を刻む大物だが、不勉強ゆえ近刊情報を見るまでまったく知らなかった。ただ、ホーザと本邦の関係を概観すると触れる機会に恵まれないのも仕方なさそうだ。何故ならホーザ作品は一九六〇~七〇年代、ラテンアメリカ文学ブームの最中に本書に収録されている『第三の川岸』『勇敢な船乗りの出発』、ほか『大いなる奥地』が翻訳された程度で、残念ながら日本に浸透しているとは言いがたい。それだけに二一編の短編小説からなる『最初の物語』が翻訳刊行されたのは偉業と言えるだろう。物語は多彩。しかし一人称にせよ三人称にせよ、言葉遣いや語順転倒を多用した言語的実験と語り部の口誦を融和させたような奇妙な文体、そして仄かな幻想の味は全編に生きている。非常に難解な文章をお書きになるようで訳者曰く「お手上げ」状態での翻訳作業だったそうだが、苦心をかさねてホーザの小説を日本語で読む機会を設けてくださった高橋郁彦氏には感謝しかない。
【実践】小説教室 伝える、揺さぶる基本メソッド
*河出書房新社(2018)
*根本昌夫(著)
小説に限定しても指南書の類は大量に刊行されており、物語論や修辞技法の教示に特化した学術的な本、小説家になるためのノウハウに特化した実践的な本、そうした書籍は選択に困るほど見かける。書名は伏せるが信憑性に欠けるあやしい本もある。勿論良書もたくさん刊行されている。読者の目的次第で理想的なテーマは変わるが、本書は文芸雑誌編集者や講師を務め、幾度も作家たちのデビューに立ち会ってきた根本昌夫氏が技術的な話と実用的な話を適度に織り交ぜながら、これから小説を書きたいという人や行き詰まりを感じている人にささやかな助言を与える内容であり、具体的に役立つ情報を与えてくれる。すでに前線で活躍されている小説家にはどれだけ効果があるかはわからないし、この一冊だけで道が開ける保証もない。けれども誰もが通る苦難、誰もが覚える苦悩を解きほぐして前向きにさせる本書の内容は、少なくとも自分のような半端者にとっては重宝である。挫けそうなときは頁をめくって(小生は電子書籍だからスライドだが)、根本氏に励ましていただこう。
流され雛の朝
*granat(2018)
*館山緑(著)
二〇〇五年に刊行された小説の電子書籍版であり、館山緑氏の電子書籍では『落下症候群』『壁の中のside-B』に続く三作目になる。大がかりな改稿を経て完全版に生まれ変わった『流され雛の朝』はサスペンスの緊張感と純粋であるが故の悲哀感を併せ持った青春物語で、端正な文体で描かれた情景が胸に染み入る。主役である万里は十二歳の誕生日に家族を惨殺される。彼女は助かるものの記憶を失い、家族の顔も思いだせなくなる。事件当時体に刻まれたと思われる逆三角形の印。その傷跡は彼女を失われた記憶と結び付けるように、悪夢を見るたび流血するという奇妙な現象を起こす。悪夢と流血、悪夢が意味するもの、こうした暗示的な事柄が不穏な空気を生みだしており、読み進めながら得体の知れない不安を覚えた。どう不安なのか、どうして不安になるのか、そうした読み手の心情を代弁するかのように万里は記憶を探り続けていく。切なくも美しい物語、その行方は淡い余韻を生む。館山氏ご自身があとがきで触れている通り人を選びそうな内容ではあるが、それだけに自分が作品に選ばれたことを嬉しく思う。
〈読書備忘録〉とは?
読書備忘録ではお気に入りの本をピックアップし、感想と紹介を兼ねて短評的な文章を記述しています。翻訳書籍・小説の割合が多いのは国内外を問わず良書を読みたいという小生の気持ち、物語が好きで自分自身も書いている小生の趣味嗜好が顔を覘かせているためです。読書家を自称できるほどの読書量ではありませんし、また、そうした肩書きにも興味はなく、とにかく「面白い本をたくさん読みたい」の一心で本探しの旅を続けています。その過程で出会った良書を少しでも広められたら、一人でも多くの人と共有できたら、という願いを込めて当マガジンを作成しました。
このマガジンは評論でも批評でもなく、ひたすら好きな書籍をあげていくというテーマで書いています。短評や推薦と称するのはおこがましいかも知れませんが一〇〇~五〇〇字を目安に紹介文を付記しています。何とも身勝手な書き方をしており恐縮。もしも当ノートで興味を覚えて紹介した書籍をご購入し、関係者の皆さまにお力添えできれば望外の喜びです。
お読みいただき、ありがとうございます。 今後も小説を始め、さまざまな読みものを公開します。もしもお気に召したらサポートしてくださると大変助かります。サポートとはいわゆる投げ銭で、アカウントをお持ちでなくてもできます。