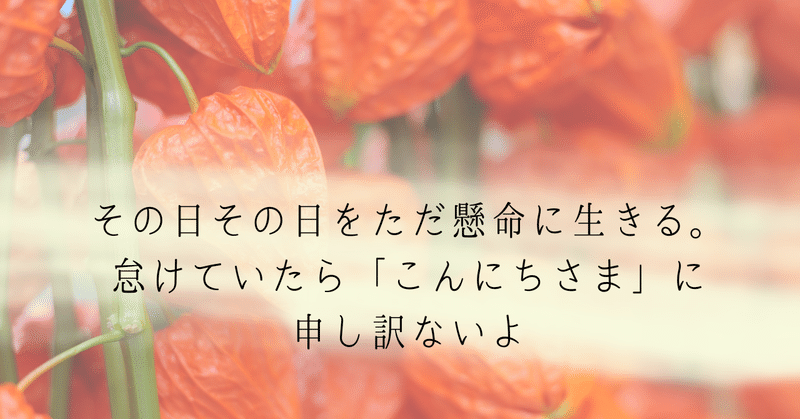
明治女に学ぶ美しい人生のたしなみ*第7回 寝るほど楽があるなかに、浮世のばかが起きて働く
加藤マツ
明治一一(一八七八)年群馬県生まれ。十歳より東京の伯母宅で女中奉公を始める。二四歳で狂言作者の加藤伝太郎と結婚。長男は四代目沢村国太郎、次男は俳優の加東大介、次女は沢村貞子。長門裕之、津川雅彦は孫にあたる役者一家。養女に出した長女は社会福祉運動家・民俗学者として活躍、ヘレンケラー賞を受賞した矢島せい子。昭和三八(一九六三)年、没。享年八五歳。
昔気質の下町女
加藤マツの名を知らずとも、名女優・沢村貞子の母と言われれば、誰もが「ああ、なるほど」と思われるのではないでしょうか。娘ばかりか、長男は歌舞伎役者から映画俳優に転身した沢村国太郎で、長門裕之と津川雅彦の父親。次男は黒澤明監督の『七人の侍』でスターの座を不動にした加東大輔と、マツは子や孫を芸能界に送り出した、役者一家のビッグマザーなのです。
とはいえ、マツ自身は決して表に出ることはありませんでした。超二枚目の狂言作者、傲慢不遜な夫には妻としてひたすら尽くし、子どもたちを大らかに育て上げた。まさに一家庭人に徹した人生だったのです。
「名も無い女性」としての存在を甘んじて受け入れ、淡々と一途に生きる。このように決して前に出ようとしないあり方は、明治女にありがちなことでした。それが「わきまえ」とされていたようです。現在の感覚ではなかなか理解しがたいものですが、マツはそれなり幸せで満足していました。もしかしたらマツは、「当たり前のことに感謝する」とか「小さな幸せを見つける」といったことを、まったく頭で考えることなく、ごく自然にできる女性だったのかもしれません。そのように、「自然とできる」「知らずに行っている」というところにこそ、力強さを感じます。どんな状況でもみずから幸せを掴み、周囲をも幸福にしていく人というのは、そうしたものなのかもしれません。
女の子は泣いちゃいけないんだよ
マツの父親は旗本、母親は御殿女中でした。両親は維新のどさくさに紛れて駆け落ちし、地方で土木建築業を始めたものの失敗。幼いながら家の貧窮を慮ってか、マツは十歳の時みずから進んで東京下谷の叔母宅へ奉公に出ました。体も丈夫で働きもののマツは奉公先でも重宝がられたようです。この頃の女中奉公というのは、預かる側は娘同然に扱うのが通例で、一人前にしたところで嫁がせることも大切な役割でした。マツもそのようにして叔母の家から伝太郎のもとへと嫁いで行ったのです。
ところが、江戸っ子で狂言作者の伝太郎は絵に描いたような遊び人、結婚後も浮気がいっこうにやみません。美人芸者が争うようにして訪ねてくるのをいいことに堂々と遊び放題なのです。芸者の方も調子に乗ってマツを小馬鹿にするようなことを言ってみたり…。今なら間違いなくモラルハラスメントですが、マツは何を言われようと相手にすることはありませんでした。一見、事なかれ主義のようですが、「絶対同じ土俵に立つものか」というマツなりの闘い方だったのかもしれません。その裏でどれほどの悔しさ哀しさをかみしめていたでしょう。
けれどマツは決して泣きませんでした。沢村貞子さんは、泣く度に「女の子は泣いてはいけないんだよ」と諭されたと回想しています。その理由を訊ねると、マツはこう言ったそうです。
「晩ご飯の仕度が遅れるからね」
泣いている暇があったら、せっせと体を動かそう。今すべきこと、しなきゃならないことをやってしまおう。
なんと素朴な対処法でしょうか。実際、あれやこれやと考えて涙に暮れていても悲しみは深まるばかりなのですから。そうやって一日中働いて、夜、休む時には決まってマツは言いました。
「寝るほど楽がない中に、浮世の馬鹿が起きて働く」
下町らしい言葉遊びですが、どこか切なさをも感じます。
「こんにちさま」のおかげ
マツが肝っ玉ぶりを発揮したのは、何といっても関東大震災の時です。辺り一面火の海と化した浅草の町を、まずは子ども達を先に逃し、自分はつづら一個を背負い、さらに腰を抜かして動けなくなった伝太郎を担ぎ、浅草寺の観音堂まで走りました。しかも、そこにも火の手が迫ってくるとみるや、マツは周囲の人を叱咤激励し、観音堂を守ろうと消火活動をしたのです。
「せっかく命拾いしたっていうのに、ここでのたれ死ぬわけにはいかないよ、だいたい観音様にだって申し訳がたたないじゃないか!」
そんな絶叫が聞こえてくるようです。マツはことあるごとに「生きていられるのは『こんにちさま』のおかげ。怠けていたら申し訳ない」とも言いました。「こんにちさま」は観音様や神仏など尊い存在のを指す言葉のようです。ゆえに火災から観音堂を守らなければ、「こんにちさまに申し訳がたたない」ということに他ならなかったのでしょう。
ここにマツの人生美学があるように思われます。「こんにちさま」に恥じない生き方をすることが、マツの人生を美しいものにし、ひいてはどんな状況でもみずから幸せを掴む力になっていたのではないでしょうか。
私たちも、何かひとつ大切なものを胸に抱きたいものですね。美学とは、時に心の拠りどころにもなるのですから。
(初出 月刊『清流』2019年7月号)
※著作権は著者にあります。無断での転載・引用をお控えください
みなさまからいただくサポートは、主に史料や文献の購入、史跡や人物の取材の際に大切に使わせていただき、素晴らしい日本の歴史と伝統の継承に尽力いたします。
