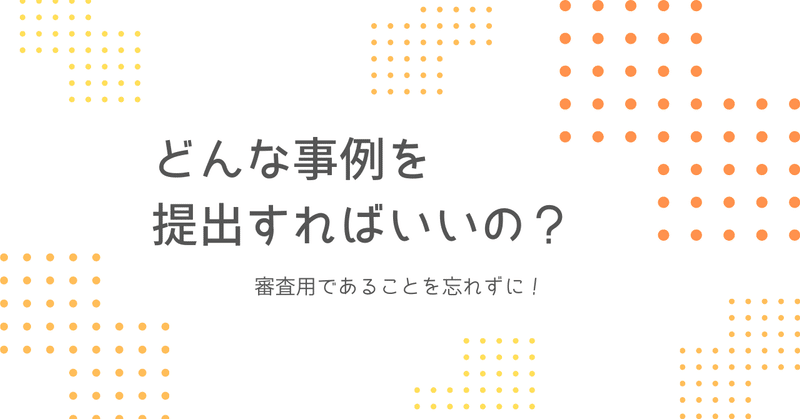
どんな事例を提出すればいいの?
APACCを受験する上で1番のハードルになるのが事例の蓄積だと思います。ここではどんな事例が審査に適しているのか、私の考えをご紹介します。
※あくまで主観です。合否の責任は負いかねます。
そもそも「事例」とは?
試験を受けるために事例を書き集めなきゃ・・・!そんな思考ループに陥っているなら要注意。なぜなら「集める」のではなく「集まる」ものだから。何度もトライ&エラーを繰り返しながら患者さんと接する中で自分の知識もスキルも上がってくる。その成果が事例という形になる。この流れを忘れないでほしいと思います。
実際、JASPOでも度々「ただ出せばいいわけじゃない」という趣旨の呼びかけが繰り返されており、2024年度には申請資格に下記内容が追記されました。
外来のがん患者に対して、薬剤師が科学的な根拠に基づき医師に提案・相談または患者に関わり、成果が得られた薬学的介入の10事例を提出するためには、がん患者を対象とした薬剤管理指導の一定数の経験に基づいた実績が必要となります。このため、2024年(令和6年)度より、実務経験として50症例以上を有し、これらのうち厳選した外来のがん患者の薬学的介入実績10事例を提出していただくこととします。
とりあえず集めた10例ではなく、多くの患者さんと接して経験を積んで、その中から審査に用いる事例を選んでくださいね、というメッセージだと私は理解しています。
必要なエッセンス
介入と言っても様々な内容がありますが、王道は「有害事象対応」です。ここを中心に候補にしていくのがよいと思います。
病態やレジメン全体を考慮したモニタリング
慣れないうちは「気になることないですか?」と漠然とした聞き取りで、患者さんがたまたま訴えてくれた症状にだけ介入していくこともあると思います。ですが、患者さんも副作用だと思っていない症状があったり、このくらいは我慢しなきゃ…と思っていることもあったりします。病態から生じやすい症状やレジメン全体の注意点をモニタリングし、サポートできる点を自分から見つけていきましょう。
患者さんからの具体的な聞き取り
「いつ」「どこが」「どのくらい・どんなふうに」「随伴症状は?」
例:下痢 ➡ いつ?何回くらい?便の性状は?腹痛や発熱は?
Grade評価や適切なアドバイスをする上でも絶対必要になる情報です。とくに時系列は後述する「化学療法の影響か」という判断にも重要なので、意識して聞き取りましょう(事例として記載する際には文字数と相談)。
化学療法の影響であるかどうかの考察
何でもケモの影響と思い込んでませんか?抗がん剤独特の症状(手足症候群など)であれば別ですが、悪心・便秘・下痢など他の理由でも起こりやすい症状に関しては、「本当にケモの影響?」という視点が重要です。
例:FOLFOX day10に嘔吐 ➡時系列的に他の要因があるのでは?
時系列や副作用発現頻度、患者さんの状態(元々便秘がちなど)なども踏まえて考察しましょう。
Grade評価
有害事象への介入は評価に基づいて行う必要があります。例えば、下痢に対してロペラミドを提案したとしても、その度合い(Grade)によっては休薬という判断も必要になることがあります。このとき、「軽微だからGrade1」「辛そうだからGrade2」のように主観で判断していないか注意してください。CTCAEの一覧表で項目を確認し、基準に沿って評価しましょう。
https://jcog.jp/assets/CTCAEv5J_20220901_v25_1.pdf
介入の根拠
何か提案するとき、何に基づいて提案したのかという根拠も大切です。経験則でやっていませんか?ということですね。化学療法に対する支持療法はだいぶ確立されていますので、ガイドラインでの位置づけや推奨度も今一度勉強しておくとよいでしょう。
介入後の経過
提案が採択されたのか。その結果、患者さんの問題点はどうなったのか。こうした結果も求められます。その後がわからないと「提案しっぱなし」ということで無責任な印象を与える可能性も…。何か支持療法が追加された際は途中で服薬フォローして、支持薬を適切に使えているか、それでコントロールできているか確認しておくとより良いですね。
Q&A
まずはJASPOから公式に出ている情報をHPで確認しましょう。
https://jaspo-oncology.org/file/858
以下はあくまで私の主観なので、非公式情報です。合否に責任は持てませんので、参考程度にご覧ください。
1つの事例に介入要素は複数必要?
JASPOのセミナーでも意見が分かれている印象を受けており、正式な決まりはないように思います。個人的には要素の数というよりも、自分がどのように考えてその介入を行ない、その結果どうなったのかという流れが見えることが重要だと感じており、実際に要素1つの事例もありましたが、合格できました。
薬局なので遺伝子変異情報とか分からない
正直、適応に関するものはわざわざ確認していません(そこ間違っていたら主治医変更が必要ですもん…)。患者さんには「ホルモンが影響するって言われました?」とか聞くことはあります。
確認する姿勢が重要だと言われていますが、事例を書くためだけに確認するのは本質が違う気がしています。その患者さんについてディスカッションする機会があれば一緒に聞いてしまえばいいと思いますが…。
例えば、イリノテカン使用時のUGT1A1のように、その情報があったほうがより適切な対応ができるなら全例において確認していくべきです。それでも個人情報云々で教えてもらえないこともあるので、それはそのように面接で伝えれば記載できていなくても構わないと考えています。
前治療が分からない
「事例を作成する」という意味では分からなくても何とかなります。ですが、前治療の影響も考慮した上で副作用モニタリングは行なうべきなので、ここは情報収集に努めたほうがよいと思います。
医療機関の専門薬剤師の方にご挨拶に伺い、患者さんをサポートするために教えてほしい旨をお伝えしてみる、というのも良いかもしれません。
処方提案した内容が通らなかった
個人的には悩ましいなぁと思います。提案が通らなかった理由が分からないとそもそも医師に自分の提案が伝わっているか微妙ですし、自分の考察・判断に足らなかった点があって提案とは異なる内容になったのであれば、事例としては提出せずに次の糧にしたいなと思います。
ただ、提案した用量より低用量でスタートになった場合は、副作用を考慮してなど理由が分かると思うので、それは医師の考えを一緒に記載すれば問題ないかなと思っています。
例:オランザピン5mgで提案 ➡ 傾眠を考慮して2.5mgスタートになった
処方提案ではない介入でもよい?
内容によると感じています。例えば・・・
・検査の依頼
ただの検査オーダー漏れに対する追加提案であれば専門性というより薬剤師の通常業務かなと思うので、これだけの介入で1事例にするのは厳しいと思います(文字数も足りないと思います)。
一方、何か有害事象を疑って、鑑別のために検査を依頼するのであれば上記よりは深い介入だと思いますし、その検査の結果、何か見つかって対応が
なされ、改善に繋がったのであれば全然OKだと思います。
・服薬指導
こういう指導をしたというだけでは不十分だと思いますが、例えば支持薬を適切に使用できていない患者さんに具体的に指導した結果、改善に繋がったという内容であれば補欠候補にしてもいいのかなと思います。ただ、指導内容だけの事例10例は厳しいと思います。
介入したけど改善に繋がらなかった
改善例であることが必須ではない旨は聞いたことがありますので、有害事象評価・介入自体が適切であれば評価してもらえるのだと思いますが、10例中1~2個程度に留めておいたほうが印象は良い気がします。
ただ、末梢神経障害のように改善が難しいものもありますので、「悪化防止」という視点で精査してもよいと思います。
まとめ
10例集めるのは大変ですが、審査という目線で見ると「たった10例」とも言えます。そのため、手当たり次第の10例ではなく、良いものにどんどん差し替えていく姿勢が大切ではないでしょうか。
珍しい介入やファインプレーである必要はありません。スタンダードな対応で十分ですので、介入を重ねてレベルアップしていきましょう!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
