
Reviews(The Nation/2016)
SPECIAL TO THE NATION May 5, 2016 1:00 am
No easy way out
An absurdist Japanese performance is both enjoyable and comprehensible
THANKS TO ITS welcome diversity in programming, Thong Lor Art Space is a great place to visit on a regular basis. Just like the vibe from the restaurants, bars and nightspots for which this neighbourhood is famous, TLAS keeps its lights on, its curtains up and its vibrancy throbbing all year round.
Last month, Thong Lor Art Space hosted “Suk-ka-sak-ka-raj”, an interdisciplinary performance in which cellist Yui Cello shared the stage with an actress/illustration drawer, a ghost writer, a physical theatre artist, a contemporary dancer, independent musicians, a sound designer and a documentary filmmaker. Although they didn’t have time to work across fields, the fact that artists from so many disciplines could be seen in one work was a rare treat in this country.
Now, it’s the contemporary Japanese performance “1969: A Space Odyssey? Oddity!” by Kaimaku Pennant Race (KPR), making its Southeast Asian premiere. From the title, which was drawn from Stanley Kubrick’s masterpiece “2001: A Space Odyssey” and David Bowie’s song “Space Oddity” released in 1969, and the fact that the show was at Avignon OFF Festival, audience members were expecting either a dance performance or non-verbal comedy with plenty of music. We were all caught by surprise.
Three performers in white unitards, namely Takuro Takasaki, GK Masayuki and Yuri Morita occupied the stage while playwright and director Yu Murai, in street clothes and with a globe attached to his hat, remained downstage watching in front of his sound effects control board. Occasionally during the show, Murai poured milk from a jar and drank it from his glass. Towards the end we could see a spaceman miniature at the bottom of the jar.
Among many scenes dwelling on absurd situations, there was one in which two performers argued about a new pair and a worn-out pair of white shoes. In another – compulsory audience participation is enforced by keeping the full house lights on – all three of them, wanting to cross the border, walked into the audience stand and asked us, in Thai and English, which direction was south. We pointed them in various directions.
The show was heavily text-based and yet, thanks to the English and Thai surtitles on the four monitors placed on four corners of the stage and visible to all in the audience stand at all times, we could all understand what they were talking about. I noticed that Japanese audience members or Japanese-speaking Thais laughed more than us, so this was perhaps another case of slightly lost in translation.
The whole experience brought back a fond memory of watching Samuel Beckett’s absurdist drama masterpiece “Waiting for Godot”, which, brought me many more smiles and laughter when I was in my early 30s than it did when I was in my late teens.
“1969: A Space Odyssey? Oddity!” pleasantly reminded me that I was born and raised in the space exploration era, when there was neither Internet nor smartphones. I recalled how excited I was to watch “Star Wars” and “Star Trek” at the cinema. I also remember how my Grade 7 classmates were impressed with my class presentation on the space shuttle, using a toy my cousin brother brought for me from the US.
But I don’t think the purpose of this show was to remind me that I am now middle-aged.
In fact, while in no way political, it made me realise that in much the same way as space exploration during the past half century hasn’t progressed very much and man’s landing on the moon remains the most exciting moment, our country has been led by one military prime minister after another, with several coups in-between. Of course, we have Internet and smartphones now, but our democracy hasn’t progressed that much. Could the new constitution be a way out or would it be 1932 eternally?
MORE SHOWS
– “1969: A Space Odyssey? Oddity!” by Kaimaku Pennant Race runs until Sunday at Thong Lor Art Space, a five-minute walk from BTS: Thong Lor. Shows are at 7.30 nightly with a 3pm matinee on Sunday. It’s in Japanese with Thai and English surtitles. Tickets are Bt500 (Bt450 in advance, Bt350 for students). Call (095) 924 4555 or go to Line ID “@lvj7157z”.
– June will have Pattarasuda Anuman Rajadhon’s staging of Josh Ginsburg’s “Stick Figures”, with Thai- and English-speaking casts alternating. For more details, Facebook.com/ThongLorArtSpace.
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2016年05月05日
簡単な出口はなし
日本から来た無条理系のパフォーマンスは、楽しく、そしてちゃんと理解できる内容だ。
そのプログラミングの間口の広さのおかげで、トン・ロー・アート・スペースは、常連として訪れたい、素晴らしい場所だ。
このエリアを有名にしている、多くのレストランやバーやナイトスポットのにぎわい同様、TLASにはいつも灯が点り、カーテンが上がり、年間を通じて活動が途絶えることがない。
先月、トン・ロー・アート・スペースは『サッ・カ・サッ・カ・ラージ』というクロス・ジャンル的なパフォーマンスを迎えたが、チェリストのユイ・チェロの共演者は、女優/イラストレイションの描き手、ゴースト・ライター、フィジカル・シアターのアーティスト、コンテンポラリーのダンサー、インディーズ系のミュージシャンたち、サウンド・ディザイナー、ドキュメンタリー映画の作家だった。
フィールドを越えて共同作業をするだけの時間はなかったが、これほどさまざまなジャンルのアーティストが一つの作品で見られるだけでも、この国では珍しいもてなしだった。
さていよいよ、コンテンポラリーな日本からのパフォーマンス、『1969: A Space Odysey? Oddity!!』、開幕ペナントレース(KPR)の東南アジア・デビュー戦だ。
タイトルは、スタンリー・キュブリックの傑作『2001年 宇宙の旅』とデイヴィッド・ボウイーの歌『スペイス・オディティ』(共に1969年リリース)から取られたものだし、アヴィニョン・オフ演劇祭で上演されたことから、観客は、ダンス・パフォーマンスか、非言語コメディーの音楽たっぷりのものを予想しただろう。
僕たちはみんなびっくりさせられた。
3人のパフォーマーは白の全身タイツ。名前は高崎拓郎、GK.Masayuki、森田祐吏。彼らが舞台を占め、作家で演出家の村井雄は、普段着のまま、帽子に地球をつけて、舞台前寄り、音響効果のコントロール・ボードを前に見守り続ける。
開演中、時々、村井はジャーから牛乳をついで、グラスから飲んだ。
終りに近づくと、ジャーの底に、ミニチュアの宇宙飛行士が見えてきた。
無条理な設定のたくさんのシーンの中に、二人のパフォーマーが、白い靴の新品とボロボロをめぐって議論する場面がある。
別の場では、客席の照明を明るくして、即興的に観客参加を強要する場面もあり、3人は揃って越境を望んで、観客席に乗り込み、タイ語と英語で、南はどっちだ、と僕たちに訊ねまくった。
僕たちは、いろいろな方向を指さした。
ショウはがっちりとテキストに基づいたものだったが、英語とタイ語の字幕が、舞台の四隅に置かれて、どの席からも見えるように配慮されたモニターに写し出されるので、彼らが何を話しているか、すべて理解できる。
日本人や、日本語のわかるタイ人の観客は、僕たちよりよく笑っていたから、もしかしたら、この舞台も、軽く“Lost in Translation”だったのかも知れない。
この観劇体験全体が、サミュール・ベケットの無条理演劇の傑作『ゴドーを待ちながら』を見た時の愉しい記憶を甦らせてくれるものだが、それは、30代はじめに見た際、10代の終りに見た時より、はるかにたくさんの微笑みと笑いを僕にもたらした。
『1969:A Space Odyssey? Oddity!』は、自分が宇宙探検時代に生れ育ったことを愉しく思い出させてくれた、インターネットもスマートフォンもなかった頃を。
そして思い出した、『スター・ウォーズ』や『スター・トレック』を映画館で見ては興奮したことを。
さらに思い出した、7年生の時、クラスメイトたちがとても感心してくれたことを、従兄弟のアメリカ土産の玩具を駆使した、僕のスペイス・シャトルについての研究発表に。
しかし、このショウの目的は、僕に自分は既に中年だと思い出させることではないだろう。
実は、全く政治色がないにも関わらず、このショウは気づかせてくれた、過去半世紀の宇宙開発はあまり進んでおらず、人類初の月面着陸にまさる感動がないように、僕たちの国は、いくつかのクーデターを挟みながら、次々と、一人の軍人宰相たちに導かれていることを。
もちろん、今はインターネットやスマートフォンもあるが、僕たちの国のデモクラシーは大して進歩していないのだ。新しい憲法は出口となってくれるのか、それともここは永遠に1932年のまま出口なしなのか。
The Nation by パウィット・マハサリナンド
(訳:青井陽治)
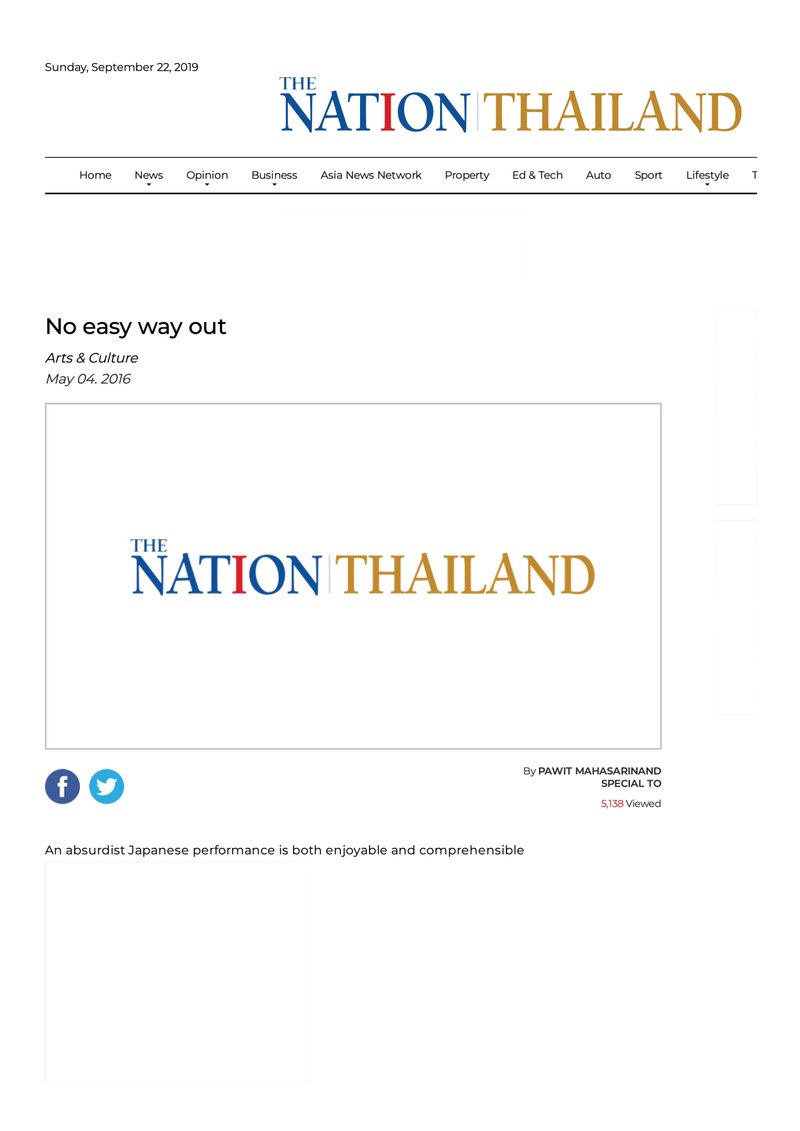

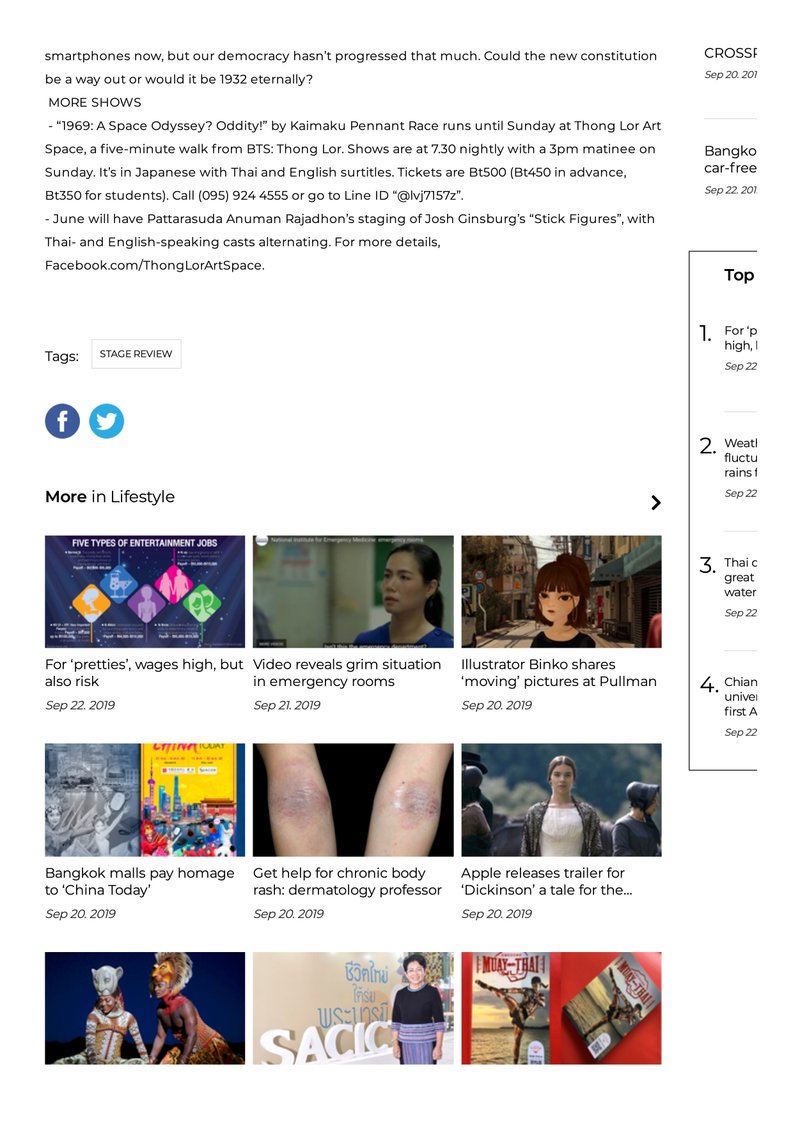
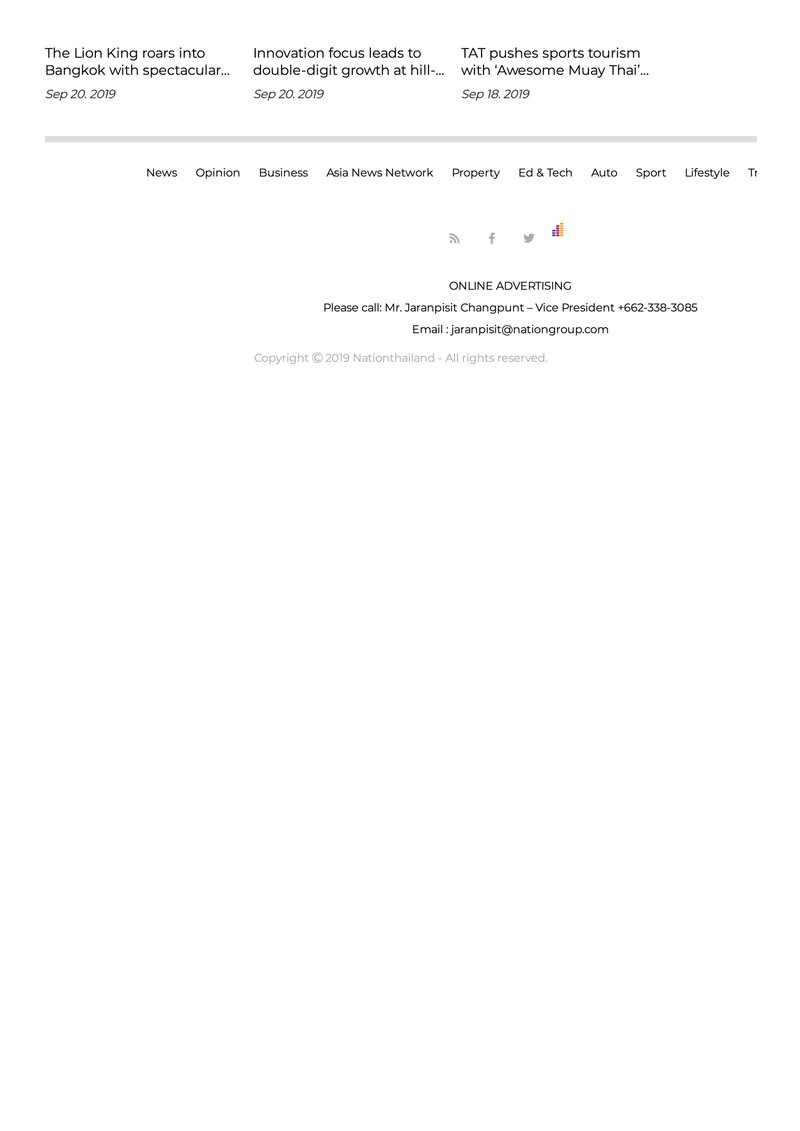
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
