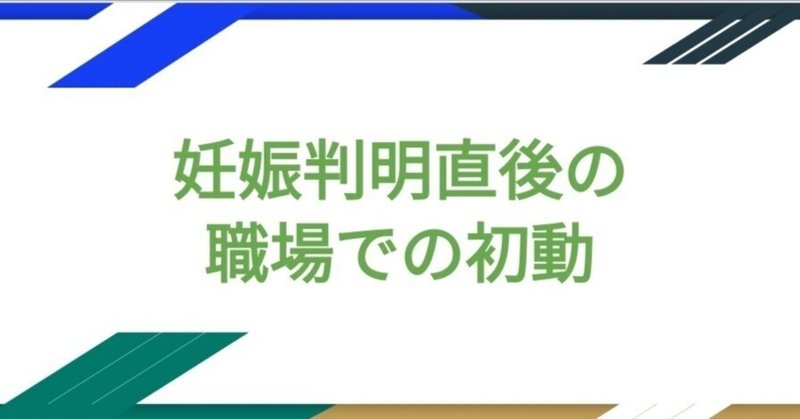
妊娠判明直後の職場での初動
六ヶ月の育休を取得するにあたり、妊娠判明時から周囲との情報共有には気を配った経験から、男性諸君のケースで書きます。あくまでの筆者の経験と見解に依るものです。ご自身や周囲の状況に合わせてお考えください。
(会社勤めのケースを多分に出しています)
とにかく早期に上長には伝える
結論はこれになります。
人により異なることは承知の上ですが、持論はとにかく早期に上長に伝える。ことです。
どのくらい早期かと言うと、妊娠検査薬の反応程度では流石に確証がないので、最初に産婦人科を受診し、妊娠の太鼓判を貰った直後が良いと考えます。
良く「安定期に入ったら」とか、「流産の可能性があるので」とか、色々なご意見があることは承知していますが、個人的には遅すぎると考えています。
とにかく早期に上長に伝える。ことです。
妊娠確定当日から育児は始まっています。 妊娠初期段階に仕事の融通を着せせる必要がある理由を以下に述べます。
妊娠初期段階 は 母子ともに不安定
妊娠初期段階とは

妊娠四ヶ月までを初期段階と言います。この初期段階で 悪名高き 悪阻 は発生します。(つわりがない人もいます)
また、流産の85.7% は妊娠初期 に分かったという厚生労働省の調査もあります。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000864366.pdf
あまりネガティブなことをつらつらと書いても仕方がありませんが、妊娠初期は 母子ともに不安定なので、父親の関与と周囲のサポートが必要な最初の山場と言えます。
早期に伝えることのメリット
様々なプロジェクトと同じで、早期の情報共有と体制の構築はリスクマネージメントの基本です。
妊娠初期に考えうる主なカウンターアクションは以下のとおりです。
妻の 悪阻がひどい場合の看護
上の子供の育児
妻や家族のメンタルケア
自分自身が心身疲弊しないような ワーク・ライフ・バランス
これらを実現するためには、周囲の理解とサポートが欠かせません。
周囲に妊娠のことを伝えておかないと、後々独りで抱え込むことになり大変なのは 自分自身そして家族です。
とにかく早期に周囲には妊娠を伝えておきましょう。
周囲への伝え方
こちらの生活・仕事環境が変わるので、仕事仲間や家族や友人などには伝えておく必要があると思います。
ここでも下手に知らせて何かがあった時に、、、と思い悩むこともあるかと思います。その思いは決して間違いではないので、パートナーと良く話し合いましょう。
その際には 育休を含め家庭への比重を高めるためには、仕事側の理解と支援が必要であることをパートナーに理解してもらえると良いですが、あくまでも個々人の考えを尊重してください。
上長への伝え方
特段のテクニックなどは必要ないと思いますが、普段の関係性などから少々の工夫は必要になるかもしれません。
会社勤めの場合、いずれにせよ公の手続きは必要になるので、まずは 簡単に立ち話やチャットする程度で良いと思います。
メールや1on1 では少しハードルが高くなるのと、堅苦しくなるので最初の一方では好ましくないかもしれません。
また、SNS などでのお知らせは 個人の判断で結構ですが、上長など関係者には確実に直接伝えましょう。「聞いてないよ~」は避けなければなりません。
とにかく早期に上長には妊娠を伝えておきましょう。
上長へ伝える内容
要点としては以下の内容になると思います。
妊娠したこと
ざっくりとした出産予定
育休を取得する予定があること
今後 家庭の方の比重が増えるであろうこと
これらをひとまず伝えておくことで、後々具体的な話を進めるための言質になります。
一度 口頭で伝えた場合には、後ほどメールなどで証跡を残しておくと齟齬もなく、スムーズに進みます。そして、あくまでも予定は予定です。
育休を取る予定については、確実に伝えて、期間もしっかりと伝える必要があります。上長からすんなりと了承が出てこないケースもあるかもしれませんが、まずはこちらの要求を宣言しないことには始まりません。
とにかく早期に上長には妊娠を伝えておきましょう。
人事部にコンタクトする
上長に伝えたあとは人事部に連絡をします。
人事部への連絡も一刻も早くした方が良いです。
普段、妊娠・出産・育児 関係の社内制度を調べることも知ることもないでしょう。当たり前です、関係ない話ですから。しかし、妊娠確定後は一変して関係おおありになるので、まずは人事部に確認します。
社内の制度については、上長や同僚の情報は話半分で聞いておきます。内容が不正確であったり、古かったりする可能性があるからです。
社内の制度について目を皿のようにして自分で確認することも大切です。特に以下の項目は良く確認しないといけません。
育児休業についての必要書類とアクション
有給や特別休暇の制度内容と残日数
有給は年度跨ぎなど要注意
特別休暇は 出産前も介護休暇など使用できるので要確認
社内の給付金
補助金やお祝い金
労働組合に入っている場合は組合からのお祝い金
社会保険の被扶養の手続き
これ以外にも色々ありますが、とにかく制度を理解し利用することが育休の第二歩目になります。
最後のまとめ
家庭外への共有タイミングと対象はパートナーとしっかり確認する。
会社員の場合、上長と人事部には早めに共有する。
社内の制度を正確に理解し、利用する。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
