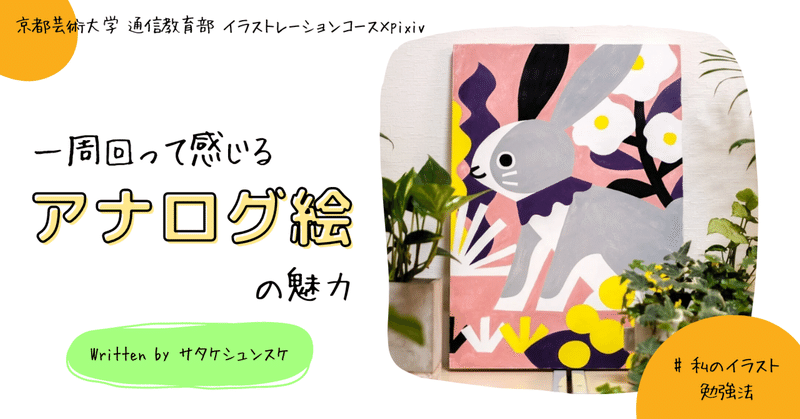
一周回って感じるアナログ絵の魅力
KUAイラストアドベントカレンダー、12月2日はイラストレーターのサタケシュンスケ先生から『一周回って感じるアナログ絵の魅力』です!
こんにちは、イラストレーターのサタケシュンスケ(@satakeshunsuke)です。この記事では、アナログ制作で絵を描くことについて、その魅力や考え方などを主観たっぷりに語ります。
もともとは非デジタル絵描きだった私
今でこそ、液晶ダブレットやiPadといったデジタルツールに囲まれ、Adobe Illustrator や Adobe Fresco をこよなく愛する、デジタルツール大好き絵描きな私ですが、じつは絵描きとして駆け出しだった頃はアナログ一辺倒な人間でした。
当時はまだ今のようにSNSなども無く、作品を人に見てもらうには展覧会やイベントなどでアピールするのが主流。必然的にアナログ作品を作って飾る必要があったわけです。

そんなアナログ人間だった私でしたが、生業にしていたグラフィックデザインの仕事を通してデジタルスキルを身に着けていきます。PhotoshopやIllustratorの基本的な使い方はこの頃に習得しました。
イラストに限らず、世の中のいろいろなことが急速にデジタル化されていく中で、私もその流れに身を任せ、気がつけばアナログ・デジタル両方で絵を描くようになりました。
そんなふうに両方を経験してきた私が、今あらためて考えるアナログ制作の魅力や気付きとは。
生産性を度外視するからこその価値
私はアナログとデジタルどちらも大好きですが、目的によって使い分けています。クライアントワークはほぼ100%デジタルで仕上げていますが、展覧会などではアナログ作品をメインで展示することもあります。
前者は調整・修正に対応しやすい効率の良さや、管理のしやすさからデジタルの恩恵が大きいことが理由ですが、後者にそれは望めません。データとしての扱いやすさがなく、つまりアナログ制作は生産性を度外視した方法とも言えるかもしれません。

描き手にとっては「効率・生産性が悪い=手間や時間がかかる」という、一見デメリットしかない面が、じつは絵を見る側にとって「それこそがありがたい」と思われていることがあります。
デジタルを否定するわけではありません。が、やはりアナログ作品では作者がかけた時間や労力が比較的目に見えて伝わりやすいことがあると思います。
やり直しの効かない世界というのはなかなかにシビアなもので、例えば一度完成させた作品を見て、なんだか気になる部分があれば、イチから描き直すといったこともよくあります。

絵の具を混色してつくった色は、二度と全く同じものはつくれませんし、出来上がった作品も年月が経つにつれて見た目に変化が現れるかもしれません。物理的に破損、紛失、盗難される可能性もあります。
デジタルデータと比べてなんと脆い存在なのでしょうか。しかし、だからこそ尊いのです。そばに置いて大切にしようと思うのです。これは(人を含めた)生き物に対する考え方に近いかもしれません。
作者が確かにそこにいたのだという残像が尊い
「そもそもデジタルとアナログを比べることに無理がある」というご意見もあるでしょう。おっしゃるとおりです。ではもう少しわかりやすい例を挙げてみましょう。
全く同じデジタルのプリント作品が2点あります。一方は作者の直筆のサイン入り、もう一方はそれがありません。さて、どちらにありがたみを感じるでしょうか?多くの人はサイン入りを選ぶのではないでしょうか。

これは作品そのものとはまた別の魅力――作者が確かにこの作品に触れ、息吹を吹き込んだ何よりの証明になるからではないでしょうか。それをなんと呼べばいいのか、うまい言葉が思い浮かばないのですが ”残像” とでも言いましょうか。
憧れの作者のアナログ作品を直に目にして、その残像を、唯一無二な存在感を浴びて、この上ないありがたみを感じます。
そうそう。仕上がりはデジタルでも、ラフやアイデアスケッチは紙に手描きで残すという方もいらっしゃるかと思います。サインと同じく、これもまたアナログならではの良さを感じられるものです。

デジタルが当たり前の時代だからこそ見直されるアナログ
世はまさにデジタルネイティブ時代。アナログ制作を全く通らず絵描きになっていく人も多いと聞きます。これはひと昔前までとは全く違う状況です。そもそもアナログに触れている人が減っているのです。
そうして図らずも希少な存在になっていく、アナログ絵描き。アナログ画材を使いこなせるだけでも、すでに優位性があるという考え方もできます。
ここ最近はNFT ARTやAIなど、デジタル新技術の話題に事欠かないイラスト業界。本当の価値はどこにあるのか?という問いに対して、見つめ直す時期が来ているのかもしれません。
アナログ制作はその時代の流れ、肥大化する競争などから一歩距離を置き、自分のペースで制作し、自分自身で価値の創造ができるといった点で一線を画しています。
ちなみに私も、デジタルツールを使ってもなお、アナログ感のある表現を追求しています。どこかで原点回帰をしようとしているのかもしれませんね。


デジタル VS アナログではない、共存こそが最高
いろいろ思うことを書き連ねてきましたが、こうしてみるとアナログ至上主義のように思われるかもしれません。ですが、決してそうではありません。
デジタルとアナログ、双方に出来ること、担う役割、持つ可能性には違いがあります。どちらか一方に絞るという選択は良くないです。
アナログでしか生み出せない表現もあれば、もちろんその反対もあります。
どちらの長所も活かしつつ、補い合える関係、共存こそが最高のかたちだと考えています。絵を描くという意味ではどちらも同じ。難しくはないはずです。
デジタルはあくまでひとつのツール、鉛筆や絵の具と同じく画材の一つだと、私は考えています。仕上げに使うこともあれば、下描きとして使うこともあります。そうした意味ではアナログ・デジタルの2つに垣根はありません。

まとめ
以上、アナログ制作について、いろいろと思うことを書きました。あくまで展覧会などを多く開催してきた私の場合の話なので、この記事の内容が皆様にそのまま当てはまらないこともあるかと思います。
最後に、デジタル制作をメインにしている方に向けて。
デジタル環境が充実してきたことで、絵を描くハードルが大きく下がったことは大変喜ばしいことです。ただそのデジタルツールの中には、これまで長い歴史を歩んできたアナログ手法や表現がベースになって成り立っている部分が多くあります。
その原点に触れてみる、ルーツを辿って体感してみることは、皆さんの創作活動において決して無駄ではないと思います。
アナログ制作を通して絵を描くということはどういうことか、今一度向き合うきっかけにしてみるのも良いかもしれません。
プロフィール
サタケシュンスケ
イラストレーター。デフォルメした動物の絵を描くのが得意。国内外でイラスト制作、本の出版。京都芸術大学非常勤講師。著書に作品集「PRESENT」(玄光社)、iPadアプリ Adobe Frescoイラストテクニック など。
https://twitter.com/satakeshunsuke
【1/15〜3/30】Web出願受付中!完全オンラインでイラストを学びながら大卒資格を取得
京都芸術大学 通信教育部 イラストレーションコースが、2024年春入学の第4期生の出願受付を開始しました!

プロ講師による実際の添削や、学生作品などをご覧いただける公式HPもございます。入学から卒業までのイメージをしっかりと描くことができますので、ぜひチェックしてみてください。
▼京都芸術大学 通信教育部 イラストレーションコース 公式HP▼
▼出願はこちら ▼
4つのポイント
・“完全オンライン”で学士を取得
・大学ならではの専門的なカリキュラムで上達をサポート
・現役イラストレーターが講師
・年間学費は34.8万円。経済的負担を軽減し、学びやすさを実現
イラストスキルを向上させたい方はぜひご検討ください。
イベントなどの最新情報を知りたい方は京都芸術大学 通信教育部 イラストレーションコース公式X(旧Twitter)をフォロー!
