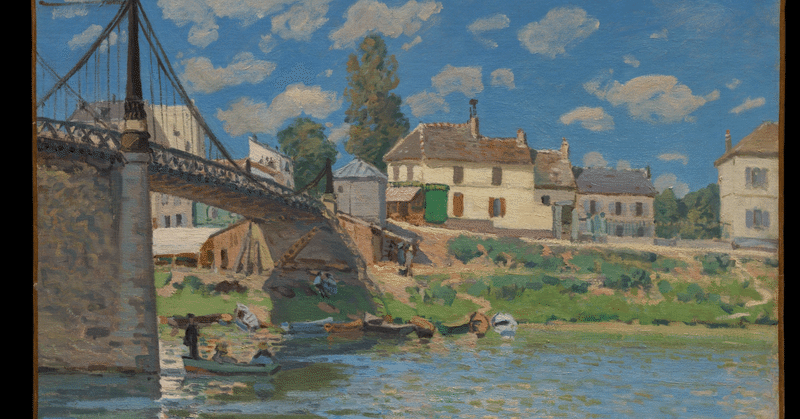
理想の感傷にひたろう!
メリークリスマス!というわけで、理想の感傷を考えてみます。好きなんです、そういうのが。それでは見ていきましょう。
①毎年クリスマスパーティーを一緒にしていた幼馴染に「今年はイブに予定があって、前日にパーティーしない?」と言われて、全てを悟る。
はい、まずはこれです。皆さんも「あ~、これね」となるのではないでしょうか。
僕と彼女は親同士が仲良いこともあって、小さなころから一緒にクリスマスはパーティーをしていました。幼稚園の頃は、一緒に夜更かししてサンタさんが来るまで待ってようなんてしてたこともあります。そのパーティーは、僕の親が遠方に転勤になってからは家族ぐるみではやらなくなっていたんですが、長年の習慣もあって今でも二人だけでささやかなパーティーをしています。それは、どちらかの部屋で集まって、フライドチキンなんかを食べながら、ホームアローンのようなクリスマス映画を見たりするといった他愛のないものではありました。しかし、その時間は僕にとって何より幸せで、今年も彼女は僕以外の誰かと過ごすことはないという安心にもなりました。
そんな彼女のことを僕は当然好きでした。でも美人でバスケ部でも活躍している彼女と、大した取柄もない自分はどう考えても釣り合わないと思って、ずっと告白できずにいました。幼馴染という関係に甘えていたんですよね。
しかし、このままの関係じゃいけないと思い、僕はクリスマスパーティーの日、彼女に告白することを決意しました。彼女を誰かに取られたくない。彼女との時間を今までとは違う関係で過ごしたい、そういう今まで抑圧していた、見ないふりをしていた自分の感情に、僕はようやく素直になれました。
そして、クリスマスの2週間前、12月上旬ごろのとある日、僕は彼女と帰り道を歩いていました。会話の間が開いて、何となく無言のまま二人で歩いていると、彼女が突然「あのさ」と話しかけてきました。そのまま「いつものクリスマスパーティーなんだけど、今年はイブに予定があって、前日にパーティーしない?」と続きました。彼女が照れくさそうにそんなことを言うのを見て、僕は彼女が今年は大切な人とイブを過ごすんだと気付いてしまいました。
後から聞いた話だと、彼女は男バスの先輩と付き合っているらしいです。とても、優しくて面白くてみんなからの人気もある人だと聞きました。僕にもっと勇気があれば、僕が彼女にもっと早く好きだって伝えることができていたら……
いや、そんなこと考えたって仕方がない。今はただ、彼女が恋人と幸せなクリスマスを過ごせることを祈ってます。楽しい日にしてね、メリークリスマス。
②帰省した田舎の寂れた神社で出会った謎の少女とひと夏を過ごしたのちに「お主と過ごす夏は悪くなかった」と言われて姿が見えなくなる。
僕は夏休みに父親の実家に里帰りをするんだけど、そこは本当に田舎で見るものなんて何もなくて、持ってきた小学校の宿題も早々に終わらせてしまって、散歩をしているんですよね。そしたら寂れた神社を見つけて、何となく入ると賽銭箱の前に座ってぼーっとする少女がいて、見た目は自分と同じくらい10歳前後に見えて、久しぶりに同じ世代の子と会えたのが嬉しくなって恐る恐る「こっ、こんにちは…」と声をかけると、その子は少しびっくりした顔で「お主、儂が見えるのか…?」と言ってきたんだよ。それが彼女との出会い。僕が一生忘れられなくなる出会いだった。それから、僕と彼女は二人でたくさん遊んだ。彼女は僕の知らない遊び場をたくさん知っていた。彼女が連れて行く場所は神秘的で綺麗だった。彼女は僕に食べられる木の実を教えてくれた。僕がびくびくしながら木の実を食べるのを彼女はケラケラと笑いながら見ていたし、僕があまりの美味しさに顔をゆるませると満足そうにほほ笑んでこちらを見てきた。僕が彼女にゲームを貸すと、物珍しそうに目を輝かせた。彼女はゲームが弱かった。対戦ゲームをすると、僕が毎回勝ってそれでムキになって何度もふくれっ面で勝負をせがんできた。
とにかく、彼女は表情豊かだった。二人の待ち合わせ場所の神社に僕が来るとパッと笑顔になって近づいてきた。僕が寝坊で遅れてしまうとむくれた顔をしていた。そういう彼女の表情が変わるのを見るたびに僕は嬉しくなって、かわいいなって思った。彼女の妙に古風な喋り方、無邪気だけれども、ミステリアスで不思議な大人っぽさ。そういうものが僕の胸を締め付けた。
しかし、ある日のことだった。いつものように神社に行くと、彼女は普段とは打って変わって寂しげに座り込んでいた。
何があったのかと不思議に思い、怖くなってキョロキョロしていると、見慣れない看板が立っていた。そこには「解体工事のお知らせ」という言葉が書かれていた。僕がその看板を見ていると彼女は「お主はいつまでこの村に居るのじゃ?」と不安げに聞いてくる。僕はあと1週間いる予定だと答えた。彼女はただ「そうか…」とだけ言った。
僕は不安になってきて彼女の隣に自分も座り「またさ、この神社無くなってもさ、遊ぼうよ。今年はもう帰っちゃうけどさ、また来年も遊ぼうよ」と励ますように言った。彼女はただ「そうじゃな」とだけ言って、僕にもたれかかり、それ以降何も言わなかった。僕は、本当はその時に彼女に何かを言うべきだったのかもしれない、それでも今にも消え入りそうなほど小さく見える彼女にしてあげれることなんて無いように思い、ただそのままずっと二人きり座り続けていた。
翌日からの彼女は普段と変わらないように見えた。いつも通り、二人きり走り回って、遊んで、笑いあった。その日々は一瞬に過ぎ去り、一週間後僕がこの土地を去る日が来た。僕は荷造りをする両親に少し待っててほしいと言い残し、いつもの神社に駆け出した。そこにはやっぱり彼女が居て、僕を見た瞬間「遅いぞ」とぶっきらぼうに言う。僕は一言謝ってそれから「君がいてくれたから、この夏凄い楽しかったよ、ありがとう。また来年もさ、二人で色んな事しようよ。ね、約束しよ?」と少し恥ずかしがりながらも言い切る。彼女は驚いたような顔をしたのちに、笑顔になった。それはなんだか嬉しそうで、でも寂しそうでも悲しそうでもあって、僕を不安にさせる笑顔だった。僕が不安をかき消せるような何かを言おうとすると、彼女はツカツカと僕に近づいてきた。そして、二人の鼻と鼻がぶつかるようなそんな距離で足をぴたりと止める。よく見れば彼女の眼には涙が溜まっているように見える。彼女は僕の顔をまじまじと見つめながら「孤独とは随分と辛いものじゃった。儂も寂しいまま最後を迎えるものと思っておった」と話し出す。その彼女の声は晴れやかで、迷いがない。「最後にお主と会えて良かったぞ。お主と過ごす夏は悪くなかった。感謝するぞ」そう言い切って彼女は笑い、僕を抱きしめる。あまりの近さで僕は驚いてしまい、目をギュッと瞑ってしまう。そのまま、彼女は「お別れじゃ、お主のこれからが良きものであることを祈っておるぞ」と言う。何か言わなきゃと必死に頭を動かしても、僕は何も言うことができない。
突然、彼女が僕の体から離れたように感じた。目を開けると、そこには彼女の姿はない。僕は呆然と立ち尽くし、それでも彼女とはもう会えないであろうことを理解した。
あとから、お父さんに話を聞いてみると、この村に小学生の女の子なんていないし、あの神社も存在は知っているけれど誰かが管理したり参拝しているのは見たことがないと言っていた。
あの子はもしかしたら……なんて考えそうになるけれど、そんなこと考える必要はないのかもしれないとも思う。彼女は僕にとって大切な存在で、彼女にとっての僕もそういう存在だったかもしれない。そう考えるだけで満足できる。彼女の言葉、表情、全てのものは、ずっと僕の中で息づいている。それだけで充分だ。さよなら。いつかまた会ったら、笑いあって遊べたら良いな。
終わり
いかがでしたか?次回「理想の感傷にひたろう!」は、中学時代の吹奏楽部で同じパートだった先輩との再会についてです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
