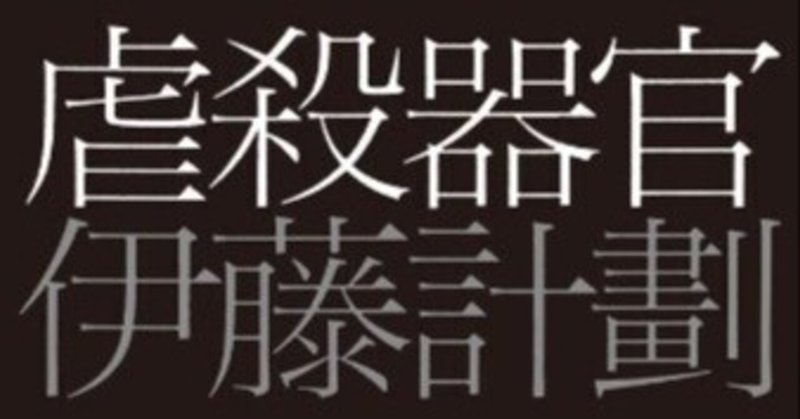
『虐殺器官』を読み、天才が描いた近未来に思いを馳せる
いつの時代、どんなところにも「天才」はいるものです。
我々凡人も努力すれば「努力しない天才」には勝てるかもしれません。でも「努力を惜しまない天才」が目の前にいたら、きっと心が折れてしまうでしょうね。走っても走っても追いつけないどころか、距離を離されてしまうのですから。
さて、あらゆるジャンルの中でも、「小説」は個々人の努力より才能が色濃く反映される世界だと言われています。つまりは天才の世界。
今回私が読んだ小説も、そんな一人の天才が書いた作品です。彼らの頭の中を覗いたかのような読後感を味わえました。
『虐殺器官』を執筆した伊藤計劃さんは、デビューからわずか二年で亡くなった短命の作家。その間に書いた『虐殺器官』『ハーモニー』は非常に高く評価されており、たった数作でゼロ年代を代表するSF作家に挙げられるまでに至った、まさに本物の天才です。ちなみに、今作は病気が回復していた時にたった十日で書き上げたらしいです。まったくもって意味が分かりません。
今作の文章を読んでいて、全体を通して感じたことは二つ。一つはアクション要素がしっかりと取り入れられているところ。小説はその性質上、どうしても静かな作品になってしまいがちです。地の文で登場人物の内面をいくらでも掘り下げることができるのはまあいいのですが、そのせいで動きが少なくなってしまい、上手くやらないとどうしてもダレてしまいます。かといって激しく動かそうとすると、今度は何をやっているのか読者に伝わりづらくなってしまう。小説で「動き」を書くのは、実は感情を書くよりも難しいのではないかと思っています。
今作の主人公はアメリカ情報軍の一員として紛争地帯に向かうので、当然ながらアクションシーンがあります。とはいえ常時激しく動き回っているわけではなく、静と動のメリハリがきっちりしている印象です。まるで映画を観ているような感覚で小説を読むことができました。
どうやら作者はかなりの映画好きだったそうですが、これにはとても納得しました。シナリオの運び方は明らかに映画を参考にしています。
そしてもう一つ感じたのは、作者の知見がとても幅広く、思慮深いこと。これに関しては読んでいただかないと分からないと思いますが、作中の登場人物の会話がとにかく賢いんですよ。賢い人がする会話。
登場人物の思考や会話は作者の頭の良さが反映されるんですよね。今作を読むと作者が天才なのは一発で分かると思います。
そんな作者がどんな近未来を描いたか、気になりませんか?
今作が執筆されたのは2006年ですが、2023年現在、世界はこの作品が描いたものに近づきつつあると感じています。
生体認証
例として、今作で幾度となく取り上げられるのが生体認証です。
作中では、テロの防止や安全のためにあらゆるサービスが生体認証によって成り立っている様子が描写されています。
これはとても分かりやすいですね。少し前にGoogleアカウントのログインに生体認証が使えるようになりました。スマートフォンでは指紋認証や顔認証が既に普及していますし、Windowsも10からはWindows Helloが搭載されるようになりました。アメリカの大手テック企業が次々に生体認証を導入していることから、パスワードが存在しない未来が少しずつ現実味を帯びてきています。
何より生体認証は楽かつ安全です。人間は「楽」には逆らえません。これからもさらに普及していくことでしょう。今作は未来のイメージをしっかり捉えています。
でも、そこまでなら他にも多くの作品が予言しています。今作が面白いのは、「その先」も考えているところ。
作中終盤にて、「アメリカ国内におけるテロを減らしたのは生体認証ではなかった」ことが判明します。
冒頭、主人公は戦争が発生している国で戦争犯罪人の暗殺を行っているのですが、実はその時点で伏線が仕込まれています。生体認証に全幅の信頼が置かれた結果、それを利用した不正な認証も裏で行われるようになったのです。作中では、戦争や事故によって行方不明になっていた人の死体からIDチップを抜き出し、自身の身分を偽装する手口が使われています。
また、生体認証によってあらゆる行動が記録される現状に嫌気がさし、行動が記録されない場所を求める人々の姿も描かれています。
信頼性の高いセキュリティー技術が生み出されると、その裏をかく人や技術も現れる。セキュリティーの歴史を振り返れば、そのようないたちごっこはずっと続いています。生体認証が普及したところで、その流れは変わらない。これは非常に説得力のある予言ではないでしょうか。
「知覚」と「痛覚」の分離
個人的に今作で特に面白いなと思ったのがこちら。
作中に登場するアメリカの軍人は、戦闘前に「痛い」と知覚することはできても、痛さを「感じる」ことはないように調整されます。痛さによって判断に遅れが生じないようにするためです。
なんだかドラえもんのヘソリンガスを思い出します。あの道具は知覚も痛覚も麻痺させてしまうのでマズいのですが、今作は痛覚のみを取っ払うことでバランスを取っています。
で、戦闘するグループの片方のみがこの処置を受けている場合なら、場を簡単に制圧することができます。では、双方がこの処置を受けていたとしたら……?
言うまでもなく、そこには地獄が生まれます。互いに原型を留めなくなるまで戦い続けられるのですから。
未来の戦闘ではこうした悲劇が実際に起きてしまうのでしょうか。現在は無人兵器が幅を利かせていますが、人体そのものを改造する路線に向かったら、かなり恐ろしい光景が待っていそうです。
自我の喪失
調整されるのは痛覚だけではありません。
主人公含めた情報軍は、子どもなどを殺しても判断が鈍らないよう、感情に関わる部分も調整が施されています。とにかく戦闘時において、個人的な感情は邪魔でしかない。それが合理的選択なのは分かります。
ただその結果、主人公は自我の喪失に苦しみます。今、自分が抱いている感情が、ちゃんと自分が感じているものなのか、それとも自身に施された処置の影響なのか、自信が持てなくなってしまうのです。
未来の戦争において、人はロボットのように改造されていく。極限状態において自我は最も邪魔なものではあるものの、それが人とロボットの最大の違いでもあるわけです。
言葉を用いた扇動
詳細はネタバレになるので伏せますが、作中のラスボスに相当する人物は、「言葉」を巧みに使うことで途上国を戦争状態に陥れます。本人は全く手を汚すことなく、日々発する言葉の中に人々の精神状態を偏らせるようなフレーズを仕込み、国全体をめちゃくちゃな状態にしてしまうのです。
ここまで極端ではないものの、このような言葉を用いた扇動は既に現実のものになっているようにも思います。特にインターネットが普及してからは、良くも悪くも言葉の持つ力はより一層強まりました。何とは言いませんが、ここ10年のアメリカは、それが顕著に現れた例とも言えるのではないでしょうか。
というわけで。
「これが2006年に書かれたってホント?」と驚いてしまうくらい、未来をかなり正確に捉えていますよね。
生体認証、痛覚の分離、言葉による扇動……
私は「優れた作品は未来を予言する」と考えていますが、この作品は未来を正確に予言しているように思いました。
じゃあこの未来をそのまま受け入れろと言われたら?
うーん、少なくとも戦争だけは起こってほしくないですね……
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
