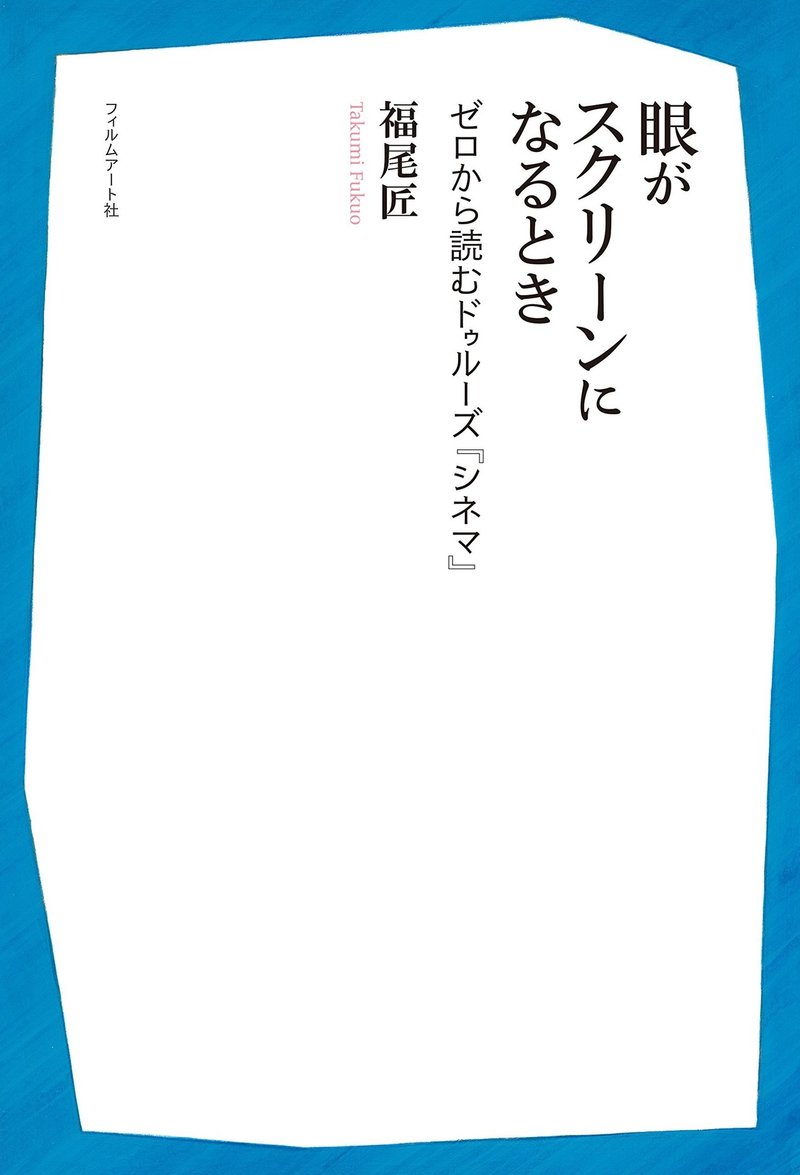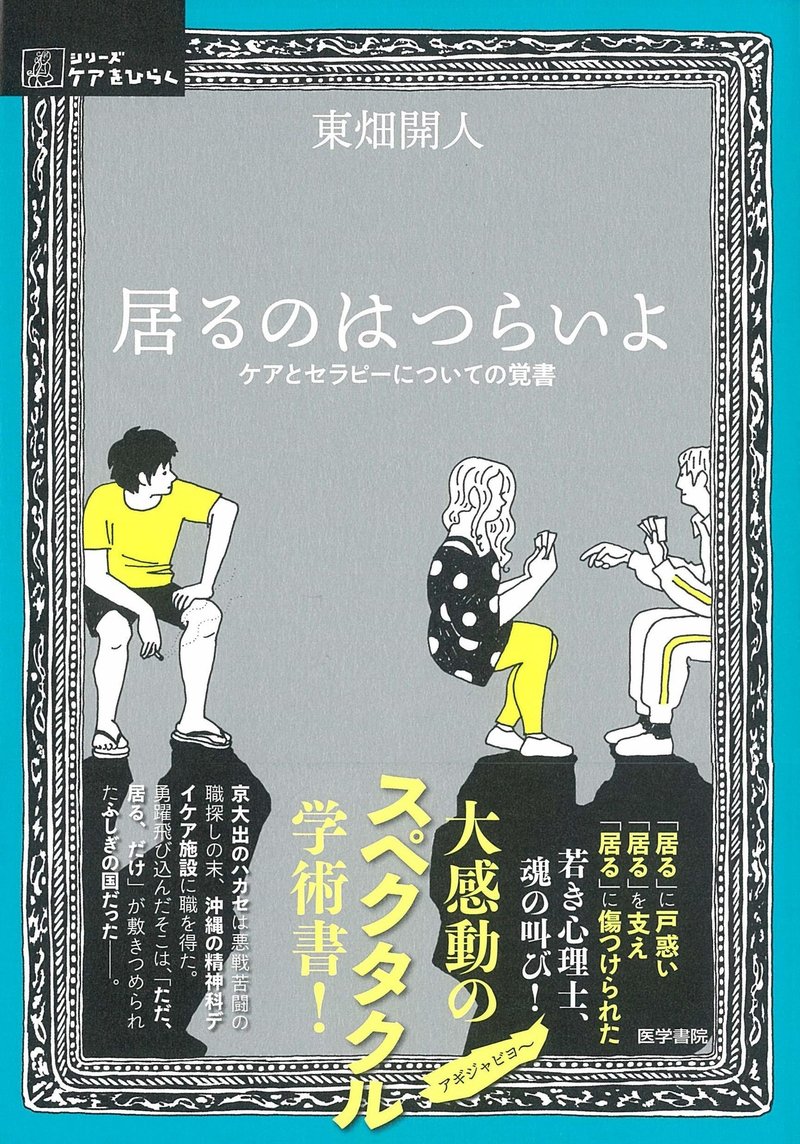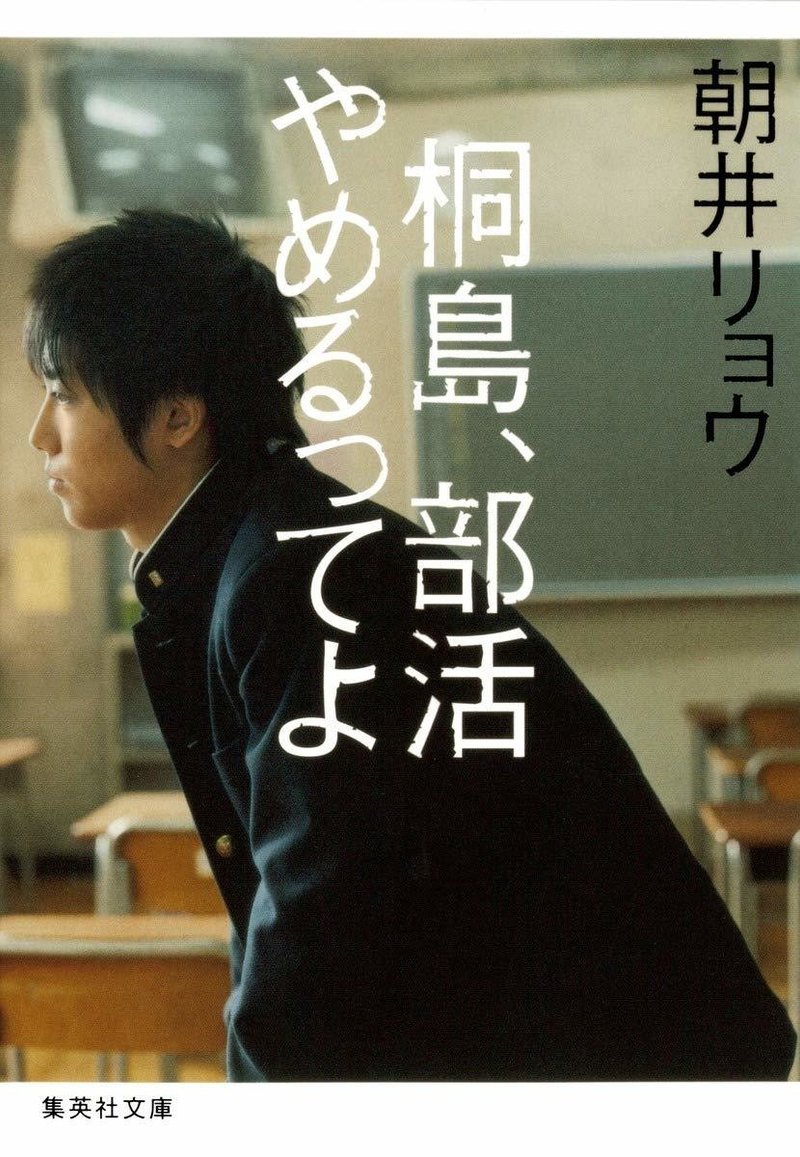いてもいなくてもよくなることについて:中森弘樹・福尾匠・黒嵜想鼎談
「あなたがいてくれるだけでいい」。
「あなたが」に力点を置けばこの「あなた」の存在がまるごと肯定されているように読めるし、「いてくれるだけで」に力点を置けばそれが誰かに関わらずとにかく誰かがそこに「いる」ことが大切なのだと読めます。いずれにせよ、たんに「いる」だけのことが「くれる/あげる」といった、行為としての価値をもつのは考えてみれば不思議なことです。こうした価値は実際のところ社会のなかでどのように機能しているのでしょうか。あるいは反対に、「いるだけでいい」ということがなおさら「いなくなれない」強制力としてはたらくこともあるかもしれません。
この鼎談では『失踪の社会学——親密性と責任をめぐる試論』(慶應義塾大学出版会、2017年)の著者、中森弘樹と「ひるにおきるさる」世話人の福尾匠・黒嵜想が「いるだけでいいこと/いなくなれないこと」の外側で、親密圏や人間関係のあり方について考えます。(2020年3月21日収録)
失踪と親密圏
福尾:そもそも中森さんの本『失踪の社会学』のことを教えてくれたのが黒嵜さんで、『眼がスクリーンになるとき』(フィルムアート社)っていう本を出したのが2018年の夏だったんですけど、その時期ぐらいから黒嵜さんに『失踪の社会学』っていうおもしろい本があるよって教えてもらって。それも、「君が読むべき本だ」みたいな感じで。
黒嵜:(笑)
福尾:僕に強く関係がある本としておすすめしてくれたんですよ。実際に読んでもすごくおもしろかった。それがきっかけで京都でこの3人で会う機会があって。お話もすごく楽しかったんですけど、当時は僕がやってることにそんな強く関係がある感じは正直わからなかったんです。
中森:僕もそうでしたね。
福尾:で、1、2年たってみるといつのまにか僕も「いてもいなくてもよくなること」とかについて考え始めてて。ある種黒嵜さんの予言が当たったみたいな感じになり、僕のなかでこの本の存在がどんどん大事なものになってきて。せっかくだしまたお話しする機会を作りたいと思って、あるイベントのなかのいち企画として対談の話を進めてたんですけど、それが頓挫して。せっかくなので黒嵜さんにも参加してもらうかたちで「ひるにおきるさる」単体で企画しなおしたという感じです。
……なんか、どうしてもこう、ちゃんと喋ろうとしてしまいますね。
黒嵜:見学者に向けて司会してしまうね、どうしても。
中森:たぶんこれも、人が「いる」っていうことの効果なんでしょうね。皆さんが「いる」だけで、それだけではすまない何かがあるっていうことなんでしょうね。
それは、僕の本のひとつのコンセプトでして。「関係する」ということに伴う、圧のようなもの。これに言葉を当てはめると何になるのかな、ということを、ずっと考えてる本なんです。たとえば、黒嵜さんが福尾さんに本をすすめて、時間がたって実際に福尾さんがこの本を重要に思えてきたというのも、同じ効果によるものかもしれません。
黒嵜:いま「予言」と彼は言ったけど、たんに洗脳しただけかもしれない……
中森:(笑)
黒嵜:あるいは気を遣っただけかもしれない……ただ、本をすすめた側として記憶に残っているのは、当時ほぼ同じ時期に出版された『観光客の哲学』(ゲンロン、2017年)という批評家・東浩紀の著作です。
東の様々な著作を貫く論題のひとつとして、あるのか(あったのか)/ないのか(なかったのか)の判断が確定しない「確率的な存在」というものがあります。それは、手紙だったりキャラクターだったり、さまざまな分析対象に見出され考察されてきました。『観光客の哲学』においても例外ではなくて、本書では、観光地を群れとしてさまよう「観光客」たち、あるいは彼ら彼女らの消費行為が「確率的な存在」として扱われています。
特に興味深いのは第一章、「観光」なる語に哲学的な定義を与えるため、いくつかの文献参照しながら既存の事業や実学において「観光」に与えられているあいまいな定義を振り返る箇所です。
そこでは、生活上の必然性ではなく生活の余剰のなかで短期滞在して、そして戻ってくること、といったようなぼんやりとした輪郭が立ち上げられているんですよ。
福尾:経済的な必要性とか、そういうものに迫られていくんじゃなくて、たんに行くということですね。
黒嵜:僕が『失踪の社会学』に興味をもったのは、まずシンプルにこの点で。つまり、『観光客の哲学』では「旅人」あるいは「難民」に区分されるであろう、「行ったまま帰ってこない」という確率的な存在を、中森さんの本は「失踪者」で捉えているのではないかと。もし二つの本における「観光客」と「失踪者」の概念が、いるのか/いないのか判然としない存在を扱う点で共通するのなら、何が見えてくるのか。
『失踪の社会学』はまず、失踪することをネガティブに扱う裏にある「無縁社会を嘆く」という現代的な論調を疑い直すところから始まります。親密圏から離脱することに対し、失踪した側もされた側も抵抗感をもつという、この当たり前に思えてしまうコンテクストが、しかしなぜ暗黙のうちに合意がとれているのか。文献やインタビューなどのさまざまな資料調査を通して、両者の言を取り出していく。『観光客の哲学』が「いてもいなくてもいい場所」を訪れる観光客を通して新しい形の家族を扱うのなら、『失踪の社会学』は「いるのかいないのか判明しない失踪者」を抱えた家族を通して「いなければならない」親密圏を問う。二つの本は、議論の構成のレベルでも対をなすようで、互いの議論の裏側を照らし出しているように読めたんです。
福尾:その手前で、近代社会はプライベートな領域においては、人々の関係性は基本的に自由なものであって、友達関係も恋人関係もそれぞれの主体の意思によっていろんな関係を結んだり切ったりできるっていう、一般的な通念がありますよね。でも、よくよく考えてみると、いま、われわれはそんなに自由にも感じていなくて、むしろ親密な関係にこそ何らかのしがらみだったり、そこから離脱することへの抵抗みたいなものを感じてしまう。自由恋愛で、友達関係も自由にいろいろつながることができるっていう、表面的な印象の裏に、じつは親密な関係から離脱することがどんどん難しくなっているような局面があるっていう問いが大前提にある。で、だからこそ失踪っていうものをいっかい考えてみようっていうことが、この本の出発点の問いですよね。
中森:なるほど、そういうことだったのかっていう感じですね。おふたりともすごく、僕の本のことを僕よりうまく話すので……(笑)
僕の本の基本的なコンセプトとしては、いまお話しいただいた通りでいいと思うんですけど、『観光客の哲学』は後半で家族の話になるじゃないですか。ある意味で観光客であることと、家族的であることが相互関係になっていると、そう読んだ記憶があるんですけど、どうなんでしたっけ。
黒嵜:ようは観光を、たんなる消費行動のひとつではなくて、ネグリ゠ハートのマルチチュード論にアップデートを迫るような資本主義肯定型の新しい社会運動のひとつとして捉え直すんですね。
そこでひるがえって、マルクスにおける「階級」なる概念の意義は、性別と文化圏を横断するアイデンティティの開発にあったと述べる。では観光客的な運動体においては運動の動機となるようなアイデンティティは何かと問い、本来もっとも保守的な共同体の単位である「家族」にそれを見る。観光を成り立たせる「家」に問いを折り返す。そのような議論は、中森さんの本における、「失踪」に抵抗感を持たせている「責任」とは何かという捉え返しにも重なるように思います。
中森:なるほど。僕にとっては、お互いがお互いにとって必要条件になっているという状況とは何か、が興味深いところであって。観光客であるためには、一方で、家族を持ってないといけない。つまり帰る場所を持ってないといけない。あるいは逆に、観光客でなければ家族であれない、っていう視点もあり得ますよね。こちらが僕の視点に近い。つまり、定期的に親密圏の外にポンポン出るような主体じゃないと、逆に、健康的な親密圏を築けないんじゃないか。
仕事とか出張とかではなくって、特に目的もなくただ行くっていうことと、一方でその人が健康な親密圏を持っているっていうことが、状況としてはカップリングしているんじゃないかという気がするんですよね。逆に、たとえば観光しているあいだに、やましいことがあって、それで帰ってこなくなった、みたいなケースをどう考えればいいのか。あるいはもうちょっと具体的にいうと、たとえば世界の紛争地域に行っちゃって、そっちの運動にコミットしちゃって帰ってこなくなる人とかもいるわけですよ。そういうことを画策した人は日本にもいたわけですけれども……べつに東さんの議論に限らず、観光客的なありかたを志向するものにとって、それを下支えするような家族的なありかたみたいなものが、もし無かったらっていうことを考えることは、現代においてすごく怖いことなんじゃないかなっていうのが、僕の感想ですね。
で、その怖くなっている理由っていうのは、さっき福尾さんからおっしゃっていただいたような、人間関係がすごく自由になっているんだけれども、他方ですごく不自由になっているっていう、「親密圏を失う不安」ですよね。
冒頭におっしゃった、福尾さんの関心がこの本の話に近づいてきた、ということについて聞かせてください。『眼がスクリーンになるとき』についても改めてお聞きしたい。
福尾:この本では「リテラリティ」という概念を使って、ドゥルーズの『シネマ』、あるいは『シネマ』の中でベルクソンがどのように読まれているかということを考えました。それはちょっと変な試みで、すごく具体的な二者関係に閉じこもって、二者の間で交わされた変化を分析するわけです。テクストとそれを読む私のあいだの直接的な関係とか、ドゥルーズとベルクソンのあいだの直接的な関係とか、ドゥルーズと映画の直接的な関係とか。それは一見、すごく純粋な、第三者を排除したその二者だけで完結してる関係性みたいなものを考えるための概念のように見える。けれどもじつは、そこで起こってるディスコミュニケーションの創造性みたいなものを考えるための概念なんです。
純粋な二者関係を想定するっていうことと、そこで起こっているディスコミュニケーションを肯定すること。このふたつが、リテラリティ、つまり文字通り性っていう概念において考えられています。だから全部をリテラルに、文字通りに読むっていうのは、たんにベルクソンをドゥルーズが反復するとか、映画で描かれてあることが『シネマ』で反復されてるとか、そういう「同じものの反復」じゃなくって、リテラルに見ること・読むことによってこそ、なんらかの違いみたいなものが生まれて、そこに創造性が宿るんだってことを考えるための概念なんですね。こういう、「二者関係に閉じこもるんだけどディスコミュニケーションを擁護する」っていうのは、たぶん、ほとんど僕の性分に近い。
めちゃめちゃ卑近な例でいうと。人としゃべってるときに、「うん」とか「はい」とか「へえ」とか相槌を打つじゃないですか。相槌って人の話聞いてなくても打てるんですよね。なんとなく相手の話のリズムとトーンだけ把握してれば、内容のレベルでちゃんと私とあなたがここにいいて、お互いの理想のコミュニケーションをおこなっているって想定しなくても、なんとなくそこでコミュニケーションが起こったことになるっていうことが、相槌っていうものによって起こってて。それって不埒なことでも自堕落なことでもなんでもなくて、むしろ人間のコミュニケーションって、そういう相槌的なものがないとできないんじゃないかなって思うんですよね。最初から私は私の意見を言ってて、あなたはあなたの意見を持ってて、それを交換しましょうっていう理想的なコミュニケーションみたいなものを最初から想定するんじゃなくて、お互いが話半分に聞いてて、お互いがなんとなく相槌を打っているような状態みたいなものを、二者関係のコミュニケーションが成立するための条件として強く考えているっていう側面があって。
そういうことを考えていくなかで、『失踪の社会学』が扱う親密圏の問題に関心を持ちました。自由な選択によって、誰かと一緒にいるはずなんだけど、いつの間にかそれが、自分に責任としてのしかかってくること。で、その責任は、関係が純粋であるがゆえに、なかなか解きほぐすことができない。『失踪の社会学』では最初のあたりで「純粋な関係」っていう概念が出てきますね。近代以降の自由恋愛とか、自由な友愛関係とかいうものは純粋な関係であると。あなたと一緒にいたいからあなたと一緒にいるっていう、関係のための関係。そういう、いるだけでいいっていう関係は、いるだけでいいからこそ、いなきゃいけなくなるし、そこになんらかの拘束力みたいなのを感じて責任として自分にのしかかってきてしまう。そこから逃れることを失踪というモチーフを通して考えているのがこの本ですね。
黒嵜:「二者関係に閉じこもるんだけどディスコミュニケーションを擁護する」こと。『眼がスクリーンになるとき』を書いたばかりの福尾くんに、『失踪の社会学』の本を薦めたのは、まさに彼がいま述べたような観点が関わってくるように思えたからです。
先ほども説明したように、『失踪の社会学』で中心的に論じられるのは、失踪への抵抗感の分析です。純粋な、「関係のための関係」がつくる「いなきゃいけなくなる」拘束力。「失踪」にまつわる当事者たちの証言や資料が、この拘束力の力学を明らかにするわけですね。たとえば、自由で純粋な関係というのは、だからこそ常に応答責任が求められる。失踪者の証言をもとに分析すると、失踪のハードルは2つあることがわかる。たんに体を離して帰らなくなるということと、応答責任を拒絶して連絡を絶つということ。で、この2つはそれぞれべつの勇気を要求するのだと、また解体されて論じられるんですが、この分析がひるがえって照らし出すのは、「応答責任なき親密圏」の不在なんですよね。
では応答しない自由の擁護、応答していないまま共存できる親密権ということは、どのように考えられるのか。本書の後半に進める議論は、そういったものの可能性も射程に入れている。この議論の先に見えるものは、『眼がスクリーンになるとき』がたどり着く二者関係の姿と近いものなのではないか。さらにここに、観光を消費による新しい社会運動だとした『観光客の哲学』を並べ、「応答に縛られない人たちの社会運動」を素描できるようにも思います。
SEALDsのように明確に「NO!」と応答して街に繰り出すひとたちだけが社会にアクションを行なっているのだろうか。矛盾したような言い方になるけれども、「応答から降りるというアクション」をこそ運動と読み替えなければ、見えてこない社会問題があるのではないか。自殺や犯罪といった極端な応答、降り方の手前で、「応答したり降りたりしている」人々はいるのではないか。失踪者たちががそのひとつであるのは確かです。
中森:なるほど。あらためて、「失踪」とは何かを説明しますね。人間、観光や出張などで移動するたびにその人の前からいなくなってるわけですけれども、でも普通われわれはそれを、失踪とは呼ばないわけです。なぜかっていうと、応答があるからなんです。いまだと、いろんなコミュニケーションツールが普及してますから、たとえばLINEで「元気?」とか「どこにいるの?」と送ったら、普通返してきますよね。失踪している状況っていうのは、それがない状況です。さっき黒嵜さんが、僕の本に触れて「失踪に二段階ある」とおっしゃったのはその通りで、まずはいなくなるっていうことは前提なんですけれど、そのうえで、たとえば家族から連絡が来たときに結果的に何も返さなかったのなら、初めてそれが「失踪」という現象になります。僕はそういう理解です。その意味で、応答のあいだにある沈黙がどういう意味を持っていて、さらにどういう意味を持ちうるかっていうことはすごく重要で。たぶんそれは僕が、この研究をはじめた当初に、より強く持っていた問題意識です。つまり、「応答してこない」という不確実な状況にある他者とはなんだろう、と。
もともとこういうこと考えだした原因って、恋愛の失敗なんですよね(笑)。恋愛ってそうじゃないですか。目の前にいても相手が何を考えてるかわかんないし、自分のことを本当に好きかもわかんないし、ようは、どんなに話してくれても、沈黙の部分って残るんですよね。で、そういうものに、自分は結構耐えれないタイプ、不安が強いタイプ。いまでもみなさんが、本当にここに来て、楽しんでくれているのか、とか考えちゃうタイプなんですよね。で、それを二者関係に適応すると、失敗しちゃうんですよ。でもそれって、自分のことも病的だと思うし、自分以外のひとにもある生きづらさだな、と思ったわけなんですよね。これはあとで詳しく話しますけど、現代って「YesでもありNoでもありうる」ような不確定な状態にすごく耐えづらい状況に陥っていると思うんです。そういうものを、どういうふうに処理したらいいか、あるいは、沈黙の意思表示としてポジティブに捉え返すにはどうしたらいいんだろうっていう問題意識から、この研究をはじめたんだったという、記憶がよみがえってきました。これを考えるのに、失踪はふさわしい論題であるように思えたんです。
福尾さんにお聞きしたいのは、二者関係におけるディスコミュニケーションについてですね。あるいは「応答の齟齬」といいかえることができるとも思うのですが、そういうものをポジティブに捉えるという立場の背景のひとつに、二者関係の息苦しさがあるということですか?
失踪が許されていない二者関係には誤配がないのかなって、ちょっと一瞬思ったんですけれども。
「いる」ことと「する」ことの外で
福尾:迂遠な答えかたになると思うんですけど、いったんこの本の話をしますね。『居るのはつらいよ』(医学書院、2019年)っていう東畑開人さんの本です。
中森:もちろん読んだことがあります。
福尾:結構売れた本ですね。内容としては、京大の医学部を出て博士号を取った東畑さんが、これから臨床心理士として頑張るぞと思ったら就職先がなくて、しょうがなく沖縄で求人があったデイケアの施設、おもに統合失調症の方が日中過ごしてる施設に就職して、ケアの難しさみたいなものにどんどん気づいていく過程を独白調で書いたものです。この本のなかで、一貫して出てる対立軸っていうのが、「いる」ことと「する」ことなんですね。その対立が、ケアとセラピーの対立にくっつけられていて。
東畑さんは、最初に沖縄に行ったときには、いままでさんざん勉強したセラピーの知識を沖縄で実践するんだと思っていた。けれども実際、沖縄で就いたところはケア偏重の職場で、そこで職員たちは何をしているかというと、ただ利用者さんたちと一緒に同じ部屋にいて、カラオケしたりバレーボールしたりしてるだけ。自分はどうしても「する」っていうことだけを教わってきたから、そこでセラピー的な実践をしようとするんだけど、しようとすればするほど、それはそこの利用者さんたちの負担になってしまって、どうやらここでは「いる」っていうことが大事なんじゃないか、ということに、だんだん気づいていく。
この本、すごくおもしろいし、いいなと思う一方で、なんか、煮え切らなさが残る点があって。たとえばですね、この、「いる」と「する」、ケアとセラピーっていう対立が、ほかにも連なっていて、「依存労働」っていう言葉が出てくるんですよ。依存労働っていうのは何かというと、いわゆる家事とか子育てとかですね。人が「たんにいる」っていうことを支えるような労働。お皿洗いとか洗濯とか、お風呂に入れない人がいたらお風呂に入れてあげることとか。それに対して「いわゆる労働」っていうのは、ふつうの、何か作ったりとか売ったりとかそういう仕事ですね。で、依存労働といわゆる労働っていうのは賃金の差が大きい。家族のなかの家事にお金が発生しないように、依存労働は比較的賃金が低い。ケアをする人と医者の賃金を比べてもそれはわかるはずだ、とされる。
つまり、いる=ケア=依存労働に対して、する=セラピー=いわゆる労働がある。前者がプライベートなもので後者がパブリックなものとも考えられますね。人々のプライベートな生活のありかたを支えるのが依存労働で、それとは違って、外の社会に出ていって仕事をするのがパブリックな労働。この対立っていうのは、ずっとこの本のなかで一貫して使われている図式で。この対立をそもそも想定してしまったことに、煮え切らなさの要因があるんじゃないかと思っていて。
中森:なるほど。
福尾:というのは、たとえば依存労働っていうのはいままでおもに女性がしてきたものとされるわけですよね。家のなかで。それに対して男性的な、外で働いて稼いで帰ってくる、みたいな「いわゆる労働」がある。東畑さんはパブリックな仕事をするんだ、と思ったんだけど、ケア的な「いる」ことのほうが大事なんじゃないかと思って、だんだん気づいていく。でも、「いる」ことと「する」ことの対立自体が残存している以上、たとえば女性的なジェンダーロールと男性的なジェンダーロールとか、賃金の差異といったある種の格差は、結局のところ再生産されてしまうんじゃないかっていう問題が残る。で、この問題をすごく雑なかたちでパラフレーズすると、「いるだけでいいだけでいいのか」と問うものになる。
黒嵜:きみっぽい言い方やな……
福尾:「いる」と「する」の対立とか、プライベートとパブリックの対立っていうものが温存されてる問いの立て方では、いなくなることとか、そこにいてもいなくてもいいっていうモーメントについて考えることができないんじゃないかと思ったんですよ。「いる」をめぐるこの袋小路について考えるうえで、失踪っていうモチーフは僕のなかですごいインスパイアリングなものでした。
もはや、なんていうか、公的権力の私的領域への介入にあらがってるだけではすまないんじゃないかという気がしていて。私的領域がすでに何らかのしがらみみたいなもの、それこそ親密なものへの責任みたいなもので、ある種の閉塞的な状況に陥っているとしたら、公的権力に対して私的領域を確保して、「こっから先は自分たちのプライバシーな領域なんだ」って私的な領域を誇示することっていうのは、もちろん無駄ではないけど、思想的なレベルでは根本的な解決にはならないような気がするんです。だからこそ、パブリックなものに対してプライバシーっていうものを守るっていうよりかは、たんに「いなくなる」ことだとか、「いてもいなくてもよくなる」こととか、そういうことについて考えたい。
中森:そうですね。いくつかお答えしておくと、まず東畑さんの『居るのはつらいよ』ですが、ただ「いる」ことの重要性に気づいていくっていうストーリーがある他方で、もうひとつ重要なのは、ただ「いる」だけなのは同時にとても疲弊すると気づいていく点ですね。沖縄のデイケアの施設でただ「いる」っていうことを過ごすなかで、同僚はどんどんいなくなっていく。ようするにある意味で「失踪」していくわけです。僕の観点でもっとも興味深かったのはここですね。
彼、じつは、この前に『野の医者は笑う』(誠信書房、2015年)っていう本を書いていて。こちらの方が刊行は先なんですけど、じつは書かれている内容の時系列は『居るのはつらいよ』の後なんですよ。で、どういう本かというと、彼もまたケアに挫折して、この沖縄の施設からいなくなり、その後に、今度はセラピーをしにふたたび沖縄に行く顛末が語られているんです。沖縄には怪しいスピリチュアルケアだとかナントカ療法だとかがあって、それをひたすら体当たりで見て回って。それらの「セラピー」と自分が勉強したセラピーの違いってなんなんだろうと、経験しながら考える。その過程で、本人もだんだんケアのつらさ、「いる」だけのつらさから回復していって、最後には東京に戻る。『居るのはつらいよ』と『野の医者は笑う』の2冊をセットにして、ケアとセラピーを往復する2本立てのストーリーが語れているんですよね。
この問題意識にはすごく共感します。僕はプライベートで、医学的な用語でいうところの「精神障害者」と接することがあるんですが、ようはセラピーって、「よくしようとすること」なんですよ。そして、ケアというのは「そのままのあなたを認めること」なんですよね。少なくとも、セラピー「だけ」だとアウトなんです。つまり、苦しんでる人に「こうすれば良くなるよ」と客観的な分析を言うだけだと、そのときは「なるほど」とリアクションを返してくれていても、回数を重ねるたびに「もう鬱陶しい」みたいな顔になってるわけですよね。でも一方で、ただいるだけだと、「じゃああなたは何をしてくれるの」という雰囲気になってくる。こんなふうにケアとセラピーのブレンドを意識していくというのは、医療現場でも一緒なんだろうという気がしますね。ある種の治療行為というのは、ケアとセラピーのブレンドによって成り立っているのではないか。ケアの割合が大きいものは例えば傾聴スタイルのカウンセリングになり、セラピーの部分が大きければ例えば認知行動療法とかになる、といったような。
ただ、おっしゃるように、そもそもケアとセラピーを分けて考えることが本当にいいのか。分けて考えることは妥当だと思うんですけど、ただ、この分類をずっと使っていて、当人が幸せになれるのかっていう問いこそが重要ではないか。『居るつら』に関して福尾さんが提示した疑問というのは、そういったものに聞こえました。
「いてもいなくてもよくなる」という発想は、たしかに僕の議論とも通じるところがあります。失踪をポジティブに捉えるって、なにも「失踪しなさい」といっているわけではなくて。「失踪してもしなくてもいい」みたいな状態を、僕もある種の到達点として書いてるんですよね。「応答してもしなくてもいい状態」と言ってもいいかもしれません。そもそも、僕は本書で自殺と失踪について比べてるんですが、自殺って、一見すると応答しない行為に見えて、じつはもっとも強烈な応答でもあるわけですよ。たとえば、かつての切腹はそういうものだった。では失踪は何かというと、ようは応答しないこと、あるいはもうちょっと踏み込んで言うと、「応答しないという選択」さえもしないことなんですよね。逆に言えば自殺というのは、「応答できない状態になる」という究極の応答なんです。つまり失踪は、そもそも応答するとかしないだとかいった図式から逃げるっていうところに、その本質がある。人は、最後までそういう選択権を保持していいんじゃないか、と提案しているわけです。で、この発想は「いてもいなくてもよくなる」ことと近いという気がします。
ただ他方で気にかかるのは、応答しない他者、「応答しないという応答」すらしないような状態にある他者と一緒にいて、人はどうなってしまうのだろうという日常実践的な懸念ですね。「ケアとセラピー」的な図式をそこで捨ててしまってよいのだろうか、と。
黒嵜:「いる」と「する」の対比が、ジェンダーロールの対比に重ねられていて、対比のなかでの乗り換えが両者の格差を再生産してしまうのではないか、という問題提起がありました。連想したのは、レンタルなんもしない人ですね。
福尾:ツイッター上で「なんもせずにいるだけ」の依頼を募集し、話題になった人ですね。
黒嵜:彼の活動は関心があって一時期追いかけていたのだけど、興味深いのは彼にまつわる「炎上」でした。もっとも印象に残っていたのは、あるフォロワーが彼に対して放った「見知らぬ誰かのところに派遣されて「なにもしない」ができるのは男性だけじゃないか」というリプライをきっかけにしたやりとり。意外にも、これに対しレンタルなんもしない人が何度も強く反論して「炎上」したわけですが、詳細を省いて要点だけ述べると、彼は「なんもしない」が非対称なジェンダー差を利用したものではなく自分独自のものだ主張します。続く第三者からのリプライは、女性がいかに「なんもしない」ままに他者(特に異性)といることが困難かを述べる。そして、ふたたび彼がこれに「そんなこと言う人はたとえ男に生まれても自分と同じことはできない」と繰り返す。このやりとりを見ていて興味深かったのは、いっけん対立しているように見える両者は、「なんもしない」ジェンダーロールが既存のものとしてあって、それに乗り換えた実践として「レンタルなんもしない人」があるとは決して認めない、という抽象的な点においてはじつは一致しているということでした。福尾くんの指摘を受けて捉え直すなら、これは「いる」と「する」の対立項に混入してしまう対比的なジェンダー観に、アレルギー反応がでたケースとして見ることができるかもしれません。
(*参照:https://togetter.com/li/1309358)
福尾:炎上後にレンタルなんもしない人はある女性がポケモンGOを街中でプレイするのに同行するという依頼を受けていました。ひとりでやると男性から声をかけられてしまうという理由での依頼だったのですが、さらに依頼後にその女性に「僕も同行できますよ」という男性からのメッセージが殺到しレンタルさんはそれで女性の「生きづらさ」に気づいたと言っていたように記憶しています。まさに「いるだけ」にともなうジェンダー差があるわけですよね。女性に対する男性の「いるだけ」はすぐ「あわよくば」になっちゃうし、女性は「いるだけ」でいられない。逆に家で家事をしていても「いるだけ」と思われちゃったりする。(*参照:https://twitter.com/morimotoshoji/status/1119446030641008640?s=20)
黒嵜:話を敷衍すると、「いる」と「する」の二項対立の裏には、一方で、取り換え可能な一個になるパブリックな労働があって、他方に、取り換え不可能な私であることで成り立つプライベートな労働がある。このふたつのあいだを折衝したり、行き来したりすることを扱おうとした論題は、ゼロ年代批評にもいっぱいあったんですよ。そのひとつに匿名的な生成力とその政治参与、というものがあった。当時のモデルとして挙げられたのは、2ちゃんねるとか、ニコニコ動画とかだったわけですが。東浩紀を中心として展開されたようなこれらの議論は、じつは中森さん著書のなかでも一部触れられています。ただ、それはやはり「圏」に力点をおいた議論なんですよね。プライベートな「生活圏」にいるまま匿名化された存在が「公共圏」の政治に参与するために、「匿名性の自由」を擁護することが、そこでは試みられた。ただ、10年代も終わったいまに至るまでどうなったかというと、みんながスマホ持つようになり、そこには各種SNSアカウントがほぼプリセットされていて、初めから常時接続の応答責任が求められ、一貫した「個」のアカウントであり続けることを義務づけられているような情報環境が出来上がったわけですよね。生活圏と公共圏の二つは圧着されてしまい、、名前をもった現れから離脱する契機は失われてしまった。そこから振り返ってみれば、2011年というのは、東日本大震災が起こった年でありながら、日本語版のLINE公式アプリがリリースされ、YouTubeの収益目的アカウントが利用可能になった年でもあり。震災以前/以後といった区分を採用するなら、その切断には、顕名的なネット空間がメジャーなものとして整備されてゆく契機も重なっていた。いまや公共圏はリアルタイムに現れる膨大な量のプライベートに翻弄され、生活圏での応答はパブリックな一貫性を保持しうるものか相互監視にかけられる。そんな状況のいま、かつての「匿名性の自由」をめぐる議論は、東が公共圏からの離脱を強調していたのに対して、むしろプライベートから降りることを強調した中森さんの仕事を補助線にして、読み替えられるのではないか。それが「圏」から提案できるものでなくなったのなら、何によって提案できるのか、ということがお二人の間で話されているように思います。
中森:そうですね。ひとつ目の話から拾うと、レンタルなんもしない人はたしかに象徴的なケースですね。「レンタルなんもしない人」と言ってしまう時点で、もはやそれは「なんもしない人」ではなくなっちゃう。そこに加えて、おっしゃったようなジェンダーの問題もやっぱりあって。これはやはり、男性というジェンダーだからこそ成立するロールにも思えてくる。なので「レンタルなんもしない人」っていうカテゴリーを男性が自分に当てはめて、それによっていろんな活動をするって、たとえ自己欺瞞だとしてもつらい話だなという気もします。けれどもより興味深いのは、この実践が流行るってどういうことなんだろう、というところですね。
あと、東浩紀さんによる「匿名性の自由」の議論。つまり、公共圏に、みずからの名前を明かさずに参入する、というアイデアですね。当時はインターネットが普及することで、自分のプロフィールだとかがネットに「晒される」ことが問題とされていました。で、ある種それのアンチとして、誰でもないものとしてこの世界にいることは可能か、みたいな提案が、そのときはホットなイシューだったんですよね。2000年代後半、僕らが大学生くらいのころ。ただ、おっしゃるように、結果的にはむしろ顕名性を称揚する向きがメジャーになりましたね。
黒嵜:福尾くんの整理した図式に差し戻して、中森さんの言葉と併せて言えば、「するだけでいい」公共圏と「いるだけでいい」生活圏が圧着したことで、「いて応答し続けなければいけない」圏が膨れ上がり、その外に出ることが困難となった状況であると言えるかもしれません。
血縁や地縁に縛られず、自由意志で結んだり解消できたりする近代的な「純粋な関係」、そういった関係のための関係は、つねにお互いに応答責任が求められるので、じつは関係が終わることの危険にさらされ続けている。したがってそれを続けること自体が、過大なストレスがかかるものだ、というのが、最初の立論だったわけですよね。であるならば、「個」のアカウントに全入させられるような状況のなか、「いて応答し続けなければいけない」という、現在のようなコミュニケーション環境の条件では、もはや応答責任の時間的・物理的制限はなくなってしまっている。かつてなく自由に「個」を発信し、関係を結べるようになった他方で、僕たちは自分の立場の一貫性を説明し、関係のための応答責任にフルタイムで追われ、かつてないストレスを抱えている。その疲弊の果てには、揺り戻しもあるでしょう。選べなかった関係、切れない関係の方がむしろ大事、といった旧来の所属への積極的な回帰ですね。
福尾:それが、ナショナリズムとかにどんどん帰っていっちゃうような新反動主義にもなりうるっていうことですね。
黒嵜:その通りです。「とはいえまあ俺日本人じゃん」、「とはいえまあ俺男じゃん」、「とはいえまあ俺大阪人じゃん」……それらは望む望まざるによらず変えられないし、だからこそもっとも交換不可能な関係に思えてくる。実際そうなのかもしれないし。そういった、「個」への疲れと揺り戻しが、たとえばトランプ大統領誕生のひとつの起点になってるんじゃないかとすら思う。しかしこの揺り戻しが皮肉なのは、より端的で強度の高い「コスパの良い」説明原理として選ばれるという点では、応答から降りているどころか、「いて応答し続けなければいけない」環境への適応になっているしまっていることですね。
そこで失踪について、あるいは「いてもいなくてもよくなる」ことの可能性について考えると面白いのは、応答責任そのものから離れるという射程においては、自殺と同様、極端な回帰も応答になってしまうからダメだ、とできる点です。これから失踪するのに説明をしなくていいように、戻ってくるのにも説明責任を追う必要はない。さらに突き詰めれば、人はたんに「いたりいなかったりする」もので、両者が折り合うような理由はなく、関係は空間的・時間的制約のなかにしかない。そんな身も蓋もないことをいかに庇護できるか、というのがトランプ現象みたいなものに対する原理的な抵抗になるのかもしれない。
福尾:まさに『失踪の社会学』で参照される、神隠しという現象についての分析はそういうことですよね。いなきゃいけない場所からいなくなるんだけど、いなくなった理由を隠し神に委託することによって、いなくなられた側、失踪された側の、ある種の共同体的な物語を立ち上げられる。それによって、まあいなくなったけどそういうもんだよね、みたいな納得が生まれる。それが現代において問題なのは、たとえば、死んだ人に対する弔いに該当するようなものが失踪者に対して考えることができるのか、ということですよね。昔だったら隠し神にさらわれたってことにすればよかったけど、いま、いなくなった人に対してどういう物語を立てれば、いなくなられた側も納得できるし、いなくなった側もそれによって自分の責任が免除されたと思えるようになるんだろう、と。
中森:かつては自分が誰だとか、何をしなければいけないのか、だとかいった物語を特定の共同性や、それに近いところにある宗教性など、自分の心の外にあるものが規定してくれていたんですよね。ところが、近代になるとその物語は個人化していって、だんだん自分の心の中、内部に入っていく。決断も、自分の内面で行うものになる。それは「主体」になったという達成でもあるけれども、それゆえのリスクも出てくるわけですよね。つまり、選択に対する不安です。AとBでAを選んだとしたら、Aを選んだことが本当に良かったのだろうか、とか、あるいはAを選んで本当にいいのだろうか。Aを選ぶことによって、こういう損害があるから、Bにしないといけない……などなど。ありえた、ありうる未来に対する応答責任の感覚。それは、ここまでの議論を踏まえるなら「確率的な不安」と言い換えても良いかもしれません。失踪とは、その不安から「降りる」選択肢であるわけですが、他方で「失踪される」ことで今度は当人に近しい人々がこの不安に強くさらされるわけです。これをどうするか。
先ほど福尾さんに紹介してもらった神隠しに関する議論も、この不安に関わるものです。失踪される側が抱える不安は、かつても今も同じものです。ただ、そういう確率的な不安に対して当時は、うまいこと説明してくれる共同的な図式や物語があったはずが、現代になるにつれだんだんなくなっていった。その中途的な段階として、「神隠し」のあとの時代、戦後の日本で流行した「蒸発」という言葉があるわけです。それは、だいたい「妻が失踪して若い男と駆け落ちして不倫してる」みたいな、そういう下世話な物語が付されるもので。逆に言えば、当時は「神隠し」に代わる説明原理として、失踪された不安をそれでごまかしていた時代だった。でもそれはやっぱり過渡期で、80年代になると「蒸発」という語もあまり見られなくなり、「失踪される」ことに意味がうまく与えられない社会になっていくんですよね。この観点から現代に敷衍するならば、「他者が不確定な状態にあることに耐えれない」不安と、「自分がどういう状態かわからない」不安は、表裏一体で生じているものと考えてもよいのではないか。
で、そこで、福尾さんにお伺いしたいのは、「いてもいなくてもよくなる」ために、ここにどう対処できるのかということですね。「確率的な不安」にさらされている状況って、いわば選択肢のうちのどっちかが表に出て、他方が裏になるという関係、ようは図と地の関係みたいなものをずっと考えないといけなくなってるわけですよね。でも、たとえば『眼がスクリーンになるとき』で語られていた主体(あるいは主体以前というもの)のあり方というのは、カメラではなくスクリーン、つまりある意味で、表と裏にあるとわれわれが考えがちなものを、全部表として見るというコンセプトであるように読めたんです。お互いが「いてもいなくてもよくなる」ことを、ここに繋げて考えられるのではないか。
ぼおっとすること、気分のスケール
福尾:さっき黒嵜さんが「個」の疲れと揺り戻しとして、新反動主義あるいはトランプ現象がありうるのではないか、と話していましたね。これは、選べなかったものをある種の運命として自分の中に深く刻み込むということで、僕は反出生主義もそれらと同根の問題だなと思っていて。人とのつながりを作ったり剥がしたりすることが自由になり、それぞれの選択にリスクがともない、自己言及的につながりの理由を調達し続けなければならない状況は、当然かなり疲れる。じゃあもとからある国籍とか、自分が男性であることとかっていうことにかえってくればいいじゃないか、という揺り戻しが起きる。それとある種同じようなものとして、産んだ親を恨むとか、自分が生まれてきてしまったこと、さらにそれを敷衍してひとが生まれること自体に憎しみの感情を向けるといった心性も現れてきているのではないかと思います。
おっしゃる通り、新反動主義とか反出生主義に感じるような違和感と、全部を自分に向けられてた「表面」として捉える、ということは僕のなかでは繋がっている話です。「目の前にあるもの以外相手にしない」という態度によって、反出生主義や新反動主義といった揺り戻しに抗えるんじゃないかと思うんですよね。というのも、そもそも生まれるということはべつに、親の主体的な選択でもなければ、私の主体的な選択でもないわけですよ。なんか「生まれちゃう」わけですよ。なんか生まれちゃうし、なんか死んじゃう。そこには「私」っていうものは存在しなかったし、これからも存在しないはずなのに、反出生主義は、生まれたっていう出来事に私っていうものを敷衍してしまうわけですよね。私とか親とかっていう、人称的なものを敷衍してしまうわけですよね。だから、そこにはなかったはずのものを投影することによって、憎しみや罪責感といったものを生んでしまう。『眼がスクリーンになるとき』における「リテラリティ」という概念によって示そうとしてるのは、まず具体的なものが目の前にあって、そこから主体性というものが調達されるのであって、すでに成立している私というものを、いまここじゃない場所に持っていってもしょうがないですよね、ということなんですよ。それが、解釈というものに対する批判でもあるわけです。
反出生主義や新反動主義、あるいは自分や他者に対する「確率的な不安」に対して、「いてもいなくてもよくなる」ことの糸口は、そのように考えることができるのではないか。書かれてあるものがあって、そこに既存の解釈図式を投げ込んで読み筋を立ち上げるんじゃなくって、まずテクストがあって、それと私が関係するっていうこと自体から始まる何かがあるはず。
中森:なるほど。よくわかりました。いま、苦しんでるひとたちって、目の前のことに集中することに困難を覚えてるんですよね。その端的なあらわれとして、発達障害という概念の流行もあるのだと思うんです。たとえばADHDでいえば、あれはまさに集中が散乱しちゃう状態を指しているわけですよね。そしてASDにかんしては、「自分は文脈がわからない人間だ」という自覚症状とも言えると思うんですけれども、この言葉を前にして自問してしまうのは、「そもそもなぜ私たちは文脈を読まないといけないのか」というところです。福尾さんの話を聞いてあらためて考えましたが、作品だったり映像だったりをそのまま受け取ることが困難になっている状況と、発達障害の概念が拡大されるに伴って、自分が発達障害の当事者であると「自認したがる人」すら現れてしまうことは、パラレルな現象なのかもしれません。「文脈がどこかにあるはずなんだけど、それがわからない」という苦しみですよね。
そこでキーになるのは、目の前のことに集中する、あるいはそのままのものを見るということだ、と。しかし、こうも文脈というものに囚われてしまう私たちは、いかにしてそれを可能にするというのか。これが僕の考えたいことの核心なんですよ。それは「いかに失踪を受け入れるか」という問いでもあります。
ようは、いないものはいないんですよ。どうなってようが。僕だって近しい人がいなくなったら、ついつい、なぜいなくなったのか、とか、本当に生きてるのか死んでるのか、とか考えてしまう。けれども、これは現代的な主体のすごくつらいあり方だと思うんですよね。そのとき「でもいないんだ」と切り替えることのできる、技法あるいは契機はどこにあるんだろう。いちばんの気になるところです。
福尾:その問いについては、おそらく実践的に答えることはできなくって。というのも、こういうふうにすればいない人をいない人として、自分のなかで処理できるようになりますよ、という一般解を出すことはできないと思うんです。
中森:そうですよね。
福尾:だた、いまここにないものに向けて、私というものを持ち出してつらくなったり悲しくなったりしちゃうというのも、もちろん、そうしてしまう人のメンタリティはわかるし僕にもあるけど、そうじゃない自分も、つねにいるはずなんですよね。だから、「こうしましょう」ではなく、「すでにどこかしらそうなってますよね」ということに気づけるような回路をつくることはできるような気がしてて……
黒嵜:ありうる実践的なケースにかなうのか、わかりませんが、少しだけごく私的な話をさせてください。僕、昨年末から今年の1月末くらいにかけて、これまで生きてきた中で最も重い鬱にとらわれちゃって。もうなんにもできなくなっちゃって。Twitterもずっと止めて、ずっと家に引きこもっていたんですよ。
福尾:僕、それで謎の罪責感にとりつかれてましたもん(笑)。僕のせいなんじゃないかと思って。
黒嵜:衝撃的なカミングアウトだ……僕はいったい何をされたのか(笑)。
……とまあ、そんな鬱になる直前に僕がやってたことというのが、芥川龍之介の自殺についての個人的な調査だったんですよね。その過程で、芥川の中国滞在にすごく興味が出てきて、こんな風にコロナが騒ぎになるぜんぜん前に、ちょこっと中国に滞在しに行ったりとか、次の滞在に向けてのコネを作ったりだとかしていたんです。例によって「唯ぼんやりした不安」という言葉にも興味を惹かれて。
そしていつの間にか鬱になった。で、普段は、そんな感じで気分が悪くなったときには、こういうことをしゃべれる友人らと集まって、グダグダ打ち明けては慰めてもらい、そうしているうちに溜飲が下がって元気になるんですよ。なんとも情けない話ですが…(笑)。ところが、今回はぜんぜん気分が戻ってこない。気がつくとどんどん深みにハマっていき、布団からも動けなくなり、いよいよヤバイことも想像し始めた。でも詳細は省いて結果から言うと、その鬱からはひとりで解決して戻ってこれたんです。
では何を試みたかというと——いや、これ、本当ですよ?予定調和のための作話ではないですよ?(笑)——今日起こったことにだけ集中するって決めて日々を過ごしたんですよ。今日には今日しかないことが起こっているはずだ、と目を凝らして生活したんです。でも、特別なことをしたわけでもない。僕がしたことといえば、片付けと、料理と、服を買いに行くこと、花の世話をしてみること。そうすると、あることに気がついたんですよね。たとえば、昨日と同じ料理を作っても……ってこれ、信じられないぐらいユルいこと言ってるけど大丈夫かな……(笑)
福尾:(笑)。
黒嵜:まあいいや、正直にこのまま続けます(笑)。どんなに同じ料理を作っても、毎日で味は細かに違うように感じるし、感じた味に応じて自分の気分が細かに変わる、ということに気がついたんですよ。同じことは、部屋や花の様子にも、服装にも感じました。そこでふと思い至ったのが、「鬱」という語が作ってしまう気分の静止なんですね。自分が「鬱」だと強く捉えてしまう限り、昨日と全く違うはずの今日の気分の動きが、無時間的なべたっとしたものになってしまうのではないか。
つまり、生活という時間は、われわれの判断の「主体」っていうものの形をこうも刻一刻と作り変えてしまうのか、と。この経験則で断言するのなら、こうも言えるのではないか。主体の前には気分があり、その気分は、気分を表現したものでまた作り変えられる。そして、じつは気分の表現ほど、思弁的で難しいことはないのではないか。私にしかできないこと、なんてものはないが、今日しか感じられないこと、今日しか起こらないことはある。私にだって今日はある。したがって、私にも今日しかできないことがある。…といったことをゆっくり捉え直してゆくうちに、いつのまにか鬱も抜けていたんですよね。
鬱のさなかで僕が試したのは、これまで僕がもっとも軽蔑し嘲笑していた「ていねいな生活」だった。そして、経験を経て思ったのが、いわゆる「ホモソーシャルな文化」といったものの弱点です。僕が普段接してる人っていうのは、哲学とか批評とか好きな男子たちが多くて、僕も彼らがすごく好きでたくさんしゃべるんだけど。僕が鬱を彼らに打ち明けると、僕を一生懸命慰めるために、憂鬱な気分の理由を、僕個人の責任問題から免責させて、ある種の集団的な必然としてパラフレーズしてくれるんですよ。もちろん善意でね。いわく「昨今の言論空間のせいですよ」だったり、いわく「批評がおかれている社会的な位置がね……」だったり。3.11以降……95年以降……戦後民主主義……みたいな話にどんどんなっていって。
中森:めちゃめちゃおもしろいね(笑)。
黒嵜:つまりね、自分を含め男性的な言語のひとつの特性として、気分を表現する際に、自分の身体よりも大きい時空間でそれを描き直し、「私」の気分の隠滅を図るというものがあるのではないか、と。そのスケールが大きいものになればなるほど、私の存在に意味が与えられるのだけども、私の気分は自分よりも巨大で固いものに必然づけられる。究極的には、出口は二つとなるわけです。私が変わるとき世界にも変革の可能性が芽生えるのだ、という使命感か、自分がいてもいなくてもどうせ世界は変えられない、という諦観か。ある種の批評というのは、「私」の気分の隠滅を図るマクロな言語表現に取り憑かれながら、この使命感/諦観を気分の表裏に固定して、コイントスばかりやってきたのではないか。
で、芥川の「唯ぼんやりした不安」には、マクロなスケールの私に対する倦怠感こそが表れていたのではないかと読み替えることにしたんですよね。「不安」も「ぼんやり」も、「唯」に留めることが重要だったのではないか。中国での滞在を経たからこそ。……詳しいことはまた、別の機会でちゃんとアウトプットしますが。
で、極端にまとめてしまうと、「いる」と「する」の二項対立的な対比そのもの、二つの応答責任そのものから降りる契機を求めて議論を重ねてきたわけですが、そのなかで提案された「目の前のことだけに集中する」という試みは、僕の場合は、「私」を気分の産物だとして、起きてから寝るまでの「今日」というミクロなスケールで捉え直し続ける実践だったといえます。そして、このエピソードをいま振り返りながら気づいたのは、「いる」と「する」の対比の極端な袋小路として、諦観と使命感のカップリングがあるのではないか、ということですね。
福尾:ちょっと細かい議論になるかもしれないんですが、『眼がスクリーンになるとき』でもそうなっているように、僕が書いてるものなかで一貫して重要なことって、身体より先に知覚があると捉えていることなんですね。この、体あるいは「私」っていう中心があって、それが知覚を生み出しているんじゃなくて、まず知覚があって、それになかば無理やり引っ張られるようなかたちで身体みたいなものが出てくるという図式です。これは僕のなかで、たんに身体論とか知覚論とか抽象的なレベルの問題であるだけじゃなくて、すごく身近な問題としても考えていて。
たとえば、さっき言われたような、今日という一日や、いま目の前にあるものに集中するというのは、その言葉だけを取り出されると、たとえばマインドフルネスの話なんだとして受け取られかねないと思うんですよ。それこそ、ADHD的なものに対する行動療法とか、癒しとかっていうものの可能性として位置づけられる、マインドフルネス。いわゆる多動的なものとマインドフルネスって、それこそ「いる」と「する」が、結局その対立を温存して再生産するように、その図式自体から脱却する契機にはならない気がするんですよ。というのも、マインドフルネスって何をするのかというと、基本的には、自分の体への自覚なんですよ。一時期、寝る前にマインドフルネスのインストラクトをしてくれる音声が聴けるアプリを使ってたんですけど。ひたすら、身体部位の名前を読み上げられるわけです。
中森:知ってる知ってる。
福尾:手のひら、手首、ひじ、肩、胸、脇腹、もも、ひざ、すね…… そういうふうに体を自覚することって、普段ないわけですよね。とくに多動的な社会においては。「する」ことが先立ってて、そこに体がどうついていってるかなんて、自覚する余裕はないわけですよ。だから、マインドフルネスによって、自分の身体がこうであるっていうことを自覚することによって、ある種の安心が得られて、よく眠れるし、多動的な人も落ち着くことができる。でも、それはやっぱり、多動的な社会と共犯関係にある。というのも、マインドフルネスっていうのはビジネスパーソンが効率よく明日も働くためのティップスとして称揚されてもいるわけですよね。
そこで、知覚のほうが先だ、というのを僕が重要に扱っているのは、身体にかえってくるというより、自分の体からどんどん出ていっちゃうっていうことが、まだ実感レベルの話でしかないけど、とても大事に思えるからなんです。べつの言いかたをすると、僕は「ぼおっとする」という言葉の意味を変えたいなと思ってるんです。ぼおっとするっていうのは、自分の体なり思いなしなりに自閉している状態として捉えられるのが一般的だと思うんですけど、僕はぼおっとするっていうのは、いま見ているもののほうに、自分がどんどんへばりついていっちゃうような状態として考えたいんですよね。たとえば僕は、電車とか、乗り物に乗るのが好きで、景色を見るのが好きなんですけど……
黒嵜:どうなってしまうんだ今日は……どんどん話がゆるっゆるに(笑)。
福尾:いつのまにかしゃべり方も子供みたいに……「乗り物が好き」ってね(笑)。
体を動かさずに自分の横を景色が流れていくだけで、本当にいてもいなくてもいいし、いるのかいないのかわかんないような感覚になるんですよね。たまにJRの電車って、在来線でもボックス席になってるやつがあるじゃないですか。自分の対面に誰かが座ってて、横を景色が流れていく。そのとき僕は窓際に座っていて、対面におじさんが座ってたんですよ。僕は進行方向に向いてて、おじさんは進行方向と逆を向いて座ってたんです。電車が動き始めて、なんとなくこうやってぼおっとおじさんを見るともなく見てると、自分が進行方向と逆に向かってるような気がしてくるんですよ。というのも、視線が跳ね返っちゃうんですよ、おじさんを見てると。
これはトリッキーな例だったけど、もっと素朴な例でいうと、リンゴの皮を包丁で剥いてるときとか、自分が回ってるのか、リンゴが回ってるのか、世界が回ってるのかわかんなくなるときがあると思うんですよ。それは、いま私がこういう身体であるということを、知覚のほうが越えちゃってる状態だと思う。とりあえず「なんか回ってる」っていう状態があって、そのあとから、身体とか対象とかっていうものが出てくる。気分にかえってくるという話も、単純にマインドフルネス的な身体回帰の話に回収されてしまうと、多動的な社会との共犯関係から、実際は逃れることができないんじゃないか。だから、僕はどっちかっていうと置き去りにされる体みたいなもののほうに興味がある。で、それはやっぱり「いなくなる」ということと、僕のなかでは強く結びついている。
黒嵜:そう、さっき僕の話でも重要なのは、かつての気分が残した身体の外の痕跡に、いまの気分が左右されるということだからね。今の話をさらに拾うと、あれ…… あと10秒くらい待って。
福尾:大丈夫ですよ。
中森:そのあいだに水を汲んできます。べつに水汲んでるあいだに思いつかなくても大丈夫なんで。
黒嵜:なんか、今日のメンツは優しいな(笑)。
中森:いつも優しいですよ(笑)。
黒嵜:あ、思い出した。一方のミクロな次元では、マインドフルネス的な身体の輪郭の素朴な肯定があり、他方のマクロな次元では、私を確固たるものにする反動的な旧来の所属への揺り戻しがあって、その両方にリスクがある。したがって、そのあいだのサイズでの変形を試みる必要があると言うと、やっぱり僕たちは、すぐさま中間共同体の話だとすぐ思っちゃう。集団って大事だよね、という結論に導かれてしまう。もちろん、その結論自体が問題なわけではないのだけど、中間共同体の提案のはるか手前で、私の輪郭自体の変容可能性に集中する分析軸っていうのを立て直さなきゃいけないくらいにまで、いま、水際まできてるんじゃないかと思うんだよね。私と世界、個と普遍、「いる」と「する」、両者の輪郭が強固にプリセットされたなかで、「あいだ」の中間共同体を考えようっていうっていうロジック自体が、じつはすでに何かのロックがかかっているのではないか。失踪にせよ「いてもいなくてもよくなる」にせよ、対比自体からいったん降りる可能性を考えることで、両者の輪郭を同時にリフレッシュすることを試せるのではないか、と思う。「あいだ」はそのあとではじめて可能性をもつのかもしれない。
福尾:そうそう。だからプライベートとパブリックのあいだに、「ソーシャル」とか「コミュニティ」とか、そういうものを差しはさむんだみたいな議論を、僕自身も、積極的に興味がもてなくて。
失踪と形見
黒嵜:具体的なケースに基づいた分析というと、『失踪の社会学』には実地調査のみならず、「失踪」が描かれた作品分析も試みられていますね。『桐島、部活やめるってよ』(朝井リョウ、集英社、2010年)を扱った箇所は印象に残りました。
福尾:ああ、いなくなった人ですからね、まさに。
黒嵜:いなくなり、つまり応答が切断された状態で、生きてるか死んでるかわからず帰ってもこないっていうことに対して……
福尾:中森さんの本では「曖昧な喪失」と呼ばれていることですね。
黒嵜:曖昧な喪失に対して、急ごしらえで「曖昧な追悼」をしなきゃいけなくなった混乱を描いた作品、といっていいのかな。
中森:難しいですね(笑)。あの作品のポイントって、いなくなったから混乱が起きてるんじゃなくて「いなくなったかどうかすらわからない」っていうことだと思うんですよね。明日帰ってくるかもわかんないし、ずっと帰ってこないかもわかんない。あるいは、本当にそのバレー部を辞めたかもすらもわかんない。もしも桐島がいなくなったことが確定したら、彼をいないものとしてあらたな世界、秩序が構築されるわけですよね。曖昧な喪失の対になる言葉って「明確な喪失」で、ようは死なんです。絶対に失われてしまった、という状況。そのような「明確な喪失」に対して、この作品で書かれた人々の姿がそうであるように、僕の本で分析した「失踪」とその受け止めというのは、「いなくなったかどうかがわかんない」状態に関することですね。
福尾:なんか桐島の話で、ちょっといままでの流れと逸脱するかもしれない、どうなのかわかんないけど思い出したのが、噂の社会的な機能の話かなと思ったんですよ。噂の対象って、基本的にいるかいないかわかんない。少なくともその場にはいないわけですよね。その場にはいない人のことを話すのが噂。で、『桐島、部活やめるってよ』は、辞めたらしいっていう噂、伝聞からはじまる。誰かがいなくなった瞬間を目撃したわけではない。いなくなりますっていう宣言を誰かが直接聞いたわけでもない。でも、なんかいなくなったらしい、っていう噂が混乱を生むわけですよね。僕の本でもちらっと書いてるんですけど、ドゥルーズがおもしろいこと言ってて、社会があってそのなかに噂が流通するんじゃなくて、噂があって社会ができるんだっていうようなことを言ってるんですね。これはどういうことかっていうと、いるのかいないのかわからない第三者の存在が、社会っていうものを基礎づけているとパラフレーズすることができると思うんですよ。だから、常識的に考えると、社会っていうのは、確固としている首長なりなんなりがいて、それによって社会が作られる。そのなかで噂が循環するっていうふうに考えるんだけど、ドゥルーズはいるのかいないのかわからない第三者からはじまって社会が作られるって考える。
中森:フーコーもそういうモデルですよね。パノプティコンなんかまさにそうで。なんで人間が規則に従う、主体化するかというと、最初は親とか具体的な他者に監視されることによって、規則を守るようになるわけですけど、それだと、親がいなくなったときに、規則を守れなくなるわけですよね。そこでどういう方法を使うかっていうと、親や規則を守るルールを課す監視者がいるかいないかわかんない状態をつくりだすことによって、逆に人はルールを守るようになる、と。どちらでもない、という状態をつくりだすことが非常に重要なんですよね。だから、監視者からは見えてるけれども、監視されてる方からは監視者が見えない、という非対称性がポイントになっている。例えば監視体制がそうであるように、いるのかいないのかわかんないっていう状態が、社会をつくるキーだというのは確かなんですよね。
さらに言うと、失踪という状態も一見すると珍しく見えますが、実は人間関係一般に潜在しているものではないでしょうか。大抵われわれはその場にいない人の話をしているわけですし、当人がいま何をしているかとかも、本当はわかんないわけですよね。そういうなかで、逆にわれわれは、想像を働かせて自分たちではない人も含めた社会のことを考えることができるようになってるわけで。ただその他方で気になるのは、難しい話なんですけれど、不在であることの質の違いが、どのような効果の違いを生むかですね。桐島とかフーコーの監視者って、いるかいないかわかんないことによって存在感を発揮するけれど、『失踪の社会学』の最後のほうで思考実験しているような、何も応答してこない、何も責任を果たさなくても許されるような状態って、まるで逆なんですよね。いるかいないかはわからなくなってるんだけれども、それであることで周囲に何も影響しない他者のあり方というか……普通、いなくなると残された人に大きな影響を与えるんですけど、そうじゃないようなありかたはいかなる形で可能か、という話でもあるのかもしれない。
福尾:いるのかいないのかわからないけどほっとける存在っていうことですよね。
中森:そういうことですね。まさに、いてもいなくてもいい、ということ。
黒嵜:物語でいうところの、「モブキャラ」というやつかな。
中森:たしかに、そうとも言えるかもしれない。ただ、いっかい親密になった人って、なかなかモブに見えないじゃないですか。「友達に普通の人はいるか」と聞かれたら、大抵「僕のまわりはおかしいやつばっかりだよ」と言っちゃうと思うんですよね。それは、われわれが周囲の人間に関してはよく知っているからですよね。やっぱり、いっかい親密になったり関係が深まっちゃうと、互いにモブにはなれないですね。だから失踪しても、「たんに今日来てた人が帰った」ということには、やっぱりならなくて。
福尾:僕のなかではなんか、最初に話したような相槌とかって、モブになることだと思ってるんですよ。だから、いかに親密な関係であっても、互いをモブとして扱ってる瞬間っていうのは結構あるはずなんですよね。だから、そういう局面を考えたい。
中森:なるほど。
黒嵜:実は初めてお会いしたときもこの話をしたのですが、中森さんの『失踪の社会学』が出たのと同じ2017年、座間市9遺体事件がありましたね。1人暮らしの男の部屋から、クーラーボックスが見つかって、その中から身元不明の男女合わせて9人分の遺体の一部が見つかったと。それ自体がまず凄惨なのですが、のち明らかになった男による犯行の手口もおぞましかった。男は、どうやら被害人数と犯行時期をみるに、毎週1人以上のペースで殺しては解体して、まるで一連の殺人を仕事のようにルーティーンを組んでおこなっていた人間で。じゃあそのターゲットをどこから調達してたかっていったら、彼はTwitter上で「首吊り師」っていう名前でアカウントをとっていて、Twitterで「死にたい」とつぶやいてる若者を見つけては、片っ端から声をかけて、家出に誘い、わが家へ迎え入れて殺していたと言うんですよね。
そして、肝心なのは9人の身元特定。遺体の損傷が激しく、犯人と被害者たちとの連絡手段が主にSNSであったこともあってか、供述の内容と照合して特定するのに時間がかかり、報道にはしばらくの間、身元不明の男女9遺体があったこと、彼ら彼女らがSNSで募集された自殺志願者であったことのみが大々的に報じられることとなった。これに対し、警視庁に、おそらく失踪者を家族や友人にかかえてる人々から「あの子ではないだろうか」と問合せがあり、それと同じくして、SNS上でも被害者の失踪時期・年齢層・生活圏などといった断片的な情報に心当たりを覚えた人たちが、それぞれに情報を投下し大きく拡散されていました。のち、このTwitterを利用した大量殺人は、厚生労働大臣や官房長官による言及も引き出し、SNS上での自殺にまつわる書き込みへの注意呼びかけの必要性が問われました。ここが、僕がこの事件でもっとも印象に残っている点です。
そのときに考えたのが、再会可能性のことです。僕たちがいま置かれてる情報環境が、2011年以降、仮にさっき話したようなSNS全入時代であるなら、それはいわば「これまで会ってきた人みんなと再会できる世界」を提供しています。かつては、学校を卒業したり新しい会社に入ったりすることで、そのたびに、リフレッシュされていたはずの人間関係。それは再会不可能な人間関係をもつ、ということでもあった。それが現在では、すべての人間関係が友達あるいはフォロワーという名称のもと一元化され、そこにアカウントがある限りは、ひとつひとつの出会いのすべてが再会可能性として、手元に登録されている状態になったわけです。
福尾:人間関係が、蓄積し続ける状態。
黒嵜:そこで気になるのは、非日常なものを想像する契機ですね。これから先も会うかどうかわからないけど、再会可能性だけはずっと手元に何百、何千と担保される状態が続くと、かつてのように、再会は奇跡でなくなる。行きて帰りしことだとか、復活だとかが、奇跡でなくなる。出会いそのものは奇跡かもしれないけど、少なくとも再会は奇跡でない。となると、この環境の日常は何において脅かされるか。それは、再会可能性のひとつだったものが失効していたことを知り、自分が保有している束がまるごとデッドストックに見えてくるような契機なのではないか。もう会えなくなっていたのに、自分は会えると思っていた、という驚きにはとても敏感になっているのではないか。なぜならそれが自覚された瞬間に、自分がストックしていた「再会可能性」の無根拠さがあらわになって反転、「失踪可能性」に見えてくるわけですから。となればときには、「失踪」の認定基準もミニマムなものに迫ってくる。どれぐらい再会していなければ「ひさびさ」なのか。いつから連絡してないか。1週間前か、3日前か……
福尾:単純に、LINEで既読がついたのに1時間たって返信が来ないとイライラするみたいな話として考えたらいいですよね。
中森:そうですね……いろいろと話すことがあるのですけど。じつは僕、座間9遺体事件について考える論考を、ずっと書いていて。そのうち出せると思うんですが。
福尾:楽しみ。
中森:ぜひ、手にとっていただきたいです。
基本的な知識について振り返れば、失踪の件数って、1990年代から2000年ぐらいがピークで、そのあとだんだん減っていってるんですよね。でもその件数って、失踪した人が自分で届け出を出すことはないので、基本的に家族が心配になって何かしらアクションを起こそうと思って届け出を出してるわけです。で、その件数が減っている、と。僕は座間事件について考える論考を書くために、死にたい人たちが集住してるシェアハウスをいくつか取材してたんですけれども。そこに実際、失踪者っているんですよ。死にたい人たちが集住してるシェアハウスだったら、4人中1人か2人失踪者がいても、おかしくはないレベルで。
黒嵜:僕の身近なところでも、思いあたるケースがいくつかありますね。
中森:だから、失踪者って本当はもっといっぱいいるはずなんですけれども、でもたぶん、それが件数ベースで減ってるっていうことをどう考えるか。やっぱりそれは、みんないつでも連絡が取れると思い込んでることに因るんじゃないか。本当は失踪してたり死んでるかもしれないんだけれども、いつでも連絡が取れるからいいや、みたいな感じになってる側面が。しかし他方では、既読がつかないだけで不安になるわけですよね。いつでも連絡がとれるっていう可能性が担保されるからこそ、逆にそういう不安も喚起してくると。で、おそらく座間事件がわれわれに与えた衝撃っていうのは、考えないようにしていたその不安が、一気に可視化されてしまったという点なのでしょう。悪い方の結末の方が、一気に表に出てきてしまった。
僕はこれまでも、失踪者の家族にたくさんインタビューしているんですが、彼ら彼女らが語るのは、なんというか、失踪の原因を何かに託す内容が多いんですよね。たとえば、僕が聞いたエピソードだと、船のなかで失踪したっていう人がいて、客観的に考えれば、それは当人が海に身を投げたようにも思える。でもその家族たちは、船に乗り出した足跡みたいなものがなかった、と話をしていて。そこで、家族たちは、船上での出来事だから、失踪者は北朝鮮に拉致されたのではないかという可能性について語るんですよね。もちろん本当に拉致されてる可能性もありますが、ともかくそういう話を聞いていると、いたたまれなくなってくるわけです。政府に拉致被害者であると認定された失踪者とは別に、「特定失踪者問題調査会」という、北朝鮮に拉致された可能性を排除できない人たちの調査をする組織があるのですけど、そこには数百人もの失踪者が登録されている。おそらくその中には、僕の感じるところでは、失踪された家族が、何らかの失踪の「答え」を求めて、一縷の望みを託して登録したケースもあるのではないか。近しい人がどうなっているのか、帰ってくるのか分からないっていう状態は、いろいろな想定を喚起しちゃうんですよね。座間事件では、一気に、そのなかでも悪い方の結末が顕在化してしまった。この事件で問い合わせてきた人々のなかにも、先に紹介したような意味で、失踪の「答え」が欲しかった家族もいるんじゃないかなという気がしますね。
たとえば大阪府ってすごくホームレスとかが多い所で、身元不明の遺体も多く見つかるんですけれども、その遺品などを開示して、「これらに心当たりないですか」と情報を募る催しを定期的にやってるそうです。そこへ、私の夫いないかしら、と夫に失踪された妻らしき人が来て、ああいなかった、と去っていく。その遺品の中に夫が含まれていてほしかったような気もするし、含まれてなくて安心した気もするような、そんな微妙な感情で来て帰っていくんだと思うんです。
黒嵜:友人に、10年以上前に渋谷で「渋家」というシェアハウスを立ち上げた、齋藤恵汰という男性がいて。いま、引っ越し資金を集めようとクラウドファンディングを立ち上げて、緊急の宣言書みたいなものをネットに上げているのですけど、僕が見てて驚いたのは、代表者の齋藤くんの名前が見当たらないことだったんですよね。いない人になってるんですよ。これはとても面白かった。過去の在籍者たちや法人化した事業の関係者も含めると、おそらく渋家のコミュニティは数百名の規模を抱えているんですが、見ている限りでは齋藤くんが記名されてないことにも言及されていないことにも、誰も文句を言っていない。というかいまだに出入りする齋藤くんを、知らない人すらいる。まさに「いてもいなくてもいい」ひととして扱われてる(笑)。
そんな齋藤くんに連れられて渋家に遊びにいったときに、彼から聞いた話が興味深かったんです。渋家は定期的に代表を交代するんですが、いま引っ越そうとしているコミュニティはKENTさんの代以降のものらしくて、つまり齋藤くんからはもうひとまわり以上若いんですよ。で、そうなってくると、彼ら彼女らのあいだで、発起人をはじめとしたかつての在籍者たちの痕跡をどうするか、あることが争点になったらしくて。それが、2階リビングの本棚の処分について、なんですね。
結果からいうと、現住のメンバーが壁一面を覆わんばかりの本棚と蔵書をまるごと撤去したんですよ。渋家の2階リビングって、事実上の公園みたいな場所になってる部屋で、いっつも知らない人がひっきりなしに来ていた場所だったんですよね。初めて僕が案内されたのもそこで、そのときも深夜にもかかわらず次から次へ訪問者がきていました。いわば本棚のあった2階リビングは渋家の顔のような部屋でした。その部屋に入ると、誰か客なのか住人なのかわからない雑然とした空間のなか、とくに挨拶もないまま座って、隣り合った人と気づけばボソボソ会話を始めていた。そして齋藤くんによれば、この本棚は「過去の在籍者の本は捨てない」という、それまでの渋家ルールの象徴物でもあったそうなんです。で、それが撤去されて、壁が見えて視界が開けた部屋になった。
そうなってから一度だけ渋家に遊びにいって驚きました。リビングが「住人の生活空間」になっていたんですよね。リビングの中心に置かれたテレビが点けられていて、その前に机がおかれ、そこに住人の男女が集合してご飯を並べて「いただきます」と団欒している。団欒の時間もあれば、消灯の時間もできている。部屋に中心ができて、住人の生活圏と客人の行動圏にきっぱり境界が引かれている。住人間にも、客人と住人の間にも、客人間にも挨拶がある。口にすればするほど当然のことなわけですが……(笑)客人として現れてしまったことで住人である彼ら彼女らになんとはなく緊張を与えているのを感じ、それで僕も緊張し、所在なげになったことで気づいたんですよね、あの本棚は住人も客人も「モブ」になれる、隠れ蓑のように機能していたのではないかと。
初めて渋家に遊びに行ったとき印象的だったのは、部屋に中心的な「団欒」がなく、それぞれに本棚を背にし、本を読んだり、パソコンを触ったりしていて、会話している人たちも個々に小さな島を作っていることでした。シェアハウスがたんに「同じ家に暮らすこと」だといっても、そこで営まれる「擬似家族」の形態はさまざまです。一時期の渋家は、2階リビングがあの本棚とセットであることで、誰もが「いてもいなくてもいい」空間であったのではないかと。それは生活上の困難が多大にあっただろうし、固定的な住人の生活を考えれば絶対に現在の方がいい。それは間違い無いのだけど、あの空間はここまでで話されてきたような、応答責任から個々人が片足ずつ降りることを許す条件を、無意識のうちに満たしていたんじゃないか。住人たちの残置物を集めた本棚の達成として、齋藤恵汰を含め特定の誰かを家長と「しない」、共住しながら失踪し合うようなコミュニティがあったのではないか、と。
中森:なるほど。「いてもいなくてもいい」ようなシェアハウスにするために必要なものがアーキテクチャやインテリアであるというのは、すごく示唆的ですね。
黒嵜:これは福尾くんの話にも出てきた「ぼおっとしている」姿と、その効果のひとつなのかもしれません。部屋を覆わんばかりの本棚があり、その周囲で何かに没頭してるように見えるだけで、応答責任があるシェアメイトと、それが不明な訪問者の、どちらでもあるような存在になれる。
中森:本棚に収められた本が、過去の在籍者たちの残置物だという点も重要ですね。人が本を残していって、その本に残った人が没頭して、けれども本を置いた人の方に意識がいくわけではなくって。ただ、その残ったものによって何かが受け継がれていく。「いる」と「する」を二分する図式を解体する手段・契機として、失踪すること・されることについてこれまで話してきたわけですが、当人同士のコミュニケーションとは別の、あいだに置かれた「モノ」の次元もこれに作用してくるのでしょうね。なぜ人は「形見」を残すのか、という問いに繋がるように思います。
渋家で撤去された本棚というのは、いわば形見ようなものに近かったのかもしれません。ポイントは、人の代わりに応答してくれるモノを残す、ということですよね。自分ではない、外化してる何かを。
黒嵜:素晴らしい指摘です。なるほど、形見か……『失踪の社会学』を読んだときに、僕が考え込んでしまったのは未練の問題でした。「あの人は帰ってくるかもしれない」「連絡を返してくれるかもしれない」という期待をどこで終わらせ、曖昧な追悼に至れるというのか。原理的には未練を終わらせる必要がないというのに。コミュニケーションの環境においても、個々の失踪の局面においても未練を終わらせる局面が逸されてるなかで、切断的であれ段階的であれ、どのように未練を決着させるのか。そういった事例を個々に扱った本だとして読んだんです。そのひとつに、形見を残すという、モノで未練をせき止める方法もある、と……
近ごろいくつかのYoutuberたちによって、「ミニマリストのススメ」のような動画もよく見かけるようになりました。 モノを積極的に手放して生活を「最適化」された様式と称揚する向きと、他方でコンマリ的に一個一個のモノたちへ供養するように感情を向ける断捨離が、同時にミニマリストの実践として称揚されているのは、「未練」に囲まれた環境であることの表裏を示唆しているのかもしれませんね。
中森:僕は、失踪において倫理的なことを考えてるんですよね。つまり、めちゃくちゃ簡単に言ってしまうと、失踪することは許されるのかどうか。この場では「いなくなってもいいじゃん」みたいな話をしていますけれども、でも当然、実際に失踪されたら大変なわけです。働き手がいなくなったら一気にお金もなくなるし、子どもがいなくなったら、親はいてもたってもいられなくなったりする。にもかかわらず、残された者に対して、まったく応答せずにいるような権利というものが人にありうるのかっていうことを、考えてるわけなんですれども。
そのときに、こんなふうに考えちゃいけないのかもしれないですけど、でも実際のことを考えると、何も残さずに失踪していった人って、あまりにも贅沢だと思うんですよ。不均衡がすぎるという意味で。その不均衡を埋めることはできないのですが、それでもせめて失踪者が何かを残していったとしたら、残された人たちにとっては、それが代わりに応答してくれるものになるのではないか。失踪が許される倫理を考えるのと同時に、失踪者に求められる倫理として、それぐらいのことは要求してもいいんじゃないか、とも思います。たとえば嘘でも構わないから書き置きがあるだけでも、ぜんぜん違うんですよね、残された方にとっても。
福尾:えっと、さっきの本棚の話で、黒嵜さん、ミニマリストっていう言葉をちらっと出されましたけど、ミニマリストってようするに部屋になんにも置かなくなるわけですね、極限まで。で、そうすると空間に逆に余白がなくなっちゃう。なにか、なんていうか、なんていうかな。「したりしなかったりする」っていうことを許してくれるものが何もなくなるわけですよね。可能性が無くなるから。本棚があると、本を読んだり読まなかったりできるし、クローゼットにいろんな服があると、これを着たり着なかったりできる。でも、本当に何もないと、いることしかできないし、あるいはパソコンだけがあって仕事をすることしかできない、みたいなことになるわけですね。ものが無くなることによって空白が無くなるっていうのは、なんかおもしろいなって思います。
さいきんすごい空間に興味があって。美術批評を書いててインスタレーションっていう空間芸術について書くことがあるんですけど。いちばん困るのが、理想的な視点がないんですよ。インスタレーションって。絵画だったら正面から見たのが理想的な視点だし、映画も席に座って、2時間半なり2時間なり見ればいちおうひととおり見たことになるけど、インスタレーションって「ひととおり」っていうものが原理的にはないんですよね。っていうのは、その空間の中に入って歩き回るっていうことの全体が鑑賞体験だから、人によって、そこに置いてあるオブジェを見る順番も違うかもしれないし、なんとなく作者の側が想定している順路みたいなものはあるかもしれないけど、それをみんなが同じようにトレースするかどうかっていうのはわからないわけですよね。だから鑑賞のありかたの複数性がインスタレーションには埋め込まれていて、そういうものを批評するときにどうやったらいいんだろうっていうのにすごく強い問題関心があって。
で、それと、またいろいろ話がとっ散らかっちゃいますけど、最近その、「デコイ」と「ルアー」っていう対概念を考えてて。デコイっていうのは囮のことですね。私がここからいなくなったっていうことを誰かに悟られないために私とそっくりな何かを置いて逃げる。だからデコイ、囮っていうのは、自分がどっかに逃げるための道具なんですよ。それに対してルアー、疑似餌っていうものは、誰かを私のところに引き付けるための道具ですよね。魚を釣るときに、魚の餌に似た何かをそこにぶら下げとくと、魚が釣れる。フィッシング詐欺的なものですね。だから、何かを捕まえるための道具と、逃げるための道具っていうので、ルアーとデコイっていう対概念を考えることができるなと思ってて。で、そのルアーっていうものがつくる関係性っていうのは、私とあなたとか、私と餌っていう、点と線なんですよね。でも、デコイがつくる空間性っていうのは、たぶんそういうものに収まらないような気がするんですよね。っていうのは…… どういうふうに空間の話にかえったらいいか、いま、自分で想定してた経路を見失ったんですけど。
中森:そろそろみんな疲れてきてますよね。聞いてるほうも疲れてきてると思うんですけれども(笑)。
福尾:……思い出してきました。インスタレーションの空間って「オブジェがたくさんある空間」じゃないと僕は思うんですよ。「何がオブジェかわからない空間」がインスタレーションだと思うんですよ。鑑賞者は、ここにはこういう空間が広がってて、こことここに見るべきオブジェがあるって最初からわかって入るわけじゃないんですよね。入って見回していくうちに、あ、あれはなんか、ディスプレイのなかに映像が映ってて、あれは確かに見るべきものだろうとか、でもこのディスプレイはなぜ壁に掛かってなくて床に寝かせられてるんだろう、みたいな。何が作品かわからない、何がオブジェかわからないっていう空間を、歩きながら自分のなかでその作品経験がだんだんとこう、秩序だっていくわけですよね。だからオブジェがあって鑑賞がはじまるんじゃなくて、まず鑑賞をしているうちに、だんだんとオブジェっぽいものが自分のなかで、ああ、あれはオブジェとして考えていいんだ、みたいなものがわかってきて、で、それで自分の鑑賞体験みたいなもののまとまりが作られるわけですよね。
えっと、絵とか映画とかっていうものを論じてるかぎりにおいては、「私」っていうものを記述からなくすことができるんですよ。っていうのは、そこにもう、見るべき全体が最初からあって、オブジェがオブジェとしてかちっとあるから、全部客観的な記述ですませることができないわけじゃないんですよね。ただ、インスタレーションはそれができない。主観的なものはどうしても入ってくる。空間的な広がりもあるし、何がオブジェかっていうことを見つけることから鑑賞がはじまるから。ただそこで、逃れようもなく持ち出さなければいけない私性をルアー的なものじゃなくてデコイ的なものにしたいっていうのが僕の意識です。ルアー的なものにしてしまうと私はこうこうこういうふうに見ました、そしてそれは本当のことです、っていうふうに当事者性に居直るか、もしくは客観的であるかのように書くっていうふたとおりが考えられますよね。でも、それどっちもあんまりとりたくないと思ってて。経験としての「本当」と知としての「本当」の二者択一になって、テクストがルアーになって、書き手が超越化される。そうじゃなくって、私っていう、ある種のデコイを動かして使うことで、インスタレーションの全体像みたいなものが浮かび上がってくるような書きかたをしたいと思ってて。でもそれは、「本当の私」である必要ないわけですよ。私っぽければ、私だと思ってもらえるので。小説における語り手みたいなものとして、批評の主観性を考えられるんじゃないか、みたいな。客観性は空間のほうに託すことができるし。それには、やっぱり空間経験が先立ってて、作品っていうオブジェが先立ってるわけじゃないっていうこと。まず知覚があってそこから対象と体が出てくること。それと、その、だから、部屋にいろいろものがあるっていうことは、オブジェになったりならなかったりするっていうことだから、それによって、空間のなかで余白をつくることができるっていうこと。そしてそのときにはモノが、未練を断ち切る形見になりデコイになっている。
中森:なるほど。そろそろまとめに入りましょうか。
いまの話と連関するのは、いるでもいないでもない状態でいかに平気でいるか、という議論のなかでキーワードとして出てきた、目の前のことに集中する、目の前のものをそのまま見る、という言葉ですね。こう言葉にしたときにまず思い浮かぶのが、自己の身体に集中する、という意味でのマインドフルネス的な実践ですよね。でも僕、それだけでうまくいってる人、マインドフルネスで劇的によくなりましたっていう人、あんまり見たことがないんですよ。たとえば結果的に瞑想に目覚めてお寺に入った、という人なら、上手くいってたりするんですけれども。自宅でマインドフルネスして鬱が治るかといえば、僕はそうじゃないと思う。多動的な社会とマインドフルネス的なリフレッシュがセットなのはここまで繰り返された通りです。
では何が重要なのかというと、それは集中の方向で。自己に集中するんじゃなくて、外のものに集中する。外のものを見る、ただ見るということによって「いるでもいないでもない」状態に平気でいられるのではないか。表裏なくオブジェ、形見、書き置きを見ること。それは他者の痕跡的なモノであり、それははさらに、ルアーじゃなくてデコイである必要がある。ルアーでは他者への執着を喚起してしまうので、よくないわけですね。
福尾:たとえば「探さないでください」っていう言葉がどう機能するかっていうことですよね。ああ探さなくていいんだとリテラルにはなかなか思ってもらえない。
中森:それは、たぶんルアーになっちゃうんでしょうね。だから、そのへんの答えはすごく難しい。あるいはそれは、答えかたの問題ではなくて、捉えかたの問題なのかもしれない。そういう、囮を用意するっていうテクニックとしての失踪って、いちばん理想的なのは、まったく自分と同じものを置いて、自分だけどこかへ行くことだと思うんですよ。それですべて解決するじゃないですか。ただ、結局そんなことは不可能なので、それに近いことを考えないといけないわけですね。デコイとしてのモノがいかに可能かっていう問題と、残された者がいかにそれをデコイとして見るかという問題。このふたつが重要になってくるでしょうね。
何ものかに執着してしまうときに、それをルアーとして見るか、あるいはデコイとして見るかって、ぜんぜん効果が違ってくる。たとえば、摂食障害に悩んでる人が、美味しい食べ物を見たときに、それをルアーとみなすか、デコイとするかで、展開が変わってくると思うんですよね。目の前のものに集中するというときに、裏があるものとして見てしまうことと、見たままに表面しかないものとして見ることという、ふたつの形がある。後者であるデコイには、執着の対象自体を変える契機が宿っているのかもしれません。
そして、これはべつに失踪に限ったことじゃなくって、たぶん、われわれの日常生活においてもありふれて現れているものだとも思います。
プロフィール
中森弘樹(なかもり・ひろき) 1985年生まれ。立教大学21世紀社会デザイン研究科助教。専攻は社会問題/社会病理学で、単著に『失踪の社会学:親密性と責任をめぐる試論』(慶應義塾大学出版会)がある。近刊に「「密」への要求に抗して」(『現代思想』2020年8月号、青土社所収)。
twitter @surippa_krhrmkn
福尾匠(ふくお・たくみ) 1992年生まれ。現代フランス哲学、批評。著書に『眼がスクリーンになるとき:ゼロから読むドゥルーズ『シネマ』』(フィルムアート社、2018年)がある。「ポシブル、パサブル:ある空間とその言葉」(『群像』2020年7月号、講談社)では本鼎談で話されたことを受けて空間論、言語論として展開している。
twitter @tweetingtakumi
黒嵜想(くろさき・そう) 1988年生まれ、批評家。音声論をテーマとし、雑誌の編集やイベント企画など多様な評論活動を自主的に展開している。活動弁士・片岡一郎氏による無声映画上映会「シアター13」 を企画、声優論「仮声のマスク」を批評誌『アーギュメンツ』に連載、Vtuber 論 を『ユリイカ』2018年7月号(青土社)に、バ美肉論をWebメディア「Rael Sound Tech」に寄稿。また、学術雑誌『想文』第一号には 「波線にさまようイドラー仏教音楽声明試論ー」を寄せ、インド仏教最高指導者・佐々井秀嶺氏の来日講演では聞き手を務めた。ほか、『アーギュメンツ#2』編集、『アーギュメンツ#3』を批評家・仲山ひふみと共同編集。
twitter @kurosoo
協力:藤村南帆、首塚
*「ひるにおきるさる」は読者からの投げ銭を次の記事の制作費にあてています。くわしくはこちらをご覧ください。応援くださる方はぜひ投げ銭もよろしくお願いいたします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?