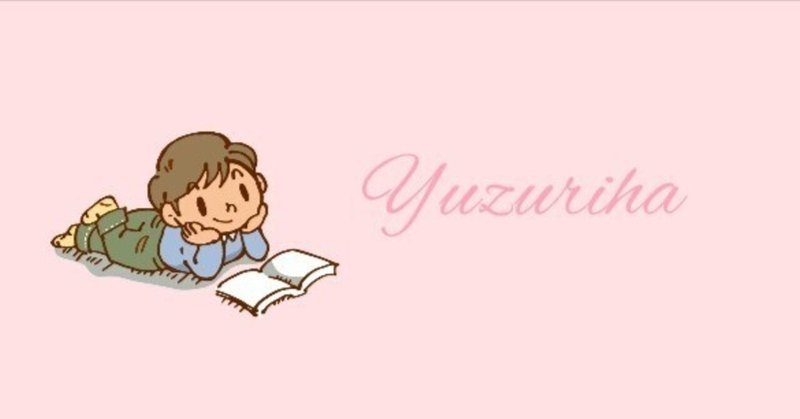
生きるための潤い
『東京余情~文人が愛した町々~』 (1982年) と題された本が、数年前に古本でやっと手に入った。様々な文士による、嘗ての東京の風景を写し取ったエッセイ、短編小説、はたまた対談が一冊に収められている。
この本を知ったきっかけは、どなたかの Twitter の書き込みだったと思う。2018年に亡くなった女優の江波杏子さんのお気に入りの本で、江波さんが知り合いの舞台演出家にこの本を貸した所、そのまま手元に返ってこなくなり、たびたびの催促も虚しく江波さんは亡くなってしまった。その演出家は、江波さんの葬儀にこの本を持参して遺族の方に返すつもりであったが気持ちが変わり、形見として戴けないか?? …… と尋ねると、ご遺族に快諾された…という。
江波さんはこの本について「昔の人の人情がいいのよ」ということを仰っていたらしいが、自分などもこういう本が大好きだ。日頃、今の町並みのつまらなさにガッカリしているので、こういった書物で昔の東京を頭に思い浮かべ、その世界に浸ることはとても楽しい。
古い日本の映画を好んで観るのも同じ理由がある。
どうやら自分は置いていかれた人間らしくて、他にも例えば、外国の小説の最近の新訳にも中々馴染めない…ということが判明してきた。つまりは、中身が同じ小説の同じ筋だとしても、今の言葉に置き換えられると自分はすぐに拒否反応を示し、こんな言葉のセンスだったら、もう読みたくない!! ・・・ と投げてしまうのだ。
新訳を発行…という動きは大歓迎だけど、肝心の文章がああいうのなら「もう結構!!」…となってしまう。
町の描写…ということで、 “あれは良かったな…” と今でもすぐに浮かんでくるのは、永井荷風の『濹東綺譚』。この小説 (…という言い方は何となくシックリ来ないが) は20代か30代の頃、友達の家に泊まらせてもらった時に知った。その友達の本を借りて、帰宅してから読んでみたところ大変気に入り、すぐに自分用にも買ったことをよく覚えている。
『濹東綺譚』の雑誌か新聞の連載時に挿し絵を描いた人……度忘れして名前が出てこない…。その方の東京の町のエッセイもとても良かった。特に、特飲街であった深川 洲崎 (元は遊郭) の様子が興味深かった。
日頃埋められない、潤いのある町への欲求は、このような種類の本に接することでしか満たせないようだ。

※[追記]
不精して確かめなかったが、『濹東綺譚』の挿し絵を描いたのは木村壮八で、本のタイトルは『東京繁昌記』でした。(5月16日--7:44)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
