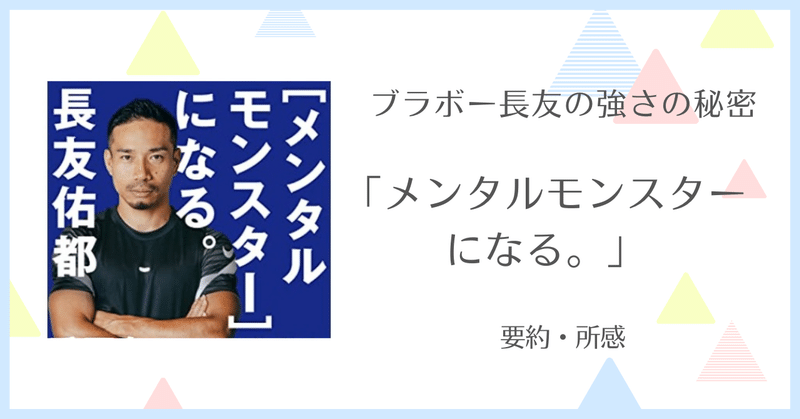
ブラボー長友の強さの秘密「メンタルモンスターになる。」要約・所感
おはようございます。本日は長友佑都選手著書の「メンタルモンスターになる。」をとりあげたいと思います。
長友選手といえば昨年のカタールW杯での活躍が記憶に新しいですね。日本人最多、自身4度目W杯出場でした。フィールドプレイヤー最年長としてチームを牽引していたのが印象的です。世界的ビッグクラブであるインテルで7シーズンプレーした一見華やかな経歴ですが、長いプロ生活すべてが順風満帆ではありません。
特に2014ブラジルW杯後の失意、今回のカタールW杯予選で起こった日本代表レギュラー争いでの「長友不要論」。多く逆境を経験しましたが、強いメンタルでそれ跳ね除けて結果へと繋げました。
長友選手自身メンタルは先天的に持って生まれるものではなく、誰もが身に付けられる技術であると説きます。本書は経験談とともにそこから導き出したメンタルスキルに触れることが出来ます。スポーツだけでなく多くの人の人生で活きるスキルだと思いますのでここにまとめておきたいと思います。
1.メンタルモンスターになるには
・ネガティブをポジティブに書き換える力
人は失敗するとどうしてもWhy?ばかり追求してしまいます。なぜあそこでミスをしてしまったのか、もちろんそれは大事な作業ですがそればかりでは中々前に進めません。
それはいつまでもミスや批判に囚われているのと同じ。どこかでスイッチをHowに切り替える。どうすればあのミスを防げたのか、大切なのはそのスイッチであり、インテル時代の長友選手の場合は車を運転することだったそうです。
イタリアでは自分ミスで試合に負けた際はサポーターから街なかで直接批判されることもしばしばありました。勝利を願ってくれる人の厳しい声を真摯に受け止め、反骨心のエネルギーにする。実際、批判の中にHowのヒントが隠れていることもあったそうです。
日本代表で「長友不要論」が話題になったときはyahooニュースでの自身の批判に溢れたコメント欄も見るようにしていたそうです。
「見たくないもの」をあえて見る→受け入れる。これが重圧との戦い、ネガティブをポジティブに書き換えるための第一段階なのです。「批判やミスの中に成長のチャンスがある」これは長友選手の信念だそうです。
ミスや批判のたびに、そこからHowを探してポジティブに書き換え続けた。その経験こそが強靭なメンタルを築き上げていったのです。
・自信と過信の違いとは
2014年ブラジルW杯は本田選手らと優勝を公言して臨み、一勝もできずに敗退し屈辱を経験しました。その時を振り返り当時の自信は過信であったと語ります。
臭いものに蓋をして、自分を都合の良いものだけで囲み「俺ならできる」と思い込んでも、それは自信ではなく過信にすぎない。
戦う重圧と不安、相手の脅威と恐怖に真剣に向き合った後しか本物の自信は生まれません。過信は僅かなプレーの違和感でもすぐにブレるもの。一方で本物の自信は予期せぬ展開でも簡単にはブレないといいます。
・ピュアだからこそ、受け入れ学べる
若い頃から代表で長谷部選手や本田選手に「ピュアすぎる」といじられていたが、本当に自分自身でそう意識しはじめてたのは、後輩である久保選手や堂安選手からも言われてからでした。
自己分析によると「まず言葉を疑わないこと」。サポーターにしかりネットのコメントにしかり、その言葉の主が誰であれ、まずはストレートにその言葉を受け止める事ができる。
もちろん全てを受け入れるわけではないが人から言われたことを一回試す価値はあるなと考えるタイプなのだそうです。
代表でもライバルである後輩の中山選手にもどうすればもっと良くなるのかアドバイスを求めていたといいます。「批判は僕にとってガソリンです。」そうまでインタビューで答えられる選手は中々いないでしょう。
純粋さはメンタルに「硬さ強さ」だけでなく「しなやかさ」をもたらします。これはメンタルモンスターの条件ともいえそうです。
2.経験を重ねて培ったスキル シーンとストーリーに分けて考える
2021年はW杯最終予選、日本代表は初戦のオマーン戦に敗れて一時は出場が危ぶまれるくらいの窮地に立たされていました。チームや監督に対する世間の批判も高まり、加えて「長友不要論」は熱を帯び増していた。
この時期、長友選手は常に重圧と批判を心に抱えて過ごしていました。そんな逆境をも、自身でも年齢を重ねたから出来たと後に分析するある考え方によって克服していきます。
それは「シーンとストーリーに分けて自分の人生を捉える」という考え方。シーンとはまさに今目の前で起きていること、直面している現実。そのシーンを連続していったものがストーリー。今の自分と未来の自分、常に2つの視点を持つことを心がけること。
苦しいことはどうやっておきたのか、その先にどうなっていったのか。長友選手にはこれまでに数多の逆境を克服した経験があり、自分の頭の中でストーリーを描く力がどんどん上達していったのです。
こういうことが起これば、こうなるというのが見えてくる。散々語られる批判もこうすれば好転する。シーンだけに見ていると気が滅入ってしまうが、ストーリーを想像することで眼の前のシーンはそのほんの一部でしかないことが分かる。30代に入ってからはどんな重圧や不安があってもこれはストーリーの一部だと考え前に進むことが出来たそうです。
3.カタールW杯での振る舞い ベテランの役割
これは本書の内容にはありませんが、今回のW杯での長友選手を見ていて思ったことを残します。最年長としての振る舞いは、間違いなくチームに欠かせないものでした。
試合以外の様子は日本代表公式のyoutube「Teams Cam」でW杯期間中の代表での活動、舞台裏を見ることができます。
日本人最多4度目の出場の大ベテランといつ立場での出場。はじめてのW杯出場の後輩が多い中で、率先してチームを鼓舞して舵を取り、雰囲気作りに徹していました。
長友選手曰く自分が初めて出場した大会では当時のベテランである中村俊輔選手や中澤佑二選手がそういう役割を担っていたそうです。その伝統を自分の形で引き継いでいたのです。
弱る毛根に鞭をうって髪の毛を日の丸色に赤く染め、ゴールが決まればベンチから真っ先に飛び出し得点者に一番に駆け寄る。極めつけは「ブラボォーー!!」。一番の経験者がW杯で一番は熱くはしゃいでいる。ベテランのそんな姿を見て後輩たちも熱くならずにはいられないでしょう。
日本代表がベスト8の壁を打ち砕くという明確なストーリーを描くことで、そのために今の自分(シーン)に何ができるのかを考え抜いた上での振る舞いであったと思います。
若手選手にもイジられるほど汚れ役を買って出て積極的に話しかけやすい状況を作ります。ベテランに対して意見が言いやすいチームは団結力が生まれます。
このような姿は仕事におけるチームづくりにも有効ですね。上下関係や地位に囚われず、若手が活躍しやすい状況を作るのはベテランの大きな役割であると思います。
本書からは仕事でミスしてしまったときや批判を受けたときの向き合い方を学ぶ事ができました。それこそ、若い頃は先輩や上司の助言や叱咤激励、いい意味での批判を受けながら目の前のシーンに必死であったと思います。
しかし30も半ばの今、時代もありますが若い頃のようには批判されにくくなっていると最近は思います。そんな時に頼れるのは自分自身を俯瞰で捉える目と成長の未来を描くストーリーの力であると思いました。
いきなり長友選手のようには行きませんが、自分のできる範囲で行動に変えていければと思います。
興味を持った方は是非とも、手にとって呼んでみてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
