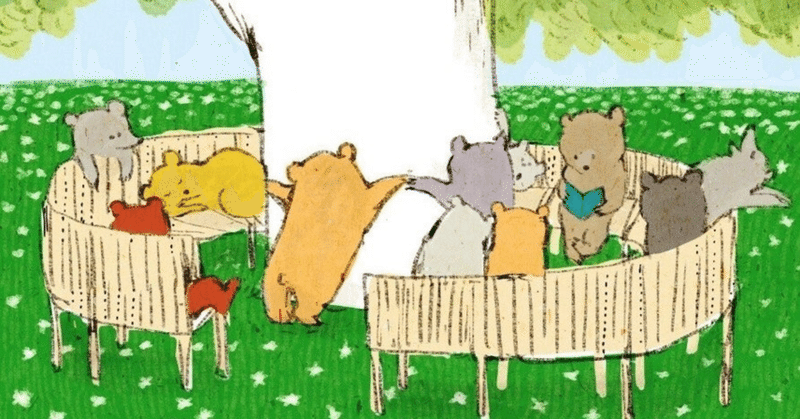
労働者協同組合を考える#3 「オキュパイと協同組合」
2022年秋に法律が施行されて設立が可能になった「労働者協同組合」について考えている。
一つ目の記事は、日本の労働者協同組合法にも定められている3つの基本原理について書いた。2つ目の記事には、17世紀にカリブ海を荒らしまわった海賊たちと労働者協同組合の共通点について書いた。
ただ、少し先走り過ぎたような気もしている。
労働者協同組合がなぜ注目に値するのか、僕自身が関心を寄せている理由を探りながら、あらためて考え直してみたい。
世界的な抗議行動
2011年は、多くの日本人にとっては、東日本大震災の年として記憶されていると思う。一方、日本の外に目を向けてみると、主に若い世代の人たちが中心となって、各地で大規模な抗議運動が展開された年だった。
チュニジアでの革命を発端にしたアラブの春、スペインでの広場占拠(15M)、ギリシアの大規模デモ、そしてニューヨークでオキュパイ・ウォール・ストリート(OWS、ウォール街を占拠せよ)が起こるに至って、そこから、資本主義、特に新自由主義に対する抗議行動が世界中に飛び火した。
当時はまったくと言っていいほど関心がなかった。なんといっても震災のことが大きかったし、事業も3年目で顧客も増え始めた頃、遠い海の向こうのことまで気が回らなかった。
でも、この一連の出来事は、現在に多大な影響を与えており、10年以上が過ぎた今でも振り返ってみるには遅くない。
キア・ミルバーン『ジェネレーション・レフト』(堀之内出版)では、2008年の金融危機の経験が、2011年の抗議行動の類を見ない規模につながったと分析されている。
世界的な経済危機によって、市場原理に任せれば経済成長ができて、社会全体が豊かになるという新自由主義の嘘と限界が明らかになり、世代間の格差(人生において保有できる資産、生活水準、成功のチャンスなど)がはっきりと可視化した。若い人の生涯見込み収入は、親の世代を超えられない。奨学金の返済を抱えているのに仕事がない。給与水準に対して不動産価格が高く、家を持つことがますます非現実的となっている。
現在のシステムの恩恵を受けられない若い世代が中心となって、世界中で大規模な抗議行動が展開された。
オキュパイと協同組合
OWS(オキュパイ・ウォール・ストリート)の特徴は、直接民主主義と水平主義だ。代表者の議論によって物事を決めるのではなく、誰もが参加し意見を表明できるジェネラル・アセンブリー(総会)で意思決定をする。指導的リーダーは存在しない。
もちろん、アセンブリーが機能しない場面があったことも、内部で対立が起こったことも、OWSに参加した人たちの証言にあるし、ニューヨーク市による強制排除により、開始から2カ月で占拠地であるズコッティ公園からの退去を余儀なくされ、OWSは目に見えるかたちでの社会制度変革は起こすことができなかった。
だからといって、2011年は失敗だったというわけでもない。この出来事はその後も形を変えながら、いくつもの波(たとえば、バーニー・サンダースやジェレミー・コービンなどの左派政治家の予想外の躍進など)を引き起こしてきている。
OWSに参加した人たちの中にはその後、協同組合の活動を始める人たちもいた(協同組合の歴史は長いし、その用語が抱える意味も広い。ここでは、協同<cooperative>によって事業をおこなうという程度の意味で使う。そこには日本の法律で定義される労働者協同組合も含む。労働者協同組合と言うと労働組合をイメージする人もいるが、肝心なのは協同組合という部分である)。
協同組合の原則は、組合員が所有し、組合員によって、組合員のために運営される事業であるという点である。「組合員」のところを、OWSのスローガンでもあった「99%」(富と権力が集中する1%の人々に対する私たちのこと)と読み替え、「事業」の部分を「社会」としてみれば、OWSが目指した方向性とほぼ同じだ。
社会制度が変わらない状況でも生活をしていなかければいけないOWSの活動家たちにとって、協同組合は、納得できる働き方で生活に必要なものを手に入れる方法として選択されたものであると同時に、理想とする民主的で相互扶助によってドライブされる社会を実現するための実験の場でもあるに違いない。
スペインでも15M以降、協同組合の活動が活発になっているという。
協同組合は、より公正で、誰もが人間らしい生活を送ることのできる世界を目指す運動の一部であると捉えることができる。
「可能な」選択肢として
別の視点から見てみよう。
デモや占拠活動は、参加するために時間とエネルギーがいる。職を失うリスクもある(OWSでは実際に、そこに参加したという理由で仕事を失った人がいる)。
これは、原発や憲法改正、開発など声を上げなければいけない場面で、実際には何もしてこなかった自分への言い訳でもあるのだけど、そうした活動以外でも何かできることが選択肢としてなければ、多くの人が声を上げる場面をつくれないし、本当に社会を変えるような波にはなり得ないだろうという思いもある。
いわゆる働き盛りの世代にとっては、時間ほど貴重なものはない。養うべき家族がいれば、失業やリストラはもっとも避けたいことになる。現在の職場環境では、常に結果を出すことが求められるのだから、気楽な稼業のサラリーマンという身分ではいられない。休日だって自己啓発。休息さえ、仕事のために必要な要素の一つに過ぎなくなっている。
今のままではまずい、より良い社会を目指したいという思いを抱えながらも、そうしたことに取り組む余裕も時間もないという、おそらくは大多数の人にとって、労働者協同組合すなわち働く人による協同組合は「可能な」選択肢となり得る。
デモに参加できなくても、公園を占拠できなくても、日々働くことがより良い社会をつくっていくための一歩となるとしたらーー。
2011年の世界の流れには乗りそこなった日本も、労働者協同組合法が制定され、選択肢が一つ増えた。
労働者協同組合が注目に値するのは、そういう理由によるものである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
