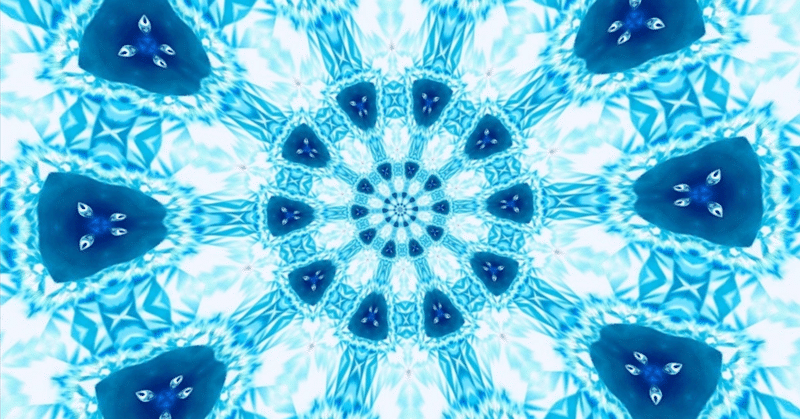
音楽理論を勉強しても曲を作れない理由
音楽制作を始めたばかりの方で熱心に音楽理論、難しい入門書から勉強する方がいるんですけど、まず結論というか、先に誤解を解いておかないといけないと思うのが、そもそも音楽理論って勉強しても曲が作れるものじゃないんです。
なぜなら、音楽理論は作曲・良い曲の方程式とかそういうのじゃないんです。
たとえば、科学って自然界に存在するものとか起こる現象とかを研究分析して解明します。そうすると、その解明した法則から物質を生成したり現象を再現したりできるんですが、音楽理論ってそういう科学と大きく違うのです。
科学はある現象から法則を導き出せれば、法則を使って現象を再現ことが出来ます。でも音楽ではそれが出来ません。音楽の最終的な結果は人間個人のの感情にどう影響を与えるかです。その点において、理論だけで音楽を構築しても、完璧な感情への再現性は得られないからです。
感情、感性は人それぞれに違いますし、さらには同じ人ですら日によって時間によって、そして他人の評価によって変化するんです。
じゃあどうすればいいかといえば、その再現性を評価する基準を自分の中に持つ努力をすることです。それは、自分の中に音楽で感動した経験を分析、蓄積することで作れます。
その感動の蓄積がない状態で音楽理論を勉強しても何も残らないのです。それっぽい形は作れるようになっても自分が感動する音楽は作れないのです。
逆です。まず音楽をたくさん聴いて、たくさんの感動を経験すること。そして、その感動が音楽のどこから来るかを深く考える。歌詞なのか、ハーモニーなのか、歌なのか、サビ前の音の無くなる瞬間、叫び、ギター、カウベル、リバースシンバル、ローファイなディレイ、めちゃくちゃ余韻を引っ張るリバーブ。
他の誰かではなく、自分にとってグッとくる感動ポイント。この曲が大好きだ!だと思える感動ポイントです。それも、感動で泣いたとかそういう大きいものだけじゃなくて、ふとした瞬間の気になった音とかそういうものもです。むしろそういう小さい感動を逃したらだめです。
そして、その感情・感覚を覚えておくこと。
たくさんの音楽の感動を自分の中に取り入れてから音楽理論とかコード理論を勉強したら、たくさん発見があります。あの好きな曲のエモい部分ってこういう音符の動きをしてたんだ!とか、このコード進行ってあの曲でやってたなと。
音楽をたくさん自分の中に取り入れてから音楽理論、コード理論を勉強すると今まで聴いた音楽の感動ポイントに名前をつけていくことが出来るんです。
つまり、たくさん聞いた音楽の中にすでに音楽理論やコード進行は詰まっていて、学ぶのはそれらに名前をつけていく作業なんです。そうやって初めて学んだことが腹落ちするのです。
作曲を本とか学校とかで勉強しなくても作れる人がいます。こういう人たちって、音楽理論を使わずに曲を作っているわけではないんです。
たくさん音楽を聴いてるうちにその好きな曲から共通点、法則性を見つけ出して、知らず知らずのうちに曲の作り方を身に着けているだけなんですね。それは、音楽理論なのです。本や学校ではなく音楽そのものから学んでいるのです。ただ、その法則やコードの名前を知らないだけで。
じゃあ理論なんて別に勉強する必要ないんじゃないの?といえば、もちろんそんなことはありません。
こうした音楽理論を勉強して特に役に立つのは、他の人と共同制作するときです。共通言語があるので、やりたいことを言葉で明確に伝えることが出来ます。だけど、感覚だけで音楽を作ってきた人は、やりたい表現をなんて言葉で表したら良いかわからずに人に伝えることが難しいのです。これが音楽理論を本などで学ぶ一番の意義です。
という感じで、順番としては
音楽を聴き込んで自分の好きな音楽を自覚する
↓
好きな曲を真似して作ってみる
↓
壁にぶつかったりしたときに音楽理論を学んでみる
というのが、一番効率の良い成長が見込めると思います。
たまに「音楽理論の勉強は作曲に必要か」みたいな論争が起きたりしますが、そんな0か1かみたいな二元論は不毛です。必要なときに必要なことを学ぶのはやったほうが良いに決まっています。
何事もバランスです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
