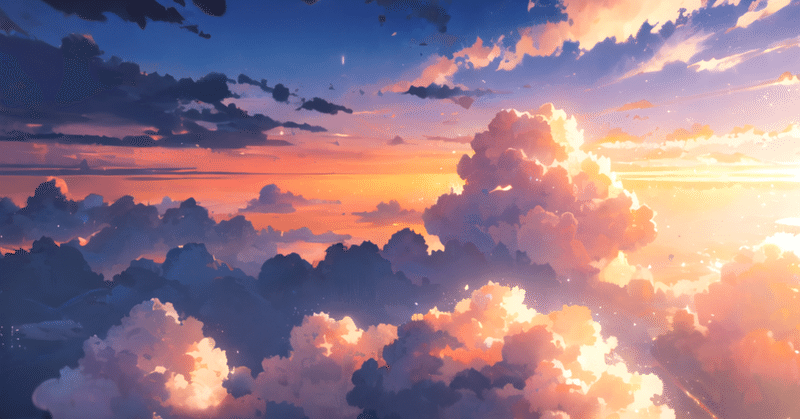
シャニアニが打った楔。広がる空と切り取られた世界。意味づけられた色達。
『アイドルマスターシャイニーカラーズ』のアニメ第一章から第三章まで見た。ネタバレを含む。
多くの沈黙と、瞳の揺れがあった。
抑制の効いた展開や大仰な表現を控えめにした演出は、その実、「見られることを意識していないからこうなる」といったラインを追求した結果だと読み取れる。
しかし、実在感を求めたゆえに、現実のものとして肉付けする方向を目指したものであっても今作はドキュメンタリー方式ではない。
「ドキュメンタリーのような~」と感じられる点としては、正しく上記の抑制の効いた展開や感情の機微を捉えようとする表現、舞台裏を描くことに執心している態度などが挙げられよう。
夜のプールでただ微かに揺れる水面と触れ合う真乃、目を輝かせるメンバーの傍らでそのユニットの仲間に視線を注ぐ摩美々といった点は散りばめられた内省や細部の表現であり、フェイク・ドキュメンタリーを作り出そうとする手法と似通う。
されど本作はインタビュー等の方法で対象の心情を明言化することはしてはいないし、外部からの283プロを評価する試みを行わず、複数の視点を用意しているわけではない。
明瞭化したテーマの元、整理され模範化した構造を呈示するものでもない。あるいはそれをしようとしても明確なものにはなっていない。
立ち位置としては視覚的な美しさや情緒的な要素が強調されたイメージビデオ、あるいは1stライブに至るまでの記録映像といった方が近しい。
巷間、シャイニーカラーズというコンテンツは「実在性」に力を入れていると語られており、方向自体は理解できる。そのスピリットを映像作品においても通底させることはブランドのイメージを固める方向にかじを切ったという意志の表明である。無論、魅力すべてを内包しているとは言わないが。
明確化した思想や主題を呈示せず、シャイニーカラーズ・283プロのアイドルはこういうものなんですという、「情報」を単に発しているとも見て取れ、それもまた受け取り手の感じたものに委ねるというスタンスである。そのような態度はシャイニーカラーズというコンテンツ全体において見受けられる。
付言しておくとくっきりとした構造や主題が示されていない、ということであって、主題が無いわけではない。むしろアニメ化においてこの方針をとったことが既に一つの思想である。
一つ一つのコミュを再構成してその総和で以てシャイニーカラーズの個性とコンセプトを提示する、
または新たにそれぞれの283プロの人間たちを掘り下げる事件を描くような作劇で、アニメ世界版としてのシャイニーカラーズを明瞭に打ち立てる。
そうした選択はされず、取られたのは、1stライブに至るまでの悩み・戸惑い・なにかを決めて仲間と話す、そうしたいっそ単調とも言える抑制の効いた、密やかな表現であった。
広がる空と切り取られた世界
3章において283プロは各ユニットの交流の下、ライブに向けて五色爆発の舞台ともなった学校で合宿を行う。
おぼつかないダンス、2日で仕上げるという意気込み、センターを打診された真乃の少しの前進。
センターをするかどうか。そうした選択をする立場に真乃は置かれるが、しかしそれは283プロを代表するイメージになるかという程度のレベルで収まっていた。
まとめ役が必要なのだという緊急性はない。ファンからの声が挙がったからということでもない。今回の1stライブを成功させるためには必要なのだという逼迫した状況はそもそも示されていない。
センター任命は「真乃が一歩進めるか」を焦点にするために置かれている。故に「真乃が思う通りに」なのである。どうするかを仲間と一緒に考えて、いかなる決断をするか。
学校での在り方が一つの重しになっていた真乃が、それを想起させる合宿の学校、プールと夜空のもとで、水面に揺れる自分とともに「一つ、進む」選択をするのも忍ばされていた必然である。
そこではプロデューサーは決意に関与しない。彼女自身の、自分の殻を破れるかのどうかの一歩の描写として、月と水と真乃が在る。
合宿2日目の声掛けで、ほんの少しだけ真乃は自分を出したように、前向きに言葉を発する。
シャニアニにおいては、こうした何に悩み、どういう決断をしたかその意味合いや重みを明瞭なものにしていない。
躊躇や思考は沈黙として表され、モノローグを混ぜない。
そうした工夫、作為がある。
仲間内の距離感、離れることの寂寥。尊敬と煥発される魅力。
283プロとして練習に励むその姿勢は、映像的な細部を伴って描かれるが、それはプロダクション内の出来事、個々人の持つ感慨という範囲で収められる。
例えば合宿中でも「ファンやお客さんのために成功させよう」という言葉は出てこない。真乃のセンターをどうすべきかにおいても、尊重されるのはあくまで真乃自身の意思である。
これは『ファンや見に来る人のことを考えていない』というわけではない。ライブでの果穂の「みなさんのことが大好き」といった言葉や、「みんなが待ってる」とのプロデューサーからの言及があり、真乃の瞳には舞台に向けられて揺れるサイリウムの躍動が宿る。そうしたものとして提示されている。
しかし懸命にレッスンに励む彼女たちからは、外の社会は意識されず、仲間との距離感に思いを馳せたり、自身の勇気を探るといった内省的な描写が繰り返される。
外部からでなく内部の価値観にフォーカスしているのは、そのキャラクターを描写する上ではある意味当然と言えるが、そのキャラクター性自体は少しだけ寂寥を吐露したり、親しみを込めた冗談を言えるようになったりと小さく細やかな描かれ方をされている。
逆に言えば鮮烈さを伴わず、強くキャラクター性や個々のアイドルの内面を押し出している形が少ない。にも関わらずカメラはひたすらアイドル達の傍らにいて、外部への言及を極めて抑えている。
なぜこうした描写になるかと言えば283プロという内世界、アイドルたちが抱いている世界観を描いているからである。
シャイニーカラーズから発せられている「主観」に寄り添った描写とも言えよう。
連なるシーン群は、彼女たちの反応や思考の様子を拾っていく形で構築される。
音楽で心理状態を裏付けするために多々使われる、フィルムスコアリングの採用はそうした一瞬の光耀と言うべきリアクションや感慨を重視していることの一つの現れである。
学校や商店街、イベント会場、あるいは撮影現場。アイドルをやる人間である以上、社会の営みとの肉薄は必然である。
2話においては監督を前に演技を深め、世界観を構築していくアンティーカがあり、
3話においてはイベントの中で難しい顔をした少年に寄り添うアルストロメリアの姿がある。
4話ではトラブルにあってもなお奮戦し、ご当地ヒーロー本人不在のショーを地元住人の繋がりもあってやり遂げる放課後クライマックスガールズが描かれている。
しかして高宮監督の映像哲学の実体は深掘りされず、一種のアイドルの演技の裁定者として彼は配置されている。花を渡された少年も、なぜ不機嫌だったのかその背景の事情がわからないままだ。「外の人と多く繋がっている」ことが色濃く表されている放クラもまた、他のユニット同様に、あくまでメンバー5人のみでの会話が以降の話で続いていく。
原作ゲームのストーリーにおいてはそうした「エキストラ」もまた、共感と寄り添いの深い眼差しが注がれることがあるが、シャニアニにおいてはそうした踏み込みが深くならない。
彼女たちがどういう人間で、このユニットはどういう在り方か。シーンごとの言葉のやり取りや、付随する表情をいっそ淡々と流す形で上映時間は過ぎていく。
W.I.N.G.の挑戦と敗退の描写であってもそれは続く。
内部の視点でお互いを撮り合いながら、アイドルとしての力量を高めて壁を越えようと、結託や努力をする姿勢をドキュメンタリー映像の形をなぞりつつ描く。
敗退シーンは個別の失意と挫折と、さらなる奮起の形を取って終えていく。
アニメ媒体でW.I.N.G.を取り上げたにも関わらず、他の出場アイドルと比べて相対的にどう優れ、どう劣っていたかは描かれず、敗退の理由とも言える外部からの審査の内実も示されない。そもそも他の挑戦者が存在感を持って描き起こされてもいない。
それらは内世界を描く上で必要がない。
焦点を当てられているのは懸命な彼女たちと、その彼女たちが不遇や困難、失意にあってどのような姿勢を示すか、という部分なのである。
自分らしくありのままでアイドルを続ける以上、「敗退」という事実はアイドル活動そのものを揺るがすものにはなり得ず、失意、あるいは理不尽に立ち会うシチュエーションという枠に留まらざるをえない。
後に述べるが、これは「継続」の先の道から振り返っているからだ。
実在性を求めて、283プロの面々をカメラが追う反面、「エキストラ」や外の社会がウエイトを占める割合はシャニアニおいては小さい。あえて小さくした描き方をしている。
それはシャニアニが、シャイニーカラーズが初期の流れを総括し、アイドルたちがいかなる存在か、どうやってここまで来れたのかを振り返るものだからである。
意味づけられた色達
283プロという内世界、アイドルたちが抱いている世界観を描いていると述べた。
しかし、シャニアニ単体では真乃の抱く悩みの内容が明確でなくよく分からなかったり、咲耶の寂しさの終着点がどこに向かうかなど「何を考え、何を悩んでいるのか、その結果どうなのか」が説明されない。
しかし真乃のためらいや、咲耶の寂しさはenzaの原作ゲームにおいては示されている。
アニメ内でなぜそれを再演し、心情を整理し、乗り越えるべき事象を定義し、その成就を構造的に描かなかったか。それはこのシャニアニが、ゲームの補完ないしシャイニーカラーズというコンテンツの補完を目指したものであるからだ。
原作ゲームには足りていなかった、「動き」。
歌い踊り、視線を揺らし、仲間にはにかむ、その実体をポリゴンピクチュアズの手による映像的な肉体が捉えることで、テクストの合間の質感に動的な肉付けが果たされたのである。
つまりはシャニマスの再演をしつつも、より補完的な立ち位置にあるということで、言うなればシャニマス初期の動き、空気感を識るための副読本的な役割がシャニア二には架せられている。
起伏はシャニマスにおいて既にあり、惑いを深掘りしたエピソードは既に原作にある。シャニアニは「その時、アイドルたちはどのような姿だったのか」を視覚的、実体的に提示することを志向した。
表情や沈黙がクローズアップされ、内省的な場面を描くことは他のアイドルアニメにもあるが、シャニアニは言ってみればそこ以外には注力しない選択をし、結果として「アイドルの姿しか見るものがない」状況を意図的に作り出している。
もっとも補完の立ち位置と言えど、W.I.N.G.の形式だったり「原作」との乖離もある。Pとの二人三脚でなく、「アイドルの姿を映す」ために必然的な変更を遂げている。
1stまでの道のりを補完するに過ぎないのならば、今作では新曲なども出ないはずであった。
しかし、今作は『ツバサグラビティ』という新曲がOP、アニメ内のライブ披露曲として生まれている。
この曲は歌詞から真乃を動かしうるものであり、現実の1stライブをなぞることから離れた、付け足された創意である。
「きっかけと言うには 頼りない予感だけ」
「全部繋がっていく 全部私だった」
「ここではないどこかじゃなく ここから」
「どんな自分だってちゃんと連れて行くよ」
「一人じゃ通り過ぎた 心のグラデーション 愛しくなる 勇気にできる この日々が私を動かす」
アイドルを踏み出す前の迷いや思考に耽る時間と、踏み出した先の鮮やかな景色。惹き合う仲間の絆。
昨日すら抱きしめる大きな愛と感謝の歌だが、とりわけシャニアニの形式と照応を見せるのは上記の部分だろうか。
シャニアニが持つ創意、「補完」ともう一つの役割。
それはシャイニーカラーズはどのような想いから始まり、なぜ続けてこれたのか。その根幹を初期を振り返る形で感謝とともに伝えることだ。
オリジンを描き直し、そのキャラやコンテンツの方向性を再定義し明確化することは多々ある。
シャニアニにおいて抽出されたイメージは「不安を抱きつつも踏み出すアイドルたち」であり、あるいは「他者を尊重し、親睦を深め、やさしい時間を作り出す少女たち」であり、「困難にあっても前を向く、等身大の懸命な人間たち」であった。
それ故、W.I.N.G.は仲間とともに挑戦を行うシーンや失意のシーンとして描かれ、イルミネの初ライブ前にはフォーメーションに課題がありつつも、Pから考えてみることを促されて3人が演ることを選択する有り様が流れる。
これらは不安にさせる材料と、不安を超える人の姿だ。
やさしい融和の時間や努力の時間を視覚的に描き足され、意味づけられた色たちは、シャイニーカラーズというコンテンツそのものが持つ初期の物語を定義する。
シャニアニはアイドルたちの振る舞いの描写を、意志を持って積み重ねた作品だ。
2018年のシャイニーカラーズ始動からこの時に至るまでの足りなかったものを継ぎ足しつつ、初期の動きをなぞり、辿り着いたシャニアニとしての到達点はどういうものか。
それはライブでの歌唱とダンス、舞台裏の克明な視点と、ステージと観客に向かいあう姿。そこで『Spread the Wings!!』と共に歌い上げられる『ツバサグラビティ』だ。
『Spread the Wings!!』に比して『ツバサグラビティ』の歌詞には
「憧れはもう走り出してる 未来へ」
「自分らしい色になれる空へ 一緒に行こうよ」
「大胆な運命 この胸に重なった 昨日ごと抱きしめる 強い引力」
「全部繋がっていく 全部私だった」
といったように、どこか完了形の表現や、過去を振り返り総括する言葉遣いが多く散りばめられている。
シャニアニそのものがシャイニーカラーズの補完であり振り返りの形をとっている。
ならば、シャイニーカラーズがシャニアニを通じて表明したものは、
「日々の細かな頑張りや奮起があり、それを信じてくれたあなた達がいる」
ということであるように思われる。
そうして続けてこれたのだ、そうしてくれたから輝けているのだ、という感謝とアイデンティティさえもないまぜになった、双方向性の中で形作られた自らの姿の定義。
あたかも個別のアイドルが描写によって存在の有り様を提示してきたことのフラクタルのように、シャイニーカラーズ自体が、自らがこうであると表明を為したのだ。
シャニア二が打った楔
――「だって君が信じてくれた可能性 最初の勇気だね」
導き手となるプロデューサーとアイドルの関係性を歌う内容は、そのままシャイニーカラーズというコンテンツとそれに理解と共感と興味を示したユーザーたちや支え続けた周囲の人々との関係性を指し示す。
自らの姿を振り返り、総括し、抽出した、シャイニーカラーズの始動からの回答。
勇気を持って踏み出す。自らの色・志向性を大切にしつつ、(それが受け入れられるのは当たり前ではないからこそ)繋がってくれた人々に感謝すること。
ツバサグラビティのフレーズを通して表出されたものはこうした主題のように思われる。シャニアニを通じてシャイニーカラーズは在り方の整理と定義を行ったと言えよう。
そしてこのアニメ化を通して「こうであった」と自らの在り方の整理と定義を行うことは、これからもこうしていくというコンテンツの運営方針の表明の性質さえも帯びる。ある種の自らに課した決意の鎖である。
先に言及したが、ライブの終盤でプロデューサーがアイドルの面々に「みんなが待ってる」と声をかけるシーンがある。
これはある意味で、シャニアニにおいて珍しい外部の視点への言及である。
一通り楽曲を披露したアイドルたちが、再びステージに向かうシーン。
たどり着いた景色。積み重ねた努力の成果。その披露が終わり、続ける最中。
成果を見せた彼女たち。再度、舞台に向かい合おうとする彼女たち。
「みんなが待っている」。見せてやれ、と送り出す言葉は、受容されていること、さらなる成果を期待されていることをアイドルたちに示す。
シャニアニそのものも一つの成果を提示しつつ、これからも(こうした在り方で)飛び立っていくという姿勢の中で終えていく。
ラスト、ピクニックの場面で真乃が見上げる、広がった空。
それはアイドルたち、シャイニーカラーズというコンテンツが躍動する舞台となるこの大きな世界の表象である。
一歩踏み出し、仲間と支え合い、飛び込んだ先で広がる空。どこまでも広がる可能性の姿であり、自分が星になっていく場所。
彼女らは歓談の中、その空を見つめ、またその空に包み込まれている。その様を提示し、新たなスタートを予感させながら、このアニメーションは締めくくられるのである。
しかし、そうして示した表明はまた、不安を呼ぶものでもあることも忘れてはならない。
自らのありのままの姿を示そうとすることは、ある意味で他者からの期待に沿わないことでもある。自らを定義づけたところで、他者との認識の齟齬を押し止めることはできない。
「こうした方向で行く」と決めることには、必ず他のやり方の可能性を切り捨てる側面がある。
このアニメの形式を含めてシャニマスであるという意思表明であるならば、このような形でアニメーションを活用するという志向性をシャイニーカラーズは持つという宣言をしたのであり、それ自体には賛否や好悪や是非の評価が伴うのは当然である。
シャニアニは完成物を公開していく以上、その表現自体は一方的である。「あなた方に支えられたからこうしている」といった感謝・表明もそれ自体が自己完結した一方的な形式にならざるをえない。(無論コンテンツからのメッセージだからそうであるべきだ)
構造を明確にせず受け取り手の解釈の自由に委ねるスタンスは、如何なる意見もコンテンツが抱えていくことを受容する覚悟とともにあらねばならない。
シャニアニが目指した「尖ったこと」「特別なやり方」は、尖ったことをやろうとする姿勢は好きだという評価も生むが、その選択自体を疑問視する観点も同時に惹起し得る。
そしてもちろん思想を持ち、志向性を持って描いた作品であれど、その姿勢への評価と、表出されたもの自体への評価はまた別なものだ。シャニアニにおいてもやろうとしたこととの齟齬が生まれていたり、踏み込みが足りていないように思える箇所はある。
(ここからの記述には批判的に響くものがあります)
初期の動きをなぞる形で、ここまで来れた、こうしてやってきたと表現するのであれば、アイドルグループとしての成長や変化、成果の描き方は抽象的な言葉に頼ることなく、もう少し具体的で切り込んだアプローチが求められるのではないか。
シャイニーカラーズの副読本的立ち位置と言ったが、2~5話あたりはアニメに向けて書き起こされたストーリーの色が濃い。
トラブルがあり、個性が強いキャラがいる。
先にも述べたように、嵐に遭っても世界観を表現することに力を注ぎこむアンティーカ、不機嫌な子どもにも寄り添って幸せを広げるアルストロメリアが描かれたが、その見せ方は「そういった姿が見せられればいい」とだけ考えて工夫が薄いまま終わった印象を受ける。
高宮監督の理想を読み取るシーンがあってもいいし、少年の不機嫌の多様な背景を描くこともできたはずだ。
そうして初めて世界観を深めるアンティーカ、人のささくれだった心にも慈しみを持って寄り添うアルストロメリアの姿が明確になる。
世界観が深いユニットや、幸せを導くユニットであれば、あり方を示す目的に沿わせるためにはそこを深くすべきだったと思えてならない。原作から示されているスピリットの継承だ。
またアイドル一人一人が、順番に目を閉じて思いを馳せたりするのは「アイドル一人一人を視覚的に補完する」シャニアニの方向性としては正しい演出である。
しかしそうした特徴的な手法を複数回繰り返しては、演出自体を『作業』に落とし、演出が陳腐化する様や創意の薄い様を晒すことになる。贅沢に画面と時間を使っているようでいてその実、安易である。
あえてリフレインするのであれば、そこに再演する必然性があるべきだ。
また真乃の勇気を描くシーンにしても、本来ならそもそも「アイドルをやる決断」だけでその勇気を描くべきであったと思う。そのほうが広がる空に飛び込んだという真乃達がやったことが明瞭に浮かび上がる。
確かに「飛び込む勇気」を最終話のライブ前に改めて配置したいがために、
「センターをするという決断」という新たな「勇気が要る選択ポイント」を用意し、真乃に選ばせたのは必然性はあると言える。言えるが、その結果としてセンターをするための具体的な努力やセンターで為した成果がいまいち見えてこないまま終わっては、「なんでもない選択に悩んだ」感さえ残ってしまう。
真乃がみんなを尊重し、融和に導き、多様性を持ったまま輝かせることができるという特質は、正直他の283プロの面々がいい子過ぎたために薄くなってしまったと思う。
後、これはどちらかと言えば懸念だが、
アイドルたちがプロデューサーからの「みんな待ってる」と言葉を受けるシーンがあるが、これは無条件に「私達は待たれている」として自己言及的に自らを位置づけているとも言えるシーンになっているのが気にかかった。
ここはともすれば外部の視点までも先回りして、内世界の中で回収してしまっているようにも取れるのだ。(もちろん、初期のシャニマスも「待たれていた」がために2018年から今日までの躍動があったのであるが)
どうしてこんな勘ぐるような不安を抱くかと言えば、シャニアニ自体が切り取られたフレームの中、アイドルを映すことに終始し、外部の存在が希薄なままに進んでいったからである。
作中においてライブに集った観客席のファンは(応援の声を張り上げたり好意を叫んだりはしているが)、その実態を個別に描かれたりはしていない。
アイドル達がたどり着いたサイリウムの海、果穂から大好きだと表明される温かい人々の総体として置かれている。
商店街の人々や、今までの仕事で繋がった人が来たりする展開はここでは見受けられない。
その状態で「待っている」とのプロデューサーからの言葉は、具体的に「みんな」を描かないまま『このスタンス、このあり方が受け入れられているのだ』という外部の意見までも自己完結的に語ってしまった構図になってしまったように思う。
多様性ある世界で、もしその感性を一方から決めてしまうことになれば、それはコンテンツの主張と噛み合わない。これは外部としてのファンの様子をくっきりと描いていれば不安は幾分少なくなったかもしれない。
『「みんなが待っている」。見せてやれと、送り出す言葉は、受容されていること、さらなる成果を期待されていることをアイドルたちに示す。』と先に述べたが、アンコールの声の中で待たれていることを更に明確にし、アイドルたちに掛ける言葉にして出したことには象徴的な意味がある。
つまり抱いた懸念の正体とは、「シャイニーカラーズというコンテンツが志向性を持って特徴的な表現を選びつつも、それが受け入れられる想定しかしていないのでは」という公式の見解への不安と言える。
もちろん是々非々の声が上がることなどすべてを承知の上で、シャニアニはこの作劇をするという選択を為したと私は信じている。
シャイニーカラーズが独自の志向に誠実だというのならば、成る程さまざまな方向で意見が出るのはむしろ道理である。
しかしシャニアニにおいては外部の視点が乏しく、内世界を追う描写に拘泥したことで、ナルシスティックとも取れる内にこもった印象を醸成している側面もまた留意せねばならない。
情緒性とエンタメ性はどちらを志向するか自体には優劣など無いし、情緒性を深く描きつつもしっかりとエンタメを両立させている作品もある。
自らのコンテンツの長所をこれだと信じるのは尊いことだ。
ブランドイメージの創造、遵守のためであっても自らの有様はこうだと示し続けることは、勇気が要る。
だからこそ、その価値観が内に閉じてしまうことがないように望む。
「楔を打ってでも続ける覚悟」が、「楔そのものが自らの存在証明」だと測り間違えることがないようにするのは注意がいる。ともすればそれはグラデーションだからだ。明言しない言外のメッセージを祈りとともに投げかけるようなやり方は、ユーザーにもある種の選民意識を惹起させるものになるかもしれない。
アニメスタッフの面々と、実際にゲームを始めとしたコンテンツ展開のハンドリングをしている面々は違うのかもしれないが、シャニアニを通じて、シャイニーカラーズは自らのあり方を発信していく。
視覚的な質感をもたらす試みはシャニソンにおいてもされているが、アニメ化においてシャニマスというコンテンツは原作を重視し、その間すら描きだそうとした。
1期のみで現状、展開が留まることも多いアイドルマスターシリーズのアニメ化において、その機会を原作の補完的な領域にとどめた判断は、それだけで「見解の相違」を産みうるだろう。
シャニアニはそうした楔を打ったのだ。
反響が悲喜こもごも、是々非々が噴出する混沌としたものになっても、その様子だけを見て「シャニマスらしい(だからこれで正しかったのだ)」として流して終わることは、運営の皆様方におかれましては無いように願いたい。
個別の感想が、それぞれの感性が、ユーザーや観客の一人ひとりの感情がそこにはある。
その声をなかったことにせず、拾い上げ、全てに応えることはなくとも、想いだけはきちんと胸に納めてもらいたい。
そうしてやっていくことが、人の心に思いを馳せて、拾い上げようとするシャイニーカラーズの姿勢であると私は信じる。
まったくの余談
「孤独」は元来、寂寥や落胆といった意味を内包していなかった。単に一人でいる状態を指しており、中世においては人々が神と相対するため、他者と離れて祈りや黙想に耽る状態を表す言葉としても使われている。
スクリーンの前でその作品と相対するのは自らの意識しかない。その演出や音響を五感で受け止め、提示された表現を自分なりに理解して、意味を確定させていく。
応援上映で緩やかな連帯や共感の波及はあれど、自分が抱く初めての評価は内世界で解釈し、あるいは想像したものとなる。
それぞれ「何を思い、何を決めたか」。それは他の来館者の横顔をちらりと見ても、その内実は悟れない。無論、スクリーンの向こう側の彼女たちを見ても同様である。
映画館というのは一人の体験として作品を刻み、内省の機会を齎す場である。
また語らないのでなく、あえて語らせていない。という作為は、その沈黙に意味合いを見出してほしい、補完を期待するという態度としても取られうる。
シャイニーカラーズに触れていた層からはその解釈を投射する「間」であり、そうでない人にとっても残された解釈の余地である。そうした描き方を提示すればその余白と間に、見る者は意味合いを付け足したり、快不快の判断を下していく。
鑑賞中の思索によって、自らのコンテンツに求めるものを掘り当てる場合もあろう。
求めるものと見せられたものの齟齬によって、その明確な問題点を言語化するために脳を賦活させる人もいよう。
映画館がもし他者から精神的な距離を置き、自意識を生活の塵埃から切り離す「孤独」を造る作用があるのならば、私達は鑑賞中、その孤独で以て、ある種の神に向かい合っているはずだ。
人それぞれの考えがあり、人それぞれに感慨がある。
そうした普遍的な事実を、私は一つ、シャニアニの感想群の中に見出す。
個別の描写に熱を込めて感想を述べる人もいれば、全体の構成から批評を加える人もいる。
運営の判断そのものを疑問視する人もいれば、コンテンツのためにネガらず盛り上げた方がいいと言う人もいる。
かつては親衛隊といったアイドルのファン集団は、一つの意識や思想におおむね統一されていたように思う。しかし現代のSNSで繋がるファンやユーザーたちは、そうした統一された意識があるようには見られない。
むしろ、「シャニマスのP」やファン、ユーザー達の集まりがそれぞれ別の異なる来歴、異なる立場、異なる感性を持っている者たちで構成されているという様をまざまざと見せている。
個別のファンの名称で全体化されるものでなく、全人格化しうるものでない。
現代のファンダムというのは、『ファン集団』といったようにくくられるものでなく、SNS等で個別に動きながら連動や連帯を見せる、『ファンネットワーク』というべき形を取っているように思われる。
それは様々な観点から価値が補完される形状であり、様々な視点から批評が飛んでくる形態である。
なるほど、コンテンツの運営においては不明瞭な物が多い時代になっているのかもしれない。
運営が特定の意見や方針を統一するのが難しくなり、その結果、様々な意見が飛び交い、ユーザーの反応も一様ではないことが浮き彫りにされている。
意見のみを流すのでなく、まず立場の表明をしたり、来歴や観点を語るのは、ネットワークの中で生きていくのであれば、必然の行為になるのかもしれない。
ネットワーク上での立場の表明や意見の交換が、孤独感を和らげつつも、ネットワーク内での居場所を確立する手段としても機能しているのだ。
「孤独」な状態でコンテンツに向かいつつも、居場所はネットワークにある。
これは、孤独ながらもネットワークを通じて共感や理解を得ることで、コンテンツ本体への関与が深化していく、そのプロセス、循環を目の当たりにしているのかもしれない。
複雑で多様なこのファンネットワークやユーザーコミュニティのあり方を念頭に置きながら、コンテンツ運営者はより広い視点で、意思決定や発信形態、コミュ二ケーションの方法を練らなければならない。
そんな多様性が脈動する時代の、輪郭を想った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
