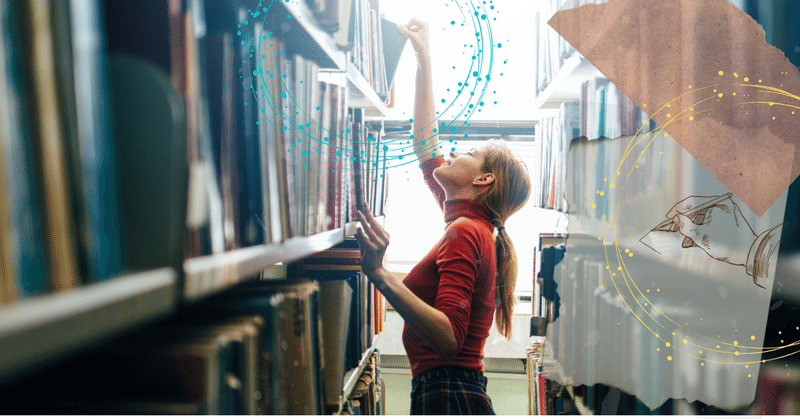
ないですよ
「その棚にはないですよ」
「えっ、どうして!?」とわたしは声をあげます。
すると彼はこう答えました。
「ああ、それは、この棚は専用なんだ。ここにある72色の本の」
「へぇ……」とわたしは再び驚嘆の声をもらします。
すると彼がこんな風に言います。
「君も興味があるんならその本から一冊貸してあげようか?」
「いいんですか?」
「うん、もちろんだよ」
そう言うと、背後に置かれていた木箱から一冊、背表紙に題名が書かれた赤い本をそっと取り出し、差し出してくれました。
「あ……でもわたし、今日はお金をあまり持っていないので……」
「いいよ。俺が勝手に貸すんだから。ちゃんと返してね。店長には内緒ね」
そんなことを言ってくれた彼の親切さに感激したわたしは、思わずこう尋ねてしまうのです。
「あの……もし、よかったらですけど……」
わたしは彼の方を見上げました。彼は優しい表情のまま黙ってわたしの言葉を待っていましたが、わたしは何も言えずただうつむいてしまいました。ふわりとした良い香りとともに、柔らかな風のような温かい声が流れてきたように感じた気がしました。
「何だい?」と彼は優しく訊き返してきました。
わたしは慌てて言い直していました。
「あっ、いえ、なんでもないです!」
「遠慮しないで言ってごらん」
「…………」
そのとき頭に浮かんだ言葉を言いたくて仕方がありませんでした。けれどわたしはそれを口にすることはできなくて、結局何も言わずに彼に背中を向けるしかありませんでした。
そしてその日以来、彼と会うことは二度となかったのです。
***
「…………」
その本は確かに懐かしく愛しい思い出と共に、俺の手の中にある。色褪せた赤い本。木箱から出した時は、深紅だった本。
「……」
あの時、彼女が言いかけた言葉は何だったのか?彼女は本当に伝えたかったことを俺に伝えようとしたのだろうか?それとも伝えなかったことを後悔しているのだろうか?もしも伝えていたら何か変わっていたのだろうか?
「……また会えるかなぁ」
俺は一人呟いてみる。しかし返事はない。
彼女の名前さえ知らないのだ。どうすれば、いいだろうか。この棚には答えがあるだろうか。
……ない、よなぁ。俺はため息をつく。
「……今日はこれで帰るか」
俺は手の中の赤い本を棚に戻した。ほかの71色の本は買われたが、この本だけは彼女のために残している。スピンがまだ半分くらいだから、きっと来るだろうと思って。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
