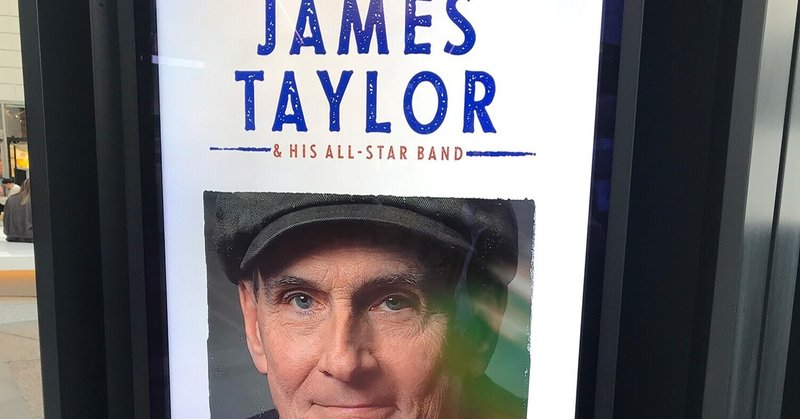
ジェイムス・テイラー コンサート雑感(2024年4月6日 東京ガーデンシアター)
ジェイムス・テイラーは、私にとって特別な存在だ。14〜5歳の頃に初めて聞いて以来40数年、ジェイムスの音楽は常に私の人生のBGMだった。20歳前後の多感な時期、彼の曲はジャクソン・ブラウンの曲とともに、私の人生の「道標」だった。「Country Road」や「Riding On A Railroad」に自分探し・アメリカ探しの旅に出る勇気をもらい、疲れた時には「Yon Can Close Your Eyes」や「Don't Let Me By Lonely Tonight」に癒された。「Shower The People」には温かさを持って人に接することの大切さを学び、「Secret O' Life」に頑張りすぎないことも必要だと教わった。ついでに言えば、「Something In The Way She Moves」や「Carolina in My Mind」「Fire and Rain」は、私のギター弾き語りの重要なレパートリーだ。
もし「デザート・アイランド・ディスク」(無人島に持っていきたいアルバム)10枚を選ぶとすると、ジェイムス・テイラーのアルバムはその中に確実に入る。実際、昔それに近いことをしたことがある。1987年、1年間アメリカに留学することになった私は、現地で自分の心の糧となるであろうアルバム10枚を90分カセットテープ5本のA/B面それぞれに1枚ずつ入れて持って行くことにした。いつでもどこでも何でもストリーミングで聞ける今では考えられないだろうが、それは一種のお守りのようなものだった。その5本のカセットに入れたアルバムは、次の通り。
Jackson Browne -- "Jackson Browne" / "For Everyman"
Jackson Browne -- "Late For The Sky" / "Running On Empty"
James Taylor -- "Sweet Baby James" / "Mud Slide Slim and the Blue Horizon"
Pure Prairie League -- "Pure Prairie League" / "Bustin' Out"
American Flyer -- "American Flyer" / "Spirit of A Woman"

このセレクションは、単に「好きなアルバム」というだけではなく、めげそうになった時に自分の志を思い出させてくれる音楽という意味合いもあったのだが、今、同じような選択をするとしてもその時とさほど変わらないように思う。元々これらの作品には後追いで接したわけだが、私がこういった音楽をリアルタイムで追いかけるようになった頃には音楽界のトレンドもかなり変わっていた。ジャクソン・ブラウンは政治的なメッセージソングをハードなアレンジで歌うようになっていき、リアルタイムではあまり共感を覚えられなくなっていた。シンセを多用したダンスミュージック全盛の80年代中盤〜後半はアコースティック・シンガーソングライターたちにとって厳しい時代だったはずだし、私自身もリアルタイムで共感できる音楽に飢えていた。そんな中、ジェイムス・テイラーが1985年に発表した『That's Why I'm Here』は、タイトル通り、やっぱり彼がいてくれたんだと安堵させてくれる作品だった。以来、彼は一度も期待を裏切ることなく、素晴らしい作品を届け続けてくれている。私にとって、新譜が出たら無条件で入手しようと思う、ほぼ唯一無二のアーティストだ。
そんなジェイムス・テイラーの音楽に生で接するのは、今回が3回目。最初は高校1年だった1981年。リンダ・ロンシュタット、J.D.サウザー、ローニンとともに、彼が甲子園球場のステージに立った「The California Live」でだった。アルバム『Dad Loves His Work』が出た年だが、その時の私は、このアルバムからの曲以外、まだ数曲しか彼の曲を知らなかった。ゆえに、「良かった〜」という印象以外は曖昧だ。覚えているのは、彼がJ.D.とのデュエットで「Her Town Too」を歌ったことと、最後の最後に出演者全員がステージに上がって「That Lonesome Road」を歌ったことくらいだ。

2回目は93年9月。ニューヨークのパラマウントシアター(現在は「シアター・アット・ザ・マディソンスクエア・ガーデン」というようだ)。ちょうど初のライブアルバム『Live』が出た直後で、ヴァレリー・カーターがバックヴォーカルで参加していた頃だ。セットリストもそのライブアルバムとかなり近かったと記憶しているが、今までに見た全てのコンサートの中でも上位に入る感動的なコンサートだった。その後、ジェイムスは2010年にキャロル・キングと共に来日しているが、その時も東京公演のみ。気付いた時にはチケットは売り切れで、貴重な機会を逃してしまった。2015年には小澤征爾のバースデー公演のために来日していたが、一般の公演はなし。そんなわけで、今回の来日は絶対逃すまいと、たった1回きりの東京公演のチケットをいち早くゲットした。
会場の東京ガーデンシアターは、壮年の観客で超満員。男女比率は感覚的には7:3くらいだっただろうか。ガーデンシアターは、2020年開業とのことで、初めて訪れたが、4層になった客席フロアはなかなかの壮観。ステージも天井が高く、音響もかなり良さそうだった。私の席はアリーナの前から15列目。アリーナとは言え、見た目にわからない程度にフロアが傾斜しているのか、さほど見にくいとは感じなかった。ステージの両脇には大きなモニター画面があったが、演奏中はなるべくモニターを見ず、ステージを凝視するようにした。ジェイムスと同じ空間にいるという感覚をしっかりと味わいたかったからだ。

近年も精力的にツアーを行なっているジェイムスだが、この日の公演は今年のワールドツアーの初日ということで、1曲目に何を演るのか予想するのも楽しかった。まず一人で登場して弾き語り曲と予想していたのだが、彼はバンド全員とともに現れた。演奏されたのは、ファーストアルバムから「Something In The Way She Moves」。全くの弾き語りではなかったが、ほぼ予想に近い曲だった。演奏後、ジェイムスは、アップルレコードと契約してこの曲をロンドンで録音した68年のエピソードを紹介。「ポール・マッカートニーとジョージ・ハリスンがスタジオに見に来ていた」と言う話は、この曲が、ビートルズの「Someting」の冒頭の歌詞を含むインスピレーションになったことを示唆するものだった。
2曲目は、同じくデビュー作からの「Rainy Day Man」。ただし、アレンジは1979年の『Flag』に収められていたバージョンに近いもので、前曲同様、古さは全く感じさせない。3曲目は、85年のアルバムのタイトル曲「That's Why I'm Here」。今まで生やライブ音源、映像作品でこの曲がライブ演奏されるのを見聞きしたことがなかったので、これには少し目頭が熱くなった。前述の通り、85年当時、私に安堵感を与えてくれた思い入れのある曲だ。歌う前、ジェイムスは、この曲は自分のターニングポイントになったと紹介した。確かに、80年代の混沌としたミュージックビジネス界にあって、前作から4年のインターバルを置いて発表されたこの曲を聞いた当時、何かふっきれた様子のジェイムスを感じたものだった。それは、「Suddenly it’s perfectly clear」というフレーズにも現れている。
この曲の2番の歌詞は友人だったジョン・ベルーシに捧げたもの、3番の歌詞はみなさんに捧げたものと彼は紹介した。2番の歌詞がベルーシに言及していたことについては、今まであまり認識していなかったのだが、そう思って耳を傾けると、シンガーソングライターとしてのジェイムスの魅力を今更ながら認識することができた。それは、自分の身の回りに起こった出来事を誰もが共感できるような普遍的なものとしてさらりと歌にしてしまう彼ならではの詩趣だ。聞き手である私たちは、そこにジェイムス自身を感じることもできるし、自分を投影することもできる。
ジョンが逝ってしまった 死んでいたんだ
ハイになって そのまま死んでしまった
後になってベッドで溺れ死んだと言われた
笑いの後に 押し寄せたのは恐怖の波
それは 鉛の塊のような衝撃だった
「火傷をしないように」って言うのは
急にハンドルを切るってことらしい
歩いているのなら歩き続けよう たとえ上り坂でも
働くことは罪ではないと心に刻むんだ
とにかく そいつらに自分の時間を奪われて
無駄にされないように
そう そのために 僕はここにいるんだ
富と名声なんておかしなものさ
赤の他人から名前で呼ばれる
何度も何度も「Fire and Rain」を聞くために
結構なお金を払うんだ
毎年帰ってくる夏のような人もいる
赤ちゃんと毛布と
浴びるほどのビールを手に持って
思わず笑ってしまったよ
でも突然 はっきりとわかったんだ
そのために 僕はここにいるんだって
Translation by Lonesome Cowboy
今回のステージでは「Never Die Young」も演奏されたが、ジョン・ベルーシのエピソードを意識して改めてその曲を聴いてみると、この曲は「That's Why I'm Here」と対をなす作品、つまり、70〜80年代のLAのエンターテイメント業界にはびこっていたドラッグの問題を歌っているように思えてきた。
「That's Why I'm Here」に続いてジェイムスは、「囚人として送り込まれた土地が実は素晴らしい場所だったという、オーストラリアのことを歌った曲」と紹介して、アルバム『Hourglass』(1997年)に収められていた「Yellow and Rose」を披露。「1年以上リハーサルをやってきたけど、なぜか今まで一度もステージで演奏したことがなかった」と言っていたが、日本公演の後、数都市を回るオーストラリア公演を意識しての選曲だろう。(下記リンクのオリジナル版には、ショーン・コルヴィンがハーモニーで参加)
この曲と、次の「Anywhere Like Heaven」がやや意外性のある選曲だったが、その他はほぼ彼のステージではお馴染みの代表曲のオンパレード。「Anywhere Like Heaven」は『Sweet Baby James』(1970年)からのカントリー調の曲で、今回のステージでは、リードギターのディーン・パークスがペダルスティールを披露。ダン・ダグモア(gu., steel)がバックを務めていた80年代のJTバンドの音を彷彿させた。
今回のバンドメンバーでもうひとり印象的だったのは、バックヴォーカルとフィドルのアンドレア・ゾン。JTのアルバムには『October Road』(2002年)から参加しているので、彼とはもう十分に長い付き合いだが、私がライブで見るのは初めて。容姿そのままの堂々とした歌いっぷりと、一瞬ヴィオラかと思うような野太い感じのフィドルの音が新鮮だった。前半のハイライトだった「Country Road」に入る前には、スティーヴ・ガッドのドラムとの掛け合いでアイリッシュ調のフィドルソロを披露してくれた。ステージでの「Country Road」は、アルバム『Live』でもそうだったが、曲の終わりにドラムの力強いストロークと一緒になって畳み掛けるように歌うジェイムスのヴォーカルが素晴らしかった。今回は、日本でも人気が高いスティーヴ・ガッドに熱い歓声が上げられていた。
演出的に興味深かったのは、第1部の終盤で演奏した「Long Ago and Far Away」。アルバム『Mud Slide Slim and the Blue Horizon』(1971年)で当時ジェイムスの恋人だったジョニ・ミッチェルがハーモニーをつけていた曲だが、今回、そのかつての録音からジョニの声だけを抜き出し、それをステージで歌うジェイムスの声に合わせるという演出がなされた。ベースのジミー・ジョンソンがその抜き出し作業を行なったという。ジョニの声だけが若いままなので若干違和感がないでもなかったが、なかなか感慨深かった。この曲が終わると、ジェイムスは「あと1曲演ったら20分ほど休憩します。何で休憩するのかわからないんだけど」と言って観客を笑わせた。これは、2枚組みCDの『Live』(1993年)の1枚目最終曲の前に収録されているMCとほぼ同じ。もう30年以上もこう言い続けていたんだろうなと思うと、何だか微笑ましかった。
第2部は、望郷の気持ちを歌う名曲「Carolina In My Mind」でスタート。その後「Mexico」「Steamroller」「Fire and Rain」と代表曲が続き、段々と佳境に入ってくる。「Steamroller」ではジェイムスがエレキギターを持ったほか、ハーモニカソロも披露。彼がハーモニカを吹く姿を見るのは、映像も含めて初めてだったが、なかなか堂に入ったプレイだった。
コンサートの中では目頭が熱くなる瞬間が何度かあったが、その中のひとつが「Up On The Roof」。彼のライブでは重要なレパートリーになっているジェリー・ゴフィン&キャロル・キングの曲だが、ジェイムスはこの曲にはニューヨークを感じると紹介していた。ゴフィン&キングへのリスペクトが、彼の歌声から滲み出しているようだった。
ジェイムス・テイラーは、短編小説のような素晴らしい曲を書くシンガーソングライター、そして独特の味のあるアコースティックギタリストとして最上級に素晴らしいのだが、もうひとつ彼のユニークな魅力は、アメリカのポップミュージックへの愛情に溢れるカバーアーティストである点だ。モータウンやアトランティックのR&Bソングから、トラディショナルなフォークソング、ロジャース&ハマースタインのミュージカルナンバーまで、さまざまな曲を彼はカバーしてきたが、いずれもJTサウンドにしてしまう彼独特の味は格別だし、それらを通じて彼が純粋に音楽を楽しんでいる姿が感じられるのが嬉しい。そういう意味では、今回、現時点での最新作である『American Standard』(2020年)から1曲も演奏されなかったのは少し意外だったが、これだけ自身のヒット曲があるアーティストなので、ファンの期待に寄り添った選曲だったのだろう。
「Shower the People」「You've Got A Friend」と続き、フィナーレのムードが高まると、いよいよ「How Sweet It Is」でアリーナの観客は総立ち。いつまでもこの時間が続いてほしいと願わずにはいれれなかった。1948年生まれのジェイムスは、現在76歳。今回のワールドツアーは、日本の後、フィリピン、オーストラリア、ニュージーランド、そしてアメリア各地を周り、9月半ばまで続くようだが、いつまで彼が今のような演奏活動を続けてくれるかはわからない。実際、今回のステージでの彼の声は、かつてに比べるとさすがに枯れている印象だった。静かな曲ではそれがやや顕著だったが、パワフルにシャウトする曲になるとあまり気にならなかったのは、さすがだと思った。
そして、今回特に感じたのは、バンドの一体感だ。出演者が「James Taylor and His All-Star Band」と銘打たれているのに違わず、バンドとのファミリー感がひしひしと伝わってきた。今回のバンドメンバーのうち、ベースのジミー・ジョンソンとコーラスのケイト・マーコヴィッツは、それこそ、アルバム『Live』(1993年)の頃からもう30年以上もの付き合い(『Live』時のメンバーからは、ドン・グロルニック、ヴァレリー・カーター、デイヴィッド・ラズリーが鬼籍に入っているし、アーノルド・マッカラーは最近ツアーからの引退を宣言した)。今回特に意識したのは、ジミー・ジョンソン。今回のメンバーの中では、スティーヴ・ガッドやディーン・パークスの目立つプレイに目が行きがちだが、このバンドを締めているのは、全く派手さのない彼の穏やかなベース・プレイだと感じた。

そして、バンドのファミリー感をとりわけ強く感じたのは、コーラス隊がジェイムスと一緒にフロントに並んで歌ったナンバー。第1部最後の「Sun On The Moon」、アンコールの「Shed A Little Light」など、ハイライト的な扱いだった。後者では、ジェイムスの奥さん、キムもコーラスに加わり、エンディングにはキムとケイトがまるで姉妹のようにしっかりと手を繋いでいる姿が印象的だった。
「Shed A Little Light」が今回セットリストのこの位置に置かれたことは、今の世界情勢を踏まえた上での彼のメッセージのような気がした。社会的なメッセージソングをジャクソン・ブラウンほどには歌わないジェイムスだが、控えめで自然体な彼の曲は、心の奥に残るような気がする。
今日は キング牧師に思いを馳せよう
そして 我々には絆があることを認識しよう
地球に生きるすべての男女に
希望と愛の絆 姉妹と兄弟の絆が
私たちはひとつに結ばれている
この世界に望む思いで
それは 子供たちが自由で逞しく成長できる
そんな世界にしたいという思い
私たちはひとつに結ばれている
目の前に立ちはだかる課題と
その先に横たわる道によって
そう 私たちは結ばれているんだ
Translation by Lonesome Cowboy
「Shed A Little Light」に続いて、彼の曲の中でも特に明るい曲調の「Your Smiling Face」でコンサートはクライマックスを迎えた。こうなると「終わらないでほしい」という気持ちが高まる。一旦、バンドメンバーが引っ込むが、ジェイムスは腕時計を指差しながら「もう1曲演ってもいい?」と舞台袖にジェスチャを送る。実はこのジェスチャは、ライブCD&DVD『One Man Band』(2007年)でもやっていたお決まりのポーズ。ただ、この後、曲に入る前のMCは今回の来日公演でしか有り得なかったはずで、それは「次の曲を故小澤征爾氏に捧げます」というものだった。ご存じの方も多いと思うが、ジェイムスの現在の妻キムは、長年ボストン交響楽団の広報ディレクターを務めてきた人。小澤さんが亡くなった時には、地元『ボスロングローブ』紙に感動的な追悼文を寄稿していた。
"The death last week of Seiji Ozawa, our Boston Symphony Orchestra's conductor for three decades, has summoned a global...
Posted by James Taylor on Monday, February 19, 2024
ジェイムスのアコースティックギターとコーラスだけでしっとりと演奏されたのは「You Can Close Your Eyes」。元々は当時恋人だったジョニ・ミッチェルのために書かれたというこの曲。近年はコンサートのクロージングナンバーとしてよく演奏されているようだが、「目を閉じてもいいんだよ」という歌詞は、まさに小澤さんに向けて書かれたかのように響いた。
だから 目を閉じて
目を閉じていいんだよ
愛の歌なんて知らないし
ブルースはもう歌えない
でも この歌は歌える
僕がいなくなっても
この歌を歌っていいんだよ
Translation by Lonesome Cowboy
この曲の後、鳴り止まない拍手に再度メンバーたちと横一線に並びお辞儀をするジェイムス。誰のコンサートでもよくある光景だが、そこにはこのバンドの温かい「ファミリー」感が確かに感じられた。最後に彼はこう言った。「今日はツアーの最初なのでちょっと緊張していたけど、皆さんが本当に素晴らしかった」。おそらく他のステージでも同じようなことを言っているのだろうが、その言葉に、彼と同じ時間を共有できた幸せを感じずにはいられなかった。
[Set List]
1) Something In The Way She Moves
2) Rainy Day Man
3) That's Why I'm Here
4) Yellow and Rose
5) Anywhere Like Heaven
6) Never Die Young
(Fiddle (and drum) solo)
7) Country Road
8) Sweet Baby James
9) Handy Man
10) Long Ago and Far Away
11) Sun On The Moon
--Intermission--
12) Carolina In My Mind
13) Mexico
14) Steamroller
15) Fire and Rain
16) Up On The Roof
17) Shower the People
18) You've Got A Friend
19) How Sweet It Is
-Encore-
20) Shed A Little Light
21) Your Smiling Face
22) You Can Close Your Eyes
[Members]
James Taylor (Vo / Gu / Harmonica)
Kevin Hays (Key)
Dean Parks (Gu / Pedal Steel)
Steve Gadd (Dr)
Jimmy Johnson (Ba)
Kate Markowitz (Vo)
Andrea Zonn (Vo / Fiddle)
Dorian Holley (Vo)
Kim Taylor (Vo)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
