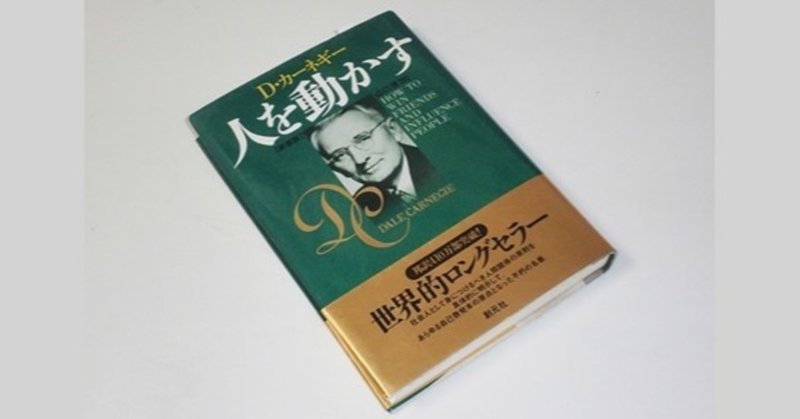
本の記憶。 D・カーネギー 『人を動かす』
本の帯の惹句に「邦訳410万部突破! 世界的ロングセラー」社会人として身につけるべき人間関係の原則を具体的に明示して、あらゆる自己啓発本の原点となった不朽の名著とある。
英文原題は「How To Win Friends and Influense People」
ここでのWinは勝ち負けのWinではなく、gain、getに近い意味だろう。influenceも名詞ではなく、動詞。影響を及ぼす、という意味だ。
サラリーマンだったころ、こういう人間関係のハウツー本を何冊も読んでいるが、この本を読むのは初めてではないかと思う。これも古本屋で三冊200円で売っていた本。忙しい最中なのだが、あらためて、パッと読みして一時間半くらいで読み終わったのだが、妙に感動した。七〇歳を過ぎて、いまさら、どうすれば人生に成功できるか、というような本を読んで感動するのもどうかと思うが、自分学的なことを書くと、オレという人間は生来の心根は素朴で単純なのである。
この本は人生で成功するための秘訣がぎっちりと詰めこまれるように書かれている本だが、この本を自分が20歳くらいのときに詠んでいたら、オレの人生はどうなっていただろうか。人生で成功していた? 成功した人生? 人生の成功ってなんなんだ。会社の社長とか、政府の偉い役人とか、テレビに出て来る売れっ子のタレントとか、具体的な名前は出さないが、名声と栄誉に囲まれた人生が成功した人生なのか。
オレたちのような年齢になって、つまり七〇歳を過ぎて、人生の大半が終わってしまったなと考えているような年齢になると、こういう本に書かれていることを後付けで考えるようになる。この本を読んで、あらためて、あのとき、ああすればよかったなと思うことの大半は、別にこの本を読まなくても、いまもそう思っていることである。ということはD・カーネギーのいっていることとオレが考えていることはたぶん、大部分が一致している。富や名声が人生の成功とは思っていないから、本に書かれていること全部を素直に肯定できるわけではないが、「人に好かれるために」とか「人を説得するために」というような項目で書かれていることをもっと忠実に遵守していたら、勤めていた会社のなかで出世して、社長にはなれなくても専務くらいにはなっていたかも知れない。しかし、マガジンハウスの専務とか社長なんて勘弁してくれという話である。木滑さんがオレのことをどう考えていたかはよく分からないが、1993年の1月に石川次郎が会社をやめてしまったあと、会社のなかで出世したいとか、偉くなりたいとか思ったことは一度もない。むしろ、自分の考える形のいい人生とマガジンハウスの社員の生活とは両立しないと考えるようになっていった。これはマガジンハウスを批判しているわけではなく、自分の編集思想とマガジンハウスが宿命的に課せられたコマーシャリズムやマーケティングとが次第に相容れないものになっていった、という意味である。
富や名声を人生の成功の証明ではないと考えるようになったとき、なにが人生成功の証拠書類になるのだろうか。
この本のなかで、オレが一番考えさせられたのは次のような記述だった。
わたしがまだ若かったころの話だが、当時、わたしは、なんとか人に存在を認めさせようとあせっていた。そのころアメリカの文壇で売り出していた作家リチャード・ハーディング・デーヴィスに、おろかしい手紙を出したことがある。ある雑誌に作家論を書くことになっていたので、彼の仕事のやり方を、直接問い合わせたわけだ。ちょうどその数週間前、ある人から手紙をもらったが、その末尾につぎのような文句が記されていた……
「文責在記者」。
この文句がすっかり気に入った。手紙の主は、おそろしく偉い多忙な要人にちがいないと思った。わたしはすこしも多忙ではなかったが、なんとかデーヴィスに強い印象を与えようとして、つい、その文句を、手紙の終わりに借用してしまった。
デーヴィスは、返事のかわりに、わたしの手紙を送り返してきた。送り返された手紙の余白には「無礼もいいかげんにしたまえ」と書きつけてあった。たしかに、わたしが悪かった。それくらいの仕返しをされてもやむをえない。しかし、わたしも生身の人間で、やはり憤慨した。とてもくやしかった。それから十年後にリチャード・ハーディング・デーヴィスの死を新聞で知ったとき、まず胸に浮かんだのは、恥ずかしながら、あのときの屈辱だった。死ぬまで他人に恨まれたい方は、人を辛辣に批評さえしておればよろしい。その批評が当たっていればいるほど、効果はてきめんだ。およそ人を扱う場合には、相手を論理の動物だと思ってはならない。相手は感情の動物であり、しかも偏見に満ち、自尊心と虚栄心によって行動するということをよく心得ておかねばならない。英文学に光彩を添えたトマス・ハーディングが小説を書かなくなったのは、心ない批評のせいであり、英国の天才詩人トマス・チャタトンを自殺に追いやったのもまた批評であった。若いときは人づき合いがへたで有名だったベンジャミン・フランクリンは、後年、非常に外交的な技術を身につけ、人を扱うのが上手くなり、ついに、駐仏米大使に任命された。彼の成功の秘訣は「人の悪口は決していわず、長所をほめること」だと、みずからいっている。人を批評したり、非難したり、小言をいったりすることは、どんなばか者でもできる。そして、ばか者にかぎって、それをしたがるものだ。
理解と、寛容は、すぐれた品性と克己心をそなえた人にしてはじめて持ちうる徳である。
長い引用になったが、この部分がオレが、この本を読んでよかったと思った、最大の箇所だった。オレもずいぶんいろんなところでいろんな人の悪口を書いている。それはオレの批判が正しいと思ってそうしたことだが、槍玉に揚げられた人たちは、気持ち穏やかではなかっただろう。いまごろ、そんなことに気が付いても遅いし、つい先日も「天地真理ちゃんもいまのような生き方はすべきじゃない」と書いたばかりである。しかし、人は皆、それぞれ都合があってそうしている。その都合というのは[個人情報]なのである。
オレは駐仏米大使に任命されることが必ずしも成功した人生の証明だとは思わないが、何年か前のことだが、元・集英社で長く仕事をしてきた編集者といっしょに本を作ったことがあるのだが、わたしがあれこれと人を批判した文章を書いた部分を読んで「集英社は人の批判をできるだけしないんです」といったことがある。
オレは元マガジンハウスで、自分を大衆文化的には前衛でありたいと考えていて、前衛性の本質は大衆性のなかの保守化した部分の現状を否定することにあると思っている。オレはそのとき「批判がなければものごとはいい方向に進まないじゃないか」と反論したのだが、そういうことでいうと批評行為というのはそもそも[現状への批判行為]なのである。ただ、それでも書き方というものがある、ということなのだろう。
人を批評したり、非難したり、小言をいったりすることは、どんなばか者でもできる。そして、ばか者にかぎって、それをしたがるものだ。
人を傷つける、という意味からすると、本当に「ペンは剣より強い」のかも知れない。このことを肝に銘じて、もの書きとしての残された日々を恬澹として過ごさねばと考えている。 この話、ここまで。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
