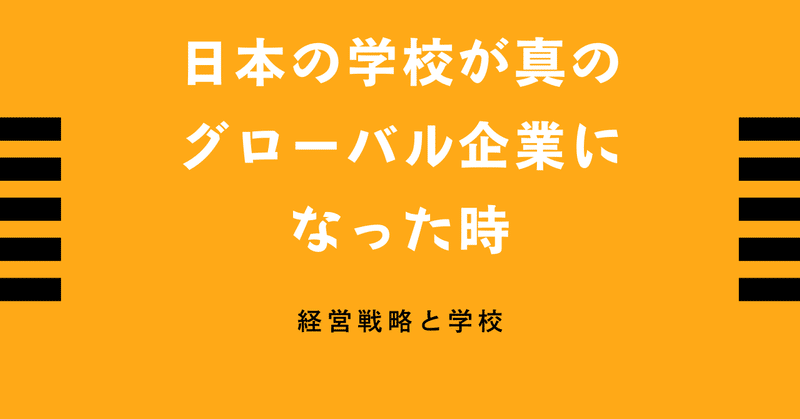
学校が真のグローバル企業になった時 に日本の教育が本当に変わる!
昨日(2022年1月19日)は勤務する私立小学校のプロジェクト会議の日でした。
テーマは2030年以降も選ばれる小学校創りです。昨年9月に30代40代の次世代を担う先生を中心に発足し、2月の管理職プレゼンに向けて佳境に入って来ました。
戦略と言う言葉も、SWOT分析も不慣れな先生達がよく情報収拾をして、考えて、議論して、ここまで来たと思います。ゴールまでもう少し!頑張りましょう!
企業では当たり前の経営戦略。弊社も小さいながらも毎年戦略を立てて動いています。特にここ数年は教育の様変わりと時代の激変で、今までのそれとは大きく違った方向へ舵を切っています。それが奏功するかどうかはこれからですが、ビジネスと勝負には偶然はありません。必然と努力の蓄積です。
幸いな事に学校は昔はあまり経営戦略など考えなくても良かったかもしれません。小渕恵三が言ったように、人口ボーナス期の日本の学校は、不味いラーメン屋にも人が集まる、と評されたほど。本当にその通りで、人が沢山いれば、あれば売れます。だから日本は大学が雨後のたけのこの様に出来たけのですが、今や・・・・
2020年が約84万人、2021年が80万人。年間出生数の事ですね。この減少は統計より7年早いそうです。比して2022年1月現在の小学1年生の人数は、約100万7000人。今から考えると今後6年で20万人減るわけです。
しかし昨年と今年はコロナの影響で空前の(とまでは行きませんが)小学校受験、中学校受験ブームです。人口統計を考えるとこれは一過性の現象と考えざるを得ず、コロナが収束したらどうなるのか?断言は出来ませんが、決して小さくない影響を受ける事は確かだと思います。ちなみに先日仕事で大手の4大お受験塾のセミナーに参加したところ、昨年小学受験全体として志願者数は増えたのですが、その大半は5校が占めていたそうです。その5校の中に私の勤務校も入っていたので、ちょっとプチ自慢でした。
さてこのような状況を考えると、もはや存在するだけでは生き残る事は出来ません。そうすると、もう教育、特に私学の経営は、企業経営と変わらない状況です。わたしは常々関わる私学の先生にはお伝えして来たのですが、私学は教育サービス業です、と。塾と若干目的は違えどジャンルは変わりません。そう考えると、企業が当たり前にやっている手法に則って経営を考えないと、児童や生徒は集まらないと言えます。また時代の変遷とともにポジションを変えないと、いつまでも同じ顧客要望は続きません。時代の変化についていけないと、企業は続きません。学校も大きな岐路に立っている事は誰も疑う余地はないでしょう。
たくさん分析すべき事はあるのですが、重要な事は大きく分けると3つ。外部環境分析と内部環境の分析、すなわちSWOT分析をしてそしてペルソナを決定し、その対象者にどんな教育を提供するのかと言う戦略を立てる事です。
世界、社会はどう変化しているのか、行くのか?私達はどんな歴史や強みを持っているのか?それらを重ね合わせるとどんな人に、どんな教育を提供して行ったら良いのか?を考え出す事なしに、生き残れる事はないでしょう。
よく、知識もスキルもないのにいきなり来年からIBを目指すぞ!とか、医学部合格を打ち出すぞとか言う学校経営者がいます。また、教育とはこうあるものだと言う古い教育観のまま進化出来ない経営者がいますが、これだけ時代が変革期にある事を考えると、どちらもうまく行きそうにありません。繰り返しになりますが、ビジネスと勝負に偶然はありません。必然と努力の蓄積です。
また、トップダウンでこれやるぞ的な80年代の野球部みたいなマネージメントでは、選手はやる気が出ないばかりか、ついてこれなくなるでしょう。若手の先生は特に、現経営者層とは全く違った時代に生まれ、違った環境で、違った教育を受けて来ています。つまり発想や考え方がまるで違います。その人達の意見を無視して相変わらずのマネージメントでは、More Betterを生み出さなければならない時代において、得策とは言えません。むしろ若手の先生の方が時代感や未来感に優れているかもしれません。それをお前はまだ10年早い!で蹴散らしては、新時代に向けた改革など到底無理と言わざるを得ないでしょう。かと行って経験がないのは確かで、時に理屈なき暴走をする事も事実。つまりは若手もベテランもそれぞれの役割を発揮しなければ、改革など叶わないと言えるかもしれません。が、学校の中、教員室の中は・・・
そう考えた時にこれも重要な戦略の一つですが、上位下達のマネージメントの改革、ありそうでなさそな評価制度の改善、これまたありそでなさそな研修制度の確立、そして見えない所でそれらを支えるカルチャー(文化)の刷新。特に文化の醸造はいくら良い戦略を描いても、それを実行する先生達の暖機運転が済んでいなければ、うまく機能するはずがありません。気づいてないかも知れませんが、学校経営者はこの点でも失敗しますよね(先生は気づいているんですけどね、言い出せないんですよね)。
ある程度の規模の組織がゴールを目指すには、其れ相応の準備が必要です。大型タンカーが車の様に進路を変えられないのと同様、組織も急には経営者の思う所へ行ってくれません。”其れ相応の” 方法と時間が必要です。が残念ながら多くの学校経営者や管理職はこのことを経験していません(いきなり外部コンサルを入れて失敗するケースも多々あります)。この至極曖昧な抽象概念を言語化具体化する事がこれからは学校経営にも必要になって来ます。
偶然寝て起きたら学校が革新的変化を遂げている事はありません。この”曖昧”を実行ベースの具体策にしないといけないのですが、残念ながら学校経営者の多くは教育のプロではあっても経営のプロでは無いようです。先生も、保護者から逐一これをやってくださいあれをやてください、と要望されても、総合的に考えて教育が効果を発揮するにはこれこれこう言う我慢や失敗や・・・が必要です!と全てひっくるめたプロの匠の技がそこにはあるはずです。
よってこれからの経営者も経営の匠の技を導入しない限り、選ばれる教育商品を世に出して経営を存続させる事は難しいでしょう。
と考えると、方法は3つ
(教育を知っている)プロの経営コンサルを雇うか、企業マネージメント経験の豊富な人を採用するか、自分で経営を学ぶか。わたしは2か3がサステイナブルだと思います。先生が今ティーチングからコーチングやファシリテーター型へ指導スタイルを変えなければならないのと同様、経営者も様々にスタイルを変えていかなければ、存続は厳しい時代が今きています。
繰り返しですが、6年後は80万人割れです。ちなみに私の昭和43年世代は1学年約220万人でした。
エピローグ
現在先駆けて改革が成功して生徒が集まっている学校もありますが、時代に即した改革かどうかを見極める必要があると思います。つまり先生は真面目な方が多いので、強く強くやれと言われれば従う方が多いですが、働き方改革やWELLBEINGとは完全逆行したやり方で改革と成功を手にしている学校もあります。つまり先生方の半ば犠牲の上に成り立った成功モデルです。
日本の教育が前進するためにも、日本がこれ以上後退しない為にも、教育の中身同様、働き方を含めた学校のあり方全てを真の改革に向かわしめる必要があると思います。その一つが経営戦略に基づいた学校経営です。真に学校がグローバル教育を提唱するのであれば、学校自体がグローバルスタンダードな経営が出来てこそ。声高に叫ばれている働き方改革もグローバル企業と言われる企業では進んでいますが、しかし現在の学校の多くはそうではありません。日本の教育が本当に変わるのは、学校こそがグローバル企業になった時では無いでしょうか?
