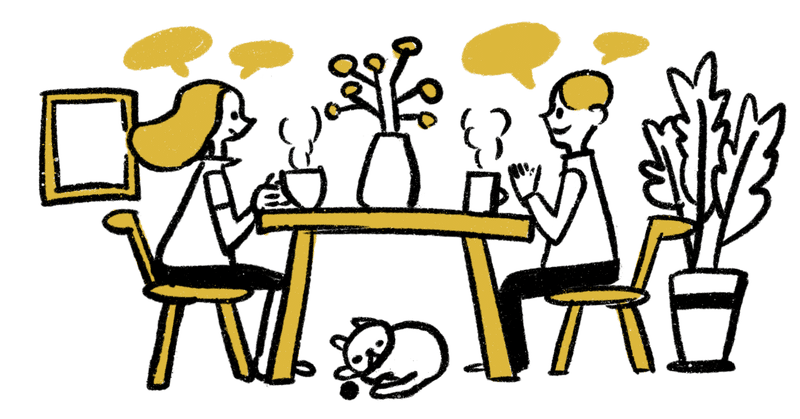
GIGAスクール過渡期の高校でICT教育をいかに実践するか
お久しぶりです。最後に投稿してからかなり日が経ってしまいました。というのも、今年の4月に新しい学校に異動となり、新しい環境に慣れるのに苦労していました。今回は、この1学期間に行なっていた取り組みを紹介します。
その前に現在の教育環境について
前任校は全普通教室にWifiが完備されており、今年度からBYODによる生徒の一人一台端末が開始されました。小・中学校とは異なり、高校は学校ごとに一人一台端末、いわゆるGIGAスクール構想への対応がされています。本県は高校については来年度から進める学校が増えてくる様子で、本校も来年度から導入する予定です。しかし、いまだに教室にWifiルータが設置されておらず、必要な時にルータを持ってきて使っています。そのため、基本的には教員の許可の元、必要に応じてスマホを活用させている状況です。異動当初は、このギャップに衝撃を受けましたが、前任校が恵まれていただけで、日本の多くの高校はネット環境も含め充実していくのはこれからなのだろうと思い直しました。そこで、まさにGIGAスクール対応過渡期にある本校で、ICTで教育を変えていくモデルケースになろうと決意し、この1学期間様々な取り組みを行なってきました。それでは、核となる2つの取り組みについて紹介します。
ペーパレスHR運営
本校の校則ではスマホは基本的に使用禁止になっていますが、教員の許可があれば授業中など必要に応じて使用可能です。校内の情報責任者によりHRごとにGoogle Classroom(以下、Classroom)が作成されており、アンケートや緊急の連絡手段として使われています。私は担任としてこのClassroomをもっと「日常化」するために、HR運営は全てClassroomで行うことにしました。いわゆる掲示物は全てpdfなどにデータ化し、Classroomの「授業」で共有をしています。また、ちょっとした連絡はストリームで行なったり、面談の日程調整や各種アンケートはGoogleフォームを活用しています。
数学のブレンド型学習
私は数学教諭で、前年度までは伝統的な一斉講義型の授業をしていました。細かい工夫はしていたものの、この授業のやり方を刷新することはしてきませんでした。しかし、GIGAスクールによりICT環境が充実してきたので、今年度からブレンド型学習に挑戦しています。授業のClassroomを作成し、予習用・復習用・発展用などのプリント教材を配信しています。紙での配布はしません。そのため、授業中はスマホの使用を自由にしています。また、授業中に教科書の動画教材を見る時間を設ける、グラフアプリでグラフの変化を見る活動なども行なっています。何より最大の特徴は、50分の授業時間の内、半分は生徒の自由な演習の時間にしていることです。これにより、生徒一人ひとりを指導する時間が確保されることと、生徒が自分で学習を計画して実行する主体性を育むことができると考えています。
今後の展望
この2つの取り組みはまだまだ発展途上で、生徒のフィードバックや他校での実践報告を元に、常に改善を続けています。また、こういった教育活動をnoteなどで共有することによって、他校の先生からフィードバックをいただいたり、GIGAスクールの過渡期で悩んでいる先生の力になれるのではと考えています。
掛川教育フェス2022
実は、今週末に「掛川教育フェス2022」というイベントでこれらの教育活動について発表させていただきます。対面・オンラインどちらでも無料で参加可能ですので、ご都合がよろしければぜひお申し込みください。

日時:8月21日 9:30~11:30
Google for Education認定トレーナー笠原先生と私で、掛け合いをしながらのコラボ発表です。イベント詳細やお申込みは以下のリンクからお願いします。
笠原先生もイベントに関する記事を書かれています。私も当日お話をお聞きするのを楽しみにしています。
実行委員長の一人の吉川先生はイベントの記事を複数書かれています。ぜひご覧ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
