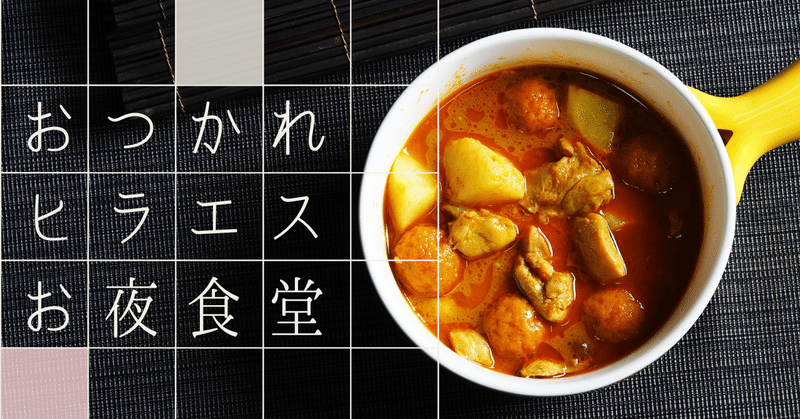
『おつかれヒラエスお夜食堂ーあやかしマスターは『思い出の味』であなたを癒しますー』第6話
第5話
第6話
ーー翌日朝から、私宛に電話がかかってきた。昨日のお客さんだ。
おっかなびっくり通話ボタンを押してみると、打って変わって申し訳なさそうな声が聞こえてきた。
「ごめんな、昨日は。あんなに遅くまで働いているあんたの気持ちも考えなさいって、娘に怒られちまったんだ。そりゃあ確かに俺だって定年前は部下の無茶苦茶なミスに振り回されて嫌な思いたくさんしたのに、あんたに同じ思いさせちまうなんてな、いやあ、悪かった」
後ろから娘らしき声が、「早く謝って切ってあげなさいよ!」と叫んでいる。
急に、電話越しの『クレームのお客様』が、ただの一人のおじいさんに変わったような気がした。
私は深く頭を下げながら答えた。
「とんでもございません。こちらの不手際のためにお客さまにご不快な思いをさせてしまいました。直接お詫びに伺うようにしていましたが」
「いやいやいや! 来なくていいよ、すまないね! いやあ、よく考えたらね、腹が立つならすぐにガチャンって切りゃいいのさ、こっちが。それなのに延々と罵倒しちまってね。それでいて『こんな遅くまで働いて云々』なんて、悪いこと言っちまったよ。本当に悪かった!」
電話が勝手に娘に変わる。
娘さんが、「ほんっとうにごめんなさい!」と詫びた。
「うちの父、定年になってから本当に電話にキレて憂さ晴らしすることが増えたんですよ! 自分で注文した通販なんだから、電話がかかってきて怒るのは筋違いだって何度言ってもこれで……」
「とんでもございません。今後の電話応対品質向上のためお父様の貴重なご意見、大切にさせていただきます」
「ああもう、ごめんなさい本当に……私が通販処理対応してもよろしいですか?」
「お父様の同意があれば可能でございます」
それからは和やかに対応は進んで行った。
コーヒーを淹れていた常盤がこちらを見て、グッと親指を立ててくれる。
上から目線で激励されてちょっとイラッとするけれど、今は気にしている場合ではない。
電話の向こうで、通話相手が娘さんからお客様に再び戻る。
彼は私を激励した。
「あんたしっかりやりなよ。応援してるからさ。あんたの誠意、ちゃんと通じたよ」
ーー娘に怒られたからって、調子いいんだから。
そう思って苦笑いしてしまうけれど、無事に終わったあとはもうどうでもいい。
電話が切れたのち、私は清々しい思いでコーヒーを口にした。
常盤がいつものように気安く声をかけてくる。
「コーヒーありがとう」
「まあね。水城さん、やったじゃん」
「本当よ。常盤に頼らなくて済みそう」
「いや、支店長が心配しすぎだっての。水城さん一人で乗り込んで行ったら危険だから、俺についていけってさ」
私は目を瞬かせる。
「危険? 私だけじゃ頼りないって思われたんじゃなくて?」
すると常盤は、ぶんぶんと大袈裟に、顔の前で手を横に振る。
「違う違う。水城さんが頼りないわけないでしょ。一番厄介なパート軍団を操りながら、売り上げトップの常連なのに」
「……」
ーー嘘でしょ? 私、そんな目で見られていたの?
私は呆気に取られた気持ちで、常盤の言葉を聞いていた。
自分が思い込んでいるものが、本当に正しいのか?
ガラガラと何かが壊れていくような気がした。
常盤はデスクにもたれて、コーヒーを飲みながら言う。
「でも残念だな。水城さんの謝罪見に行きたかったのに」
「謝ってるところ見に行きたいって、趣味が悪いわね」
「ああ違う違う。水城さんクレームの謝罪上手じゃん」
彼は笑って言った。
「水城さん、柔らかく相手を立てつつも、しっかり毅然と相手に折れないでしょ? そのやり方がすごく上手いから真似したいんだけど、俺それ無理なんだよなあ。笑ってごまかしゃいーじゃんってなってさ」
初めて聞いた。
「俺ってすみませんでした! ってストレートに謝るか、こっちが悪くてもゴリ押しで笑顔でなあなあで押し通す感じじゃん? そういうやり方じゃ太刀打ちできない相手も出てくるから、あの手この手で相手を黙らせる水城さんの手腕、しっかり見ときたかったのに」
「笑って誤魔化せるのも才能でしょ、ずるいわよ」
私がそう言うと、彼は「まあね」と片目を閉じる。
「でもそんな風に思われてるなんて知らなかったわ……だって支店長、私よりあなたのことを評価してるって感じだし」
「は? それ嫌味? 俺、水城さんにバチバチに対抗意識燃やしてんだけど」
「ええ……」
「まあ、SVリーダーは俺がもらってくけどね」
目を眇めてニヤリと笑い、常盤がコーヒーカップを置いて去っていく。
私は呆然としていた。
ーー定石じゃない、定番じゃない。
そう思い込んでばかりでーー自分を一番否定していたのは、自分だったのでは?
私はなんだか、急に、世界の見え方が変わったような気がした。
◇◇◇
昼休み。
私は休憩室でスマートフォンをいじろうとして、胸ポケットに入れていたショップカードに気づく。
「そうだ、うまく行ったこと店長さんに報告に行かなきゃ」
あれだけ赤裸々に自分のことを話した後だと、ちょっと気恥ずかしいけれど。
あのカレーもまた食べたいし。
「あれ……」
私はショップカードに書かれた住所で店を検索する。
けれど店は、どう頑張っても出てこない。
この世にはない地名だった。
「プリントミスかな? じゃあええと……終点の駅のところから探せば……」
私は乗り慣れた電車の終点をチェックして、私はハッとした。
ーーそうだ。あんな場所が終点のわけがない。
終点はあんな駅じゃないと、知っていたのに。どうしてそのことを忘れていたのか?
「そ、そうだ。クレジットカードの使用履歴!」
私は慌ててクレジットカードアプリを開いて、使用履歴をチェックする。
しかし。
「……2回払ったはずなのに、書いてない……」
一人だけの休憩室で、私はただただ狐につままれたようなショックを受けていた。酔っ払いならともかく。ショップカードという証拠がないならともかく。
私は2回も行って、2回も、美味しいカレーを食べたのに。
私はショップカードを改めて見る。
そこには可愛らしい丸文字で「またどうぞ」と描かれていた。
書いてくれた女の子と、店長は確かに存在している。
けれど、私が二度といけない場所に彼らはいるらしい。
「……『おつかれヒラエスお夜食堂』、か」
あれは夢だったのだろうか。
疲れたあまり、道を間違えて入り込んでしまった場所なのだろうか。
なんとなくもう二度といける気がしない。
少なくとも、私が『思い出』の味を欲しない限りは。
「不気味なのに、なんだか怖くはないんだよね……」
そう。私は不気味だと感じていなかった。
二人との出会いはーー例えば、道に迷ったときに道を教えてくれた、名も知らないどこかの親切な人との一度限りの出会いのような。
たまたま偶然かつ幸運なな出会いだったように思う。
このショップカードがあるあいだはーー私まだ、頑張れる気がした。
◇◇◇
そして帰り。
すっきりした気持ちでタイムカードを押し、電車に乗った。
もう一度あのお店に行けるかな、と思ったけれど、立ったまま目を閉じてうたた寝っぽいことをしてもきっちりいつもの駅にたどり着いた。
ところてんのように駅から押し出されると、目の前にあるスーパーの輝きが妙に目に止まる。
スーパーが開いている時間に帰れているのだと、新鮮な気持ちになった。
「久しぶりに……自炊しよっかな」
私は久しぶりにスーパーに寄った。
生ゴミが出るのが嫌で、料理をするのも嫌で、最近は全然やっていなかった。
その時ふと、生鮮食品売り場に見慣れないものを見かける。
「これ……パックの野菜? 簡単でいいわね」
野菜を切って火を通してパックにしてあるものが置いてある。二人分くらいの食材の量。
まないたを汚さずに、時短5分で煮物料理!と書いてある。
母の背中を思い出す。あの頃の母のように苦労した誰かが、このパックを考案したのかな。
私はパックの野菜と一緒に、母が好きだったブランドのカレールー、そして「カレーには牛乳だよね」と、牛乳をかごに入れる。最後にレジの近くに置いてあった、パックの千切りキャベツも最後に放り込んで。
料理なんて時間の無駄だと思っていたけれど、不思議と楽しいと思えた。
帰宅して誰もいないワンルームに帰り、疲れてごろ寝したくなる前にキッチンに行く。
長い間使っていなかったコンロの元栓を開いて、鍋を軽く洗ってコンロに置いて、水を入れて野菜を入れる。
すでにくたくたに煮込まれている野菜は、水の中で気持ちよさそうにゆっくりと広がっていった。
コンロの炎とキッチンの灯りを前に、私はじっと過去を思い出す。
ふと、母の笑顔を思い出した。
忙しくても、キッチンに立って手料理を作ってくれていた母。
それは『手料理の母の義務』を務めようと必死だったのだろうけど。
「お母さん、嬉しそうだったな……」
私が陶器のお皿やガラスのコップを割らずに洗えるようになった時、濡れた冷たい手で頬をつついて褒めてくれた時の笑顔。
一緒に味見をして、味を確かめて一緒にルーを溶かした時間。
鍋がふつふつと湧き上がるのと同じように、涙が頬を伝った。
鍋を前に確かに、二人で幸福な時間を過ごした幻が見えた気がした。
ーー出来上がったカレーを前に、私はハッとする。
「あ……ご飯、炊くの忘れてた」
思わず出てしまった自分の声が、あの日の母の声にとてもよく似ていて。
母もそういえば、ご飯を炊くのを忘れて天を仰いでいた日があった。
「……ふふ、そうだよね。忙しかったら忘れちゃうよね」
私はパックの千切りキャベツを皿に盛り、カレーをたっぷりと上にかける。
アラサーの夕食なのだから、糖質制限するのもまた一つの形だと気持ちを切り替えた。
野菜が時短パックでくたくただから、しゃきしゃきのレタスでちょうどいい歯応えになるだろう。
最後にシンクで、お皿とスプーンを丁寧に洗う。
「うん。…… ご馳走様、お母さん」
スプーンの表面に映る私は、あの日の母によく似た顔で、にっこりと微笑んだ。
第7話
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
