
【幡野広志さん①】鎮静死だけでは取り除けない死の需要。死にたい理由は痛みだけじゃない
関口祐加監督によるドキュメンタリー映画シリーズ『毎日がアルツハイマー』(略して『毎アル』)の公式noteにようこそ。
このnoteでは、シリーズ最新作『毎日がアルツハイマー ザ・ファイナル〜最期に死ぬ時。』の公開まで、映画のテーマである「死」についての記事を定期的に更新していきます。
今回は、昨年がんであることを公表された写真家の幡野広志さんに、病気がわかってから、感じ、考えたことについてお話しを伺いました。
認知症のお母さんの立場で、この映画を見た
―『毎日がアルツハイマー ザ・ファイナル』をご覧になって、いかがでしたか?
「まじか!」って言っちゃいましたよ。最初のほうで、関口監督と話しているお母さんが「なぜ私が家を出て行かいないとならないんだ」って怒るじゃないですか。でも、1時間後にはもう忘れて、久しぶりに会ったかのように接するという。
うちの近所に妻の実家があって、86歳ぐらいの祖母がいるのですが、やっぱり認知症なんですよ。僕も何度も会っているので、認知症のことはちょっとわかっているつもりでした。でも、全然そんなことがありませんでした。これは大変だなと思いましたね。同時に、「自分がそうなった時にどうするか」とも考えました。
―そういう見方をなさるとは、思いもよりませんでした。
僕は多発性骨髄腫という血液のがんで、治る見込みはありません。がんは、死ぬ前に「せん妄」といってボケちゃったようになることがあります。だから、僕はこの映画を認知症のお母さんの立場になって見ました。スイスのエリカ先生(自死幇助クリニック院長)は「脳卒中や認知症になり、自分で決断できなくなることが一番の恐怖」と言っていましたが、わかるんです。僕もやっぱりそうなんですよ。
―自死幇助は日本では認められていませんが、この方法についてどう思われますか?
あっていいと思います。でも、自分にはできないだろうな。
2017年12月にがんが見つかって、とんでもない痛みだったんですよ。横になることさえできない痛みが、長期間続きました。夜もイスにもたれかかったまま30分ぐらいウトウトして、また痛みで起きるっていう繰り返し。それが2~3週間も続くと、だんだん判断力が下がってきて「死のう」と思うんです。強烈な痛みからは逃れられないし、誰からも理解されませんでしたから。
―死を考えざるを得ないほどの痛みなのですね。
そう。僕は狩猟をしますが、がんが見つかった12月はちょうど狩猟の時期なんです。だから散弾銃も実弾も家にあった。その弾を込めて引き金を引けば、自分がどうなるかはわかっています。散々、鹿とかイノシシとか大きな動物の死を見てきましたからね。それでも、やっぱりできなかった。死ぬのは、怖い。
だけど選択肢の一つとして、自死幇助はあっていいと思うんです。
―それはなぜでしょうか?
日本の年間自殺者数は減ってきたとは言え、まだ2万人以上います。さらに、不審死が毎年1万人くらいいるという説もある。それだけ自死の需要があるということですよね。
僕は青木ヶ原樹海で、まさに自殺しようとしている方に会ったことがあります。中年のサラリーマン風の男性でした。樹海は電車とバスを乗り継いでやっとたどり着くところですから、「なぜわざわざこんな所で死のうと思うんですか?」と聞きました。その方は「死ぬ場所がないんですよ」と言われました。電車に飛び込んだら多くの人に迷惑がかかる、家で死んだら家族に迷惑がかかる、ビルから飛び降りたら下にいた人をケガさせるかもしれない、と。 その話を聞いて、ちゃんと死ねる場所があってもいいんじゃないかなって、正直、思いましたね。
―もしも自死幇助を行う機関があれば、相談に行って自殺を思いとどまる人もいるかもしれません。
そうそう。逆に救いになる可能性がある。
僕は、本の執筆のために色んな人に取材をしていますが、自死幇助が合法化している国の医師に会ったことがあります。その国では、医師が用意した致死性の薬を自分で飲むそうです。でも、薬をもらったことで「いつでも死ねるわけだから、今じゃなくてもいい」と思う人もいるんですって。
そういう話を聞くと、自死幇助や安楽死は単に死ぬためだけの方法じゃないぞって思います。
―場合によっては、自死幇助や安楽死が最後のセーフティーネットになり得るのですね。今回の映画の中で、イギリスのヒューゴ先生(認知症ケア・アカデミー施設長)は、「安楽死というオプションを持つことで、はじめてそれを『しない』という選択ができる」と言っていました。
そこにはすごくうなずきました。誰だって苦しんで死にたくはありませんから。でも、がんで家族を失ったご遺族に取材すると、多いんです。苦しんで亡くなっている方が。痛みに苦しみもだえて、壮絶な最期を送ったという方が結構いて、ご遺族はトラウマになるくらい後悔にかられるんです。僕は、自分ががんで死ぬことがわかっています。その時は、家族にトラウマを残さないで逝きたいですね。
―苦しまずに死ぬことは、ご家族のためでもありますね。
そうそう。仮に自殺をしてしまうと、残された家族はまたとんでもないトラウマを抱えます。「どうして私が救えなかったんだろう」と苦悩する人の話をたくさん聞いてきました。だから、自殺は全力で避けるべきなんです。それでも、どうしようもない場合があるから、自死幇助や安楽死という選択肢はあった方がいいんじゃないかな。
鎮静死だけでは取り除けない死の需要
―日本は自死幇助や安楽死は認められていませんが、人工的に眠らせたまま息を引き取る「ターミナル・セデーション」(鎮静死)は行われています。幡野さんはTwitterで「鎮静死だけでは取り除けない死の需要がある」と投稿されていました。このことについて詳しく教えてください。
日本の医師は、がんで苦しんでいる患者に「痛みは取り除きます」とよく言います。実際、痛みは薬を使ってコントロールできるわけですが、死にたい理由は痛みだけじゃないんです。
僕が取材した60代くらいの男性は、がんで緊急入院をしたそうです。翌日、勤務先の会社の方がお見舞いに来られましたが、そこで会社を辞めてほしいと告げらました。社宅に住んでいたそうですが、会社を辞めた翌月から家賃が発生するとも言われました。その方はパニック状態になりながらも、渋々受け入れるしかありませんでした。
会社を辞めて収入が途絶えた上、治療費や家賃は発生する。失業手当は、次の仕事を探す人がもらえる手当ですから、重い病気じゃもらえない。そして体はつらいわけです。さらに、その方は離婚されていて、看護師が一生懸命、別れた奥さんに連絡しようとしても全然つながらない。この状況で、「がんの痛みは取りますから」と言われても、全然、大丈夫じゃないわけですよ。
―死を考えてしまうほど追い詰められてしまう、と。
痛みが取れたとしても、その先に生きる希望がないとしたら、そうなりますよね。
僕は、がんの痛みを取り除いたことで、まだやることがあると思ったし、子どもも小さいから生きていける。でも、その男性と同じ立場だったら、絶望していたかもしれません。
これは医師の認識不足なところだなと思うのですが、病気の症状を抑えたから大丈夫なんてことはないんです。人間の人生はもうちょっと複雑ですから。鎮静死で安らかに亡くなる人は、実は一部の幸せなケースじゃないでしょうか。健康な時にどういう人間関係を作っていたかが、ものすごく反映されるのが最期なんだなって思います。
―ある医師が話していたのですが、重い認知症で家族がいない患者さんの終末期をどうするか決める際は、主治医や看護師、ケースワーカーに加えて、第三者の医師も交えて話し合うそうです。
病院によって違うとは思いますが、ターミナル・セデーションを施す時も主治医、患者、家族だけじゃなく、ほかの医師や看護師、薬剤師も含めたチームで議論するそうです。もちろん、それは必要なことだと思います。でも、ターミナル・セデーションにストップがかかる可能性が高くなっちゃうんです。
患者が「もう楽にしてほしい」と思っているのに、医師は「いや、まだいける」と治療を続けたがるケースはすごく多いようです。よく、医師は「引っ張る」という言い方をするのですが、それによりなかなか緩和ケアを受けられません。
―まだまだ命を引き延ばすことができる、ということですか。
そう。僕も血液がんですが、特に血液がんの医師はその傾向が強いみたいです。血液がんの患者さんやご遺族に取材すると、亡くなる4日前にようやく緩和ケアを受けられたという話もあるくらい、本当にギリギリまで引っ張られるんです。
だから、最期をどうするかの議論に色んな人が関わるのはいいのだけれど、医療者だけでなく、もっとほかの立場の人も関わる必要があるのではないでしょうか。
「患者と看護師VS医師と家族」の闘い
―なかなか緩和ケアを受けられないのはつらいですね。
僕は自分の体験から、がんになった人は最初から緩和ケアを受けた方がいいと思っています。だけど緩和ケアに対する一般的な認識は「亡くなる間際に行くところ」です。これまで医師の判断によって亡くなる1~2週間前にならないと行けないところでしたから、それはそう思いますよ。
医療者は変わってほしいし、一般の人もちゃんと考えてほしいですね。最終的に苦しむのは患者と家族です。自分が苦しみたくない、家族にトラウマを残したくないのであれば自分から緩和ケアを求めて、それはできないと言われたら病院を変えたっていいわけです。
―幡野さんが緩和ケアを受けることができたのは、医師に繰り返し苦痛を伝えたからだとか。
もう何度も何度も言いました。とにかく痛みがつらい、眠ることもできないと主治医に訴えたら、「1回、緩和ケアで診てもらいましょうか」となって。
緩和ケアでは痛みを薬でコントロールするだけでなく、精神科医や看護師、カウンセラーが患者の話を聞いてくれます。緩和ケア認定看護師という資格を持った看護師がいるのですが、僕はその方と出会えたことで救われました。お名前はたぶん一生忘れないでしょうね。命の恩人と言っても過言ではありません。
看護師に話を聞いてもらうだけで、患者としては劇的に救われるんですよ。なぜなら誰も話を聞いてくれなかったから。痛いと言っても誰も理解してくれなかった。
―ご家族もですか?
申し訳ないけれど、理解してくれなかった。無理もないんです。想像を絶する痛みですから。こればかりは当事者になってみないとわからない。
―ご家族は、幡野さんのがんに胸を痛めている最中でもありますものね。
そう。家族は家族で精一杯。だけど、こっちはそれ以上に緊急事態が起こっているわけです。いろんながん患者さんを取材すると、みなさん孤独を感じていました。というのも、医師が目指すゴールと患者が目指すゴールは、往々にしてちょっと違うんです。医師はとにかく長く生かしたいけれど、患者はとにかく苦しみたくない。でも、家族のゴールは医師と同じで、長く生かして欲しいっていうことが多い。医師と家族がタッグを組んだら、患者に勝てるわけがありません。
だから、「医師や家族が言うから」と望まない治療を受けている患者も少なくないんです。本当に患者の味方になってくれるのは、看護師だけだと思います。看護師は一歩引いて見ていて、「先生、ここまでしなくても」とか裏で言ってくれることもあるんです。ただ、医師と看護師では圧倒的に医師の立場が上ですから、患者と看護師VS医師と家族じゃ、やっぱり負けるんですよ。
―家族は患者さんの気持ちに寄り添うイメージがありましたが、必ずしもそうではないのですね。
家族は時として「敵」になってしまうものだなと、僕は思いますね。闘病って病気と闘うだけではなくて、そういう内輪揉めと闘わなくてはならないことが結構あるんです。
―現在、幡野さんは奥様と足並みをそろえて闘病されていますが、奥様が目指すゴールは少しずつ幡野さんの方に寄ってきたのでしょうか?
やっぱり最初は、少しでも長生きしてほしいと言われました。子どもがまだ小さいので、妻からすれば当然でしょう。でも、長い時間をかけて説得しました。生きていればいいというものではないと。
僕と妻が同じ目的地を持てば、医師はそこに行かざるを得ません。自分が望む最期に至るには、まずは患者側が目的地をしっかり決めることがとても大切だと思います。けれど、がんの患者さんの多くは高齢者ですよね。非常に難しい問題と思います。
(インタビュー:越膳綾子)
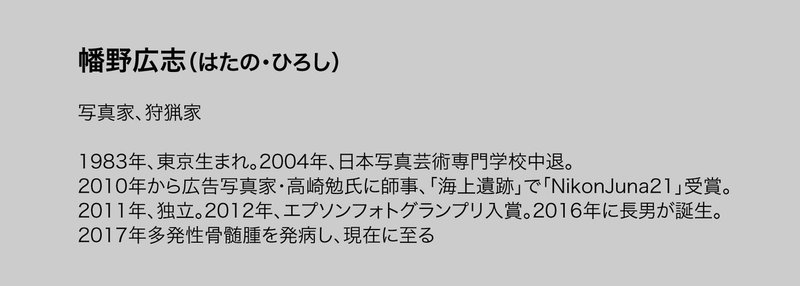
次回も引き続き、幡野広志さんのお話を伺います。そちらもお楽しみに!
『毎日がアルツハイマー ザ・ファイナル〜最期に死ぬ時。』
7/14(土)〜ポレポレ東中野、シネマ・チュプキ・タバタほか全国順次公開
>>>「最期の時」を考えるトークイベントを連日開催<<<
>>>好評・再上映中<<<
『毎日がアルツハイマー』
『毎日がアルツハイマー2 関口監督、イギリスへ行く編。』
6/30(土)〜7/13(金)ポレポレ東中野
7/1(日)〜7/13(金)シネマ・チュプキ・タバタ
ヒューゴ・デ・ウァール博士(『毎アル2』出演)来日 記念イベント
〜「認知症の人を尊重するケア」その本質とは?〜
【日時】7月24日(火)19:00〜 (開場 18:40)
【会場】日比谷図書文化館・コンベンションホール
映画監督である娘・関口祐加が認知症の母との暮らしを赤裸々に綴った『毎アル』シリーズの公式アカウント。最新作『毎日がアルツハイマー ザ・ファイナル 最期に死ぬ時。』2018年7月14日(土)より、ポレポレ東中野、シネマ・チュプキ・タバタほか全国順次公開!
