
【井藤佳恵先生】どんなに認知症が進行しても、今現在の意思を尊重する
関口祐加監督によるドキュメンタリー映画シリーズ『毎日がアルツハイマー』(略して『毎アル』)の公式noteにようこそ。
このnoteでは、シリーズ最新作『毎日がアルツハイマー ザ・ファイナル〜最期に死ぬ時。』の公開まで、映画のテーマである「死」についての記事を定期的に更新していきます。
今回は、東京都立松沢病院・精神科医の井藤佳恵先生のインタビューです。認知症の方の終末期についてお話しを伺いました。
―井藤先生は老年精神医学がご専門ですが、認知症のある人はどのように終末期に至ることが多いのでしょうか?
病院に入院している人の場合は、徐々に口から食べられなくなり、誤嚥性肺炎を繰り返すようになります。だんだんと体力が落ちて寝ている時間が長くなり、終末期へと向かいます。
食べることへの関心がなくなった時、あるいは食べたいけれど嚥下(飲み込み)機能が損なわれている時に、水分や栄養の補給をどうするか。ここが大きな分かれ道です。
昔であれば老衰としてとらえ、「水を一口飲んだね」などといいながら在宅で2週間くらい過ごして、枯れるように亡くなっていたのだと思います。しかし、病院ではそれが難しくて、何らかの医療的処置をすることがほとんどです。
―どのようなオプション(選択肢)があるのですか?
多くの場合、病院で水分を点滴します。それでも高齢者の血管はもろいので、針を刺すとつぶれてしまいやすい。血管から点滴ができなくなったらどうするか。
次の選択肢の一つは中心静脈栄養(IVH)で、鎖骨下の静脈に針を刺したままにして栄養を入れます。ほかに、胃ろうを増設して胃に直接、栄養を注入する方法と、経鼻胃管といって鼻から管を通して胃に栄養を入れる方法がありますし、持続皮下注射という方法もあります。
持続皮下注射がご本人にとって最も侵襲性(体に有害となり得ること)の低い医療と考えられます。皮膚の浅いところに針を留置して、1日500ミリリットルくらいの水分を少しずつ浸透させます。生命を維持するには十分な水分量ではないので、方針としては、静かに看取るということになります。
―家族はそうした処置が必要になったことを、すぐに受け入れられるのでしょうか?
「食べられない」ということを、その人の寿命だと考えるのか、認知症の経過に含まれる以上は病気と考え、治療の対象としていくのか、どちらの捉え方をするかだと思います。
現実には、治療に責任を負っているのは主治医ですので、その価値観に家族が全く影響されないということはないかもしれません。医師にもそれぞれの医療倫理があって、最期をどう過ごすかという時には医師の信念が出てきます。それに家族が同調する場合もあるし、受け入れない場合もあります。
誰しも、人がいつ死ぬということは知っていても、死が「もうすぐ」という状況についてはあまり知りません。認知症のある人も、いきなり食べられなくなるわけではなく、よくある経過は、亡くなる1年前くらいからだんだん食欲が落ちていきます。体重が5キロくらい減ったところで、家族が「何かの病気じゃないか」と思って病院に連れてきます。家族は、当たり前のように精密検査をして、治療をして治るものと思っています。でも、すでにそういう状態ではないこともあります。
―例えば、どんなケースですか?
例えば、重い認知症の人にがんが疑われる場合を考えます。認知症が進むと予想外の動きをすることもあるので、CTや内視鏡などじっとしていなければならない検査が難しいことが多くて、検査の際に使う鎮静薬や造影剤も体に害を与えるリスクがあります。
ですから、家族には「とりあえずの検査が命に関わりかねません」という説明から始めます。現実を受け入れるには時間が必要で、「本当にそうなんですか」「放って置いて病気が進んだらどうするんですか」と言われることがあります。
―そうしたなか、どのように意思決定をするのでしょうか?
患者さん本人の意思がわかるのであれば、もちろんそれを尊重します。しかし、認知症が進行しているとなかなかご本人とじっくりまとまった会話をして決めていくということができません。そういう場合は、本人のことをよく知る家族、担当医師、看護師、ケースワーカーなど、多職種で話し合うことになります。
点滴までに留めるのかどうかという判断がまず1つあり、そうでなければ次のステップとして、IVHか経鼻胃管、胃ろうの大きく3つがあります。最近は「胃ろうは絶対にいやだ」と言いながら、経鼻胃管は希望する人が非常に多いです。2つは原理として同じなので、矛盾しているようにも感じるのですが、「何もしない」という選択をするのは家族にとってはすごく辛いことなんですね。そういう辛さは医療者にとっても同じです。
―前もって自分が受けたい医療処置について書いた「事前指示書」を用意している人はいますか。
家族がそうした書面を持ってくることはあります。意思が残されていれば、それは頼りにします。何もないよりはうんといいです。でも、人の意思はその時々で変わるものです。認知症がどんなに進んでも、その時点で示した意思を尊重したいと思います。
認知症が進行してほとんど寝たきりの状態でも、「もういい」と手を払ったり、顔をしかめたりして意思表示をすることがあるんです。その行動が意味するところは、点滴がいやなのか、点滴を続けて延命することがいやなのか、あるいは別なことなのかはだれにもわかりません。親しい家族がいる場合は、本人がいやがっているように見える処置を続けて予想される予後、やめる場合の選択肢とその予後について説明し、どのような選択をするか話し合います。
“生”への執着があるからこそ、終活ノートを書く
―昨今、書店には終活関連の本が並び、「自分の希望を書いておくことが大事」と言われますが、それで解決するわけではないのですね。
ほとんどの場合、終活ノートには自分の理想の姿を表現している人が多いように感じます。でも、いざ死が迫った時も同じ気持ちとは限りません。
「食べられなくなったら何もしないでほしい」と意思表示をしていた人が、がんの告知をされてむせび泣くこともありますし、認知症が進んで嚥下が困難になった時に盗食を繰り返すこともあります。
“生”に執着したくないからというより、“生”への執着があるからこそ、終活ノートを書くのではないでしょうか。
―どういう時に、終活ノートに書いていたことと、実際に死期が近づいた時のギャップが大きくなるのですか。
食べたいという気持ちより前に、身体の機能が低下してしまった時などはそうです。そうすると本人の中でまずギャプが生じてしまう。
例えば、レビー症型認知症は身体機能の衰えが先に始まります。本人は、まだ食べたい、動きたいという気持ちがあるのに、それが難しい。逆に、医療的処置によって体の機能は保たれているのに、アルツハイマー型認知症が進んで食べることへの興味を失うこともあります。脳と体が同調して年を取れたらいいのにな、と思います。でも、必ずしもそうはならないわけです。
家族は、生にすがる姿を見て「変わってしまった」と感じるかもしれません。でも、今の姿を否定して、病気になる前が本来の姿ととらえるのは、さみしいことです。
―本人が意思表明していても、家族は難しい選択を迫られそうです。
ある女性は、お母さんの死期が近づいた時、「私が母の寿命を決めることはしたくない。もう従前の医療をしてほしいとしか答えられない」と言っていました。本人ならどう思うと推測しますか? と聞くと「あらゆる延命はいやだと言っていたので、胃ろうも経鼻胃管もいやなはずです」と即答されました。それでも、娘である自分が最終決定をすることはできないというのです。とても正直で自然な気持ちだと思います。自分が親の死期を早めたかもしれないと思うと、そのあと生きていくことが大変になる家族もいるのです。
―意思決定をしたあとで、家族の気持ちが変化することはありますか?
もちろんよくあります。病院では、皮下静脈注射をしてから亡くなるまで、2~3ヵ月くらい穏やかな時間が続きます。ここで「本当に何もしなくていいのか?」「もう少し回復できるのでは?」と家族は悩むのです。「やっぱり栄養を入れてほしい」と言う家族もいます。
多分、病院の中に、穏やかな時間が続くことを「こういう時間がもててよかった」と思うよりも、「もっと良くなるんじゃないか」と思う価値観があるので、そういう中で家族が「穏やかならチャレンジしたい」と思われるのも理解できます。
―家族は常に葛藤しているのですね。
そうですね。ある女性は経鼻胃管の処置の際、ものすごい抵抗を示されているので、ご主人に「本人にとっていい処置なのか正直、わからない」と話したことがありました。親族全員が集まって話し合ったところ、結果は、ご主人の望むことがその女性の望むこと、でした。女性は、ご主人が会社をやめてもついて行くような放浪の人生を、直近まで送っていたそうです。最期だけ夫の意見に反対したがるとは思えないと。確かにそういう生き方もあるわけです。
―終末期をどう過ごすかは、それまでの生き方や家族との関係性が密接に関わっているのですね。
終末期というと、あたかも本人に確固たる意思があって、それを叶えるべき、と語られがちですが、幻想だと思います。
だって、人間は生きている時から、自分の希望だけで物事を決めることはあまりないじゃないですか。ずっと家族のためにと生きてきた人なら、それまでの人生と切り離して、終末期だけ個人の意思を聞いても「最期だけは私の自由にさせて」とは言わないかもしれません。
いずれにしても、家族が悩んで決めたことに対して、後悔して欲しくないと思っているので、「最後の最後は医師が決めた」という形で引き受けることもあります。
認知症があってもなくても、親の意思はわからない
―本人と家族の意思がかけ離れているケースもありますか?
現実問題として、家族は必ずしも患者さん側に立っているとは限りません。生存し続けることを願う家族もいれば、どこかで早く亡くなって欲しいと思っている家族もいます。それぞれに事情があります。
例えば経済的な問題。入院が長くなると、差額ベッド代のかかる病室に移る病院が多いのですが、1日5000円とすると月15万円もかかります。ほとんどの家族は簡単に払えません。
―日本には「医療費を払えない」とは言えない風潮があります。
それだけに家族だけで抱え込んでしまうことが非常に多いんですよね。
では、退院して在宅医療にできるかというと、訪問看護や往診を受け入れるには、独居の方たちもそういったサービスはつかっていらっしゃるので、家族の同席が必須ではないのでしょうが、家族が家にいなくてはならないという気持ちになります。医療や介護の費用を得るために働きたくても、在宅を求められるわけです。家族は、ご自分の気持ち、倫理のことやお金のこと、自分たちの生活など、全く次元の違うことで悩んでいます。患者さん本人の意思ばかりを考えていられない状況があるのです。
―そうした時、家族が混乱しないための方法はあるのでしょうか。
混乱を招く因子を、一つ一つ分けて考えてみることです。経済的なことは、利用できる社会資源がないか、ケースワーカーに相談するといいでしょう。亡くなる前に遺族年金の計算をしようとは思えないかもしれませんが、それをすることによって、どこまで医療費をかけられるかが明確になります。少し余裕があることがわかって、差額ベッド代は高くても自宅近くのきれいな病院で看取りたい、という人もいます。
子どもにどう伝えるか悩んでいたら、家族全員を集めてミーティングすることをお勧めします。そこに医師も協力できます。問題を一つ一つクリアしていくことで、残された時間をどう過ごすか判断できます。
―情報があることで、じっくり考えることができるのでしょうか。先ほど胃ろうを拒否しながら経鼻胃管は受ける人の話がありましたが、経鼻胃管は情報量が少ないことが関係していますか?
情報があるからといって、必ずしも考えられるとは限りません。例えば成年後見制度はかなりマスコミ取り上げていますが、利用について話し合っている家族はわずかです。おそらく、人は自分の身に起こりそうなこと、起こらなそうなことを無意識のうちに選別するのだと思います。高齢ドライバーの交通事故がどんなに報道されてもなくならないのは、「自分は大丈夫だ」と思う人が多いからかもしれません。胃ろうを拒否する人は、胃ろうの話を聞いたときに「自分は長生きするだろう」と思い、それはやめてほしいと思ったのかもしれない。経鼻胃管のことは見聞きすることが少なかったり、知ったとしても「関係ない」と思ったのかもしれません。
―終末期をどう過ごしたいかという希望は、あくまでも元気だった頃の延長線上にあるのですね。それを家族が推測するのは非常に難しそうです。
そもそも、認知症があってもなくても、自分の親が何をしたいか本当にわかる人はいないと思います。患者さん本人ですら、実は何が自分にとって幸せかはよくわかっていないかもしれません。本人の気落ちは常に変わりうるものです。だからこそ、家族も医療者も「これでいいのか」と葛藤することをやめてはいけない。最期をどう迎えるかは、なってみないと本当にわからないものなのですから。
(インタビュアー:越膳綾子)
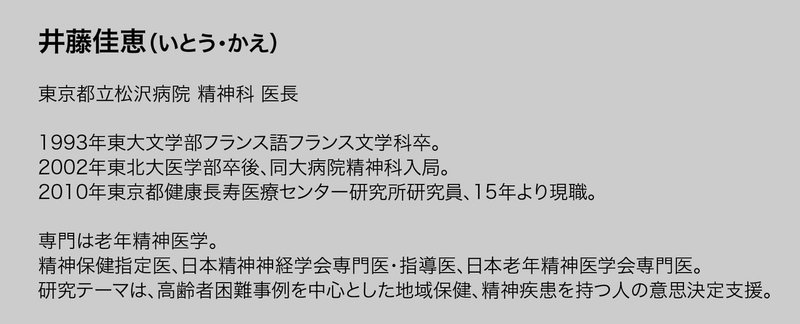
次回の更新では、緩和ケア専門の在宅診療クリニック「しんじょう医院」院長の新城拓也医師に、緩和ケアと在宅での最期について伺います。そちらもお楽しみに!
『毎日がアルツハイマー ザ・ファイナル〜最期に死ぬ時。』
7/14(土)〜ポレポレ東中野、シネマ・チュプキ・タバタほか全国順次公開
>>>6/23(土)13:30〜全国一斉特別先行上映会 開催!<<<
>>>再上映決定!<<<
『毎日がアルツハイマー』
『毎日がアルツハイマー2 関口監督、イギリスへ行く編。』
6/30(土)〜ポレポレ東中野
7/1(日)〜シネマ・チュプキ・タバタ
ヒューゴ・デ・ウァール博士(『毎アル2』出演)来日 記念イベント
〜「認知症の人を尊重するケア」その本質とは?〜
【日時】7月24日(火)19:00〜 (開場 18:40)
【会場】日比谷図書文化館・コンベンションホール
映画監督である娘・関口祐加が認知症の母との暮らしを赤裸々に綴った『毎アル』シリーズの公式アカウント。最新作『毎日がアルツハイマー ザ・ファイナル 最期に死ぬ時。』2018年7月14日(土)より、ポレポレ東中野、シネマ・チュプキ・タバタほか全国順次公開!
