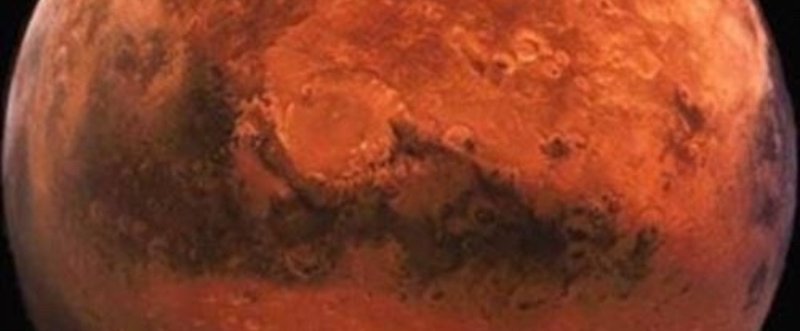
リトル・ドラゴン②
2.火星とジーンズのポケット
「この世界をカタチ作っているのは全て周波数なんだよ。別の言い方をすれば、存在する全ての物を周波数で表現できるってことだ。そうだろう?」
マルコは前を歩きながら言った。
「うん、まあ分かるよ。確かに色や重さや距離や、ありとあらゆるものが周波数で表せるよね。」
「そう。で、ここからが重要なんだけど。君たち地球人が認識している周波数以外にもいくつか他の周波数が宇宙には存在してるんだ。高いとか低いとかそういう意味じゃなくて、全く別の種類の周波数っていう事なんだけどさ。」
「全く別の種類の周波数、、、。」
そんな事は知らなかったし、考えた事もなかった。
「で、君は今、理由はわからないけれど、地球人が存在していない周波数で出来た世界に迷い込んでしまったんだ。だから、君が今まで存在していた世界と全く同じ場所に居るんだけど、今まで見えなかった物が見えたり、あるいは見えていたものが見えなくなったりしている。」
「あ、え?、、そんな事があるの?」
「あるんだよね、これが。だって、君には今まで見えなかった物、例えば僕やこの洞窟が見えるし、今まで見えていたもの、地球が見えなくなっているだろう?でもココは紛れもなく火星。地球にもっとも近い場所にある星の一つなんだよ。」
にわかには信じ難かったけど、確かにそうだった。
「あの、俗にいうパラレルワールドってやつなのかな?」
それを言うとマルコは嬉しそうに微笑んで、
「ああ、その通り!確かにそう言うね。うん、パラレルワールドだ。」
といった。
なんとなく、この不思議な状況を少しだけ理解したような気がした。
・
・
・
あの時、「本当に地球に帰る気があるのか?」と尋ねられ、僕はなにも答える事が出来なかった。
マルコはしばらく僕をじっと見つめた後、「ま、いっか。」と言うと宇宙船のハンドルを握りしめた。そして、
「とりあえず、火星に行こう。」
ニコッと笑っていきなりそんな事を言った。
「火星?」
驚く僕には目もくれず、マルコは手元にある操作盤のスイッチをいくつか押していった。
「あの、マルコ、これ動かせるの?」
どきどきしながら僕は尋ねた。
「まぁね。別にこの船が壊れてるわけじゃ無い。たまたま軌道を少し外れただけだ。」
「そうなの?じゃあ、火星に行くより、このまま地球に戻ればいいんじゃないの?」
慌てて僕が言うと、マルコは「いや、それは出来ない。」と言い、1度手を止めた。
「だってどこにも地球が見えないだろ?」
マルコはまた真面目な顔で僕を見た。
確かに、360度どこを見ても地球を見つける事が出来なかった。しかし、いくらなんでも地球が見えなくなる程の距離をこの旅行用の宇宙船が飛べるはずもなかった。機能的にも燃料的にも不可能だ。
「本当だ。なんで気がつかなかったんだろう。」
僕はまた急に怖くなった。そこにあるはずの地球が、ない。 帰る方法どころか、帰る場所すら無くなってしまったのだ。
「いまさらだなぁ」
マルコは苦笑いを浮かべながら首を二、三度振ると
「大丈夫。大した事じゃない。地球はすぐそばにあるよ。消えたりしていない。」
と言った。
「ど、どういうこと?」
「まぁ、後で説明するけど、今の君はいつものジーンズを履き違えてしまったようなもんだ。で、きのう右ポケットに入れたはずのレモンキャンディーが見つからなくて一人で泣いてる。」
マルコの言っている事はさっぱり分からなかったけど、僕は確かに今大切な何かをなくして、目の前が滲むほどに涙がこみ上げていた。
「でも、キャンディーが消えて無くなったんじゃない。友達のジョンに食べられたんでもない。ただ君が、いつもと違うジーンズを履いてしまっているだけさ。」
「いつもと違うジーンズ、、、」
「例えだから気にしないでいいよ。わからなくても仕方ない。とにかく、火星だ。そこに答えはある。さあ、早くベルトを締めて。」
そう言われた僕は訳のわからないままに、何個もあるシートベルトを締めていった。
「あの、マルコさ。」
「なあに?」
なんども質問を繰り返す僕に、マルコはちょっとだけめんどくさそうになっていた。
「この船でどうやって火星まで行くの?」
それでも僕はきいた。間違いなく火星は遠くに見えているけど、この旅行用宇宙船でいける距離では到底なかったからだ。
「心配性だなぁ。この船の力はコンロの種火みたいなものだよ。この動力をきっかけに一気にワープさせるんだ。」
「た、種火?」
マルコは例え上手な龍だった。
「なあ、ポール。少しでいいんだ。少しだけ、魔法を信じてみなよ。」
と、声のトーンを下げてマルコは言った。
魔法。そういえば、さっきもマルコはそんな事を言っていた気がする。
「分かった。よろしく頼むよ。」
もちろん、全てを理解出来た訳ではなかったけれど、地球を失った僕はもう彼に任せるしか無くなっていた。
「そうこなくっちゃ。それじゃあ行くよ。しっかり、歯をくいしばってね。」
「うん。オーケー。」
「いいね。そう、大丈夫。あっという間だから、心配しないで。さあ行こう。3、2、1、ゴー!!」
マルコが大声で叫ぶと宇宙船は一気に加速した。重力が身体中を締め付けた。自分の骨がギシギシと音を立てるのが鼓膜の奥側から聴こえた。そして、目の前を巨大な岩が通り過ぎていくその瞬間、白く眩しい光が船全体を包み込んだ。
僕は声をあげることも出来ずに、思いっきり目を瞑った。
#小説
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
