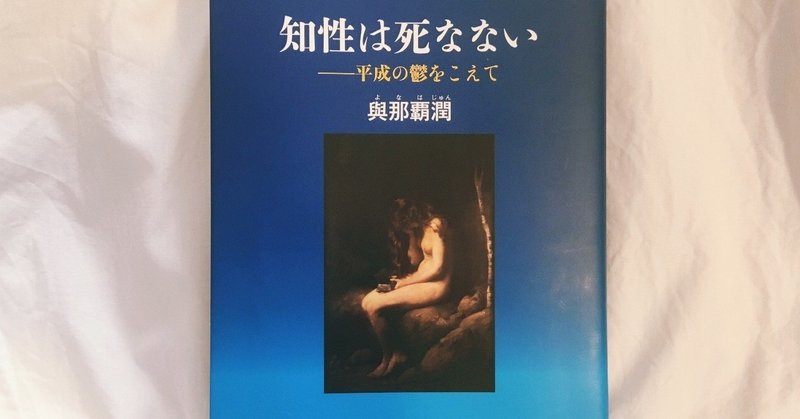
「身体」が実感すること 〜「知性は死なない」を読んで〜
ときどき、心を軽くしてくれることばに出会う。
それはきっと、ふとした会話の中で、なんとはなしに読んだ小説の中で。
例えば、今ではわたしの大のお気に入りの1冊となった、平野啓一郎の「ある男」を読んだとき。
弁護士の城戸は、かつての依頼者である里枝から、「ある男」についての奇妙な相談を受ける。
宮崎に住む里枝には、二歳の次男を脳腫瘍で失って、
夫と別れた過去があった。長男を引き取って、十四年ぶりに
故郷に戻ったあと、「大祐」と再婚して、幸せな家庭を築いていた。
ある日突然、「大祐」は事故で命を落とす。
悲しみにうちひしがれた一家に、「大祐」が全くの別人だという
衝撃の事実がもたらされる・・・・・・。
「ある男」そで より
あまりに好きな小説で、ひとことであらすじを語ることができないので、カバーのそで部分のあらすじを引用した。
わたしがこの小説の中でもっとも心打たれたのは、物語の大筋となる「大祐」とはいったいだれだったのか、ということではなかった。わたしにとってそれは、里枝と、その息子 悠人との関係だった。
はじめてこの1冊を読み切ったとき、なんとも言えないあたたかい気持ちで包まれた。これは「大祐」をめぐる物語の形をとった、愛の表現だと思った。里枝から大祐への愛、大祐から里枝への愛、悠人への愛、悠人からの愛、そして、城戸とその周辺の人たちとの愛・・・・・・。
あまりに感動して、感想をノートに綴っておきたかったけれど、どうしてもことばにすることができなかった。ことばにしてみても、そこからこぼれ落ちるものの方が多いように思われた。
けれどたしかなことは、この小説はわたしの心をあたたかい気持ちで満たしてくれ、わたしはなぜだか心を救われ、そして涙を流したということ。
小説を読んでいると、そんなふうになぜだか心が軽くなってしまう体験にときどき出会う。あの感情の動きはなんだったのか。心が救われるという体験に興味のあるわたしのそんな問いについて、すこし解像度を高めてくれた本に出会った。
與那覇潤 「知性は死なない ー平成の鬱をこえて」。
「言語」と「身体」という二分類
「知性は死なない」の中で、わたしにとって新しかったのは「言語」と「身体」という二分類のアプローチだ。
人間に対するアプローチには、「言語」と「身体」の両極がある、としたうえで、「言語(ことば)」には、ものごとを理詰めで分析していく作用があり、「最初は理解不能としか思えない体験でもことばで腑分けしていくことで、『起こっていたのはこういう事態でした』というかたちである程度理解可能にできる、と書かれている。
一方「身体」は、『どれだけことばで語ろう、ととらえようとしても、けっしてとりつくすことのできないなにかというニュアンスで用いられるもの、とされている。
そして、意識は言語に近く、無意識は身体に近く、理性とは「言語を適切に運用できる能力」で、感情は「身体からわきおこるもの」のように思われるが、実際にはきれいに二分できるものではない、という。身体的な感覚があれば、それを正当化することばなんていくらでもあるし(ことばが理性をうらぎる)、言語が暴走して身体をひきずる(ことばにしたことで感情がエスカレートする)、などがある。
つまり、人間について考えるとき、「言語」と「身体」の二分類があるが、そのふたつは絡み合った存在で、どちらが先であるとか、どちらが意識的なものかは、きれいに分類することができない、ということ。これらを元にそのバランスが崩れたときに精神病が生まれること、そのバランスの崩れ方と躁と鬱の関係について書かれているのだが、重要なのは「言語」と「身体」の分類なので、ここはいったん話を進めたい。
正直なところ今までのわたしは、「身体」と「言語」という二分類の概念を持っていなかった。なにかを感じるとき、わかるとき、それは論理的なものにせよ感情的なものにせよ、どこか言語(ことば)の問題だと思っていた。だからことばを聞いて、読んで、納得するし、理解した、という感覚を持つのだと。けれども、それは決定的になにかを忘れている。「これだ」という感覚。この身体的な感覚がなければ理解することも納得することも、感じることもできない。ことばは宙に浮いてしまう。
では、「心が軽くなる」「心が救われる」、これらはことばの問題ではなく、ことばと身体の問題だとしたら。
「これがわたしの欲しかったことばだ」と思う瞬間があるとする。実際、そういう瞬間は訪れる。そのときわたしは、「ことば」を求めていたのだろうか。小説を読んで、なんとなく、心があたたまったような感覚がする。そう、「なんとなく」。
「あの一節が、あの台詞が、わたしが求めていたものだったのだ」と思う。ほんとうに?わたしが求めていたのは、一節の文章なのか。台詞なのか。
それはきっと、すこし正しくて、すこし、間違っている。
「身体」としての実感
「ある男」に話を戻す。
あのあたたかい気持ちはなんだったのか。あの感情の動きは、涙は。
わたしは、「ある男」という小説に、愛されたのだと思う。それは身体感覚をともなった実感としての愛。
好きな台詞も、好きなシーンもある。けれどその一節が、わたしの心をあたたかくしてくれたわけでは、恐らくない。母親である里枝と、息子である悠人との関係、物語の中で動いていく時間、相手を思って現れる行動と、それに至る感情の揺れ。それらをひっくるめて、なんとなく、身体で感じる。里枝が悠人を愛しているということ。悠人が里枝を愛しているということ。そしてその愛を読み手であるわたしも受け取る。わたしも彼らに愛される。「愛」ということばだけでは、思いやりに溢れた文字だけでは、どうして表現しようもないことを、小説を読んでいると感じることができる。ことばを介して、身体の実感をともなって。
つまりはそれが感情移入だと言われればそうだろう。けれど感情移入にも種類があって、「感情」をある人物にのせて、第三者としての自分が物語や状況を上から眺めているようなものと、「感情」も自分も、その人物にのせられるものに分けることができるとしたら。「ある男」を読んだとき、わたしはきっと後者の読み方をしていた。そしてそれが、あのときの、ことばにできないあたたかさの正体だったと思う。
小説によって、ことばによって、心が軽くなるとき、心が救われるとき、そのことばを求めていた、と感じる。それはすこし正しくて、きっとすこし間違いだ。ほんとうに求めていたのは、そのことばが引き寄せてくれる「これだ」という身体の感覚なのかもしれない。
「小説は君のためにある」(藤原治)という新書に、「僕たちは文章を読んでいる時、その文章に書かれていることを、経験しているのである」と書かれている。そうなのだと思う。そしてさらに言うなら、その経験は疑似体験ではなく、かぎりなくほんとうに近い、身体的な感覚を連れてくるのだと思う。
「腑に落ちる」 身体
「知性とはまなぶ方法のことであって、まなぶ対象をさすものではない」。それは、教員として大学の教壇に立つ以前から、変わらぬ私の信条でもありました。
ほんとうは、どう読んだか/考えたかが、たいせつなのに。だから、知性とは旅のしかたであって、行き先のことではありません。
「知性は死なない ー平成の鬱をこえて」おわりに より
「知性は死なない」の最終章「おわりに 知性とは旅のしかた」に書かれている文章だ。
この本の中でいちばん面白かったのが「言語」と「身体」に関するはなしだったから、そのことを中心に書いてみたのだが、「知性」に関するはなしもほんとうに面白かった。だからまずは、この本を「どう読んだか/考えたか」書いてみたくなったのだ。
そしてこの文章を書きながら、さまざまな身体の感覚に耳をすましている。ちゃんと説明できた、と腑に落ちている部分もあれば、正直なところすこし強引にまとめてしまったり、整理がつかず書けなかったこともあって、すこし歯がゆい部分もある。むしろ歯がゆさのが多い。
けれど、その身体感覚に意識が向くようになったということが、この本がわたしにくれたものだから、ひとまずはこれでいい。
その感覚は、腑に落ちている。
最後まで読んでくれてありがとうございます。いただいたサポートは、大好きな読書と映画鑑賞にあてさせてください... ついでと思ってコメントもいただけたら、見えないだろうけど満面の笑み...喜びます...!
