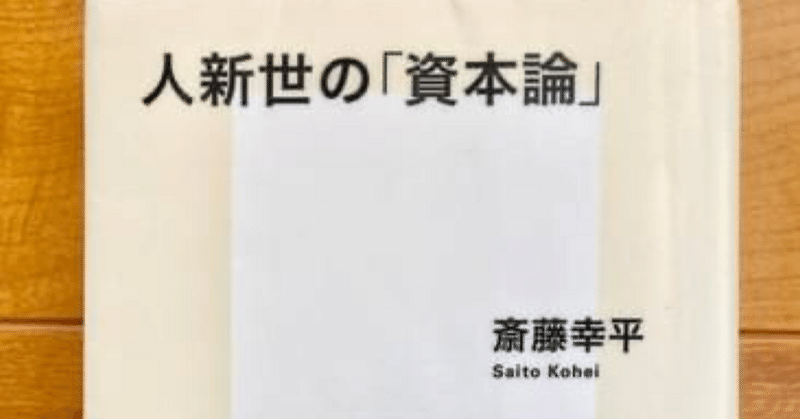
エコロジーについておまけ「人新世の資本論」
エコロジーに関連してもう一つ、斎藤幸平さんの50万部売れた本「人新世の資本論」で提唱されている「相互扶助と自治に基づいた脱成長コミュニズム」に触れた。
この本は私は心理的抵抗があって読みにくかった。というのは、お恥ずかしながら、私の中にコミュニズム≒マルクス≒共産主義≒独裁→何か危ない。のようなステレオタイプ的な雑な偏見に基づくイメージがあったからだ。
そこで、ジョナサン・ハイトの論で左派が見落としがちな盲点を最後に補足しつつ、コモンの大切さを備忘録的にメモしてみたい(間違っている部分があるかもしれません。また、単なる私田村一個人の見解に過ぎません)。
コモンや、ソーシャルキャピタルや、社会的共通資本というのは、細かく言えば異なる概念のようだが(怒られるかもしれないが)だいたい似たようなものだとざっくりと捉えてみる。
コモンとは「水や森林、文化、知識といった根源的な富のこと」のように説明されることが多い。
これらはGDPにほぼ現れないだろうし、お金に換算しにくいので、経済至上主義のような世界観ではこの価値が見落とされがちであるし、私もなんでもお金に換算する価値観に嫌気がさしてきたところでもある。
さて、コモンには「自然」も含まれる。これはプライスレスな豊かさ(斎藤幸平さんは「ラディカルな潤沢さ」と呼んでいた。)だ。
ある人がこのコモンについて、「おじいちゃんと湧き水」でわかりやすく言っていた。
たとえば自然の豊かな山村で、美味しい湧き水が出るところがある。もちろん無料だ。
あるおじいちゃんは、それを山道を通る時に飲むことを毎日の楽しみにしていた。
ところがここに資本が入ってくる。とある企業が、そこの土地にフェンスを作り工場を建て、その湧き水をペットボトル水に加工して流通に乗せる。
そうすると、無料だったものが商品価値をもって市場に出回り、当然、国全体のGDPも増える。
しかし、おじいちゃんの生活は豊かになったか?
かけがえのない自然は工場のフェンスに囲まれて入れない。
あの毎日の散歩で湧き水を飲むという、プライスレスな豊かさは無くなり、お金が無いという類いとは異なるなんとなくの「生活の貧しさ」が、おじいちゃんの心の幸せを蝕む。
おまけにその水をどうしても飲みたいとなれば、お金を出してペットボトル入りのを買わなければならない。おじいちゃんの財布も、工場がなかった時より貧しくなる。
そういった支出が様々増えて、財布がさらに貧しくなると、年金だけでは足らず、高齢の体に鞭打ってアルバイトでもしなくてはならなくなるかもしれない。
こうして資本が、人をたとえば「工場の部品」のように扱うなど、様々な方法で色んな人をモノ化して行くということが起こるし、それが進むと、人が自分の価値を「市場価値」でしか見出せなくなったりすることも起こる。
さらに何よりも、自然が搾取されて、自然が痩せ細って貧しくなっていくのだ。
このように、資本は何もかも飲み込んで行き、さらにブレーキがついていないので、どんどん自然という「コモン」から、搾取したものを「お金」に変えて行っている面がある。
ここに、高度経済成長期に、国のGDPは増えて豊かになったはずだけれども、国民はいまいち幸せになっていない、という要因の一つがあるだろう。
さて、企業が水を取るだけなら、環境負荷はまだ小さいかもしれないが、自然を大幅に搾取する事業は控えた方が良いのだろう。
しかし資本はブレーキが効きにくく、「エコロジーなんてのはタテマエ」といった具合にどんどん人や自然を飲み込んで行くので、どこかで歯止めをかける部分も必要だろう。
そこで斎藤幸平さんは「相互扶助と自治に基づいた脱成長コミュニズム」を提唱する。
社会活動から公共を作って行ってそれを広めて行くという、奥田知志さんの抱樸の「きぼうのまち」のようなものと非常に相性の良い考え方なのだ。
しかもここで「自治」というのがミソで、市民が民主的・水平的に共同管理する。ということなので、国が一括管理すると言った独裁政権のようなものに飲み込まれにくくなる利点もあるように思われる。
少しここでジョナサン・ハイトの「社会はなぜ左と右にわかれるのか」のp450から、リベラルや共産主義の盲点を挙げている(リベラルと共産主義は異なるが「社会の変革を目指す」というくくりでまとめて語っているのだろう)ことを引用してみる。
【社会や組織を変革する際、その変化が道徳資本にもたらす影響を考慮に入れなけれ ば、やがてさまざまな問題が生じるのは明らかだ。これこそまさに、リベラルの抱える根本的盲点だと私は考えている。これは、リベラルの改革がたびたび裏目に出る理由を、さらには共産主義者の革命が独裁政治に陥りやすい理由を説明する。また、思うにそれは、自由と機会均等の実現に大きな役割を果たしてきたリベラリズムが、統治の哲学としては不十分な理由を説明する。
つまりリベラリズムは、ときに行き過ぎてあまりにも性急に多くのものごとを変えようとし、気づかぬうちに道徳資本の蓄えを食いつぶしてしまうのだ。それに対し、保守主義者は道徳資本の維持には長けているが、ある種の犠牲者の存在に気づかず、大企業や権力者による搾取に歯止めをかけようとしない。また、制度は時の経過につれて更新する必要があることに気づかない場合が多い。】
つまり「相互扶助と自治の脱成長コミュニズム」は、もしかしたらどこか統治の哲学が弱い部分があるかもしれないので、どのように秩序が保たれるのか、また、まとまらなくなった時に強権的に権力を振り回す人が出てくるかもしれないというような懸念があるかもしれない。
そのことに留意することを忘れなければ、非常に魅力的な方向性だと思う。斎藤幸平さんは、ゆるやかな変革を目指していて、これはたとえば保守主義の父と言われるエドマンド・バークの「改革は性急では無くゆっくりと」という知恵とも共通する、欠点の少ない論だと思われる。
*ちなみにマルクスの有名な言葉で「宗教はアヘンである」があるが、それは、かなり雑に要約すると、「資本に飲み込まれて労働者が人間性を失ってこき使われ続けたら、宗教でもやって心の痛み止めやってでもしないと生きていけないよね。」というような文脈で語られたことなのだそうだ。だから旧ソ連や中国共産党が、(キリスト教を含む)宗教迫害をしたのは、マルクスの考えとは異なるらしい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
