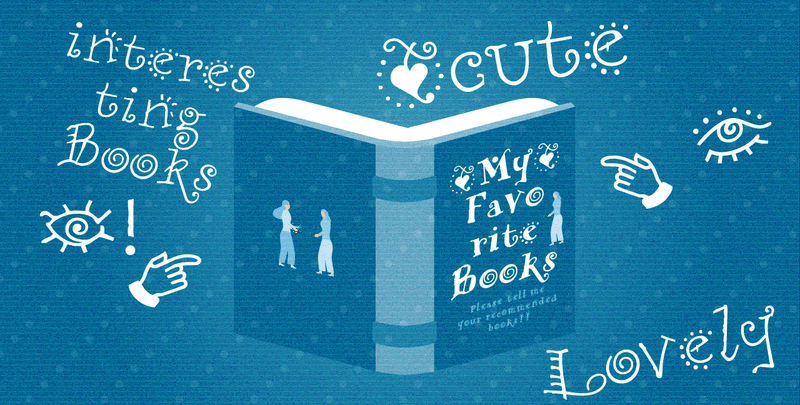
Amazonメカニズムを読んで
★イノベーションを起こさせる仕組みがある
①ワーキングバックワード
→企画の段階で、PRとFAQを作る→顧客視点から始まるように仕組みを作っている
⇒森岡さんの「USJを成功させたたった1つの方法」でも同じようなことを言っている。
日本は技術起点での商品開発のため世界で通用しない、必要なのは今その技術があるかどうかではなく顧客が何を欲しているか。
<疑問点>
・FAQ、PRから始まることがなぜ「顧客視点」になるのか?
→FAQはわかる。想定質問が出るということですでに顧客視点に立てているし、それを企画内容に盛り込むこともでき、事前の企画原案のブラッシュアップができるという意味だと思う。
〜プレリリースとは〜
新商品の発売や新サービス、新規事業の開始、あるいは経営・人事などの企業情報を、ニュース素材としてメディアの記者が利用しやすいように、文書や資料としてまとめたものです。 企業・団体がメディアを通して社会へメッセージを届けるための基本的なツールとして活用されています。
→社外への周知をする際の説明を考えることで、機能やサービスの矛盾点を先回りして見つけることができる。社内の企画書とは違うう点は「外部の視点や意見」を意識できるという点かな!
②社内政治が発生しないための予防策
「パワーポイントの使用禁止」「必ずワードファイルで1枚、3枚ないし6枚にまとめる」「箇条書きは禁止」「グラフ・図の使用禁止」「意見はすべて散文形式で表現する
+会議冒頭で、出席者は配られた資料を黙読する。会議前に具体的な提案内容を伝えるのは禁止。
→人に文章で伝える力を磨くためだろうか…?
例えば、社内でとっさに説明を求められても図やグラフを使って説明することは考えづらい。資料が無かったり、手法が限られたりしている中で言葉で伝えられる社員の育成のため…?
「必ずワードファイルで1枚、3枚ないし6枚にまとめる」→これだけ異質な感じ。
1枚にまとめるまではわかる→簡潔に要点をまとめよといううことだと思う。
3〜6枚→なぜ2枚が省略されているのか??
※ないし=○〜○にかけてという意味。(数字に使われている場合は)
予測:2枚にとどまる程度なら1枚におさめられるだろってい意味かな。3枚にまで及ぶなら1枚に収めるのは不可能??蛇足のような不要な情報をカットするのが目的だろうか。
3〜6枚について→3については上記の通りだろう。4、5、6枚については不明。
この「ないし」が「または」という意味でつ買われていたらだいぶ内容は変わってくる。→文脈的にはこちらの方が近い気がする。松竹梅で文章の枚数規定があり、適切な枚数を選択するため…?
どんなに長い企画書でも最長6枚になる→「読ませる」企画書であることが重要。(7枚以上だと読む気が失せるということだろう。それにしてもフォントサイズはどうするのかとかも気になる。そこは規定ないんだろうか??)
会議前に具体的な提案内容を伝えるのは禁止→なぜ??
話すデメリット→一部の人間に話すことで出席者間で理解度の差が生まれるというのはわかる。これが社内政治につながる意味がわからない。
アメリカの会議においての評価体制はわからないけど、その場で考えたアイディアと、事前に用意したアイディアの質に差が出ること想像しやすい。ドラマとかでよく見るのは、いい意見だしをできた人間はプロジェクトにアサインされるなど人事につながることがあるのかな…と予測。
②意思決定時のスピード軸
ワンウェイドアorツーウェイドアなのかで慎重度を測る。
・ワンウェイ→慎重に予測し検討すべき
・ツーウェイ→準備不足でも前に進めてよい
<上記をもとに意思決定を進めていくことの効果>
①意思決定スピードの上昇
②ミドル層のマネージャーに起業家精神を植えつけること
→いまいちわからない…。②に関してはツーウェイドアのことを言っているのだろうか?準備が万全でなくても探りながら進めていくことのできる人材の育成を指す?
④シングルスレッド・リーダーシップ
⏩要約すると、責任者に兼務をさせず一案件にパワーを集中させること。
1ー戦略やリソースの使い方、プロジェクトの結果まで、すべてに対して1人のリーダーがオーナーシップを持つということ
2ーリーダーはほかの仕事を掛け持ちせず、自らのリソースをすべてプロジェクトに注ぎ込む
→1つのプロジェクトにおける起業家のような存在になる
⑤社内カニバリゼーションの推奨
→これはそのままの意味。現存の事業がそれによって衰退する可能性があったとしても全力投資しイノベーションを起こしていこう!ってこと
⑥Sチームゴール
Sチームとは…各事業責任者等で構成されている。社員のイノベーション創出を支援
★Sチームが関わる企画実現の流れ★
PR/FAQが承認される⏩人員採用枠、予算が与えられる⏩プロジェクトのインパクトが大きいと判断された場合に「Sチーム」がフォローアップにつく⏩4半期単位の目標達成に向けサポートが入る⏩Sチームがレビューする⏩経営幹部からのアドバイスが返ってくる、必要であれば、リソースの追加依頼も可能
→何が他の企業と違うんだろう??
Sチームの存在が特異なのかな?目標設定は誰がするん…?
各事業部の責任者がレビューするってことは、他事業部の視点も取り入れることができるってことか。
普通はその事業部と経営幹部だけな気がするから、そこが違うのかな。
他事業部からのノウハウの共有だったり、関わる部署が増えていくとそれだけいろんな視点での指摘が出てクオリティが上がったりより革新的になる、ということと解釈。
⑦イノベーション重要を継続発信する
Sチームはベゾスのメッセージを繰り返し伝える役割も持つ。全社員に浸透するよう働きかけ、組織文化の定着に貢献している。
Sチームの役割は、ここがメインになるのかもしれない。(レビューもここを汲みとったレビューとなるだろう)
まとめると、
★徹底した顧客視点での企画立案ができるシステムが整っていること
★意思決定の速さを助ける文化があること
⏩これらはイノベーションを助け
★社内政治が発生しない体制を整えていること、伝える力を育成していること
⏩これは社内でも自由な精神を育むことと、社内でのコミュニケーションを円滑にし
★各プロジェクトリーダーに社内の起業家同然の役割を与えること
⏩これは独立しているようなプロジェクトを作ることで当事者意識を高め
★ベゾスの考えを忠実に伝える特別チームの存在
⏩これは全社の統率力を高め、皆が同じ方向を向けるよう軌道修正する役割を持つ
ということかな。
以上!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
