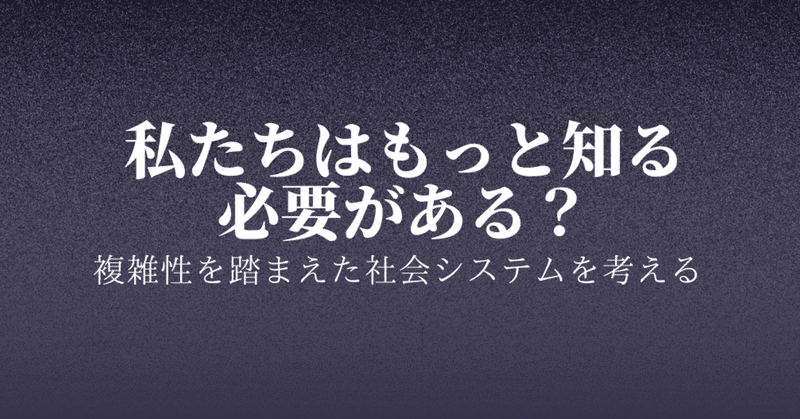
私たちはもっと知る必要がある?
前回の続きです。
社会の本質を清濁併せて受け止められるか
「私たちはもっと知る必要がある。」これはよく思う事なのだけれど、一方で大きな誤解や争いを生みかねないという事もやっぱり考える必要がある。人間の手に余るほど肥大化したテクノロジー、取り扱い注意な無数の情報、それらを取り巻く不可視化された人間達の生態系、そういった事を安易にみんなで理解しようとしたり、ほかの誰かにゆだねてもよいだろうか、そこのところも考えてみる。
おかしな選択をする人達
コロナパンデミックでもおかしな陰謀論や荒唐無稽な話は尽きないし、SNS上ではそれらをフォローする人たちもいる。現実にそんな人間がいるのか疑わしいこともあるのだが、やっぱりどこかにある程度は生きていて色んな思惑や思考回路でもって賛同しているのだろう。そういうことに対して私がおかしいと思う一方で私もおかしいと思われているのだろう。
まぁ確かにコロナにせよワクチンにせよ未知の部分はたくさんある。その未知の部分を恐れて色んな自衛策を講じるのも分かる。しかし多くの人が様々な見地で検証したことや証明されている事実でさえも、自分にとって都合がいいように解釈を変えたり、理解しやすい文脈に勝手に並べ替えたり、身近な人に同調したりで、少しずつ前提となることすら曖昧になったりもする。一人一人がどうしてそんな変な選択をしたのか正確に測るのは難しいが、そんな複雑な理解の系があるのだろうとそのように推察している。
普通に考えたらお互いにとってマイナスになるような選択を取り続けてきたとしても、意外と命を失うところまではいかないかもしれない。”なんとなく”を省みることなく選択し続ければ、自分のとっての利害関係、社会にとっての利害関係など理解する余地もなく”なんとなく”でお互いを害していく。
誰かの”なんとなく”や直感がもしかすると自分自身や誰かを殺すかもしれない。これは個々の性質や能力の違いや限界とも考えられるが、社会全体でみれば人間の能力値の限界という事も考えられる。みんながみんな”なんとなく”で行動すると、生き延びる事や発展繁栄を元にした合理性の中には生きられない。特にお互いに無関心ならざる負えない現代においては、”なんとなく”という感覚をより狂わせていくように思われる。いいとかわるいとか他人に言われないと気づけないことはやはり多くある。ただし生まれもってあまり鍛えていない”なんとなく”という感覚を元に全体性をイメージすると生き死にも含めてもっとカオスな状態が生命としては落ち着いた形なのかもしれない。その中で淘汰し選別されていくだけの話であって、それが今に続いている。
人間同士の争いについて
人間同士でもやっぱり争いはある、同じように生き延びる事や発展繁栄を元にした合理性を持っていたとしてもそれをどの範囲まで適用するかという事で線が引かれてしまう。自身や身内の発展繁栄のためには、その外側にいる存在に何かを強いたり害したりという事も実は往々にして起こりうる。藪をつつけば蛇が出るとは分かりやすいたとえだけれど、一方で蛇が出るぞと思わせておくことで敢えて藪のままにする事も戦略的に行われていたりもする。
目の前に”みんな協力しないと全滅する”という確固たるルールが目の前に示されない限りこういった線引きは続くだろう。もしかするとそれでも協力しない人もいるだろう。そもそも趣味趣向の違いや個性があって性別が分かれていて、素晴らしい出会いがなければ命や意思が続いていかないという生物のデザイン自体が混沌した状況を生み出すように作られているようにも感じられる。
手に余るテクノロジーと統治の機能不全
それでもなるべく共存共栄という道を選び取ろうという発想もなければやっぱりお互い破滅するのがわかりきった未来であり、そういう選択をするのが極めて理性的な判断だと思うが、あまりにも不平等感や絶望感も感じるからもう少し考えようかと思う。その過程で敢えて藪をつつく必要も出てくるだろうが、今のままの社会全体の指揮系統で大丈夫かとか政治や統治を司る部分に機能不全があるのではないか、というのをそれこそ”なんとなく”感じる生きづらさや未来への絶望感から想像されるので。
結局のところ最悪の未来への予測がある程度目先に迫った時に一致団結してこれではまずいと改革に進んでいくのかもしれないが、だからといって誰しもがほっとくと最悪の未来がその想定を超える形で実現するかもしれない。ただしその臨界点があまりにも遠い未来やなんとなくでは理解しにくい事柄の場合誰にも理解されないので、貧乏くじを引かされるような状況にもなりうる。
目立って評価される事の重要性
ここまでの事を踏まえて今やるべきと思う事は色んな面で今予測しうる最悪の未来を回避するにはどうすべきか、分かりにくいが危機回避のために重要な行動をとる人が貧乏くじを引かないようにするにはどうすべきかという事であり、そのための社会システム構築をしたいという事だ。いつか報われるだろうという事にはちょっと不器用な人が集まり、器用な人は目先に迫って評価されそうであれば進む。結局みんなの視線が集まる先にいることが、評価もされ、お金も稼げて、賢い選択となる。注目の矛先が変わりそうな潮目を見て、ひたむきに行動していた人の横にいつの間にか並んで立てばいい。実際に社会のリソース配分が変わってしまえば、前後の文脈等無視する事は恐らく簡単だろう。
都市と田舎にも似た関係を感じていて時たま私のところに訪ねて来てくれる若者に、「田舎はいいぞ」という事はやっぱり少ない。要求される物事が多いわりに、目に見えてのお金で帰ってくることは少ないから。目に見えない何かや価値のわからない物事に意味を見出せそうならいいけれど、そういうのはちょっと変わり者という感じの人だけだ。都市と田舎をいきなり抽象的に区切って話しても仕方がないかもしれないが。
少し話がそれたけれど、ともかくどんなに素晴らしそうな話でも、”なんか面白そう”とか”刺激的で新しい”とか”なんとなくめっちゃいい”とかそんなソーシャルグッドが集まる取り組みの見せ方も必要だろうという事だ。しかしそっちばかりに思考がいくと、当初の「私たちはもっとよく知る必要がある」という目的から離れてしまう。あらためてなんとも難儀な話を考えているのかもしれない。
目立たなくてもやっぱり必要だから残すという発想
一方でやっぱり必要だよねと言って見直されず残っている仕組みも結構ある。それは旧態依然とした教育かもしれないし、付き合いで行われる飲み会のようなものかもしれない、伝統的に意味もあまりわからず続いている文化や風習的なことかもしれない。中身はともかく先に生きた人の好きな経験や体験をもとに残っている事も多い。ある人からすればいやな風習、ある人からしたら必要不可欠な要素、ある人からしたら空気のように続いている事とも捉えられる。特に防災や建築といった部分はまぁ当然いるよねといった感じで、概ね比較検討されずに残っていることもおおい。
ちょっと防災や地域を守る的な発想について考えてみる、自分たちの住んでいるところを厳重に守っているうちに住んでる人がどんどん減っていったら、以前のように守る必要があるのか。また厳重に守りすぎた結果、誰も寄せ付けない場所になってしまわないか。とも考えてしまう。特に消防団の無意味に思える行進などの訓練や行事に参加していてよく感じる。防災や自衛というのも大事なことではあると思うが、そのリソース配分とかは考え直してもよいのではと感じる。そういう事含めて全体像を見える場所がないからまず見通して考えてみたいという事もやはりあるが、みんながそれぞれ担当的なところを持ってその効果はともかく責任感を持ってやってるのが意外といい距離感だったりもする。
この辺も含めて結局立ち行かなくなるところまで行きついてから考えりゃいい話と言われればそうなのだけれど、一般の人は考えるだけ無駄というのに覆いつくされた社会はいやだなと思うわけだし。じゃ過酷なレッドオーシャンへ飛び込みで押し合いへし合いして一般の人じゃなくなるのを目指すかと言われればそっちもいやだなと思う。だからこそあれこれ考えるわけだが、一人一人のなんとなく心地いいやり方を受け入れつつ、一人一人のなんとなくの感覚のいい加減さも理解した上で、全体性を考えなければならないのかもしれない。まぁやっぱり難儀な話である。
で結局どこを目指すの?
私自身がどこを目指したいのかここまでを踏まえて改めて言語化すると「もっと気軽に生きる事を楽しめたらいい」というのが今の気持ちには近いかもしれない。これは私自身もそうだし、ふと「なんで生きてるんだろう」とか考えてしまうようなストレス社会に生きるすべての人を巻き込みたいとも思う。だからこそ繰り返しの日常にも安定した希望を描けるような、または変化や努力をしたらそれが報われるような。かといって今目先の利害ばかりを見据えて「あなたの夢ややりたい事は何?」と一々問い詰めてしまうような事ばかりではいけないような。やっぱり難儀だなと思いつつ、それぐらいの方がやりがいがあるかとこれからもあれこれと考えて進めていこうと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
