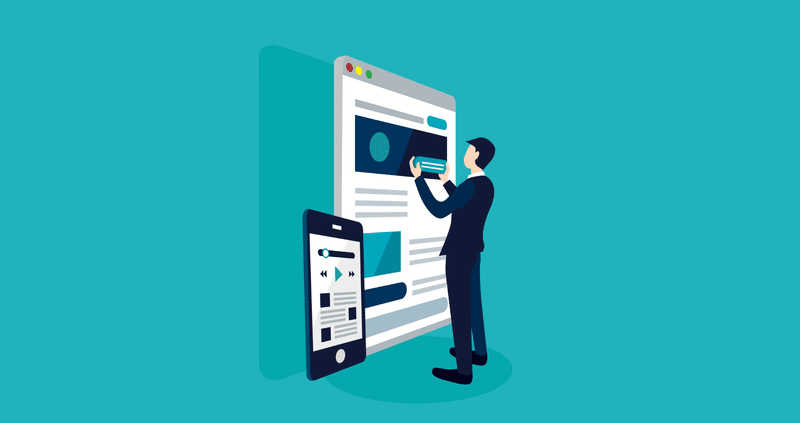
④タックスプランニング 事業所得
◎事業所得
◯計算方法
①棚卸の計算
年初の商品棚卸高+仕入高−年末の商品棚卸高(届出をしていない場合○最終仕入原価法☓先入先出法☓総平均法)
②減価償却費の計算
届出をしていない場合⇒定額法(個人)
車:定額法
金額×定額法×月数/12×台数
(毎年一定額を償却する定額法と、毎年の残存価額の一定割合を償却する定率法があり、どちらの償却方法を適用するか届出をしない場合、個人は法定償却方法である定額法となる(法人は定率法)。また月数は切り上げ)
③所得計算
(売上高−売上値引および返品高)−①棚卸高−必要経費−減価償却費−控除額
※控除額
①青色申告
最高65万円
・適用基準
正規の簿記の原則に従い記録
貸借対照表等の帳簿書類を確定申告書に添付
納税地の所轄税務署長に申告期限内(翌年の2月16日から3月15日まで)に提出
②白色申告
事業専従者控除
要件
・15歳以上
・生計一にする親族
・6ヶ月を超える期間事業に従事
控除額
・事業主の配偶者86万円
・その他の親族50万円
or
不動産、事業、山林所得の金額の合計額/1+事業専従者の数
◎青色申告
◯欠損金の繰越控除
ex.
今年赤字が1,000万円あり、今年は法人税がかからない。この1,000万円の赤字を最長10年間繰り越すことができる。翌年黒字が300万円あり、1,000万円の赤字と合算できる。翌年も法人税が全額かからない。
・控除期間
10年間(H30以降)
・控除出来る額
①1億円超
今年の黒字の半分だけが合算可能
②1億円以下
今年の黒字全額控除可能
・青色申告→白色申告に変わっても欠損金の繰越控除の適用を受けることが出来る。
・2以上の事業年度において生じた欠損金
⇒古いものから順に繰越控除
・事業初年度の欠損金の繰越控除額の限度
=繰越控除前の所得金額
FP1級20201/1㉜
1) 欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出していれば、その後の各事業年度について提出した確定申告書が白色申告書であっても、欠損金の繰越控除の適用を受けることができる。
⭕
2) 繰り越された欠損金額が2以上の事業年度において生じたものからなる場合、そのうち最も古い事業年度において生じた欠損金額に相当する金額から順次損金の額に算入する。
⭕
4) 資本金の額が1億円以下である普通法人が2019年4月1日に開始する事業年度において欠損金額を損金の額に算入する場合、損金の額に算入することができる欠損金額は、繰越控除前の所得の金額が限度となる。
⭕
FP1級2018/9㉜
1) 資本金が2億円であるA社の平成30年4月1日に開始する事業年度において生じた欠損金額の繰越期間は、最長で7年間である。
❌
10年間
2) 資本金が1億円であるB社の平成30年4月1日に開始する事業年度において生じた欠損金額の繰越期間は、最長で10年間である。
⭕
3) 資本金が2億円であるC社の平成30年4月1日に開始する事業年度において、繰越欠損金の額が2,000万円、繰越欠損金控除前の所得の金額が1,200万円である場合、繰越欠損金控除後の繰越欠損金の残高は1,400万円である。
⭕
黒字1,200万円の半分の600万円と赤字2,000万円を合算し繰越欠損金の残高は1,400万円
4) 資本金が1億円であるD社の平成30年4月1日に開始する事業年度において、繰越欠損金の額が1,500万円、繰越欠損金控除前の所得の金額が1,000万円である場合、繰越欠損金控除後の繰越欠損金の残高は500万円である。
⭕
黒字1,500万円と赤字1,000万円を合算し繰越欠損金の残高は500万円
◯事業用の車両を売却した場合
(事業で使用しているトラック等)
⇒資産を譲渡した
⇒譲渡所得(土地建物等、株式等以外の)
❌事業所得
FP1級2020/1問58
事業所得
①棚卸の計算
年初の商品棚卸高0+仕入高1,500万円−年末の商品棚卸高(最終仕入原価法)600万円=900万円
③(売上高1,700万円-売上値引および返品高100万円)-棚卸高900万円-必要経費500万円=200万円
A.200万円
FP1級20201/1㉕
2) 個人事業主が、事業所得を生ずべき事業の用に供している取得価額130万円の車両を売却した場合、事業所得の金額の計算上、当該車両の売却価額を総収入金額に算入し、当該車両の未償却残高を必要経費に算入することができる。
❌
譲渡所得
3) 個人事業主が、生計を一にする親族が所有する土地を賃借して事業所得を生ずべき事業の用に供している場合、事業所得の金額の計算上、当該親族が納付した当該土地に係る固定資産税に相当する金額を必要経費に算入することができる。
⭕
FP1級2019/1問58
次の設例に基づいて,下記の各問に答えなさい。
《設例》
個人事業主であるAさんは、妻Bさんと小売業を営むとともに、所有する賃貸マンションから賃貸収入を得ている。Aさんは、営んでいる事業が軌道に乗り、さらなる拡大を企図して、将来的に法人化することを検討している。
Aさんは、2019年中に、非上場株式の配当金を受け取った。この配当金については、総合課税により配当控除の適用を受ける予定である。また、加入していた生命保険契約を解約し、解約返戻金を受け取った。
Aさんの家族構成および2019年分の収入等に関する資料は、以下のとおりである。
なお、Aさんは、2019年は消費税について免税事業者であり、税込経理を行っている。
〈Aさんとその家族に関する資料〉
Aさん(50歳) : 青色申告者
妻Bさん(50歳) : 2019年中に青色事業専従者として給与収入80万円を得ている。
長女Cさん(24歳): 大学院生。2019年中の収入はない。
長男Dさん(20歳): 大学生。2019年中にアルバイトにより給与収入100万円を得ている。
〈Aさんの2019年分の収入等に関する資料〉
I.事業所得に関する事項
(1)2019年中における売上高、仕入高等
売上高:9,960万円
仕入高: 7,500万円
売上値引および返品高:14万円
年初の商品棚卸高 :710万円
年末の商品棚卸高 :745万円
必要経費※ :690万円
※上記の必要経費は税務上適正に計上されている。なお、当該必要経費には、青色事業専従者給与は含まれているが、売上原価および下記(2)の減価償却費は含まれていない。
(2)2019年中に取得した減価償却資産(上記(1)の必要経費には含まれていない)
車両1台※:7月12日に事業用として48万円で購入し、取得後直ちに事業の用に供している。
(耐用年数4年、償却率(定率法 0.5 / 定額法 0.25))
※償却方法は法定償却方法とする。
II.不動産所得に関する事項
賃貸収入:720万円
必要経費:750万円
賃貸用不動産の取得に要した負債の利子:60万円
(土地の取得に係るものが42万円、建物の取得に係るものが18万円)が含まれている。
III.Aさんが2019年中に受け取った非上場株式の配当金に関する事項
配当金額 : 60万円(源泉所得税控除前)
※その支払の際に、所定の所得税および復興特別所得税が源泉徴収されている。
※当該非上場株式を取得するための負債の利子はない。
IV.Aさんが2019年中に解約した生命保険に関する事項
保険の種類: 一時払変額個人年金保険(10年確定年金)
契約年月 : 2009年8月
契約者(=保険料負担者) : Aさん
被保険者 : Aさん
解約返戻金額 :370万円
正味払込済保険料:300万円
※妻Bさん、長女Cさん、長男Dさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
※Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※Aさんとその家族の年齢は、いずれも2019年12月31日現在のものである。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
Aさんの2019年分の事業所得の金額を求めなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は円単位とすること。なお、Aさんは、正規の簿記の原則(複式簿記)に従って記帳し、それに基づき作成した貸借対照表および損益計算書等を確定申告書に添付して、確定申告期限内に提出するものとし、事業所得の金額の計算上、青色申告特別控除額を控除すること
解答解説
事業所得の金額=売上−売上原価-必要経費-青色事業専従者給与-青色申告特別控除額
・売上9,960万円-売上値引および返品高14万円
・売上原価=期首棚卸高+当期仕入高-期末棚卸高
=710万円+7,500万円-745万円=7,465万円
・必要経費690万円
・青色事業専従者給与0円
・青色申告特別控除額65万円
・減価償却
=48万円×1台×0.25×6ヶ月/12ヶ月×100%
=6万円
(定額法OR定率法?個人で届出をしない場合⇒定額法
償却できるのは事業で使った月数分だけ
減価償却費=取得価額×償却率×事業での使用月数/12ヶ月×事業専用使用割合
Aさんの車両の使用開始日は7月12日なので、1年のうち5ヶ月と20日間だけ使用していますが、1ヶ月未満の使用月数は切り上げ。6ヶ月使用したとみなされる。
A.17,200,000(円)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
