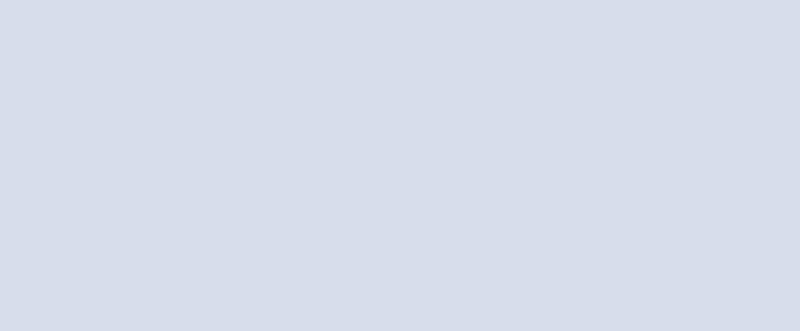
不死身について
男は不死身とあだ名されていた。
不死身は私の祖父だった。いつも、にんまりと、いたずらっぽい、なにかを企むような笑みを浮かべていた。はっきり言えば田舎のがきんちょが体だけ大きくなったみたいなものだった。
不死身に、不死身というあだ名がついた日のことをたまに思い出す。
ある日、一本の電話が入った。それを聞いた両親は真っ青な顔をし、突然病院に行くと言い私もそのまま連れられた。小さい頃だったからあまり詳しく覚えていないけど、不死身になにかがあったのだということだけが分かっていた。症状が重篤だとか軽微なのかも分からなかった。多分子供には何も伝えなかったのだろう。
病室に案内されると、そこにはちょっと恥ずかしそうに笑う不死身がいた。体を起こしていたし、色んなところに包帯やら絆創膏をしていたけど、確かにピンピンとしていた。
横を見上げると、電話の時からずっとあった、親の顔に走る緊張が消えたのを見た。それと同時に、もーーーー、と言いながら溜め息をつき、本当にやめてくれよと、泣き真似をしながら呆れたように笑っていた。
どうも、出かけようと軽トラでバックしながら家から道に出たらしい。
残念ながら、ここはくそ山の中であり、家は山の斜面の中腹にあって、道はそこに沿ってつけられていて、道に付くガードレールの向こう側は崖だった。その下は7メートルくらいあって、田んぼになっていた。
つまり、バックしていたらそのまま道を外れて、下に落ちていたのだった。
親戚も集まってきた。皆が思ったよりも元気にしている本人を見てびっくりしていた。親戚で一番口の悪いおばさんは、来てすぐに、あんたには呆れたとかいい加減にしろだとかまくし立てて、それから親に、今度から呼ぶな、本当にこれは死にそうだと思う時だけ呼ぶようにせえと怒っていた。誰もが苦笑いをしていた。不死身は大笑いしていた。
不死身は私を近くに呼ぶと、耳を指差してから、見ろ、切れた!と、得意気な声を出した。
見ると、耳はまるでスパッと刃物で斬られたみたいに、うえの方1センチくらい綺麗に横に切れて無くなっていた。ぽかんとした。そんな私を見てヘラヘラと不死身は笑って、尚且つ勇気の証かのように自慢気な表情をしていた。
皆にしこたま怒られて、しばらくして不死身は退院した。耳はちょんぎれたが、ごく元気そうに帰ってきたのを見て、人は驚き、不死身と呼ぶようになった。
幼い私も、この人は不死身だと思った。この人が簡単に死ぬものか。永遠にこうやって元気に軽トラを走らせ、畑を打ち、スパスパと煙草をふかし、日本酒をたらふく飲んで、いつものように私の名前を呼んでくれるような気がしてならなかった。
不死身は動物が好きだった。絶え間なく犬を飼っていた。小さい頃にいた大きな雑種は、ジョンという名前だったのに、ひどく訛っていて、ゾンと呼んで可愛がっていた。
猫もいる。家に行けば今も、ちまっこく年老いたおばあちゃんになったけど、一緒にテレビを見ていた部屋でいつものように寝ている。
まるで、何事もなかったかのように、ふたりの間を少し空けつつも、もういないその人の近くにいるようだ。
また、知り合いの精肉屋から大好物のセンマイを袋に一杯買ってきたから焼き肉を食うぞと言いながら帰って来るかもしれない。センマイは、2、3回噛んだら飲み込んでしまうんだと教えられて、横で母親が詰まらせたらどうするんだと嘆いたことを思い出す。
しこたま食べれば、風呂に入ってしまえと言うだろう。昔は薪のお風呂だったから、すごく熱くて飛び上がりそうだった。自分の山から、先祖が邪魔なところに植えよったと桜を伐ってきたから、雑な本人には似つかわしくない、良い桜の香りのお風呂。
お風呂上がりでもいとこと遊んで、不死身の部屋で一緒に寝る。なんか話をしてくれよとねだる。
メロン太郎、と話し出した。桃太郎と一緒の話。ただ不死身はめんどくさがって、川からメロンが流れて、そのまま過ぎ去っていきました。終わり、と締めてしまう。いとことゲラゲラ笑いながら、短い、もっとちゃんと話してよと騒ぐ。
次のレモン太郎はおじいさんがレモンを持ち帰ったが、切ってもなにもなかった、で終わった。そんなことで笑ってるうちに、そのまま眠りにつく。
不死身は変な奴だった。世の中どこ探しても、耳がちょんぎれた祖父がいる子なんかいないだろう。でも、その変な感じは私を包んでくれていて、何をするのも怖くなどなかった。
私も相当に変わっているんだろうということは、大きくなってから気付いた。平凡でなければならないように思えたが、それはすごく難しくて、つまらなかった。自分のなかがぐちゃぐちゃで、何を言われるのも癪だったときも、不死身は会うたび変わらず、いつものように笑っていて、何も言わずにただ昔と同じままでいた。
不死身は不死身ではなかった。癌になって、死んだ。
結婚するのだと旦那と言いに行った時、鼻に管を挿して生活しているのだと分かって、もう昔のようにはいかないのだと思った。なんだか耐えられそうになかった。不死身は、世間話を一通りしたあとに一番気に留めていた、いとこに付き合ってる人が出来たみたいなんだと言った。その子も私も、上手いこと世渡りしていくタイプでないから、心配の種だったのだと、その時気づいた。
不死身は昔より老いぼれた顔をくしゃくしゃにして笑いながら、ぽろぽろと泣いていた。
この人は本当は涙もろいことを知っている。火垂るの墓を見て号泣していたところを見たことがあった。私は火垂るの墓を見たことがない。不死身をこんなに泣かせる映画を見ることをためらう。普段あんなにふざけているのに、こんな風に涙を見せるだなんて勘弁してほしい。
いとこの話を聞いたら、私はそこから早めに話を切り上げて帰った。とてもその場にいて、そのまま話を続けることなどできそうになかった。帰り道に旦那がハンドルを握りながら、あなたは変わってるって言ったけど、常識があるいい人じゃんかと言ったから、泣いてしまった。
それから何年かかけてゆるやかに、でも確実に弱っていくのを見つめた。最期は見れなかった。
あれから少し経って、私は生活に追われ、忙しなく日々を消費している。少し前、高畑監督の追悼で火垂るの墓が放送されたとき、不死身のことを思い返した。あの耳を思い返す。あの泣き顔も。猫にちょっかいかけてキレられている時も。
本当にふざけた思い出ばかりが浮かんでくる。一人で笑ってしまう。
不死身が死んだということが、最初ちっとも入ってこなかった。悲しみが受け入れられないとかではなく、単純に理解が追い付かなかった。こうしてたまに思い出す時、ああもうあんなに面白かった人はいないのだと、私は改めて知らされる。そうやって、少しずつ理解のゲージが貯まって、ようやく死というものを実感する。
同時に、たくさんの思い出されることが、不死身の生を示す。思いだし笑いをするときに、こうやっていつも笑わせてくれたのだと分かる。何度も何度も振り返るたび、不死身のあのにやっとした顔を思いだす。不死身と私は、生きていたのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
