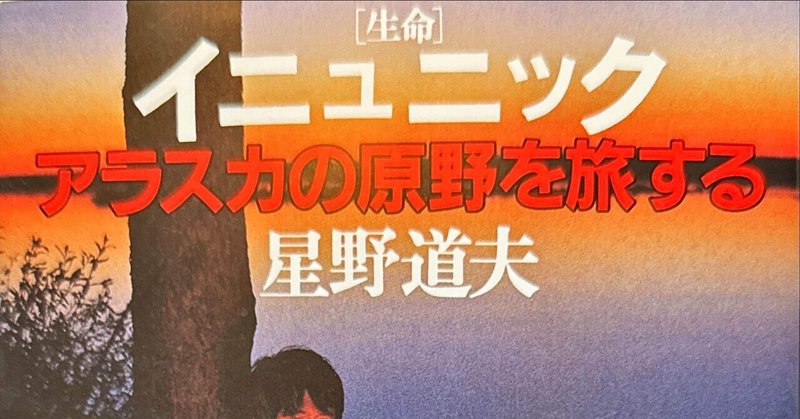
『イニュニック〔生命〕―アラスカの原野を旅する―』ノート
星野道夫著
新潮文庫
最近、星野道夫の著作を集中して読んでいる。彼の自然と生命に関する含蓄に富んだ文章にふれるたびに、筆者は時代を超えたアラスカの魅力に取り憑かれ、まだ見ぬ地への想像力をかき立てられている。
アラスカという極北の大地と、その地に長く住み滅びつつあるインディアンやエスキモーの人たちの素朴でありながら哲学的な一言を味わうため、さらには星野と同じようにアラスカという大地に魅せられて住むようになった人たちと星野の友情溢れる物語が何故か懐かしくなって再読したくなる。
アラスカの歴史に触れてみる。
アラスカは、1867年にアメリカ合衆国がロシア帝国から買い取った広大な土地である。その面積は147万8千平方キロメートル。数字だけではピンとこないが、日本の総面積の約4倍もあり、アメリカ合衆国の国土の16%を占めている。そんな広大な土地をロシア帝国が売ることした理由は、クリミア戦争後の財政難克服のための資金調達のためで、当時中立国であったアメリカに売ることにしたのだ。総額720万ドル(1平方キロメートルあたり5ドル)であった。
その後、ユーコン川近辺で金鉱が見つかり、1896年にゴールドラッシュが始まって、白人が押し寄せ、いまのフェアバンクスなどの町はこの頃できた。
アメリカが買い取ったアラスカは、最初は準州、その後1959年にアメリカの49番目の州となった。州の中では一番広大な面積を占め、人口密度は一番低い。
さらに遡ると、およそ2万年前のこと。地球上で繰り返されてきた最後の氷河期(ウィスコンシン氷河期)の時代に地表面の水が凍り、1000メートルから2000メートルの厚さの氷が地球上を覆っていた時代がある。そのため海水面はいまより100メートルほど低下して、今のベーリング海峡(ちなみにいまのこの海峡の平均深度は約40メートル)は干上がっており、「ベーリンジア」という平原が広がっていた。日本列島でいうと、「縄文海進」の前になる。
ユーラシア大陸を東に進んできたモンゴロイドは、その回廊を渡って、最初はインディアンの祖先、そのあとにエスキモーの祖先がアラスカに到達し、それ以来、アラスカはエスキモーとインディアンの土地であった。エスキモーは鯨などの海洋動物中心の狩猟生活で、インディアンは内陸部でカリブーやムース(ヘラジカ)を獲って長い間生活をしてきた。
アメリカの49番目の州となって、変わりゆくアラスカ――原住民とアメリカ政府との話し合いがもたれ、英語教育を進めることが発表された。
その時に、あるエスキモーの老人が、自分たちの暮らしのことは自分たちの言葉で語りたい。英語ではどうしてもその気持ちを表現できないといい、その例として英語ではsnowの一言でも、じぶんたちにはたくさんの雪がある。同じ雪でも、さまざまな雪の言葉を使いたいという。
エスキモーの様々な雪を表す言葉を書き出してみると――
●アニュイ(ANNUI)……降りしきる雪
●アピ(API)……地面に積もった雪
●クウェリ(QALI)……木の枝に積もる雪
●プカック(PUKAK)……雪崩をひきおこす雪
●スィクォクトアック(SIQOQTOAQ)……一度溶けて再凍結した雪
●ウプスィック(UPSIK)……風に固められた雪
一年のほとんどを雪や氷の中で暮らす彼らにとっては、雪の様々な状況や状態を示す言葉は日々の生活環境に直結した表現なのである。それは単なる言語ではなく文化だ。それを英語に統一してしまうことは、自分たちの生活様式を一変させるものであって、老人たちにとっては、これからの日々の生活が描けなくなってしまう恐れもある。
若者たちが共通言語の英語とそれに伴う文化に染まっていくのは、時の流れとしていたし方ないことではあるが、それは自分たちの元々の言語がなくなってしまうことに繋がり、やがてエスキモーやインディアンの文化やコミュニティの消滅をも意味するのである。
星野道夫が初めてアラスカに移り住んで10年経つが、結局自分は旅行者に過ぎないのではないかと星野は思い始めていた。小さな小屋を借りており、生活のベースはあったが、旅行者であることに、ある種の疲れと物足りなさを感じ始めていた。
ちょうどその頃、自分の家の隣の森が売りに出たとフェアバンクスに住んでいる友人が知らせてくれ、星野はこの地が気に入り、1990年、家を建てた。
この本は、家を建ててから1993年秋までの出来事が収められており、「マザー・ネイチャーズ」(新潮社刊)という雑誌の連載記事に、新たに3つの旅のことを書き加えたエッセイからなっている。
星野はアラスカの手つかずの自然の雄大さと過酷さ、そこに棲むカリブーやムース、ブラックベアなどの多くの動物との出会い、エスキモーやインディアンの人たちとの交流、星野と同じようにアラスカの手つかずの自然に魅せられ、定住するようになった家族との交流など、印象的な出会いを書き綴っている。
その中で、一つだけ異質な物語が描かれる。
それは日本軍が占領していたアリューシャン列島のキスカ島を、1993年8月、日米の合同慰霊祭のため、当時の日本兵2人と米兵10人が訪れたときの話である。星野はその取材のために同行した。
1943年7月29日、約5500人の日本兵が、濃霧が立ちこめる中、わずか40分でキスカ島を脱出した。のちに〈奇跡のキスカ脱出〉といわれるのだが、その時に脱出した2人の元日本兵と、そのあともぬけの殻になったキスカ島に上陸した元米兵の10名がこの慰霊祭に参加した。
上陸したとき、まさか日本兵がいないとは思わず、霧で視界が効かないために同士討ちが頻発し、多くの米兵が命を落としたという。
この奇跡の脱出の約2ヶ月前、アッツ島の玉砕(2638人が戦死)があった。
12人の老兵たちとキャンプをしながら過ごした5日間を貴重な体験だったという星野は次のように書く。
「人々は、どうしようもなく、時代と共に生きている。そして気の遠くなるような戦死者の数も、決して戦争の悲惨さを伝えてはこない。それを知るためには、死んでいった無名の人々のかけがえのない生涯と、残された者たちのそれからの戦後を、ひとつひとつたどる途上でしかわかり得ないのだろう。戦争とはそんなものだ、とはどうしても言い切れない理不尽さを知るのであろう。」
アリューシャンでは珍しく晴れ上がったある日、星野は元米兵の中で一番親しくなったジョージ・アールと草の上に腰を下ろして話をした。彼は戦後、故郷のメイン州に戻り、大学の美術の教授になった人物で、キスカ島に駐留していたときも何枚かの絵を描いたという。
5日間滞在したキスカ島を去る前夜、アールは一つ言い忘れたことがあると言って星野のところに来てこう話しかける。
駐留していた頃の自分は、キスカ島の荒涼とした風景に魅了されて絵を描いたが、その時は足もとの小さな自然には気がつかなかった。ツンドラに咲く小さな花々、風に揺れる草、こけの美しさなど50年ぶりに戻って来て、いま初めて気づいた。それだけを星野に伝えておきたかったとその老兵は微笑んだという。
最後にもう一つ。この本の最後に柳田邦男が、「言葉の発見者としての星野道夫」という解説を書いているが、この文章が星野道夫という存在の本質を余すところなく描いており、一読に値することを付記しておきたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
