「石母田正の英雄時代論と神話論を読む――学史の原点から地震・火山神話をさぐる」
以下はアリーナ2015年(第18号)に書いたものです。長いです。そのうち本にしたいと思っています。
民族の歴史学を継承する
――石母田正の英雄時代論から地震・火山神話をさぐる-
はじめに
一九四八年に発表された石母田正の「古代貴族の英雄時代」という著名な論文は、まだしかるべき研究史的な評価をえていない。この論文の達成と限界、そして誤りを確認することはきわめて重要である。私には、それが曖昧になっていることは、この国の「古代史」研究における戦後派歴史学の初心に関わる問題であるように思える。
この論文のことを考えるためには、まずその時代に戻って考えてみる必要がある。そこで、最近、たまたま目に触れた、岡本太郎の証言を紹介するところから始めたい。以下は岡本の『日本再発見ー芸術風土記』の出雲の項の一節である。
先日、石母田正に会ったら、大国主命は土着の神ではないという新説をたて、いずれ発表して定説をくつがえすと言っていた。出雲大社は伊勢神宮や鹿島神宮と同じように、政治的な意味で中央から派遣された神社であり、大国主命の伝説も、むしろ近畿、ハリマあたりの方が本場だというのだが。
岡本太郎と石母田正の交友の経過は知らないが、気の合う仲間だったのであろうか。この文章がのった『芸術新潮』は一九五七年七月号だから、岡本が出雲を訪れたのは、その年の初夏らしい。だから、石母田が岡本に右のようなことを語ったのは、それ以前である。
石母田が出雲神話を論じた第一論文「国作りの物語についての覚書」は、この年、一九五七年の四月に刊行された『古事記大成(二)』(平凡社)に載り、第二論文「古代文学成立の一過程(上・下)は、同じ四月・五月に発行された『文学』(二五-四・五)に載っている。つまり、石母田は、おそらくこれらの論文を書いている途中か、書き終えた頃に岡本と話しているのである。これは、この時期の石母田の研究関心を示す重要な情報である。
岡本の文章の傍点部に注意されたい。「出雲大社は伊勢神宮や鹿島神宮と同じように、政治的な意味で中央から派遣された神社であり」という部分である。これらの論文では、まだそこまでは踏み込んでいない。石母田はこれらの基礎となる論文を書き上げた段階で、その先の抱負を岡本に語ったのであろう。この出雲大社論が実際に論文「日本神話と歴史ーー出雲系神話の背景」に発表されたのは、二年後の一九五九年六月となった(『日本文学史三』(岩波書店)。
しかし、これによって石母田が「定説をくつがえし」、新たな神話論の方向を示すことに成功したかといえば、私はそうはいえないと思う。なにしろ石母田は歴史学の社会的責務にかかわる運動に大きな責任を負っていて多忙であった。私のように、平安時代・鎌倉時代を専門にしているものにとっては、一九五六年というと、石母田が『古代末期政治史序説』の刊行を終えると同時に、佐藤進一との協同研究を始め、いわゆる国地頭の研究に入った年であり、その結果としての「鎌倉幕府一国地頭職の成立」の発表は一九六〇年となった。この国地頭論が、いわゆる治承寿永内乱論、鎌倉期国家論において決定的な意味をもつ論文であったことはいうまでもない。凡人の常識からすると、この時期の石母田は、研究時間のほとんどを、それに費やしていたはずである。
そして、それを終えた段階でも、石母田は神話論に戻ることはできなかった。それはもちろん、神話論固有の難しさという問題があったろう。しかし、何よりも、石母田は、第二次大戦終了後も古代史のアカデミズムがぱっとしないのに強い危惧を感じて、ともかくも古代史研究に筋を通す仕事を急がねばならないと考えていた。よく知られているように、当時、『中世的世界の形成』の影響は大きく、直接の影響をうけた稲垣泰彦・永原慶二・黒田俊雄・網野善彦・戸田芳実などが群をなすようにして研究を進めていたから、あとは委ねてよいという判断があったといわれる。そして、この古代史研究への転進は、一九六二年の岩波講座(第一次)では「古代史概説」と「古代法」に最初の結実をみせ、一九七一年の『日本の古代国家』の刊行で完結した。
そして、一九七三年には『日本古代国家論』の第一部と第二部が出版された。この『日本古代国家論』(第二部神話と文学)のあとがきで、石母田は折から企画されていた『日本思想大系 古事記』の編纂・解説作業のなかで「古代貴族の英雄時代」を再検討する課題に立ち戻ると宣言した。ところが、石母田は、その直後一一月に発病して新たな仕事をする条件を失ってしまったのである。これはいわゆる戦後派歴史学の学史では著名な経過である。
それ故に私たちは、第二次大戦直後の諸論文から、石母田の構想を読みとり、その意義と限界を考えるほかないのである。そして、その中心はやはり岡本に石母田が語ったというオホナムチ=オホクニヌシ論である。その内容はさすがに見事なものであるが、現在の段階では詳細な再検討が可能となっている。本稿は、「古代貴族の英雄時代」から出発して、このオホナムチ論の点検に進み、それに対置してオホナムチを地震火山神とする私説を述べることを課題としている。
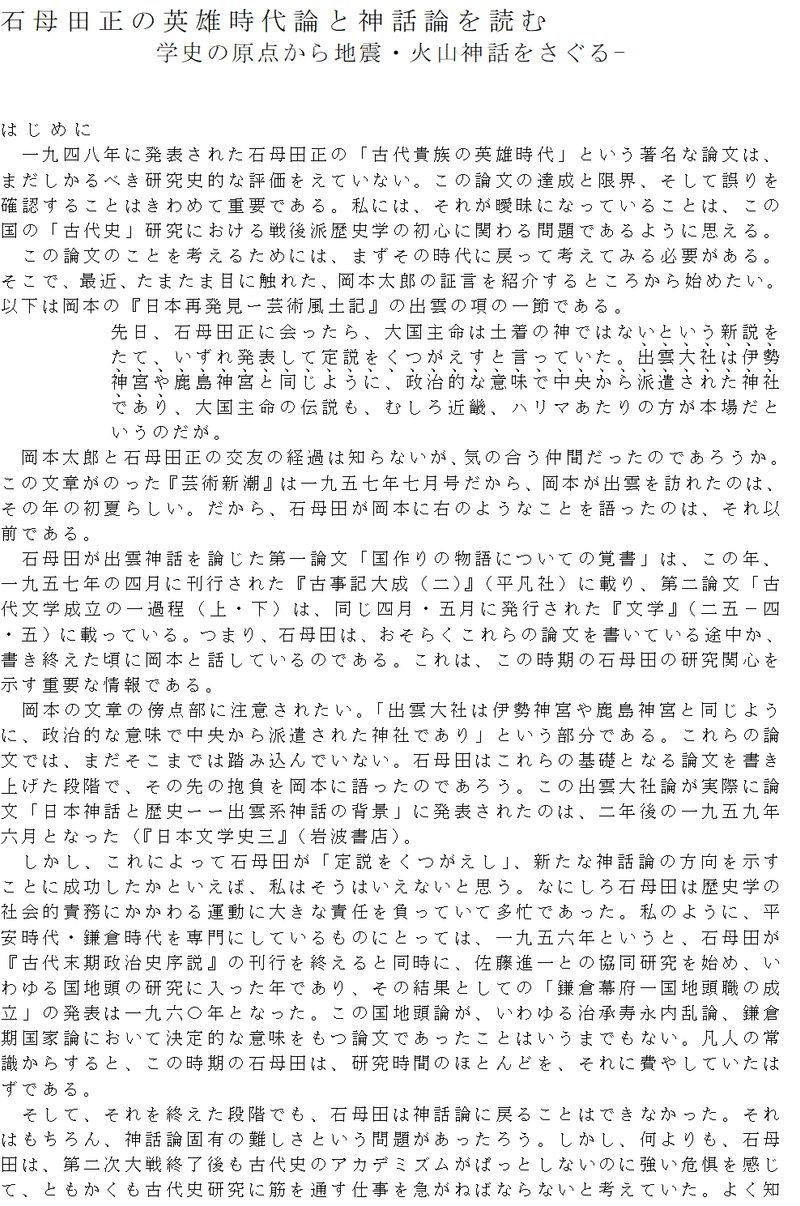
一 英雄と英雄神論――イワレヒコとヤマトタケル
まず論文「古代貴族の英雄時代」の内容にそくして、石母田の神話論を紹介していくことにするが、石母田が神話論の課題としたのが何だったかは、相対的に明瞭な問題であろうと思う。つまり、日本が帝国と侵略の道を歩み、アジア太平洋戦争を引き起こすうえで、神話にもとづく国家イデオロギー(皇国史観)は決定的な意義をもっていた。それを全面的に再検討し、神話とは、日本列島に棲むものにとって何を意味するのかを論ずることが、国民の歴史意識を考える上で欠くことができない。石母田は、そう判断していたのであろう。「古代貴族の英雄時代」の「はじめに」は、古代史研究の誘惑的な魅力は「古代世界が成立してくる過程」において働いた「原始的な力という以外にはない運動」「人間の原始的創造的な力」の発見にあるとはじまる。このことは、石母田の神話論がなかば世界観的な要素をもっていたことをよく示していると思う。また石母田が『古事記』について「その文学としてのあり方を研究することはそのまま歴史学の課題とならなければならない」としたのは(一~二頁、以下、頁数は断りのない場合は、『石母田正著作集』一〇巻の頁である)、もちろん、学術的な方法の問題であったが、そこには神話を一つの民族的な文化として受けとめるという趣旨が含まれていたことも明らかである。
もちろん、石母田は、それを「古代」の社会と国家の形成過程論を構想するなかで解こうとした。その姿勢は本格的で、かつ強烈なものであった。第二次大戦後の石母田が、このような高い地点から出発しえたのは、『日本歴史教程』の中心であった渡辺義通を囲んでもたれていたグループの一員として、戦争体制下においても神話の研究を蓄積していたためであることはいうまでもない。
A津田史学と混迷した英雄時代論争
(1)津田史学の評価について
石母田の神話研究は津田左右吉の仕事に学び、それを乗り越えようとする営為であった。津田の『古事記』『日本書紀』の研究はリベラルで徹底的なものであった。それが天皇制ファシズムによって問題とされ、津田は大学から辞職するところまで追い込まれたことはよく知られていよう。
石母田は皇国史観との戦いを担った津田史学を評価する点では人後におちない。津田史学が国家的なイデオロギーとの戦いのなかから生まれたという見方が石母田の津田史学に対する評価の基本であった。石母田は「記紀における英雄物語をそのまま歴史的事実として、あるいは歴史的事実に根拠のあるものとして考え、記紀の作者が後代の政治組織に適合するように意識的に述作した英雄物語をそのまま民族の英雄時代であるとしいる」(八四頁)、そういう国家イデオロギーに対して、津田は果敢に戦ったという。
津田は『古事記』『日本書紀』の神話史料について厳密な批判を加え、その枠組がきわめて強い政治性をもっていることを詳細に明らかにした。津田は、『古事記』『日本書紀』の記述には、中国六朝の神秘思想、神仙思想の文学的な影響が強いとしているが、私も、それに依拠して『古事記』から『竹取物語』へは中国神仙思想の影響が筋のように貫いていると論じたことがある(『かぐや姫と王権神話』洋泉社新書二〇一〇年)。倭国においては、少なくとも七世紀までは神話時代が続いており、奈良時代は神話時代から完全に分離していたわけではなかった。『古事記』『日本書紀』は、そういう時代に、隣接の中国・朝鮮からの急激な文明化の影響の下で生まれたものである。津田のいうように奈良時代の知識人は中国朝鮮の最新の文芸動向や神仙思想を受け入れ、それを下敷きにして自国の神話を語ったのである。『古事記』『日本書紀』の叙述の見事さは、ほとんどそれによっているといってよい。そして、逆にいうと、このような稀有な歴史経過によって、『古事記』『日本書紀』は、神話史料としては、世界でも珍しいほどに政治性が強く、見事な文芸作品という外見の下に強固な国家思想を秘めたものとなったというべきであろう。私は、津田のこのような業績と方法を知らずに、この国で歴史家であることは許されないと考える。
しかし、問題はその先にあった。つまり、このような決定的な仕事をした津田が戦争の終了後にどのような発言をするかは必然的に歴史学者全体の注視をあびた。そのなかで、津田は一九四六年四月に「建国の事情と皇室の万世一系の思想の由来」(『世界』)を発表し、天皇制とその文化を擁護する立場を宣言して、いわゆるマルクス主義に対する批判を展開したのである。これに対して同年六月、石母田は「津田博士の日本史観」を発表して、津田の史観を「余りに浪漫的な」として、その「歴史に優位する民族の範疇」に対する原則的な批判を行った。
そもそも津田は歴史学が社会科学であるということ自体を認めようとしなかったのであるから、私は、この石母田の津田批判はマルクス主義云々ということをこえて、歴史学と社会科学の方法論からいって当然の批判であると思う。しかし、網野善彦が指摘するように、「戦後派」の歴史学にとって、ここに現れた津田と石母田の関係をどう考えるかは、一つの根本問題である(『網野善彦著作集』第七巻)。そこで網野は、津田に対する石母田の姿勢に「思い上がり」があったという厳しい感想を述べている。これは、当時、石母田のそばにいた網野の実感であって、おそらく事態の核心をついている部分があるのであろう。
しかし、この網野の論評は、率直にいって、やや個人的な発言となっていて、津田と石母田の間の学術的な論争の全体像をとらえていない。つまり、網野は、どういう訳か、一九四八年に発表された、この論文「古代貴族の英雄時代」における石母田の津田批判についてまったく論及していない。もちろん、すぐに述べるように、この石母田の論文を契機として始まった英雄時代論争は混迷としかいえない状況をもたらしたのであるから、石母田の津田批判の意味が極小にみえたのは当然であろう。しかし、石母田は、津田を批判した責任上、この論文を起点として、神話論のレヴェルにおいて、津田左右吉との格闘を生涯の最後まで続けたのである。網野の視野には、この石母田が最後まで津田批判を続け、学問的な責任を取ろうとしていたことは入っていない。これは網野のような研究者にとっても、他の時代の問題となると、戦後派歴史学の学史の要部に関わる問題であろうと、それがみえていなかったことを示している。
とくに注意すべきなのは、この論文「古代貴族の英雄時代」において、石母田は右の「津田博士の日本史観」で述べたような歴史学と社会科学の方法論に属する問題にいっさい言及することなく、むしろ津田の神話論を高く正確に評価した上で学術的な論述内容に議論をしぼっていることである。石母田にとって、所詮、方法論の相違は二の次の問題であって、学術的な認識内容そのものこそが本質であることは明瞭なことであった。
石母田は、『古事記』は、その基本的な性格としては、口承によって民衆の間に伝承されてきたような叙事詩、民衆の精神・感情・生活を体現しているような叙事詩ではないという津田の見解を承認する。そして『古事記』『日本書紀』などを古代貴族階級の精神的所産として読む津田の方法を共有すると明瞭に述べている。そして、石母田は、精神史の取り扱い方が、「歴史学的=唯物論的方法」において「従来あまりにも機械的俗流的であった」。その弱点を克服するためにも、津田に学ぶことが必要であるとして、津田史学の優位性が精神史的な視角にあることを認めている(四頁)。
石母田の津田批判が優れていたのは、それを認めた上で、「津田博士の方法からすればまさにこの点こそ稔り多き収穫が予想され」るにも関わらず、津田の記紀論が「記紀のあいだに見られる微細ではあるが重要な相違」を見のがし、「物語としての歴史的評価はほとんど果たされていない」と指摘したことにある(八五頁)。石母田が「文学としてのあり方を研究することはそのまま歴史学の課題とならなければならない。(中略)歴史的事実であることだけが歴史の真理であるのではなく、文学的な真実もまた歴史学の事実でなければならない」(二頁)としたのは、その意味で津田への批判を含んでいたのである。たしかに石母田が「考証的学問が終わったと考えるところから実は真に学問的思惟を必要とする困難な問題がはじまるのである」と揚言していることは、考えようによっては石母田が津田の仕事を「考証的学問」と決めつける「思い上がり」のように読めるかもしれない。しかし、続いて「史家の文学史に対する無理解と文学史家の歴史的なものに対する無感覚は両者の協力と統一を困難なものとしてきた」(八五~六頁)とあることは、それが歴史学と文学史・精神史の協同を呼びかけるという趣旨であることを示している。石母田の津田批判は、いわゆる内在的な学術批判の節度をまもったものであったと考える。
(2)「英雄・英雄神」への着眼への正当性と誤り
こうして石母田は文学史的な視座と精緻な分析こそ、津田に欠けているものであると判断して、『古事記』の中から英雄の物語を摘出し、それを「古代貴族の英雄時代」の精神的所産として読もうとしたのである。石母田は、その際、高木市之助『吉野の鮎』の指摘に依拠し、さらにヘーゲルが『美学』で述べた英雄と叙事詩の概念を援用した。石母田は、このようにして『古事記』『日本書紀』のテキストのなかに、支配層と国家による英雄時代の記憶あるいは回顧を発見し、これによって「その背後にある世界を歴史的に位置づけることは記紀の本文批判において従来まったくかえり見られなかった方法であって、ここに津田博士の文献批判を超えてゆく一つの道が存在する」(三六頁)と考えたのである。
私は、神話テキストの分析においてまず英雄または英雄神の表現とイデオロギーに注目して、そこに神話の分析の端緒をもとめることは正当であると思う。英雄または英雄神の神話は現実の世俗世界との関係をもっとも濃厚にもつ神話だからである。歴史学はこの神話類型を超越して、直接に神話的想像力の世界に直行する訳にはいかないのである。また叙事詩、叙事文学は歴史の回顧であって、歴史の実体を表現するものではない。しかし、その文学的な特質が歴史性、実践性、客観性にある以上、歴史学の立場から行ってその分析が緊要な位置をもつことは否定できない。この研究段階で、このような問題設定をした石母田の天才は輝かしいものである。
また石母田が『古事記』などの神話テキストから、英雄の諸類型を析出する手続きも、それ自体としてはテキストの総合的な分析をふまえたものであったと思う。つまり、石母田は、第一に神武東征物語の本文に描かれるような政治的顕彰の対象となった英雄の形象、第二に社会集団の中に描かれる戦闘指揮者としての英雄の形象、第三に孤立した遍歴する勇士として、神々と闘う英雄の三つを抽出した。これ自体は英雄物語の分析、類別として、十分な学術的な手続きと根拠をもっており、いまだに有効なものである。
しかし、だからといって、石母田がそれを「第一は神武天皇に象徴され形象化されたいわば散文的英雄であり、第二には萌芽的であるが神武東征物語の歌謡群のなかにおける叙事詩的英雄であり、第三は日本武尊において典型的に見られる浪漫的英雄である」と特徴づけたことに(七〇頁)賛同できるとは限らない。
石母田の説明を詳しく見ていくと、まず第一の散文的英雄とは、政治的理念の拙劣な実体化と顕彰を述べる単調な記述において描かれた英雄像であって、神武東征物語の本文、およびそれと相似した性格をもつ雄略天皇に関する物語の本文、あるいは『日本書紀』本文に描かれたヤマトタケルの物語などを事例として提出されている。物語は空虚に装飾されていて、そこに描かれるのは英雄とはいっても独立性も文学性もない散文的なものにすぎない。そこでは発端も結末も最初から決められており、行動する集団は主人と従者の絶対的関係にあって英雄的な対立も性格を欠く俗物的なものである。そして、その背景として、石母田は専制的な世襲君主と、族制的=カースト的傾向を措定している(三〇、四五頁、六二、六九頁など)。
これに対して第二の叙事詩的英雄とは内的必然にもとづき独立的に行動し、運命に耐える意力と苦悩を起動力とする存在であり、同時に社会集団の代表として生き生きとした集団生活の中で描かれる肉体的な戦闘者であるという(二六頁)。この指摘は、高木市之助『吉野の鮎』を参考にしつつ、『古事記』のイワレヒコ=神武の大和攻略の物語に載せられた「久米歌」と呼ばれる歌謡群を素材としてなされている。たとえば「厳々し 久米の子らが 垣下に 植ゑし椒 口疼く 我は忘れじ 撃ちてし止まむ」という歌謡に登場する「我」は、久米という氏族集団に対して戦闘を呼びかける強盛な英雄的個人、首長、王である。これは、実際の神武あるいはイワレヒコではないことは当然としても、「四・五世紀の歴史時代を表現する断片」(三八頁)として宮廷に回顧的に伝承されたものであるという。
第三の浪漫的英雄とは独立的個性をもち運命と闘う存在であって、英雄としての矜持をもち悲劇性も事欠かない存在であるが、孤立した勇士であって、あらゆる社会集団からはなれ、政治的世界から追放された存在として主観的・主情的な性格、浪漫的な性格に流された存在である。石母田は、これについても高木市之助『吉野の鮎』に依拠しつつ、ヤマトタケルを浪漫的英雄の典型としている。たしかに、タケルは景行天皇に嫌われ、遠ざけられ、ほとんど孤立して東国を放浪したのであって、それ故に、この物語は英雄的叙事詩を形成していないということになる。
(3)石母田のヘーゲル依存の問題性について
前述のように英雄または英雄神に着目し、それ関係する史料を三つに分類して論じたことは妥当であるとしても、しかし、上記の散文的、叙事詩的、浪漫的などの意味付けに大きな問題がある。以下、少し長くなるが、論文「古代貴族の英雄時代」の「結語」から、それを示す部分を引用する。
古代文学が創造した二つの典型的な英雄としての神武天皇と日本武尊との対立は、古代貴族の精神構造=政治構造の対立的側面の表現とみられる。すなわち帝王的専制的=散文的精神と族長的貴族的=詩的精神との対立である。この散文的英雄と詩的英雄とを別々のものとして考えるならば、それは古代貴族の精神を正しく理解することにはならない。二つのものは対立しながら補い合っているのであって、古代文学におけるみじめなものとすばらしいものとの混淆もかかる統一的立場からのみ理解しうるであろう。したがって日本武尊の物語のすばらしさも、ただあまりに俗悪的散文的である世界においてのみ珠玉のように見えるのであって、文学的価値から見て過大に評価することはゆるされない。全体として中途半端な迫力の弱さは誰しも否定しがたいのであるが、それは政治的な東征物語の外観のなかに神々と闘争する遍歴的英雄の物語を展開しようとし、しかもそれを主情的抒情的なものに形象化しようとした不純と混乱――おそらくこの混乱は一人の芸術家による創作でなかったことにも由来するのであろう――からきたものと考えざるをえない。古代貴族の精神の二つの側面は相互に規定し合って文学精神の創造力の薄弱さの根柢をなしているように見える。このように散文的英雄も詩的英雄もともに古代貴族の精神的表現であるから、それを何か国民的民族的英雄のごとく語ろうとすることほど誤った態度はないのである(しかしかかる態度をたんに国家主義的な文学史のぎまんとばかり責めることは、かかる英雄がいかなる意味で階級的文学であったかを具体的に法則的にわれわれにしめそうとしなかった文学史家の怠慢を覆いかくすことになろう)。階級的であると同時に民族的でありうるのは、ただ英雄時代の叙事詩的英雄のみである。わが国の古代貴族の文学は散文的英雄と浪漫的英雄を形成し得たが、叙事詩的英雄は、若干の断片的歌謡にかすかにその存在を記録したのみで、ついに物語として創造し得なかった。この文学における叙事詩的英雄の貧困ほど日本の古代貴族の運命を象徴する事実はない。それは国家の創造、列島の統一において英雄的役割を果たした古代貴族階級が、五、六世紀におけるその内部の激しい対立争闘を通してついに皇室に隷属するにいたった結果を――その争闘はいかに激しいものではあっても叙事詩的な何ものもなく、矮小で俗悪で散文的な過程であった――、すなわち古代貴族の努力の達成を皇室が収穫してしまった事実を語るものであり、古代貴族がその独立性と主体性を喪失して、皇室の祖先と系譜的血縁的につながること、天皇制的な神々の系統樹の一枝であるという自己ぎまんの中にみずからの存在価値と無上の誇りとを見出そうとしたその堕落を告白するものである。ヘーゲルは叙事詩の歴史を民族精神の画廊eine Gallerie der Volksgeister であるといったが(Ⅲ.333)、日本古代文学におけるさまざまな英雄類型の系列、すなわち歌謡群の主体としての叙事詩的英雄と神武天皇および日本武尊にそれぞれ形象化された散文的英雄と浪漫的英雄との三つの英雄類型の系列と対立もまた古代貴族精神の歴史と運命の画廊であるといえよう。
このカオスのような文章に含まれる論理力と構想力をもって石母田は倭国神話の体系を英雄および英雄神の神話から解こうとしたのである。私は、このような石母田の志向そのものが無意味であったとは思わない。
しかし、これには根本的に賛成できない。何よりも問題なのは、上記の文章のうちの傍点部分であって、散文的英雄・詩的英雄とことさらに区別して英雄時代の叙事詩的英雄を国民的民族的英雄のごとく語ることには国家主義(nationalism)に片寄ったものになりかねない。私は民族(esnisity)というものは、現実に一つの公共圏として存在するものであると考えるが、それは職能・地域・性別・年齢などに根拠を社会の集団編成の多様性を前提としたものでなければならず、そのすべてを代表する「国民的民族的英雄」などというものが存在するということ自体が「一つの誤った態度」であると考える。
「英雄」というものがさまざまな形とニュアンスで存在しうることは事実である。しかし、「国民的民族的英雄」というものを実態として設定し、「英雄時代」を設定することには賛同できない。そして、叙事詩的英雄の文学的形象の存在もしくは非存在を、その民族の歴史の価値評価の基準とするかのような石母田の論調には強い違和感をもつ。私は『美学』を読んではいないが、「すべての偉大にして顕著な民族は彼の本来的精神を表現するところの最初の書物をもっている」(九頁)というヘーゲルの英雄物語についての記述を肯定的に引用していることも了解できない。ヘーゲルの論理に依拠して相当の勢いで書いた「若書き」であることが想定される以上、これはやむをえないことかも知れないが、「英雄時代の王はあくまで彼の支配する世界といきいきした統一と連関をたもっている」「この時代にあっては人民の支配者たる王族のみが独立自由の個性たりえた」(一四頁)などという記述は無意味なヘーゲル主義である。石母田が、ここで「国家の統一、列島の統一」を無前提に意味のあるものとしており、「国家の形成という困難で壮大な仕事」(二三頁)などという国家幻想に類する用語を使用し、記紀の原形が成立する以前の倭国、「四・五世紀の時代がうつぼつたる英気をはらんでいた」(六〇頁)などとすることにも強い違和感がある。
もちろん、石母田は英雄時代を国家の形成の時代と位置づけ、それはすでに根本的には階級社会として規定されることなどとしている(一八頁)。しかし、石母田は、その「英雄時代」の変化の方向を英雄的なものと停滞的カースト的なものの矛盾(四八、八九頁)という形で設定した。それは英雄的なものをギリシャ的なもの、カースト的なものをアジア的なものとする二元論であって、結局、カースト的なものが全体を押さえるというのが石母田の図式である。これはほとんどヘーゲル歴史哲学そのままの図式であって、そのままではとても歴史学的な仮説ということはできない種類のものである。石母田の議論には根本的な問題があったといわざるをえない。これはカースト論をどう考えるかとは別個の問題である。
こうして神話とナショナルなもの、そして形成期の国家をどう考えるかなどの問題を中心とした英雄時代論争は、最初から稔りないものとして運命づけられていたというほかないであろう。もちろん、列島における国家形成をどのように捉えるか、そこにおける族長(首長)と共同体の関係をどのように段階的に捉えるかなど、大きくみれば現在でも確定していないような論争自体に意味がないという訳ではない。しかし、率直にいって、これは当時の研究段階では議論条件がなく、解くことは不可能な問題であったといわざるをえないと思う。
B石母田のイワレヒコ論とヤマトタケル論の限界
(1)イワレヒコと久米歌――益田勝実の見解
もちろん、この論争が無意義であったというのではない。神話史観=皇国史観を批判し、その上で、神話とは何かについて歴史学的な検討の道をつけていこうという志向は歴史学界共通の問題意識であったはずであり、歴史科学協議会の編集した『歴史科学大系』第一巻(校倉書房、一九七二年)の第三部「英雄時代論」をみると、それを意識した研究者が、独特な熱意をもって議論に参加した様子がみえる。
しかし、神話論という観点からみると、みるべき内容は、結局、北山茂夫が一九五三年に発表した論文「日本における英雄時代の問題によせて」のみであったといえるだろう。北山は、石母田が英雄叙事詩の断片とした『古事記』のイワレヒコの大和攻略の物語に載せられた「久米歌」について、その成立は石母田のいう四・五世紀の「英雄時代」ではなく、六世紀以降のものであろうと論じたのである。北山は、この久米歌は「デスポット的性格を強めつつあった段階の、倭宮廷に従属した部集団の活気にみちた雰囲気をとらえて歌われ、しかも宮廷歌舞に様式化されたものだ」と論じたのである(『日本文化の起源2』、平凡社)。しかし、石母田が、「デスポット的性格」をもつ「倭宮廷に従属した部集団」が「活気にみちた雰囲気」をもっていることをどう捉えるのかと反問したのみで議論は終わってしまった(「英雄時代の問題の所在について」『石母田正著作集』一〇巻)。端的にいえば、石母田は自分の提出した問題は、高木市之助『吉野の鮎』が描いた問題であって、それ自体は学史の上で確実なものである。問題をそこにもどって検討してほしいと一種の退却を行ったのである。
石母田自身は、一九五三年に『世界歴史事典』(河出書房)に「日本神話」という大項目を執筆し、神話論研究を本格的に開始し、一九五七年には「はじめに」で岡本太郎の証言との関係でふれた出雲神話論、オホナムチ論を用意するにいたった。そのなかで石母田は、「英雄時代」論文で考えたことを執拗に考え続けていたはずであるが、表面的には、石母田の「英雄時代」論文は忘れ去られていたようにみえるのである。
しかし、石母田のカオスのような構想力と論理、そして、石母田が神話論に取り組む情熱と問題意識がまったく受けとめられずに無意味に終わったという訳ではなかった。私は、それを示すのは、益田勝実が、やく二〇年後、一九七二年に発表した著作『記紀歌謡』であろうと思う。益田は高木、石母田、北山が問題にした久米歌の中には「むしろ古代王権から古代律令国家へのプロセスの中で、氏族という枠の中で、その枠の範囲に限られながら、デスポティズムに押さえ込まれ果ててないものが生きつづけていたことを認めてもよいのではないか」「そういう一種の前代の残留といえばいえるうたの生存までもありえないとするのは、どうだろう。ある時点まで、久米部を率いる久米直のような氏族的結合が、野性的な人間の自由さを温存しえていた段階があり、それが氏族のうたに結晶している」と述べたことによることができるだろう。益田は、久米歌を「英雄時代の歌の断片」というよりも八世紀になっても野性的な氏族の歌として生きていたというのである(『益田勝実の仕事』3,記紀歌謡、三一二頁)。
この益田の意見は明らかに北山の意見よりも石母田の側に近いが、石母田とも異なっていて、久米歌自体には英雄の形象をみとめない。「生活のにおいがプンプンとし、出陣祝いの酒の肴の韮や椒のイメージもちらつき、なにか原始戦闘的な気魄が立ちこめている」とするように、久米歌は集団の歌そのものであるというのである。なお、ここで益田が「厳々し 久米の子らが 粟生には 韮一本 其根が本 其根芽繋ぎて 撃ちてし止まむ」「厳々し 久米の子らが 垣下に 植ゑし椒 口疼く 我は忘れじ 撃ちてし止まむ」という久米歌について「酒の肴の韮や椒のイメージ」と述べているのは興味深い。たとえば後者については、普通、「垣のもとに植えたハジカミは口の中でひりひりする(それと同様、敵の攻撃は手痛かった)のを俺たちは忘れていない」などと解釈される(『古事記』思想大系本)。しかし、益田に従えば、この部分は「みんなで食べた椒の味の鋭さを忘れないぞ、みんなでやっつけよう」というように、単純に共食の経験を想起したものと解釈すべきであろう。ここでは共食の経験が想起されているのであって、敵は目の前にいるだけである。この歌自体では、「我」はあくまでも集団のなかの「我」なのである。さらに益田は「これらは、大葬のような宮廷儀礼に用いられるうたであり、久米部という氏族の歌である。『古事記』は楽府が吸収した久米歌全体を神武の創業伝承に結びつけようとするが、わずか八年後の『書紀』は、現存の久米部のうたがみな神武の伝承の中で育ってきたものとは認めない、という姿勢を取る」とも述べている。
これは久米歌を詳しく検討したネリー・ナウマン『久米歌と久米』(言叢社)においてもほぼ同様である。ナウマンは、これらの歌を山間に粟の焼き畑を営み栽培し、狩猟・採集を生業とする久米の人々にふさわしいものであるとし、その戦闘性についてもかならずしも職務的に軍事的なものではない。高木・石母田が強調した『我』には族長を窺わせたり、命令者の役割が付与されているような記述は確認できないという(一九頁)。とくにナウマンが、久米歌の継受された場として宇陀郡における?歌の存在を示唆していることは重要であろう。そこに原始的な戦い、共同体的な闘いの記憶が反映しているにしても、それは?歌の場で伝承されたものであるということになれば、それ自身に英雄叙事詩を読みとることはいよいよ困難である**1。
ようするに益田とナウマンは、久米歌が神武=イワレヒコ伝承と結びつけられるのは後次的な現象あるいは別のレヴェルで考慮されるべき現象であって、その意味では、これを英雄叙事詩とする高木・石母田の議論には賛同していないのである。
(2)イワレヒコのタカミムスヒ祭祀
益田勝実『記紀歌謡』と石母田が英雄時代論に立ち戻るという宣言をした『古代国家論第二部』の刊行は同じ一九七三年であったから、状況によっては、英雄時代論争が振り出しにもどって復活することになったかもしれない。もちろん、前述のように、この年、石母田が発病したことによって、石母田が何を考えていたかは明らかにされることはなくなった。
しかし、このような経過からすると、議論は、久目歌を素材として、『古事記』『日本書紀』の神武=イワレヒコの物語を叙事詩的英雄とすることができないという益田とナウマンの結論から新たに出発することにならざるをえないであろう。つまり、石母田が「叙事詩的英雄」と分類したイワレヒコの大和侵攻の物語と久米歌の二つの史料は分離して扱わざるをえないことになるだろう。つまり、イワレヒコの大和侵攻の物語自体を「英雄」神話として、どのようにみるかを問わざるをえないことになるのである。
そもそも、『日本書紀』ではこのイワレヒコのヤマト侵攻の物語の中心は高皇産靈尊=タカミムスヒを祭って粥を「厳瓮」と「八十平瓮」なるものを使って炊く祭祀である。このタカミムスヒという神は大王の祖先神であるが、その実態が雷神であることは『歴史のなかの大地動乱』で論じた通りである。イワレヒコの部隊は、この粥を食べて出陣した。「神風の伊勢の海」とはじまる「うちてしやまむ」の久米歌は、『日本書紀』の文脈のなかでは、この共食の儀礼のなかで歌われたものであるといってよい。歌謡の中身と共食の祭礼の意味そのものは区別しなければならないのである。
そこで、このタカミムスヒを祭る祭祀について詳しく説明すると、イワレヒコは、特別な「埴」を準備して、それによって「八十平瓮」と「厳瓮」を作って神霊を呼び降ろし、勝利の預言をえた。その後に、イワレヒコは、その神の威力を自分の身につけるため、「丹生川の川上の五百箇の真坂樹」を抜いてきて、準備した埴瓮をセットした上で、自分がタカミムスヒに扮し、副将の道臣命に「嚴媛の號」をあたえて「齋主」に任命した。「嚴媛の號」というのがたんに名前だけのことであったとは思われない。道臣命は久米部の主とされる大伴氏の祖神であるが、道臣命は、実際に女装をし、巫女となって、物忌みのなかで神懸かったイワレヒコに奉仕したのである。
益田は、このような男が男に女装をさせて自己を祭らせる「神ー齋主」の関係をサルのマウンティングにたとえて絶対的服従の儀式であるとしている(益田「日本の神話的想像力」『益田勝実の仕事4』筑摩書房)。石母田は、前述のように散文的英雄としてのイワレヒコが従者を絶対的に従える主人であったとするが、ここではそれが呪術宗教によって媒介されていることを問題としなければならない。このような王=英雄を叙事詩的英雄ということはできないことは明らかである。むしろ、石母田が後にオホクニヌシについてking-magicianという言葉を使って、王=族長の呪師的側面を指摘しているように(一九九頁)、このような存在は呪術的英雄、シャーマニックな英雄というべきであろう。ここではタカミムスヒ祭祀を行うシャーマンking-magicianは運命に耐える意力と苦悩を起動力とするというような叙事詩的英雄ではない。また彼と配下の軍勢の関係は、集団に対して戦闘を呼びかける強盛な英雄的個人などというものでもないのである。それ故に、イワレヒコのタカミムスヒを祀る戦闘儀礼と久米歌は内容的に連関して社会集団の代表と構成員を生き生きと結ぶというようなものではなく、両者の関係はそれ自体としては偶然、無関係といわざるをえないのである。
以上のように、石母田のいう叙事詩的英雄の存在は否定される。その姿はいわばシャーマニックな英雄が配下の共同体を指揮するシャーマン軍ともいうべきものとなるのである。
(3)ヤマトタケルは浪漫的英雄か?
次の問題は、石母田が、この論文の第四節「古代文学における英雄物語について」において提出した浪漫的英雄なるものをどう考えるかということである。私は、もちろん、石母田が日本武尊、ヤマトタケルの物語を「英雄」の物語として分析したこと自体に大きな意味があると考える。しかし、それをヘーゲルにしたがって浪漫的英雄とすることに特段の意味があるとは思えない。
石母田がヤマトタケルの物語を分析対象に選んだ理由は、それを『古事記』と『日本書紀』の文学的な相違をもっとも明瞭に示す物語として位置づけたためである。まず、これが石母田の津田批判の趣旨に直結していることを確認しておきたい。それはこの論文の結語に次のようにある通りである。
「津田博士の業績をみる場合に大切なことは、(中略)、たとえば小論の主題の一つとなった日本武尊の物語についての研究を見るならば、それは主としてこの物語が歴史的事実でなかったこと、国家の組織が確立された後の後世的な産物であることを証明することに全力を集中されているのであって、記紀のあいだに見られる微細であるが重要な相違はそのディテイルにいたるまで追求されず(されてもその意義が深く考えられず)、したがって歴史的事実であることを否定された後のたんなる物語としての歴史学的評価はほとんど果たされていないのを見るであろう」(八五頁)。
石母田が「われわれは『書紀』から『古事記』を類推したり、『書紀』を通して『古事記』を読んではならない。『古事記』の物語はそれ自体独立した芸術的世界として理解しなければならない」(七三頁)と強調した趣旨が、ここに明瞭になる。それは『古事記』をもっぱら文学作品として読むという趣旨ではなく、その歴史学的評価のためにこそ、それが必要だという趣旨なのである。
さて、石母田は『日本書紀』ではタケルの物語は景行天皇の西征物語の延長として語られており、タケルの人格は天皇の代理、分身としてきわめて抽象的に描かれている。これに対して『古事記』では乱暴にして剛勇、独立的で激情の人物として描かれており、クマソを打った後に東国行きを命じられたタケルが「天皇はやく吾を死ねとや思ほすらむ」と憂い泣いたという、一種の悲劇性ももっているという。
もちろん、石母田は『古事記』のヤマトタケル物語について「ただあまりに俗悪的散文的である世界においてのみ珠玉のように見えるのであって、文学的価値から見て過大に評価することはゆるされない」(八九頁)と冷静な評価をしている。石母田は、そもそもヤマトタケルを叙事詩的英雄とは評価しない。『古事記』ではタケルは「軍衆を賜はずて」東国征討に出発したとされており、タケルの行動は叙事詩的英雄にとって必須の社会的行動、集団が巻き込まれる歴史的運命のなかでの苦闘という要素を欠いている。クマソ討伐は一つの英雄征討譚としての文学性をもっているが、タケルは東国行においては孤立した勇士であって、ヤマトタケルの物語は前半と後半で分裂していて文学的な完成度は低いのである。そのためにタケルの英雄的性格は、叙事詩的英雄としての強さをもたず、いちじるしく主観的内面的な傾向をとっており、この点でタケルは浪漫的英雄というのがふさわしいというのが結論である。
しかし、文学的表現は別として、ヤマトタケルの英雄像があらゆる社会集団からはなれ、政治的世界から追放された孤立した勇士として主情的・浪漫的英雄として描かれているというのは無理な枠づけであろう。現実には、ヤマトタケルは個人として浮浪したのではなく軍隊の指揮をとる存在であったというのは、物語の前提とされていたはずである。
(4)ヤマトタケルの遍歴と神々との戦い
むしろ重要なのは、このような限界のなかにありながら、石母田が、ヤマトタケル物語の後半の東征の物語を遍歴の英雄が神々と闘う物語と規定し、ヤマトタケルが東国の神々を言向け平らげたという物語は、各地域の族長が自然を開発し、「自然=神々に対置されうる資格ある」「英雄」として登場する姿を代表していたとしたことである。石母田は「川、森、山、海、険阻な坂道、いたるところに住んでいたこれらの神々は古代人にとって現実に存在し生きていた実在であった」「尊の遍歴はこれらの神々との闘争にほかならなかったのであ」るという(七九頁)。
そして、『常陸国風土記』(行方郡)に登場する族長箭括氏麻多智=ヤハズノウヂマタチの谷地の開墾神話を族長的な開発行為の典型として位置づけたのである。このヤハズノウジマタチは行方郡の豪族であって、西の谷の葦原を開発しようとしたところ、蛇体の「夜戸の神」が群集してきたので、堺の杖を立てて、神の地と人の地を分離したという人物である。河音能平がこの開墾神話に注目して七世紀から一〇世紀への社会・自然・神々の関係を描き出すキーに使ったことはよく知られているが(『河音能平著作集2』)、それを最初に指摘したのは石母田であった。
石母田はこれらの神々を「’まつろはぬ者ども’、皇威に服しない賊、かかる政治的なものの神格化ではない」(七九頁)と述べる。もちろん、その背景には社会的な集団がいたとしても、それ自体は自然=神と考えなければならないというのである。そしてそれとの闘いの手段は呪術によるほかない。実際、石母田は、「(ヤハズノウヂマタチが)開墾した耕地の周りに杭をたて堺の堀をさだめて神々の支配する区域を特別に設け、彼らが征服しようとした神々を祭壇に祀ることによってこの妥協を調和させようとしたのである。神々の征服者は神々の創造者に転化する」(八〇頁)と述べている。私は、ヤハズノウジマタチの「堺の杖」は、ヤマトタケルが杖を衝いて歩いたという伝承によって「杖衝坂」といった(『古事記』)というのも同じような呪術観念を示すものだと思う。そう考えれば、弟橘比売が「菅畳八重、皮畳八重、?畳八重」を波の上に敷いて身を投げたというのも、出雲の青柴垣神事と同じような呪術、あるいは人身御供の呪術を感じさせる。
これは益田勝実も示唆するところであるが、さらに益田は焼津の地で火攻めをうけたヤマトタケルが草薙と向かい火をもって反攻したことを合理的な知恵とし、「呪術もまたその知恵のある段階での現れである」とする。そして、ヤマトタケルによるクマソタケルやイズモタケルのだまし討ちも、そのような意味での知謀と考えるべきであるとする(「王と子」『火山列島の思想』)。ヤマトタケルは「人々が何よりも知謀を尊敬していた時代」「人間の知恵というものの力に対する強烈なあこがれが燃えていた世界」における知謀をも兼ね備えた英雄として描かれているという訳である(参照、保立『かぐや姫と王権神話』洋泉社、一一六頁)。このように考えれば、ヤマトタケル物語の前半はヤマトタケルの知謀、後半は呪術に重点をおいて書かれており、両者を通じていえば、ヤマトタケルを知謀に満ち、呪術にすぐれた神のごとき勇者というイメージで統合的に捉えられることになる。
そもそもヤマトタケルは物語の前半でクマソを討伐した後も、「山の神・河の神と穴戸神と、みな言向け和し」て上り、東国征討においても、同じように「言向け和平したまひき」という。この「言向け和平」そのものが呪術的なものを含意していた可能性は高い。イワレヒコと同様に、ヤマトタケルもking-magician、呪術的、シャーマニックな英雄としての要素をもっていたのであって、イワレヒコと違うのは、彼が遍歴するking-magicianであり、その闘いの対象が自然、あるいは自然的神格として描かれていることにあったのである。
これは最近、平川南『律令国郡制の実像』がヤマトタケルの神話的遍歴譚の背後に七道や国堺の確定の事業を想定していることとも関係してくる。平川によれば、四世紀中葉の東日本各地にみられる前方後方墳から前方後円墳への転換はヤマト政権が東北地方にまで侵入していったことにともない、東国の重要性が増大した結果であり、ヤマトタケル物語に描かれたルートは、この時期の古東海道、古東山道ルートの形成を反映したものとみることができる。ヤマトタケル物語における甲斐酒折宮の伝承が重要で、甲斐国は「交ひ」の国として、飛騨・美作などと同じ、七道の結節国という位置をもつ。これは道制の成立とヤマトタケル物語の関係を示すものとすることができる。そして「足柄坂」「碓日坂」「科野之坂」などで祭祀が行われたことは国堺の設定を意味し、それらはさらに北東の蝦夷世界を明瞭に位置づけたことにも全体として関係している。ヤマトタケルの蝦夷ルートが海路であることも蝦夷侵入における紀伊水軍の動員という事実と関わっている可能性があるという。ヤマトタケルの神話的英雄としての姿は、国家的な交通路の組織が神話意識に反映したものであるということになる。
石母田は、「神々との困苦な闘争を体験してきた古代人は尊のような英雄を彼らの内部からも創造せざるをえないのであって、清水や井戸や池堤が中央から遍歴してきた一人の素晴らしい英雄によってはじめてひらかれたという伝説は地方人の心にも素直にうけとられたのであろう」(八一頁)と述べる。最近、坂江渉も論文「『風土記』の「荒ぶる神」の鎮祭伝承」(『出雲古代史研究』二五号、二〇一五年)で、坂をめぐる境界祭祀の事例を総覧し、「荒ぶる神」の鎮祭伝承の背後に中央派遣に由来する諸集団の存在を摘出して、王権や広域権力による地域編成の在り方を論じたが、このような地盤の上にヤマトタケル物語が展開したことは明らかであろう。
ここには、族長や共同体の領域を超えた交通網を背景とした国土に対する高権が、神話的なイデオロギーという形をとって登場しつつある様子をみることができるのである。交通形態の中に組織された自然神話の列島規模での象徴化ということもできようか。石母田はすでに『中世的世界の形成』において、「国家の領土高権」について「大化前代の族長の荒蕪地にたいする所有権は、村落民の入会地用益権を排除するものではないことは族長的支配関係の特質から考えて当然であるが、律令制国家は大化前代のかかる関係を廃棄せず、国家の土地一般に対する権利として普遍化した」と述べている(第一章藤原実遠)。この「古代貴族の英雄時代」は、そこまでは論及していないが、石母田が、ヤマトタケル物語を、この視野のなかで考えていたことは明らかであろう。
C前方後円墳論と英雄時代論争
(1)王権祭祀と前方後円墳
以上のように、イワレヒコ神話は軍事指揮をとる呪術的な英雄、ヤマトタケル神話は自然を征服する遍歴する呪術的な英雄を描いたものであった。この二つの神話のなかには相似した呪術世界を見通すことが必要なのである。このように考えると、石母田の「英雄」が土俗の呪術世界から離脱したあまりに概念的なもので、叙事詩的英雄あるいは浪漫的英雄などの説明が事態の中心をとらえていないことが明らかとなる。
さて、石母田はあまりに概念的な説明を補うために前方後円墳には「英雄」が葬られたとし、前方後円墳について次のように説明する。「山麓にうずくまっている原始人の臆病さを破って、河川の氾濫する広い平野をよく開墾し、人間の世界を未知の世界にまで広げた英雄たちが、これらの古墳に葬られている」(四〇頁)というのである。石母田は古墳が族長たちの「独立不羈」な性格をよく示し、また副葬品に「日常の生活や生産に必要な道具」が含まれていることをとって、「日常的な器具を大切にすることは働くものの特質である。死後にいたるまで鍬や斧や鑿や紡錘車とともにおることを欲した古代の族長たちは、これらの道具が現実につかわれている社会、その気風や慣習や道徳の全体的な世界のなかでまだ生々と呼吸しているのである」とまで述べている(四〇~四一頁。なお四八頁も参照)。
この前方後円墳論は、あまりに牧歌的なものといわざるをえない。石母田の議論はここから徹底的に検討していく必要があるが、まず注意したいのは、先にふれた『日本書紀』のイワレヒコの大和侵攻神話において描かれたタカミムスヒ祭祀が古墳祭祀と同じ本質をもっていた可能性である。
つまり、イワレヒコは、そこで「八十平瓮」と「厳瓮」を作って神霊を呼び降ろし、「嚴媛」を「齋主」として物忌を行ったのであるが、この「厳瓮」と「八十平瓮」は、形成期の前方後円墳の周囲に設置されるに「特殊壺・特殊器台」と同じものと考えられるのである。まず「八十平瓮」については、『神宮雑例集』(二、天平賀事、『群書類従』第一輯巻四)に、一一二一年(保安二)に伊勢神宮正殿の床下にあった「天平賀十九口」が「倒れ臥し」、「三口」が「居ながら破損」しているのが発見されたという事件が記録されている。「烏の所為か」と疑われているが、「倒れ伏す」といわれている以上、平瓮がある程度の高さをもっていて、倒れることがあるものであるということを示している。また『釈日本紀』(巻九)に「供神物を盛るの土器なり。今の世、伊勢太神宮の御殿の下に多くもって安置す。或説、諸神参候の神座云々」とあるのも参考になるだろう。「座」という以上、ある程度の高さがあって上端部が平なものであろう。本居宣長は、『釈日本紀』の「神座」という説について「心得ぬことなり。後の附会なるべし」とするが、『神宮雑例集』の記事とあわせると、それなりに理解できるように思う。『神宮雑例集』や『釈日本紀』は後の史料ではあるが、平瓮が器台を意味することは揺るがないだろう。
これに対して「厳瓮」は普通の「瓮」であろう。参考になるのは、次ぎの『万葉集』に残された大伴坂上郎女が十一月の氏神祭りにあたって作った歌である。
ひさかたの 天の原より 生れ来たる 神の命 奥山の 賢木の枝に 白香つけ 木綿とり付けて 齋瓮を 齋ひ穿り居ゑ 竹珠を 繁に貫き垂り 鹿猪じもの 膝折り伏せて 手弱女の おすひ取り懸け かくだにも われは祈ひなむ 君に逢はじかも (『万葉集』巻三、三七九番)
この『万葉集』の「齋瓮」と『日本書紀』の厳瓮が同じものであることは明らかである。『日本書紀』のイワレヒコによる祭祀が「これより始めて厳瓮の置物あり」と厳瓮の由来を説くという形をとっているのも、厳瓮なるものが、八世紀になっても何らかの形で継続していたことを意味している。それがまさにこの齋瓮なのではないだろうか。齋瓮の祭りにあたって、「奥山の賢木の枝に白香つけ木綿とり付けて」と榊が使われることも一致している。
岡田精司は、この『万葉集』の齋瓮について「古い形式の古墳では埴輪の原型にあたるものとして、壺を並べている例がある」としている(『神社の古代史』大阪書籍、一九八五年、一五六頁)。岡田も『万葉集』の齋瓮の祭祀、つまり『日本書紀』のいうタカミムスヒの「厳瓮」の祭祀と同じものが古墳祭祀の根本にすわっているといっていることになる。このことは古墳における「壺」というものの位置を根本的に考え直す必要を示唆する。すでに本書第■章でも論じたように、前方後円墳の形は、巨大な壺・瓮を横に伏せて、半ばまでが土に埋まった様子そのものである。三品彰英が「前方後円という異形の高塚古墳も巨大な一つの『壺』であり、またその石室の周囲に死者の御霊を護るがごとくに埋めてあるのも、これまた『壺』であります」と述べたことは、結局、正しかったのである(三品「前方後円墳」『三品彰英論文集』第五巻)。この仮説は山尾幸久がその立場をとるとして以来、文献史学の側でも無視できないものとなった(『古代王権の原像』学生社、二〇〇三年)。
もとより、この「前方後円墳=壺型墳説」が本当に成立するかどうかは、今後の考古学界を中心とした議論によって決せられるほかないのであるが、それがイワレヒコ神話の評価に直結する問題であることを銘記しておきたいと思う。いずれにせよ、神話時代における族長層が共通して営んだ古墳は、シャーマンとしてのイワレヒコのイメージに示されるような土俗的な神権制にもとづいていたのであって、叙事詩的英雄にせよ、浪漫的英雄にせよ、石母田のいう英雄とは大きく異なる世界のなかにあったのである。
(2)前方後円墳と骨カルト
これに関わるのが、西嶋定生の前方後円墳論である。西嶋は中国史家として前方後円墳という葬送の制度、葬制においてもっとも特徴的なことは、それが「殯によって骨肉を分離し骨のみを葬る」ものであったことにあるとした(「古墳と大和政権」、歴史科学協議会編『歴史科学大系』3所収、原論文『岡山史学』発表、一九六一年)。
西嶋は前方後円墳に一種の「骨」崇拝をみたのである。中国では、このような「骨」崇拝は存在しないから、西嶋の着目は当然のことであったといえよう。西嶋がそのおもな根拠としたのは、上毛野(現群馬県)の国造の始まりを示す『国造本紀』の記事に、古墳時代(と仮託された時代)に、大王崇神の子ども豊城命の孫にあたる彦狭島命という人物が東方十二国を支配したとあることであった。これに対応する記事が『日本書紀』(景行五十五年条)にあって、それによると彦狭島王は実は東国に赴任しなかったという。そもそも祖父の豊城命は大王崇神から東国統治を命じられており、彦狭島王は、その血統をうけて東国の支配を命ぜられたのであるが、赴任の前に大和国で死去してしまった。それを知った東国の百姓たちは、王がやってこないことを悲しみ、ひそかに王の「尸(かばね)」を盗んで上野国に埋葬した。この尸=遺骸は古墳に埋葬され、こうして彦狭島王は上野国の国造家の始祖として神格化されたというわけである。
西嶋は、国造家のような地方氏族が王家との同族関係の象徴として聖なる骨を身分標識のように扱っていることに注目したのである。人々が、他所にある墓を暴いて、そこに納められた「尸」を盗んで自分たちの土地に埋葬するなどというのは、いわば骨カルトというべきものである。「骨」あるいは「遺骸」の現物の衝撃力は強い。その人物が尊貴な身分にあった場合や強い威力をもっているとされた場合には、その全身骨格が、その人物の存在を代表するものとして特殊視されたということは理解できるように思う。こういう考え方からいくと、古墳の末期形態を示すという群集墳などはいわば骨カルトの在地社会への広がりということになる**2。
このような骨カルトの存在を示唆する史料はほかにもある。たとえば、『播磨国風土記』には•Ê(‚킯‚Ì)別(わけの)ì(‚¢‚ç‚‚ß)嬢(いらつめ)が城宮で死去したのち、河を隔てて「日岡」という場所に墓を作ったとある。ところが「その尸を挙げて印南川を度るとき、大き飄、川下より来て、その尸を川中に纏きいれき」という。これは神が骨を動かすという奇跡を語るのであろう。また、飄が尸を運ぶ話しは『日本書紀』天和歌彦にもある。旋風が尸を巻き上げて天に運ぶというのは、死者の魂魄が骨となって昇天する幻想を示すのであろう。
また同じような話は、ヤマトタケルの神話のなかにも知ることができる。つまり、伊吹山で負傷したヤマトタケルは伊勢国能褒野で死去し、そこに陵墓を作って埋葬された。しかし、ヤマトタケルの魂魄は、そこから白鳥となって飛び立ち、大和・河内に舞い降りたため、そこにまた陵墓を作ったが、白鳥はそこにもとどまらずに天に去った。これがヤマトタケルが三つの白鳥陵をもつ由来であるが、人々が最初の能褒野陵のヒツギを開いたところ、そこには衣のみがあって「屍骨」は存在しなかったという。つまり屍骨は白鳥になって飛び立ったという訳である。おそらく要点は、そこに腐敗にまかされる遺体はなかったということなのであろうが、白骨化は霊魂の解放と精霊化の前提であると考えられていたのであろう。
八世紀後半の骨壺に人間の骨とともに白鳥の翼の指骨が入っているのが発見されたことがあるが(佐倉市の高岡新山遺跡出土、二〇一一年二月一八日朝日新聞夕刊「魂をはこぶ白鳥の骨」)、これは骨が白鳥のようになって遊飛するという幻想が奈良時代まで残っていたことを示すのであろう。白鳥の白さは骨の白さに対応しているのではないだろうか。
(3)前方後円墳と「屍=骨=カバネ」身分
さらに重大であったのは、西嶋が人々の族姓身分を表示する「姓=カバネ」という言葉の原義は、「屍=骨=カバネ」にあったと主張したことである。もちろん、このこと自体は、西嶋も引用している幕末の国学者の著作「大勢三転考」などにも記され、栗田寛「氏族考」、柳田国男「葬送の沿革について」『定本柳田国男集』一五巻、筑摩書房)**3、中田薫「可婆根(姓)考」などによって繰り返し言及されていたことである。しかし、西嶋が右のような史料にも依拠しつつ問題を古墳論として展開したことは画期的な意味をもっていた。
西嶋は古墳時代に列島のほとんどにひろがった古墳のネットワークを、いわば「骨」のネットワークであるとみたのである。そこでは「姓=カバネ」が「同族関係の象徴的表現としての骨と同語となっている」ということになる。古墳時代は骨が身分をもつ社会であり、古墳に葬られた大王・王族・首長たちの骨は、彼らの身分を表現する。『日本書紀』持統五年八月条には、諸氏族に「その先祖の墓記」を進上させたとあるから、墓が身分の表現であったことは疑いない。それはヤマト王権の国家的な身分秩序としてのカバネの制度を表現している。そして、全国にたくさんある古墳の墳形や規模は、古墳に内蔵された骨の身分を外に表現したものであって、それは古墳時代の国家と社会の秩序を表現する可能性があるということになる。
この西嶋の指摘は、考古学界に大きな影響を及ぼした**4。しかし、石母田は「古墳のもつ重要な機能の一つが何らかの身分秩序の表現である」ことを一応は承認しながら、「私は古墳をカバネという身分秩序の表現とみる見解はとらない」「古墳による身分秩序の表現はカバネのそれに先行する」として、古墳は、「古墳の形式と立地条件という可視的で、即物的な標識」による身分秩序の表現であるところに特徴があり、それと比較して、カバネはより観念的・制度的な新しい身分秩序の表現であると述べたのである(『日本の古代国家』著作集3、三〇二頁)。西嶋の文章に誤解を呼ぶ部分があり、この石母田の批判は穏当なもののようにみえるが、西嶋も古墳と氏姓制度を区別しないといったのではなく、両者の間に連続性があると主張したのであるから、より慎重に検討するべきであったと思う。そもそも西嶋の主張は古墳の外形や位置は第二次的なもので、骨こそが本質的なものである、その意味では前方後円墳に内在するイデオロギー自体もきわめて「観念的」なものであるという主張を含んでいたから、これは議論のすれ違いであった。
もちろん、石母田が、さらに古墳時代末期の倭国のシステムを「始祖を系譜によって天皇氏に連結し、あるいは神代史の物語によって神話的に統合するという独自の形態」と説明し、そこには「系譜と族姓によって、あるいは神話と説話によって下層から上層にいたるまでが連結されていく擬制的・観念的な連続性」のネットワークが存在したとしたことはてことはさすがに見事な定式化である(『日本の古代国家』著作集3、四〇二頁)。しかし、この定式化は、諸首長が(私の言葉でいえば)「骨カルト」というべきイデオロギーを共有しているのではないかという西嶋の主張の基本点を無視している。西嶋のような観点に立つことによって、前方後円墳の広域的なネットワークはそのまま統一国家の存在を示すのではなく、それはまずは特定の神話やイデオロギーの共有を示すという捉え方が可能になったはずなのではないか。
私は、この石母田の見解は、石母田が栗田・柳田・中田などの見解を伝統的学説として軽視したためであり**5、また石母田が前方後円墳を「原始人の臆病さ」を破る「英雄」にふさわしいものとみる感じ方を脱却できなかったためではないかと考える。今となっては詳細はわからないことであるが、私は、西嶋・石母田と深い関係をもちながら研究を進めた近藤義郎が前方後円墳を「原始共産制」にひきつけて理解するようになったのは、実際上、石母田の意見に導かれたものではないかと想像する。
問題は、この批判によって、西嶋が自説を撤回してしまったことにあった。石母田が本格的に問題に立ち戻ることができれば事態は異なっていたであろうが、この問題についての論争も不発に終わったのである。こういうことがなければ、「始祖を系譜によって天皇氏に連結し、あるいは神代史の物語によって神話的に統合する」という石母田の見解にそって、より具体的な議論が進展し、「神話→系譜→古墳」という形で神話イデオロギーの物質的基礎を論ずることが早くから可能になっていたかもしれない。
『新撰姓氏録』の序文は「ウジカバネ」を「氏骨」と表記しているというのは早くから指摘されていることであるが、それに対応する大量の氏族神話が存在したはずであろう。たとえば、倭国神話の最高神であるタカミムスヒは大国主命の国造りを助けるためにやってきた少彦名命について、「この子は少し憎らしい感じのこどもで、いうことをきかず暴れて、私の指の間から地上に落ちていってしまった子だ」といったという。興味深いのは、その時、「わが産みし児、すべて一千五百座あり」といったということで、ようするに、倭国のほとんどの神が、天神も地神もすべてタカミムスヒの子どもだったというのである(『日本書紀』(神代第八段一書第六)。全国で五〇〇〇を越えるといわれる前方後円(方)墳を考える場合、このタカミムスヒの神統譜を前提としておくことは許されるではないだろうか。さきにふれた彦狭島王の事例が示すように、神聖視された骨を記念する墳墓は、その被葬者が神統譜に参加していることの物的な証拠となったのであろう。
(4)英雄時代論争をどう考えるか
以上が、石母田の「英雄時代」論文の内容と、それが研究史にあたえた影響、そして若干の私見の概略である。
石母田の『歴史と民族の発見』(正・続)と『戦後歴史学の思想』は、この困難な時代における石母田の苦闘を示している。私たちは、石母田が激動期のなかで政治的な間違いにおちいったことを事実として確認しておく必要があると思う。たしかに石母田は学術と政治を厳密に区別していたが、石母田個人において政治的な間違いと学術的な間違いが相互浸透していたことも否定できないと思う。
今後、この時期の石母田の文章は詳細に点検するためにも、ここで、石母田の英雄時代論について、いくつかの問題を述べておきたい。
最大の問題は石母田の民族論の激しい動揺であろう。石母田は、一九四六年の津田批判においては、津田の「歴史に優位する民族の範疇」に対する原則的な批判を行っている。しかし、すでに述べたように「英雄時代」論文では、「英雄時代」の叙事詩的英雄を国民的民族的英雄のごとく語る過剰な民族主義的議論にふみいっている。神話を一つの民族的な文化として受けとめるのは正しいとしても、石母田にとって「英雄時代」論文が転換点であった可能性があると思う。これは明らかに、当時の日本共産党の内部に存在して石母田が親近感をもっていた民族主義的な分派の展開した文化運動から強い影響をうけたものであろう。この頃、若い歴史家たちが「ヤマトタケルを讃える歌」をともに歌ったということを、私は聞いたことがある。
しかし、私は、学術の問題としては、この「英雄時代」論文が遍歴の中で自然的な神々と関わるという英雄像を具体的に示したことを大事だと思う。冒頭に述べたように、日本列島に棲むものにとって神話が何を意味するのかを論ずることは、依然として大きな課題であるとすれば、石母田が、神話のなかに対自然関係をみようとしたことの意味は評価すべきであると考える。石母田はこの論文の「はじめに」で、「人間の原始的創造的な力」の発見を重視すると述べたが、そのベースには対象的自然との規定、被規定の感覚があるはずである。このような「原始」への注目は網野善彦が受け継いで研究を進めたのであって、それを確認しておくことは、この国における第二次世界大戦直後の激動的かつ流動的で困難であった時代の歴史学の学史を考える上で大事なことだと考える。
第二の問題は、この論文に流れているギリシャ的なもの(英雄的なもの)とアジア的なもの(専制的なもの)という二元論をどう考えるかということであろう。前記のように、石母田は英雄時代を国家の形成の時代と位置づけていたが、その運動の様相を、この二元論で説明した。この図式的な枠組が失敗であったことはいうまでもない。
しかし、ここで石母田がアジア的なもの(専制的なもの)としてカーストを論じようとしたこと意味は、そこに何の具体的な成果がなかったとしても、重要であったと思う。ここでカーストというものをどう考えるかという大問題を議論をすることはできないが、私は、西嶋の「屍=骨=カバネ」の議論は、あるいは当時の社会に現実に存在した神話的なカースト的身分制(あるいはその初期的形態)を表現するものとして捉えることができるのではないかと考える。実際、たとえば、ピーター・メトカーフ『死の儀礼』(未来社、原著一九九一年)が示した、インドネシアやマダカスカルにおける死者の「骨」に対して営まれるフェティッシュな儀礼などは前方後円墳における骨の儀礼を考える上で示唆的だからである。石母田は『日本の古代国家』以下の諸論文、そして「古代インドの王権とカースト制」(『石母田正著作集』一三巻)と題された浩瀚な理論メモなどを読めば明らかなように、この後も一貫してカーストという概念を歴史分析に使用することを考え続けた。述べてきたような経過によって、これはいわゆる「古代史」の分野では挫折したままになっており、石母田のカースト論はむしろ黒田俊雄・網野善彦・大山喬平などの平安時代以降を先行する研究者に受け継がれてきた**6。しかし、そろそろ石母田の初心に戻った議論が必要であり、可能であるように考える。
第三は、石母田の文学史の方法にかかわる諸問題である。これが石母田の英雄時代論のキーであったことはいうまでもない。石母田の方法は、叙事詩の英雄的精神と抒情詩の浪漫精神の二元論によって、七・八世紀から一二世紀にたる文学史をとらえようというものであった。石母田はそこでは後者の微温的な抒情詩の心情が支配的であったとしたが、これもヘーゲルの「抒情詩的なるものが浪漫的芸術のいわば原動力的な根本性格をもっている」(『美学』)に依存したものであった。石母田は、結局、「古代貴族」は「頽廃した抒情詩の形式」に囚われ、平安末期における天皇制秩序の解体まで「抒情詩的世界にひたすら沈湎するにいたる」としたのである。
これが、石母田が一九四三年に執筆した「『宇津保物語』についての覚書」(著作集第一一巻)の延長に位置する議論であることはいうまでもない。石母田は、この論文において「漢文学と儒教的強要が身について来るにつれて、抒情詩的精神がかってない深さと広さを獲得して来るという特質的な文学の展開は『万葉集』の成立の基礎的な研究課題をなすものであろう。古代貴族の古典時代ははやくも終わりをつげて、古代世界におけるいわば近代的=浪漫的なものが現れはじめる。『古事記』が神々と闘争する英雄的な巨人を描こうとしながら、それがたえず抒情詩的浪漫的英雄の方へ牽引され、そこに古代人的英雄よりもむしろ初期万葉集的な人間像を見出さざるを得ないということは、『古事記』のこの物語(ヤマトタケルーー筆者注)の作品としての成立が意外に新しかったことを示唆するものである」とさらに論及を広げた。ここで石母田が世界精神を表現するはずの漢文学は、実は退廃的な抒情詩の心情世界に支えられているとしたのは、後に『日本古代国家論 第二部 神話と文学』にまとめられた石母田の漢文学論とそのバックとしての「古代帝国主義」論につらなるものである。
しかし、このような石母田の議論は、当時の段階では文学史の研究と噛み合った問題提起としての意味があったとしても、いわば「ないものねだり」の議論であって、現在ではほとんど意味がなくなっている。重要なのは、益田勝実が英雄時代論争をうけたものと明言して、石母田が弱く頽廃的なものと評価した抒情の位置を復権するという方向を打ち出したことである。つまり益田は「抒情」というものをややもすれば近代的なものと評価する石母田に対して、「『神語』をはじめとする記紀の歌謡の多くのものが、実は、神々や先人のうたに託して、人々がその中で恋し、悶え、悲しみ、恨みした抒情の姿、われわれの近代の個の魂の抒情とは異なる、もう一つの抒情の姿ではないのか」として、そこに和歌に先行する文学世界あるいは物語世界をみようとした(『益田勝実の仕事』3,記紀歌謡、七〇頁)。古橋信孝のいう「神謡」の世界である(古橋『古代歌謡論』冬樹社、一九八一年)。これは記紀歌謡の文学史的評価という側面からいえば、あくまでも神話それ自体の文脈のなかで記紀歌謡を位置づけようとするものであった。益田は、高木以来、記紀の歌謡と説話を分離して考えていき、両者を統合する方法を軽視するという主流的な考え方に対して距離をおいて、神話的想像力全体のなかで問題をみようとしていたのである(『益田勝実の仕事』3,四七七頁)。私は、ここに英雄時代論争を積極的に乗り越える方向があると思う。
二 地震神・火山神論――オホナムチ・オホクニヌシ
「古代貴族の英雄時代」は、第二次大戦後の石母田の仕事の根底にすわっていた論文であるが、それはもっとも示唆的な内容をもつヤマトタケル論をふくめて、一つの構想にとどまっていた。それは問題提起の論文であって、歴史学の仕事としてみると、現在の段階で参照すべき部分は少ないといわざるをえないであろう。この段階では、さすがの石母田もほとんどヘーゲルを典拠として議論をしており、この段階では神話論の全域に踏み込む用意はなかったのではないかと思われる。
しかし、「古代貴族の英雄時代」の発表の五年後、一九五三年、『世界歴史事典』に石母田は長文の「日本神話」という項目を書いた。参考文献には松本信広、肥後和男、高木敏雄、松村武雄、武田祐吉、倉野憲司などの著書が上げられており、「日本神話の成立とその政治的性格」「神話に潜在する古代民族の生活相」「出雲神話と大国主命」「高天原神話と出雲神話の媒介者としての素戔嗚尊」という小節の構成からわかるように、倭国神話の全体についての体系的な議論である。そこでとくに重要なのは、スサノヲについて、「日本武尊とつながる性格をもつ」「同一の基盤から成立していった」「日本神話上もっとも英雄的な性格をもつ神」と説明されていることである(二六九頁)。これはオホナムチにも通ずることであろう。石母田は、ヤマトタケルを通じて、「出雲神話」という倭国神話のさらに深部に属する神に焦点を合わせていったのである。そして石母田は、このさらに四年後、一九五七年に「国作りの物語についての覚書」「古代文学成立の一過程(上・下)」、そして、一九五九年に「日本神話と歴史ーー出雲系神話の背景」発表した。そこで展開されたオホナムチ=オホクニヌシ論は石母田の神話論の到達点を示している。
以下、本来は、これらの石母田の論文を跡付け、それに即して議論していくべきであるが、あまりに問題が錯綜しているためもあって、ここではおもに松村武雄の神話学との関係を中心に石母田の議論の意味を確認することとする。その上で石母田のオホナムチの理解に対置して私説の全体を述べることにしたい。
A松村神話論への石母田の批判
(1)松村武雄『日本神話の研究』--神話学と歴史学
一九五四年から五五年に、神話学の泰斗、松村武雄の大著、『日本神話の研究』(全三巻、培風館)が、一挙に出版された。これは右に挙げた石母田の出雲神話論に大きな影響をあたえたものと考えられる。それ故に、石母田の神話論の展開を考えるためには、まず松村に代表される神話学の研究の位置を明瞭にしておく必要がある。津田の文献学的な方法と、松村のような神話学の達成は方法的な位相を異にしてくるからである。
前述のように、津田は『古事記』『日本書紀』などの神話テキストの背後に、口承によって民衆の間に伝承されてきたような神話的観念の反映を基本的にはまったく認めない。そこには民衆の精神・感情・生活を体現しているような内容はないというのが津田の見解の基本である。率直にいって、津田の仕事はこう割り切ることによって可能になったのであるが、それは突き詰めていえば、『古事記』『日本書紀』の神話が実際上は神話ではないというに等しいことだった。
これに対して、その史料批判の仕事の意味を認めながらも、神話学の側が津田の見解の根本に違和感を抱いていたのは自然なことであったといえるだろう。日本の神話テキストは、世界的にみても有数の神話テキストである。中国・朝鮮に残された神話史料がきわめて断片的なものにとどまっているのと対比すると、東アジアにおける神話論にとってきわめて貴重なものであり、良い悪いは別にして、神話学者には、そのような割り切りはむずかしい。このことは松村の大著『日本神話の研究』が「古典神話は果たして神話なるか」という章をもってはじまり、そこで津田に対する批判がもっとも重視されていることに明らかである。
もちろん、津田に一世代に遅れて、この国の神話の本格的な研究を開始した松村は、津田の仕事の意義を十分に認めている。松村は一九四七年に発行した『日本神話の実相』(培風館)において「かくして、吾人の考ふるところにして謬なくば、記紀に見ゆる神話体系は、少なくともその根幹部分の関する限り、決して日本国民自身の心と手で成立させられたものではない」(五〇頁)として、津田のいう日本神話の政治性をほとんど承認している。また神話学者であっただけに松村は「支配階級や之に阿る徒輩が古典神話の語るところの真義を撓め若しくは法外に誇大化して、それによって国民の叡智を曇らし尽くしたところに、若しくは国民自らが、神話の悪しき理念・観想に溺惑したところに、古典神話は、国家及び国民に災禍をあたえるものとして機能する(今回の惨敗降伏の由って来るところの、少なくとも一因は、そこにある)」(二〇八頁)と論じている。
石母田は、このような神話学の動向に敏感であった。前述の一九五三年に書いた「日本神話」という短文で石母田は「神話に潜在する古代民族の生活相」という一節をもうけ、「国土創成物語がかりに政治的意図によってつくられたとしても、それがそのディテイルにおいて民族の宗教的な生活や観念(中略)によって肉づけせざるを得なかったことはたしかであろう。(中略)日本神話を周辺民族および後世の神話伝説との比較研究によって明らかにしようとする神話学者の努力が必要な理由もここにあった」(二六二頁)と述べている。石母田は、そのレヴェルの神話の問題は極力神話学の議論にゆだねるという態度をとっていたようにみえるが、石母田が津田を乗り越えようとするなかで、神話学の仕事を学んでいたことは確実である。
そもそも、神話とは、本来、この世界と宇宙がどのように存在しているか、どのように形成されたかについての世界観的な直感である。松村は、神話学者として、記紀神話に「宇宙生成神話」というべきものが反映されているということは正面から認め、その点で津田を強く批判した。とくに重要であったのは、松村が、国生神話を火山神話として解釈したことであろう。すでに右の『日本神話の実相』で、松村は、イサナキ・イザナミが「ミトの婚合」ののち日本の島々を生みだすのは海底火山の噴火の経験を条件としているという把握を提出している。「土地の起源が人の生殖として語られたことは(世界で)他に類例がない」「無理な考え方」であるというのが津田左右吉の神話論の基本的な前提の一つであったが、松村による批判によって、それはすでに成り立たなくなっているということができる。この見方は神話学では松前健に受けつがれていて、この二人の神話学における位置からしてすでに通説といってよいだろう。さらに文学史の益田の『火山列島の思想』は文学者の方法意識にたちながら、同時に、いうところの「神話的想像力」の問題を重視して示唆多い議論を展開している。また私も、それらを前提として、先述のタカミムスヒは雷神・火山神としての性格をもっており(『歴史のなかの大地動乱』岩波新書)、タカミムスヒが主宰する天孫降臨神話も火山神話と考えることができると論じた(『物語の中世』文庫版あとがき)。倭国神話には火山神話が骨絡みであったと思う。
その意味では、松村の仕事はきわめて大きな位置があると考えるのであるが、しかし、それにも関わらず、実は、松村は記紀神話そのものを「自然神話」という観点から解いていくことにきわめて慎重であり、消極的であった。そこには、松村が津田を批判しながらも、その研究と観点を尊重しているという事情が大きかった。しかし、さらに決定的なのは、松村が、一九世紀のクーン、マックス・ミューラーなどの「自然神話学派」に対する批判という形で進展していた二〇世紀神話学の動向のなかにいたことである**7。ヨーロッパ神話学の研究から出発した古典的な文献神話学者であった松村には、神話学のシェーマをそのまま倭国神話に適用するという傾向があったことは否定できないように思うのである。以下紹介する松村のオホナムチ論は、その傾向がとくに強く現れている。
(2)松村武雄のオホナムチ論と小川琢治「東西文化民族の地震に関する神話及び伝説」
さて、松村は「出雲国家」というものを想定し、オホナムチという神はその成立の史的経験を反映する神であるという。この神は「八千矛神」という別称に表現される武力、そして呪師能力によって出雲国家を代表する文化的英雄神である。このうち松村が強調するのは後者であって、この神は死からの蘇り、蛇・呉公・蜂の害の防除、医術、琴などの呪具の使用、因幡の白兎やスクナヒコナを癒した医術などの呪師能力を本質的な職能とするという。
その前提となっているのは、出雲系神話が「天孫系若しくは高天原系神話群」から独立した体系と伝承地域をもった神話群であるというものである。松村は天孫系民族と出雲系民族という用語も使用しており、そこには民族あるいは部族の相違があるというのである。こういう出雲神話の基盤に部族的なものを想定するというのは、現在でももっとも一般的な見解であって、石母田の批判の対象は、ここにあった。
このような見解は、一種の俗論のようにもみえるかもしれない。しかし、注意すべきなのは、これが松村の神話学的見識に由来するものであったことである。つまり松村によるとギリシャ神話の実態は高華なオリュンポス的国民神ではなく、むしろそれと各地域に存在した民族的・部族的な宗教生活の関係にこそ注目しなければならないという。松村の大著は『古代希臘に於ける宗教的葛藤』(培風館、一九四二年)と名付けられているように、ギリシャ神話に普通に登場する神(Theos、テオス)ではなく、ヘーロース(Heros)などといわれるギリシャにおける部族のダイモンや低格の神々のあいだの宗教的葛藤に注目したものである。松村は、オホナムチを、このヘーロースという特定の部族あるいは民族に固有な神格において、出雲部族のヘーロースとして捉えようとしたのである。
ヘーロースは、本来は一定地域・部族において尊崇された地下霊・祖霊である。それは本来はエレクテウスなどの神名で伝えられる地震を引き起こすような原初的な地下霊の姿をとっていた。しかし、それは第二段階において「地下霊的・祖霊的な性格を希薄にして史的・文化的英雄の色調を濃厚にしてきた」。そして第三期のヘーロースはもっぱらその社会集団が他の集団を制圧したという伝統意識を核として信仰的な文化的英雄となるという。松村は、オホナムチ=オホクニヌシはこの第三段階のHerosであるとしたのである。松村はこの神話学の図式によって、オホナムチには「地下霊」的な性格は希薄であるとしたのであり、松村のオホナムチ論は、ここから演繹的に図式化されていく。
問題であったのは、地質学の小川琢治にオホナムチの地震神としての性格を論じた「東西文化民族の地震に関する神話及び伝説」という論文があったことである。この論文は『支那歴史地理研究』(一九二八年、弘文堂書房)という東アジアの歴史地理と地質学に関する浩瀚な著作におさめられたもので、小川はそこで世界の地震神話についての紹介をしている。その中で興味深いのは、スサノヲが海神であると同時に地震神であるというのはギリシャ神話のポセイドン(ローマ神話ではネプチューン)と同じであるとしたことである。小川は彼らが、「(海神であると同時に)地震の神とされた訳は、ギリシャ半島の地中海に突出した部分は地震の頻発する土地であって、その入江には、これにともなって津波が起こるからである」としている。小川は日本神話における地震神がスサノヲであり、オホナムチはその地位を引き継いだとしたのである**80。
これに対して、松村は、「氏の専攻の理学から観ずると、こうした解釈に到達するかも知れないが、自分たちにはいかにも奇妙な論歩の進め方のように思われて遺憾ながら納得しがたい」として具体的な検討に進もうとしなかった(『日本神話の研究』第三巻、二六二頁)。よく知られていたはずの寺田寅彦のスサノヲ地震神説(「神話と地球物理学」『寺田寅彦随筆集』四巻」については一顧だにしていない。神話学ではポセイドンが海神であり、地震神であることは一種の通説であるから、海神スサノヲを地震神とする議論は了解しやすいように思われ、これは不思議なことにみえる。しかし、松村がこのような鎧袖一触という態度をとったのは、実は、松村がこの通説の批判者であったためであった。松村の大著『古代希臘に於ける宗教的葛藤』(培風館、一九四二年)は、海神ポセイドンはパルテノンにおいてアテネと争う地位にあるような国民神であって、エレクテウスなどの地下霊と同一視することはできない。ポセイドンを地震・津波などの神格によって物理的に説明するphysical explanationは正しくないと論じていたのである(三八〇頁、八二六頁)。それが前述のような「自然神話」学派への態度からも促進されたことはいうまでもない**91。
そういう立場から、松村はスサノヲやオホナムチの「地」的性格を否定してかかったのである。それは、松村がオホナムチという神名について論ずる態度に現れている。オホナムチは大己貴、大穴持命、大名持などと表記され、大国主命、大国玉神、八千矛神などの別名をもつが、『日本書紀』そして『古事記』の黄泉国訪問まではオホナムチという名前をもっている。それ故にこの神の名義的理解においては、オホナムチという神名が問題の中心となるが、それについては、①大名持(優れた名前の持ち主、本居宣長『古事記伝』)、②大地持(「な」は地震を「なゐ」と読むように「地」の意味、敷田年治『古事記標注』)、③最高尊貴者(大+感動詞(あな)+御主(みち)、松岡静雄)などの諸説がある。
ここで「オホ」は「大」であることに問題はないので、問題は「ナムチ」の理解となるが、松村はまずムチについては、オホヒルメムチ(大日?貴)、ミチヌシノムチ(道主貴)と同じ「貴」の意味であろうとした。この見解が正しいことは現在では確定している(オホナモチという訓もあるが、それは後次的なもの)。
中心は「ナ」の理解になるが、松村は『日本神話の研究』の最終巻(第四巻、一九五八年刊行)で、「ナが『地』の意味であり、ひいては『国』を意味することは疑いもない」(三七五頁)とする。「ナ=地」は右の②の意見、敷田年治『古事記標注』の見解と同じであるが、松村は立ち入った論証なしに、それに「国」を付加し、「ナ=地=国」という等式をつくった。そして、それによって「オホナ」は「大国」と同じ意味であると断定する。その目的はオホナムチという神名の意味をオホクニヌシと等置し、それを「オホナムチの含意をくみ取っての、その一種の翻訳名であろう」という形で逆推することにあった。しかし、そもそも、オホクニヌシという神名は、『日本書紀』本文には見えず、一書六、一書一に神名として登場するのみで、『出雲国風土記』にも登場しない。基本的には『古事記』に特殊なものであって、『万葉集』などをみても、この神の一般的な名称はオホナムチ=大汝であった**10。このように特殊なオホナムチという言葉の解釈にひきつけてオホナムチの神名を考察することは正当でない。しかも、すぐにふれるように、「クニ」には独自の語源がある以上、このような等置は乱暴といわざるをえないだろう。ようするに、松村には、オホクニヌシ、「大いなる国主」、国の建設に貢献した「大いなる国主」として伝承される文化英雄神がオホナムチであって、オホナムチは地霊ではないというギリシャ神話論からくる前提があって、その図式にあわせてオホナムチの神名を解釈しているのである。
こうして松村は、オホクニヌシを「ある自然物素若しくはある自然現象を原体とした、それの人格化・神格化ではない」としたのである。松村が火山神話論の基礎構築に進み出ていただけに、またオホクニヌシが本来的には地下霊としての性格をもつHerosであることを認めていただけに、これはきわめて残念な経過であった。当時の学界に、地質学・神話学・歴史学の間で自然神話にふみこむような議論を展開する条件はなかった以上、これはやむをえないことであったかもしれない。また松村にとっても、第二次大戦から終戦にかけて、この列島の国家と社会のなかで自己の研究を続け、それを三巻の大冊にまとめ上げることは孤立した苦闘であったようにみえるから、これが限度ギリギリであったのであろうか。
(3)石母田正のオホナムチ論
石母田は、以上の松村の問題提起をふまえつつも、松村が弱かった点、つまり、オホナムチの神話テキストを内在的に読み抜くという作業に挑み、オホナムチをヤマトタケルと相似した位置にある英雄神として位置づけた。石母田が松村の仕事をよく読んだことには証拠がある。つまり石母田は、松村が『日本神話の研究』第三巻で述べた大国主命論について「今後の研究は、この業績を基礎として出発する必要がある。そこで確定された重要な結論の一つは、従来、この神を自然物または自然現象、たとえば地震・風・雷などの人格化・神格化した神と解釈する説(中略)と明確に訣別し」(一八四頁)たことであると述べている。石母田は、「この神の基本的性格は、国作りの神としての英雄神と見るべきことは正しいとみられる」(二〇三頁)として、松村の見解の中枢を承認したのである。
しかし、石母田は、他方で、松村のオホナムチ論の抽象性・形式性を明瞭に批判している。つまり右の一文は「しかし、古典古代のヘーロースの概念や歴史をこの神に単純に適用する方法は困難であるばかりでなく、日本古代の英雄神の特質を識別し、その根拠を探求する努力を弱めることになろう」と続いているのである**112。
そういう立場から石母田は第一にオホクニヌシは松村のいう部族神よりもより広い信仰域をもつ神であると考えたようである。国民的な英雄神であり、松村の用語でいえば、第三期のヘーロースを超えてテオスに近いものと考えたようである。つまり、石母田は、論文「国作りの物語についての覚書」での『出雲国風土記』におけるヤツカミヅオミツヌによる国作りの分析をふまえ、松村が、ヘーロースの舞台となった部族を「出雲」および「出雲国家」と等置していることに批判を向ける。そして、「出雲国にはヤツカミヅオミツヌの命という土着の国作りの神があって、『出雲国風土記』では(中略)、その国作りが終わった後に、オホナムチの神は杵築宮に祀られたにすぎないことになっている。(中略)むしろこの神の出自、その本拠は畿内とその周辺であったとみられ、この神が出雲の杵築宮に祀られたのは、畿内勢力による出雲の征服を契機としたものと考えられる」(一八七頁)とし、オホクニヌシは松村のいう「出雲部族」を超える存在であるとしたのである。冒頭に石母田が岡本太郎に語ったという「大国主命は土着の神ではないという新説をたて、いずれ発表して定説をくつがえす」「大国主命の伝説も、むしろ近畿、ハリマあたりの方が本場だ」などという抱負を紹介したが、まさにその問題である。石母田が岡本に語ったというひっくり返すべき「通説」は、以上のような事情からすると直接には松村の見解を意味していたのであろう。これが鋭い問題提起であったことは疑いない。
また石母田は、松村のようにオホナムチの地霊としての側面を切り捨てて、もっぱら国作りの神としての英雄神とみることにも反対している。「古典古代のヘーロースは、いくつかの段階に区別されるprogressiveな発展をしめしているが、大国主はむしろそれらの諸段階を、一箇の英雄神の諸側面として保存しているのが特徴である。『禁厭之法』を定めたという文化的英雄神は、他面では地神であり、洞窟に住む神である」(二〇三頁)という。これも松村批判として有効なものであった。
これは石母田が、オホナムチの神名について、オホアナムチという訓、そしてそれに対応する大穴持命という漢字表記を正しいものとみて、『万葉集』にみえる「大汝少彦名のいましけむ志都の石室は幾代経ぬらむ」という和歌を神名論において重視したことに関係している。このオホナムチの神名は本来、オホアナムチであるという石母田の見解は、大己貴のもっとも一般的な呼称が「大汝」であることからすると、松村のいうように成立しえないであろう。これについては後にオホナムチの神名を考えるときに再度ふれることになる。しかし、石母田がオホナムチの地霊としての側面を強調したことの意味は否定できない。つまり石母田は「地霊の神格化した神の住処として洞穴はふさわしい場所の一つであろう。少なくともオホアナムチの語義についての従来の説にはしたがいがたい。大国主またはオホアナムチの基本的な性格が、英雄神であったとしても、それはまだ地の神、山や丘の創造神であるという畿内・近国の農村社会でひろく信じられていた観念から絶縁はしていなかた」(一八五頁)という。石母田は、オホナムチを地震などの具体的な自然現象の力に引きつけることはしなかったものの、その地霊としての性格に深い根拠があることは承認していたのである。たしかに、この神の神格は地霊から英雄神に移行していくが、移行後にも地霊としての性格は保存されているという捉え方は正統なものと思える。
Bスサノヲ論--海・八又大蛇・地震・火山
以上、石母田のオホナムチ論を、とくに松村の見解との対比において紹介し、若干のコメントをしてきた。もちろん、石母田の見解は、これに尽きるものではない。その文学的な感性と論理力を生かして史料を総合的に読み抜いた仕事は、さらに細かく点検する価値がある。しかし、以下、そこを離れて、その検討を通じて考えるようになった、私自身のオホナムチの神格理解について述べていくこととしたい。神話が一つの世界観として体系をなしている以上、多様な問題にふれざるをえず、叙述は錯綜するが、ここでは基本的には石母田が「地霊」と述べたものの中身をさらに具体的に考えることに問題を限っていく。それは自然神としての地霊であり、とくに自然の猛威、地震・津波・噴火などの地殻災害の脅威に関わる問題である。
(1)国生・神生神話と火山の女神イザナミ
オホナムチの神格を論ずる前提として、まず簡単で断言的な記述となるが、国生神話とスサノヲの神格について確認していく。
松村の『日本神話の研究』がいうようにイザナミは「ミトの婚合」ののち噴火によって日本の島々を生みだした。イザナミこそこの列島の大地母神として火山の女神であるというのである。神話学の大林太良によっても、出産によって国や島が生まれるというスタイルの神話は、太平洋地域に広く分布しているという。私は、その分布地域がまさに環太平洋の火山地帯にあたることに注目すべきだと思う。ほぼ同じ地域に「海中に火の起源を求める神話」が分布するというのも重要であろう。これらは海底火山の噴火の経験の神話化と考えるべきであろう**123。
この地域では地母神は火山の女神というスタイルをとり、火山の本体は女神と観念されたと考えられる。火山列島・日本の山の神が女神であることも自然なことであって、たとえば、『常陸国風土記』には、「御祖の尊」が富士と筑波の神のもとを訪れた時のエピソードがあるが、この「御祖の尊」の御祖については漠然と「尊貴な祖先の神」と理解されることが多い。しかし、たとえば賀茂御祖社の例が示すように、「御祖」とは母親を意味する。この神は、山々の「御祖」である大地母神なのである。この母親の訪問に対して、富士の神が「今日は『新粟』の新嘗の収穫祭の夜で物忌の最中なので、申し訳ないが駄目です」といったのに対して、筑波の神は「物忌ではあるけれども、親のいうことが何よりです」といって歓迎したという訳である。彼らも女神であろう。このエピソードは、富士の位置からして、列島の地母神の中心に母娘の火山の女神がいたことを示している。もとより、筑波山は、火山ではない。しかし、御祖尊が筑波を褒めて「愛しきかも我が胤 巍きかも神宮」と謡ったことは、当時の「神宮」の用例からすると、筑波山が火山とみなされていたことを示している。筑波山は、地下で固まって噴火しなかったマグマだまりが地上に露出したものであって、今でも火山と思われることも多い。そして標高が高く、磐座の発達した方を女体山としていることも示唆的で、筑波の神が女性上位であったことは間違いないのである。
国・島などの自然を生んだ後、イザナミは環境の神々を生む。つまり、自然としての国土ではなく、自然を居住と生活の有用的な環境として占有するときの「魂」、海山川や家宅の神々などを生んだのである。たとえば後にふれる「水戸神=速秋津日子神・妹速秋津比売神」などは、勢いの強いことを示すハヤに「アキ」がついた神で、ミナトの口には巨大な男女の水神が屈んで口を開けており、そこに水が流れ込んでいくという訳である。
次ぎに生まれるのが「天之石楠船神、大宜都比売神、火之夜藝速男神」など、文明の象徴としての火にかかわる様々な神々であって、天之石楠船神は彗星の神である。重要なのは、次の女神・大宜都比売神であって、大林によれば、彼女は列島における最初の農業の女神、大地の富を表現する地母神、具体的には、焼畑における火入れを象徴する女神である(大林『稲作の神話』一九七三)。その神話学的な論証は説得的なものであるが、そこで掲げられた文献的な証拠は「粟国は大宜都比売」(『古事記』上)といわれること、つまりオオゲツヒメが粟国=阿波国の女神であるとされることのみであった。歴史学の側からそれに追加できるのは、『歴史のなかの大地動乱』で詳しく触れた九世紀における伊豆神津島火山の女神が「阿波神」という名をもっていたことであろう。こうして「オオゲツヒメ=焼畑の女神=粟神=阿波神=神津島の火山の女神」という等式を描くことが可能になるのである。富士山の女神が、右の物語で「新粟」の新嘗の夜の物忌を行っていたというのは、焼畑に関係している。この「粟」を穀物一般と理解することにとくに根拠はなく、粟の焼畑の収穫と考えて問題はない。富士の女神は火山の女神であるとともに粟焼畑の女神でもあったのである。ここには火山神話が作物起源を語る豊饒の神話に展開する事情がよく現れている。
イザナミの生んだ第三の火神、火之夜藝速男神は別名を「火之炫?古神」「火之迦具土神」ともいった。このカグツチを生んだことで、イザナミは「美蕃登」(陰部)を焼かれてしまい瀕死の重傷をおって病臥した。松村は、地母神イザナミが死去しなければならないような大地そのものの激しく痛ましい負傷としては火山の爆発を考えるべきであり、この神話は火山の噴火の端的な経験をベースに考えるほかないという。
さて、瀕死のイザナミは傷つき苦しみ、のたうち回って、多具理、つまり反吐を吐き、そして脱糞し、尿を垂れ流す。益田が「へどとくそと尿は、上流の山中での砂鉄採取によるタタラの鉄製錬、中流の陶土採取による窯業、下流の灌漑による農業生産を鳥瞰図的に表現している。吐き、くだし、汚穢・不浄のなかで、神聖な火と鉄と陶土と水と生成力の神たちが生まれた」(『古事記』一〇一頁)としているように、この神話は、そのような大地の苦しみのなかから、富が産出されると語る。これまで地母神という場合、もっぱら農業の富に局限される傾向が強く、そこには鉱業と金属の富の神という要素も含まれていることは無視されることが多かった。しかし、この時代における富の現実のあり方を前提とすれば、むしろこれこそがもっとも豊かな富なのであって、人々が鉄をイザナミの吐瀉物と想像したことはきわめて興味深い事実である。口から吐き出した冨がもっとも価値が高いのであろう。
どの富にも火が関わっていたということであろうが、とくに示唆的なのは、イザナミの排泄した「屎」についての『日本書紀』(神代第五段、一書第二)の説明である。それは、瀕死のイザナミは倒れ臥しながら土神・埴山姫と水神・罔象女を生むが、それをみた火神・カグツチは、土神・埴山姫に挑みかかって犯し、その結果として稚産霊が生まれたというグロテスクなものである。火の神が埴山姫に挑むというのは、粘土・陶土を焼き固めることの暗喩もふくむが、火と土の関係一般をふくむのであろう。人々が土の中の火気に強い関心をもっていたことは、怒った父イサナキが、火神の首を切ったとき、カグツチの血が諸方に飛んで、「石礫・樹草に染る。これ草木・沙石の自ずからに火を含む縁なり」とあることにも示されている(『日本書紀』第五段一書第九)。
(2)海神スサノヲと穢のスサノヲ
夫神のイサナキは、こうして、のたうち回るようにして死んでいったイザナミの枕辺に腹ばい、足もとにはらばい、「愛するお前は自分の命を子ども一人に代えてしまおうというのか」と嘆き悲しむ。そして、イザナミの遺体は、「出雲国と伯伎国との堺の比婆山」に葬られたというのが、『古事記』の説明である。これに対して『日本書紀』本文は、イザナミの死去それ自身を語らず、異伝はその死を語るものの第五の一書が紀伊国有馬村に葬られたとするほかは、葬送の場所も語らない。その意味については後に述べる。
父神イサナキは怒りのあまりに巨大な剣を振るってカグツチの頸をはねた。そして、妻を失った嘆きに耐えず、「根の堅すの国」に妻を訪ね、彼女を地上に取り戻そうとしたのである。ギリシャ文明、マヤ文明その他、世界各地に残された死後婚の神話である。『古事記』の語り口は見事なもので、有名なギリシャ神話のオルフェウス神話にまさるとも劣らない。
しかし、イサナキは、遺体を「覗くな」というイザナミの願いに反して、タブーを犯し、妻を連れ戻すのに失敗してしまう。そして死者の国でふれた妻のイザナミの精気を身体にまといつかせて、地上に戻ってきたイサナキは、海岸で禊ぎをし、水中にその「穢」を放出する。イサナキの汚れた身体そのものから生まれた神が、「穢の神=大禍津日神」であり、次ぎに目と鼻をあらったとき、左目から生まれたのが日神オホヒルメムチ、右目から生まれたのが月神ツクヨミ、そして最後に鼻から生まれたのがスサノヲであった。イサナキがアマテラスを高天原の神とし、ツキヨミを夜の月世界の神とし、スサノヲを海原の神としたことはよく知られている。
しかしスサノオは母を慕って「根の堅州国」へ行きたいと「哭きいさちる」。弱いところをつかれた父神のイサナキは怒り狂ってスサノヲを追放し、傷心のまま隠棲してしまう。こうして父に見放されたスサノヲは、天にいる姉のアマテラス(オホヒルメムチ)を慕って、アマテラスの治める高天の原に駆け上がった。その時、スサノヲは「山川ことごとく動み、国土みな震りぬ」(『古事記』上)という事態を引き起こした。これはスサノヲがまさに地震神であることを示している。また『日本書紀』(神代第六段)には「溟渤もて鼓き盪い、山岳ために鳴り?えき」とある。この「溟渤もて鼓き盪い」という部分は大津波を意味するのではないか(なおスサノヲが天に昇るときに同じような地震を起こすという記述は『書紀』(七段、異書三)にも「天を扇し、国を扇して」ともあることを付記しておく)。
さて、小川琢治や寺田寅彦は、この点をとってスサノヲの地震神としての性格を主張するのであるが、問題は、スサノヲの神格全体のなかで地震・津波の神としての性格をどう位置づけるのかということであろう。たしかに小川が、海神スサノヲが地震・津波の神であり、ギリシャ神話のポセイドンと同じであるというのは基本的な点をついているが、しかし、それを倭国神話の筋道に即して論ずることが必要なのである。
最近、水林彪はスサノオが本質的には「水の神」であることを強調している。たしかにイサナキがスサノオに「海原」の支配を命じている以上、これは自然な想定であろう(水林彪『記紀神話と王権の祭り』岩波書店、四〇九頁)。スサノオが母を慕って泣き「青山は枯山なす泣き枯らし。河海は悉く泣き乾しき」と述べられているのは、イサナキにゆだねられた水界の統治をスサノオが放棄したためであるというのが物語の論理であろう。しかし、問題は、海神スサノオの神格をさらに具体的に考えることであり、その点で注意すべきなのは、スサノオがイサナキの鼻から生まれたという設定である。これは普通、スサノオの風神としての性格を物語るものとされる。鼻は息が通る場所だからという訳である。しかし、風神はスサノオの神格の中ではけっして大きな位置をもっていない。これはむしろ本居宣長が「鼻に嗅ぐ悪臭気は、深くてそのなごり亡がたき故に、須佐之男命は悪神なり」(『古事記伝』)といい、平田篤胤が「深き御鼻の汚穢の流離ひ出るによりて出生座し」(『古史伝』六巻)としていることが正しい。水林は鼻からの誕生には意味はない、三貴神は汚れが除去されきった後に生まれた神であるから貴神なのであるとするが、これは形式論理のように思う。三貴神の中で、スサノオが鼻から誕生したことは、顔面において鼻がもっとも汚れた器官であることに関係しているといってよい。その穢はもとを質せば母の穢であるから、それをもっとも身に深く受けているという意味ではスサノヲはマザーコンプレックスの塊のようなものともいえるのかもしれない。
私は、平田篤胤の見解をうけて、神道史の西田長男がスサノオは前記の汚穢の神、「八十禍津日神、大禍津日神」と同一の神格であるとしたことに賛成したい。管見の限りでは、西田の意見は孤立したままだが、そもそも、大祓の行事はスサノオと密接に関係するものである。つまり、大祓は宮廷をはじめ国中をはらい清める行事として、六月・一二月の晦日、および疫病流行の時などに行う祭祀である。スサノオは、たしかに海原を統治し、海原の神々の上に立つ性格をもっているのであるが、それは綿津見神、筒男命などの本来の海の神々のみでなく、八十禍津日神以下の水界の汚穢を体現し、同時にそれを清浄化する威力をもつ神々との深い関係を意味していたのである。スサノオは海原の神であると同時にその汚穢をも背負った神であったのではないだろうか。そのような神としてスサノオはエネルギーにみちた「貴神」なのである。
この海の支配神であると同時に穢神であるというスサノヲの複雑な業の深い性格が、スサノヲをエネルギーにあふれた神にした。そのような神が、母の蘇生に失敗した父・イサナキに反抗し、身体が大きくなっても成熟せず、母を恋い慕い、母のいる「根の堅州国」に行きたいと「哭きいさちる」ということになったのである。
(3)根国の无間大火と気吹戸主(いぶきどぬし)
もちろん、この観念を端的に表現した史料は『日本書紀』『古事記』などには存在しない。しかし、『延喜式』に記録された「大祓祝詞」は、それをおぎなうものである。この「大祓祝詞」は原型が天武の時代には成立し、徐々に九世紀までかけて文詞が調えられたものとされるものである(青木紀元「大祓の詞の構造と成立過程」『現代神道研究集成』1(古典研究編)、神社新報社、一九九八年)。関係するところを引用しておくと、次のようになる。
遺せる罪は在らじと、祓ひ給ひ清め給ふ事を、高山の末、短山の末より、さくなだりに落ちたぎつ、速川の瀨に坐す瀨織津比咩と云ふ神、大海原に持ち出でなむ。此のごとく持ち出で往かば,荒塩の塩の八百道の,八塩道の鹽の八百会に座す速開都比咩と云ふ神,持ちかが?みてむ。此のごとくかが呑みては,気吹戸に坐す気吹戸主と云ふ神、根の國・底の國に気吹き放てむ。此のごとく気吹き放ては,根の国、底の国に坐す速佐須良比咩と云ふ神,持さすらひ失てむ。
罪穢は山の上から落ち下る速川にいる瀨織津比咩という神が大海原にもっていく。次ぎに多くの潮流がぶつかるところにいる速開都比咩という神が、それを海底まで呑み込む。そして海底の気吹戸というところにいる気吹?主という神が根の國・底の國に吹き込んでいく。最後には、根の国、底の国にいる速佐須良比咩という神が身にうけて消滅させてしまうのである。
すべての「罪・咎・憂い」は、海底の根国にいて汚穢を「持ちさすらひ失ひてむ」女神、速佐須良比咩(ハヤサスラヒメ)が消滅させてくれるというのであるが、ハヤサスラヒメが、山から海底まで罪穢を流していく瀨織津比咩と速開都比咩という二人の女神のネットワークの最後に位置していることが興味深い。とくに重要なのは後者のハヤアキツ姫が『古事記』に「水戸」の女神、「速秋津比売神」として登場することである。大祓祝詞と『古事記』で漢字表記は速開都比咩と速秋津比売神というように異なっているが、この神名の由来は、穢を「かが?む」、つまり口を「開」けてがぶがぶと呑み込むという大祓祝詞の表現によって説明される。速開都比咩の「開」も港の開口部を意味するのであろうから、大祓祝詞の漢字表記が的確なのである。大祓祝詞は依拠するにたる史料であると思う。こうして、ハヤサスラヒ姫やセオリツ姫という女神は八世紀史料に登場しないが、ハヤアキツ姫の例からいって、これらの女神も早くから存在したであろうということがわかるのである。これらは女が穢を清める、あるいは掃除をするという観念の反映であるといってよい。
このハヤサスラ姫については、時代は鎌倉時代初期まで下るが、神道書、『中臣祓訓解』の次の部分によれば「伊弉那美尊(イザナミ)」自身であるとされている。関係部分をあげておきたい。
根国・底国<无間の大火の底なり>
速佐須良比咩神<伊弉那美尊。其の子速須戔烏尊なり。焔羅王なり。司命・司禄等は此の神の所化なり。一切の不祥の事を散失するなり>
つまり、「根国・底国」は「无間の大火の底」にあって、そこを主宰する女神が速佐須良比咩神=伊弉那美尊であるという。しかも、そこには「その子、速須戔烏尊(スサノヲ)」が「焔羅王」となって棲んでいるというのが興味深い。『古事記』には、スサノヲが「根の国」の王になったとあるだけで、イザナミはどうしているのかは書かれていないが、実は、彼女はハヤスサラヒ姫と名前をかえて、「根の国」の女王でありつづけており、スサノヲは母のもとに行くことに成功したという訳である。
私は、この『中臣祓訓解』はスサノヲとイザナミの神話的表象の本質をついていると考えるものだが、その場合に、注意しておきたいのは、大祓祝詞のいう「気吹戸に坐す気吹戸主と云ふ神」の正体である。『倭姫命世記』はこの神を「神直日・大直日神」と説明している。『倭姫命世記』は平安末期から鎌倉時代初期の史料ではあるが、その解釈は依拠するにたりるものである。そもそも神直日・大直日神とは、黄泉国を訪問したイサナキが海岸で禊ぎをした時に生まれた神である。前にもふれたように、イサナキは、その身体にべったりと付着していた黄泉の穢を水中に放出し、そこから穢の神=大禍津日神を産むが、この神直日・大直日の二柱の神は、それにつづけて生まれた神であって、穢を「直す」、祓う神として設定されている。とはいっても、神道史の西田長男がいうように、穢自体を象徴する大禍津日神と、それを「直す」、神直日・大直日神は表裏の関係にいる神であって、穢が強力ならば、祓神も強力になるという関係にあり、実際上、これらの神は同体であるという。それ故に彼らはスサノヲと同じ神なのである。スサノヲは強力な穢の神であると同時に強力な祓え神でもあったのである。西田は、このような事情について「禍津日神は”禍事を為し給ふ”神ではなく、”禍事を為す”のは我々人間なので、この人間の犯した禍事を・罪事を指摘して、人間をしてそれより脱却せしめようとされる神と解すべきではあるまいか」と説明している。(「古代人の神」『古事記大成』第五巻、一九五八年)。
こうして「気吹戸主」=「神直日・大直日神」=「大禍津日神」=スサノヲという等式が神道史学の教えるところなのである。つまり、「気吹戸主」=スサノヲであり、大祓祝詞はスサノヲが「根国・底国」に通ずる海底の気吹戸というところにいて、悪と穢をハヤサスラ姫のところへ吹き込んでいるというのである。これは『中臣祓訓解』が、スサノヲが「根国・底国」の「無間の大火」のなかにいるハヤサスラ姫の子神であるというのと同じイメージである。
そうだとすると、『中臣祓訓解』においてハヤサスラ姫がイザナミと説明されているのも十分に了解できることになるのではないだろうか。海の底に降り積もってきた、この世の罪咎のすべてを息子神スサノヲが母のイザナミのもとに吹き込んで、すべてを燃やしてしまうという訳である。西田は、このような女神の祓神としての姿を「人々が川辺に着衣を脱ぎ棄て、瀬を選び、禊ぎをするときに介添えをする禊ぎの女・水の女の神格化したもの」と説明し、この水の女が平安時代に三途川の奪衣婆に変身していくのだとしている。スサノヲが海の神であるというのは、海が穢を浄化する場であることと関係しているのであろうか。ともあれスサノヲは、「気吹戸主」という神格においては、このような「水の女」に依存して浄化の役割をはたす息子神であったのである。
なお、この「気吹戸主」という神について、青木は「大祓の詞の中で、文章の綾とともに生まれ出た観念的な神々」であるとしているが、しかし、風邪の吹き抜ける近江国の伊吹山のイブキという地名は、この気吹戸主の神格とかかわるものであったことは確実であろう。つまり、よく知られているようにヤマトタケルは伊吹山の神の祟りをうけて死去したとされるのであるが、この神は『日本書紀』(景行紀四十年)では大蛇として登場している。ここからすると、気吹戸主という神は、龍の一種で、海底にいて地底の国に気吹=風を吹き込んでいたというイメージであろうか。黒田日出男は、列島の大地の底には龍が行き来する穴道が縦横に通っていると観念されていたとしているが(『龍の棲む日本』岩波新書)、地中の龍穴という観念はだいたい九世紀には史料で確認することができる。そうだとすれば、この大祓の祝詞は、この地中の龍穴が深海の底に「気吹戸」をもっていたというイメージを示しているのではないだろうか。考古学の春成秀爾によれば、すでに弥生時代から龍の図像は土器などに描かれて広く存在し、雷電や蛇のイメージとダブルイメージになって天空と水界にひそむ霊的な存在と観念されていたという(春成「変幻する龍」(『ものがたり 日本列島に生きた人たち〈5〉絵画 』岩波書店)。彼らのイメージは遅くとも九世紀には成立していたということになるのであろう。
なお、ルクレティウスの『物の本質について』には、エトナ火山の下の深くまで、海から空洞が通じており、そこから火焔があがるという記述がある。「無間の大火」のもえる「根の国」に気吹戸から風が吹き込まれるというイメージはそれに一致している。ギリシャ・ローマの人々は地震の原因を「風」に求めたのであるが、このような海と地下、火山の地下が通じているという観念こそ、ポセイドンとスサノヲが同じように海神であり、地震神である理由なのではないかと思われる。
こうしてスサノオが、大海原の神であると同時に、汚穢の神、汚れた水の神としては地下の「根国・底国」に関わり、さらに地震の神であるということになると、スサノオをポセイドンと同格であるという小川琢治の見解は、ほとんど確定的といってよい説得力をもつように思う。スサノオが海の神である以上、海から天に昇るときに国土を揺らすだけでなく、大津波を起こすというのも当然であることになろう。
(4)スサノヲと出雲、八又大蛇、「八雲たつ」
このようにして天に上ったスサノヲは、しかし、姉とも喧嘩をして、結局、地上に追い落とされる。そして、「天より出雲国の簸の川上に降到りま」して、人身御供にされようとしていた奇稲田姫を助け、八又大蛇を斬って、その尾の中にあった天叢雲剣、いわゆる「三種の神器」の一つとされる草薙剣を獲得してアマテラスに捧げ、アマテラスとの和平がなったという話はよく知られているであろう。そしてスサノヲはクシナダ姫を妻として出雲の須賀に宮を立てたところ、そこから雲が立ち上り、スサノヲは「八雲立つ 出雲八重垣 妻籠みに 八重垣作る 其の八重垣をという歌をつくり、子孫を儲けて、遂に「根国」に入ったという。
ここで問題にすべきは、まずこの八又大蛇は何を意味するかということであるが、私見では、この八又大蛇から出た剣の話は、『捜神記』(巻一一)に残された楚王の宝剣に関わる物語を原型とするものである。それは楚王の命で宝剣を鋳造した刀匠の干将は、楚王が二本と同じ剣を作らせないために自分を殺害しようとしていることを察知し、ひそかに二本目の剣を作って秘匿し、妻に自分が殺されたならば、産まれる子供にその剣をもって復讐させるようにと遺言したという。その隠し場所を示す謎の言葉が「戸を出て南山を望めば松、石上に生ふ。剣、その背にあり」というものであったというのである。
この物語は魯迅が『故事新編』でいわゆる「眉間尺」の復讐譚として翻案したことで著名なものであるが、中国の宝剣に関わる神秘の物語が東アジア全域に影響したことは福永光司が強調するところで(福永一九八七)、三品彰英は、この物語が、朝鮮に伝わり、『三国史記』(高麗本紀第一)では朱蒙の子の類利が父の謎言葉を解いて王となったという物語になったとした。
興味深いのは「松、石上に生ふ」という刀匠、干将の謎言葉が、朝鮮では「七嶺七谷の石上の松」となったということであって、これこそ「松柏、背上に生ひて八丘八谷の間に蔓延(はひわた)れり」(『書紀』本文)といわれた八又大蛇のイメージの原型ではないだろうか。松が「七嶺七谷の石上」に生えて、その下に剣があったというのは、剣を体内にもった大蛇そのものと考えれば八又大蛇そのものである。相違は「七」と「八」という数字のみであるが、これは倭国では「八尋殿・大八洲・八衢」など「八」が聖数とされたためである。
この推定を支持するのは、三品自身が「高句麗からわが国に眼を転ずるに、この石上松下に蔵されたという夫婁の宝剣は、全くわが石上のフルの宝剣(中略)を連想せしめずにはおかない」としていることである。三品は百済より渡った七支刀が石上神宮の神宝、フルの宝剣のもとであり、それと同時に「石上松下」の八又大蛇神話の原型が伝わったとする。時期的な前後関係はあるとしても、「石上神宮」の名称のもとが、ここにあることは確実であろう。
そもそも八又大蛇の尾からでてきた剣ではなく、スサノヲが大蛇を斬った剣、つまりスサノウが最初から帯びていた佩剣は、『書紀』(異書一)によれば石上神宮におかれており、『書紀』(異書四)では吉備の神部の許にありといわれるが、これは備前赤坂群の石上布都之魂神社であり、どちらにしても石上神宮との縁が深いのである。この剣が『書紀』(異書二)では「韓鋤の剣」と呼ばれていることも示唆的であろう。三品はスサノヲ神話は倭国神話を代表する物語の一つであるが、それは中国・朝鮮諸国から受け入れられたものであることとしているが、それは『書紀』(異書四)に高天原から追われたスサノヲはまず新羅国に天降って「曾尸茂梨」に居を構えたとあることからもいえることである。
また石上神宮は物部氏の氏社である。菊地照夫によれば物部氏は祖神の饒速日尊や高倉下がおのおの天の羽羽矢や布都御魂などの天から授かった武器を献上し、その武器庫を核として神社を創設し、各地に石上の末社や物部神社を作って、古墳時代における畿内王権の軍事体制の中心にいた氏族である。その重要拠点がスサノヲ神話の残る出雲西部であって、物部氏は出雲西部の有力な出雲氏=神門氏と連携して一帯を支配していたという(菊地二〇一六、平石二〇〇四)。
このような状況からすると、スサノヲ神話は出雲西部を場として形成された可能性は高いだろう。『書紀』『古事記』がスサノヲが宮を営んだとする大原郡の須賀、そしてスサノヲの神名を残す飯石(いいし)郡の須佐は、どちらもスサノヲが降臨したという斐伊川の水系に属する。とくに注目したいのは、スサノヲが自身の御魂を鎮めたという飯石郡の須佐の西にそびえる佐比売山(三瓶山)には一四〇〇年ほど以前に山頂噴火堆積物が確認されていることで(福岡孝・松井整司 二〇〇四「三瓶火山の噴火様式の変遷」『島根県三瓶自然館研究報告 』2号)、これが「八雲立つ 出雲八重垣」という歌の「八雲」に関係している可能性である。火山噴火がしばしば「八重雲」といわれたことは本書第一篇の高千穂噴火神話を論ずるなかで詳しく記したが、「八重雲たつ」を五字に減らして「八雲立つ」として出雲の枕詞としたのではないだろうか。
出雲の枕詞としての「八雲たつ」は『出雲国風土記』の冒頭に「出雲と号くる所以は、八束水臣津野命、詔りたまひしく「八雲たつ」と現れるものであり、スサノヲ神話のみでなく広く出雲の景観に関わって与えられた枕詞である。しかし、有名な新羅や越から土地を引いてきたという国引き神話において、ヤツカミズオミツノは出雲の東と西に巨大な「加志(杭)」を打ってそれを固定したというが、東の「加志」は伯耆の「火神岳」(伯耆大山)であり、西の「加志」は石見との国堺をなす「佐比売山」(三瓶山)であったという。これは出雲という国の成り立ちにおいて火山が大きく考えられていたことを示している。東西のランドマークに火山をもつ国、出雲が、その火山噴煙によって「八雲立つ 出雲」と歌われた可能性は高いように思う。このような問題について確実なことはいえないが、松江城から雪におおわれた伯耆大山をみて。さらに出雲大社背後の奉納山公園から稲佐の浜の円形に浮き上がる三瓶山をみたときに、それを実感した。大社の地は古来よりの出雲大神が三瓶山を祭るにはここ以外の場はないように思う。
出雲は越の白山と並んでもっとも畿内地域に近い火山地域に位置している。東北から下りてきた第四紀火山フロントは、近畿地方に近づくと西に方向を転じ、中国地方の日本海側で右にふれた伯耆大山と三瓶山という活発な火山を通って、九州につながっていく。出雲の人々はたんに噴火・噴煙のみでなく火山に特有な地質・地形の認識をもっていたはずである。
もとより、スサノヲが須賀宮を立てた場所から立ち上った雲とは、直接の文脈においては『書紀』(本文)が八又大蛇の居る上には「常に雲気あり」と述べた雲気であり、それはたとえば斬蛇剣をおびた漢の高祖劉邦の上には「常に雲気あり」(『史記』)とされていることのコピーである。三品がここから八雲立つの歌は、こうした中国古典の有名な物語にヒントをえて作られたものだというのも当たっているところがある。しかし、右にふれた国引き神話における「八雲立つ 出雲国」という詞章をすべてスサノヲの天村雲剣や劉邦の斬蛇剣に帰することも極端なように思われるのである。
スサノヲが「八雲立つ」宮から「遂に根国に就でましぬ」(『書紀』本文)というのは、後に述べるように火山の地下の国に行ったということを意味するのではないだろうか。
(5)スサノヲからオホナムチ--地震と火山
スサノヲがいったという根国が、どのような世界であったかを示すのは、そこに兄たちに攻撃された大穴持命=オホナムチ(後の大国主命)が逃げ込んできたことにはじまる物語である。
よく知られているように、オホナムチとスサノヲの娘の須世理姫はすぐに相思相愛の関係におちいった。そして二人は気脈を通じて、父のスサノヲをだまして逃げ出そうとした。その時、彼らはスサノヲの三つの宝物、「生太刀・生弓矢・天の沼琴」を盗み出すのであるが、この時、スセリ姫をオンブしたオホナムチの担いだ「天の沼琴」が「樹に払れて地動鳴みき」(木にさわって大地がゆれた)という。このジャックと豆の木の童話でジャックが竪琴を盗んで逃げ出したときに、竪琴が鳴り響いたことを想起させる物語は、「天の沼琴」が地震を発する呪具であったことを示している。
スサノオが、眠っている間に、家の戸は大石でふさがれ、彼の髪はその房ごとに屋根の椽に結びつけられていたという。そのために天の沼琴の引き起こした地震に驚いて目をさましたスサノオは、起きあがって家を引き倒したものの、椽にからんだ髪を解きほぐすのに時間がかかり、二人は逃亡に成功した。スサノオが遠く逃げていく二人を見はるかしたのは、ようやく黄泉比良坂の上からであって、スサノオはあきらめて、大声でオホナムチに呼びかける。それは「お前は、その生太刀・生弓矢の力で兄たちをやっつけ、大国主神と名乗って、我が女のスセリ姫を嫡妻として栄えよ。こいつめ」というものであったという。「大国主神と名乗れ」という命令が何を意味するかは後に論ずることとするが、ともかく、これはスサノヲが、二人の結婚を認め、オホナムチに後継者の資格をあたえたことを意味する。こうして、オホナムチは地震を起こす呪具を身につけ、スサノヲの地震神としての神格を受け継いだのである。
スサノヲのもっていた「琴」が地震の呪宝であったことは「地が震り来ば 破れむ柴垣」「琴頭に 来居る影姫 玉ならば」という記紀歌謡にもかいま見える。この歌は大王武烈が太子のころに、影姫という美女を豪族の平群臣鮪との間で争った時の歌として伝えられているものであるが、歌題の中心は琴である。つまり二人の男が一人の女をめぐって争っており、一人の男が琴をもってかきならし、他の男に対して、「おまえの柴垣などは、この音で破ってしまうぞ」と述べ、女のことを自分の琴頭に来る「玉」であると称していると読めるのである。この歌謡は琴の地震を呼び起こす呪力を歌ったものではないだろうか(『日本書紀』武烈前紀)。
この解釈が歌謡の解釈として成立するかどうかは今後の検討が必要としても、文学史の三田村雅子氏の教示によれば地震を引き起こす「琴」という観念はたしかに存在した(座談会「平安時代の天変地異と『源氏物語』」、『天変地異と源氏物語』翰林書房二〇一三年)。一〇世紀の『宇津保物語』のテーマはそこにあったという。つまり、『宇津保物語』の「俊陰」巻は、遣唐使となった清原俊陰がペルシャで天女から琴を与えられる話で、俊陰の琴は多くは天皇に献上されるが、もっとも威力の強い琴は娘に伝領される。そして、俊陰の死後、娘は子どもと一緒に洛外にでて木の「うつぼ」に棲む運命になるが、そこで東国の武士に襲われそうになった時に、琴をかき鳴らした。するとと、山が崩れ、その武士を山の下に埋めてしまった。この琴は「山くずれ地割れさけ」るという力を持っているというのである。
このスサノヲとオホナムチの遭遇の物語で、もう一つ重要なのは、スサノオが逃げていくオホナムチを黄泉比良坂まで追ってきて、その上から大声でオホナムチに呼びかけたという設定である。
問題は、この黄泉比良坂の理解にあるのであるが、これを考えるためには、イザナミの死の物語から確認が必要である。つまり、『古事記』ではイザナミが葬られたのは「出雲国と伯耆国との堺の比婆山」であったという。イサナキは、彼女を追いかけて「黄泉国に追ひ往きましき」といい、イザナミは来訪した男を「殿の?戸より出で向かふる」という。山に「葬りまつりき」とある以上、地中に埋めたというのが素直な読み方であろうが、山のどこにどう埋めたのかまではわからない。女神が男をむかえた「殿」というのも何を表現してるのかは不明である。ただ、イサナキはその中に入るのに「火」を灯したというから、「殿」の内部は暗かったのであろうか。
そしてイサナキは黄泉の国を逃げ出すのであるが、そこと現世の間には「黄泉比良坂」という坂があったという。イサナキは、怒った黄泉の雷神に追われて、その坂の下(「坂本」)まで逃げてきて、そこに立っていた「桃」の木の桃をとって雷神たちに投げつけ、桃の呪力によって、どうにか彼らを撃退するのに成功した。雷神たちは「ことごとく坂返りつ」、つまり坂を逃げ帰ったという。その時、イサナキは、「桃」の木に対して、「葦原中国にあらゆるうつしき青人草の、苦しき瀬に落ちて患へ惚む時に助くべし」と語ったというから、この坂は、黄泉国と「葦原中国」の堺であったのである。この黄泉比良坂がオホナムチが逃げ下った黄泉比良坂と同じものであることは明らかである。イザナミ・イサナキの物語においても、スサノヲーオホナムチの物語においても、その国と現世のあいだには「黄泉比良坂」という長大な坂が存在するとされていたのである。
この黄泉比良坂という坂は、イザナミ・イサナキの物語の描写からしても葦原中国にむかって下がってくる坂である。逆にいうと、現世から黄泉国にいくためには坂を上らなければならない。リルケのドゥイノの悲歌のいうdie Berge des Ur-Leids(the mountains of pain)、原初の痛苦の山を上らなければならないという訳である。スサノヲーオホナムチの物語でも、スサノヲは、逃げていくオホナムチ・スセリ姫を「黄泉比良坂に追ひ至り、遙に望ケて」決別の言葉を叫んだのだが、この「遙に望ケて」というのが坂の上から下にむけて叫んだというのが適当であろう。根の国と葦原中国との間にある黄泉比良坂という「坂=堺」は、こちらに向かって下がってくる坂なのである。
このことは、早く益田勝美『古事記』(岩波書店、シリーズ『古典を読む』、一九八四)が「ヨモツヒラサカは、当時の観念としてはヨモツクニが高く、人間界が低い関係で、山中の地下から地上へ下ってくるというイメージだろう」といっている通りである。「山中の地下から地上へ下ってくる」というのは意味が通りにくいかもしれないが、益田の含意としては、「現に生きている人たちの地上世界をとりまいて、周縁地域の地下に(傍点筆者)、中心からは『四方つ国』と呼ばれた死者たちの住む世界が観念上存在していたようである」ということである。つまり山の地下からまず山の上にでてきて、それから坂を下って、この世界にもどったということである。このような見方は最近では考古学の北條芳隆によって鮮明に打ち出されている**134。
「山中の地下」から一度、地表にあがってから山の坂を下りてくるというのであるから、これは山頂に地上への出口、地下への入口の「穴」があることを意味する。これが火山の景観であることはいうまでもない。スサノヲもオホナムチも火山の神でもあったのである。
C火山地震神としてのオホナムチ・スクナヒコナ
(1)オホナムチの神名の理解--前提として
このようにしてオホナムチはスサノヲの地震・火山の神という神威をうけついだということになるが、しかし、オホナムチ=大己貴神について本格的に論ずるためには、松村・石母田の見解にふれて紹介したようなこの神の名の語義についての議論を処置する必要がある。
問題の中心は、そこでも論じたように、オホナムチの「ナ」の理解になる。そして、これについては敷田年治『古事記標注』が「地」の意味としたのを採用したい。新村出によれば、その語源は、ツングース諸民族が「大地」を「ナ」naとしたことにある**145。それは「ウブスナ(産土)」の「土」(な)に通ずる言葉だという。新村はさらに「ナ」につけられた「ゐ」は、一種のStability、固定性を示す用語だという(新村出一九七一「天と地」同全集4)。つまり、雲の静かな状態をクモヰ(雲居)、田圃の田をタヰ(田居)といい、また敷居、屋根居などという言葉があるように、「ゐ」は、漢字でいえば「居」であって、「なゐ」とは漢字であらわせば「地居」となる。「地居震る」「地居動む」というのが「地震る」「地動む」の正確な表記なのであるが、それが忘れられて、地震自体のことも「なゐ」というようになったというのが新村の説明である。ようするに「大地=ナna」というのは、自然としての大地という意味であることになるだろう。前述のように「ムチ」は貴人を表現する接尾語であるから、これを前提とすると、オホナムチとは「大きな大地を象徴する尊貴な神」いうことになる(ただし、この「ナ=大地」という説を採用する注釈類は多くない。問題は残るが、語尾に「な」をもって土砂を表現する語の例も重視して、これを採用した。なお、私は「土地範疇と地頭領主権」という論文(『中世の国土高権と天皇・武家』所収)で「地」という言葉が、平安時代になっても、網野善彦がいうように自然としての大地の意味で使用されていることを論じたが、問題はそこにつらなっていく)。
(2)オホナムチの火山神としての本質
さて、オホナムチの神名については、もう一つの問題がある。つまり、前述のように、石母田は、大己貴の本来の神名の訓はオホアナムチであるとした。そして、この神名は「穴」に中心があり、オホナムチとは大きな洞穴=石窟に棲む地霊の意味であるとしたのである。これが成立しがたく、その読みはオホナムチと考えるほかないことはすでに述べた通りであるが、益田勝実は名著『火山列島の思想』において、この石母田説に賛同し、それを前提として「アナ」はより具体的には火山火口を意味するとした。この理解は石母田説同様に成立しがたいが、しかし、オホナムチが火山神としての性格をもつことを指摘したことは益田の卓見であった。それはスサノヲが火山神としての性格をもつという前記の想定からしても自然なことであり、逆に、これによってスサノヲの火山神としての性格を確証することになる。
益田が論拠としたのは、大隅の火山神オホナムチであった。この神の活動は七四二年(天平一四)の大隅国で六日間にわたって太鼓のような音が聞こえ、同時に大地が大きく震動したという事件から始まった。このとき、聖武天皇は、使者を遣わし、「神命」を聞かせようとしたという(『続日本紀』)。この事件は、爆発音がありながら、目に見える噴火はないまま大地が震動したというのだから、おそらく海底火山の噴火にともなうものだったのではないだろうか。というのは、それから二〇年以上も経ってからのことであるが、聖武の娘の孝謙女帝が再即位した直後、七六四年(天平宝字八)十二月に、大隅国の国境地域の信尓村の海で大噴火がおこったのである(『続日本紀』)。
「西方に声あり。雷に似て、雷にあらず」といわれているように、爆発音は奈良にまでとどろいた。その被害は民家六十二区と八十余人に及び、その七日後に、煙霧が晴れると三つの火山島が出現していたという。この噴火は地質調査をふまえた歴史火山学的な研究によって、桜島の東部の鍋山を形成した噴火であることが確定している(小林哲夫「桜島火山の地質:これまでの研究の成果と今後の課題」『火山』27巻4号)。その噴火の様子はあたかも神が「冶鋳」の仕業を営むようであり(「冶鋳の為のごとくなるあり」)、遠望すると島のつながりが神の棲む「四阿」のようにみえたという。「四阿」は別荘を意味するのであろうから、おそらく神の本宅は、桜島ということになるのであろう。ここには火山に神が棲むという観念が明瞭にあらわれている。そして、しばらく後の史料に「去る神護年中、大隅国の海中に神ありて、嶋を造る。其名を大穴持神といふ」とあって、この島を造成した神がオホナムチであったことがわかるのである(『続日本紀』七七八年(宝亀九)十二月)。
この噴火記事は、この列島における火山活動を具体的に描いた初見史料としてきわめて貴重なものである。とくに重要なのは神の仕業が「冶鋳(やちゆう)」、つまり鍛冶と鋳造を営むようであったという部分であろう。益田勝実は残念ながら、この「冶鋳」という言葉の意味を見逃してしまい、オホナムチの鉱業神・金属神としての性格を見逃してしまった。またこの「冶鋳」は倭国神話の最高神タカミムスヒが「預ひて天地を鎔造する功あり」とされていたことに直結する(『日本書紀』顕宗紀三年条)。この「鎔造」とは鋳型による鋳造を意味する。タカミムスヒは、天地創造、世界創造の神として、天地を焼き焦がすような巨大な火を駆使して、天地を鋳造・冶鋳するかのように創造したのである(詳しくは本書■■■頁を参照)。このような巨大な火の観念が大隅の海中火山を噴火させたオオアナムチの神格にも貫いていたことになる。ようするに、これはギリシャ神話におけるヘファイストゥス(Hephaiatos)、ローマ神話における火山Volcanoの神ヴァルカンVulcanが火山底に棲む鍛冶の神であることと同じである。スサノヲとオホナムチは倭国神話における火山の神であり、ヴァルカンVulcanであったのである。
(3)巨人神オホナムチの地震神としての本質
さてオホナムチがスサノヲの根の国から逃げ出した後、彼は基本的にオホクニヌシと名乗り、神話は国造りの物語に入る。後に詳しくふれるが、『古事記』ではオホクニヌシは松村や石母田がいう国作りの英雄神を象徴する神名であるといえよう。ただ、問題は、この場合、国造りに協力する神が最初は少彦名命(スクナヒコナ)であったが、途中でスクナヒコナは去り、三輪山の神に交替することである。そこで、ここでも、この国作りの神話をスクナヒコナが協力する第一段階と、三輪山の神が協力する第二段階にわけて検討することにする。
ここで最初に注意すべきなのは、『古事記』における国作りの物語は基本的にはオホクニヌシの神名のもとに語られるとはいっても、石母田がいうように(二二二頁)、オホクニヌシがスクナヒコナとともに登場する場合は一貫してオホナムチ+スクナヒコナという神名が使われ続けることである。これは神話的な国造りにおいて、その第一段階においては、自然的な大地の神としてのオホナムチの性格が実際には強く残ることを意味しているのではないだろうか。
石母田は、津田が、このような二神の協力は神代史の神話テキストが一度できあがってから添補されたものに過ぎないとしたことを批判して、すでに記紀成立期の「民間」において、この二神が「特定の山や谷の創造者」として抽象化されないままに未発達ではあれ「人格神」として意識されていたとする(二二五頁)。これは松村のスクナヒコナ論(『日本神話の研究』三巻第十三章「少彦名命の神話」)を参照した結果であり、石母田が津田と松村の仕事の丁寧な突き合わせから自己の議論を導いていることを示す点でも興味深いことである。
実際、『万葉集』にも「大穴持命少御神の作らしし妹背の山」(四・一二四七)、「大汝少彦名の神こそは名づけ始めけめ」(六・九六三)、「大汝少彦名のいましけむ志都の石室」(三・三五五)、「大己貴少彦名の神代より」(一八・四一〇六)などとあってオホナムチという神名こそが一般的である。そもそも大国主命=オホクニヌシというのはほとんど『古事記』にしか登場しない神名であり、いわば『古事記』イデオロギーを代表する神名であるように思う。
さて、問題は、この二神の協力の内容をどう考えるかということであるが、よく知られているように、二神の関係は、オホナムチが国作りを開始しようとして出雲の海辺にたたずんでいたときに始まる。そこへ、波頭をつたってガガイモの船のって鵝の皮の服を着た小人神がやってきた。オホナムチが、その素性をタカミムスヒの妻にして大地の姥神であるカミムスヒに問い合わせたところ「たしかに、この子は私の子。あまりに小さいので、私の指の間から落ちてしまった子だ。おまえと兄弟になって、国を作り堅むであろう」と述べたという。後にもふれるが、私は、この「二柱の神相並びて、この国を作り堅めき」、つまり「作り堅む」ということによって、『古事記』は、国作りの第一段階を象徴したと考える。
それ故に、ここでは二神の対照において、二神の神格を考察することが必要になるのであるが、それはいうまでもなく、まずは大と小の対照であろう。つまり、まずオホナムチは巨人である。カミムスヒが「汝葦原色許男命と兄弟と為りて、その国を作り堅めむ」とスクナヒコナの役割について述べていることからいって、小人スクナヒコナに対応する場合は、その巨人としての姿は「葦原醜男」―葦原で活動する強勢な男―と呼ばれたらしい。彼が『播磨国風土記』において巨人として登場する際にしばしば「葦原醜男」と呼ばれているのはそのためである。『風土記』は、彼が喧嘩や遊び、恋愛をし、その腰掛けたところ、置いたもの、さらには米粒から糞まで、その落としたものが山や丘陵になっていると語っている。石母田正は「国作りの神としてのオホナムチは山・岡・峯との関係が不可分である」「むしろ山作りの神である」として、この巨人の具体的なイメージは柳田国男が発掘した全国各地に残るダイダラ坊伝説によく現れているとしている(石母田「古代文学成立の一過程」)。ダイダラ坊とは大地に働きかけ、山を盛り上げ、山を蹴開き、湖水を流し、足跡を池として残すような巨人である。『播磨国風土記』には託賀郡の地名伝説として、天に頭がつっかえてしまうような巨人が播磨国で初めて身をのばして行くことができた、そこで「高」が郡名になったのだという一節があるが、柳田は、これをダイダラ坊伝説の原型としている。播磨がスサノヲ・オホナムチの重要な活動場所であることからして、石母田の想定は正しいだろう。『万葉集』にはオホナムチについて「多胡の嶺に寄せ綱延へて寄すれども」という歌が残っており、このように大地を動かし地形を改変するというのは、巨人「葦原醜男」(オホナムチ)にとって本質的なことであったと考えてよい。
『出雲国風土記』(意宇郡)には「五百津?々猶所取々而(五百津?の?なお取り取らして天の下造らしし大穴持命」ともあって、オホナムチは五百箇の?(‚·‚«)?(すき)を動かして大地を改造する巨人の力をもっていると表象されている。それは「童女の胸?取らして大魚のきだ衝き別けて、はたすすき穂振り別けて、三身の綱うち挂けて、霜黒葛くるやくるやに、河船のもそろもそろに、国来々々と引き来縫へる国」■■■という詞章で知られる有名な国引き神話と同じものである。石母田のいうように、ここには人間の労働、集団労働と鉄器の威力が歌い上げられているといってよい。これは「古代文学成立の一過程ーー『出雲国風土記』所収「国引き」の詞章の分析」と「国作りの物語についての覚書」の二本の論文により明らかにされたことであるが、神話テキストのなかにこのような関係を過不足なく読みとることに成功した石母田の洞察力は素晴らしいものがあると思う。
しかし、石母田のいうように、オホナムチがスサノヲから奪取した「琴」を含む宝器は「国作りをするために必要な手段」(一八〇頁)として位置づけられている。それ故に、琴に大地の鳴動と地震を引き起こす力を仮託されている以上、このような大地を動かし地形を改変する力の原印象に、この神の地震神としての側面が横たわっていたと考えるのは自然なことであろう。やや時代は下るが、『今昔物語集』(巻二四ー一三)には死去した文徳天皇のための陵墓を占定しようとした陰陽師を、「千万の人の足音」のような地鳴りを響かせて地神が追いかけたという説話がある。その地神は「地震の振るように暫し動きて過ぎぬ」というから地震の霊なのである。彼らの巨歩はダイダラ坊が国土に残した足跡が池になったというイメージと同じものであろう。石母田が引証している柳田国男の蹴破伝説についての言及をみても(「ダイダラ坊の足跡」『定本柳田国男集』⑤筑摩書房)、国作りの原動力として地震の自然的な力が印象されていたことは確実であると思う。
■■■ オホクニヌシは地震神であり、その国作りは地震を手段としていたことは「石母田正の英雄時代論と神話論を読む――学史の原点から地震・火山神話をさぐる」で書いた。それと同じことだ。鯀はスサノヲ、その子の禹はオホクニヌシということになる。
このスレッドを表示
中国神話も洪水神話。倭国神話でも同じ。天浮橋からみると、下は泥沼。重要なのは鯀(こん)が帝の俊のもつ「息壌(いきづくつち)」を盗んで洪水を防いだとされること。山海経郭注は「漢の元帝のとき、徐県で地踊ること長さ五・六里、高さ二丈、これが息壌か」とする。これは地震断層の露頭だろう。
(4)スクナヒコナの土壌神としての本質
これに対して、スクナヒコナは小人神である。『古事記』は、スクナヒコナの正体が何なのかについてタニクグ(谷蟆)**156に問い、クエビコ(案山子)に聞いたという民話を語る。タニクグとは山椒魚のことで、谷の神であろう。クエビコは木霊の神であろう。これは、つまり谷の神に聞き、クエビコの記憶を呼び起こせば世界のことは何でもわかるというような観念を示す物語である。より具体的には谷が鳴動して、クエビコがそれを繰り返すという訳である。人々は倒木の響き、落雷、地震の鳴動、噴火音などの大地の音というべきものに敏感であった。地震の鳴動の史料などにも谷に響くという表現は多い。これはスクナヒコナが大地に関わる神格をもっていることを意味するのかも知れないが、しかし、スクナヒコナの神格が具体的にどのようなものであるかは分からない。
管見の限りでは、これまで、これについては了解可能な見解はないように思う。松村は、その神名の解釈についての諸説として①佐(補佐)とする説、②宿弥と同義で直系の意味とする説、③大に対する小であって、小名であるという本居の説、④「『少』+『国土』として大なる国主に対する小なる国主の意とする言語学の金沢庄三郎の説、⑤「大兄」に対する「小兄」であるという説、⑥体躯の矮小の意とする説などを上げ、どれも納得できないとし、不分明とするほかないとしている。結局松村は、この神を体外魂・遊離魂を小人神の印象で表現した物とするのであるが、これはいわば理屈であって具体的な説得性はないように思う。それはオホナムチを文化的英雄神としたのに対応する文化論的な見方に過ぎない。しかし、オホナムチを地震などの威力をもつ「大+地+貴」なる地霊と考える即物的な理解が正しいとすれば、この理解にそのまま従うことはむずかしい。
さて、敬称を意味するムチ(貴)とヒコ(彦)がうまく対応する以上、やはり問題の解明はオホナとスクナの対比から出発すべきであろう。松村は、スクナヒコナのナを「地」の意味の名と理解しようとしない。松村が、『少』+『国土』として大なる国主に対する小なる国主とする金沢庄三郎の説は、スクナヒコナの支配する小国というものを想定できない以上、成立しがたいとするのは、その通りであろう。しかし、ナを「国」でなく「地」と理解すれば、そこには問題はないだろう。前述のように松村が「国」と「地」を区別しないことが錯誤のもとなのである。オホナのナが「地」それ自体であるならば、スクナのナも「地」を意味する可能性は否定できない。スナは砂=素土、「ヘナ」は赤土**167、「ヨナ」は火山灰であり(『日本国語大辞典』小学館)、関西では「石な」とは小石のことをいう(松村『日本神話の研究』第二巻一四五頁)。またナの音はニと母音の変化を行って「白土」はシラニ、赤土はアカニ、青土はアヲニ、殖土はハニとなる。ようするにオホナムチは「大きい地霊」であり、「スクナ」の厳密な語義はすぐにふれるような問題を含むとしても、そこに「小さいナ・地」という含意をみることは許されるだろう。
この点で注目されるのは『続日本後紀』(嘉祥二年三月)に「日の本のやまとの国を かみろぎの少彦名が 葦菅を殖え生ふしつつ 国固め造りけむより」とあることである。スクナヒコナがガガイモの船に乗って登場したとか、粟の茎にはじかれて常世の国にいったなどという物語は、彼が草木のような小さな植生に関係する存在であったことを示すが、「葦菅を殖え生ふ」というのは葦菅の育成を意味する。そして、「葦菅を殖え生ふし、国固め造り」とは「葦原中国」に土壌を固定していくことではないだろうか。
『播磨国風土記』にはオホナムチとスクナヒコナが糞をせずにいるのとハニを担うのとどちらが耐えられるかという遊びをし、結局、オホナムチの方が耐えられずに休んで糞をしたという物語がある。巨体を休まずに動かすエネルギーと小人の耐久力のどちらが強いかという話であるが、このエピソードは、火の神カグツチを生んで傷ついた大地母神イザナミが苦しんで排泄した糞が埴山姫という土壌の神となったという物語を想起させる。オホナムチ・スクナヒコナの国作り神話を生き生きと語る『播磨国風土記』の各条におのおの「土」の豊度の規定があるのは無意味なこととは思えない。そこからみると、この『播磨国風土記』の一節は、彼らがこのようにして土壌を作っていったという民話でもあるのではないか。神話時代の人々は、どのようにして豊穣な土壌を形成するかについて意識的であったことはいうまでもないのである。
(5)「豊葦原水穂国」か、「瑞穂国」か――本居宣長の農本主義
これは「葦原醜男」という名をもつオホナムチのみではく、スクナヒコナも「葦原中国」という国土観に密接した神格であったことを示唆する。最近、西谷地晴美は「豊葦原水穂国」といわれる場合の「水穂」の「ホ」は「秀」であって「葦原の広がる水の豊かな国」と理解すべきことを明らかにした(西谷地晴美「水穂の国の変換と統治理念」(『古代・中世の時空と依存』塙書房、二〇一三年)。「豊葦原水穂国」という国土観は湿性の土地、湿潤な国土を表現するものなのである。
西谷地晴美によれば、『古事記』と『日本書紀』の神武、崇神、仁徳などの統治論理に深く関わる記事を比較対照すると、たとえば「農は天下の大きなる本なり」(崇神紀)のような文言が『書紀』には現れるが『古事記』には現れない。これは『古事記』と『日本書紀』の世界観の違いを表現している可能性があるという(西谷地晴美「水穂の国の変換と統治理念」(『古代・中世の時空と依存』塙書房、二〇一三年)。それはおそらく『古事記』は神仙思想あるいは老荘思想の影響が強く、『日本書紀』には儒教的な統治論理の影響が強いことと関係しているのであろう。この西谷地の指摘は宣長の『古事記』の読み方を根底から突きくずすことになるだろう。
西谷地は『古事記』では「豊葦原水穂国」という言葉が使われるのに対して、『日本書紀』では「豊葦原瑞穂国」という言葉が使われていると指摘している。つまり『古事記』ではオシホミミへの降臨の命令は「豊葦原の千秋長五百秋の水穂の国は、吾が御子、正勝吾勝勝速日天忍穂耳命の知らす国ぞ」とあり、ホノニニギへの降臨の命令は「この豊葦原の水穂の国は、いまし知らさむ国ぞ」となっている。西谷地の詳細な語彙分析によると、「豊葦原の水穂の国」自体には水田稲作という意味はなく、「葦原の広がる水の豊かな国」と理解するのが正しい。「水穂」とは、「水秀(みずほ)」であって「水に豊かな」という意味なのである。『古事記』は「豊葦原の水穂の国」という言葉をもって開発の対象としての列島の湿潤な国土を表現したのだと思う。それは列島の大地の自然的あるいは地質学的な特色を語った言葉なのであろう。
これに対して『書紀』が「豊葦原千五百秋瑞穂国」という「瑞穂」の「瑞」は「祥瑞」の「瑞」で「めでたい稲穂」ということであるが、西谷地は「豊葦原水穂国」ならば、「葦原の広がる水の豊かな国」であって自然であるが、「豊葦原瑞穂国」というのは「葦原の広がるめでたい稲穂の国」となるから、これは何とも訳しがたい矛盾をはらんだ言葉であるという。ようするに『書紀』が「水秀」を農本主義的な観点から「水穂」→「瑞穂」と机上で置き換えたために生まれた矛盾なのである。
ところが、現在、『古事記』のどの注釈書においても、『古事記』の「豊葦原水穂国」も、『書紀』の「豊葦原瑞穂国」も、例外なく同じように「豊かに稲穂のみのる国」「瑞々しい稲穂のみのる国」と理解されているという。西谷地はこの史料批判の欠如は研究者の一種の無思想性を表現するものとしつつ、その理由が宣長の『古事記伝』にあることを正確に指摘している。つまり、最初に、この『古事記』の「豊葦原の水穂の国」を「みずみずしい稲穂の豊かな国」と解釈したのが『古事記伝』(一三巻、三葉)なのである。こういう読み方の背景には、宣長が「水穂国と云号も、此の齋庭の穂に由縁あることなり」として、その解釈の起点を天孫降臨神話における「齋庭の穂」においていたことについては第一章を参照されたい。
なお、『日本書紀』で使われた「瑞穂国」の用例の中でもっとも重要な事例が、アジア太平洋戦争で利用されたアマテラスの「天壌無窮の神勅」における「豊葦原千五百秋瑞穂国(とよあしはらちいほあきのみずほのくに)は、是、吾が子孫の王たるべき地なり」(『日本書紀』異書一)であったことも指摘しておきたい。この「天壌無窮の神勅」が『書紀』の天孫降臨神話条の中では加上されたアマテラス系の文飾であることは本書第一章で述べたが、この「天壌無窮の神勅」の皇国史観による利用には、宣長の責任もあったというのが深刻な問題である。宣長は、「天孫降臨」神話の中にまぎれこんだ水田中心の農本主義的な記述は、『日本書紀』に独特なイデオロギー的な加筆であって、後に加上されたものであったことを見逃し、しかもそれが『古事記』本来のものであると解釈するという二重の錯誤をおかしたのである。
(6)土壌神スクナヒコナと硫黄・焼畑
オホナムチとスクナヒコナのペアは、このような国土を「国作り堅す」神々なのであって、そこには地形を作るということのみでなく、それに対応する土壌やその特定の豊度を作り出すことをも含んでいたということになる。この二人の神は、山を作り、土を動かすエネルギーをもった巨神と草木に宿って土壌を作り出す小さな精霊、大地の巨人神とそれに付着して動く土壌の小さな精霊という訳である。
ただし、スクナヒコナの神名の理解にはまだ問題が残っている。松村のいうように、オホナとの対比で「スクナ」が「小さい」という意味を含んでいることは否定できないだろうが、「オホナ」と比べて「スクナ」という語の構成は分かりにくく、「スク+ナ」の合成語というよりも「スクナ」で一語であるように見えるからである。
こう考えた場合に、スクモという言葉の理解が重大となる。この言葉は多様な意味をもっているが、『日本国語大辞典』(小学館)はまず「つのくにのなにはたたまくおしみこそすくもたく火の下にこがるれ」(『後撰和歌集』)、「すくもびのけぶりもいとどたつはるをもゆるなげきとかすめてしがな」(『能宣集』)**178などの用例をあげて、葦・茅などの枯れたもの、葦の根、さらに藻屑などをスクモというとしている。まさに葦原の植生が腐朽し、炭化して土壌が形成されていくのであるから、これは「葦菅を殖え生ふ」土壌の神スクナヒコナの神格に直結するものであろう。すでに九世紀の『新撰字鏡』の段階で籾殻や糠をスクモといい、地虫は「須久毛虫」と説明されているから、枯れた葦・茅や堆肥様のものもスクモといっていたに相違ない。「スクモ」のモは、作毛、地毛、土毛などの古くからある言葉と同じ、草や繊維状のものを意味すると考えることができるであろうから、「スクナ」と「スクモ」は音韻からいっても共通する意味をもつことは確実である。
しかし、さらに、このスクモという言葉が、「すくも火」という燃えふすぼる火との関係で秘かな恋情を語るのに好んで使われていることに留意しなければならない。すでに早く柳田国男は「燃ゆる土」という短文で、塵芥などの可燃性のものを含んだ燃えやすい「土」、あるいは泥炭などを「スクモ」ということに注意している(『定本柳田国男集』三〇巻、筑摩書房)。『日本国語大辞典』(小学館)を参照すると、たしかに泥炭という用例は多く、『松屋筆記』には「薪土」とあり、『大和本草』に「すくも〈和品〉近江国野州郡老曾村は〈略〉其辺の地をほればすくもと云物多くいづ。土にあらず、石にあらず、木にあらず。柴の葉のくさりかたまりたるが如し。火にてたけば能もゆる。里人これをほりて薪とし、是をうりて利とす」とあるのは、湿地帯に形成される泥炭ともいいにくいような可燃性の土の実態をよく示している。時代を下る例であるが、「スクモイシ」という言葉が「石炭の異称」とされていることも参考になるだろう(『和英語林集成(初版』)。柳田が紹介した『四隣譚藪』(一)なる本に「土くれにて燃ゆるもの也。水田に地しぶ浮きたるところに出る。春に至りて蘆のきざしをふくめるや、焼き捨つるに火消えず、硫黄の気多し」とあって、とくに硫黄気が強調されているのが示唆深い。
さらに興味深いのは、折口信夫が柳田の下で開かれた連歌会で「手のひらにすくもはたけば光る也」という上句を読んでいることである(『定本柳田国男集』筑摩書房、二六巻五四四頁)。これはオホナムチがスクナヒコナにあった時、スクナヒコナはオホナムチが手の上に乗せて玩んだのに怒って、飛び上がって頬にかみついたという『日本書紀』(巻一第八段一書第六)の一節、またスクナヒコナがカミムスヒの掌中から跳ね転んで行方が知れなくなったなどという『古事記』の一節を彷彿させる。この話を折口が「手のひらにすくもはたけば光る也」と脚色したのは、スクモというものの可燃性の性格を意識していたのであろう。
小人の精霊の通則として、スクナヒコナは、この種の強い反発力をもつものと考えられていた訳であるが、「手のひらにはたけば光る」爆発性の可燃の「ナ=土」から連想されるのは硫黄である。最近、近代史家の小路田泰直は、全国の硫黄泉のあるところ、出羽蔵王の酢川温泉神社や紀伊白浜温泉、伊予道後温泉、摂津有馬温泉には少彦名命が祭られていることに注目して、スクナヒコナは硫黄の神だと指摘した。そして硫黄は皮膚病その他に薬効があり、薬問屋の町として栄えた大坂道修町の鎮守が少彦名神社であるのもそのためであるという(小路田『邪馬台国と鉄』)。
火山と硫黄は切っても切れない関係があることはいうまでもないから、この小路田説を前提とすると、スクナヒコナが火山の神としての性格をもつオホナムチと対になることはきわめて理解しやすい。火山の硫黄臭さである。大地の巨人神と土壌の小精霊は火山の巨人神と爆発性硫黄の微細な精霊でもあったということになる。
そもそも『伊豆国風土記』によれば、この二人の神は「我が秋津洲に民の夭折ぬることをœà(‚ ‚í‚ê)憫(あわれ)み、始めて禁薬と湯泉の術を制めたまひき。伊津の神の湯もまたその数にして、箱根の元湯これなり」と讃えられる医術と温泉の神である。ここでは火山・温泉・硫黄がセットとしてあらわれる。従来、オホナモチ・スクナヒコナの国作り神としての性格と温泉や医術の神である側面は、別個のものとして取り扱われていた。たとえば石母田正はオホナムチの自然の開発神としての側面と医術の神、King-magicianとしての側面を区別したが、それは区別されたままで統一的に捉え直された訳ではない。しかし、オホナモチ・スクナヒコナの多様な側面の基底に、その火山神、大地の地霊としての側面が存在することを見逃してはならないと思う。
こう考えると、有名な因幡の白ウサギの物語でオホナムチは蒲の穂の花粉をもってウサギの肌を治すのであるが、蒲の黄色い花粉は止血剤としての薬効をもつ。それと硫黄の黄色い粉のイメージは重なっていたのであろう。この意味で、『古事記』(中)に「くしの神、常世にいます、岩立たす、少名御神の豊寿き」と歌われるように、スクナヒコナは「薬」の神なのである。なお、この歌で、スクナヒコナが「岩立たす」と讃えられるのも岩をも飛ばすような硫黄の爆発力を表現したものであろう。普通、この「岩立たす」という言葉は岩に示現するという意味でとらえられるが、「立たす」という他動詞形にそくして理解は可能である。スクナヒコナの「岩立たす」とは「岩をも立たせる」というそのままの意味ではないだろうか。
ただ、それにしてもスクナヒコナという神名の理解はむずかしい。小路田は、東北地方に多い「酢」「酸」のつく温泉や地名の「酢」「酸」はすべて「ス」と読むことを根拠にして、「スクナ」の語源は「酢粉」(スコナ)であるという。たしかに、「スクナ」の「スク」は「少ない」という意味のほかに「ス=酸」の意味を含んでいる可能性、あるいは可燃性のものという意味が潜在している可能性があるかもしれない。しかし、「酸粉=スコナ」という解釈については、「スクナ」「スクモ」から「ナ」と「モ」を外した語幹部分の「スク」の語義の解釈と関わり、すぐに賛同することはむずかしい。
むしろ、この神の神格はより広い視角から考えるべき点が多い。つまり、松村による諸説の整理の後に大林太良は、スクナヒコナを「粟の穀霊」とする見解を提起した。「『日本書紀』宝剣出現章第六の一書によれば、スクナヒコナは淡島に行き、粟の茎にのぼって、それにはじかれて常世の国にいったという。また『伯耆国風土記』の逸文にも、相見郡粟島にスクナヒコナが粟をまき、その粟に乗って常世の国へととび渡ったとしている。これらからみて、スクナヒコナは粟の穀霊だったと考えてよいだろう」というのがその見解である(大林『稲作の神話』一六頁)。粟は焼畑の耕作物であることはいうまでもないから、これを敷衍すればスクナヒコナは焼き畑の精霊であるということになる。そしてスクナヒコナの本質が土壌の神という点にあったという前記の推論が正しいとすれば、スクナヒコナは焼畑の土壌の神、炭化した植生と腐葉土を体現する精霊ということになる。
そもそも、大林の見解に依拠してすでに論じたように、倭国の農業の原初に存在した農業の女神は焼畑の女神オオゲツヒメであった。そうであるとすれば、本来、このスクナヒコナは女神オオゲツヒメとペアになるような小人神、土壌の精霊であるということになるのではないだろうか。日本の地質の上層を覆っている、「黒ボク土」といわれる表土は、縄文時代以来、長期にわたって焼畑耕作が営まれたことによって形成されてきたという(山野井徹『日本の土』築地書館、二〇一五年)。人々は火山灰や風成土壌の上にある黒ボク土の特性を生産と労働のなかで認識していたであろう。それはいわば環境的自然のなかに人間の労働が対象化されていることの表現であったのではないか。オオゲツヒメとスクナヒコナのペアは、神話意識の内部にそのような知識が包含されていたことを示す神格なのではないだろうか。
オオゲツヒメが焼畑の粟神であると同時に火山の阿波神でもあったことは前述の通りである。また草木・沙石が「自ずからに火を含む縁」は、火神のカグツチの血が諸方に飛んで染みついたためであるという、前述した『日本書紀』の所伝も火山伝説の一つであろう。この二神が焼畑の神話を代表していたということは、人々にとって焼畑が火山と切っても切れない縁のあるものであったことを示すように思うのである。
(7)津波の光と海から来た土
スクナヒコナの神格に関わる問題で最後に残るのは、最初、スクナヒコナが海から登場したことである。『古事記』にはスクナヒコナは、オホクニヌシが出雲の御大御前にいた時、「波の穂より天の羅摩船に乗りて(中略)帰り来る神」であったとある。一一世紀くらいから、日本海沿岸にはいわゆる「寄物」(漂着物)の史料が多いが、スクナヒコナはそういう海からの「寄物」の神だったのである。そして「国を作り堅め」る仕事が終わると海の彼方の「常世の国」に去ったという。その代わりに同じく海の向こうから、「海を光して依り来る神」がやってきた。この神はオホナムチと同体の神であって三輪山の雷神となり、「御諸山の上に坐す神なり」として大物主神となったことはすぐにふれるが、この神が海を光してやってきたということは、スクナヒコナもおそらく同じような光とともに登場してきたのであろう。それは、常陸国大洗磯前にオホナムチ・スクナヒコナが来臨した際、「夜半に海を望むに、光耀、天に属す」とあることからもわかる(『文徳天皇実録』斉衡三年一二月)。スクナヒコナは実態としていえば「火ーー硫黄」の神であるから、スクナヒコナの乗ってきた「波の穂」というものも津波、あるいは大きな高波であったとすれば、その様子はまったく同じパターンである。
これがいわゆる海中他界観といわれるものであることはいうまでもないが、土壌神スクナヒコナが海からやってきたというのが興味深いところである。神話学によれば、海中に原初の「土」が存在したという「土」の起源神話が、東ヨーロッパから、さらに北米にまで広く分布しているというが、スクナヒコナの神話はその一類型であるということになろうか(大林太良『神話学入門』七一頁)。スクナヒコナの神話は、広く見れば、それが、これは天地の始めの大洪水の混沌の中に最初に萌え騰がったという「葦芽」に付着した原初の泥土のイメージに連なるものなのではないだろうか。列島の水穂の国、葦原中国の神話的原景である。
D生業神・性神としてのオホクニヌシ・大年神
さて、オホクニヌシの国作りの第二段階は、スクナヒコナにかわって、三輪山のオオモノヌシの協働によって動き出す。ただ、それを論ずるためには、まず、オオアナムチの場合と同様に、オホクニヌシという神名そのものの理解から始めなければならない。これ以降、『古事記』はオホクニヌシという神名のみをもって、この神を語るのである。
(1)オホクニヌシの神名の理解--前提として
この神名は、スサノヲが黄泉比良坂の上から、娘のスセリ姫を負ぶって逃げていくオホナムチを自分の婿として認め、「生太刀・生弓矢・沼琴などの呪宝の力で兄たちをやっつけ、大国主神と名乗って栄えよ」と叫んだところからはじまる。
オホナムチに代わる大国主命=オホクニヌシという神名の語義の理解の鍵は「クニ」という言葉にある。その原義は、本居宣長の『古事記伝』に「クニという名は限りの意なり。東国にて垣根をクネというにて知るべし」とあるように、区画され領有された土地をいう。それは自然としての大地それ自体ではなく、すでに特定の生業の必要と有用性におうじて区画された土地なのである。この言葉は、クナとも同じで、日常語としては垣根とか堺などの「囲う」「囲い込む」という即物的で素朴な意味が基礎にしていることが重要であろう*18。クニとナは日常語として区別されている言葉なのである。
もちろん、オホクニヌシの「クニ」はこれらの「クニ」よりも大きな範囲、いわゆる「国」の意味になる。松村が述べたように、オホクニヌシは、その神名からいっても、「国」という政治領域の支配者という意味での「国主」を本質とする神なのである。松村は「大国主」とは「大国の主」ではなく、「大いなる国主」であって、いわゆる国造的存在を「国主」ということに対応して、そのもっとも大なるもの、あるいはそれを統括する神としている。石母田も、松村が提示した『日本書紀』の天孫降臨条一書第二に「国主、事勝国勝長狭を召して訪ひたまふ」とある例にくわえて、『播磨国風土記』(揖保郡)でオホクニヌシ自身が「汝は国主たり」と呼びかけられている例を示し、これが首長を象徴する称号であるとした。「国という概念は(中略)それぞれの王=族長に支配されるところの政治的領域という具体的・歴史的な観念である」(一八四頁)という訳である。
そうだとすれば、この神が本来の名前である大己貴=オホナムチオからオホクニヌシに改名したこと、スサノヲから「大国主命となれ」と指示されたことは、自然神としての地霊からより社会的・人文的な神格への変化と理解すべきことになる。
(2)三輪山の龍神、王権の性神
しかし、オホクニヌシはスクナヒコナとともに活動していた段階では『古事記』でもしばしばオホアナムチと呼称され、原始の地霊としての本質を維持していた。オホクニヌシが本当に石母田のいう意味での「国主」となるのは、彼がオオモノヌシと協働する国造りの第二段階でのことである。あるいはオホクニヌシが石母田のいう意味での国造りの英雄神という性格に適合するのは、ここでいう第二段階からのことであるということもできる。
さて、『古事記』『日本書紀』によると、スクナヒコナが常世国に去った後、オホクニヌシの前に新たな神が海を光らせながら登場した。この海を光らせる神威はこの神が海や津波と深い関係をもち、龍神としての性格をもっていることを示すことは先に述べた通りである。そして彼は、『古事記』では「吾をば、倭の青垣の東の山の上にいつき奉れ」と要求し、オホクニヌシは、その要請通りにこの神を「倭の青垣の東の山の上」に祭った。この神こそが「御諸山の上に坐す神ぞ」という。また、『日本書紀』でも登場した神は大国主命に対して、「吾はこれ汝が幸魂奇魂なり」と述べ、「吾は日本国の三諸山に住まむと欲ふ」といって大和の三輪山の神、大三輪の神となったという。
問題は、この三輪山の神の実態であるが、この神は大蛇の姿をした龍神であり、雷電の神であったことは、『日本書紀』に少子部連蜾蠃(すがる)が大王雄略の命令で三諸岳で「大蛇(をろち)」を捉えて連れてきたが、雄略は「其の雷虺虺(ひかりひろめ)きて、目精赫赫く」に負けて殿中に逃げ隠れたという話でわかる(雄略七年条)。八世紀末期に成立した日本最初の説話集、『日本霊異記』冒頭の第一話は、この小子部栖軽(ちいさこべのすがる)が側近の従者として雄略天皇に仕えた様子を述べているが、それによると、栖軽は雄略天皇が、白昼、后と「婚合(まぐわい)」しているところに誤って踏み入って事を妨げてしまった。天皇は激怒し、栖軽に鳴雷(なるかみ)を連れ戻せと命令したという。ここで天皇が激怒したのは、雷電がなる下での「婚合(まぐわい)」=性交が王者の血統にとって緊要な位置をもっていたことを物語っていることはすでに述べた通りである(■■■頁)。
三輪山の神が性神であったことは、「崇神紀」に、大王崇神の大伯母の倭迹迹日百襲姫に三輪山の神が通ったという神話によっても知ることができる。この迹迹日百襲姫は、夜にのみ通ってくる三輪山の神の姿を見顕わそうとしながら、実際に神の蛇体をみた時に驚き怯えた。怒った神は空を飛んで三輪山に去り、それを悔いた姫は陰部を箸でついて死んだ、その墓が現在の箸墓古墳であるという物語である。
重大なのは、『先代旧事本紀』(地祇)や『新撰姓氏録』(大神朝臣)には同じような神話がオホナムチについても伝えられていることで、オホナムチは「天羽車大鷲」にのって天を飛び、屋上から零雨となって入りこんだとされている。まさに多情の神魂、雷神ゼウスそのものである。しかも重要なのは、『先代旧事本紀』ではオホナムチは陶邑の活動いくから吉野これはオホナムチと三輪山の神が実質上は同じ神であったことを明瞭に示している。
つまり、『日本書紀』では三輪山の神が「吾はこれ汝が幸魂奇魂なり」といっているように、オホクニヌシの魂=本質である神であって、やはりスクナヒコナと同じようにやはり一身同体の神なのである。そのような神として三輪山の神は王家の血統に入りこんだ性神であり、それによって王権の特殊な血統が形成されたことになる。王権の精髄がセックスにあるというのは、マルクスの著名な立言であるが(『ヘーゲル国法論批判』)、その似姿としての神にとっても、その精髄は性そのものであった。オホクニヌシは、三輪山の神を精髄、「幸魂奇魂」とすることによって、このような能力をあたえられたということになろうか。オホナムチとスクナヒコナのペアが対象的な自然、大地それ自体を象徴する神とその要素をなす小さな土壌の精霊として一身同体であったとすれば、オホクニヌシと三輪山の神のペアは、主体的な自然、肉体そのものを象徴する神とその精霊として目に見えない性神のペアとして一身同体であったいうことになる。『日本書紀』のいう「幸魂奇魂」とは、端的に言えば、神の繁殖機能、性機能そのものを意味したのである*19。
なお、山幸彦ヒコホホデミの直系の子孫、あるいは益田によると同体と考えられるイワレヒコは「事代主神」が「八尋の熊鰐」に化して玉櫛媛(別名、三嶋溝咋姫)に通って生ませた娘、ホトタタライススキ姫を妻としたという。これは『日本書紀』に「また曰く」として記されていることであるが、興味深いのは『日本書紀』の前段は、問題の「御諸山の上に坐す神」、三輪山の雷神こそがイワレヒコの妻のホトタタライススキ姫の父であるとしていることである。つまり、三輪山の雷神は龍神としてイワレヒコの妻の父であったというのであって、これはヒコホホデミとトヨタマヒメの父が龍神であったのと同じことである。しかも事代主神は大国主命の息子神であるから、この説明は、「八尋の熊鰐」=事代主神=大国主命の息子=三輪神=「海に照らして来る神」ということになる。王権と性の関係としては、女神にせよ、男神にせよ、海から来た神が性神となる関係が重大であろう。
(3)三輪山の大年神
なお、このような三輪山の神の性神としての性格は、『古事記』では、この神が多くの子孫を儲け、神統譜の始祖にすわったという形で表現されていると思われる。ただし、それを考えるためには『古事記』の該当部分の解釈を正確に考えることが必要なので、次ぎに関係の部分を引用する。
「”吾をば、倭の青垣の東の山の上にいつき奉れ”といひき。こは御諸山の上に坐す神ぞ。/故、その大年神、神活須毘神の女、伊奴比売を娶して生みし子は、大国御魂神、次ぎに韓神???」
『古事記』の活字本では、この部分は「故、その大年神」の前、つまり/の前で改行されている。これは本居の『古事記伝』以来のことで、つまり、この「故、その大年神」の前で、「御諸山の上に坐す神」の話は終わっているとされているのである。そして、この大年神とは、一代前にもどって、スサノヲの子神であるという。この大年神は、スサノヲが出雲に宮を作った後に、スサノヲがスセリ姫ではなく、大山津見神の女、神大市比売との間にもうけた子神であるというのである。それ故に、この「故れ、その大年神」に続く話はオホナムチの国作りに関係する物語ではなく、はるか前のスサノヲ神話に話を戻っているというのである。
しかし、これが文脈として不自然であることは従来からいわれていることで、私は、ここで「故れ、その大年神」といわれているのは直前の「御諸山の上に坐す神なり」を指すと考えている。そもそも「故れ、其の」という書き出しは『古事記』の所々にみえ、前段をうけて話が続いていることを示す語法である。たとえば、「故、其の櫛名田比売もちて」「故、其の八上比売は」「故しかして、其の大国主神を問ひたまはく」などとあるのであるが、前者の「故、其の櫛名田比売もちて」とあるのは八岐大蛇と櫛名田比売についての前段を直接にうけたものである。この「故れ、その大年神」のみ例外と考えるのは無理であろう。私は、「御諸山の上に坐す神なり」とだけいって、この神の神名をあげなかったため、すぐにそれを「大年神」と説明したとみたい。つまり、『古事記』は海を光らせてやってきて三輪山に坐した神を大年神と呼んでいたのである。(なお、この神の名は『日本書紀』神代紀下の一書からは大物主という名で現れるが、それは、この神の祟りをなすような威霊としての側面におもに使われたものであろう。むしろこの神の本来の呼び名は大年神であったろうというのが私見である)。
ようするに「海を光して依り来る神」=「御諸山の上に坐す神」=「大年神」という単純な筋書きであり、大年神の物語は、オホクニヌシの国作りの物語の重要な内容をなすと考えてよいのである。この「大年神」がスサノヲの子神として登場する大年神と名前が重なるのは、スサノヲも自己の年神をもち、オホクニヌシも自己の年神をもったということであろう。農業の女神のオオゲツ姫も『古事記』では神の各世代に登場する。「大年神」の「年神」も毎年の「年」(稲の稔り)をもたらす男神であるから、それと同様に、一種の普遍神として神々の各世代に登場するものと考えて何の問題もない。
(4)大年神の系譜
さて、年神とは五穀と生業の繁盛を司る神であることはいうまでもない。しかし、この神が三輪神の実態であるということは、先述のように三輪神が王家の性神であった以上、この神が性神であったことを意味している。『古事記』が「その大年神、神活須毘神の女、伊奴比売を娶して生みし子は」云々と、この神が多くの女神を婚して二四柱の子神をもうけたと続くのは、それを端的に示したものであろう。神話時代の考え方では人間の身体の豊穣を担う「性神」と自然の豊穣を担う「農業神」は、しばしば同じ生殖の神となるから、これは自然なことである。
さて、『古事記』によれば、この三輪山神=大年神は、二四柱の子神をもっていた。それは、以下のような神々である。(1)大国御魂神、(2)韓神、(3)曾富理神、(4)白日神、(5)聖神(この五柱の母は伊怒比売)、(6)大香山戸臣神、(7)御年神(この二柱の母は香用比売)、(8)竈神(奧津日子と奧津比賣)、(9)大山咋神、(10)庭津日神。(11)阿須波神、(12)波比岐神、(13)香山戸臣神、(14)羽山戸神、(15)庭高津日神、(16)大土神(この九柱の母は迦流美豆比売)。そして、これらの神のうち、その子(つまり大年神からいえば孫)が書き上げられているのは、(14)の羽山戸神の子供たちのみで、彼がオオゲツ姫を妻としてもうけたのが、次の八柱の神々である。(17)若山咋神、(18)若年神、(19)妹若沙那売神、(20)弥豆麻岐神、(21)夏高津日神、(22)秋毘売神、(23)久久年神、(24)久久紀若室葛根神(なおオオゲツ姫は、こういうように何カ所にもでてくる)。
このうち傍点をうった大年神・御年神・若年神などの「年神」は、宮廷が毎年二月に行う祈年祭の祝詞の冒頭に「御年の皇神などの前に申さく」と現れる神であって、この祭祀の主神である(武田祐吉『日本古代の国家と祭儀』)。また十一月の新嘗祭で祀られるいわゆる「御膳八神」のうち「御歳神、庭高津日神、阿須波神、波比岐神」の四神が、これら二四柱の神との重なりが大きいのも無視できない。祈年祭は収穫の予祝であり、新嘗祭は収穫の感謝の祭りであるから、これらの神々は農業の「ナル」「成る」神であるといってよい。
さて、これらの農耕祭祀の原型は大和盆地の農耕祭祀であるから、その親神である大年神(大歳神)が三輪山の神であるというのは、三輪山のもっている位置からして自然なことであろう。三輪山神は雷神であり、気候をつかさどり稲光を発して穀物をはらませる神であって、「年神」たるにふさわしい。奈良の人々にはよく知られているように、いまでも大神神社では豊年講が営まれ、新春の御田植祭りや、その場での籾種まきが大切な行事として続けられている。
この大年神が香用比売との間にもうけた御年神、そして孫にあたる若年神の系列が、三輪山にかかわる神々の中心なのであろう。若年神の両親は里山に座す穏やかな山神、羽山戸神と、もっとも原始的な焼き畑の女神、オオゲツ姫であり、兄弟は若い山咋神、若沙那売神、弥豆麻岐神(水まき=灌漑)、夏高津日神(夏の日・光)、秋毘売神、久久年神(茎の神)、久久紀若室葛根神など、詳細は不明な部分もあるとはいえ、農耕にかかわる神々が並んでいる。
しかし、この部分の神名の列挙は国占めにともなう「成る」祭祀、農業祭祀のみでなく、国占めそれ自体にかかわる神も含まれている。つまり、右の二四柱の神々のうち、まず(1)大国御魂神、(6)大香山戸臣神、(13)香山戸臣神などには大和の地主神ともいうべき色彩がある。また(2)韓神と(3)曾富理神は、後者の曽富理神が韓国語のsio-por(都)にあたることから、おそらく渡来系の色合いの強い王都の神であろうとされている。そして、さらに注目されるのは(8)竈神(奧津日子と奧津比賣)、(11)阿須波神、(12)波比岐神などのグループである。オホナムチが八上姫との間にもうけた御井神を加えれば、これらの神々は明瞭に宮廷の巫女たちが祀る神々に重なってくるのである。
(5)山末の大主神(日吉と松尾)の系譜
さてオホクニヌシの性神=大年神の二四柱の子神のなかでもっとも注意しなければならないのは大年神が迦流美豆比売との間にもうけた(9)大山咋神である。『古事記』の該当部分の全文を掲げると、「次に大山咋神その名は山末の大主神。この神は近淡海国の日枝山に座し、また葛野の松尾に座す。鳴鏑もつ神者なり」となる。日枝や、葛野の松尾は、普通は九世紀以降に平安京との関係で登場するように考えられており、なによりも、前後に登場する韓神、曾富理神などの渡来系の神をふくめて、これらの神の神統譜が明らかでないために、この部分には古くから疑問が持たれており、いまでも、後の挿入であるという意見は残っている。また西田長男がこの疑念を根拠にして『古事記』偽書説をとなえたことも有名である。
しかし、日枝や松尾が九世紀以降の神であるというのはとくに根拠のあることではない。この大山咋神の別名の「山末の大主神」の山末とは、おそらく丹波・若狭から続く山並みの末に位置する神ということではないだろうか。それを出雲・越の国々への広がりのなかで考えるべきものだと思う。そう考えれば、北にオホクニヌシ=大年神の子神として大山咋神がいるというのは了解可能なこととなる。いまでも日吉大社東本宮奥殿の神札は「大物忌神・大年神」となっており、大山咋神の父神とされている。もちろんこの神札は近代のものであるが、大年神に農業の神と注記されているのも興味深い。東本宮は日吉の水源地でもあったから、ここでも大年神は大和と同じようにオホクニヌシの精髄としての性神であると同時に農業神でもあったのであろう。
なお何よりも重要なことは、別に論じたように(保立「南海トラフ大地震と『平家物語』」災害・環境から戦争を読む』山川出版社、二〇一五年)、大山咋神は日吉神社の神体山、牛尾山に鎮座しているが、この神は少なくとも平安時代の末には京都周辺においてもっとも重要な地震神であったことである。関白後二条師通は、日吉神社の神人の強訴のなかでこの地震神のはなった鏑矢によって死去したという。
このようなオホクニヌシ(=大年神)と大山咋神についての『古事記』の記述は、天智天皇の時期の神話的な特色に関係している可能性が高い。つまり、岡田精司は天智の大津京の時期には伊勢齋宮派遣の記事がなく、かつ天智の時期には、大嘗祭の禊ぎが大津で行われていることに注目し(天智系の桓武・平城・嵯峨も同じ)、伊勢よりも日吉大社を重視した可能性があるとしている。これは難波京の八十島祭に対応するということになるが(岡田精司「奈良時代の行幸と八十島祭」「伊勢神宮の成立と古代王権」『古代祭祀の史的研究』)、これは琵琶湖への神の水上来臨の神話の神話の存在を示すという。
ここには、いわば近江系神話というべきものが存在したのではないか。日吉大社では、天智の近江遷都の翌年、大己貴大神が三輪山より日吉大社に勧請された時、大神は唐崎を経て石占井神社の故地に来て、石に坐した占いの女神に会い、鎮座すべき聖域はどこかと尋ねた。女神は大神の御足を井戸で洗い日吉大社まで案内したと語られている。これは伝承であるが、「耀天記」には大神が唐崎まで来たとき、船を樹木の上枝に持ち上げて懸けるという奇瑞をみせ、それをみた神人の祖先が大神に奉仕して祝となったという記事がある。これが大津神人の由来であるというのである。後の時代であるとはいえ、津波が船を樹上に載せたという史料は多く、これも大神の水上来臨が津波をともなったという神話なのであろう。またこの神人の経歴のなかに登場する神秘の「琴」も地震の琴との関係があるように思う。
天智の息子の大友天皇は、近江京の主権者であったから、大友に対して反乱した天武は、近江京の守護神としてのオホクニヌシに対して叛逆したという側面があるのではないか、後に述べるようなオホクニヌシと「出雲神話」をふくむ『古事記』の構想は、そこに関係するのではないかというのが、ここで提出する仮説である。これについては後に『古事記』論を述べる際に立ち返ることとする。
(6)オホナムチ(+スクナヒコナ)からオホクニヌシ(+大年神)へ
以上、ようするに、スクナヒコナが常世国に去った後に登場して、オホナムチを助けた三輪山の神=「海を光して依り来る神」=「大年神」は、性神であると同時に、大地の上で営まれる生業や国の経営に関わる神々であり、それは近江のような王権の中枢をなす国々においても同様であったということになる。その意味で、この神がオホナムチに対して「能く共与に相作り成さむ」といったというのは、「ナルこと、ナスこと」、大地の上の生業の成就とそれを支配する国の経営という国作りの最終段階を助けようという意味であったといってよい。
このようにして、オホナムチはスサノヲの「お前は大国主神となれ」という祝福の予言をみたし、二段階にわたる国作りの事業を果たして、正真正銘の大国主命となった。国作り神話の本質は、このオホナムチから大国主命への神名の変化に端的に現れているということができる。
三「根の堅州国」と火山列島――『古事記』と出雲、
石母田の神話論の中心がオホナムチと「出雲神話」をめぐるものとなった理由は、それが『古事記』と『日本書紀』の物語においてもっとも相違の大きな部分であるからである。石母田は、その相違が生まれた理由を追及して、当時における神話の形成・編纂の実情、ようするに神話の現在をみようとした。石母田は倭国神話論の研究において、『古事記』と『日本書紀』との性格上の相違を明らかにすることにはじめて本格的に挑戦し、文学史的な研究をふまえながら、両書の相違の背景にどのような歴史的な事情があるのかを追求したのである。
A出雲神話の位置
(1)石母田の出雲神話論
なぜ『古事記』においてオホナムチを中心とする「出雲神話」がヴィヴィッドに描かれたのか。
石母田は、『日本書紀』におくれて成立した以上、『古事記』の出雲神話部分の成立を七世紀半ば前後の成立と考えるという点から出発し、当時、出雲神話が強調される伏線として、第一に、六五九年(斉明五)、「是歳。出雲国造<名を闕(もら)せり>に命せて、厳神の宮を修めしむ」という出雲杵築神社の大修造がされたこと、第二に、壬申の乱において出雲国造の一族と考えられる出雲臣狛なる人物が活躍していること、第三に、壬申の乱においてオホナムチの子神、事代神が神武イワレヒコの陵に馬・兵器などを奉納せよという託宣を下したことなどの事情を上げた(二三六頁)。
石母田は、これらは大和に分布する出雲系氏族の進出を反映しているとした。とくに第三の事代主の託宣が神武陵への幣物の奉納であったことは重要で、これは神武以下三代の后が事代主神あるいは大物主神という出雲系諸神の出自をもっているという神話に反映している。またイワレヒコは熊野で体制を立て直すが、この物語の背景には熊野と出雲のあいだの深い氏族的・神話的な関係があるとした。『古事記』『日本書紀』において神武紀はもっとも成立が新しいものとされるが、それは、この背景から生まれたものだというのである。
さらに続いて石母田は、「天武天皇の『意思』について」という節をもうけて、このような動きは、天武が出雲神話の位置を強調し、それによって地方社会をふくむ広汎な族長層、氏族・階層の共感をうることができる物語としようとしたためであろうと論じた。『古事記』はそれを通じて個々の氏族の神話的由来を神々の血族的体系の一部として位置づけようとしたのだという。そして『古事記』を文学的な記述としようという以上、専制者=デスポットとしての神権的な物語の位置を高めるためには、その理念とは異質の世界をそれなりに説得的なものとして展開せざるをえないのだという。「津田博士のようにそこに単純に出雲人のしわざ=作為を見出すことで終わるのでなく、また松村博士のように、『天皇氏神話圏』と『出雲系氏族神話圏』とを分離することによって解決するのではなく、なぜ天武天皇は、その政治理念を『古事記』によって具体化するさいに、出雲系の異質の物語をとりいれざるを得なかったのかを、主体の矛盾として問題とすることにある」(二四六頁、傍点筆者)というのが石母田の観点である。
このような石母田の見解は、やや出雲神話の位置を体系的・整合的な位置づけにおいて処理しすぎているようにもみえる。しかし、これは石母田がオホナムチを畿内から播磨、出雲までを覆うような広い神話圏をもつ文化的英雄神ととらえたことに深く関係するものであり、そのような神であったからこそ、デスポットの神権制に対する対抗者、対抗神話として描き出す価値があったというのが石母田の言いたかったことだろう。
私なりに敷衍していえば、『古事記』の出雲神話は、そのような広い裾野をもっていた神をいわば出雲に局限された神として祭り籠めるという過程を反映していたということになるだろう。
(2)村井康彦『出雲と大和』の観点と母子王朝論
その上で重要なのは、石母田が、それを天武天皇側の「主体の矛盾」を通じてみようとしたことである。この石母田の構想は基本的に継承するべきものであり、はるか以前に、このような見通しを示した石母田の力はさすがであると思う。
最近、村井康彦『出雲と大和』(岩波新書)は、そこに新たな分析を付けくわえた。村井が注目したのは、斉明天皇が出雲に対して強い強迫観念をもっていた可能性である。つまり村井は、六五九年(斉明五)の出雲杵築神社の大修造は、前年に建(タケル)皇子が死去したことの衝撃のなかで行われたのではないかという。タケル皇子は天智と遠智娘の間に生まれた第三子で姉に太田皇女と鸕野讃良皇女(後の持統)がいた。つまり、本来彼こそが天智の正統な跡継ぎであったことになるが、この皇子は「唖にして語ふこと能はず」という生まれであった。
村井は、この皇子のイメージが同じような生まれつきであった誉津別王と重なり、『古事記』の誉津別王の記事が迫真のものとなったという。誉津別王は大王垂仁の子どもと伝えられ、『古事記』『日本書紀』は、彼が物をいえなかった原因はオホクニヌシからのいわゆる「国譲り」の時、杵築神社の社殿を立派に造営するという約束が曖昧になっていたためであるとしている。彼が(天皇の氏族霊である)白鳥を追って杵築神社に行くことによって言語を発することができたというのは有名な物語である。しかし、タケル皇子は、そのような幸運に恵まれることなく八歳で死去し、孫を溺愛していた斉明は、その衝撃のなかで杵築神社の「修厳」に全力をあげたのである。
この村井の議論が興味深いのは,第一には、それが邪馬台国は出雲勢力が立てた国であったという主張を追求するなかからでてきたものである点である。私はこれに賛同することはできないが、出雲と大和のあいだには、本来、領域的な一体性があり、オホナムチの信仰はその全域に及んでいるが、出雲に深い縁をもっていたということは了解可能であろう。邪馬台国論は、ここでは論ずることはできないが、私も有名な『魏志倭人伝』のいう邪馬台国への行程は日本海ルートで丹後を経過したものとする小路田泰直の新説*20に賛同して、『かぐや姫と王権神話』において、丹後から大和の一帯がヤマト王権膝下の広域地域であったことを論じ、そのなかに丹後奈具社から大和広瀬神社をむすぶ月神・豊受姫の信仰域をみることができると論じた。オホナムチの出雲から大和を覆う信仰域もそれに重なるものであったのであろう。
しかし、ここで重要なのは、第二に、村井が石母田のいう「主体の矛盾」を天武個人ではなく、皇極(=斉明)と天智・天武の母子が構成した王権全体の中に置きなおしたことであろう。大ざっぱにいって七世紀王朝は皇極(斉明)とその息子天智・天武の母子の影響力と在位期間が長く、母子王朝という特徴をもっていたということができる*21。おのおのの在位期間は皇極は六四二~六四五年、斉明は六五五~六六一年(計一一年)、天智は斉明死後の「称制」が六六一~六六七年、即位が六六八~六七一年(計一一年)、天武が六七二~六八六年(一五年)。全体で三七年である。しかし、皇極(斉明)は譲位した弟の孝徳の在位期間(六四五~六五四年、一〇年)も「皇祖母尊(すめみおやのみこと)」の地位にあって、義江明子によれば「王室の長たる女性」、「天皇・皇太子とともに『君』として臣下に対峙する存在」として「太上天皇の前史として位置づけられる」ものである(義江明子二〇一一『古代王権論』)。しかも皇極は舒明(在位六二九~六四一年、一二年)の皇后であったのであるから、要するに七世紀のうち六〇年近くは皇極(斉明)と天智・天武の母子が王権の中枢に居続けたのである。この母子の間の諸関係とそれに絡まって展開した天智・天武の争いなどの母子王朝に内在する矛盾こそを問題にしなければならないのは明らかであろう。
(3)七世紀の地震と斉明・天智・天武の母子王朝
この村井の意見に、さらに七世紀にしばしば大和飛鳥を襲った地震の影響を付け加えるべきであろう。オホナムチ神話の本質は地震火山神話にあるのであるから、これによってはじめて『古事記』におけるオホナムチ神話の記載を内在的に理解することが可能になるのではないか。
つまり、七世紀に入る直前、五九九年(推古七)四月、「地動りて舎屋ことごとくに破たれぬ。則ち四方に令して地震の神を祭らしむ」(『日本書紀』)とある。この段階の『日本書紀』にあまりに遠くの地震が記され伝承されたとは考えにくいから、この地震は大和あるいは畿内で起きたものと考えることは許されるであろう。「舎屋」(建物)がすべて倒壊したというのが事実であるとすると、相当規模の地震であったことになる。残念ながら、この時期の地震痕跡は考古学的には確定しておらず、『日本書紀』の史料を(地質学的な)地震史料として利用していいかどうかは問題が残っている。しかし、少なくとも、六世紀の末頃に「地震神」を祭ったこと自体は事実として認めてよいだろう。そして、すでに述べてきたことからして、この神の実態はオホナムチであったとしてよい。
別に述べたように、このヤマト王権による地震祭祀のなかには、吉野宮などのある吉野渓谷への入口、吉野川右岸にこんもりと立つ伏鉢形の妹山樹叢の麓にある大名持神社が含まれていた(保立二〇一九「『宇治拾遺物語』の吉野地震伝承」)*22。岡田精司は『万葉集』の「大穴持命少御神の作らしし妹背の山」(四・一二四七)という歌をこの妹山と対岸にある妋山のことであるといっているが、その可能性は高い(岡田一九五六「国生神話について」)。またこの神社については、和田萃「古代の出雲・隠岐」(『海と列島文化 日本海と出雲世界』小学館、一九九一年)が、その畿内の神社のなかでの飛び抜けた位階の高さを強調している。つまり、この吉野大名持神は九世紀半ば、八五九年(貞観一)に全国の神々の位を整理したとき、従一位から正一位になっており、無位の伊勢神宮を別とすれば、淡路国の伊佐奈岐命の一品に並び、神産日神、高御産日神の従一位などを抑えて神々のトップに立ったのである。従二位の三輪山の大物主神など、他の高位の神々のほとんどもオホナムチと同体、あるいは息子や親族の神であることは、この神の隔絶した位置を物語っている。吉野山塊の主峰、金峯山の神が正三位につけていることも強調しておきたい。
前述のように、石母田はオホナムチ=オホクニヌシに地霊としての性格をみとめ、「それはまだ地の神、山や丘の創造神であるという畿内・近国の農村社会で広く信じられていた観念から絶縁はしていなかった」(一八五頁)としているが、そのような畿内近国における神話観念を表示するものとして、吉野大名持社や摂津莵原郡大国主西神社があったのである。その意味では、吉野大名持社などへの宗儀は推古の段階からさらに古くににまでさかのぼると考えることもできる。もちろん、吉野大名持社の祭祀が国家的に調えられたのは、和田がいうようには斉明朝であった可能性が高い。実際、『日本書紀』には皇極(重祚して斉明)の即位の年、六四二年(皇極一)一〇月に二日連続で地震が発生したことが記されている。この年は「客星月に入る」という天文の異常や雷の記事が多く、これが即位の初年のことであっただけに、和田の指摘のようなオホナムチの祭祀が整えられたことの傍証となる。村井が、その意味を明らかにした六五九年(斉明五)の出雲杵築神社の修営は、その延長線で考えることができる。
問題は、このような斉明のオホナムチ信仰を天智・天武の兄弟がどう受けとめたかであるが、すでに六六七年(天智六)の天智の近江京の遷都にふれて、天智が日枝社における大己貴=大国主命=大年神の祭祀を強調した可能性にふれたが、天智が母のオホナムチ信仰と神話観を受け継いだことは確実であろう。それに対して、天武は母と兄のオホナムチ信仰に対しては距離をおいたのではないか。少なくとも天智の息子の大友天皇に対して反乱した天武は、天智ー大友の拠点である近江京の守護神の位置にあったオホクニヌシに対して忸怩たるものがあったのは確実であろう。蜂起した天武が、伊勢の神助をえたと称して、伊勢アマテラスに対する信仰を強化した重要な理由の一つはここにあったと考えられる。このような経過に、皇極=斉明と天智・天武の母子の間の一種のマザーコンプレクスが働いていた可能性も高い。石母田のいう「天武天皇の『意思』」「主体の矛盾」はもちろん政治的・イデオロギー的な問題と考えるべきものであるが、しかし、その中枢には、このような王権内部の齟齬や反目が確実に存在したというべきであろう。
天武がオホクニヌシを意識せざるをえなかったのは、天武の時代に入って地震が連続したことである。『日本書紀』には、六七五年(天武四)、六七七年(天武六)と、大和国での強震の記録が残っている。飛鳥は地震の多い地域であるが、一般に地震が記録に残されるかどうかは支配層の吉凶意識の表現である。そしてその上に、六八四年(天武一三)に大規模な南海トラフ地震が発生した。この地震では、山崩や洪水・溢水が発生し、諸国の官舎、百姓倉屋、寺院神社などが、破壊され、多くの人間と家畜が死傷したという。注意すべきなのは、このとき、出雲も強く揺れた可能性があることである。総理府、地震調査研究推進本部のデータベース「都道府県ごとの地震活動」によれば、出雲は局地地震のほか、南海トラフ地震と日本海東縁変動帯で発生する大規模地震によって大きく揺れたり、津波におそわれる地域である。石橋克彦も一七〇七年(宝永四)、一八五四年(安政一)、一九四六年(昭和二一)の南海地震が出雲を大きく揺らしたことに注意しており(石橋『南海トラフ巨大地震』四六頁)、南海トラフ地震は出雲を揺らす特徴をもっていた可能性がある。しかも、紀伊半島から南九州にかけての津波堆積物の調査をした高知大学の岡村真によれば、紀元前後の南海トラフ地震は一七〇七年(宝永四)の南海トラフ地震とならんで、歴史上きわめて巨大なものであったという(岡村真、松岡裕美,「津波堆積物からわかる南海地震の繰り返し」『科学』八二巻,二〇一二年)。詳細は今後の地質学的調査に期待するほかないが、六八四年の南海トラフ大地震は出雲を襲った可能性はきわめて高い。
この南海トラフ大地震の直前にはハレー彗星、直後にももう一つの大彗星が夜空を覆うという天変地異の輻輳も異様なものであった(斉藤国治一九八二)。この後から天武の健康に問題が出たこともあって、王権は震撼したに相違ない。とくにこの地震で斉明が建造した飛鳥の酒船石の地盤と石垣の崩壊が崩壊したことが発掘調査で確認されている。『書紀』は酒船石などの建築を斉明の狂心の表現であるとするが、斉明の建造した宮殿建造物が大地震で揺れ、地震神オホナムチの神威が示されたことは、オホナムチを敬遠してきた天武に大きな衝撃を与えたであろう。天武がこの地震のなかに、オホクニヌシ信仰から離れた自分に対する母の憤懣をみた可能性は高い。
こういう経過の中で、オホナムチの神威はいやがうえにも王権中枢に新たに印象づけられた。『古事記』は、天武ー持統ー文武ー元明ー元正と続いた天武の王統の中で構想され、編集されたが、とくに持統・元明・元正などの女帝たちにとっては斉明のオホクニヌシ信仰の重みは大きかったであろう。こうして宮廷中枢には、斉明・天智の神話意識に密接し、かつ威神として畏れられたオホナムチを出雲に祭り込めようとする意思が生じたのであろう。それが出雲大社の大規模な修造などの実際の宗教行為に表現されると同時に、宮廷神話・宮廷物語としての『古事記』の編纂をもたらしたのであろう。『古事記』の物語・文学としての洗練は、『書紀』とはまったくことなって、そのような宮廷・内廷の雰囲気なしには考えられないように思う。私は梅沢伊勢三が指摘した『古事記』が『書紀』と異なって宣命体に近い和文風の文体をもつことはそれ抜きに考えるべきではないと思う(梅沢一九八八)。内廷の雰囲気は持統ーー元明ー元正という女帝を中心としたものであったはずである。なお、それは以上のような経過からいって伊勢の女神アマテラスの地位の上昇とも裏腹の関係にあったことも特記しておきたい。
B根の堅州国ーー火山と温泉の出雲
さて、「出雲神話」についてすでに論じたことは多いが、これまでスサノヲ・オホナムチ・スクナヒコナなどの神々の神格の解明を論述の中心にしてきたため、『古事記』が出雲国の性格を端的にしめす言葉として使った「根の堅州国」の語義についてはふれてこなかった。そこで、まずこの言葉は火山列島の地下世界を表現する言葉であったことを明らかにし、次いで、『古事記』がそれを実際上は出雲国を示す言葉として作り出したことの意味を考えてみたい。それは、右に述べたようなオホナムチの出雲への祭り籠めという観点からの分析となる。
(1)「根の堅州国」の諸解釈
「根の堅州国」という言葉は、『古事記』にしか登場しない言葉である。『日本書紀』では「根国」という言葉が登場するが「根の堅州国」の使用例はない。そうだとすると、この言葉の語義の確定が出雲神話の理解において決定的な意味をもっていることは明らかであり、そのためもあって、その語義をどう考えるかについて、きわめて錯綜した議論が行われてきた。
「根の堅州国」という言葉は「根」と「堅州」の二つの語素からなっているが、理解が困難とされてきたのは後者の「堅州」であった。まず本居宣長『古事記伝』(神代五、二五丁)は、「堅州国」について「片隅国の意なり、そは横<東西南北など>の隅にはあらで、竪<上下>の片隅にて、下つ底の方を云なり」としている。〖倉野注釈〗〖西郷注釈〗はそれを踏襲しているが、これはややコジツケに近い議論で語法上考えがたく、そのため松村は「堅州」は「堅い洲」と理解するほかないとし(松村④)、近年の〖西宮注釈〗〖石母田注釈〗『山口注釈』は松村に従って「堅い州(中州)の国」としている。問題は松村がさらに「根」を地下の意味とすると「地下の堅い州」では意味が通らないとして、「根」は「底」ともいいかえられており、「底」は「遠く離れた状態」をいうこともあるから、「根の国」とは「遠く離れた国」、しかも水平的に遠く離れた国としたことである。右の諸注釈のうち、『山口注釈』(およびその根拠となった神野志二〇〇八)のみはこの松村見解に全面的にしたがっている(他の注釈は「地下の堅い州」の国としている)。
『山口注釈』のこの部分は共著者の神野志隆光が「遠く根国に適ね」「遠き根国」「極遠の根国」などという『日本書紀』の表現によって、「根」とは「さいはて」を意味するという形で松村見解を補強したことに依拠しているが(神野志『古事記の世界観』吉川弘文館、一九八六年)、しかし「根」と「底」を等置することも、また「底」「根」を垂直的でなく水平的に「遠く離れた」ことだと解釈することには無理があるといわざるをえないだろう。そしてそもそも「遠く離れたところにある堅い中州の国」というのも意味が通らないことは同じであろう**23。
やはり「根」は普通に「地下」と解釈するほかはない。つまり『古事記』には四十八箇所の「根」という語があるが、多くは神名や王名にあらわれるもので、そのままではどのような意味なのか判然としない。しかし、うち二例については植物の根の意味であり、また四例が「底つ石根」という言葉となるから、やはり「根」は地下の意味であり、とくに神話時代の人々は地下の世界を「底つ石根」の世界と考えていたのではないだろうか。スサノヲがオホナムチとスセリ姫に対して坂の上から二人の住む宮殿についてふれた言葉は「宇迦の山の山本に、底津石根に宮柱ふとしり」となっている。「底津石根」という言葉は、まさに一つの世界観を表現する言葉である(なお、最初に『古事記』の四十八箇所の「根」という語を検討したのは水林彪であるが、水林はどういう訳か例の少ない植物の根に注目し、この「根の国」の「根」は「葦原中国」の葦の根であって、そのようなものとして「中国の根源をかためる国」であるとした。しかし、具象的なイメージを考えると、葦の根は地下茎であって国の根源を支えるにたるものかどうかは疑問であろう。葦の根の届く深さは周知のことであったはずである。また水林は「根の堅州国」を「黄泉国」と同じものだとするのであるが、この黄泉国とは「(葦原中国の)四方(ヨモ)=山(ヤマ)」の世界であるという。しかし、そうなると、「葦原中国」の根は「中国」の地層にしかないのであって、「黄泉=四方=山」には葦の根は広がっていない。水林の議論は矛盾している)。
(2)「根の堅州国」は「地下の鍛冶の国」
次に問題となるのは、「根の堅州国」の「堅州国」の語義である。これも錯綜した議論になっているが、ここではそれらの諸見解を一つ一つ整理するのは省略して、最新の研究である水林彪『記紀神話と王権の祭り』に依拠して私見を端的に述べることとしたい。
さて、『古事記』では、「堅」の用例は(「根の堅州国」の例のほかに)全部で一三例あり、どれも字義本来の「カタイ」という意味をもって用いられている。
水林は「堅州」の「州」は音仮名であり、それ故に「堅州」とは「堅す」という動詞であるということを示した。つまり、「州」という文字は『古事記』の五箇所に登場するが、たとえば「州羽=(諏訪)」「氷羽州比売の命」「凝烟=(州須、煤)」「國稚く浮かべる脂の如くして久羅下なす(原文「久羅下那洲」)、ただよへる時」など、すべて地名・人名・物の名の仮名表記など、音仮名の「ス」として用いられている。「州」という文字を字義通りの「州」として利用している例はないのである。そして、この用例のうちでもっとも参考になるのは、最後に掲げたものであって、そこでは「久羅下なす」(「久羅下那洲」)として、「なす」という動詞の送り仮名として「州=ス」が使われている。水林は、「堅州=カタス」の「州=ス」はこれと同じ音仮名であって、「カタス」は「堅す」という動詞であろうとした。これは了解しやすい見解である。
ただ、水林は、「根の堅州国」の「根」を主語にあて、「堅す」を「しっかりしたものとする」という一般的な意味にとって、「根の堅州国」を「根源がしっかりしたものにする国」と解釈した。しかし、水林の見解はやや法理念的な理解が強すぎるのであって、歴史用語はより歴史具体的に読まねばならない。つまり、次ぎに『字訓』の「かたす」の項目を引用するが、私はそれにそってより端的な解釈を採用したい。
「<鍛>。四段。刀剣などをうちきたえることをいう。『かたす』の『かた』はおそらく『きたす』の『きた』と同じで、語の分化したものとみてよい」「『新撰字鏡』に「鑃<きたひがね>、『名義抄』に「冶・鍛<キタフ>」、『字類抄』に「淬<カタス>」とみえ、「鍛冶」のことをいう」とある。また「かた<形・型・像>」の項目には、「一定の形式をもつ平面または立体の輪郭。ものの外形・形状を定める規範的なもの、範型となるべきものをいう。「堅し」「型」と同根の語。鍛作することを「かたす」という。たたき堅めて、型を作るからである。『新撰字鏡』に「模<加太支なり>、『和名抄』に「鎔<伊賀太>、鋳鉄の形なり」とあり、それが「かた」の原義である」。
つまり、「堅州国」の「堅州」の「州」が送り仮名であるとすれば、「堅す」はサ行四段の「鍛す」という動詞の連体形であり、「鍛冶をする」という意味となる。「根の堅州国」は全体としては「地下の鍛冶の国」ということだったのである。
なお、この「堅州国」=「鍛国」の用法は、『日本書紀』(垂仁紀)にあらわれる「鍛地」という言葉と近いものであろう。つまり、大王垂仁に関する記事のなかに、王陵への殉葬をやめて土製の埴輪を立てることにしたという有名な記録があるが、それを献策し、かつ埴輪を作成する部民(土師部)を統括した野見宿弥を土師職に任命し、そのための「鍛地」をあたえたというのである。ここで「鍛地」といわれているのは、火をつかって物を堅くする場所、埴輪を焼くための窯場の意味であろう。そうだとすれば、この「鍛地=かたしどころ」と「堅州国=かたすのくに」はほぼ同じことではないだろうか。「鍛地=かたしどころ」が地下に存在するというのが「根の堅州国」の幻想なのではないかということになる。
野見宿弥は出雲に所縁が深いから、その血をひく土師氏は、こういう幻想を強く維持してきた氏族であろう。彼らは、いわゆる埴輪(特殊器台=瓮+平瓮)を作るのみでなく、それ自体、一つの瓮(=壺)である前方後円墳の造営と管理の担当者であった。土師氏は奈良時代になっても、諸陵頭の地位にあり、野見宿弥が仕えたと伝承される垂仁大王陵から成務陵・日葉酢姫陵・神功皇后陵などの所在する大和添下郡の秋篠・菅原の地を本拠として、山陵関係の技術者・管理者としての職掌を維持していた(直木孝次郎「土師氏の研究」『日本古代の氏族と天皇』塙書房、一九六四年)。とくに興味深いのは七三四年四月に起きた河内大和地震が歴代の天皇や有功王の山陵を動かしたときに、「諸王と真人」につけて土師宿弥が調査のために派遣されていることである(『続日本紀』天平六年四月条)。この地震は高市親王の陵墓を揺らしたと考えられ、しばらく前に自死に追い込まれた高市の子どもの長屋王の怨霊の所為であったのではないかとされた。聖武がそれにおびえたことが東大寺大仏の建立を導いたと考えられることは別に述べたところである(保立『歴史のなかの大地動乱』)。
これまでの見解からは飛び離れたものであるが、以上の「根の堅州国=地底の鍛冶の国」という仮説は、何よりも先にふれた大穴持命による島造の「冶鋳」、またタカミムスヒによる「天地鎔造」にぴったりと対応する。神話論にとっては、これがギリシャ・ローマ神話におけるヘファイストスやヴァルカンが地下の鍛冶の神であることに通ずることになるのもきわめて大きい。
(3)火山と温泉の葦原中国――「底津磐根を焼き」「火瓮なす光く神」
このような「根の堅州国、冶鋳、天地鎔造」などという言葉の連鎖は、地下の磐根の世界は熱いという観念が火山列島の人々に共通する知識だったことを示すのではないだろうか。いくつか、それを傍証しうる史料を上げてみると、まず興味深いのは、スサノヲの跡をついだオホクニヌシが国譲りを強制された際、天神に饗応の料理を献上するための火を焚いたときの誓いの言葉である。
「是の、我が燧れる火は、高天原には神産巣日御祖命のとだる天の新巣の凝烟の八束垂るまで焼き挙げ、地の下は底津磐根を焼き凝らして」((『古事記』)
つまり、この呪祷は「この、私がおこした火は、高天原にむかってはカミムスヒの立派な天の新居に、煤が長く垂れるほどに焼きあげ、地下にむかっては地底の大盤石の根を焼き固めるほどの大きさであって」という意味になる。天上と地上の神々が、天上に届くような巨大な焚き火を通じて関係を結び、しかも、その火が地底の石根を焼き固めるという幻想は、きわめて興味深い。このような地底についての観念こそが、「根の堅州国」のイメージの基礎にあるのではないだろうか。
同じような観念は「出雲国造神賀詞」(『延喜式』)の「豊葦原の水穂の国は、昼は五月蠅なす水沸き、夜は火瓮(ほべ)なす光く神あり」という一節にも現れている。すぐに述べるように、益田勝実はこの「火瓮なす光く神」について、「夜になると、火を盛った壺のように輝きを放つ神といえば、それこそ<オホナムチ>の相貌ではないか」と考えたと述べている。「火を盛った壺」というのを火山の表現と考えたのである。後に述べるような理由で益田はこれを考え直したが*24、しかし、この一節は、『常陸国風土記』(香島郡)に「豊葦原水穂国」について「荒ぶる神等、又、石根・木立・草の片葉も辞語ひて、昼は狭蠅なす音声ひ、夜は火の光明く国なり」、また『日本書紀』(神代第九段異書六)に「葦原中国は、磐根・木株(このもと)・草葉も、猶能く言語ふ。夜は熛火(ほべ)の若(もころ)に喧響ひ、昼は五月蠅如す沸き騰る」とあるのと同じことであろう。この「熛火」の読みは異書六末尾に「裒倍」と訓が記されている。これはホホと読むという見解もあるが、そこに特段の根拠はなく、火瓮=ホベとして問題はない。これらの夜に耀く光りをもっぱら神秘的な異光と考えるのは無理があるのではないか。拙著『歴史のなかの大地動乱』で紹介したように、九世紀の伊豆神津島の噴火において誕生した噴火丘は「其形は伏鉢のごとし」「その体は瓮を伏せるがごとし」などといわれている。この「火瓮」が、いわゆる神名火形をした火山とその噴火丘に火が燃えている様子を表現したものであるとすることに大きな問題はない。
重要なのは、これらが葦原中国の景観一般についての定言であることである。葦原中国を開発したオホナムチ=葦原醜男は火山神であることは、すでに述べた通りであり、オホナムチのペアとして葦原を土壌に変えていった神スクナヒコナが土の火気の神、焼畑と硫黄の神であることを想起されたい。列島の大地は西谷地晴美のいう農本主義的あるいは水田中心主義的な観念よりも豊かなものであることが、ここにも示されている。ここでは、木株(このもと)や草葉が物をいうというアニミスティックな幻想の中に「磐根が物言う」ことが位置付いており、夜も「火瓮=熛火」なす火山噴丘が光るという神秘は、その延長線上にあるのである。「火瓮」の存在が葦原中国の一つの特徴とされていることは明らかである。そして、それと対句になった「昼は五月蠅なす水沸き」「五月蠅如す沸き騰る」とは、ただの泉ではなく、益田勝実が言うように、ブツブツと音を立てるような湯地獄型の温泉や間欠泉の逸出を意味するものであろう。オホナムチが温泉の神であることはすでに通りである(なお、右の『書紀』のいう「木株(このもと)」は、『古事記』のいう兄たちに追われたオホナムチを大屋毘古神が地下世界へ逃がした「木俣」と同じものであろう。つまり「木株(このもと)・草葉が言語ふ」という神秘自体が地下世界との関係で意識されていたと考えていい)。
前述のように『書紀』には「根の国」とあるだけで、「根の堅州国」という言葉は、登場しないが、しかし、以上から「根の国」という言葉だけでも、火山列島の地下の磐根は熱火の世界であるという知識が前提にあったと考えてよいはずである。
(3)『古事記』出雲神話の文学的想像力
しかし、『古事記』は、この「根の堅州国」の空間的な位置を出雲国の地下に設定した。スサノヲの物語が出雲国に、本来、出雲国に由来が深かったことは否定できないが、しかし、「根の堅州国」という具体的なイメージにみちた言葉を作り出すことまでして、スサノヲとオホクニヌシの物語という出雲神話の舞台を出雲国に設定し、「根の堅州国」は出雲の地下が中心であるというニュアンスを含んでいる。
これはやはり『古事記』の文学的設定である。つまり『古事記』は、イサナキがイザナミを葬ったのは、「出雲国と伯耆国との堺の比婆山」であったとしている。イサナキは、そこを訪れ、逆にイザナミの怒りをかって逃げ帰り、「黄泉比良坂」という坂の下(「坂本」)まで逃げてきた。この坂は「今に出雲国の伊賦夜坂と謂ふ」と説明されているから、『古事記』はイザナミの葬地が出雲にあることを再確認しているのである。しかし、『書紀』には異書もふくめてイサナミの葬地が出雲にあったという伝承はない。むしろ『書紀』(異書五)はイザナミの葬処を紀伊国熊野の有馬村としている。ここが紀伊国熊野の有馬の海辺にある花の窟にあてられていることはよく知られているが、イサナミ・イサナキの二神の伝承は出雲国にも広がっているものの(坂江渉二〇一九「倭王権形成期の海人の地域間交流」『島根県古代文化センター研究論集』二二集)、その中心は瀬戸内東部と紀伊、伊勢、若狭などであるから(岡田精司■、)、紀伊国という伝承の方が本来のものである可能性は高い。イザナミが出雲国に葬られたというのは『古事記』が虚構したといわないまでもあくまでも一部で語られたものにすぎないだろう。
これがスサノヲの「妣の国」に行くのだと泣き叫ぶ姿に結合された。つまり、母神イザナミの復活に失敗した父神イサナキに対して、スサノヲが「妣の国、根の堅州の国に罷らむと欲ふ」と泣き叫んだという一節である。それはスサノヲが、天に上って姉のアマテラスにあったときにも「僕は、妣が国に往かむと欲ひて哭く」と繰り返されている。そののち、アマテラスとの競争に負けたスサノヲは、出雲の肥の河の源流に降っていき、大蛇と戦って奇稲田姫を獲得し、結局、出雲の須賀に宮を造った。「妣の国」=「根の堅州国」=出雲というのが物語の流れである。この「妣」という字は亡母のことであるからイサナミのことである。
もちろん、『日本書紀』(五段、異書六)でもスサノヲは父のイサナキに対して「吾は母に根国に従はむと欲す」と言い放っているが、「泉津平坂は復別に処所あらず、但死るに臨みて気絶ゆる際、是が謂かといふ」と説明されており、出雲には特定されていない。『古事記』はイサナミの死からスサノヲの母恋いまでを「妣の国=出雲=根の堅州国」の物語として貫いているのである。これが大地や海原を「地母」「母なる大地」と観念する心理にそのままつながっていることはいうまでもない。それは松村が『古事記』がイワレヒコ(1神武)の兄の稲■(氵と氷)命が「妣が国として海原に入りましき」としたこととあわせて、「人の子が母に対して持つ一般的な情念の問題」と述べた通りである。このような「母なる大地」の観念は「根の国」にも「綿津見の国」にも成立しうるのである。ここには『古事記』が母性の論理によって文学的虚構を貫いていることが明らかである。
これに対して、『書紀』(五段本文)ではスサノヲは「父母の二神」に根の国に行けと命令されるのであって、母恋いの物語としては描かれていない。むしろ『古事記』は母にも嫌われたスサノヲが、どうせ根の国に行くならば、姉のアマテラスにあってからにしたいという姉恋いの物語になっている。そしてスサノヲは出雲に降って八又大蛇を斬り、奇稲田姫をめとって出雲の須賀に宮を立て、オホナムチを設けてから「遂に根国に就でましぬ」ということになるのである。ここにあるのは追放の論理であって、母性の論理はない。また「根国」の地理的な位置も明瞭ではなく、それは『書紀』(異書三)でもスサノヲは「底根の国に適ね」とのみいわれているのと同じである。さらに『書紀』(異書五)では「熊成峯に居まして遂に根国に入りましき」とあるが、よく知られているように、この熊成峯は紀伊の熊野であるか、韓国の山であるという見解も有力である。
ようするに、『古事記』が出雲に「根の堅州国」を特定したことは意識的な設定であり、文学的な想像の産物という要素が強い。こういうプロットの上に『古事記』はオホナムチの物語を描き出したのである。
これに対して『日本書紀』では、オホナムチの根の堅州国訪問はまったく語られない。『日本書紀』の語るのは、一書第六がオホナムチの国作りを語るだけである。国作りが出雲に関わっていること、オホナムチが出雲の神であることは示されるものの、「出雲神話」の話題はすべて記載されず、オホナムチの根の国訪問も語られない。これに対して『古事記』はオホナムチに対する兄たちの迫害から、オホナムチが母や祖母神のカミムスヒの援助をえて「須佐能男の命の坐せる根堅州国」に向かう物語が全面的に語られることになる。そして、そこでオホナムチはスサノヲの娘のスセリヒメと結ばれ、姫の助力をえて根の堅州国を脱出して、黄泉比良坂を下り、現世に帰ってくるのである。そこでスサノヲはオホナムチに対して、出雲の宇迦能山に宮を造れと指示している。『古事記』を引用しておけば、「おれ、大国主命の神となり、また宇都志国玉の神となりて、その我が女、須世理毘売を嫡妻として、宇迦の山の山本に、底津石根に、宮柱ふとしり、高天原に、氷椽たかしりて居れ、是の奴や」という訳である。
私は、ここにも母性の力が繰り返し語られることに注意したい。これは天武ー持統ー文武ー元明ー元正と続いた天武の王統の矛盾と、それを糊塗し、ともかくも繋いでいった女帝たちの論理と雰囲気を反映しているというのが私見である。
また、いうまでもなく、このようにしてスサノヲとオホナムチの物語を連続的に描いたことによって、『古事記』の物語は、火山や地震の物語としての統一性をもつことになった。はるか離れた現代に生きる私たちは、これまで『古事記』の出雲神話が地震と火山の物語をちりばめていることに気づかなかったが、「根の堅州国」とは、それを象徴する言葉だったというべきであろう。『古事記』の編者とそれを享受した宮廷社会は、この物語によって、七世紀の地震や天変地妖を振り返り、従来は葦原中国全域にわたる国土神・火山神・地震神として位置づけられていたオホクニヌシを、強い畏怖の念をもって出雲に祭り籠めようとしたのである。それは文学的想像ではあるが、しかし、『古事記』編纂は出雲大社の巨大建築の完成と荘厳の時期に重なっており、それは国家の力量によって支えられていたのである。
C奈良王朝と多元神話
(1)出雲神話の本質
このようにして、この列島の神話における出雲神話の位置という、長い間の難問に、これまでとはまったく別の側面から、つまり自然史研究との学際領域から、一つの新しい光を当てることができたことになる。
神話時代の人々は、出雲が火山噴火と地震のひそむ地域であるという認識のもとに神話的な地域像を作りだしていた。『古事記』が出雲国を「根の鍛す国」としたのは、そこに根拠があった。先に見たように、「根の堅州の国」の語義は「地下の鍛冶の国」ということにあったが、それは「磐根が火によって焼き固められる国」であり、具体的には、火山の地下に存在する鍛冶場ということであった。まさにローマ神話において、火山Volcanoの地下に鍛冶の神ヴァルカンVulcanが活動しているというのと同じ世界観である。
火山の山頂の磐座の磐根には巨大な火が宿っており、そこではしばしば地震が発生するというのは、今も昔も、この列島に棲むものがよく知っている事実である。『古事記』は、この火山神話の枠組をきわめて有効に使用して、イサナキの黄泉国訪問の物語、スサノヲの地震神としての天界上昇と降臨の物語、オホナムチの根の堅州国訪問と脱出の物語などの物語を流れるような筋をもって語りだした。それが『古事記』の叙述に不思議な魅力と臨場感をもたらしているのだと思う。『古事記』の叙述の文学的な創造性のベースにある自然観を見のがしてはならない。
そもそも、『歴史のなかの大地動乱』で論じたように、畿内を初めてとして各地に造営された前方後円墳は、火山を模した造形であった可能性がきわめて高い。前方後円墳が「壺型」であることは、先に三品などの見解を援用して述べたところであるが、もっとも端的な史料としては、九世紀の神津島の噴火において形成された火山丘の形状が「瓮を伏せるが如し」といわれている(『続日本後紀』承和七年九月二三日条)。瓮を横に伏せたような様子というのは、まさに前方後円墳の造形であろう**252。これは火山を瓮の形の相似物としてとらえる観念を明瞭に示している。中国思想史の小南一郎によれば、東アジアにおいて「壺」が人々が幻想のなかで天と交通するためにもっとも適当な道具であり、形であったという(小南一九八九)。前方後円墳は地下の黄泉国、根国と、天上の間の直通ルートを作る装置なのである。
これによって、『古事記』の独自性の謎がどこにあったかという問題についても新たな見通しをうることができる。つまり、このような地震・火山のイメージは『古事記』独自の物語である。地震や火山というものが物語のキーとして語られるのが『古事記』であるといってもよい。それに対して『日本書紀』は出雲神話をかたらず、そもそも地震・火山についてほとんど触れることがない。しかし、『日本書紀』の編纂が進む中で倭国神話の全体が想起され、その中から絞り出すようにして神話のエッセンスとしての地震・火山神話が明瞭な姿をもって登場してきたのであろう。
(2)多元神話の収斂と伊勢・東大寺
神話のエッセンスという場合、『古事記』の記述の文学性に惹かれる人々は、従来、どうしても、その神話の内容を無前提に民間的なもの、あるいは民族的なものと考える傾向に陥りやすかったように思う。しかし、すでに述べたように、そのような神話の凝縮の場は、王権にあったことを忘れてはならない。つまり、『古事記』は斉明・天智・天武という母子王朝において物語化され、蓄積された王権神話のなかから記述されてきたものなのである。
ここで問題となるのは王権神話の多元性である。これまで、倭国神話の多元性は、そのもっとも熟考された形においても、溝口睦子の著書『王権神話の二元構造ーータカミムスヒとアマテラス』(吉川弘文館、二〇〇〇年)の題名が示すように、タカミムスヒとアマテラスを軸とした王権神話の二元性として語られてきた。もちろん、タカミムスヒにも火山神としての性格があるが(保立『歴史のなかの大地動乱』)、この二元性は基本的には天神の世界における二元性である。この二元性も長く残ったが、少なくとも表面では、伊勢アマテラスの位置の強調のなかで一元化の道をたどったことは否定できない。
しかし、そもそも神話は、本来多元的なものであって、同時にきわめて地域的なものである。『かぐや姫と王権神話』で論じたように、丹後から諸国を流浪した月と豊饒の女神トヨウカ姫、その系列を引く広瀬社のワカウカ姫、伊勢のトヨウカ姫も独自の神話世界である。また、『古事記』の出雲の物語は、地神オホナムチの神話を明瞭に示している。他面において『古事記』が、この地神オホナムチの神話を出雲に押し込め、祭り籠める営為を表現していたことは事実であるが、しかし、スサノヲとオホナムチという地神の世界は簡単に消えていくものではないだろう。少なくとも七世紀までは倭国神話の世界は、そのような多元性のなかにあったはずであって、そのような多元神話世界に対する王権と国家の関わりも多元的なものであったはずである。拙著『黄金国家』で述べたように、私は、八世紀の律令王国までは、倭国国家は民族複合国家というべき特徴を維持していたと考えているが、もしそうだとすれば神話世界の多元性は当然のことであろう。
もちろん、八世紀を通じて、全体として王権神話と国家宗教が伊勢神宮と東大寺に一元化していったことは否定できない。それが仏教と道教という中国宗教の圧倒的な影響の下に倭国の神話時代が最終的に終了していく過程であった。これも拙著『黄金国家』で述べたように、聖武天皇の時代、王家の宗儀・宗教空間は王家の氏神・伊勢神宮と王家の氏寺・東大寺に密接な関係をもって一元化されていったのである。こういう多元的神話の一元化という動きのなかで、都市的宗儀としての神道が都鄙に広まっていき、そこに神話から神道へという動きが作動したということになるだろう。
(3)天武の「吉野神話」とその変容
これらについては拙著『かぐや姫と王権神話』で必要なことを述べたが、それをさらに神話論に内在して跡づけることは、すでに本稿の課題範囲を超える問題である。
ただ、ここでは斉明・天智・天武の七世紀王朝が深く関わっていたオホナムチ神話の軸が、そう簡単に消えることはなかったことのみを確認しておきたい。そもそも、前方後円墳=火山には地下世界が表象されており、スサノヲ・オホナムチなどの姿は消そうとしても消せるものではなかった。八・九世紀における地震や噴火の頻発が、人々に彼らの猛威をあらためて印象づけたこともいうまでもない。こういう地震火山神話の復活ともいうべき時代のなかで、多元的な神話は消滅していったのではなく、形態を変化させて執拗に残っていったのである。
もっとも重要なのは、吉野大名持社の位置である。つまり、前述のように吉野大名持神は九世紀半ばに全国の神祇のなかで飛び抜けた位置をもっており、それは奈良王朝においても同様であったはずである。そして、その原点は天武・持統朝にあったろう。天武・持統の時代、吉野が王家内部の宣誓を行うような神聖な場所であることはよく知られているが、そこには「吉野神話」ともいうべきイデオロギーがかぐや姫のような天女幻想をふくんで多様な形で展開した(「『竹取物語』と王権神話」『物語の中世』所収)。この吉野神話の根底には吉野渓谷への入口、吉野川右岸の大名持神社への天武・持統の信仰あるいは畏怖が潜んでいたのは当然であろう。
問題は、このオホナムチ神がいわゆる神仏習合の中で一〇世紀には自在天神と同体であるとされるにいたることである。いうまでもなく、この自在天神の別の顔が菅原道真なのであるが、一〇世紀には、道真が吉野金峯山の地下の地獄にいて醍醐天皇を責め問う地獄の王者の地位にいたと広く観念されていたことは有名な事実である。とくに重要なのは、『扶桑略記』によれば、道真は、そこで「火雷大気毒王」を手下にして「山を崩し、地を振ふ」力をもつ地震の怨霊と化していたとされることである。『宇治拾遺物語』(巻二ー四)に、「この(金峰山の)金をとれば、神鳴、地震、雨ふりなどして少しもえ取らざんなる」という吉野の金伝説のなかに、「地震」が登場するということは、吉野の神は地震を起こす神であるというのは、当時、一般的に信じられていたことなのである。もちろん、その表側には、吉野は「金」が埋蔵されている場であり、金峰山の地獄は、同時に黄金浄土であるという観念があり、だからこそ、藤原道長その他の吉野詣が行われたことはいうまでもない。また右の『宇治拾遺物語』の吉野の金伝説の、京都七条の薄打が「みたけまうで」の途次、「金崩」の場で金鉱石を拾得したが、それによって作成した薄の一枚一枚に「金のみたけ」という銘が浮き出たという説話は、吉野金伝説が鉱業関係者にまで広まっていたことを示すものであるといってよいだろう(これらについては保立『黄金国家』青木書店、二〇〇四年を参照)。
このことを考える場合、自在天神、道真が菅原氏の出身であり、菅原氏は、少し前にさかのぼれば土師氏であることに注目しておくことが欠かせない。つまり、前述のように、土師氏は陵墓の管理者として深く王権による地下世界の管理に関わっていた氏族であるが、彼らは、八世紀には、その技術力などを梃子として律令官人として立身する動きを強めた。とくに八世紀末、光仁天皇が土師氏の本拠に近い、右京から大和添下郡付近を本拠とし、土師氏出身の母をもっていた高野新笠を妻としたこともあって、土師氏は、菅原氏・大枝氏・秋篠氏などに改姓して、陵墓担当氏族の伝統から離陸することに成功した。高野新笠が桓武の母であったことはいうまでもない。
私は、この氏族的な記憶は菅原氏自身のなかにも、また菅原氏という氏をみる宮廷社会の目のなかにも強くのこっていたのではないかと考える。そのような観念がオホナムチ神を媒介として天武の吉野神話にまで遡ることに注目しておきたい。こう考えてくると、菅原氏の出世頭、菅原道真が怨霊となって吉野の地下、大名持社の地下の地獄にいるという観念は、このような長い伝統をふまえる形で形成されたと考えることもできよう。オホナムチへの畏怖は、このような形で、国家宗教、国家イデオロギーの枢軸部になかば自己矛盾的な要素として維持され続けたのである。
なお、私は、こういう吉野に地震の神が棲むというのは、おそらくその近辺を中央構造線が通るという列島の地質学に根拠をもっており、形態を変化させつるも、列島の歴史において長く引き継がれたものではないかと考えているが、これについては後の考察に譲りたいと思う。
おわりに――石母田のめざしたもの
もう一度、石母田の神話論に立ち戻ると、石母田の神話論は、中途で終わっており、かつ多くの問題を含むものだったとはいえ、石母田の他の仕事と同じように歴史学にとっての基礎構築の役割を果たしたものであることは明らかであろう。歴史学が倭国神話に取り組む際、方法論的にいって最初に取り組まなければならない神話が、ヤマトタケルやオホナムチの問題であるからである。これによってこそ、神話論研究は社会経済史その他の基礎研究分野と連接することができるのである。
もちろん、歴史学的な神話研究は、第一には津田左右吉が代表する神話の文献学的な研究を十分にふまえなければならない。それによって神話テキストの政治性、その政治神話としての様相を批判的に明らかにすることは必須の作業である。また、第二には、神話に対応する国家的な祭祀儀礼を詳細に分析していく、岡田精司によって開拓された祭儀神話論といわれる研究方向が重要なことはいうまでもない。
これらなしには神話の歴史学的分析は中空を舞うことになってしまうだろう。しかし、ここで石母田が基礎構築を果たしたというのは、神話の内容に即した神話のイデオロギー分析のことである。歴史学が、これを分析する上では、人間の英雄化という物語としての英雄神神話、そして人間の棲む大地・自然を神格化する大地の神々の神話の分析こそがすべての基礎にすわらなければならないというのが石母田の判断であったのだと思う。歴史神話学は、この類型の神話の分析をふまえながら、王権神話や宇宙創造や諸天体に関わる神話の内容的、イデオロギー的分析に進むことができる。それなしには、神話の分析は根拠をもつことはできない。
石母田正は倭国神話の研究において、『古事記』と『日本書紀』との性格上の相違を明らかにすることにはじめて本格的に挑戦し、文学テキストとしての神話の分析に挑み、基本的な論点を明らかにすることに成功した。それは自己目的ではなく、神話の歴史学的なイデオロギー分析こそが目指されていたことはいうまでもない。
本稿全体で強調してきたように、石母田の神話論は、第一には津田左右吉の政治神話論を乗り越えようとする、一生を通じての営為だったのであるが、しかし、第二には、松村武雄を代表とする神話学プロパーの仕事に学び、それを歴史家として再構築しようとする仕事であったのだと思う。石母田は、この二人の仕事を総合的に乗り越えることで、神話の歴史学的なイデオロギー分析を目指したのだと思う。
皇国史観という神話史観によって、この国家が全面的に色づけられていた時代はけっしてはるか昔の時代ではない。石母田は、それをふまえて、本居宣長からはじまる近代的な「民族神話」の理解のレヴェルを徹底的に批判し、現在にふさわしい神話の理解を準備しようとしたのだと思う。神話とは、日本列島に棲むもの、この民族にとって何を意味するのか。石母田にこの問題を意識させたのは強烈な現代認識であったのだろう。第二次世界大戦という野蛮を神話の跋扈のなかで経験した歴史家にとっては、神話のもつ「原始的な力」「人間の原始的創造的な力」をどう位置づけるかという「古代貴族の英雄時代」の問題意識は抜き差しならないものであったに相違ない。有名な石母田の首長制論を初めとする議論が人類学的な諸研究への興味・関心によって支えられていたことはよく知られているが、そこには、このような意味での原始と神話の追求の衝動が潜んでいたのではないだろうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
