
西松秀祐「大分から函南へ(1日目)」
新しい地域へ旅をするときに、どの交通手段を使って行くのが良いのか、いつも私は迷ってしまう。その理由は「移動の仕方」によって街の第一印象というものが大いに異なる様に思えるからだ。結局迷った末、私は丹那トンネルを通って函南へ到着することにした。その丹那トンネルは事前説明会でも少し話が出ていて、函南町を訪れたことのない私にも、その場所は函南にとってとても重要なものに思えた。
丹那トンネルは熱海〜函南間を貫通する全長7807mに及ぶトンネルで1918年から16年間にも及ぶ工事の末、完成した。トンネル工事は、坑内から溢れる丹那の湧水と温泉まじりの粘土等によって難航し多くの犠牲者を出した。その中には朝鮮人労働者も大勢含まれている。そして試行錯誤の末、トンネル内の水を抜く方法に「水抜き坑」と呼ばれる、トンネルとは別に水を抜くためのトンネルを掘る方法が進められた。
函南町は昔、水田がたくさんあり、わさびなども取れる、水が豊かな土地だったそうだ。しかしその水はトンネルの掘削に伴い、丹那の山から失われ、稲作が中心だったこの地域では稲作にかわるものとして酪農の振興に力をいれていくことになった。
大分県杵築市にある自宅を朝9時に出発し、11時大分空港発の飛行機に乗る。そして成田に到着し、事前に知った丹那トンネルを通り函南へ向かうため、そこから新幹線には乗らず、普通列車で向かうことにした。電車の中では、これから出会う函南町についての自分がしっている情報を整理したり、風景を眺めながら過ごした。
:丹那トンネル / 近代と戦争(函南の近代、日本の近代を考える)
:丹那の丹の字について・地質との関係で見てみる(函南の古代を地質学的、そして民俗学的に考える)
:柏谷横穴群と占部性、そして亀卜について(伊豆、そして函南の古代を民俗学的に考える)
:函南と乳製品 / 伊豆と乳製品について(酪農と丹那トンネルの関係)(幕末、アメリカ領事館があった下田で米国総領事ハリスが日本で初めて牛乳を購入したらしい。この観点でも近代化と伊豆について考える)
:伊豆半島の地質、地盤と風土について(伊豆半島がのっているフィリピン海プレートは年間4cmのスピードで移動している。大地の移動と人の移動について考える)
窓から富士山を眺めていると、三島で借りる予定だったレンタカー屋から電話があった。「営業が6時までなので、その前までにお願いいたします。三島駅からは少し遠いので気をつけてください。」時刻はすでに15時半になっていた。予定では函南で一旦外にでて散歩をして、5時くらいに三島へ行く予定だったが、どうも函南で散歩する時間はなさそうだった。
電車は丹那トンネル内に入り、少し進んでいくと耳鳴りが鳴り出した。久しぶりに感じるその音は無線の何かのシグナルのような気がすこした。そうやって私は初めて丹那トンネルを意識した。
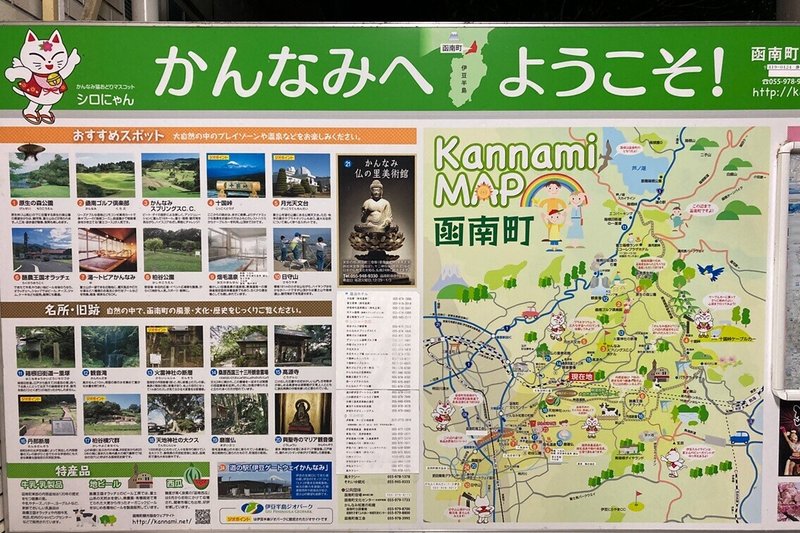
三島に着いてからはレンタカー屋に間に合うようにバタバタと慌ただしかった。ギリギリ時間内に入り、とりあえず函南駅へ車で向かったが、到着した時はもう夜で辺りは何も見渡せず、明日はどこから散策しようとか考えなら三島でとったホテルへ向かった。
