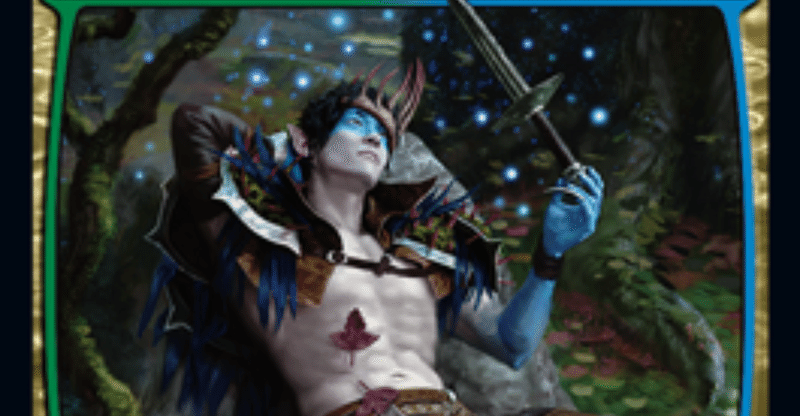
Dr未熟者の読む処方箋(フードミラー編)
0.挨拶
皆さんこんにちは。未熟者といいます。普段は精神科医をやっており、仕事がそこそこ忙しいこともあるため大学生の頃より練習時間がとれていないのですが、その分ひたすら考えることでイベント前の準備をするようになりました。今回は現スタンダードについて備忘録的に自分の考えを残しておこうと思います。
1.序論
読者の皆さんも知っての通り、今のスタンダード(GRN〜ELD)はオーコによって定義されていると言っても過言ではない。MCリッチモンドにおいてもフード系デッキのみで60%超、オーコを使用してるデッキは約70%となっており、近年に例を見ないほど1つのアーキタイプが強い、誤解を恐れずに言えば一強時代と言える。
そのようなスタンダードにおいてはフードミラーは多発し、イベントで勝ち抜くためにはフードミラーの肝を押さえることは必須であると強く感じる。実際、私も先日のMF名古屋2019にスゥルタイフードで参加し、2bye明けの13回戦でフード系デッキと10回対戦した。結果は11-4(2bye)で負けはスゥルタイフード3つとラクドスサクリファイス。スゥルタイフード相手にあと2回勝てていればPT権利をとれていたと考えるとやはりミラーを制することは今のスタンダード環境において非常に重要なものであると考える。
まず、現環境に存在するフード系デッキに関して知識を整理しつつ、そこからミラーの肝についてや細かい採用カードについてスゥルタイフードをメインに考えを進めていきたいと考えている。
1.フード系デッキのバリエーション
フード系デッキが金のガチョウ、意地悪な狼、王冠泥棒、オーコ、世界を揺るがす者、ニッサを核としたミッドレンジデッキであることは最早言うまでもないだろう。しかし、その核以外のカード選択で多くのバリエーションがあり、それぞれについて把握しておくことは重要である。以下にそれぞれの特徴を簡潔に示す。
A.シミックフード
青緑でまとめられたフード系デッキの最もベーシックな形。自由枠には厚かましい借り手と霊気の疾風を採用しており、バウンスでテンポをとりつつ、フード系デッキの中ではライフをいち早く0にすることを目指すデッキで構成としてはテンポデッキを意識している。バウンス呪文も多く、フードミラーの肝である意地悪な狼を最も上手く対処できるのも大きい。2色であるため、土地周りのストレスが最も少なく、スクライランドや総動員地区のようなミシュラランドも多く採用できる。反面アドバンテージ手段には乏しく、長期戦になると後述するスゥルタイフードには徐々に不利な展開を強いられることも多い。


B.バントフード
シミックフードに白をタッチすることで時を解す者、テフェリーや拘留代理人を採用しているタイプ。3色であるため土地によるライフダメージは多いが、対インスタントデッキに強いテフェリーがあるため、アンチスゥルタイフードデッキである青白コントロールやティムール荒野の再生デッキに耐性がついている。シミックフードもインスタントタイミングでの動きが多く、テフェリーの存在は大きい。一方、タッチしているテフェリーも含め、スゥルタイフードの害悪な掌握で対処できるカードが多いため、スゥルタイフードに対してはシミックフードよりも不利を強いられやすい構成といえる。基本的にメインの除去枠には霊気の疾風をとっているためシミックフード同様テンポデッキを意識しているが、メインから集団強制をとり長期戦に強くしているリストもある。


C.スゥルタイフード
フードミラーにおいて有効な除去となる害悪の掌握や環境に多く存在する色対策である害悪な掌握や霊気の疾風で触ることができない戦慄衆の将軍、リリアナ、フードミラーで一発逆転を狙える戦争の犠牲など強力な黒のカードを採用するためにシミックフードに黒を足したタイプ。重いカードが多く、1対1交換を繰り返すカードも多いため、フードミラーでは長期戦に最も強いタイプである。反面、土地によるライフダメージも多く、テンポデッキとして振る舞うフードデッキに対してはライフで押し込まれ易い構成ともいえる。また、メインから緑と白以外には全く強くない害悪な掌握に多くスロットが割かれており、フードミラー以外のマッチアップ(例えばティムール荒野の再生やラクドスサクリファイスなど)でメインボード戦を落とし易い。現在のメタゲームにより存在し得ているデッキといえる。


D.ティムールフード
エンバレスの宝剣や王家の跡継ぎなど赤のカードのために赤をタッチしたタイプ。現在は使用者が少ないが、探索する獣+エンバレスの宝剣のコンボなど爆発力は高く、注意は必要。


以上4タイプからメタゲームやプレイスタイルに合わせてフードデッキを選択しているプレイヤーが多い。現時点では安定感からシミックフード、長期戦や後手での試合の捲り易さからスゥルタイフードを選択しているプレイヤーが多いように見える。
特に基本的には長期戦を目指すべきではないシミックフードやバントフードは理想的な動きの再現性(いわゆるドブンムーブ)を目指すことが必要であり、マリガンは積極的に行う方がよいと考えられる。動きの再現性を担保するためにむかしむかしが4枚採用されていることが多いのだから当たり前といえば当たり前だが。逆にスゥルタイフードは相手の再現性に対して如何にして干渉し、長期戦を目指していくかが問題になる。続く章ではこの理想的な動きの再現性について考えていく。
2.理想的な動きの再現性
すでに述べた通り、フード系デッキがメタゲーム占有率を多く占めるこの環境においてミラーゲームの肝を押さえることは重要であると考える。まず、純粋なフードミラーにおけるゲームを決定付ける序盤の動きについて考える。
a.2ターン目オーコ
1ターン目金のガチョウ、2ターン目王冠泥棒、オーコという1番速い動きである。干渉がない場合、オーコの+1から3/3が生まれるもしくは-5能力で金のガチョウを手に入れることができる動きで、すでに金のガチョウが出ているため、毎ターン2マナを支払うことで3/3が生まれる1番の動きである。この環境ではショックインでライフが18になっていることも多く、無干渉であれば3→6→9と3ターンで18点が削れ、早急にゲームが終わることになるため相手は完全な無視ができない。一方で各デッキ2マナの除去があるため、(特に後手の場合は)そこで上手く干渉していくことになることが多い。

b.3ターン目ニッサ
1ターン目金のガチョウ、2ターン目マナクリーチャー、3ターン目世界を揺るがす者、ニッサという動き。オーコと違い、土地さえあれば特に縛りなく毎ターン3/3(しかも警戒!)が生まれる上、ニッサを処理されないと次のターン以降使えるマナが大幅に増えるためX=6以上のハイドロイド混成体をキャストしたり、アクションの手数が増えたりと相手の裁く手数がまず足りなくなる。また、ニッサが出たターンにもクリーチャー化する土地によっては打ち消し、除去、夏の帳などを構えることもできる(それらのカードがなくても金のガチョウから食物トークンを生んだり、むかしむかしを唱えたりもできる)ため、テンポで押すことができ、ミラーにおいては非常に有利な展開となる。完全に私見だが、2ターン目オーコのパターンよりも対処するターンが遅れるほど取り返しがつかなくなるケースが多いと感じる。

c.4ターン目ハイドロイドX=6
ニッサが絡まなくとも稀なケースとしてこれがある。1ターン目金のガチョウ、2ターン目楽園のドルイド、3ターン目マナクリーチャー2体、4ターン目ハイドロイド混成隊X=6キャスト。これも速いターンに6/6飛行トランプルが生まれ、3ドローで後続の脅威を引きに行けるため、非常に強力な動きである。フードミラーにおいて、PWの初期忠誠度は能力起動込みで6であることが多く、ハイドロイドのサイズは(飛行を含め)強いプレッシャーとなる。

以上のような動きを再現することが早期にゲームを決める上で重要であり、フード系デッキはこの動きを目指していくことになる。こう考えると動きを再現しようとしているフード系デッキに対してはここに如何にして干渉していくかが肝になる。すなわち、如何にして相手のマナクリーチャー展開を阻害しつつ、こちらが盤面を展開していくかがゲーム展開での1つの鍵となる。また、オーコ、ニッサ両PWが3/3を製造し続けることを考えるとミラーを定義するサイズはパワー3であり、3/3製造機を無視せずきちんと処理していくためには3/3が2体ブロックされずにコンバットできる場を如何にして作っていくかも重要と考えられる。要はどうやって相手より2体多く3/3を作るかという話である。この3/3が跋扈する盤面を制する上で肝になってくるのは除去、もっといえば意地悪な狼ということになることは明らかである。

加えて、除去の枚数を考えるとやはり除去は貴重なカードであり、除去をなるべく3/3製造機に使わずに盤面だけで処理できる場を作っていくかを意識していかねばならない。
3.3/3が跋扈する盤面をどう制するか
このように書くと当たり前なことに思えるが、3/3製造機を放置しないことと3/3を使ったコンバットを如何にして有利にしていくかがミラーの肝になる。そのためには4/4以上のクリーチャーをどう用意するかもしくは3/3を相手よりどれだけ多く用意していくかという話になってくる。そこで重要になるのはハイドロイド混成体と意地悪な狼である。
特に意地悪な狼は起動能力によりサイズが上がることと破壊不能になることが自分の場を強固にする上で肝要であり、それに加えて除去能力も内蔵しているためフードミラーの盤面の取り合いでは非常に重要な役割を持っていることがわかる。裏を返せば相手に意地悪な狼を上手く使わせないことも意識しなくてはならない。ミラーでは意地悪な狼をより強く使えるプレイヤーが勝つことになるはずだ。
4/4を用意して相手の意地悪の狼を誘って除去を構える動きも大切だし、これだけ意地悪な狼が重要であるならば食物トークンがない状態で出して相手のオーコ-5で奪われるようなことは基本的には避けるべきだ。早い段階で相手の意地悪な狼を大鹿にすることがゲームを決めることもあるだろう。
意地悪な狼の起動型能力を上手く使うためには当然だが食物トークンが必要であり、食物トークンの供給源はガチョウとオーコであることがほとんどである。その点においてフードミラーはガチョウを巡るゲームであるとも言える。

ここまで考えると、金のガチョウを1ターン目に出しても2ターン目に起動能力を構えることの合理性もみえてくる。起動能力を使って食物トークンを2つにしておくと相手のガチョウをとりつつ3ターン目に食物トークンを残したまま、意地悪な狼を出すこともできる。再現性という話もしたが、この環境における再現性というものがある程度煮詰まってきており、お互いに干渉を意識するようになれば、このような動きにも価値が出てくる。万が一ガチョウに除去が打たれるようであれば後続のオーコが残り易くなり、3/3を2ターン連続で作ることもできる。また、食物トークンを増やしておくのは後のオーコのために2マナを貯金しておくという考え方も出来る。2マナというのは除去のコストと同じであり、後半に除去を含めたダブルアクションをとることも有利な場を作るためには必要となることも多いだろう。
また自分のハイドロイド混成体をオーコで大鹿にすることも検討しなくてはならない。こうすることで4/4以上のサイズを用意することが出来、3/3製造機の取り合いで有利になることも多い。相手が食物がないからと言って3/3製造機を棒立ちさせるようなことがあれば6/6以上の大鹿で落としに行くチャンスも生まれる。
ここまで書いてきたことで完結してはいるが一応簡素にまとめておくとオーコの運用については基本的には3/3を作れる場合は3/3を作っていき、必要に応じて相手の脅威を3/3にすることや自分の狼を強く使うために食物トークンを出す、マナを伸ばすために相手のマナクリーチャーをもらう、自分の場に4/4以上の大鹿を作るということも適宜検討していくのがいいということだろう。
4.自由枠の検討
ここまで書くと害悪な掌握や霊気の疾風については除去カードとして必要であることは当たり前のように感じる。追加として厚かましい借り手が採用されるのも納得できる。3/1飛行というカードも3/3製造機の取り合いにおいて信頼できるアタッカーである。一方で干渉へのアンチカードということを考えると夏の帳というカードの理不尽なまでの強さも理解できる。1マナで干渉カードを無効化しつつ、1ドローもすることができ、相手と2枚のカード差、さらにテンポまでもとることが出来てしまう。フードミラーの研究が進み、干渉に重きが置かれるのであればメインボードから採用されるのも理解できるだろう。そうなると自由枠に関しては上記の除去カードと夏の帳に強いカードをとることを考えなくてはならない。その点、霊気の疾風はカウンターとして見れば夏の帳でアドバンテージ(とテンポ)をとられないためある程度信頼できる干渉であると考えられる。また、(余談ではあるが)自由枠ではないが意地悪な狼も害悪な掌握には強いカードであるがバウンスには弱いため夏の帳がない場合はある程度考えてプレイしなくてはならない。
集団強制は盤面のとり合いで非常に強力なカードであるが夏の帳でカウンターされるため、重さに対してリスクが大きい。色拘束も大きいため、キャスト出来ないリスクを考えると現環境ではあまりオススメ出来ない。戦争の犠牲も同様である。呪われた狩人、ガラクも非常に強力なカードだが-3能力が夏の帳でカウンターされ、害悪な掌握や霊気の疾風で除去されることを考えると現環境ではあまり輝かないカードであると考えられる。ゴルガリの女王、ヴラスカもこの環境においてはガラクと同じことが言えそうである。


そう考えると除去カードで干渉されず、どの能力も夏の帳でカウンターされないことから戦慄衆の将軍、リリアナは非常に安定したパフォーマンスを発揮できるカードと考えられ、最も考慮すべきカードと考えられる。
リリアナは起動込みの初期忠誠度が7であり、上述の3/3製造機と違って3/3 2体のアタックで落とせないことも大きい。クリーチャー死亡時誘発も強力で奥義もゲームを決定付ける。長期戦においてはほとんど肝と言ってしまっていいだろう。

5.サイドボーディング、マリガンについて
フードミラーにおいてはあまり過剰なサイドボーディングは行わない方がよい。上述のようにお互いに動きを再現するゲームであり、それをあまりにも歪めるのは干渉を考慮しても敗北に直結することがほとんどだからだ。そう考えると、テンポデッキであり、再現性を求めるシミックフードやバントフードは(特に先手では)あまりむかしむかしを抜き過ぎない方がいいのだろう。反対にスゥルタイフードは長期戦を見据えているデッキであるから、むかしむかしを抜いても干渉カードがあればある程度ゲームをつくれるためあまり大きな問題にはならないと感じる。

後手に関しては如何にして相手の先手の再現性に立ち向かっていくかというのが論点になる。やはり、ダブルアクションを取ることで先手と後手の動きをひっくり返すターンを作るのが単純明解であり、そう考えると後手の場合は神秘の論争と軽蔑的な一撃という軽いカウンターを相手のビッグムーブに上手く当てていく必要があると感じる。


このように後手は基本的に再現性への干渉を行おうとするので、先手では特に夏の帳が強い。といってもサイドカードに関しては噛み合いも大きいので相手のフードミラーへの理解度によって柔軟に対応すべきである。後手に関しては干渉を入れ過ぎると夏の帳でハマるパターンも多く、注意が必要なことは確かだ。プレイに関しても相手の夏の帳になるべく得をさせないようにすることが後手では特に重要だろう。そのためにもソーサリーの除去(上述したようなヴラスカやガラクなど)は可能な限り避けるべきでインスタントの除去に抑えておくことが1番嫌なパターンでハマることはないのではないかと思う。

併せてマリガンについてもここで述べる。上述のようにシミックフードやバントフードは再現性を目指すデッキなので、マナクリーチャーがないハンドは強気にマリガンする方が結果として勝率は上がるだろう。スゥルタイフードに関しても再現性はもちろん追求すべきだが、ハンドによっては、例えば序盤には干渉カードを使い、続いて意地悪な狼や3/3製造機で相手の展開を追いかけることが出来るのであればキープすべきだろう。スゥルタイフードは長期戦も可能なデッキなのだから。
6.終わりに
この環境はオーコばかりで息苦しいという話をとにかくよく聞く。その気持ちは非常によくわかるが、再現性と干渉をテーマとした序盤のやり取りに関しては理解度によってゲーム展開を捲ることが十分可能であり、非常に面白い環境であるとも考えられる。私が考えるにこの環境のフードミラーは半分の定石と半分のドロー運によって成り立っていると思う。恐らく、次回の禁止改定でスタンダードの環境は大きく変わるとも考えているが、来週までこの環境を少しでも楽しめるようになれば幸いである。ここまで読んでくださった読者の皆様に幸あらんことを!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
