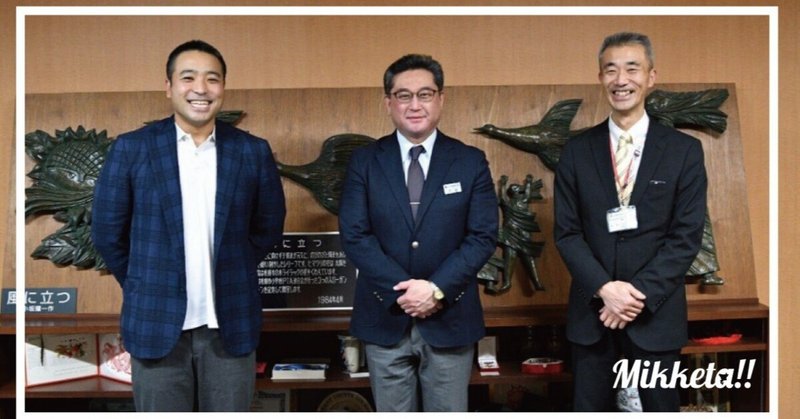
札幌市のGIGAスクールは今 〜前回取材から1年〜
この記事は、2021年7月2日に北海道のIT情報発見!発掘!マガジンのmikketa!!に掲載されたものです。
昨年10月にお伺いし、学校教育のDXである「GIGAスクール」についてお話を伺った札幌市教育委員会。
GIGAスクール開始前の3月から4月にかけての、Mikketaへのアクセスはほぼ「GIGAスクール」というワード検索での流入が多く、皆様の関心度の高さを伺い知ることができました。
さて!今日は続編です!!前回お話を伺ってから1年が経ち、あの当時は「まずはなんとか1人1台端末の導入実現を」という段階ではありましたが、実際どのような感じで進んだのでしょうか!早速お話を伺ってきました!
想像以上に順調に進んだ導入と推進
お話をお伺いしたのは前回同様、札幌市教育委員会の水野課長と今年の4月から学校より異動されてこられた伊達課長です。「1年ぶりですねー!」のご挨拶とともに、水野課長が持っている紙に視線が釘付けになる編集部。その紙には「GIGAスクール通信」と書かれていました。
GIGAスクール通信は、札幌市内の小中学校でICTをうまく活用できた!という事例を現場から集め、教育委員会が月1回学校現場へ事例紹介として紹介するために作成しているものだそうです。

この「おたより」とついつい呼びたくなってしまう、可愛いフォーマットのお知らせは、インターネット上でも公開されていて、誰でも見ることができます。
おたよりには、導入されているツールの活用方法以外にも、授業内でどういった取り組みが行われているのか、どのような工夫をしているのかが記載されており、市内小中学校の教員宛に配布されているものとのことでした!こういったおたよりがあると、他の学校の取り組みを知ることができ、良いものをどんどん取り入れていく土台が作られていきそうですね!!
前回の取材から1年が経過し、モデル校以外の生徒たちが端末やICTに触れるようになった4月から早くも8ヶ月が経過したわけですが、学校現場からの反応はどうだったのでしょうか。
「概ね良好です。新しいことに学校として取り組んでいくにはたくさんのエネルギーが必要となります。例えば、新しいソフトウェアを入れたら、その使い方を教員がマスターしなければ、子どもに教えることはできませんので、教員はとても大変でした。でも、端末やソフトを活用することに慣れてきたら、今までできなかったことが一気にできるようになるなど、学びの可能性が広がることを実感できます。(端末やソフトウェアの)導入時は大変でも、実際に活用してみて、その効果を感じている教員は多いと思います。」と、伊達課長は言います。言葉に熱があるなぁ。なんて思いながらお話を聞いていたのですが、それもそのはず、今年の3月までモデル研究校である中央中学校の教頭先生をされていたんだそうです。実際に現場にいて、先生方や生徒たちの反応を見ていたからこそ、良い面だけではなく悪い面もご自身で経験されていたからこそ、話される言葉に重さと熱さがあったんですね。
「私自身、ICTに詳しかったわけではないのです。学校全体を俯瞰して、うまく進むように体制づくりをしていくのが教頭の役割なので、教員同士による学び合いなどのコーディネート等は、ICT担当教員や積極的な教員に任せていました。モデル研究校としてやってみて思うのは、みんなでICTを導入していこうという、雰囲気の醸成がすごく大事だということです。そのために、教員の役割分担を明確にしました。最も高かったハードルは教員の意識改革です。教員が受け入れなければ、子どもへの活用を促してはいけないので、いかに前向きに取り組んでもらえるか。ということを常に意識して、働きかけを行っていました。」
”概ね良好”と、伊達課長がいう札幌市のGIGAスクール推進。「今年1年間は展開の年。」と、以前のインタビュー時にも言っており、1年間かけて「みんな1人1台端末を活用できるようになったね。」と言えるようにするというのが初年度の計画だったといいます。ですが、先生方の頑張りと、児童・生徒の頑張りの相乗効果によって、想像以上のスピードでICT活用の教育活動が進んだそうです。
「端末を活用できるようにすることが目的ではなく、端末を学習ツールとして効果的に活用し、学びにつなげることが目的である。」というのが、札幌市教育委員会の共通の認識だといいます。ツールを使えるようになった上で、子どもたちの”学び”にどういった良い影響があるのか。また学校での活用だけで終わらせるのではなく、学校の授業と家庭学習を接続するというのも、GIGAスクール構想を考える上での大事な観点の一つです。

「端末の家庭への持ち帰りについては、感染症や災害時にやむを得ず登校できない児童生徒に対する学習支援のために行うことを可能としていましたが、9月からは平常時における持ち帰りも可能としました。このことにより、授業と家庭学習の接続を図るだけでなく、学習・生活習慣づくりにも期待できます。新しく導入した学習を促進させるソフトウェアは自宅でも活用でき、子どもは端末を活用しながら、自分のペースで学びを進めることができるようになっています。また、苦手な部分を克服するための問題を重点的に解くことも簡単にできるようになっています。まさに、個別最適な学びにつなげていけるというわけです。」
差ができないような工夫と取り組み
とても順調に進んでいるGIGAスクールですが、次のステップを見据えた際の課題について、「学校差ができないように底上げをする、というのが現時点での大きな課題」と伊達課長が教えてくださいました。
これはどこの組織でも、新しいものを導入した際に、起こり得ることですよね。新しいものをおもしろい!と思ってドンドン試していくグループと、既存のやり方の踏襲を目指すが故にゆっくり進むグループと、組織が大きかったり、独立化していると起きやすい問題だといえます。札幌市には小中合わせて約300の学校があります。それぞれが同じ場所にあるわけではないので、同じように進まず、進度に凹凸が出てしまうのも仕方ないことだと言えるのかもしれません。
一方で、こと子どもの学びとなるとそのようなことは言っていられないのも現実です。例えば、中学校への進学のことを考えてみるとどうでしょう?「あんなに小学校で端末を活用していたのに、中学校では、・・・。」ということが起こる可能性があります。また、小学校から中学校に進学する際、同じ小学校からの生徒だけではなく、周辺の小学校から生徒が集まってくると言ったようなこともあるのではないでしょうか。そうなった時に、「うちの小学校ではこんなことはやってなかった・・・」ということが起こる可能性もあります。小中連携・小小連携は、ICT活用という側面からも重要です。

「来年4月から、市立の高校でもGIGAスクールが始まります。まずは1年生からという形です。中学校で使ったものを高校になったら、『ちょっとできません』という話にはならないですよね。ちゃんと継続させていかなければなりません。」
「本市では、小中一貫教育の促進も行っています。言葉は聞かれたことがある方もいらっしゃるかもしれません。言葉だけ聞くと、小学校と中学校が同じ土地にあって、同じ校舎で学んでというものをイメージされるかと思うのですが、本市は、小中一貫した教育として、小学校1年生から、中学校3年生までの9年間を通した学びのつながりや、子ども理解・生徒指導の連続性を大事にしていきましょう。というのを全ての市立学校で展開していきます。この小中一貫した教育は、次年度から全面実施となります。」
具体的に話を聞くと、各中学校がハブ(中心)になり、周辺にある複数の小学校とパートナーになり、校種間の連携による連続性のある教育活動の充実を図っていくというものだそうです。学びは、各学年だけで終わるものでもないですし、小学校だけで終わるものでもありません。小学校と中学校の9年間がつながって初めて、基礎となる学びが身につくとも言えます。そうなった時に、中学校に進学したからといって、今まで学んでいたものが活きなくなってしまうと非常に勿体無いですよね。そう言ったことがないように、9年間通して子どもの学びや成長を支えていきましょうという取り組みなのだそうです!今後どのように展開されていくのか、とても楽しみですね!!
GIGAスクールが始まって起きた変化
「実は、GIGAスクールが始まったことで、別室登校している子どもにも、教室で受けている授業と同じ授業を届けられるようになったんです。その結果、クラスの雰囲気に馴染むことができ、教室に入れるようになったという報告もあります。」
思わぬ変化だったと二人は口を揃えて言います。もちろん、毎日教室に行くようになるというのは非常にハードルが高く、教室に行ったり、別室登校をしたり、状況によって使い分けているのだそうですが、「教室に入ってみる」というアクションができるようになったのは、紛れもなく遠隔で教室と同じ授業を受けることで、クラスの雰囲気を知れたことが要因なのではないでしょうか。

そうなると、授業もオンラインでできるようになるのでは??と思い聞いてみるとこのような回答が返ってきました。
「新型コロナウィルスの第六波に向けて、9月下旬に各学校に通知を出しています。授業配信等に向けた接続テスト並びにリモートテスト(双方向体験)を実施してください。といった趣旨のものです。ですから、11月中旬現在では小・中学校約300校全てにおいて、授業配信ができるようになっているんです。」
授業配信に向けて、着々と準備を進めてきたという、札幌市教育委員会ですが、一方でこのような考えでもあると教えてくれました。
「(家庭における)オンライン授業っていうと、授業配信だってみんな思いますよね。でも、オンライン授業は、授業配信だけじゃない。授業配信を大切にしつつも、それ以外の学習方法も大切なんです。」
ずっと画面を朝から見っぱなしも、子どもにとってはしんどいことですよね。同じ場所に座って授業を受け続けるというのは集中力が切れますし、健康面からも決して良いことではありません。
「授業配信、課題の配信、端末を活用しない個別学習の時間など、そういった様々な学びの要素をハイブリットで組み合わせることが、札幌市のGIGAスクールなんです。」と先生方にも伝えているんだそうです。
今後の展望について
「私から言えるとすれば、ICTの活用が学びに直結し、子どもがその学びのよさを実感できることが大切です。『先生、こんなことが分かったよ!こんなことができるようになったよ!』と、学びのよさを実感している子どもたちの姿を見ることができたら、それが教員にとっての喜びであり、実感になりますよね。」そう、伊達課長は頬を緩めました。
子どもにICTを活用させる、学ばせるとなると、「どううまく使えるようになるか、プログラミングができるようになるか」そう言った論点で話されることが多いかも知れません。
インターネットという世界には限りがないため、知りたいことがたくさんある子どもは、たくさん調べることができ、たくさんのことを吸収することができるというメリットがあります。一方で、限りも垣根もないため、常に危険とも隣り合わせだとも言えるデメリットもあります。メリットデメリット合わせて、しっかりと使い方や付き合い方を、小学校の時点から学んでいくというのは、この先のデジタル社会を生きていく子どもたちにとって、大きな礎になっていくでしょう。今後がとても楽しみですね。
入澤取材後記
今回、1年ぶりに訪問して定点観測でその進歩を見れたことがとても驚きでした。文中にもありますが、前回は、「さて、端末を配ることは決まった。果たしてどうやって行くか?」だったところですが、GIGAスクール通信に代表されるように、各学校が率先して取り組みをし、良い取り組みをシェアしながら底上げを図っていて、本当に素晴らしい取り組みだなと思いました。
「体験をシェアする」というのは、手間もかかるし、そう簡単に出来ることではないですが、先生たちも率先していろんな事例を送ってくれるそうです。掲載待ちな事例が結構あるとか。様々な産業のDXも、こうした「事例」がたくさんあると、それがヒントになりとてもいいですね。Mikketaでも、どんどん掘り起こしていきたいなと思っています。
取材の中で、負の側面の話もいろいろありました。チャット機能によるいじめ問題が顕在化した他都市の事例なんかがあったときに、「札幌市はどうなってるんだ?」との問い合わせもあったようです。札幌市は、チャット機能は使えなくなってるため、同様の問題は起こらないようになっているとのこと。また、アンケート結果では、スマホも含めインターネット環境がない家庭も全体の3%ほどあるそうです。そのため、コロナで学級閉鎖や出席ができないこどもたちに対し、Wifi端末などを貸し出すことも行っているとのこと。現場では、そうした負の側面にも、しっかり考え取り組みを行いながら、「子どもの学び」を底支えしてるんだなと思いました。
アプリ環境は、基本はGoogle Classroomを活用しており、それに加えて、NTTコミュニケーションズ社製「まなびポケット」やベネッセ社製の「ドリルパーク」などを導入されてるとのことです。そういった新しいアプリも導入され、また、来年にはさらに進化してるのではないかと期待もしていますが、デジタルはあくまで手段であり、デジタル技術で学びたい人がもっと学べて、学びが追い付かない人は、何度も復習ができて、子どもの学びが実現されることが、一番の目的だという事は、決して忘れてはいけないと思いました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
