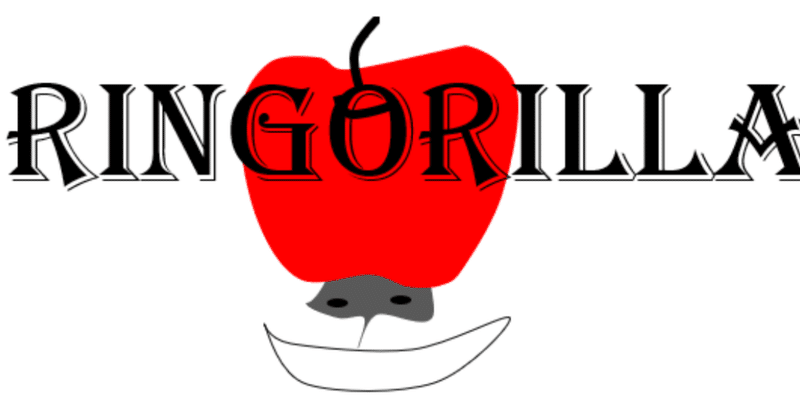
リンゴリラ #2
新富町シティホテル
夏の夜、祭り、ジンジャエール……。庵月は頭の奥にあるイメージの世界にいる。だが、そこは現在からあまりに遠ざかった場所だ。そのため、庵月にはその世界のルールがうまく思い出せない。なぜこんなにも朧気なのかは分かっている。これは母が死ぬ前の世界だからだ。正確には、母が植物状態から完全なる死へとシフトする前。
一人の少女の影がちらついている。シルエット。それだけだ。偶然の出会い……いや、そうではない、庵月はこの少女を探すために夏祭りに出かけた。なぜか彼女がいるのではないか、という淡い期待は大抵当たる仕掛けになっていた。それがその世界の、あるいはその季節のルールだったのだ。それは今ではいくぶん神話じみてさえ見える光景だ。
花火。
だが、その光は、その後のあまりに長い闇に薄められている。
現実。庵月は目を動かす。
自分のいる空間を思い出すように。シティホテルとは名ばかりのカプセルホテルの一室。ベッドにはレイが横たわり、寝息を立てている。庵月はゆっくりとベッドから身を起こし、レイの両こめかみに人指し指を当てる。
「君は掃除屋じゃない」
眠ったままレイは答える。
「私は……掃除屋を殺した」
「恋人か」
どちらとも分からない微笑。目は閉じられたままだ。
「とにかく、君は何らかの理由で長い間掃除屋と一緒に暮らしていた。手伝ったこともあるね?」
「何度も」
「それでも君自身は掃除屋ではない」
頷く。
「なのに君は月島アークホテルにやってきた。なぜだ?」
「お金が必要だった」
「高飛びでもする気だった?」
頷く。
「君が無事任務を遂行すれば、掃除屋の口座にお金が入る。つまり、君は掃除屋の口座を握っているんだな?」
頷く。
「口座の暗証ナンバーは?」
「〇九一九」
庵月は立ち上がり、財布から銀行のカードを調べていく。いちばん手前にあるカードだけ名義が違っていた。セイワエイタロウ。掃除屋の名前だろう。庵月はそのカードをポケットにしまう。
再びベッドに戻り、レイのこめかみに指を当てる。
「君はこれから三日間ここで眠る。これまでの人生で味わったいやなことを忘れ去るには十分過ぎる時間だ。ただし、起きたときは注意することだ。まったく別の人生が待ち受けている」
庵月は部屋を出ると、フロントを通って外に出る。道路の向かいにファミレスがある。庵月はATMでセイワエイタロウの口座から三十万円下ろし、ファミレスに入る。
「フレンチトーストとブレンドコーヒー」
注文してから、トイレに向かう。洋式トイレの便器の中にレイのシルバーの携帯電話を落とす。セイワエイタロウの電話番号だけはメモしてある。
元の席に戻って座る。コーヒーはすでにテーブルに到着している。フレンチトーストはまだのようだ。寝かせ屋になって以来、ファミリーレストランでフレンチトーストとコーヒーを食べるのは、仕事の終わりの儀式のようなものになっている。
庵月はコーヒーをすすりながらフレンチトーストの到着を待つ。
いまのところ、ミスは一つ。「184」と「186」を押し間違えただけだ。致命的なミスとも言えるし、仕方ないと笑って誤魔化せる程度のミスとも言える。どちらなのかを決めるのは、これから何が起こるかにかかっている。
たとえば、いまフレンチトーストが一向に出てこないのには意味があるのかもしれない。そして、トイレに行っている数秒の間に、ほかの客が一人残らず消えてしまっているというのも。
と、一人の男が目の前の空いている席に腰掛ける。その男は異様に鼻が丸っこい。そのうえ、頭は白髪で、どこかのイカれた科学者のようにボサボサに自由に伸びている。目はサングラスのせいで表情が読めない。
「はじめまして」
庵月は軽い会釈で答える。
「携帯電話を出せ」
言われたとおり庵月は自分の黒い携帯電話をテーブルの上に出す。
男はその携帯電話をしばらくいじっていたが、やがて静かにテーブルの上に戻した。
「これじゃない、別の携帯だ」
「これ以外は持っていない」
男の狙いは明らかだ。男の左手に握られた奇妙な機械からもそれは分かる。
「最近はGPSって機能でぜんぶ分かっちゃうんだよ」
男はそう言いながら左手で機械のボタンを押して遊ぶ。
「あれ? 消えちゃったみたいだ」
「残念なお知らせだ」
「そうでもない。俺の仕事が終わったんだからラッキーさ」
男はそう言いながら、にやりと笑って庵月のコーヒーを飲み干した。そして、唐突にテーブルに顔を伏せて倒れた。
「他人のコーヒーを飲んじゃ駄目だ」
庵月は一日の終わりに、コーヒーに睡眠薬を溶かして飲む。それでも、眠りは一向に訪れないのだが。自分は本当に眠りから見放されているのかもしれない、と庵月は思う。
庵月は丸鼻男のこめかみに指を当てて尋ねる。
「月島アークホテルを荒らした組織の人間か?」
「知らない、俺の仕事はGPS探査だ」
「NASAみたいな奴だな」
「元NASAだ」
「エリートじゃないか」
「クソだ」
「お前を雇った奴の名前は?」
「ルーベンス」
「それは画家だ」
「ルーベンスだ。ボスが絵画マニアだ」
こめかみから手を離す。男に仮死状態が訪れる。
庵月は、男が飲み干してしまったコーヒーの中を覗き込む。
「今夜も眠れそうにないな」
そのとき、テーブルのうえで電話が鳴る。見知らぬ番号だ。
「もしもし」
女の声。聞き覚えがあるのかないのか、よく分からない。
「もしもし」
庵月が返事をしないでいると、再度女から呼び声がかかる。せっかちなタチらしい。
「眠れないの」
その声で、ようやく庵月は、電話の相手を特定することができた。
「アニマリック」
「正解!」
彼女はケタケタと楽しげに笑う。
「眠るのは得意と聞いていたが?」
「確かに得意よ。でも、今夜は私にとってちょっとモニュメンタルな夜だったの。だから、そう、特別なんだわね」
女はそう言いながら大きなあくびを一つした。
「目をつぶってじっとしているんだ。そうすると、すぐ眠くなる」
「もう一時間も試してるけど駄目みたい」
「二時間試してみるといい」
また笑い声。
「ねえ。寝かせてくれるの? くれないの?」
「三万五千円だ。払えるか?」
「三万五千円を払えない人なんかいるの?」
いる、と言いかけて庵月は黙る。
「悪いが今は時間がない」
「私にはあるわ。それより、あなたがなぜ寝かせ屋なんて職業を選んだのか、教えてもらえない?」
「悪いが、今は時間がない」
「しょーがないわね。でもいいわ、あなたにはまだ分からないのよね、自分がどんな竜巻のなかにいるのか」
「竜巻?」
「そう、トルネード。ヒデオ・ノモ」
「ねえ、悪いんだけど……」
「1995年、なぜ演奏ができなかったのか、ゆっくり考えてみて」
そこで電話は唐突に切れる。
1995年? 演奏? 庵月はしばらく切れた携帯電話の画面を眺めていた。だが、頭のなかにはまるでべつの世界が広がり始めていた。映像でも音でも匂いでもないもやもやとした何か。庵月の頭はいま、そいつに汚染されている。
目の前のテーブルでは、丸鼻男が規則的な寝息を立て続けている。
池袋サウスタワー
通常、人間は5階建のビルをタワーとは呼ばない。不動産の戦略が誤った形で表に出たケースだろう。「池袋サウスタワー」のエントランスでエレベータを待ちわびながら、ルーベンスはそう分析した。
ルーベンス。それは組織名であり、彼自身の通り名でもある。中世の画家とは無縁なアウトサイダーの生涯のタイトルには、いささか不釣合いだ。
頭部の北半球まで侵食した広大な額に汗が伝う。
となりにいる男は、さっきからエレベータの止まっている階を示すランプを見つめている。男は《庭師》と呼ばれている。左手につねに通販で手に入れたらしい伸縮高枝バサミを持っていることからルーベンスに命名された。ルーベンスは《庭師》の生い立ちを知らない。
つい一年前、仕事を求めてルーベンスの前に姿を現す前まで何をしていたのか、ルーベンスは一切尋ねなかった。通常であれば、ルーベンスは人を一人雇う場合、その人間の背景を顕微鏡レベルのミクロセンサーではっきりさせることにしていた。闇の世界であればあるほど、素性ははっきりさせる必要がある。だが、こと《庭師》に関しては、そのセンサーは働かなかった。それは信頼などと呼べるものではなかった。むしろルーベンスは、下手をするといつか《庭師》は自分をそのハサミで殺すかもしれないとさえ考えていた。頂点まで上り詰めて時間が経つほど、死への緊張感は弛緩してゆく。いわば《庭師》の登場は、そんなルーベンスの神経を刺激し、痙攣させる毒薬だった。ルーベンスは、半ば必然的に《庭師》を雇用することになった。その大きく虚ろな眼差しは、見つめられた人間を、無力な宇宙の塵に変えてしまう。まるでピーテル・クラ―の絵画みたいだ、とルーベンスは思う。闇の社会のなかに、ぽっかりと口を開けたブラックホール。不毛な存在たちの最大の墓標として、《庭師》はふさわしい存在感を放っていた。
「開く」
「ああ、そうだな。ドアが開く」
「乗る」
「ああ、そうさ、我々はコイツに乗るんだ」
「開く」
「そうそう、五階に着いたらドアがまた開く」
「降りる」
「そうだ、我々はそこで降りる」
「歩く」
「そうこなくっちゃな。歩いてドアの前まで行こう」
「開く」
「そう、たどり着いたらこの鍵でなかに入ろう」
《庭師》はそこで左手の伸縮高枝ばさみを持ち上げて見せる。
「そうそう、それだ」
「一人で行く」
「いや、我々で行く。やる前に尋ねておきたいことがあるからな」
《庭師》は不吉な沈黙を保った。それが《了解》を意味するのか、《不服》を意味するのかは、判然としない。あるいは、そのどれでもないのかもしれない。《庭師》の沈黙は、いつでもそのような人間らしい意味を越えている。
《庭師》からは雪国の匂いがする、と以前からルーベンスは思っていた。この男は雪の降る地方で、あまり裕福ではない家庭で育ったのではないか。そして、親や兄弟をどこかで殺している。ルーベンスには、肉親を殺したことのある人間の匂いが分かる。ルーベンスは、半ばゾクゾクする思いで、《庭師》に対して「我々」という言葉をよく使う。我々はファミリーなのだ、そう、お前がいつか殺したのと同じ、ファミリー、そしてお前にとって何の価値ももたないファミリーだ。ルーベンスにとって、《庭師》に「我々」と呼びかけるときほど、スリリングな興奮を味わえる瞬間は、この数年なかった。
エレベータが到着した。
「乗る」
「そう、我々はコイツに乗る」
砂漠を歩いていたところ、突如噴出した湧き水に溺れて、セイワエイタロウは夢から目覚めた。ひどく気分が悪かった。何より、後頭部がじくじくと痛んだ。
「目覚めたかい、掃除屋さん」
セイワエイタロウの目の前では、目と目の間の皮膚を洗濯バサミでつまんだような、いびつな形相の男がニタニタと笑っていた。無限大に広がった額にはアメリカ合衆国のような巨大なシミがある。
「ル、ルーベンスの旦那」
「そう、ソイツがオレの名前だ。そしてアンタはセイワクリーナーのセイワエイタロウだ」
セイワエイタロウは、かつてこんなにも至近距離でこの男と接したことがなかった。遠くで見るよりも、ルーベンスの顔には幾重もの皺が幾何学模様に走っていた。だが、それより気になるのは、ルーベンスの背後にいるもう一人の影だった。
セイワエイタロウの壁にある写真や雑貨を虚ろな眼差しで見ている。特に大きいわけでもないし、強そうにも見えないのに、なぜか危機感に煽られ、セイワエイタロウは落ち着かない気持ちになった。
──大体、オレはなぜここにいるんだ?
「いいかね? 我々が知りたいのは、なんでアンタが、まだここにいるのかってことだ」
それが分からなくて困ってるんだ、とセイワエイタロウは思う。「分かりません。ただ、分かるのは……」
分かるのは、後頭部の疼きだ。セイワエイタロウは、背後に手を当て、そこが妙にぬるぬるしているのを感じた。そして激痛。
恐る恐る当てた手を目の前に持ってくる。手のひらにはべったりと血が付着している。セイワエイタロウは記憶を探る。思い出せる部分もあれば、思い出せない部分もある。
「あの女……」
セイワエイタロウには三人の女がいた。一人は娼婦で、一人は週に一度ペットになりたがる人妻、それと、「清掃」の助手だ。だが、この助手はフェラチオも「清掃」も一向に上手にはならなかった。セイワエイタロウとしては、あとは彼女を「監禁部屋」に入れて弄ぶ以外に使い道が見出せなかった。セイワエイタロウは、女に隠し事をしない性格なので、この事実を正直に女に伝えた。女はその話を黙って聞いていた。
「そんなわけだから、明日から『監禁部屋』がお前の家になる」
セイワエイタロウは、俯く女の姿を、受諾と解釈した。女というのはいつでもこういう風に男の言いなりになっていればいいのだ。セイワエイタロウの父親も祖父もそうしてきたように、セイワエイタロウは女に対してこういった接し方以外知らなかった。
そこへ電話がかかった。ルーベンスからの電話だった。緊急の仕事で、見積もりはあとで出せということだった。「見積もりはあと」というとき、大抵それは死体の数が一体や二体ではないことを意味していた。セイワエイタロウは舌なめずりをした。そのお金が入ったら、娼婦の女としばらくハワイにでも遊びに行くのもいいかもしれない。
セイワエイタロウは、急を要する仕事ということで、念のため助手の女にも声をかけた。
「グズグズするなよ。ただでさえ愚図なんだ。愚図がグズグズしたりしたらだなぁ……」
そこで記憶が途切れている。
セイワエイタロウは女に背を向けて着替えをする最中だった。
「女です。女に頭を殴打されて……」
「アンタ、女に殴打されると、我々との仕事の約束も忘れちまうってわけかい?」
「いや、そうじゃないです……旦那」
「冗談だ。気を失ったんじゃしょうがないよな」
ルーベンスはそう言って、セイワエイタロウの肩をポンと叩いた。
そのとき、ルーベンスの肩越しに何かが光った。
だが、その光ったものの正体をセイワエイタロウは捉えることができなかった。セイワエイタロウの視線よりも早く、その光はセイワエイタロウの首を捉えた。
鮮血。
「おいおい、オレの顔が真っ赤になったぞ、掃除屋さん」
だが、セイワエイタロウはそれを聞いていなかった。彼の首は床をごろごろと回転してベッドの下に入り込んで見えなくなった。
ルーベンスは首なしのセイワエイタロウに話しかけた。
「掃除屋が部屋を汚しちゃ駄目だ。自分の首も分からなくなっちゃうよ」
《庭師》は長く伸ばした伸縮高枝ばさみを元のサイズに戻すと、ハサミの部分を布で丁寧に拭い、それからうっすらとオイルを塗った。
「母親の写真が一枚。豚の置物がひとつ」
「女がいたはずだ。一度だけ見たことがある。眼鏡をかけたオドオドした女だ」
問題は、とルーベンスは思った。問題は、その女が、どういう経緯で電話をかけてきた男とつながったか、だ。そして二人はいまどこにいるのか。
ルーベンスはすでに携帯電話の位置をGPS探査でダンゴに調べさせていた。だが、一時間経つというのに、まだダンゴから連絡はない。
「さて、お次は月島アークホテルの現状を把握しなきゃならん」
だが、《庭師》はまだ写真を見ていた。
「こんなものをなぜ部屋に飾る?」
ルーベンスは改めて《庭師》の横顔を見た。《庭師》は奇妙な昆虫を見つけたような顔で写真を見続けていた。
「壁に穴でも空いていたんだろう」
ルーベンスはそう言って、首なしセイワエイタロウの肩を小突いた。「なあ、そうだろ?」
首なしセイワエイタロウは、ぐにゃりと床に転がった。
ステーション豊洲
匂いは地下鉄まで続いていた、とウォンは言った。あの時間にはもう上り電車が終わっていたことから考えると、女は下りの電車に乗ったと考えるのが妥当だ。だが、有楽町線の下りの停車駅は、月島から先もまだけっこうある。一駅一駅を嗅いで回るわけにもいかない。
「ウォン、お前の推論によれば、ホテルのロビーに漂っていた香水の女が、リンゴを持ってるってわけだ」
「恐らく」
ウォンは、パンツにそれ以上追及されるのを避けるように窓の外を眺めた。窓の外にはネオンが蠢いている。
二人は豊洲駅に向ってレクサスを走らせている。道路は深夜のため非常に空いている。
「お前、あの中国人の女のことを考えてるのか?」
ウォンは答えなかった。
「本当は人違いだとは思ってない。そうだろ?」
パンツは合点がいったというふうに笑い、そうかそうかと言った。
「中国人ってのは意外と感傷的な生き物なのか?」
ウォンは窓を開けた。ごおおおおと風が鳴いている。
縄跳びを教えてくれた少女。寺院の庭で二人で遊んだ記憶。ウォンの脳内に広がるのは懐かしい雲南の景色だ。少女と何を話したかは具体的には何も思い出せない。だが、それでもウォンは折に触れ少女と何度か一緒に遊んだ。そして、少女が年頃の女になってからは、道ですれ違うと、時折女を目で追った。それだけだ。深い関係があったわけではない。だが、今日二人は決定的な絆で結ばれた。ウォンは彼女を殺してしまったのだ。
十七歳になるかならないかの頃から彼女を見かけなくなった。どこか中国の別の省にでも移ったのだと思っていた。だが、彼女はここ東京にいた。それも、恐らくは娼婦をやっていたのだ。
ウォンは自分のてのひらから飛び立ったはずの蝶を、最後には自分の手で握りつぶしたのだ。パンツは感傷的と言ったが、恐らくパンツには俺の感傷の本質は理解できていないだろうとウォンは思った。ウォンはこの世のものとは思えない幸福に打ち震えていた。
まさか、自分が彼女の一生にとどめを刺すことになるとは。そんな幸運が自分に訪れるとは。ウォンは物心ついた頃から、彼女の首筋にナイフを突き立ててみたかった。そして恐怖におののく彼女の顔を自分だけの宝にしたいとさえ思っていた。だが、その頃のウォンにはそうするだけの度胸がなかった。ウォンは結局のところリボルバーを手にすることで初めて冷酷を手に入れた。
そのとき、二人の席の間に置かれた携帯電話が鳴る。パンツの携帯電話だ。パンツが片手で運転をしながら電話に手を伸ばす。
「もしもし」
相手はルーベンスだろう。こんな時間に連絡をとってくるのはルーベンス以外には考えられない。
「……リンゴを探すためには仕方なかった」
パンツは静かな口調でそう答えたが、そこには怒りが見え隠れしていた。
「多すぎる? 何が? 地球の人口に比べれば屁でもない」
長い沈黙。
「は? あんた何言ってるんだ?」
短い沈黙。
「ふざけるな! あれが一番手っ取り早いんだ!」
長い沈黙。
「処理できないって……あんた、掃除屋呼んだんだろうが? 来てたぜ?」
何か問題が起きたのだ。ウォンはとなりで事態をしばし見守る。外気音がうるさいので、再び窓を閉める。
「来てない? 死んだ?」
沈黙。
「それが俺たちとどういう関係があるんだ?」
フィニッシュ。
「クソ! 切りやがった!」
パンツは道の脇に車を寄せて急停車した。何度もハンドルにスキンヘッドをガンガンぶつけ、そのたびにクラクションが鳴り響く。
ウォンはスーツのポケットからマルボロを取り出し、口にくわえて火をつけると、再び窓を開けた。
「俺たちを、消す気らしい」
ウォンはその言葉を黙って聞いていた。まだウォンの胸のうちは幸福感でいっぱいだった。
「消せないさ。俺たちを消すのは無理だ」
パンツは再びハンドルに頭を打ちつけ始めた。
「ルーベンスは俺たちを警察に売った。だが、恐らく警察に捕まる前に俺たちを消すだろう」
ウォンはふっと笑った。
「だからさ、消せないって」
パンツはウォンの顔を見た。
「当たり前だ。だが、今日の稼ぎがパーになったのが許せない」
「それもまだ分からない」
ウォンは幸運のリボルバーを、煙草を持っていないほうの手でさすった。長い夜になりそうだった。
「あそこに見えるのは豊洲駅か?」
そうだ、とパンツは答えた。ウォンは助手席から降りると、豊洲駅に向って歩き始めた。そして豊洲駅入口に立ってしばらくじっとしていた。それから戻ってきた。
「間違いない。女はここで降りた」
「おい、まだ女を追う気じゃないだろうな? 俺たちはルーベンスに……」
「仕事は仕事だ。金もきちんともらう」
パンツは笑い出した。
ウォンは窓の外に顔を出したまま。
「この道を左に曲がってくれ」
レクサスが静か過ぎるエンジン音とともに再び動き始める。
それから、パンツは矯正金具に指を当てながらつぶやいた。
「すると、あの掃除屋は何者なんだ?」
二人がほぼ同時に思い描いたのは、無駄に体格が大きい男の顔だった。眠たげな顔をして、頓珍漢なことを言う不気味な男。だが、もはやそれを確認する手立ては二人にはなかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
