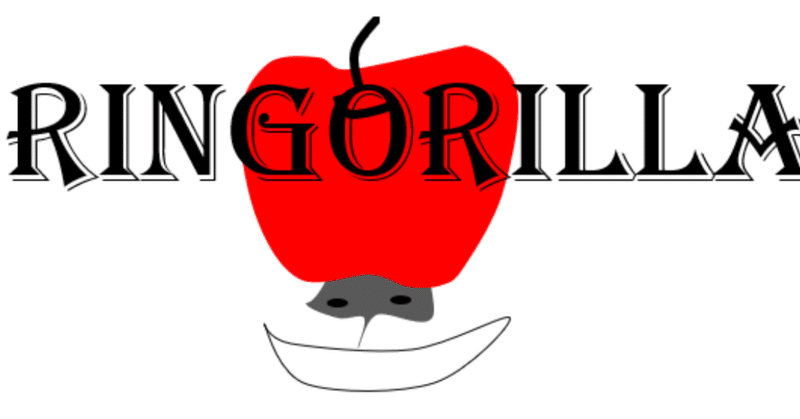
リンゴリラ #4
オン・ザ・隅田リバー
ルーベンスは夢を見ていた。犬を抱く夢だ。ルーベンスはその犬を撫でて可愛がりながら、首をへし折った。ルーベンスははらはらと夢の中で泣いていた。
目覚めた。
頭のなかにこびりつく会話。ルーベンスが目覚めたのはタクシーの中だった。
「おい、どこに向かってる?」
ルーベンスは運転席の男に銃を突きつけた。
「ひ、ひぃ……上野動物園です」
ひどい渋滞だった。何者かが自分に奇妙なことをしたのだ、とルーベンスは思った。だが、自分は《庭師》と一緒にいた。《庭師》の目を掻い潜ってルーベンスを拉致することなどできるだろうか? そして一体どんな方法で?
思い出そうとすると、わけの分からない光景が浮かぶ。背後にいたはずの《庭師》が目の前に瞬間移動したような錯覚。あれは…。
何はともあれ、恐らくこの渋滞のおかげで自分は救われたのだろう。ルーベンスはそう考えた。それからゆっくりと月島アークホテルで起こった出来事を思い出そうとした。ルーベンスと《庭師》は月島アークホテルに入り、死体を確認した。そこまでは覚えている。だが、そこから先が不明だ。
──そうだ、《庭師》が一つ下のフロアへ死体を確認しに行ったときだ。
そこから記憶が途切れている。だが、自分が朦朧とした状態で誰かと話したという漠然とした感覚はある。そして断片的な会話も。
──お前にはがっかりだ。
──は? あんた何言ってるんだ?
──余計なことをしてくれたな。
──ふざけるな! あれが一番手っ取り早いんだ!
──死体が多すぎて処理しきれないから警察を呼んだよ。
──処理できないって……あんた、掃除屋呼んだんだろうが? 来てたぜ?
──掃除屋は死んだ。
これは何だ? 自分で話しているのか? そして話している相手は、これは……。
「パンツ……」
自分はパンツに最後通告を突きつけたのだ。自分の口で。
「車を停めろ」
「いま端に車を……」
ルーベンスは一万円札を渡すと、その場で車から降りた。
何者か、得体の知れない奴が入り込んでいる。恐らくその男は、掃除屋の代わりにホテルに現れ、電話をかけてきた男だ。
一体、何者だ?
ルーベンスは携帯電話をかける。まずは《庭師》に。だが、《庭師》は電話に出ない。ルーベンスは舌打ちをしながら、今度はパンツに電話をかける。誤解が解けるだろうか? パンツはオレに裏切られたと思っているだろう。何しろ、俺自身がそう言ったわけだからな。
……と、電話がつながった。
「……これが、これが十五年もあんたに尽くしてきた者への仕打ちか」
悲しみすぎだ、とルーベンスは考える。たしかにさっきの自分がかけただろう電話はショッキングな電話だった。だが、ここまで打ちひしがれるほどパンツは弱い男だっただろうか?
ルーベンスは頭の中で、スキンヘッドにする前のパンツを思い返す。夏にはパンツ姿で借金取りに出向き、殺しの仕事も飄々と行う。その青年を「パンツ」と名づけ、可愛がったのは、その青き冷酷さのなかに若い頃の自分を見るような気がしたからだ。度重なる修羅場のために歯並びがぐじゃぐじゃになっていたパンツに矯正させたのは、掛け値なしの自己愛だった。
「パンツ、いいか、オレはお前を誇りに思っている」
電話は、すでに切れていた。パンツはルーベンスを殺そうとするだろう。パンツには自分が殺せるだろうか? 分からない。やってみればいい。何でもチャレンジだ、坊主。何しろ、お前はオレなんだ。
拾い直したタクシーが勝どき橋の上までやってきたとき、もう一件の電話を思い出す。
「カエル……」
そうだ、オレはカエルにも電話をかけた。つまり、本当にパンツとウォンの二人を売り飛ばして、この事件に幕を引こうとしていたわけだ。なんてこった。
ルーベンスは広い額をかきかき、小暮に電話をかける。小暮は甲高い声でどーもーと出る。
「旦那、いま豊洲に向かってますよ」
「豊洲? 豊洲に何がある?」
「とぼけないでくださいよ、二人の殺し屋です、第二豊洲アパートメントってとこに隠れてるみたいなんですよ」
「ほほう」
「ほほうって、何言ってるんですか、ちゃっかり先に刺客を送り込んでたくせに」
カエルの下卑た笑いが左耳にまとわりつく。
「現地で会おう、カエルくん」
「え? 旦那も豊洲に来るので?」
「不都合でもあるのかい」
いや、不都合ってほどのことは何も…ともごもご言う。ルーベンスは構わず電話を切る、
「ヘイ、ミスター。行き先変更だ。第二豊洲アパートメントまで頼もう」
だが、運転手は案の定それでは納得しない。
「お客さん、アパートの名前を言われても分かんないですよ」
「たぶんパトカーがいるはずだ」
運転手は黙る。パトカーが目印として有効かどうか考えているのだろう。あるいは、自分が「ミスター」の名に値するのかどうかを考えているのかもしれない。
「仕事ってのは何はともあれ、やり遂げることに一番の価値があると父は言っていました」
「いいダディだ。そう、オレも百五十パーセント同じ考えだよ、ミスター」
「やってみましょう、混沌とした世界のなかで、これくらい単純なルールもないわけで」
「そう、あんたはあんたの仕事をまっとうする。いたって簡単なルールだ。このカオスに満ちた世界においてね」
世界はカオスに満ちている。一時間前までつながれていたはずのビーズがバラバラになった。
まるでボッシュの絵画みたいじゃないか。
ルーベンスは思った。これはオレがリンゴを求めたことと関係があるのだろうか? オレがリンゴを求めなければ、すべては今までどおりだったのか?
刺客とは何だ? それはオレを眠らせた奴なのか?
ルーベンスは、ゲームをリセットする必要性を強く感じていた。戦争と呼べる規模の大量の血が流れるかもしれない、それでも、いったんリセットしなくてはなるまい。
「ヘイ、ミスター。これ、何て曲だい」
「何でしたっけね。とにかく外人のトランペッターの曲ってことだけは確かです。お客さん、知ってました? この隅田川にいる魚はみんな雑食だって噂です。とくに江戸時代に大量の土佐衛門が流されたんで、人肉が好みだって話ですよ」
「それは面白い話だ」
「昔はね、隅田川の向こう側は死の世界が広がっていたわけです」
タクシーの運転手には二種類いる。しゃべる運転手としゃべらない運転手。ほかに選べないなら、特に文句は言うまい。
「つまり、お客さんは死の世界へ渡ってるんです」
「らしいね」
ルーベンスは、ひどく愉快な気分になってきた。
第二豊洲アパートメント
第二豊洲アパートメントは、女が住むにはずいぶん質素なアパートに見えた。アパートというよりも、特大サイズのトランクルームといったほうが近い感じの、愛想のない建物だ。
「ここで間違いないのか?」
「中国製の優れた鼻を信じるならな」
パンツは、中国製の優れた鼻を信じることにした。
ウォンは、一階から順に丁寧に匂いを嗅ぎ分けていった。
「一階じゃない」
二人は二階の階段を上った、その間にパンツは銃を左手にもち、右手で銃弾を詰め込んだ。パンツは、なぜかふと初めてこの仕事に就いたときのことを思い出す。ルーベンスに拾われ、十代のガキには手に余るほどの小遣いをもらって引き受けた仕事だ。決して気持ちのいい仕事ではなかった。女を殺す仕事。それも、人工呼吸器をつけた植物状態の中年女性を殺す仕事だった。
パンツは、非常口のランプで緑色に光る病院の白い階段を駆け上がり、人工呼吸器を取り外した。あのとき、植物状態で口も聞けないはずの女が、突然カッと目を見開き、思いがけずパンツを抱き寄せた。
パンツは、怖くなって叫び声を上げた。その声で、看護婦が走ってくる音が廊下に響いた。パンツは夢中になって女を自分から引き離し、ドアから入ってくる看護婦を突き倒して逃げた。
なぜ今頃になってこんな光景を思い出すのか? 恐らく、ルーベンスとの関係性が再び不確かになったせいだろう。あのとき、パンツは、自分がしくじったことをルーベンスに言えなかった。もし言えば、殺されるかもしれないと考えると恐ろしかった。だが、次の日も、その次の日も、新聞に事件が掲載されることはなかった。
三日後ルーベンスからの電話がきて、ようやくパンツは女が無事に死んだらしいことを知ったのだった。あの何日間かの緊張は、その後のいかなる殺しでも味わうことはなかった。
ルーベンスと自分との間に生まれた一種奇妙な絆は、その後十五年にわたって育まれてきた──はずだった。
パンツは頭からすべてを追い出した。二階の201号室から順にドアノブを壊していく。パンツが破壊し、ウォンが入る。
201号室の住民は、友人と電話中だった。明かりのついた狭い部屋に特大のベッドを設置し、そこに腰掛けていた。片手にはビールが握られ、トランクスにYシャツという奇妙な格好をしていた。恐らくいま仕事から帰ってきたところだったのだ。スーツを脱ぎ、恋人か学生時代の親友にでも電話をかけ、あとはつまらないテレビ番組をつけっぱなしにして朝まで眠るつもりでいたのだろう。まさかその脳天に直径25ミリの弾丸が入り込むなんて思いもしない。
──もしもし? おい、聴いてるのか? もしもし?
202号室へ移動。今度はカップルだった。別れ話か身の上話をしていたのか、ジャージ姿の男は赤ら顔をぐしょぐしょにして泣いており、女だけが素っ裸でそれに寄り添っていた。最初に女の脳みそが白い壁に飛び、そのうえに男の脳みそが重なった。
203号室は一人だった。四十代はじめのカメラマンらしい男が、室内を真っ赤な電球で照らしてフィルムを現像している最中だった。ドアが開かれたせいで写真は台無しになったかもしれない。だが、部屋が赤いせいで血は赤く見えなかった。男は現像液の中に顔を突っ伏して倒れた。
204号室には誰もいなかった。灯りは点いていたが、誰もいなかった。ソファベッドが置かれただけの生活感のない室内。
この部屋だ、とウォンが手で合図を送った。二人は靴のまま上がりこむ。室内は眺め回す余地のないほど狭い。二人は同時にユニットバスのドアを注視する。シャワーの音。ウォンはシャワールームに当たるはずの白い壁のあたりに五発撃ち込む。パンツはドアを開け、シャワールームに入り込む。だが、そこには誰もいない。代わりに、洗面台の鏡の前に置かれた携帯電話が突然鳴り始める。着信音はどこかで聴いたことのあるジャズだ。このメロディはたしか……。
パンツはこのメロディを知っていた。ウォンが携帯電話を手に取る。着信表示画面には「公衆電話」とある。ウォンから奪ってパンツが通話ボタンを押し、耳に当てる。
「おめでとう。ゆっくり休んでね」
女の声はそれだけ言って切れる。電話を切ったパンツの額に汗がにじむ。ウォンと目が合う。ウォンはパンツの目から何かを察知しようとする。
轟音。
体の皮膚を一気にはがされるような激痛。
体が吹き飛ぶ。
壁に強く打ち付けられ、倒れる。
降り注ぐ破片。埃。
ウォンはどこだ?
パンツはよろめく体をどうにか立たせ、ウォンを探す。ウォンは玄関のあたりに倒れている。パンツと同じようによろよろと立ち上がる。顔が腫れ上がっている。お互い、もう元の顔には戻れまい。爆心地から近すぎたのだ。
ウォンの後方でドアが静かに開く。ウォンの首から上が放物線を描いて飛んできたのは、それと殆ど同時だ。パンツは醜く腫れ上がって皮膚のめくれたウォンをキャッチする。
首のないウォンの胴体が、どーっと倒れる。
その背後に立っている男の影に、パンツは銃口を向ける。
「お前は……」
この男がなぜここにいるのだ? この男は……。
「爛れた皮膚の男、二メートル前方、相棒の首を抱えている」
男はパンツの言葉など聞こえていないようにぼそぼそとした声で何事かつぶやいている。
「答えろ!」
「裁断」
男の左手が動く。パンツは動物的勘に頼って左に飛んだ。その拍子に、ウォンの首が床にコロコロと転がり、パンツを見返す。
男の長く伸びた棒は壁に突き刺さったまま。ハサミ型になっているらしい先端部が壁に深く刺さり、抜けなくなったのだ。パンツはその一瞬をついて男を撃つ。男は素早く前方に転がって移動し、壁に刺さったハサミを抜き取る。その後姿にパンツはもう一発撃ちこむ。当たった。恐らくは脇腹あたりに。
だが、男は一瞬動きを止めただけですぐに動き出す。棒は伸縮自在らしい。一瞬縮まったかと思うと、パンツの鼻先でハサミの刃が閉じる。そして再び……。
パンツは背後を手探りで確認する。出窓。すでにほとんど砕けている窓ガラスを突き破り、窓から駐輪場の屋根に仰向けで落下した。突き出たネジが背骨と接触した。皹くらいは入ったかもしれない。間髪を入れずにハサミが襲い掛かる。パンツは左に逃げる。だが、背骨の痛みのせいかわずかに逃げ遅れ、右の胸部にわずかに抉れた。パンツはうめき声を上げながら二階の窓へ向って銃を放つ。
だが──男の姿がない。玄関から回って降りてくる気か…。
すると、突然目の前にウォンが現れる。
「忘れ物だ」
声はウォンではない。後ろからだ。振り返ると同時に、その喉仏にハサミが突きつけられる。
「なぜだ…なぜこんなことを……」
「運がなかった。でも、コイツよりはあるかもしれない」
男はウォンの首をぶらぶらと左右に振る。そのたびにパンツの顔に血の雨が降る。
「そいつはこのハサミが決める。祈ってみろ、コイツより自分は強運だと」
この男は狂っているのだ、とパンツは思った。
「掃除屋が来なかったのはお前たちのせいじゃない。でもお前たちのせいかもしれない。オレのせいかもしれない。ルーベンスのせいかもしれない。あとは運のいい奴が残る」
激痛。
「う…ぁあああ!」
「それほど運は良くはなかった。でもコイツよりはいい。祈った甲斐があった」
パンツはなくなった左足を見つめてもがき続けた。男はパンツのもがれた左足を持ったまま立ち上がると、屋根から飛び降りて消えた。
左足を失ったパンツは、首から下すべてを失ったウォンを抱き抱え、這うようにして移動する。その最中に携帯電話が鳴る。着信画面に「ルーベンス」と表示されている。パンツは通話ボタンを押す。
「……これが、これが十五年もあんたに尽くしてきた者への仕打ちか」
ルーベンスは黙っている。なぜ電話をかけてきたんだ? オレを笑うためか? パンツにはこの電話の意味が分からない。パンツはルーベンスの返答を待たずに通話を切り、携帯電話を投げ捨てた。
それからパンツは、芋虫のようにゆっくりと這いながら、闇の中を進み始めた。左脇にしっかりとウォンの首を抱えながら。
第二豊洲アパートメント周辺
庵月が第二豊洲アパートメントの無愛想な外観を見ていた時間は数秒だった。不意に口に何かを充てがわれ、奇妙な匂いを嗅がされた。恐らく麻酔薬を塗布した布だったのだが、庵月は、十代の終わりごろから麻酔その他催眠に関する一切の薬剤に対する耐性が備わっていたため、臭いという以外には何も肉体的影響は認められなかった。
強力な腕が庵月の首にかかり、そのまま狭いところに押し込まれた。庵月はすぐに紙袋を頭にかぶせられ、こめかみに銃口を押し当てられた。
「チェックメイト」
Kの発音が強すぎる。英語圏の人間の発音ではない、と庵月は考える。
「チェスはやらない」
「この先もやることはないだろうね」
男は殺意を持っている。だが、その殺意は、殺意と呼ぶにはいささか理性がありすぎる。庵月は男の行動論理を考える。
「ジンジャエールはどこだ?」
あの電話の中国人だ、と庵月は理解する。そう、確か爪楊枝。
「どこだと思う?」
腹部への一撃。胃液が喉のほうに上がってくる。
「内臓が壊れると、臓器売買ができなくなるぞ」
男はその言葉を嘲う。
「お前の内臓に興味はない。いまお金になるのはもっぱら子供の臓器なんでね。なぜか分かるかい?」
「臓器移植法が改正された。だが、幼児の親はまだ子供の脳死を死だとは認めたがらない」
男がべつの男に話す。
「おい、コイツ馬鹿ではないらしいぞ」
「頭のよしあしが味に作用するといいんですがね」
「ソイツはこれから確かめればいい」
二人は笑う。
エンジン音。
ここは車の中らしい。
「お前はジンジャエールのボーイフレンドだ、そうだろう?」
「俺がボーイでフレンドならそうなる」
一撃。胃が破裂したかもしれない。激痛に身悶え、横に倒れようとする庵月の体を男が抑える。
「おい、走り出せ」
その一言で車が動き出す。エンジンの振動具合から察するにスタビリティの高い高級車だろう。BMWの軽さはなく、ベンツの硬質さもない。かといって日本車の安全第一という匂いが濃厚な安定性でもない。と、そこまでで庵月は車種推測は中断する。
「どうも読めない。あの大量の死体の山は何だ?」
「何者かがあのホテルの客を無差別に襲った。理由は知らない」
「そしてお前はわざわざ死んでいる女の携帯電話をいじって雇い主に知らせた。狙いは何だ?」
「困ってるだろうと思ったのさ」
視界が突如開けた。紙袋が外されたのだ。いい兆しではない。顔を見られても構わないということは、こちらの死を意味している。
役作りのために痩せたときのデニス・クエイドのような顔をした中国人が、庵月の顔を覗いている。右目と左目の焦点が合っていない。どちらかが義眼なのか、単に斜視なのか。暗闇では眼球の真贋までは見抜けない。
「庵月ユウジ。十代の終わりにトランペットで国際コンクールの銀賞を受賞している。現在の職業は寝かせ屋。業務内容はきわめて不鮮明。どうだ、よく調べただろう?」
「一つだけ間違ってる。国際コンクールの銀賞は受賞拒否している」
「どうでもいい」
「同感だ。どうでもいい。あんたの調べた個人情報はどうでもいいレベルのものだ。それで?」
「いま車を運転している男は何でもよく食べる」
確かに、運転席の男は、その肥えぶりから察するに、タイヤだってチェーンソーだってよく食べそうに見える。
「これから、お前はこの男の食事になる」
「なぜ?」
「なぜ? 用がないからだ。くわえて、たった今お前はジンジャエールを殺した」
「俺じゃない」
「いや、お前だ。お前はさっきまでずっとジンジャエールと一緒にいたはずだ。そして、何らかの事情で彼女を殺すことにしたわけだ。もしくは彼女が死んだと思わせようとしている」
「あんた、しゃべり過ぎてるぜ」
「これから死ぬ奴に何をしゃべっても構わない」
「俺の職業が何だか調べてるんだろう?」
「寝かせ屋だ。それがどうした?」
「人を寝かせるための方法は様々だ。マッサージ、睡眠薬の投与、経穴の刺激、それから……催眠法」
「催眠法?」
「あんたはしゃべり過ぎた。おかげで俺はもうあんたの無意識に入り込むことができる。あんたの無意識の世界はそれほど広いわけじゃない。でもちゃんと残されている」
「自分の置かれた立場が分かっていないらしい」
「俺の立場ははっきりしている。寝かせ屋だ。あんたの立場もはっきりしている。三秒後、あんたは眠りに落ちる」
三秒後の世界など庵月には想像できない。いつもそうだ。だから庵月は何も考えない。三秒後に消えるのはこの中国人の意識かもしれない。自分の命かもしれない。それは庵月にとって同じことである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
