
『ナトリウム オブ ラヴ』
梅雨に入ってから、妻の具合がよくない。
天気や気圧が不安定なせいか、いつもグッタリとして辛そうだ。悪いのは体調だけでなく気分も塞ぐようで、表情も暗い。
「炭酸水が飲みたい。そしたら気分もスッキリするかも」
なにか欲しいもの、食べたいものはないかと聞くと、妻はそう答えた。おれは早速コンビニでペットボトルの炭酸水を買ってきた。だが妻はそれを一口飲むなり、こう言った。
「ちょっと、ちがう。もっと天然の、すごい自然でさわやかな泡がシュワシュワしてるような」
そのリクエストに応えるため「炭酸水 天然」というキーワードに引っかかる、ありとあらゆる炭酸水をネット注文した。それくらいの労力と出費で妻が元気を取り戻してくれるのなら、お安いものだった。
「ちがう。こういうのじゃなくて」
ところが妻は取り寄せた炭酸水を一口飲むなり首を横に振る。そしてそれ以上飲もうとはしない。ネット通販ですぐに手に入る「天然もの」はすべて試してみたが、どれも彼女の求めているものとは違っているようだ。
「……ごめん。やっぱり身体辛いから、もう横になる」
すまなそうに謝って、妻は寝室に引っ込んでいく。
妻は最近では仕事も休みがちだ。じつのところ自分の調子もよくはない。本当なら夫婦そろって会社を休んで寝ていたい。しかしおれの方は仕事が立て込んでいてそうもいかない。
部屋の中は冷房を入れないと蒸し暑い。だが入れたら入れたで肌寒い。そうやって空調を管理しようとしてしきれないでいるうちに、湿気を吸った身体が重たくなっていく。なんとも気だるい気分だ。
今夜も窓の外で雨が降っている。シトシトとマンションのベランダと、その向こうの街を濡らしている。

妻が寝室に引っ込んでしまうと、リビングに残されたおれは一人、大量に余っている炭酸水でウィスキーを割り、ハイボールを作った。とくにうまくも不味くもなかったが、とりあえず飲み心地は悪くなく、まあ普通に酔える。アルコールが回れば気分もすこしはマシになった。
.。o○
「炭酸がわき出る泉がある」
「なんの話ですか?」
「天然ものが欲しいんだろう」
「あ、炭酸水か。そっちにもリクエストしてたんですね」
「そこは誰にも知られていない場所で、天然中の天然といえるような炭酸がコンコンとわいてる」
駅を出て会社に向かっている途中、妻の実家から電話が入った。緊急の事態かもしれないと焦って出てみると、相手は義父だった。義父は、いきなりその話をはじめた。
「飛行機か船に乗って行かなきゃならないけど、べつに外国でもないしな」
「その炭酸水、ネットとかで買えないんですか」
「自分で取りに行くんだよ。なにしろ天然もので、誰にも知られてないんだ。その辺で売ってるわけがない」
妻の実家はみんなどこか浮世離れしていたが、とくに義父は変わっていた。普段からこんな調子で、いきなり突拍子もない事を言い出す。この間の会食の席でも、何の脈絡もなく何故か日本各地に伝わる浦島伝説について語り始めた。妻の実家ではそんな義父にも慣れ切っているようで、とくに誰も反応しない。だから民俗学であるとか、そういった類の話に詳しいわけでもない自分がひたすら横で相槌を打つ羽目になる。
「ちょうど周期が来てる。だから娘のためにも、そして君自身の為にも、あそこで最高の天然ものを」
「……すいません、お義父さん。もうすぐ会社に着いちゃうので。その話は、また今度お願いします。一旦切りますね、すいません」
出勤時間にもギリギリだったので、おれは義父の返事を待たず一方的に通話を終わらせた。これからまた一日、意に沿わない業務に励まなくてはならないのだ。義父のことは決して嫌いではないのだが、月曜日の朝から現実離れした話に付き合う余裕はなかった。

それからすぐに会社に着いた。傘立てにビニール傘をグイと突っ込む。ズボンの裾が雨や跳ね返りで濡れている。通勤電車は今日も満員で、しかも生乾きの洗濯物の匂いが充満していた。朝からすっかり消耗して、どこか苛立ってもいた。あたりの様子を確認して、おれはカバンに入っていたウィスキーの小瓶を取り出し、一口飲んだ。琥珀色の原液が喉から腹の底を一瞬熱くした。もう七月に入っていたが、まだ梅雨は明けそうにない。
「ああ、いやな季節だ」
思わず口にしてしまったのが聞こえたのか、同僚の若い女が怪訝そうな表情でおれを見ていた。
.。o○ .。o○
さっきから会議を無駄に長引かせている、あの男が気に食わない。あの男というのは、おれより年下のくせに「コンテンツディレクター」などというよく分からない肩書で営業のおれなどより数段高い給料を取っているらしい、髪型や喋り方までとにかくすべてが気に食わない、いまおれの目の前で得意そうな顔でしゃべっている野郎の事だ。
「実のない横文字ばっか並べ立てやがって。とにかく気に食わねえ。このバカが。とりあえず黙りやがれ!」
気がつくと、おれは自分の考えを端的に表明しており、また表明しただけではなく直接行動に出ていた。つまり、おれは会議机の上に躍り上がり、呆気に取られているコンテンツディレクターの顔面に思い切り掌底を打ち込んだのだった。
「ぎゃッ! ……な、なにをッ!?」
掌底を受けた直後に漫画みたいな悲鳴を上げ後ろに仰け反った奴の無造作に流しているだけに見えるのだが実際は無造作に見えるように毎朝入念にセットしているであろう整髪料臭い髪を無造作に引っつかみ、おれはそのまま机の上から床に飛び降りる。
グシャッ!
前のめりに倒れた奴は、顔面を思い切り机に打ちつけた。丸メガネに顎ヒゲという、いかにもなクリエィティブ面がさぞや傷んだに違いない、たしかな手応えがあった。
「とにかく全部お前が悪い」
おれは本当に、心からそう思っていた。だから腹の底から勝手に笑いがこみ上げてくる。
「……あははははは!」
すくなくとも、ここ最近おれの調子が悪いことの原因の一つが、目の前でのたうち回っているこの男にあった事に違いはないのだ。
「なにがクリエィティビティだ、マーケティングだバカヤロー。ちょっと一発当てたくらいであからさまに調子づきやがって」
おれの口からは、おれの心にあった本音が勝手にこぼれ出た。それに続けて狂ったような笑いもこぼれ出る。
「こんなインチキみたいなもん、実際売ってやってるのは誰だと思ってやがる? ……おれだよ! あーバカらしい。バカらしくて逆に笑えるのがまた笑える。あっはっはっは! 毎日毎日、汗かいて必死になあ! 」
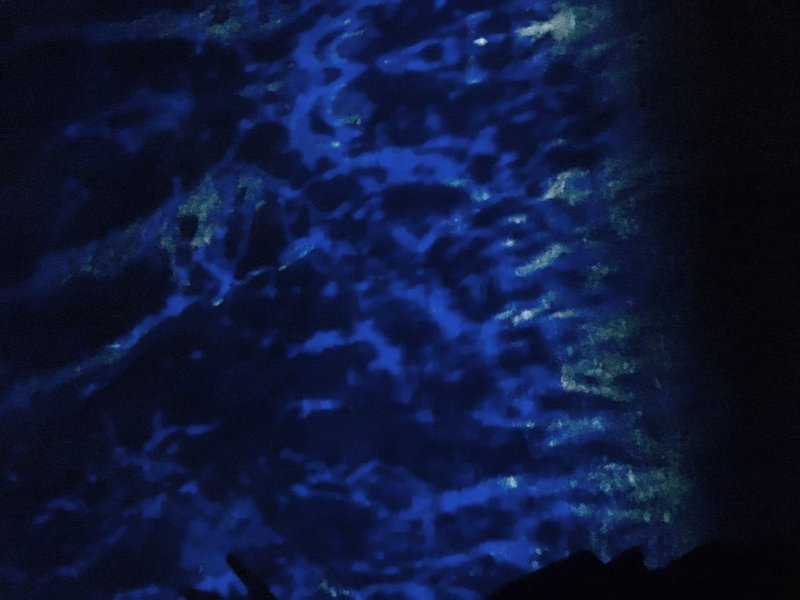
さっきの会議中、冷房が急に止まった。きっと故障したのだろう。しかし自分の他に誰もそれに気がつかない。温度と湿度は果てしなく上がっていき、蒸し暑く粘っこい空気がせまい会議室の中で淀んだ。ジワジワと肌が汗ばんでいく。肌着が背中にベットリ貼りついた。そうやっておれが味わっている不快感にまったく気がつかず、コンテンツディレクターは目の前でとうとうと能書きを垂れて止まない。その得意気な面と永遠に続きそうなこの時間と空間に我慢ならなくなった。
そこまでは何となくおぼえている。
「この歳になってキレちゃうとか! ……あははは! 太陽がまぶししかったから? いや部屋が蒸し暑かったから? おれって、すごい日本的なサイコ野郎?」
まだ笑いが止まらない。
なんて事をしてしまったんだ、おれは一体どうしたんだろう。そうやって月並みで不毛な後悔を始めようとする自分も実はいるのだが、同時にこれは当然の帰結なのだと納得して居直ってもいる。いままでの自分、そしてこれからの自分が、現在の自分から乖離していくような感覚。ここ最近、そんな違和感がずっと続いていた。だから単に切掛を求めていただけなのかもしれない。
「この野郎ォォォォ、死ねェェェェ!」
そこでようやく起き上がったコンテンツディレクターが懐から飛び出しナイフを取り出し、いきなり突進してきた。口と鼻からは血と涎と鼻水が入り混じったものを飛ばし、目もギラギラと血走っている。おれを本気で刺し殺すつもりらしい。やあ、こいつもキレたのか! まあ当然だ。あはは。笑える。
ガラガガラガッシャーン!
おれは軽く身をひねって、野郎の一撃をスルリと交わした。コンテンツディレクターはおれの足に蹴躓いて、会議室のホワイトボードに頭から突っ込んで派手な物音を立てた。それからピクリとも動かなくなった。その場はシーンと静まり返っている。会議室にいた他のメンバーは一連の騒動の間中ずっとフリーズして固まったまま最後まで誰も何も言わない。部屋の湿度は耐えられない程に上がっていた。とても日本的だった。
「それでは私はここで失礼いたします」
とにかく暑苦しい会議室を出て、そのまま早退することにした。さらにそのまま退職となる可能性も大きいだろう。とりあえずは手荷物だけ持って会社を出ることにする。タイムカードに打刻することは忘れない。有給はかなり残っているはずだ。

会社の外に出てから、傘を忘れたことに気がついた。雨は相変わらず振り続けていた。
雨のオフィス街を歩いていると、尻ポケットでスマホが振動した。着信を確認すると妻の実家からだ。どうせまた義父だろう。すこし迷ったが、おれは電話に出ることにした。
「もしもし……」
.。o○ .。o○ .。o○
「チケットはもう取ってあるから、自分の端末に落としたらいい」
電話の向こうで義父は言った。航空会社のアプリを確認してみると、自分のスマホに飛行機のチケットが発券されていた。
まったく便利な時代になったものだ。
さっき会社で騒ぎを起こしてから、わずか一時間余り。おれは搭乗手続きを手早く済ませ、飛行機に乗り込んでいる。ちょっとした高飛び気分だった。あまりにスマートな流れで、おれの現実感はさらに希薄になっていく。飛行機は滑走路からスムーズに離陸した。

「ご出張か何かで?」
「ええ、まあ」
ビジネスカジュアルなおれの格好を見て、乗務員がビジネス的な親切心で声をかけてくる。おれもビジネススマイルで応える。
飛行機で数時間、洋上に浮かぶ離島に向かっている。義父によれば、その島のどこかに天然の炭酸水がわき出る泉があるらしい。そこから炭酸水を持ち帰り、臥せっている妻に飲ませる。それが自分に与えられた目的だった。
「南の方にある島だから、もう梅雨は明けているのかな」
ふと気になって、乗務員にたずねてみる。
「はい。もう七月に入ってますし」
「それはいいですね。忌々しい梅雨も終わりだ。これで色々スッキリする」
「でも元々雨が多い亜熱帯の島で、現地の天気も雨のようで」
……なんだ、また雨か。
思わず意気消沈する。とはいえ飛行機はキーンとなんら問題なく運航、やがて滑空に入った。
○o。.
空港の玄関口を出ると出迎えの車が来ていた。どうやら義父の手配らしい。さすがに手が行き届いていると感心した。

「こんな離島のタクシーに最先端技術。ギャップがすごい。なんで?」
「ソレハ私ニハ分カリカネマス」
義父が寄越した出迎えは、完全無人タクシーだった。なんでも最新技術のAIが搭載されていて、自動運転機能だけでなく「お客様とのスマートで気の利いた会話も可能!」らしい。すくなくとも車内に貼られた広告にはそう書いてある。
「やっぱり嫌な客乗せると、気分悪かったりする?」
「ハイ。ソレモ分カリカネマス」
とにかく色々と分かりかねるらしかった。まずは目的地、そこまでの所要時間、あるいはこの島自体について、なにを聞いても返事は「分カリカネマス」だった。じゃあ一体何が分かるのか知りたい。しかしある意味でこのAIは誠実なのかもしれない。世の中や他人の事、下手すると自分自身のことだって、分かった気になっているだけで本当は何も分かっていない。おれ自身も含めて世の中にはそんな人間ばかり……なんてぼやく自分は、やっぱり疲れているのかもしれない。
「……まだ蒸し暑いな。もうちょっと冷房効かせてくれるかな」
「ハイ」
ようやく車内の温度が冷えて、快適になる。無人タクシーのAIは命じられた仕事はきっちりこなす。なかなか偉い。
「現在ノ島ノ天気ハ、曇リ時々ニワカ雨……」
「見た所その通りだね」
窓の外では霧のような雨が降ったり止んだりしていた。島は湿度も温度も高い。梅雨が明けたという感じはしない。まあこれが亜熱帯気候なのだろう。
車はさっきから起伏の激しい道路を走っている。他の車は走っておらず、歩いている人の姿もない。道路の両脇に生い茂る植物の緑が次第に色濃くなっていく。まるでジャングルのようだ。昼間だというのに辺りは薄暗い。
「設定サレタ地点ニ到着シマシタ」
島の中心部にある山の中腹辺りでタクシーが停まった。自然公園の駐車場のような所だった。どうやらここで舗装道路は終わっているらしい。
「ゴ利用アリガトウゴザイマシタ」
おれが降りるとドアが自動で閉まり、タクシーは走り去っていった。ちゃんと帰りも迎えに来てくれるのか不安だったが、聞いたところで答えは「ワカリカネマス」に決まっている。何も分からないおれは、辺りを歩いて回ることにした。
『南方富士 登山道コチラ』
古びた案内板があった。ここからは登山道になっているようだ。義父の言う泉は、この先にあるのだろうと思われた。他にそれらしいものは何も見当たらなかった。
意を決して、おれは山道に足を踏み入れた。
○o。.○o。.
登り始めて、すぐに後悔することになった。
山道は思った以上に険しく、自分の体力がすっかり落ちている事を思い知らされた。社会人になってから運動らしい運動はしてこなかった。そんな自分には十分過ぎるほどにハードな道のりが続いた。
それから大変に蒸し暑い。やはり亜熱帯なのだ。歩いていると湿った熱気が常に周囲にまとわりつく。汗がダラダラと流れ落ちる。その汗と霧のように細かい雨を吸ってYシャツはグッショリ濡れた。スラックスは太ももに張りつく。舗装されていない山道に革靴は歩きづらく、水が染み込んで濡れた靴下が蒸れて不快だ。
全身湿りきっている自分の身体が、いつもの何倍にも重たく感じた。

鬱蒼としてジャングルめいた植物で視界が悪い。地面は所々ぬかるんでいて足を取られる。すぐ近くで聞いたことのない不気味な鳥の声。かなり山深い所まで入ってきたようだ。
それでも登山道自体は分かりやすい一本道で、そこを外れなければ迷うようなこともないだろう。しかし逆にそれが自分には都合が悪いのかもしれない。自分の目的は、どこか人知れぬ場所にあるという、天然の炭酸がわき出る泉だ。人知れぬ場所にあるのだから、親切に案内板が出ていたりはしないだろう。このまま登り続けていれば、いずれ頂上に出てしまう。そこで「ヤッホー」などと叫んで達成感と共に下山する、それでは何にもならない。ここまで来た意味がない。
「天然の、炭酸……」
今朝も仕事を休んで、マンションの寝室にこもっているであろう妻の弱々しい声と表情が思い出された。
……天然の炭酸水。
まずは自分でそれを飲んでみたいものだ。ひどく喉が乾いていることに気がつく。登山だというのに、おれは飲み水も何も用意していなかった。体力的にも限界はそう遠くない。義父に電話をして詳しい場所を聞こうとしたが、電波がない。あてもなく道を外れれば遭難の可能性も考えられた。とりあえず立ち止まっていても仕方がないので、おれは登山道をまっすぐ登っていく。
次第に景色が開けてきた。

鬱陶しいくらいに生い茂っていたジャングルのような植物群が姿を消し、ゴツゴツとした岩場の地形が目立つようになった。
間もなくして頂上にたどり着く。
見渡してみると、山頂は見事なカルデラになっている。かつての噴火口の周りを、尾根がぐるりと一周している。こんな尾根を伝って火口を一周することをたしか「お鉢巡り」という。妻か義父、あるいはネットから仕入れた知識かもしれない。急にその言葉が頭に浮かんだ。

「……おや、あんたもお鉢巡りで?」
後ろから急に声をかけられた。驚いて振り向くと、そこに一人の男が立っていた。
「……いや、別にそういうわけでは」
「なら、何の用があってこんな場所に?」
その男は島に来てから初めて接するまともな人間だったが、よく見ればあまりまともでもない。会社を出て着の身着のままのおれも人のことを言えないが、目の前の男の恰好はさらにおかしなものだった。
「……なんだ、ずい分と遠慮なく人を視るじゃないか」
その男はタイトな黒のスーツ上下に先の尖った皮靴というスタイル。それから何のつもりなのか、頭から白いビニール袋をすっぽり被っていた。
○o。.○o。.○o。.
「へえ、あんたにはそう視えるのか。……クラゲには、やっぱり視えないよな?」
クラゲ? そんなものには見えない。まあ暗がりで目を思いっきり細めれば、そのビニール袋がクラゲのように見える……かもしれない。どちらにしても、おかしな事を言う男だと思った。
「なるほどな」
何故か納得したようにつぶやくと、男はスーツの胸ポケットからタバコとジッポを取り出し、ビニール袋の内側にガサゴソと手を入れた。……カチャッ、シュボッ。どうやらタバコを口にくわえて火を点けたらしい。それから大きく煙を吸って吐き出したようだ。頭部のビニール袋と肩の隙間から白い煙がもれ出て、ゆっくりと立ち上っていく。
ものすごく煙たそうだ。何のためにあんなものを頭に被っているのだろう。どう考えても邪魔だろう。
「これは一種の仕事着なのさ。制服みたいなもんだ。いまだって、一応は仕事中でな。……なあ、もしかすると、あんたも何か困り事じゃないか? なら言ってみろ。力になってやれるかもしれない」
そうだった。おれはお鉢巡りをしにきたわけではなく、天然の炭酸水がわく泉を探しにきたのだ。
「その泉なら、このカルデラのなかできっと見つかる」
おれは崖から身を乗り出して、切り立った尾根の内側を覗き込むように見下ろした。カルデラの底には、やはりジャングルのような植物が鬱蒼と生い茂っていた。なるほど、色濃い緑に覆われたどこかには秘密の泉が隠されていそうな気配があった。
「この火口のちょうど向かい側に、下まで降りていく道があるんだ。そこまで案内してやるよ」

意外にも親切らしいビニール袋の男に先導され、火口の周りを尾根伝いに歩く。頂上に出てから、雨はもう降らない。しかし風がつよい。打ちつけてくるような横風に、身体ごと持っていかれそうになる。
「吹き飛ばされないように気をつけろよ。ここから転がり落ちたら、さすがに死ぬ」
所々に生えている背の低い高山植物をつかみ、尾根にへばりつくようにして慎重に進んだ。ほとんど歩伏前進のような状態だ。
「そこはすべりやすい。気をつけろ」
親切なビニール袋のクラゲ男(手渡された名刺には『リュウグウノツカイ』と書いてあった)は、なんとも軽快な足取りでヒョコヒョコ歩いていく。細く頼りない身体がときおり突風にあおられて危なっかしいが、本人的にはまったく平気な様子だった。
「ほら、ここから下っていけばいい」
男が立ち止まって、その道を指し示す。
かなりの急な下りだが、たしかに一応は道になっている。へっぴり腰のおれでも、なんとか下まで降りられそうだ。
「あんた自分では気づいてないのかもしれないが、案外と厄介な所に踏み込んでるんだぜ。……引き返すなら、いまのうちかもな」
カルデラの底に降りていくおれを見送りながら、ビニール袋男は忠告めいた言葉を口にした。よく意味が分からなかったが、どちらにしろいまさら引き返すなんて選択肢はあり得ない。ようやくここまで来たのだ。
急な下り道を慎重に降りて、火口の底にたどり着く。そこから群生植物をかき分け、おれはさらに奥へと進んだ。その先に求めている泉があるのだと、確信に近いものを感じていた。
.。o○○o。.○o。.
果たして隠された泉は存在した。おれは見事そこにたどり着いたのだ。
この泉が特別な場所だということは一帯に漂っている雰囲気からも察せられる。あまりにも特別で、現実感のない景色だった。だからこそ余計に、そこが自分のためだけに用意された場所に思えてしまったのかもしれない。

携帯が鳴った。ついさっきまで電波がなかったはずだ。カルデラの底にきてそれが突然つながるというのもおかしな事だったが、自分はもうすっかりおかしな状況に全身はまり込んでいるのだ。さっき、あの男が別れ際に言った通りに。いまさら不自然なことは何もない。
「無事に着いたようだね。あとは水を汲んで帰って、娘に飲ませてやればいいんだが……」
電話をかけてきたのは、やはり義父だった。
「まずは自分で飲んでみるといい」
じつは、ずっとそうしたくてたまらなかった。おれは電話を放り出して、その場にかがみ込む。泉の水面に顔を近づけた。底が見えない、深く青い泉。水面に立ち上っている、微かな気泡。
両手でその水をすくい上げ、一口飲んでみる。
……うまい。なんてうまい炭酸水なのだろう。こんなもの、いままで飲んだことがない。
かすかに甘味を感じさせる水が、沁み込むように喉の奥へと消えていく。口中に残される、柔らかな刺激。なんとも絶妙な加減の炭酸だ。ひどく爽やかな快感が口中に、それから乾いていた全身の細胞へと広がっていく。
最初のひとすくいは一瞬で飲み干した。すぐにもうひとすくい。うまい。うますぎる。いくらでも、いつまでも飲み続けてしまう。なんなのだ、この炭酸水は……。
「君は酒を飲むのだろう。これで酒を割ったら、さぞやうまいだろうな」
地面に転がった携帯から義父の声が聞こえてくる。この炭酸水で割った酒……。たしかに素晴らしくうまいだろう。間違いない。おれはリビングで一人飲んでいたハイボールの安っぽい味を思い出す。梅雨に入ってふさぎ込む妻をながめながら、ずっと飲んでいた。アルコールと気鬱が入り混じり、おれの内と外を湿らせた。あれはあれで悪くはなかったが……。
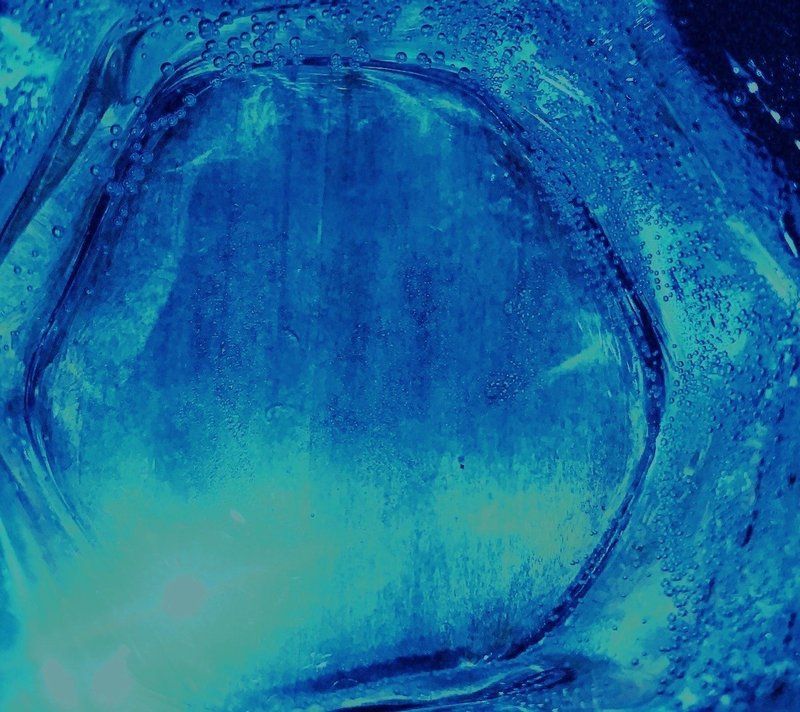
「アルコールでもなんでも飲みたいだけ飲めばいいのさ。そもそも人体の約八割は水で出来ているんだ」
いま聞こえているのは義父の声のようでいて、実際には違ったものかもしれない。しかしそんな事はどうでもいい。おれはとにかくこの炭酸水にみせられていた。もっと、いくらでも飲んでいたい。酒を割って飲みたい。この爽やかさにアルコールの酩酊が加われば、まさに至上の飲み物だ。カバンにはウィスキーのポケット瓶がまだ入っているはずだ。しかしカバン自体をここにくる途中でなくしてしまった。まったく惜しいことをした。至高にして究極のハイボールが味わえないとは。じつに悔しい。しかしなにはともあれ、とにかくもっとこの炭酸を味わっていたい。おれの乾きはまだまだ満たされない。
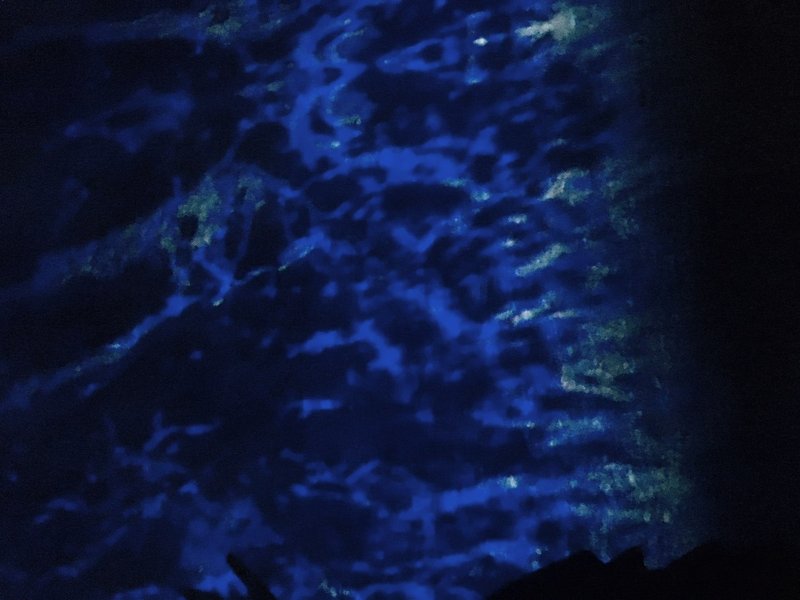
いつしか泉に頭を突っ込んで、水面に直接口をつけていたおれは、そのまま水中に落ちたらしい。飲み込まれたように沈んでいく自分の身体が、すべて濃い青色の世界に包まれている。おれの口からゴボゴボとこぼれる空気が、泉の炭酸の気泡と一緒に水面に立ち上っていく。水面からは、微かに光が差し込んでキラキラと泡が輝いていた。
「……存在とは頼りない泡のようだ。つかの間に弾けては消え、すべてが入り混じり、やがて解けていく」
義父の声らしいものが水中に響き渡っている。おれの身体の周りには細かい炭酸の泡がまとわりついてシュワシュワといっている。
「そもそも歴史的に最初の炭酸水というのは重曹にレモン果汁、つまりナトリウムにクエン酸を加えた化合物だと言われている」
そうなのか。そんなことは知らなかった。そういえばナトリウム化合物をソーダとかいったりしたような気もする。……でも、それが何だっていうのだ。義父の話はやはり突飛でよく分からない。
「一方こうして天然の炭酸水が地下からポコポコとわき出ている。こんな天然の炭酸水が、どうやって出来ているのか、ムコ殿に分かるかい?」
知らない。それは分かりかねます。義父の問いに答えようとするのだが、その言葉はゴボゴボと泡にしかならない。まあ大体おれの知っていることなど、ほんのわずか。たかが知れているのだ。ほとんど何も知らない。じつのところ子供と同じだ。ただいろんなことを分かった気になっていただけの。だからこうして溺れてもがいても結局はただ沈んでいくことしか出来ない。
「誰かがね、化合しているんだよ。どこかの水底で、ナトリウムだったり二酸化炭素だったり、呪いだったり祝福だったりする愛や夢や絶望を」
おれはもがくのをやめて、沈んでいくに身を任せるようにした。すると呼吸が楽になった。というより呼吸の必要を感じなくなったようだ。
やがて泉の底が見えてくる。
「……こうした泉には、必ずヌシがいるものでな」
水底に、誰かが寝そべっているのが見えた。
「天然の炭酸水をつくっているのは、ほら、あそこにいるヌシなんだ」
とうとう泉の底に足がつき、サラサラと白い砂の上をおれは歩いた。その泉のヌシにゆっくりと近づいていく。
「……ご苦労だったな」
ヌシはおれを見て、義父とまったく同じ声で話かけてきた。……いや、同じなのは声だけではない。いかにも田舎の親父然とした野良着に、ツルリと禿げ上がった頭。柔和なようでいて、こちらを見透かすような独特の目つき。つまり義父そのものだった。ただしサイズがかなり小さい。泉の底にいるヌシだという義父は、おれの手のひらに乗るくらいの大きさしかない。
「天然の炭酸水はな、我がこうしてナトリウム化合している」
小さい義父は、そう言って手に持っていたストローをくわえ、その先端から小さな泡を吹いて出した。その泡はさらに細かい気泡に分裂して、水面に向かって立ち上っていく。
「さあ我を連れて地上に。されば汝が妻の病も癒えるであろう」
義父だかヌシだか分からない存在が、おれに語りかけてくる。
「つまり、この天然の炭酸水がいつでも飲み放題ってことだ。ムコ殿が好きなハイボールも、それこそ溺れるくらいに飲める」
おれは泉のヌシあるいは小さい義父を片手につかむと、両足で水底を思い切り蹴った。
「さあ出発だ。外の世界は久しぶりだ」
とにかくこれで目的は達成される。あとは家に帰って妻に天然の炭酸水を飲ませ、そしておれも至高のハイボールを。
「とりあえずは風呂にでも水を張って我を沈めておけばいい。天然の炭酸水が出来るぞ。例えばその水を湯にして浸かれば、そこらの高濃度炭酸泉など比にならぬ位に血行もよくなり二度と病気にならない身体になり若返り効果も抜群で、さらに年収も上がって貯金もたまる」
よし、まずはハイボールだ。まさに浴びるほど、溺れるほど飲んでやろうじゃないか。この炭酸で割れば、どんな安酒だって、どんなバーでも飲めない至上の味に変わる。……それから極上炭酸水を生み出す無限のリソースについて、うまい利用方法をじっくりと考えるとしよう。
「そうだ、ムコ殿。その意気だ。我をうまく使えよ」
小さい義父がストローで泡を吹く合間に発破をかけてくる。こんな義父となら、これからもうまくやっていけるに違いない。
.。o○.。o○○o。.
「おーい。お前ちょっと」
水面に向かって泳ぎ上っていく途中で、呼び止められた。声のした方を見ると、青く薄暗い水中に白いクラゲのようなものがユラユラと揺れている
「悪いことは言わない。そいつは元の場所に置いていけ」
そいつというのは、このミニサイズの義父のことだろうか。おれはそのクラゲを無視することにした。どれだけ苦労してこれを手に入れたと思っているのだ。泉のヌシあるいはミニ義父は、素知らぬ顔でストローを吹いている。ストローの先端から泡が出て立ち上っていく。その泡を追いかけるように、おれは水面に向かってまた泳ぎ出す。
「だから待て。戻れ」
ユラユラと漂うように、しかしクラゲの泳ぐスピードは思いの外に早かった。すぐに進行方向をふさがれた。
「やれやれ。心配して来てみれば案の定」
目の前に浮かびふさがったクラゲの下から、人間の身体が生えていた。つまりビニール袋をかぶった細身のスーツ姿の男がそこにいた。さっきカルデラで出会った、あの男だった。
「……そこをどけ。おれは家に帰る」
「帰るのはいい。まだ間に合う。ただし、そいつは置いていけ」
「邪魔される筋合いはない」
「身に過ぎたモノを持っても、いい結果は生まない」
「なんだその説教は」
「お前のためを思って言ってる」
お節介なビニール袋野郎が、細い腕をのばして、おれの手から義父を奪おうとする。それに抗って、おれは野郎を思い切り蹴飛ばす、というか足で思い切り押し出すようにしてやった。頼りないクラゲのように軟弱な野郎は、それこそクラゲのようにユラユラと遠くへ漂い去っていった。
「よし。いまのうちだ」
「ああ、分かってる」
手の中で義父が急き立てる。おれは炭酸の細かい気泡と共に上を目指して一心に泳ぐ。もう水面が近い所まで来ている。

「ぶはっ」
ついに水面に顔を出した。ここにきて呼吸するということを思い出したように思い切り酸素を吸い込んだ。
泉の真ん中に顔だけだして浮かんでいる自分。首の周りには細かい気泡がくっついてシュワシュワいっている。手のなかには、その泡の元になる泉のヌシ、ミニサイズの義父。
これで目的は達成された。至上の天然炭酸水は永久におれのものだ。
「……よう。遅かったな」
聞き覚えのある男の声。「チッ」思わず舌打ちして視線を向けると、そこにはやはりクラゲ男の姿。泉の横にある岩に腰かけている。奴の顔面を覆うビニール袋のすき間からは、白い煙が立ち上っていた。
「待ちくたびれて一服してた所だ」
「……お前は、何なんだよ」
「だから、私はリュウグウノツカイ。つまり九頭竜のお嬢に雇われたエージェントで」
「違う、そんなことはどうでもいい。ここまで案内しておいて、なんで邪魔するのかってことを言いたい」
「まあ、これが私の仕事……みたいなものだからな」
にらみ合っていても埒が明かない。おれは陸に上がり、このクラゲ男と対峙した。
目の前の障壁を突破しなければ、おれの目的は果たされないようだ。立ちふさがるクラゲ野郎はやはりクラゲのように頼りなく脆弱な身体をしている。ここは腕力頼みで、問題なく押し通れるだろう。エージェントだか何だか知らないが、営業職をなめてもらっては困る。
「『お前は何なんだ』と、さっきお前は私に聞いた」
「……だからどうした。そんなこと、どうでも」
おれは義父を胸ポケットに押し込み、クラゲ男にジリジリと歩み寄った。何としても目的を達成する。そのためにはどんな手段もいとわない。この義父がいれば、おれの俗な願いの大半は叶ってしまうに違いない。
「その言葉を自分自身に、もう一度問いかけろ」
「はっ、何を言っていやがる」
おそらくは、このクラゲ野郎も義父を狙っていたのだ。なるほどそれで合点がいく。エージェントだの何だのと結局は利益の追求が目的だ。おれはおれが手に入れた利益の元を黙って渡すわけにはいかない。
「自分に見合った領分に留まれと言っているんだ。……まあ道を踏み外したくなる気持ちは、私にもよく分かるが」
「……お前に、なにが」
ザッパッーン!
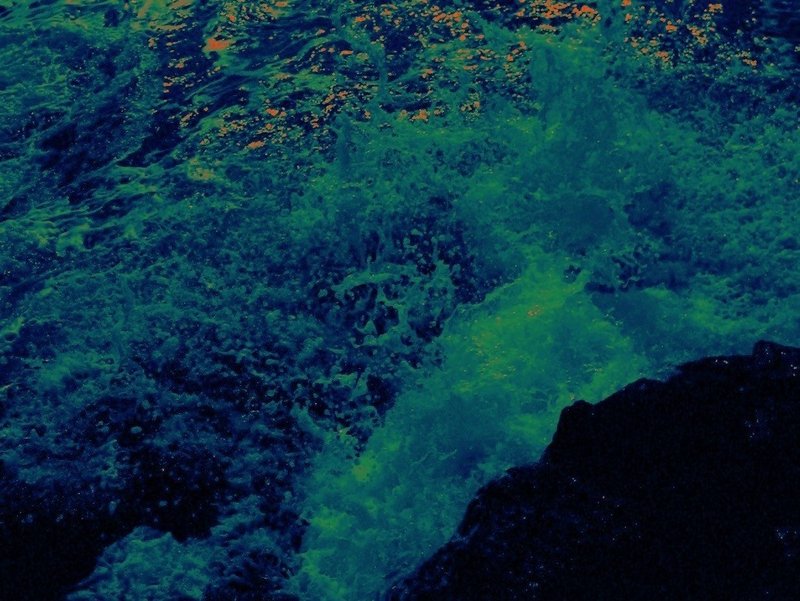
背後で大きな水音がして、あたりが広く影に覆われた。咄嗟に後ろを振り返ったおれは、信じられないものを目にした。瞬間的に慄いて、身体がまったく動かなくなった。
「……悪いな。さっき本部に連絡して手配したんだ」
この泉から飛び出した、超巨大なサメ。おれの身長の数倍はあるであろう、そいつが眼前まで迫っていた。
「とにかくお前は」
巨大なサメはすべてを飲み込んでしまいそうな位に大きな口を開けている。よく見ればサメには違いないだろうが、映画で有名な人食いザメとは違って、ずいぶんと間が抜けた顔をしている。
……これはたしか、メガマウスとかいうやつだ。年末に妻と一緒に観たドキュメンタリー番組に出てきた幻の大鮫、メガマウス。
そのメガマウスのあんぐりと開けたバカでかい口に、おれはすっぽり丸ごと飲み込まれた。その瞬間に視界と意識が急速フェードアウトしていく。ここでゲームオーバーらしいとおれは悟った。
「自分に本当に必要なことを思い出せ……」
そこでクラゲ野郎の声を聞いた。……ああ、そうだ。病気の妻がおれの帰りを待っているんだった。しかしもうこれで帰ることはできない。「すまない」と心で妻に詫びた。こんな自分をゆるして欲しい。おれは無知な愚か者で、すぐに溺れてしまう。何度生まれ変わっても繰り返す。それから老人の慄き声のようなもの、波の音、心音、胎動、小さい子供や犬の鳴き声……模糊とした暗闇のなか、おれの意識は微かに保たれて、それらの音をただじっと聞いていた。
.。o○.。o○.。o○
「お客様、もう間もなく着陸に入りますので」
次に気がついたときには飛行機に乗っていた。客室係に声をかけられ、おれは意識を取り戻した。
「あの、おれ、いや私は、どこで何をして、どんな存在……なんでしたっけ?」
「……スイマセン、私ニハ分カリカネマス」
混乱した問いかけ、そして焦点の定まらないおれの表情に対して、客室係は無表情に事務的な応答を返し、足早に去っていった。
おれは自分の胸ポケットを探った。
……ない。
やはり、そこには何も入っていない。
天然炭酸水の元になる、あの泉のヌシ。手の平サイズの義父、あるいは義父のような何か。
一度は手に入れたそれは、やはり失われていた。
「天然の、炭酸水が飲みたい」
そして家で待っているはずの妻を思い出す。
……ああ、おれはまた失敗してしまったのだ。悔しさで身じろぎした拍子に自分のひざの上にのっていたものが床に落ちた。身をかがめて、それを拾い上げる。
汚いペットボトルだった。まるで海岸に打ち捨てられたゴミのように古びれ汚れている。しかしキャップはちゃんと閉まっていて、中には透明な液体が入っていた。じっと眺めていると、微かな気泡が立っていることに気がついた。
……これは、あの炭酸水に違いない。
「とりあえず奥さん大事にしろ」
超巨大サメに飲み込まれる寸前、あるいは飲み込まれてから。いまとなっては夢か現か分からぬ世界でたしかに聞いた、あのクラゲ男の声が思い出された。親切に道案内をされ、しかし肝心な所では邪魔をされて猛烈に腹が立ったような記憶があるのだが、やはりあいつはいいヤツだったんじゃないかと思った。
.。o○.。o○○o。.
「おかえりなさい」
マンションのドアを開けると、そこに妻が立っていた。
おれが差し出したペットボトルを見た途端に「あ、これ天然の」と言って、ためらわずにキャップを開けて飲み始めた。自分のハイボール用にすこしだけ残してくれと言いかけたが、そんな間もなく妻は一気にそれを飲み干した。
「そうそう、こういうの。これが飲みたかったの」
妻は、そう言って満足そうに笑った。
……まあハイボールなんか別にもう。おれはすぐに思い直した。妻の笑顔を見るのは、本当に久しぶりだった。
げぷっ。
一息で炭酸を飲み干したせいか妻はいきなりゲップをした。「やだ、ごめん」と妻は恥じらいながら侘びた。
「……むかし失くした、大事なものが戻ってきたような気がする」
そのときの妻の言葉は、おれには意味がよく分からなかったが、この一連の出来事の意味がそもそも理解不能だ。だから、まあ別にいいとしよう。そんな事を気にしている暇はもうないのだ。
あの日、おれがコンテンツディレクターを殴り倒し会社を出てから、なんと一ヶ月近くが経っていた。その間にようやく梅雨は開けたようで、いまや季節は夏。妻は子供を身ごもっていた。おれはやっぱりハイボールが飲みたくなって時々飲んでみたりはするが、とにもかくにも新しい仕事を見つけなければならない。これから新しい家族が増えるのだ。公務員の中途採用の募集情報など眺めている今日この頃。常識的な小市民には安定が一番だ。義父からの電話はとりあえず無視している。
了
お読みいただき、ありがとうございます。他にも色々書いてます。スキやフォローにコメント、サポート、拡散、すべて歓迎。よろしく哀愁お願いします。
