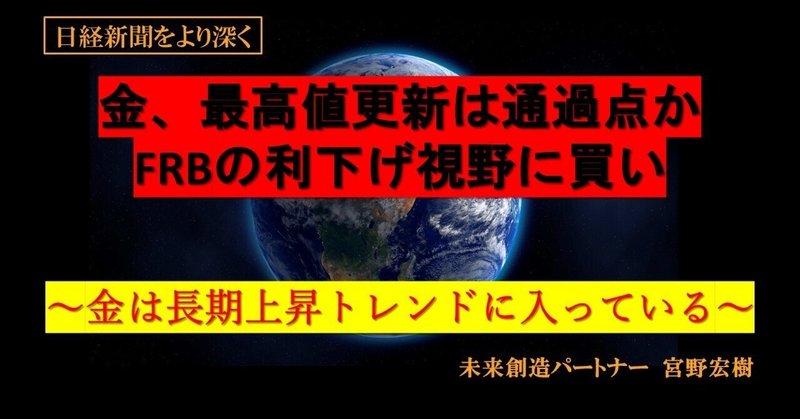
金、最高値更新は通過点か FRBの利下げ視野に買い~金は長期上昇トレンドに入っている~【日経新聞をより深く】
1.金、最高値更新は通過点か
金相場の先高観が強まっている。6日のニューヨーク先物市場では3連休を前にした持ち高調整が優勢だったものの、中心限月である6月物は1トロイオンス2000ドル台を維持。2020年8月に付けた最高値(2089.2ドル)の更新を視野に入れている。欧米の金融システム不安に加え、米景気の減速感が強まるなか、投資マネーの流入が続いている。
米中堅銀行シリコンバレーバンク(SVB)の経営破綻に、スイス金融大手UBSによるクレディ・スイス・グループの救済合併と、金融市場が大きく揺れた3月。「恐怖は金相場を短期から中期で動かす要因」(ゴールドマン・サックス)というように、金融システム不安が市場全体へ波及することへの警戒が根強く、金相場は月間で8%上昇した。
ワールド・ゴールド・カウンシルが6日発表した3月の月次調査によると、金価格に連動する上場投資信託(ETF)と米先物市場への資金流入額(流入から流出を引いた値)は19年6月以来の高水準となった。ETFの月末時点の金保有残高は11カ月ぶりに増加。32.1トンの純増分のうち、欧州が57%、北米が36%をそれぞれ占め、危機の「震源」にいる投資家の需要が支えとなったことが分かる。
金融システム不安がひとまず落ち着きつつあるなかでも、金相場の上昇の勢いは止まっていない。米経済を取り巻く環境がすでに変わってきているからだ。今週は米サプライマネジメント協会(ISM)の景況感指数やADP全米雇用リポートなど、市場予想を下回る統計の発表が相次いだ。経済指標の実績と市場予想の乖離(かいり)を指数化したシティグループのエコノミックサプライズ指数は6日時点でプラス31.4。プラス60を上回っていた3月下旬をピークに急降下している。
特に目立つのは労働市場の過熱感が薄れてきたことだ。チャレンジャー・グレイ・アンド・クリスマスが6日まとめた調査では1〜3月の米企業の人員削減数は27万416人と前年同期の4.8倍に達し、同期間としては20年以来の高水準となった。2月の雇用動態調査(JOLTS)でも求人件数が減少しており、賃金の上昇圧力は次第に和らぎつつあるとの見方が広がる。
景気の減速感が強まるなかで、SVBの破綻の余波で一部の地方銀行から預金が流出し、金融機関の貸し出し態度はより厳しくなりつつある。米連邦準備理事会(FRB)は利上げを打ち止めにした後、早期に利下げに転じる可能性は高まっている。
短期金利先物市場の値動きから、米連邦公開市場委員会(FOMC)ごとの政策金利を予想する「フェドウオッチ」では、6日夕時点で12月に4.00〜4.25%とみる確率が37%弱と最多。現在の4.75〜5.00%を基準にすると、0.25%の幅で3回の利下げを織り込む動きが出ていることになる。FRBはこれまで年内の利下げを否定してきたが、市場では年内の現状維持を織り込む確率はほぼゼロとなった。
「利上げサイクルが終了すれば、金には上昇する余地がある」。バンク・オブ・アメリカは今週、10〜12月期の金価格の予想を2000ドルから2200ドルに引き上げた。実際、FRBが利下げに転じた07年や19年は金相場の上昇に弾みが付いた。
過去を振り返ると、金相場が2000ドルを上回る水準を維持してきた期間は短かった。だが、新興国の中央銀行が基軸通貨であるドル離れを進めるなかで、金を準備資産として積み上げている。ETFを中心とした投資需要が再び盛り返すなかで、金を売らない「投資家」は増えている。最高値を更新した後も、金が一段の上値を追うシナリオは十分にあり得る。
2.金価格の第一の性格
米国の銀行危機から金がひときわ上がっています。4月17日1トロイオンス1985.0ドルです。

ドルの「実効レート」が下がる期待があるとき、米国とロンドンの市場で「金買い/ドル売り」が起こります。実効レートは「ドル/円」の通貨ペアではなく、主要通貨に対するレートです。
ドルレートは1)米国の期待インフレ(予想インフレ)、2)外為市場でのドルの市場予想、3)ドルへの信認という3つの要素を基本に決まるといって良いと思います。
金価格は原油のようにドルレートより何倍、何十倍も大きく動く時期があります。これは、3つ目の要素である基軸通貨ドルへの信認とドル債券への信認が弱くなった時です。2023年3月からの金の急騰は、米国の銀行危機の発生により、「ドル預金への信認が低下」したから起こったものです。
2023年3月からの金の急騰は、米国の銀行危機の発生により、「ドル預金への信認が低下」したから起こったものです。今回の金価格の上昇は、米銀の破産として現れたドルへの信認の低下という、数十年サイクルの長期的変化によるものだと感じています。もちろん、商品相場ですから、上昇途中の利益確定売りや先物売りが勝ち、価格が下がることもあるでしょう。
しかし、今回は、金価格の上昇の主な原因が、ドルからの逃避であると思われ、一定の変動幅(ボラティリティ)をもって、2~3年の長期で上がると個人的には考えています。

3.22年11月から23年4月にかけて350ドル(19%)上がった原因
金は22年11月の1650ドルを底値にして、2023年の4月まで5カ月一本調子で2000ドルまで上昇しました。
最初の上昇の主な要因はインフレ率の低下からFRBの利上げは5%付近(3月)でピークを打ち、23年夏からは逆に0.25%の利下げがあるかもしれないと市場が見ていたことです。米国の期待金利の低下は、短期的には金価格の上昇要因です。しかし、期待金利(3~6カ月先の予想金利)による金価格の短期予想は要素が多すぎるので、非常に難しい。
一方、2023年3月からは「基軸通貨ドルへの信認の低下からの金価格の上昇」となる傾向が強いことから長期での高騰の時期が予想しやすいものとなっています。今回の上昇は、コロナによる世界のゼロ金利の中で、40年ぶりの世界インフレを引き起こしたドルへの信認の低下から起きていると思われます。また、脱ドル化が進展しており、ドルでの貿易決済が減ってきており、この面からもドルへの信認の低下が起きています。
現在、米欧の銀行危機を起こしたドル預金の流出とその一端が現れたドルへの信認の低下、また中東での原油決済を人民で行うなどの脱ドル化の波でドルへの信認が低下しており、金価格を押し上げていると言えます。
もう少し細かく2022年11月から2023年4月への金価格の上昇要因を見ていきましょう。2つの要因が考えられます。
一つ目の要因は、この時期、米国のインフレの鈍化(23年3月インフレ率5%)から、FF金利のターミナルレートは5%程度と見られるようになったことです。FF金利の上昇は23年3月の5%で終わるか(30%の確率)、6月の5.25%までの上昇で終わるか(70%の確率)という、金融市場の期待が広がっています。6%台も視野にといわれていたことを思うと、かなり下がりました。
二つ目の要因は、市場が織り込んでいなかった銀行危機です(23年3月)。以前からのドル金利上昇の裏で起こっていたのは固定金利の債券(国債、MBS、社債、ハイイールド債)を資産とする、銀行とノンバンク(ファンド)の経営危機でした。
約4ポイントの金利の上昇から時価価格が下がり、米国債とMBSの債券の売りが増えました。そのため、米国債とMBSを保有する米銀に含み損が発生して銀行危機となったのです。結果としてこの時期から安全資産とされている金へのマネー逃避が世界的に起こりました。これが「22年3月から見せた金価格高騰の長期化の傾向」の大きな要因です。
現在は「米ドルへの信認の低下」という、これまでにない金価格の上昇時期でしょう。
今回の上昇は「長く続き、上げ幅も大きくなる可能性」があります。もちろん、相場の金融商品なので、短期的には価格の上下はあります。ですから保有する場合は長期で持つことが大前提です。
金の上昇が長期化すると考えるのは、米欧の銀行危機が長期化すると考えているからです。銀行の預金流出の危機に対するFRBの緊急マネー投入(レポ金融:債券などを一定の価格で売り戻しあるいは買い戻しする条件を付した売買取引のこと)で、株価が一時的に戻っても、銀行危機は債券のポートフォリオのバランスシートの中で、深まっています。
時間とともに簿外損失が増加し、資金繰りのための換金売り(=成り行きの投げ売り)で巨大損が出てくるプロセスです。
多種の債券に、時間をかけて玉突きのように波及していくので、「今回の債券の売り損失に比例する、金価格の高騰は長期化する」と考えるわけです。
そして、もう一つ銀行危機が長期化すると思われる大きな原因が不動産です。米国の商業用不動産の価格の下落が始まっており、銀行が持つCMBS(Commercial Mortgage Backed Securities:商業不動産担保証券)が25%も下がっています。これは23年8月ころからはリーマンショックの時のような住宅価格下落にもなっていくでしょう。
欧州ではすでに住宅価格が下がっています。欧州でも住宅ローンは米国と同じように証券化されていて(10兆ドル:1,330兆円)、RMBS(Residential Mortgage Backed Securities:住宅ローン担保証券)銀行が買って銀行の資産となっています。これが下落すると広範囲の銀行危機になります。

EU圏の経済の中心であるドイツではすでに住宅価格がー2.9%と下落しています。

米欧ともにインフレの中、ローン金利が21年比で米国では2倍、ドイツは4倍に上昇しています(米国では6%台、ドイツは4%後半)。ローン金利が下がる見込みは当面ありません。そうなると、コロナ期の約3年のローン金利の低さ(米国では約3%)を要因とする不動産の上昇はあり得ないことになります。不動産の価格は下落方向にしか向きません。

コロナ後の金利が上がり、債券が下落したことが原因の米欧同時の銀行危機は、通貨の危機です。金価格が大きく上がる要因になります。
4.2023年はBRICS中央銀行の金買いが急に増加
BRICS(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ)と新興国のグローバル・サウスはウクライナ戦争以降、ロシアー中国側に立ち、上海機構につきました。
EU委員長のフォン・デア・ライエンとフランス大統領のマクロンは北京詣をしました。中国の資源、商品の輸入、産業への浸透のためです。ウクライナ戦争は、実質的には終わっているといえます。ロシアの優勢は逆転することが不可能な域に入っています。
また、米国の機密情報の流出事件はまだ影響は大きくなるでしょう。この流出事件は米政権内部の対立、つまり、このままいけば、米露の核戦争を懸念する勢力のリークではないかともいわれています。このまま軍事支援の停止につながっていくかもしれません。
BRICS連合は自己都合を優先するドルから離れるため、金・コモディティリンクのデジタル通貨(CBDC)を国際通貨にする構想を進めています。国を持たないIMFの通貨バスケットSDR(特別引き出し権)のようなものです。
米国がウクライナ戦争の時、制裁としてロシアのドル外貨準備(6300億ドル:82兆円)を凍結し、米国が許すまで引き出せないようにしたことが大きなきっかけとなり、進展しています。この時からBRICSと南アジアを含むグローバル・サウスはドル離れを決定したのです。これらの国々のGDPの総計は世界の50%を占め、GDP成長率は5%と高い成長を記録しています。
ドル圏に残る米国、EU、英国、カナダ、オーストラリア、日本は老大国と言えます。GDPの成長率は高くても2%台です。10年後の勝敗は明らかです。
中国は約3兆ドル持つ外貨準備(80%はドル)を目立たないように少しずつ売って、金を買っています。BRICS連合も中国に倣っています。中国は新興国のリーダーとしての地位を高めています。
5.中央銀行の金買い
金価格は中央銀行の金地金と機関投資家による金ETFの買いが増えたときに上がり、金ETFが売り越されたときに下がるという単純な性格を持っています。
1年間でいえば、中央銀行の地金買いとETFの合計で400トン以下の買い越しの時は価格が下がり、およそ600トンの時は価格維持、およそ1000トン以上の時、価格が上がっています。
金の供給は4800トン/年で一定しています。個人とファンドはゴールドバーを先物を含めて売買しています。宝飾需要46%(2200トン)と工業用は6.5%(310トン)です。(2022年)
中央銀行の金地金の買いは、生産量の24%(1150トン:2022年)に増えました。リーマンショックからドルが下がった後の2010年から中央銀行は買い越しを続けています。リーマンショック(2008年~2012年の4年間)はドル危機だったからです。
ドル基軸通貨が安定していた2007年までの約30年間、年平均400トン(合計1万2000トン)を売り越していたのですから信じられない変化です。
中央銀行の金買いは、金地金とETFを併せて2018年650トン(価格維持)、19年730トン(価格維持)、20年1006トン(価格上昇)、21年261トン(価格下落)、22年1025トン(価格上昇)でした。

中央銀行と個人に買われた金地金は売り越して市場に出ることはないでしょう。ただし、銀行・ファンド・機関投資家が売買しているペーパーゴールドの金ETFでは、売り越しの年度があります。金ETFが売り越された年は価格は下がる傾向にあります。
2022年の四半期には中央銀行は417トンの金地金を買い込んでいます。(1年1600トンのペース)。これが22年11月から金が上がった原因です。
2022年の9~12月に個人で金地金(投資用ゴールドバー)を大きく買った筆頭が中国人(228トン)、EU(314トン:うちドイツ人185トン)、米国人(128トン)です。(WGC2022年金の供給と需要データ)。
2023年1月から3月までのデータはまだ公開されていません。この時期の価格急騰から見ると、1)ドルから離脱する中央銀行の買いの増加、2)銀行危機からの個人の投資用バーの買いの増加が推計されます。
2023年からの金価格上昇を予想する要素はドル離れのためのBRICSの中央銀行の買いの増加と世界の個人投資家の買いの増加です。現物が市場で足りないので、金ETFも買いも増えるでしょう。
4800トンの年間供給は変化しても100トン(±2%)です。需給の関係から2023年から2025年ころまでは1980年(4倍)や2005年から2011年(4.5倍)のような約20年サイクルの金価格の高騰期に入ったと予想します。
大きな要素はBRICSとサウジをリーダーとする産油国(OPEC)の準備通貨の「ドル離れ→金買い」です。中国は世界一の産金国(370トン/年)ですが、輸出は厳禁し、輸入して貯めこんでいます。ロシアは世界3位の産金国(300トン)であるため、輸入は25トン(2022年)、産金国の世界2位のオーストラリアは330トンです(2022年)。
日本は2022年に何と世界に逆行して11トンを売り越しています。
1980年には米国がイランのホメイニ革命の時、イランのドル預金を凍結しました。中東は米国が凍結のできない金を買って対抗したのです。この産油国の買いのために、金価格は1オンス200ドルから800ドルに1年半で4倍に上がりました。この時の雰囲気に2023年は非常に似ていると感じます。
これらはあくまで予測です。しかし、歴史的な脱ドル化が起きている中で、金が見直されていることは間違いありません。
未来創造パートナー 宮野宏樹
自分が関心があることを多くの人にもシェアすることで、より広く世の中を動きを知っていただきたいと思い、執筆しております。もし、よろしければ、サポートお願いします!サポートしていただいたものは、より記事の質を上げるために使わせていただきますm(__)m
