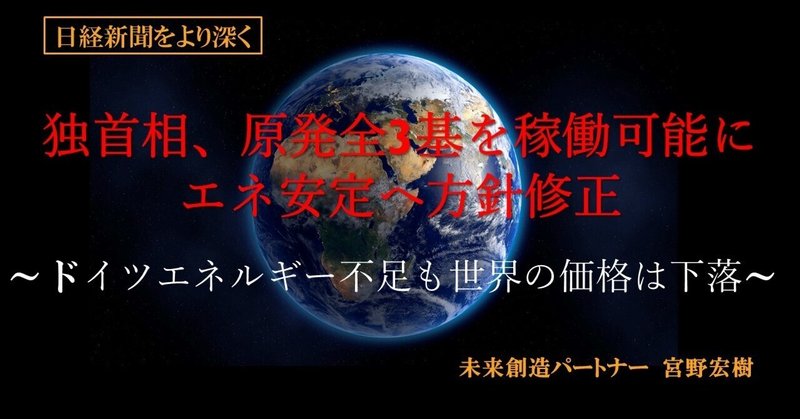
【日経新聞をより深く】独首相、原発全3基を稼働可能に エネ安定へ方針修正~ドイツエネルギー不足も世界の価格は下落~
1.独首相、原発全3基を稼働可能に
ドイツのショルツ首相は17日、国内にある原子力発電所の全3基を2023年4月まで稼働可能な状態にする方針を固めた。独メディアが一斉に伝えた。これまでは2基だけを対象とし、残る1基は年内に運転を終える予定だった。原発の運転延長を求める世論が高まるなか、不測の事態に備えてエネルギー供給を安定させる。
ドイツ政府は9月上旬、南部にある「イザール2」と「ネッカーベストハイム2」の原発2基を非常用の予備電源として活用できる方針をまとめたばかり。残る1基で西部にある「エムスラント」は年内の運転停止を目指していたが、他の原発と同様に23年4月中旬まで稼働できる状態を保つ方向だ。法整備に向けて、ショルツ氏がハベック経済・気候相らに書簡を送った。
当初、独政府は22年末までに「原発ゼロ」を完了する計画だった。東京電力福島第1原発の事故を受け、メルケル政権時代の11年5月に脱原発を決めてからは段階的に廃炉を進めてきた。
ところが、ウクライナ危機でエネルギー不安が高まると、最後の3基をめぐり運転延長を求める声が広がった。独DPA通信が10月にまとめた世論調査では、24年以降の原発稼働に前向きな回答が全体の56%に達した。原発を無期限で稼働すべきだとの回答も19%を占めており、ドイツ政府が予備電源としての活用を表明してもなお延長論が勢いづく。
ドイツはドイツ社会民主党(社民党、SPD)、緑の党、自由民主党(FDP)の3党連立の新政権が2021年12月発足しました。オラフ・シュルツ首相は連立政権のバランスに腐心しています。
ただ、原発再稼働の背景にはそもそもエネルギーが無いことが問題です。そのための原発再稼働です。
2.エネルギー不足はインフレを引き起こしている。
ドイツはロシアからの天然ガスの供給に依存してきました。しかし、ロシアのウクライナ侵攻後、供給が減少し、その後停止。さらにはパイプラン爆破によってノルド・ストリームは完全停止したままです。
したがって、天然ガスをロシア以外に求め、何とか、今冬の備蓄はできているようです。ただ、これまでの安く、安定的であってロシア産の天然ガスは手に入りませんので、そもそもエネルギーが無いという状況で、様々な手段で集めなければなりません。
これまでロシア産の天然ガスは長期契約で安価に輸入していました。しかし、現在、購入しているのはスポット価格です。そのため、価格が高い。これは、ドイツにインフレをもたらしています。

ドイツの9月の消費者物価指数は前年同月比で10.0%の上昇で、ドイツメディアによると1951年以来の高いインフレ率です。エネルギー価格は43.9%、食品価格は18.7%上昇しています。
そのため、ドイツ経済は苦境に陥っています。

上記をドイツのPMIです。PMIとは「Purchasing Manager’s Index」の略で、「購買担当者景気指数」のことです。製造業やサービス業の購買担当者を調査対象にした、企業の景況感を示す景気指標の一つです。購買担当者に、生産や新規受注、受注残、雇用、価格、購買数量などをアンケート調査し、結果に一定のウエートを掛けて指数化したものです。中でも製造業の購買担当者は、製品の需要動向や取引先の動向などを見極めて仕入れを行うため、製造業PMIは今後の景気動向を占う「先行指標」とされています。現在は多くの国(地域)で調査・公表されており、発表時期が国内総生産(GDP)など他のマクロ指標より早いため速報性が高く、マーケットはこのPMIに注目しています。
PMIは50を景況感の分岐点としており、50を下回れば景況感が悪く、50を上回れば景況感が良いとされています。現在、3カ月連続で50を切っており、景況感の悪化が鮮明になっています。
ドイツ経済の苦境は、EU圏の経済の苦境も意味することになります。
3.しかし、世界ではエネルギー価格が下落している。


ドイツおよびEU圏、英国などはエネルギー価格が高騰しました。そして、今もインフレをもたらしています。しかし、これはロシア産の安いエネルギーが入らなくなり、長期価格ではスポット価格で、また、パイプラインではなく、液化天然ガス(LNG)での輸入でコストが上がっているからです。
実は原油価格も、天然ガス価格も市場では下落しています。この背景には世界経済の減速があります。特に大きいのが中国の需要減です。2022年は前年比で2.7%減の見込みです。中国の原油需要が減るのは1990年以来で、世界全体の原油需要への影響度も大きいといえます。
大きなポイントはOPECの減産発表があって、一瞬は上がった原油価格が再び下がり始めていることです。この下落トレンドは、世界経済、特に中国の景気後退を意味していると思われます。
地政学の問題から、エネルギー危機は続きます。しかし、価格はそれほど上がっていませんから世界経済の後退は確実に進んでいます。
2023年は世界景気の後退、もしかすると、年央には米国でも住宅バブルの崩壊が鮮明となり、金融危機もあり得るかもしれません。いずれにしても、世界経済としては2023年の後退は確実でしょう。
ただ、これは旧体制の崩壊を意味し、ここから新しい経済や世界秩序の誕生前の混乱と考えています。この混乱の先を見据えることが大切ですね。
未来創造パートナー 宮野宏樹
【日経新聞から学ぶ】
自分が関心があることを多くの人にもシェアすることで、より広く世の中を動きを知っていただきたいと思い、執筆しております。もし、よろしければ、サポートお願いします!サポートしていただいたものは、より記事の質を上げるために使わせていただきますm(__)m
