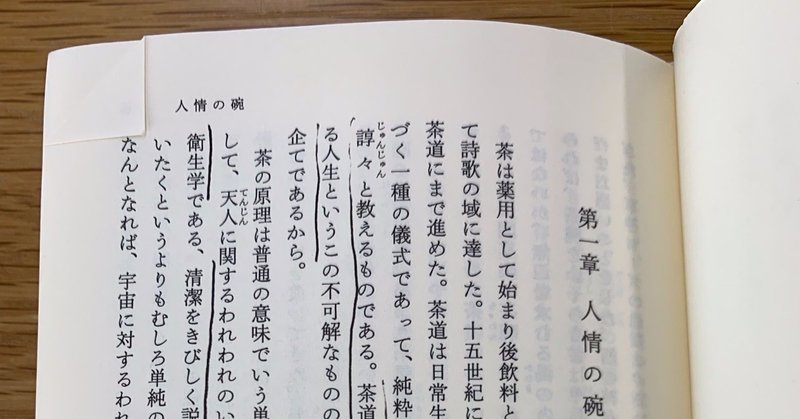
[茶の本 岡倉天心] Underline
茶の本を読みながら線を引いたところを書き出しています。
【人情の碗】
●茶道の要義は「不完全なもの」を崇拝するにある。いわゆる人生というこの不可解なもののうちに、何か可能なものを成就しようとするやさしい企てであるから。
●茶の原理は普通の意味でいう単なる審美主義ではない。
●ほんとうの茶人チャールズ・ラムは、「ひそかに善を行って偶然にこれが現れることが何よりの愉快である。」というところに茶道の真髄を伝えている。というわけは、茶道は美を見出さんがために美を隠す術であり、現すことをはばかるようなものをほのめかす術である。
【茶の諸流】
●涅槃はつねに掌握のうち、不朽は永遠の変化に存すという道教の考えがかられのあらゆる考え方にしみ込んでいた。興味あるところはその過程にあって行為ではなかった。真に肝要なるは完成することであって完成ではなかった。
●茶の湯は、茶、花卉、絵画等を主題に仕組まれた即興劇であった。茶室の調子を破る一点の色もなく、四囲の統一を破る一言も発せず、すべての行動を単純に自然に行う―こういうのがすなわち茶の湯の目的であった。
【道教と禅道】
●「相対性」は「安排」を求める。「安排」は「術」である。人生の術は我らの環境に対して絶えず安排するにある。道教は浮世をこんなものだとあきらめて、儒教徒とは異なって、この憂き世の中にも美を見いだそうと努めている。
●物のつりあいを保って、おのれの地歩を失わず他人に譲ることが浮世芝居の成功の秘訣である。われわれはおのれの役を立派に勤めるためには、その芝居全体を知っていなければならぬ。個人を考えるために全体を考えることを忘れてはならない。この事を老子は「嘘」という得意の隠喩で説明している。物の真に肝要なところはただ嘘にのみ存すると彼は主張した。たとえば室の本質は、屋根と壁に囲まれた空虚なところに見いだすことができるのであって、屋根は壁そのものにはない。
●おのれを嘘にして他を自由に入らすことのできる人は、すべての立場を自由に行動することができるようになるであろう。全体は常に部分を支配することができるのである。
●禅は梵語の禅那から出た名であってその意味は静慮である。精進静慮することによって、自正了解の極地に達することができると禅は主張する。
●真理は反対なものを会得することによってのみ達せられる。
●禅門の徒は事物の内面的精神と直接交渉しようと志し、その外面的の付属物はただ真理に到達する阻害とみなした。この絶対を愛する精神こそは禅門の徒をして古典仏教派の精巧な彩色画よりも墨絵の略画を選ばしめるに至ったのである。
●極致を求めんとする者はおのれみずからの生活の中に霊光の反映を発見しなければならぬ。禅林の組織はこういう見地から非常に意味深いものであった。祖師を除いて禅僧はことごとく禅林の世話に関する何か特別の仕事を課せられた。そして妙なことに新参者には比較的軽い務めを与えられたが、非常に立派な修行を積んだ僧には比較的うるさい下賤な仕事が課せられた。こういう勤めが禅修行の一部をなしたものであって、いかなる些細な行動も絶対完全に行わなければならいのであった。
●茶道いっさいの理想は、人生の些事の中にでも偉大を考えるというこの禅の考えから出たものである。道教は審美的理想の基礎を与え禅はこれを実際的なものとした。
【茶室】
●ある美的必要を満たすためにおく物のほかは、いっさいの装飾を欠くからには「空き家」である。それは「不完全崇拝」にささげられ、故意に何かを仕上げずにおいて、想像の働きにこれを完成させるからには「数寄屋」である。
●茶の湯の基をなしたものはほでもない、菩提達磨の像の前で同じ碗から次々に茶を喫むという禅僧たちの始めた儀式であったということはすでに述べたところである。が、さらにここに付言してよかろうと思われることは禅院の仏壇は、床の間ー絵や花を置いて客を教化する日本間の上座ーの原型であったということである。
●待合から茶室に通ずる露地は黙想の第一段階、すなわち自己照明に達する通路を意味していた。露地は外界との関係を断って、茶室そのものにおいて美的趣味を充分に味わう助けとなるように、新しい感情を起こすためのものであった。この庭径を踏んだことのある人、常緑樹の薄明に、下には松葉の散りしくところを、調和ある不ぞろいな庭石の上を渡って、苔むした石灯籠のかたわらを過ぎる時、我が心のいかに高められたかを必ず思い出すであろう。たとえ都市の真ん中にいてもなお、あたかも文明の雑踏や塵を離れた森の中にいるような感がする。
●茶室はある個人的趣味に適するように建てられるべきだということは、芸術における最も重要な原理を実行することである。芸術が充分に味わわれるためにはその同時代の生活に合っていなければならぬ。それは後世の要求を無視せよというのではなくて、現在をなお一層楽しむことを努むべきだというのである。また過去の創作物を無視せよというのではなくて、それをわれらの自覚の中に同化せよというのである。伝統や形式に屈従することは、建築に個性の表れるのを妨げるものである。
●現在日本に見るような洋式建築の無分別な模倣を見てはただ涙を注ぐほかはない。
●ギリシャ国民の偉大であったのは決して古物に求めなかったからであると伝えられている。
●美しいものの真の理解はただある中心点に注意を集中することによってのみできるのであるから。
●「数寄屋」はわが装飾法の他の方面を連想させる。日本の美術品が均斉を欠いていることは西洋批評家のしばしば述べるところである。
●彼らの哲学の動的な性質は完全そのものよりも、完全を求むる手続きに重きをおいた。真の美はただ「不完全」を心の中に完成する人によってのみ見いだされる。
●禅の考え方が世間一般の思考形式となって以来、極東の美術は均斉ということは完成を表すのみならず重複を表すものとしてことさらに避けていた。意匠の均等は想像の清新を全く破壊するものと考えられていた。
●生花があれば草花の絵は許されぬ。丸い釜を用いれば水さしは角張っていなければならぬ。黒釉薬の茶わんは黒塗りの茶入れとともに用いてはならぬ。香炉や花瓶を床の間にすえるにも、その場所を二等分してはならないから、ちょうどそのまん中に置かぬように注意せねばならぬ。少しでも室内の単調の気味を破るために、床の間の柱は他の柱とは異なった材木を用いねばならぬ。
●西洋の家ではわれわれから見れば無用の重複と思われるもにしばしば出くわすことがある。
●お祝いの饗宴に連なりながら食堂の壁に描かれたたくさんのものをつくづくながめて、ひそかに消化の傷害をおこしたことは幾度も幾度もある。
●茶室は芸術的精神と自由に交通する唯一の機会を与えてくれた。偉大なる芸術品の前には大名も武士も平民も差別はなかった。
【芸術鑑賞】
●偉大な絵画に接するには、王侯に接するがことくせよ。傑作を理解しようとするには、その前に見を低うして息を殺し、一言一句も聞きもらさじと待っていなければならない。
●わが国の沙翁近松は劇作の第一原則の一つとして、見る人に作者の秘密を打ち明かすことが重要であると定めた。
●日本の古い俚諺に「見えはる男にはほれられぬ。」というのがある。そのわけは、そういう男の心には、愛を注いで満たすべきすきまがないからである。芸術においてもこれと等しく、虚栄は芸術家公衆いずれにおいても同情心を害することはなはだしいものである。
●すなわちわれら特有の性質がわれらの理解方式を定めるのである。
●偉い利休は、自分だけにおもしろいと思われる物をのみ愛好する勇気があったのだ。しかるに私は、知らず知らず一般の人の趣味にこびている。実際、利休は千人に一人の宗匠であった。
●人は自己の感情には無頓着に世間一般から最も良いと考えられている物を得ようとかしまし騒ぐ。高雅なものではなくて、高価なものを欲し、美しいものではなくて、流行品を欲するのである。
●過去がわれらの文化の貧弱を哀れむのも道理である。未来はわが美術の貧弱を笑うであろう。われわれは人生の美しい物を破壊することによって美術を破壊している。
【花】
●原始時代の人はその恋人に初めて花輪をささげると、それによって獣性を脱した。
●彼が不必要な物の微妙な用途を認めた時、彼は芸術の国に入ったのである。
●喜びにも悲しみにも、花はわれらの不断の友である。花とともに飲み、共に食らい、共に歌い、共に踊り、共に戯れる。花を飾って結婚の式をあげ、花をもって命名の式を行う。花がなくては死んでも行けぬ。
●われわれはいずれに向かっても「破壊」に面するのである。上に向かうも破壊、下に向かうも破壊、前にも破壊、後ろにも破壊。変化こそは唯一の永遠である。
●われわれが花に求むるところはただ美に対する奉納を共にせん事にあるのみ。われわれは「純潔」と「清楚」に身をささげる事によってその罪滅ぼしをしよう。
●彼らは一枝一条もみだりに切り取ることをしないで、おのが心に描く美的配合を目的に注意深く選択する。彼らは、もし絶対に必要の度を越えて万一切り取るようなことがあると、これを恥とした。
●花が色あせると宗匠はねんごろにそれを川に流し、または丁寧に地中に埋める。
●彼らは生物に対する限りなき心やりのあまり、暴風に散らされた花を集めて、それを水おけに入れたということである。
●茶人の花は、適当に生けると芸術であって、人生と真に密接な関係を持っているからわれわれの心に訴えるのである。
●晩冬のころ茶室に入れば、野桜の小枝につぼみの椿の取り合わせてあるのを見る。それは去らんとする冬のなごりときたらんとする春の予告を配合したものである。またいらいらするような暑い夏の日に、昼のお茶に行って見れば、床の間の薄暗い涼しい所にかかっている花瓶には、一輪の百合を見るであろう。露のしたたる姿は、人生の愚かさを笑っているように思われる。
●たしかに日本の桜花は、風に身を任せて片々と落ちる時これを誇るものであろう。
●宝石をちりばめた雲のごとく飛ぶことしばし、また水晶の流れの上に舞い、落ちては笑う波の上に身を浮かべて流れながら「いざさらば春よ、われらは永遠の旅に行く。」というようである。
【茶の宗匠】
●われらに認めたい心さえあれば完全は至るところにある。利休は好んで次の古歌を引用した。
花をのみ待つらん人に山里の雪間の草の春を見せばや
●この人生という愚かな苦労の波の騒がしい海の上の生活を、適当に律してゆく道を知らない人々は、外観を幸福に、安んじているようにと努めながらも、そのかいもなく絶えず悲惨な状態にいる。われわれは心の安定を保とうとしてはよろめき、水平線上に浮かぶ雲にことごとく暴風雨の前兆を見る。しかしながら、永遠に向かって押し寄せる波濤のうねりの中に、喜びと美しさが存している。
●美を友として世を送った人のみが麗しい往生をすることができる。
広告営業、広告制作の現場、そして社長業を通した実体験を元に記事を書いています。よろしければサポートをお願いいたします。
