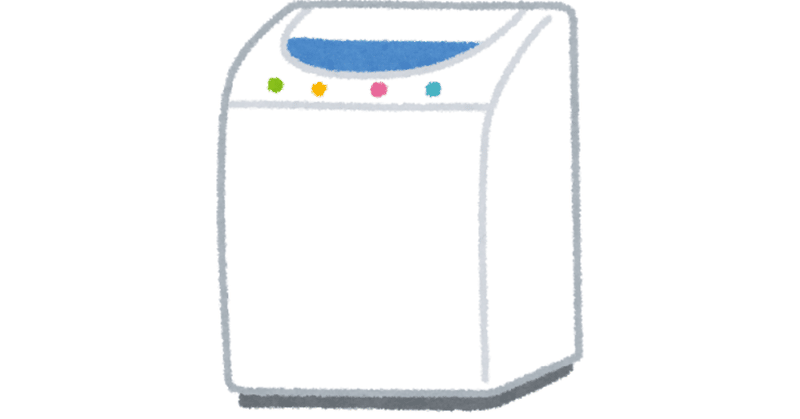
[掌篇集]日常奇譚 第50話 裏返し
何かに憤ったことが一度もないのではないかと思うような女性が知り合いにいて、そのことについて少し話をしたことがある。
「もちろん怒ることはある」と彼女は言った。「ただ、それをすぐには出さないようにしているだけ。まずいろいろ考えることにしている」
「なにを?」
「いろんな可能性」
「可能性……?」
「思いこみや決めつけが多いと思うんだよね。人間の感情や考えって。あいつが悪い。あいつが犯人だ。でも実はそうじゃないかもということはよくあって。だから本当にそうなのかということをとことん疑ってみることにしている。結論を出してしまう前に。早まって出した結論が、取り返しのつかない結果を招くこともあるから」
そんな会話から彼女の話が始まった。
ここから先は、そのときに彼女から聞いたままの話だ。
👕👚👗
きっかけは洗濯物だった。そのほかにも細々としたことがあってそれが洗濯物の件に集結したのかもしれなかったが、そのときにはもうとにかくそれが大問題であるかのように思われた。
最初に気づいたのがいつだったのかはよくわからない。たいした問題と感じていなかった時期がしばらくあったことは憶えている。ということは、きっと無意識下ではずいぶん以前から気づいてはいたのだろう。
無意識下でのそれがいきなり異質な形をもって浮上してきたときのことはよく覚えている。
そのとき、それまでは霧のようにおぼろであったものが、ふいに凝縮して不快なざらついたものに変わった。
たぶんタイミングのせいだ。
いまはもう夫ではなくなった以前の夫と、つまらない口喧嘩をした直後だった。
彼女は苛立ちをかかえたまま、洗濯し終えた洗濯物を干していた。喧嘩をしたばかりの相手の洗濯物を処理していると、なぜ自分があんな男の服などを洗ってやらなければならないのかと黒い怒りがふくれあがってくる。ついつい洗濯物を扱う手つきも乱暴になってくるというもので、いちいち裏返っている彼のシャツまでやけに癪にさわった。いったいなんだって、こいつらはいちいち裏返るのか。まるで嫌がらせのように。
手がとまったのはこのときだ。
裏返ってねじれた夫のシャツをもとに戻そうとしていたとき。
これは偶然だろうか?
ふいにそんな疑念がわいてきた。裏返しのこのシャツ。そういえば彼のシャツはいつも裏返しになっていたり、盛大にねじれていたりするような気がする。これは偶然だろうか。ひょっとしてあの男のいやらしい嫌がらせでは?
洗濯をするのはいつも彼女と決まっている。夫は洗濯機に手も触れない。陰険な嫌がらせにもってこいだ。わざとシャツを裏返しに脱ぎ、わざと何枚かまとめて脱ぐ。その光景がまざまざと見えた。
パズルのピースがパチンと合った気がした。
馬鹿馬鹿しいほど些細でくだらない嫌がらせ。
けれど、たまらなくいやらしい。
そしてたちが悪い。
その日から、夫の様子と洗濯物の様子をそれとなく観察するようになった。
意識して観察してみると確かに彼のシャツや下着などはしょっちゅう裏返しになっていた。ひょっとしたらこれはそういう癖のある洗濯機なのではないだろうか。そんなあらぬことまで考えた。もちろん洗濯機のなかで勝手に裏返ってしまうこともあるだろう。しかしそれにしては頻度が多すぎた。
彼女はそのうち、裏返った服をそのまま、つまり裏返しのまま畳むことにしはじめた。そもそもこんな嫌がらせを受けている彼女がきちんと直してやる道理などない。夫は特になにも言わなかったが、反撃でもするかのように洗濯物はことごとく裏返しになっていた。彼女のものまで。
的確な反撃だと彼女は憎々しく敵のやり方の効果を認めた。夫の衣服はどうでもいいが、彼女自身の衣服は必ず彼女がどこかの時点で戻さなくてはならない。
さらには、下着などあえて裏返しにして洗いたいときもあるにはあるのだが、そう思ってわざと裏返しておいた洗濯物に関しては逆に表に戻っているのだった。つまり「裏返されている」わけだ。
それにしてもぞっとするのは、彼女の洗濯物に手をつっこんで裏返している夫の姿だ。もちろん目撃したわけではなく彼女の想像上の姿であったが。想像のなかの彼は彼女の衣服を裏返しながらひどく意地の悪い、そしていやらしい笑いをニタニタと浮かべているのだった。
「けど、そんなことってあるかね」と話を聞いた啓子は言った。啓子とはときどき会っておしゃべりをしまくって互いに憂さ晴らしをする。「いくらなんでもそんなことする人いるかなあ」
「変な話だとは私も思ってる」
「うん変な話」
「でも現実に洗濯物は異常な確率で裏返りつづけてる」
「だけど洗濯物は勝手に裏返らない。少なくともそんなに異常な確率で」
「そういうこと」
「証拠はないんだよね?」
「まあね。現場をおさえたことはないけど。でも証拠うんぬんじゃないよ。そうとしか考えられないじゃない」
「そうか……。ほかになにか可能性はないかな」
「ほかに? なんだろう……」と彼女は一応考えてみたが、何も思い浮かばなかった。「ないよね。ふたりしかいない家で。洗うと必ず洗濯物が裏返る。やっぱり、ないよ。ほかの可能性なんか」
「そういう洗濯機だとか」
「水流かなんかのせいとか? それは思ったことがあるけど、すぐ却下した。そんなわけないし。だって、全部だよ。ほとんど、全部」
「じゃあ幽霊とか」
「あ、証拠、ある」と彼女は幽霊説を無視して言った。「裏返るのは洗濯機のそばに私がいないときだけなんだ。絶対にそう。人為的なことなのかちゃんと確認しようと思って、洗濯しているあいだ洗濯機のそばにずっと張りついていたことがあるんだけど、そのときは裏返らなかった。何度か確かめたけど。見張っていると裏返らなくて、見張っていないと裏返る。イヤだったけど、洗濯機に入れる前に服が裏返っていないことを全部確認して、とかそういうのもやったんだよ」
そうか、それなら間違いないんだね、と啓子は認めたように言った。そして、気持悪い男だね、と付け足した。
表面上は、彼女も夫もなにも問題が起きていないふうに装っていた。
時機をのがしてしまったとも言える。最初のうちなら口にすることもできたのかもしれない。しかしもはや互いの嫌がらせは露骨なレベルに達していた。「ねえちょっとおかしなことがあるんだけど」とか「ねえなにか気づかない?」とか、そんなしらじらしい言いぐさはあまりに"いまさら"だ。口にしたとたんに一気にすべてが崩壊しておそろしいことが起こりそうだった。
彼女たちは平穏を装って淡々と静かに生活しつつ、洗濯物を通して血みどろの激しい闘いを繰りひろげていた。
こんな状態がいつまでも続くはずもない。終わりは着実に近づいてきていた。
彼女たちの関係はもちろんどんどん悪化し、ふたりともちょっとしたことで諍うようになっていった。
やがてそれぞれに蓄積されていったものは当然のごとく噴出し、ふたりは結局のところ激しい罵り合いを経由して離婚した。
せいせいする、とはこういうことだ。慰謝料がどうのという話はふたりとも口にしなかった。そんなことで話をこじらせるよりも早く終わりにしたかった。とにかくいまは。
そして、身のまわりのものを少しと一匹の猫だけを連れて彼女は彼のもとを去り、ひとり暮らしをはじめた。
まったく寂しくなかったかというとそんなわけはない。腐っても一度は好きになった男だ。
ひとり暮らしをするのはこれが始めてだったし、だから不安も大きかった。
でも彼女には猫がいた。孤独を優しく癒してくれる小さな生き物。それに、彼女の脱いだ服に手を突っこんでニタニタしながら裏返す気持の悪い男はもういない。いまはこれで充分だ。延び延びとした生活を楽しもうと彼女は思った。
だがそれからしばらく経ったある日。
洗濯物を手にして彼女は愕然としていた。
洗濯物がことごとく裏返しになっていた。
実はその少し前からきざしはあったような気がする。裏返し現象はしっかりと発生していた。そんなはずはないと思いこもうとしていただけだった。けれどもその日の洗濯物は見事にすべてが裏返っており、それはもはや人為的なものであるとしか考えられなかった。
その場で悲鳴をあげそうになったのは、まだ近くに彼が潜んでいるかもしれないととっさに思ったからだ。最近まで夫だったあの男が。こうなってしまうと彼はもはや脅威でしかない。身の危険を感じた。
あわてて玄関と窓の鍵を確認してまわった。しかしそこで、下手に鍵をかけてしまうと、もし彼が部屋のなかにいたときには逃げ場がなくなってしまうと気づいた。密室になってしまう。だがそんな激しい動揺にもかかわらず彼はどこからも現れなかった。
新しいひとりの部屋はもう安全な城ではなくなっていた。
事態がよくわからぬまま、洗濯物はそれからも裏返しになりつづけた。
気味の悪いその事態に対してなにもしなかったわけではない。アパートの周囲の不審者には気を配っていたし、脱衣したものが裏返しになっていないか確認もしていた。それでも洗濯物はいつのまにか裏返しになっているのだった。わずか目を離したすきに。
そんなあるとき、ついに業を煮やし……というか我慢できなくなり、彼女は安価なカメラを借りてきて隠して設置した。ビデオ撮影ができる小型カメラだ。そしてわざと洗濯中に外出してみた。
帰宅してさっそくビデオを観ると、そこにすべてが映っていた。
そしてあっけないほどにあっさりとすべてがわかった。
カメラには彼女の愛猫が映っていた。カメラのなかで猫は洗濯機の上に昇って蓋を開け、驚くべき器用さで洗濯物を取り出しては次々と裏返しにしていた。
息をのんで思わず脇にいる猫のほうを見ると、猫は毛を逆立て、牙を剥いて威嚇してきた。
ああ、そうだったのか、とその様子を見ながら彼女はさとった。愛猫などと思っていたのは彼女の身勝手さにすぎなかったのだ。この猫のほうはずっとひどく気に入らないことがあってそれに耐えていたのだろう。もしかしたら彼女自身を嫌っているのかもしれない。
そして……ああ、なんということだろう……と彼女は激しい動揺のなかで続けて思った。
あれだけひどく罵倒して致命的なまでに傷つけて互いに血みどろになってすべてを壊し合ったかつての夫は嫌がらせなどまったくしてはいなかったのだ。
サポートしてええねんで(遠慮しないで!)🥺
