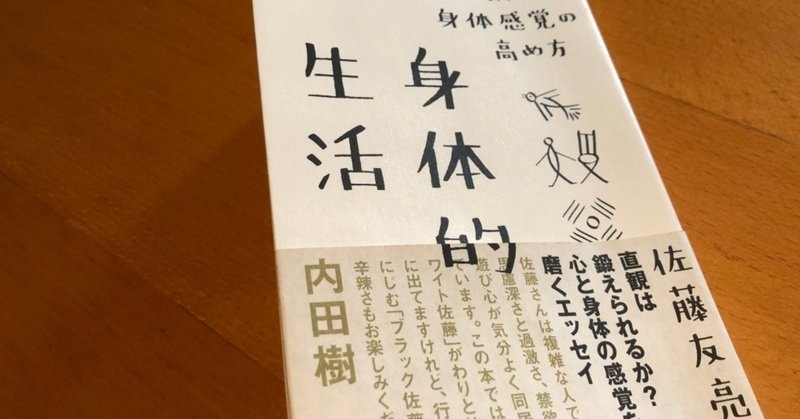
私のフロー体験
私の手には、一冊の本があります。
佐藤友亮著【身体的生活ー医師が教える身体感覚の高め方ー】
著者の佐藤さんは、私が通う道場「合気道凱風館」の塾頭であり尊敬している先輩です。
この本は、第一部にチクセントミハイのフロー理論を
①「非分析的判断」とはどのような時に行い、どうやったらその精度があがるのか?
②「非分析的判断」を行うための身体感覚は、どうしたら高まるのか?
という2つの問いに答える形で丁寧に説明しています。
「非分析的判断」
分析的・論理的に判断を下すのに必要な情報が得られなかったり、情報を解釈する時間的余裕がなかったりする場合に行うものである。
また、いくら情報を集めても、不確定要素が多すぎて、あらかじめ正答を想定しにくい問題、すなわち、引っ越し、結婚、進学、就職など、最終的には「実際にやってみなければどうなるかわからない」ことについて行う判断のことである。
<本文p111より引用>
そして、第二部では、第一部を踏まえて著者の佐藤さんが医師や合気道家としての経験を通じての身体的生活を詳細に告白してくれています。
特に人生に迷っておられる方にはお読みいただきたい一冊です。
さて、私のフロー体験を語る前にフローについて本文から引用。
フローとは、行動の対象に深く没入した状態のことを指し、人間がレベルの高いパフォーマンスを行っているときに見られる。(中略)フローは、トップアスリートに限らず、子供から高齢者まで意識を持つ全ての人間において認められる可能性がある。意識が最高の状態で統制されている状態のことを、チクセントミハイは「最適経験」と称している。チクセントミハイは、フロー理論を最適経験の科学と考えている。<本文p33より引用>
経験者と面談すると”流れ”という表現を使っていたのでフローと呼ぶようになったそうです。トップアスリートでいうところのゾーンに入るということと似ている感じですね。
この本を読み進めて行くうちに、そういえば自分自身もフロー体験してたやん!と気付いてしまいました。
大きく3つくらいでしょうか。
一つは、選挙カーでのカラス(ウグイス)の時
二つに、朝の駅立ちの時
三つに、本会議の議場での質疑の時

《選挙カーのカラスの時》
議員仲間の選挙において応援に伺った時、選挙カーに半日程度乗車することがあります。一般的には、ウグイスさんが綺麗な声で喋っているのですが、私のような男性が選挙カーのマイクを握る時は、カラスと言います。
選挙カーで訴えることが許されているのが8:00から20:00ですので、8:00から14:00、14:00から20:00の二交代制でシフトが組まれることが多く、一回乗ると6時間乗車していることがあります。結構しんどいです。
選挙カーに乗って最初にマイクを握った時は、とても緊張して声が変な感じになったりします。もう数え切れないくらい経験をしている現在でも最初は緊張します。選挙カーの中の空気やその街の空気とのチューニングがうまくいってない感じです。
時間が経つにつれて徐々に馴染んではくるのですが、マイクを握っていると様々なことに注意を払います。
スピーカーの音量、後続車の状況、街行く人の反応、2階以上から見てくれている人がいないか、乳母車を押している人、犬を散歩させている人、マイクを通しての自分の声の質、選挙カーの中の人の状況などなど、
候補者の名前と候補者の訴えたいことを喋りながら、様々なことに注意を払いながら声の大きさや声の質を変えたりもします。
ふと気が付くと、1時間喋りっぱなしということがあります。
その時は、間違いなくフローに入っているのだと思います。
言葉は、次から次へと用意されていく感じでそれを自動的に口にしています。もちろん、様々なことに注意を払いつつ。
”途切れることなくずっと喋り続けて凄いですねえ。”と言われたりしますが、自分では何を喋っていたのかあまり覚えていませんし、苦痛でもなく、むしろ身体は心地よいのです。

《朝の駅立ちの時》
駅頭に朝の7:00から9:00の二時間程度立って挨拶をしています。
「おはようございます。」「いってらっしゃいませ」「お気を付けて」などの挨拶をするという至ってシンプルな行為です。
以前は、スピーカーで話をしたりしていたのですが、何だか独りよがりだと感じて身体が気持ち悪くなったので、現在は挨拶だけにしています。こちらの方が、何か相談事があった時、声を掛けてもらい易い感じがします。私から何か伝えたいことがある場合はチラシをお配りするようにしています。
さて、フローについてです。このシンプルな行為でフロー状態になるのか!?
単純に挨拶だけ行っている場合は、フロー状態にはなりません。
フロー状態だと感じる時には、必ず目的を持っているということに気付きました。
「相手の正中線に向かって挨拶しよう」とか「相手の丹田に向かって挨拶しよう」という目的を持っているのです。また、その場の異物としてではなく、その場に最初からあったように立ちます。
そうすると相手との僅かな気の感応を感じることができて、気がつけば1時間程度経っているという状況になります。
これもフロー状態に入っているのだと思います。

《本会議の議場での質疑の時》
何回も議場で演台に立っているのですが、毎回緊張します。
事前に調査をし、担当課へのヒヤリングを行い、担当課と意見交換を行い、行政の考え方を聞き、私の意見を伝え、と事前に充分準備を行った上で登壇するのですが、やはりそれでも毎回緊張します。
議員によってスタイルは様々ですが、私の場合1問目の質疑については、質疑事項を一言一句文章にした原稿を行政へ渡しています。これは、微妙なニュアンスの違いで質疑と答弁がチグハグになることを防ぐためです。しかし2問目以降は渡しません。大まかな項目は伝えますが、質疑の原稿自体を作らないようにしています。質疑すべき項目だけを記しておくようにします。
それは、現場のライブ感を大切にしたいからです。
当日の本会議場の空気の中で、答弁者がどの様な態度でどの様な表情でどの様な声で語るのか。
そして、それを聞いた私自身は、そこで何を感じ、何を思うのか。
2問目以降も質疑の最後まで、すべて原稿を読み上げる方もいらっしゃいますが、事前に準備した原稿を読み上げる形だと、そこで何も起こらないし、本会議場で質疑する意味の大切なものが失われてしまうように私は感じるのです。
原稿を読む時には、フロー状態には入らないのですが、2問目以降の質疑から、後から振り返るとフロー状態だったと感じることがあります。その時は、自然と適切な言葉が自分の身体からあふれてきて、準備していなかった質疑をすることになります。

これら三つの例を、「身体的生活」の本文に書かれている”フローを成立させる八つの条件”に照らし合わせると、なるほど、大なり小なりすべて当てはまっています。
それと、もう一つ記さねばならないことがあります。
それは、これらのフロー状態を経験したのが合気道の稽古をはじめてからだということです。
合気道を5年以上続けてきて、フローを体験することのできる身体的生活ができているのだと嬉しくなりました。
合気道の教えの中で私が一番大切にしていることは、
道場は楽屋であり、本番は日常の生活である
というものです。試合の無い合気道においては、道場での稽古はあくまで練習の場であって、その成果を発揮する場所は、それぞれのフィールドであるということです。
私の場合であれば、茨木市議会議員としての活動自体が、稽古を重ねた合気道の本番となります。
ますます、身体的生活を意識してこれからの人生を送っていきたいです。
そして更に、自分自身の人生そのものがフロー状態に入る様な一生にしたいなあ。
佐藤さんの著書のお陰で、自分自身を整理することができました。有難うございます。
最後までお読み下さり、有難うございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
