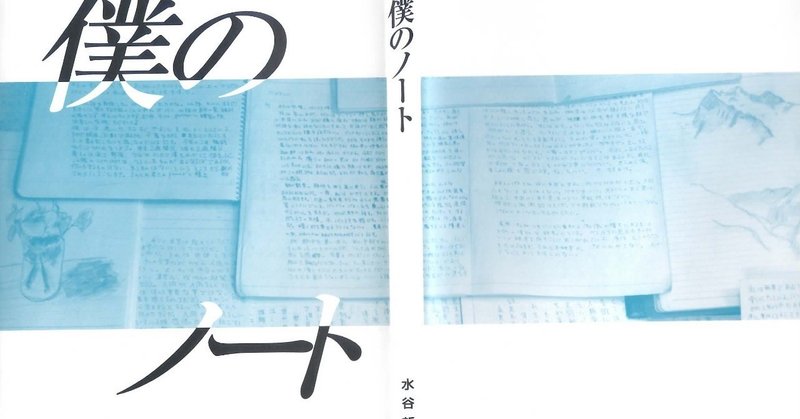
困難を表現すること――個にとっての重みに辿り着くために
春の盛り。身近にある桜は、ほとんどが散り、咲き始めがゆっくりの幾本かが葉桜になっている。時は、新緑が眩しい季節に移りつつある。死んだ弟、水谷哲史の誕生日3月30日と命日4月27日に挟まれたこの季節は、いつも弟を思い出しながら過ごす。とりわけ、死の一週間ほど前に(ちょうどいまの時期だ)、入院中の精神科病院から一時帰宅していた弟と二人で実家の近くを散歩していて、新緑が春の陽射しに神々しいまでに光り輝いていた一角に同時に立ち止まり、「きれいだね」と言葉を交わしたことは忘れられない。
春と初夏の狭間に偶然、訪れた一瞬の至福の思い出を記念して、3年前に『α-Synodos』vol.193(特集:支援とアート、2016年4月1日発行)に寄稿した文章をここに再掲する。
§ § §
困難を表現すること――個にとっての重みに辿り着くために
1991年4月27日土曜日、私は2歳年下の弟を自殺で喪った。「軽い精神分裂病(現在の統合失調症)の初期」と診断されて3週間経つか経たないかの出来事だった。
◇半分、正しくて、半分、間違っていた
1991年4月27日土曜日、私は2歳年下の弟を自殺で喪った。「軽い精神分裂病(現在の統合失調症)の初期」と診断されて3週間経つか経たないかの出来事だった。
精神科病院に入院中だった彼は、週末の一時帰宅のため、前夜から実家にいた。私は当時、新米の美術館学芸員として土日もなく深夜まで働く日々を過ごしていたが、その日は夜には出勤する約束でオフをもらい、弟に会いに行くことになっていた。だが、午前中から昼にかけて別の用事を二つほど済ませ、午後半ばに実家に辿り着いた時にはもう遅かった。弟は私を待っていてはくれなかった。前夜に母に「死にたい」と打ち明けた彼と、久しぶりの空き時間にほっと一息ついていた私の時間の流れは、違っていたのだ。
弟は、夜遅くに両親に伴われ、警察から白木の棺に入れられて戻ってきた。「損傷が激しい」という理由で、私は遺体に会うことも許されなかった。その夜、両親の部屋で(両親は別室で棺に付き添って寝た)一睡もできずに考え続けるなかで、私は3つのことを決意した。
「自殺や精神疾患をstigmatizeもromanticizeもしない。差別も聖別もしない。だから、精神分裂病と診断されていたことも含め、決して隠さない」
「(弟の死にまつわるすべてのことを)決して後悔しない」
「90歳で老衰で死ぬのも、24歳で自殺で死ぬのも、死という意味では等価であると思う」
人は必ず死ぬ。生きていれば、人の死に遭遇するのも避けられないこと、当たり前のこと、ありふれたこと。特別なことじゃない。自殺だからと言って、苦悩の末のヒロイックな悲劇のように語りたくも、語られたくもない。精神疾患もまた、生きていればかかり得る、ありふれたもの。特別なことじゃない。「狂気」などというものものしい言葉を使って、あたかも繊細で鋭敏な感受性の帰結のように語る言辞は、拒否したい。
つまり私は、日々、起こる諸々のことと同じように、それらと同等のものとして、弟の死を淡々と受け止めようとした。いま思えば、その後、起こり得ることを直感的に察知して、そう決心することで、自分の感情にロックをかけようとしたのだろう。
この私の決意は、半分、まったく正しくて、半分、徹底的に間違っていた。でも、その半分の間違いに気づくのに20年以上の歳月と自分自身の精神疾患への罹患が必要だった。
10年近く頑なに決意を守り続けたあと、2000年に精神科に通わなければならなくなって、初めて弟の死をめぐる自分の感情に向き合い始め、それからまた10年近くかかってようやく治療のなかで本当の意味で語れるようになり、そしてさらに年単位の時間をかけて、やっと自分は実にたくさんのことを深く、深く後悔していたのだと認められるようになった。
弟の自殺は、確かにこの世の中で数限りなく起こっている出来事の一つ、ありふれたことだった。また、スティグマ化されるべきものでも、ロマンティックに語られるべきものでもなかった。
でも、私にとってはとてつもなく大きなことで、一生かけて向き合い、考え、抱えていくような性質のものだった。そして弟にとってもまた、ありふれた、よくある、しかし、命を絶つほどに苦しい状況だった。だから死んだ。
◇困難を外に出して初めてわかること
「支援とアート」というテーマで依頼されたこのテキストを、遠い過去の思い出から始めたことをどうか許していただければと思う。
精神障害や疾患、トラウマ、あるいは何と名指されなくてもさまざまな困難を抱えて生きる人(むろん私もこれを読んでいるあなたも含めて)の表現(注1)について考える時、あの夜、眠れぬ頭で必死に考えていた私が心から望んだことと、それゆえに誤ったことをどうしても思い出してしまうのである。
望んだのは、偏見やその裏返しとしての過度の空想化、ロマン化に陥らずに、目の前の出来事をとらえること。しかし、特別視を避けようとするあまり、そのことの個にとっての意味や重みを取り逃してしまった。振り返ればそれは、受けとめきれないほどの大きな衝撃のなかで、衝撃自体を否認するためでもあった。
あることの個にとっての意味や重みを測ることは、とても難しい。とくに、わけもわからないまま困難なことに巻き込まれ、すっぽり呑み込まれて、自らの内も外も区別できずに溶け込んでしまっている状態(注2)だと、それが大変なことだとまず本人がわからない。ただしんどい、苦しい、うまくいかないと感じるだけで、何がしんどいのか、何に困っているのか、その輪郭も中味もわからなければ、大変なことだと認識さえできないのだ。そして、大したことない、なんとかできない自分が悪い、等々と思ってしまう。
大変だとわかるには、困難に呑み込まれ溶け込んで内も外もわからない状態から、自分と困難を分け、困難を外に出して、眺め、それが何だかを知ることが肝要である。「外に出す」とは「表現する」ことであり、表現して初めて、眺めることが可能になる。このそれ自体、難しいことを一人でやり遂げるのは不可能ではないが、表現の受け取り手として、表現すること自体を触発し、可能にする他者の存在があれば、大きな助けになる。
私は、上に書いた通り弟の自殺を決して隠さないと決め、近しくない相手に時候の挨拶とほとんど変わらない調子で「ごきょうだいは?」と聞かれた場合でも、「弟がいたけど、自殺で死にました」とぶっきらぼうなまでに直截に答えていた。しかし、そこには一切の感情が伴っていなかったし、ほとんどの相手は絶句するので、話がそれ以上、進むこともなかった。
反対に感情があふれ出てきた時は、まったく言葉にならず、ただ号泣するしかできなかった。自身が治療を始めてからは、治療者たちや稀にそれ以外の人にそれなりに長く話すようになったが、やはりあまり感情が出てこなかったし、取り乱すこともなかった。
だが、5年前にグループセラピーで初めて、同じくセラピーを受けている数名の当事者を前に「弟は自殺した」と切り出そうとした時、それまでとはまったく違うことが起こった。言葉を絞り出そうとしても出てこず、治療者の助けを借りてなんとか話し始めると、自分でも驚くほどにどんどんと感情が湧いてきた。
そして、一通り語り終えた時には、身体が自分では支えられないほどぐったりと重くなっていて、椅子に座ったまま腰から二つ折りになり、前のめりにぐにゃりとくずおれてしまった。
弟の死をめぐる感情と言葉が、死後20年経って、初めて絡まり合った瞬間だった。そうして初めて、感情と言葉がつながることが、どれほど――身体が支えを失い、地の底に引きずられるように重くなるほど――大変なことだったのかを理解した。だから、感情と言葉を切り離さなければならなかったのだ。
これは、切り離して、なかったことにしていた感情を言葉とともに「外に出す」すなわち「表現」して初めてわかったことであり、その「表現」は受け取り手がいて初めて可能になった。それ以前に治療者たちを前に話をしていた時は、もしかしたら感情を置き去りにしたままでも了解してもらえると、言葉をただ投げ出して平気だったのかもしれない。
しかし、自分と同じような、それぞれに傷つきと痛みを抱えた当事者、すなわち仲間の存在を受け取り手として感じた時、ぺらぺらの言葉でも、感情の大爆発でもない、二つがつながった、不完全でも全体性を備えたものを差し出す、何か責任のようなものを私は感じたのではないだろうか。それで、それまであいだを塞いでいた見えない隔壁になんとか通路を開けて、感情と言葉をつなごうともがいたのだ。
この時、私は、自分の語りが十全に受けとめられたと感じたわけではなかった。20年間、ばらばらだった感情と言葉を途切れ途切れにつないで吐き出したのだから、受け取る方も受け取り切れなくて当然だっただろう。私にはすべてのエネルギーを使い果たしたような疲れと、何か違うという漠然とした苛立ちが残った。
しかし重要なのは、「表現したもの」がその場で丸ごと理解され、受けとめられることではなく、そのようにつないで「表現」として出す場がたとえ一度でもあったこと、そして、他者のいるその場の光景が自身の身体の感覚とともに記憶に残ることである。その記憶は、その後の「表現する」ことを支える拠り所となるだろう。実際、私はこの時をきっかけにして、弟の死をめぐるグリーフと本気で向き合えるようになった。
もちろん、苦しいことを外に出したからと言って、すぐに何かが変わるわけではない。でも、何度も言葉で、あるいは別のかたちで、表現しているうちに、抱えていたものをさまざまな角度から眺めることが可能になり、その輪郭や中味がおぼろげながらでも見えてくることがある。
そのなかに溶け込んでいる時は、その存在すら認識できなかった困難の大きさも、相変わらず圧倒されるほど巨大かもしれないが、つかめてくるだろう。苦しいこと、つらいこと、困りごとのサイズや輪郭や中味――個にとっての意味や重み――が見えてくれば、問題は解決しなくても息がつけるようになるし、対処の方法を探すことも可能になるかもしれない(注3)。
先にも言ったように、この作業を一人で行なうことは不可能ではない。ノートやPCに思いや考えを書き、読み直し、また書くというサイクルを繰り返して、目の前の問題や状況を整理している人は多いだろう。しかし、呑み込まれるほどの困難に直面している時は、やはり表現を可能にし、受け取り、ともに眺めてくれる他者の存在が重要である。自分を苦しめているものを表現することは、時に逃げ出したくなるほどの痛みを伴い、持てるエネルギーのすべてを奪っていくことだから、一人で続けるのはとてもしんどい。でも、伴走してくれる人がいれば踏みとどまりやすくなるし、それが仲間であれば、互いに支え合うことも可能になる。また、他者とともに眺めることで、一人では気づけなかったことに気づき、その発見がさらなる表現の動機になることもある(注4)。そして何より、人とのつながりの回復になる。
◇「アート」のジレンマと醍醐味
そのような表現の場や機会として機能し得るものは、制度的なものからそうでないものまで多様にあるだろう。精神保健の分野では、各種の治療セッション、自身の抱える苦労のパターンを仲間とともに研究し、解明していく「当事者研究」(注5)、自助グループのミーティングやわかちあいの会(注6)、治療枠組みでなく行なわれるさまざまな創作活動(注7)、アーティストとのコラボレーション(注8)などが考えられる。
私は偶然を含むいろいろな出逢いによって、主に治療セッション(サイコドラマ、アートセラピーを含む)と当事者研究、そして少しだけ自助グループに助けられてきた。でも、治療枠組みの外で行なわれる創作活動やアーティストとのコラボレーションの機会に出逢っていたら、そちらを表現の場や機会としていたかもしれない。しかし、そうした場や機会自体が多くは存在しないこともあり、残念ながら巡り逢えずにここまで来ている。
大切なのは表現し、それが受けとめられる場や機会があることである。今回のメルマガのテーマが「支援とアート」であることや、私自身が病気で離職する前は現代美術を専門とする学芸員であったことを考えると、他と比べた場合のアートの特殊性や優位性を強調すべきかと思うが、正直、ほどほどに機能している場や機会で、その時のその人に合ったものであれば何でもいいと考えている。一つひとつが違うし、一人ひとりも違うし、一人もつねに同じではないから、何が「よい」といった一律の解はない(注9)。
もちろん、アート(造形だけでなく文芸やパフォーマンスなども含めて)にはアートならではの特徴と強みがある。そのなかから本稿では、アートが他と大きく異なる点について二つだけ触れたい。
一つは、虚構、嘘が許されること。これは、「本当」のことを表現しなければならないというプレッシャーから当事者を解放し、遊びや工夫や一休みを可能にする。
もう一つは、展示や出版、公演などを通して、不特定多数に向けて表現を公開、発信できること。人や社会との接点を失いがちで、孤独感や疎外感に苛まれがちな当事者にとって、ふだん活動をともにしているコミュニティを超えた、より大きなコミュニティとの連絡の回路が開かれることには、さまざまなプラスの意味がある。
だが一方で、表現の受け取り手の幅が広がることによって、受け取り手とのあいだに距離の問題が生じることには留意しておく必要があるだろう。日頃、活動をともにしていればよく起こること、たとえば、誰かの一見とても些細な表現(ちょっとした仕草や表情の場合だってある)に、あれっ?と引っかかったり、おおっ!と感嘆したり、ワクワクドキドキしたり、じーんと胸を打たれたり、それによって自分の表現が変わったりといったことは、遠い受け取り手とのあいだでは起こりにくい(そうした瞬間こそ貴重でおもしろいのに!)(注10)。
むろん時間と空間を長く共有したからといって、一つひとつの表現の個にとっての意味や重みを感じ取れるようになるとは限らない。しかし、そこに至るプロセスやコンテクストを知らなければ、感じ取ることはいっそう難しくなるだろう。
ここに当事者の表現を「アート」として(注11)一般に公開する際のジレンマと、そしておそらく醍醐味がある。表現のプロセスやコンテクストに障害や疾患が深くかかわっている場合、一般の受け取り手はそれを知り、理解する必要があるだろうか? 障害や疾患に対する偏見やスティグマ、あるいは逆にロマン化された思い込みが、受け取り方を左右する可能性はないだろうか? 反対に、表現が偏見や思い込みを変えることもあるのではないだろうか? いやいや、そんなことは置いておいて、ただそれぞれの表現の個にとっての意味や重みを、同じく個として受け取りたいと願う人もいるのではないか? そうやって、弟が自殺したその夜に私が望んだこと、犯した間違い、両方が表現の送り手と受け取り手のあいだで、さまざまに変奏され、こだまするだろう。さらに、アートには「価値」や「評価」といった問題がつきまとう。優れている、優れていない? おもしろい、おもしろくない? アートの価値って? そもそも、アートとは、表現とは何? 送り手も受け取り手も自問することになり、議論が生まれるだろう。
◇「『何者』にもならなくていい」
最後に、ここまで書いてきたことすべてにかかわることとして、宮地尚子の『トラウマ』から、私自身がずっと支えとしてきた言葉を紹介して終わりたい。宮地は、トラウマを原動力としたアートの例を紹介したあとで、大事なのはトラウマから素晴らしい作品が出来上がることではなくプロセスだと述べ、同書をこう締めくくる。
「何者」にもならなくていいということ。それがトラウマからもたらされる想像力や創造性の帰着点です。そして、それがまた新たな想像力や創造性の原点となるのです。(注12)
私はこの言葉を、苦しんだ経験を「生かし」て、アーティスト、表現者という意味だけでなく、どんな意味でも「何者」かになろうとしなくていい、という呼びかけとして受け取りたい。
トラウマの文脈だとPTG(Post-traumatic Growth 心的外傷後成長)と言われるようなものを期待されるのは息苦しい。障害や疾患や困難を得て苦労したからといって、別に成長しなくてもいい。「よく」ならなくてもいい。嫌な部分、困った部分が残ったままでいい。ただ、抱えているわけのわからないものを何らか表現して、一息ついて、人や世界とどこかでつながって、生きていければいい。
そうすれば、もうちょっと表現を続けようかと――つまりは、自分とかかわり、世界とかかわることを諦めずに続けようかと――たとえ消極的にでも思えるようになる、かもしれない。それが表現することの帰着点であり、原点になると思う。
注
(注1)「支援とアート」というテーマは非常に大きく、かかわり得る領域も幅広いが、本稿では、私自身が当事者である精神保健関連領域の支援および自助活動に焦点を絞って書く。
(注2)これは、必ずしも障害や疾患や困難が他者から見て重度だったり、認知されやすいものだったりすることを意味しない。外から見て軽度だったり、名前のつかないことだったりしても、本人にとって非常に大きな困難になっていることはよくあるし、軽度だったり名前がなかったりすればこそ、あまりに当たり前の日常になってしまい、何だかわからないままに呑み込まれてしまうこともある。
(注3)北海道浦河町の主として精神障害をもった人たちのコミュニティ「べてるの家」では、よく問題は「解決」しなくても「解消」されると言う。べてるの家は、あとで述べる「当事者研究」の発祥の地であるが、当事者研究では、さまざまな困難を抱えた当事者が、仲間と対話しながら自らの苦労のメカニズムを解明していく。そして、研究を通して見出した苦労への対処法を「自分の助け方」と呼び、仲間たちの共有財産としていく。
(注4)私は「ともに眺める」ことの重要性を、数限りなく受けてきた治療セッションと当事者研究から学んだ。当事者研究における、ともに眺め、探究することの意義について、綾屋紗月と熊谷晋一郎は、「体験の一次データについては本人がいちばんよく知っていても、その解釈については本人がいちばんよく知っているとは限らない(中略)。そこで共に解釈作業に取り組んでくれる仲間の存在が必要になる」と表現している(綾屋紗月・熊谷晋一郎『つながりの作法――同じでもなく違うでもなく』NHK出版生活人新書、2010年、128-129頁)。
(注5)当事者研究については、注3および注4も参照のこと。
(注6)依存症のグループ・ミーティングや死別体験者のわかちあいの会など、さまざまなものがある。
(注7)精神科病院で行なわれている創作活動としては、たとえば、安彦講平が東京足立病院(東京都足立区)、平川病院(東京都八王子市)、袋田病院(茨城県久慈郡)で開催している「造形教室」などがある。
(注8)日本では近年、広く「コミュニティ・アート」あるいは「ソーシャリー・エンゲイジド・アート」などと総称されるようなアートの潮流がますます大きなうねりになっており、アーティストと多種多様なコミュニティとのコラボレーションの事例が増えている。とくに、東京オリンピック・パラリンピックを見据えて昨年、発表された「東京文化ビジョン」で、「障害者アートへの支援や障害者の鑑賞・参加を促す活動の推進等、文化の面でバリアフリーな都市として認知される取組の展開」が主要プロジェクトの一つに規定されたなどのこともあり、障害のある人とアートをつなぐ取り組みが盛んになっている。精神障害や疾患の当事者とアーティストのコラボレーションも行なわれている。
(注9)ただ、日本の精神科医療を取り巻く現状において、ほどほどに機能している場や機会で、その時のその人に合ったものに辿り着くのは易しいことではなく、私自身もかなり彷徨ったことを付記しておく。
(注10)日々の活動のなかで生まれる、そのままでは消えてしまいがちな味わい深い表現を、見て触れるかたちにして幅広い受け取り手に届けることに成功した興味深い事例として、東京都世田谷区の就労継続支援B型事業所「ハーモニー」の「幻聴妄想かるた」がある。医学書院から『幻聴妄想かるた』(2011年)、ハーモニーから『新・幻聴妄想かるた』(2014年)が出版されている。http://www.geocities.jp/harmony_setagaya/index4.html
(注11)美術の領域では、プロセス自体を「アート」として提示することは1960年代から始まっている。日常の些細な表現や協働のプロセス、人と人との関係性など、通常はコミュニティの内部に留まっているようなことも、「アート」ととらえ直すことで広く社会に向けて提示することが可能になる。
(注12)宮地尚子『トラウマ』岩波新書、2013年、251頁。
*『α-Synodos』vol.193(特集:支援とアート)、2016年4月1日より転載
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
