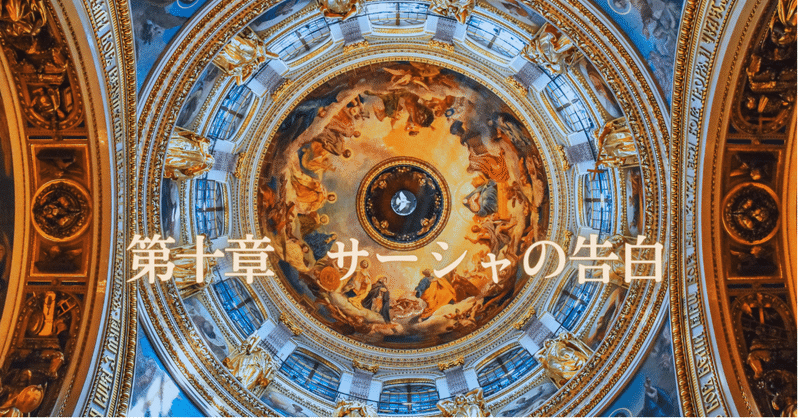
青の緞帳が下りるまで #32
←(前回)「青の緞帳が下りるまで #31」(サーシャの告白 1)
サーシャの告白 2
それからほどなくして、私は鏡の館の音楽家に連れられ、王室劇場にも行けるようになった。同じく王宮の内部にある劇場の建物は、鏡の館からそう遠くないところにあった。
私は誰かの親戚の子ということにされていた。裏口の門から関係者通路を通って中に入り、階段を上る。天上桟敷に空いている席があれば、そこに自由に座ることができた。
アルトランディア王国の青を基調とした六層の馬蹄形の王室劇場。そこは王侯貴族の社交場であり、そのチケットは庶民にとって高値の花だった。青い幕が上がると、そこにアナイ・タートの恋焦がれる舞台があった。
有名な歌劇も何度か見ることができた。舞台はおもしろかったけれど、ほんの少し、がっかりもした。アナイ・タートの歌ばかり聞いていた私は、最上のものを知ってしまったがため、不幸にも誰の歌を聞いてもいいと思えなくなっていた。
舞台を知れば知るほど、アナイ・タートが舞台に立てないのが不思議でたまらなかった。
なぜヤローキンは彼女を放置したままなのだろうか。性格に問題はあっても、彼女ほどの歌手はこの国最高峰と言われる王室劇場にもいないというのに。
劇場の話をすると、アナイ・タートの顔が曇るので、見たもの聞いたものはすべて胸のうちにしまっておいた。
私の音楽教育が始まると同時に、アナイ・タートの生活にも変化が訪れた。王女の声楽教師の仕事依頼が入ってきたのだ。
ニコライ十世の一人娘アナスタシアは我儘で手のつけられない王女として有名だった。
リトヴィスの後ろ盾を傘に来て、父王すらも意のままに操り、家庭教師として派遣された名のある音楽家を悉くクビにしてきたという。
「とにかく王女の教師陣は手をやいているということだった。きみさえよければ、推薦するけれど?」
ヤローキンの話にアナイ・タートは懐疑的だった。これまで鏡の館の外には一歩も出られなかったというのに――。憮然とした彼女の顔に、感情の揺れが見えた。
「……本気なの?」
アナイ・タートのその言葉には、アルトランディア人の自分が王女の家庭教師になってもいいのかという危惧もあったようだった。
ニコライ十世の治世は外の世界ではリトヴィスの傀儡政権と称されていたようだが、私には政治のことはよくわからない。鏡の館の住人はすべてアルトランディア人だったから、その風潮はあまり感じられなかった。
国王とリトヴィス王女ソフィアの結婚後、王宮の共通語はリトヴィス語になったというのは、王宮勤務の住人から聞いていた。本来、アルトランディア語が流暢に話せないソフィア王妃のための措置のはずが、王妃が亡くなったあともそのシステムは継承され、今ではリトヴィス語が王宮勤務に必須とされていた。常にリトヴィスの人間に取り巻かれたアナスタシア王女がアルトランディア語を話さないからとも言われていた。
王宮ではリトヴィスの人間を重用し、アルトランディアの人間でリトヴィス語ができないものは遠ざけられた。鏡の館の住人の中でも王女の家庭教師の依頼を受けたものもいたが、リトヴィス語が話せないという理由で任を解かれた。
アナイ・タートのリトヴィス語力は日常会話程度だった。語学以上に彼女には性格的な問題があった。
「とにかくアルトランディア王国内にほかに教師が見つからないのだよ。十一歳の誕生日を迎えた王女には異性の家庭教師は相応しくないという声もあり、女性教師が求められている。女性の人材は少ない。きみは亡き王妃と面識があったから、リトヴィスの連中もきみをむげには扱わないと思う」
ヤローキンの話では、王室側も王女の教師すべてをリトヴィスの人間にするのだけは止めたいという意向だったようだ。
紆余曲折あったが、最終的にヤローキンが国王印の入った任命書を携えてきたことで決着がついた。権力に阿ることのないアナイ・タートが教師の職を引き受けたことは少し意外だった。
週に一度のレッスン場所には王宮と鏡の館の間に設けられた東屋が指定され、そこにピアノが運び込まれた。かくしてアナイ・タートは週に一度とはいえ、一時間ほど、鏡の館から出られる許可を得たのだった。
気まぐれなアナイ・タートに教師がつとまるのか鏡の館の住人たちは心配していた。それも相手は王女。何か粗相をしでかしたら、一大事になる。皆親身になり、王宮でのマナーをアドバイスしたが、アナイ・タートは取り合わなかった。リトヴィス語の勉強もしなかった。
「私は声楽を教えに行くのですから」と彼女は毅然と言った。
***
皆の不安は杞憂に終わった。アナイ・タートの初授業、なんとアナスタシア王女は五十分間、一度も席を立たなかったという。
「一体、どういう魔法を使ったんだい?」
皆からの詰問にアナイ・タートは答えなかった。あとでヤローキンが教えてくれたところによると、アナイ・タートは王女を無視して、一方的にソロリサイタルを行ったらしい。
「いい音楽を聴くのも勉強です」
歌いきって満足したアナイ・タートはそう言い放つと、挨拶もろくにせず、王女のもとから去ったと言う。
「あの石造りの東屋は天井が高くて音響効果がすぐれているのよ。気持ちよかったわ」
帰ってきたアナイ・タートは珍しく饒舌で、鼻歌まじりに部屋に上がっていった。
絶対クビになると誰もが思ったが、アナイ・タートはその翌週も、また翌週も、鏡の館から出て行った。
「アナイ・タートにあのわがままな王女の相手がつとまるとは思わなかったね」
「わがまま同士、うまがあうんじゃないの?」
皆は勝手なことを話し合った。
一流の芸術家が一流の教師になれるかといったらそれは別の話。そう言ったのは鏡の館の古参、画家のイェグレスだった。
彼は物心ついたときから絵を描いていたらしい。夢中になると寝食を忘れ、筆を握っていた。彼はまともな人物画も描けるのに、なぜか馬の頭の中に人間が入っていたり、骸骨を踏みしだく半人の猫とか奇妙奇天烈な絵ばかり描いていた。
「目に見えるものを目に見えるとおりに描いて何が面白い」というのが彼の口癖だった。
王立芸術学校に通っていたそうだが、そこで彼の絵はほとんど評価されなかった。
たまたま先代国王の目に留まり、外国の展覧会に出したところ、大絶賛を受けたことが鏡の館の住人になる契機となった。その異様な絵には、独特のグロテスクさに顔をしかめつつも、やはりもう一度見たくなってしまう。不思議な魅力があった。イェルグレスはまた、「いかに美しい青を表現するか」という課題を自らに課し、キャンバスを黒一色で塗りたくっていることもあった。その感性は教えられて生まれるものではなかった。
詩人のナルスルもそうだった。何か話すときに韻を踏まないと気がすまない病人のような息子をもった彼の母親は「教師をバカにしている」と何度も学校から呼び出しを受けたらしい。彼の国語の成績も下から数えたほうがはやかったそうだ。その彼は常人ではまず思いつかない言葉や表現を次々と生み出していった。彼にとっては鏡の館の粗食が芸術を生み出す原動力になるらしく、よく空腹で行き倒れになっていた。惚れっぽい性格で男女問わず、すぐに人の美点を見出すことができ、恋に落ちてはすぐ破れ、そこから珠玉の作品を生み出していた。
ヤローキンに頼まれてヤローキンの曲に歌詞をつけることもあった。その言葉は不思議と旋律にぴったりとおさまるのだった。
ヤローキンの歌曲が世間に広まるきっかけとなったのは彼の功績も大きい。
ニコライ十世はひとつ所に集めた一流の芸術家を師に、王室の人間の教養をつけさせようとしたのかもしれないが、その試みが成功したとは言いがたかった。
アナイ・タートもよく言っていた。
「学問にしろ、芸術にしろ、人に強要されてうまくなるものじゃない。歌がうまくなりたかったら自然と繰り返して自分が納得するまで練習するものよ。自分がイメージする場所に到達できるように」
一流の人たちは一流の目を、一流の耳を持っていた。その遥かなる高みを見据え、そこを目指してそれに見合う努力する。
目測を見誤ったり、努力に裏切られたりすることなど、この人種にはありえないのだった。
それを考えれば、鏡の館の住人の中で私だけが平凡な人間だった。
もちろん、だからこそ皆から可愛がられたのかもしれないが、皆の話を聞きつつ、そのスケールの大きな話に聞き入ることしかできなかった。ピアノの練習は続けていたけれど、周りの人たちのレベルが高すぎて、自分が上達しているのか、下手になっているのかもわからなかった。
あれは一年前のことだった。
「アーサス、遣いを頼まれてくれないか?」
コックに言われ、私はピアノの蓋を閉じた。
材料が切れそうになると、王宮の厨房まで注文に走る。そのついでに鏡の館の住人の郵便物を取りにいき、屋敷の主人への定期連絡もしなければならない。用は山積みだった。
その日は朝から雨が降っていた。ぬかるんだ庭園を突っ切って王宮の建物に行きたくはなかった。それでルートを変え、石畳で覆われた東屋を経由して行くことにした。
東屋に近づくと、建物の中から椿姫の「乾杯の歌」が聞こえてきた。美しいソプラノの声はアナイ・タートに違いなかった。彼女にしては珍しい選曲だった。そういえば王女とのレッスンがあったと聞いていたけれど、時間的にはレッスンはとっくに終わったはずだった。
一人で残って歌っているのだろうか。もしかしたら、雨が降ってきたので雨がやむまで東屋に居残っているのかもしれない。
そのとき私は傘を一本持っていた。だから何も考えずに東屋に足を向けた。
扉を開けた瞬間、険しい顔をした二人の女官に行く手を遮られた。
「何者か!」
リトヴィス語だった。
踵を返そうとしたが遅かった。リトヴィスの警備兵まで飛んできた。
「厨房の使いで……アナイ・タートに用があって……」
知っている限りのリトヴィス語を駆使して説明したけれど、恐怖におびえる私の説明は要領を得なかった。アナイ・タートの名を告げても、彼らには通じなかった。
ふっと歌が止んだ。アナイ・タートに説明すれば助けてくれるかもしれない――。
私は顔を上げ、靴音がする方向を見据えた。
私に近づいてきた影は、アナイ・タートではなかった。
「何なの、騒がしい」
相手は子供だった。背丈は私と同じくらい。黄金の長い髪をリトヴィス風に結い上げ、薄桃色のドレスを着ている。一目でわかった。彼女は――アナスタシア王女だ。
眉を顰め、不機嫌そうな顔をした彼女は、その澄んだ青い目で女官を睨みつけた。女官たちは反射的に頭を垂れ、私もそれに倣った。
「……子供?」
自分もまだ子供なのに、王女は大人びた口調で私に言った。
「ふーん」
王女は私の顔を上げさせると、じろじろと眺めた。リトヴィスの血を引いているのに、彼女の目はアルトランディア人のように青いのだと私は頭の片隅で考えていた。
「ごめんなさい、アナイ・タートが歌っているのだと思ったんです。それでてっきり……」
「服装からして王宮の下働きのようですが」
リトヴィス人の女官が王女に告げた。
私はアナイ・タートが出てきて私を助けてくれるのを待った。だがアナイ・タートはいつまでたっても出てこなかった。それで私は知った。今しがた、歌っていたのは王女だったのだ。
信じられなかった。声質はまるで同じ。ちょっとした間の取り方、ブレスにいたるまで、王女はアナイ・タートを正確に模倣していた。
「さて、どんな罰を与えたらいいかしらね」
王女はにっと私に笑いかけた。
「これ、弾きなさい」
王女は持っていた譜面をひとつ、私に投げてよこした。伴奏譜だった。
「弾けたら、許してあげる。弾けなかったら……」
王女の言葉に女官たちが顔色を変えた。その表情からして、ただならぬ罰が待っているのは想像できた。
しかし、私は皆がおそれるアナスタシア王女に対してそれほど恐怖心を抱かなかった。我儘な人間はアナイ・タートで慣れていた。
伴奏譜は――。ヤローキンの楽譜だった。
原曲ではない。アリアだけ抜粋して誰かがピアノ伴奏曲用に手を加えたものだった。ざっと見て、こんなにピアノにうるさく弾かれたらアナイ・タートが怒りそうだと思った。オーケストラの音を追っているのだけど、歌を生かすなら、もっとシンプルにした方がいい。
「この譜面通りには無理だけど、多分、できると思います……」
王女は私をグランドピアノの前に座らせた。手入れの行き届いた、いいピアノだった。
楽譜のテンポはアンダンテだったけれど、もう少し落としたほうがいいと思った。その方がゆっくりと気持ちよく高音をのばすことができる。ルバートをかけてもいい。
弾き始めた私にアナスタシア王女は少し驚いたようだったが、すぐに楽譜に視線を移し、一呼吸おいて歌いはじめた。
歌声はアナイ・タートによく似ていた。だけど落ち着いて聴いてみると、やはりアナイ・タートとは違っていた。いい声はしているけれど音程はふらふらするし、息切れがする。それでもヤローキンの曲調をよくとらえていた。
世間一般レベルからすると、十歳そこらでこれだけ歌えると、神童やら天才呼ばわりされるのかもしれない。私は不幸なことにアナイ・タートの声しか知らなかったから、どうしても粗が見えて仕方がなかった。
「……おかしいわ。私はこんなに下手なはずじゃないのに」
演奏を終えたとき、王女は真っ赤な顔をしていた。
「お前が勝手にテンポを遅くするから、とちってしまったじゃないの!」
完全な言いがかりだった。「恐れながら――」と口を開きかけた私の頬に強烈な衝撃が振ってきた。一瞬、何が起きたのか理解できなかった。私は椅子から転げ落ちていた。
王女に張り手で殴られたのだった。
王女は鼻息荒く、その部屋から出て行った。
「消えなさい。大嫌いよ! お前の顔など、見たくない!」
王女がいなくなった後も、私の頬には激しい痛みが残った。
なるほど、皆が言ったとおり、きまぐれな王女だった。
けれど、痛みや驚きより、無事解放されたことへの安堵感が強かった。
ただ王女との偶然の遭遇は誰にも話せなかった。叱責を受けるのが怖かったというより、一刻もはやくあの一件を早く忘れたかったからだった。
それが翌日あっさりとばれてしまった。
「王女がアーサスをさがしているらしい」
ヤローキンが溜息交じりに私に告げた。
「声楽のレッスンにピアノを弾ける子をつけてほしい」とアナスタシア王女が父ニコライ十世に直訴したらしい。
断ることはできなかった。ヤローキンの手には国王直々の任命書があったからだ。
ヤローキンは、青ざめ、口のきけなくなった私を前に、さらに話を続けた。
王宮の規則で、同じ年頃の異性の同席は許されない。王女にお気に入りができたというだけで一大事なのだから――と。
→(次回)「青の緞帳が下りるまで #33」(第十章 サーシャの告白 3)
ありがとうございます。いただいたサポートは活動費と猫たちの幸せのために使わせていただきます。♥、コメントいただけると励みになります🐱
