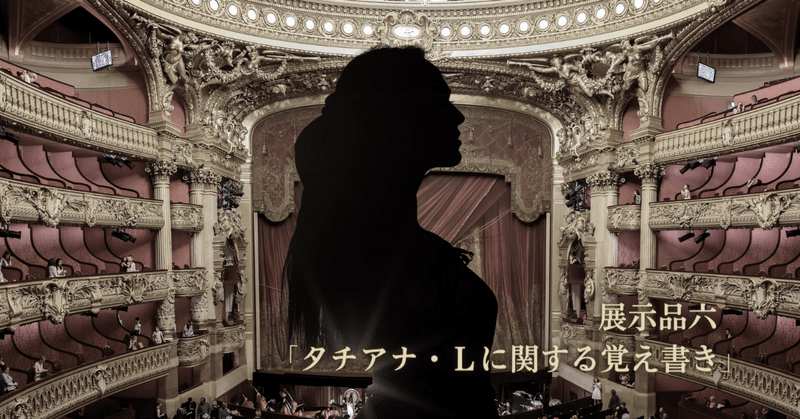
青の緞帳が下りるまで #25
(前回)「青の緞帳が下りるまで #24」(第六章「タチアナ・Lに関する覚書」 1」)
第六章「タチアナ・Lに関する覚書」 2
彼女はコネがまかり通っていた音楽院に新風を巻き込む存在でした。彼女を担当したのはヴィシュニコワ先生です。
徹底的に基礎を叩きなおす先生の授業にタチアナが姿を見せることはありませんでした。
なぜか器楽科やピアノ科の授業には真面目に出ていたようです。「自分に足りないものを補う」ために。
語学の授業にも熱心でした。そこで驚いたことは、彼女はドイツ語もイタリア語もほぼ初心者同然だったということです。歌の発音は完璧だったというのに。
葬式でもないのに全身黒ずくめ、バレリーナのようなお団子頭の彼女は、学生たちの間で「黒いバレリーナ」の渾名がつけられていたようです。
校内をいつも不機嫌そうな顔をして、首のショールをなびかせながら、颯爽と歩いていました。そんな彼女に話しかける隙はなく、まわりからは変人だと思われていたようです。
週に一度の私の音声学の授業にも、遅れてくることがしばしばで、指名してもろくに答えようとしませんでした。
一年の前期で、単位はほとんど取れていませんでした。いくら実技がよくとも、単位が足りなければ卒業はできません。
今にして思えば、彼女は卒業する気などさらさらなかったのかもしれません。彼女の目標は音楽院卒業ではなかったのですから。
タチアナは、静かにチャンスを待っていたのです。
いつだったか私は彼女を呼び止め、聞いたことがあります。
「どうして音楽院に入ったの?」
「ここの出身でなければ、青の緞帳の舞台に立てないからです」
青の緞帳――というのは、王都にある王室劇場のことです。
当時、王室劇場の歌手は王立音楽院の卒業生に限られていました。幅広く応募者を募っていましたが、音楽院出身者以外は、実技オーディションを受ける前の段階、書類選考で落とされてしまうのです。
タチアナの言うとおり、音楽院出身であることが舞台に立つ手っ取り早い方法でもありましたが、タチアナの言を聞き、私はまた一つ、おそろしく思いました。もしかしたら音楽院と王室劇場のなあなあな関係のシステムは、今までタチアナのような才能をどんどん斬り捨ててしまっていたのではないかと――。
芸術と音楽教育を誇るこの国では、全国各地に王立音楽院付属音楽学校があり、十歳までに才能を見出された子供たちに無償でエリート教育を受ける制度が確立されていました。しかし、その制度の最大の問題点は、十歳から十六歳までの者に対する入学試験を行っていないことでした。
では、タチアナのように音楽学校に入学する年齢を過ぎ、自発的に歌手になりたいと思った子はどこで教育を受ければいいのでしょう。選抜試験の年齢制限を超えてから、才能が開花する子供だっていたでしょうに。
たいていの親は子供が十歳で音楽学校に入れなかった時点で諦めます。この国の人間ならば、誰でも一度は音楽を志したことがあり、最後まで到達するのが難関であることを理解しているからです。到達できぬ夢ならば、最初から諦めてしまったほうが子供にとって幸せと考える親も多いのです。
諦めきれずに自己流で続けるものもいましたが、あくまでも趣味の範囲にすぎず、専門家になることはほとんどありませんでした。一般的にこの国の人間は音楽院出でない音楽家を見下す傾向にあるからです。
音楽学校出身でもないタチアナは、どこかで正規の教育を受けていました。それが、彼女がどこかの貴族の縁の人間ではないかと思われた所以でした。
実際のところ、それが真実かどうかはわかりません。彼女の慎ましい生活ぶりと貴族出身という噂はどうしても結びつきませんでした。入学の際、音楽院に多額の寄付金があったという事実もなかったようです。
作曲家ヤローキンがどこで彼女を発掘したのかはわかりませんが、彼一人の力でタチアナを教育したとも考えにくいのです。初歩の音楽教育を施した可能性は高いですが、ヤローキン自身は歌い手ではありません。きっかけはヤローキンにしろ、タチアナの入学は彼女本来の素質と努力で勝ち取ったものです。
タチアナほど目的意識のはっきりした子はいませんでした。舞台に立つために彼女は考えうる最短コースを邁進していったのです。
タチアナが入学して三カ月経った頃、新年の音楽祭がありました。
オペラの舞台で、一年生にも合唱の配役が割り当てられました。音楽院卒業生の作品を持ち回りで上映するのです。その年はヤローキンの年にあたっていました。
オペラ実技の授業でその合唱練習があったのですが、タチアナは練習をすべてすっぽかしました。王室劇場のオーケストラとの合同練習にあたり、やっと出てきたわけです。それも大遅刻を悪びれもせず。
四年生のクセニアがその態度を詰問したといいます。先輩に対する態度もなっていない、遅れてきたことも詫びもしない、皆に迷惑をかけたのだと皆の前でタチアナを叱ったそうなのですが、タチアナを庇うものはいませんでした。かくいうタチアナは馬耳東風でしたけれど。
見かねた音楽監督が「練習に差し支えるからその辺で」と止めにはいったとき、タチアナはあろうことか彼に直談判したのです。
「私は合唱に向きません。主役をください」
端役ではなく、主役をくれと――。
皆が世間知らずのタチアナに呆れ顔を向けました。音楽院では一番下の学年は合唱や雑用、役がつくのは上の学年になってからというのが常識です。
思い上がった編入生を誰かが説き伏せ、「一年生は合唱だから」と合唱の列に並ばせました。それも彼女が持っていた楽譜を奪い取り、「それだけの大口が叩けるのだから、合唱パートも全部暗譜しているのだろうね」と意地悪さえしました。
二幕の一場。教会で主役のマリアが不実の懺悔をするシーンでした。そのアリアは技巧がちりばめられた作品で、クセニアはこれを歌えるようになるまでそれこそ血のにじむような努力をしてきたことを皆が知っていました。そうして彼女はソロを勝ち取ったのです。彼女のソロを聴けば、この思い上がった一年生も考えを改めるに違いないとその場の人間は思っていたようです。
オーケストラの前奏のあと、合唱隊の賛美歌が始まるのですが、その中から一筋、あきらかに異質な声が混じっていました。合唱にあわせて声量は落としてあるのに、そのソプラノの一人の声だけが悪目立ちするのです。
思わず、皆目でその歌い手を探しました。
信じられないほどの美しい声に、指揮者は演奏を中断することができませんでした。
気がついたときには、誰もクセニアのアリアを聴いていませんでした。声量があるのは彼女の方です。なのに耳に入ってくるのは彼女の背後で歌う合唱隊のタチアナの声ばかりなのです。
「ああ、合唱隊、悪いがもう少し抑えてくれないか」
指揮者は的外れな指摘をしました。どんなオーケストラの大音量の中でも彼女の透き通る声だけはまっすぐ届いてくることを知らなかったのです。
「合唱に向かない」といったタチアナの弁は間違っていませんでした。何度そのシーンを繰り返しても、タチアナの声は周りから浮き上がってくるのです。タチアナをはずした方が合唱隊としてのまとまりはよくなります。しかし彼女をはずす決断はしかねました。一番うまいのは彼女で、その声質は賛美歌にふさわしいもので、文句のつけようがなかったからです。
学生たちも動揺を隠せなかったようです。思えば、これまで誰もタチアナの歌をまともに聞いたことがなかったのです。
騒然とする舞台をとりまとめたのは王室劇場の副指揮者です。このオペラの舞台監督を任されていました。
「きみ、タチアナと言ったね」
名前を呼ばれ、タチアナは憮然とした顔で一歩前に出ました。「自分が間違っていると言われるのは論外」という表情でした。
当然です。タチアナは一音も間違っていません。ただ、異質だったのです。
舞台のクセニアは狼狽していました。
副指揮者は「きみはマリアのソロを歌えるのかい?」とタチアナに笑顔で訊ねました。
彼の表情は興奮を隠しきれていませんでした。タチアナは昂然と頷きました。
副指揮者の発案はちょっとした好奇心のなせる業だったのでしょう。「彼女が歌ったらどうなるのか、本当に歌えるのか、見てみたい」という。
クセニアの自尊心を思えば、そこにいた私はそれを止めるべきだったのかもしれません。しかし、私も編入試験以来、ろくに聴いていなかったタチアナの歌をもう一度聴いてみたかったのです。あのとき聴いたあれが、幻でなかったのならば――。
「クセニア、悪いがちょっと黙っていてもらえないか」
副指揮者の指示はクセニアにとっては屈辱だったでしょう。ほかの学生にしてもです。
下積み生活の長い彼らの晴れの舞台。一番の主役に、無名の編入生が抜擢されようとしているのですから。
オーケストラとの音合わせは初めてでありながら、タチアナは出だしを間違えませんでした。彼女の辞書に緊張とか物怖じするとかそういう精神状態を示す言葉はないのでしょう。
劇場にいた人間は全員、舞台上のタチアナに釘付けになりました。
細く華奢な体から舞台中に溢れる美声。
音楽神《ミューズ》の申し子のような声。
そして彼女一人の声で、オーケストラも合唱隊もレベルを引き上げられたのです。
練習だからと手を抜いていた一部の団員も目を覚ましました。指揮者も細心の注意を払い、音楽を完成させました。彼女の歌に引っ張られるように。彼女の音楽性を壊さないように。
驚嘆すべきは彼女がいかに言葉を大事にしていたかということです。その音楽にのせられた言葉が神からのメッセージのように、胸に染み渡るようにおさまっていくのです。
声を張りあげるあまり、おろそかになる言葉は一つもありませんでした。
圧倒的な音楽に溺れることもなく、溢れる音の中で、彼女はバランスを保ち続けました。恐るべき精神力でした。
それまで私は正直、ヤローキンという音楽家の作品をそれほどいいと思っていませんでした。もちろん、自分が作れない音楽を作るという点では天才と認識していましたが、彼はちょっとしたフレーズにも必ず技巧をちりばめ、曲を難解にするのです。自分の力をひけらかさんばかりに、新しい音を入れる。でも、それは必要だったからだとわかりました。
彼女の歌を聴き、必要なだけ音はあり、必要なだけ装飾を入れているのだと。
ヤローキンが紛れもなく偉大な音楽家であったことを再認識した一日でもありました。
当時、あの場所にレコーディング機械がなかったことが悔やまれてなりません。
最後のパッセージを高らかに歌い上げた彼女に、副指揮者のブラボーの声が上がりました。オーケストラ団員からの絶大な拍手。
私たち教師も思わず手を叩いていました。つられて彼女に反感を持っていた学生たちも。
タチアナは驚きもせず、喜びの顔も見せず、やはり当然といった面持ちでした。拍手が鳴り止まなかったので、彼女は前に進み出て、優雅に礼をしました。
この国から、一人の歌手が生まれたこと、その誕生の場に居合わせたことに私は感謝しました。
この興奮と拍手は彼女の時代を予期していました。彼女は何年にもわたり、この国に君臨するオペラ歌手になると。
ところが、その年の音楽祭にタチアナの姿はありませんでした。
やはり一年生を主役に抜擢することはできなかったのです。音楽監督と舞台監督の二人が抗議しても、音楽院の規則を覆すことは不可能でした。
配役に変更はなく、合唱隊の中に彼女の姿はありませんでした。クセニアは素晴らしく上手に歌い、観客席から惜しみない拍手が送られましたが、タチアナの完璧な歌を聴いてしまった人間は物足りなさを感じました。
それはクセニア本人もでした。その後、王室劇場の専属歌手となり、海外公演に出た後亡命したクセニアは、西欧で長くにわたって活躍するのですが、その生涯においてこのアリアを歌うことは二度とありませんでした。
冬季休暇に入り、私がユヴェリルブルグの叔母の家に行ったのも何かの運命だったのかもしれません。
「うちの教会区の聖歌隊のレベルはおそらくアルトランディア一だよ」
叔母が何かと話の種にするユヴェリルブルグ聖歌隊の話を私は眉つばで聞いていました。誰でも身内びいきになるものです。叔母は音楽を嗜みますが、音楽院の出ではありません。ちょっとうまいくらいの子を素人は絶賛するものです。
叔母は渋る私を教会の礼拝に引っ張り出しました。その聖歌隊はなるほど、地元では評判だったようで、教会区外の人間も聴きにきていたほどでした。私はすぐに出られるように扉の近くに立ち、聖歌隊の歌を待ちました。
一声聞いてすぐにわかりました。
そこで歌っていたのがタチアナでした。
「あの子、王都に越したらしいんだけど休暇で帰ってきたんだよ。なかなかだろう?」
叔母の言葉に私は苦笑しました。なかなかどころか、音楽院で彼女の上をいく歌手はいないのですから。
叔母の家に行くのを渋っていたことを悔やみました。もっと早く来ていれば、ヤローキンより早く彼女を発掘できていたかもしれないのに。
そこで、私は彼女について多くのことを知りました。貧しい家庭の出であること、音楽院卒の音楽教師についていなかったため、音楽学校の推薦入試を受けられなかったこと。
事実、ユヴェリルブルグの聖歌隊のメンバーのレベルも高かったのです。そのままコンサートを開き、お金をとれるくらいに。
これだけの人材が国境の街に埋もれていたことも衝撃的でした。
教会から出てきたタチアナは、私がいたことに少し驚いたようでしたが、会釈をして通り過ぎていきました。ヤローキンに会ったときに、どういう経緯で彼女を発掘したのか聞かなければと思いました。彼女に正規の音楽教育を施したのは、彼だったでしょうから。
年に何回かは音楽院に現れるヤローキンはその年に限って姿を現しませんでした。
新国王ニコライ十世の即位記念式典の作曲に追われ、王宮に閉じこもっているのだろうという噂だけが飛び交っていました。
年明けの三月のことでした。
記念式典のヤローキンの献呈曲の歌手の一人にタチアナが大抜擢され、話題になりました。練習を見にきていた、あの副指揮者が推薦したのだそうです。
これまで音楽院の卒業生が王室劇場の舞台に立つことはあっても、新入生、それも合唱や脇役ではなく独唱での出演は、異例中の異例でした。一体どんなコネクションを使ったのかと取りざたされましたが、彼女の歌唱力を見せつけられた人間たちは、実力でもぎとったものと確信していました。ヤローキンの名を借りて入学してきたとはいえ、彼女の実力は本物だったのですから。
記念式典で彼女が歌った「国王賛歌」は大成功をおさめました。観客総立ちの上、感激した新国王ニコライ十世とソフィア王妃は直々に彼女を祝福したそうです。
その場面に遭遇した、音楽院唯一の招待客である音楽院長は、居並ぶ貴賓来客から賛辞を受け、ほくほくと帰ってきました。
音楽院声楽科の教師としては複雑な立場でした。音楽院の在校生という肩書きであるため、タチアナの華々しい活躍は望むところでしたが、実際の彼女はほとんど授業に出ていなかったのです。
前途洋洋に思えたタチアナでしたが、その後、突然授業に来なくなりました。再三の通告にも返信はなく、除籍しなくてはならないことになったのです。
「王室劇場の舞台に立つために」彼女は音楽院さえも踏み台にしたのではと思いました。
訪ねていっても、彼女が住んでいた下宿先には既に別の人が住んでおり、一切の足取りが掴めなくなってしまいました。彼女ほどの子を失うのは、損失でした。彼女がいなくなった理由を知ることはできませんでした。
それから間もなくして、音楽院でタチアナ・Lに関する緘口令が敷かれたのです。音楽院での彼女の記録はすべて抹消されたと聞きます。
誰かが囁きました。「彼女は王宮の後宮に上がったのではないか……」と。
それは考えにくいことでした。当時、ニコライ十世はリトヴィス人の王妃を迎えたばかり。リトヴィスが目を光らせている中、愛人を膝元にあげることは不可能でした。
今でも惜しまれるのは、ユヴェリルブルグの教会で彼女に会ったとき、どうしてもっと話をしなかったのかということです。
あれが、私があの黒いバレリーナを見た最後だったのです。
***
ニコライ十世即位記念式典に出席したロシア大使の覚書(回想録より抜粋)
祝典で、ものすごい歌手に会った。
華奢な体型。長身。黒い細身のドレス。
私は音楽の良し悪しはわからない。あくびをこらえているのが精一杯だった。彼女の歌がはじまったとき、ようやく目が覚めた。
信じられない美声だった。本国にもこのような声をもった歌手はいないだろう。
「王の御世に栄光あれ」
全世界が国王に祝福するような、説得力のある歌だった。感激した国王は立ち上がり、拍手した。隣席の王妃はより一層興奮していた。そうしてもう一度、今の曲を演奏するように命じた。彼女の独唱のあとに合唱が続く。「王の御世に栄光あれ」
わかりやすいフレーズで、その場にいる全員が唱和した。あの夜の興奮は今でも忘れられない。国王と王妃は退出前にその歌手を呼び寄せた。
「あなたのような歌手がこの国にいたことを誇りに思う」
「王室劇場で歌うのが夢だったのです」
「夢が叶ったのですね」
「はい」
国王夫妻と歌手のやり取りは短かった。
歌手の名前を聞きそびれたことが悔やまれてならない。
→(次回)「青の緞帳が下りるまで #26」(第七章 キリル・シェレメーチェフの追想 )
ありがとうございます。いただいたサポートは活動費と猫たちの幸せのために使わせていただきます。♥、コメントいただけると励みになります🐱
