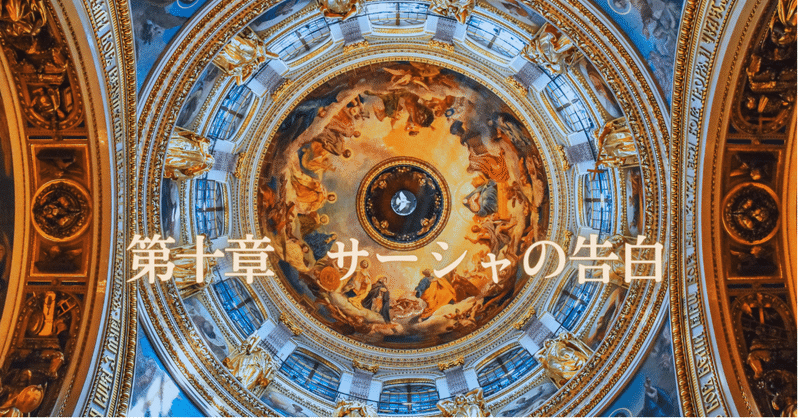
青の緞帳が下りるまで #035
←(前回)「青の緞帳が下りるまで #32」(サーシャの告白 4)
サーシャの告白 5
次の瞬間、私はアナスタシア王女の部屋にいた。アルトランディア人の立ち入りが禁じられている彼女の私室に。
王宮の内部もほとんどの者は劇場に向かったのか、兵も手薄だった。女官が二人、アナスタシア王女の着付けと仕度に残っているだけだった。
「殿下、急いでお支度を。もう式典は始まってしまいましたよ」
女官はリトヴィス語で王女に言った。
「遅れるのはいつものことよ。どうせアナスタシアは母親似で病弱ってことになっているんだから、病気を口実に遅刻したって平気よ。むしろ、遅刻魔の私が時間通りに到着するほうがおかしいわよ」
そうだった。王女は彼女を産んですぐに亡くなったソフィア王妃同様、病弱で式典にもなかなか顔を出さないと言われていた。その皆が思っているアナスタシア王女像と、実際のアナスタシアは大きくかけ離れていた。王女は顔色もよく、見るからに健康そうだった。
なぜ、世間ではアナスタシア王女のことをそう思っていたのだろうか。
「殿下、この子は何者なんです?」
突如、私は女官に腕を掴まれた。この女官と顔を合わすのは初めてだった。王女の私室に入ってきた小姓姿の私に女官は不信感を隠さなかった。
「ああ、この子にその衣装を着せてやって」
「殿下!」
叫んだのは私と女官、同時だった。
アナスタシア王女が指差したのは銀糸の刺繍装飾が入れられた、目も覚めるような鮮やかな青のドレス。王女の正装衣装だ。
王女の気が触れたのではないか――。
女官の顔はそう言っていた。私自身、あまりの衝撃に口が利けなくなった。
「誰も行かなくて穴を開けるよりはましでしょう?」
「お言葉ですが殿下……」
「ぐずぐずしない! 私が行かなかったら、お前の解雇は間違いないのだから!」
女官はためらいながらも王女の命令に従った。命令となれば私も逆らえない。有無を言わさずドレスを着せられ、肩章と勲章をつけられた。
アナスタシア王女の金髪と同じ色の鬘をかぶせられ、その上には銀色の宝冠、耳と首も、青い宝飾で飾り立てられた。最後に化粧を施すと、女官が驚きの目で私を見た。
「ヒールの低い靴をはけば、私と同じ身長なのね。これは驚きだわ」
私たちは体型もよく似ていた。まるで合わせ鏡のように。
シルエットだけなら、王女を日頃よく見ている女官ですら見間違えてしまうほどに。
アナスタシアは私が脱いだ服を着た。
「ふふふ、王子とこじきね」
「殿下、いたずらにもほどがあります」
私は完全に困惑した。王女の気まぐれに? それとも身長と髪の色をのぞくと、私たちがあまりにも似すぎていたことに?
理由がわからないことに、頭は混乱した。
「あら、陛下は意外と冗談がお好きなのよ。ばれたとしても、こういった趣向をお喜びになるかもしれないわ」
アナスタシアは小姓の身軽な服装を楽しんでいた。
彼女は本気だった。本当に私を身代わりとして王室劇場に行かせてくれようとしていたのだった。
そのとき、私は心から彼女に感謝した。
このことが露見したらどうなるかまでは考えなかった。国王に会ったらどう言い訳するのか、それがどんな大罪になるのか、そんなことはすっかり吹っ飛んでしまっていた。
舞台に立ったアナイ・タートの歌が聴ける。そのことで私の胸は躍った。
アナスタシア王女は私の腕をつかんで言った。
「大公夫人の出番は後半だから、まだ十分間に合うわ。私の警護兵はリトヴィスの人間よ。アルトランディアの軍人より腕が立つっていうんでつけてもらっているんだけど、アルトランディア語は話せないの。お前、リトヴィス語はできるんでしょうね」
「できます。勉強しましたから」
アナスタシアはふっと笑った。その笑い方にほんの一瞬、アナイ・タートの微笑が重なった。
「殿下、ご厚意にどうお礼を言っていいのかわかりません。ですが、どうして……」
「王女としての義務を果たすだけよ」
「義務……ですか?」
それは普段の王女らしくない物言いのように感じた。
「プショーク、私は気まぐれなのよ。二度目のきまぐれは期待しないことね」
アナスタシア王女は猫のように笑った。
「行くがいいわ。大公夫人はあなたの――なんだから」
女官に気づかれないよう、耳元で囁いた彼女の言葉に私は思わず振り返った。
私には彼女にその言葉の意味を問い返す暇はなかった。
王室劇場に到着した国王陛下がなかなか到着しない王女に業を煮やし、使者をよこしてきたのだ。馬車も止まっていた。
早足で正面階段を駆け下りる私に王女は叫び続けた。
「風邪だの体調が悪いだの、理由をつけて早く帰ってくるのよ! 晩餐会まで居残らないように! なにかあったら、叔父様――サルティコフ大公を頼りなさい。彼なら助けてくれるわ。馬車の中にネコ用のケーキをとっておいたの。お腹すいたら食べなさい」
頷きながらも私は王女の言葉があまりにも自然にわかることに驚いた。彼女はいつからかアルトランディア語で話していたのだった。
とてもきれいなアルトランディア語だった。
「サーシャ!」
最後に、彼女は私の名前を呼んだ。その声が、心に突き刺さった。
彼女は私の本当の名前を知っていたのだ。
「無事に帰ってきたら、……大公夫人の歌がどうだったか、聞かせてちょうだい」
その一言でわかった。アナイ・タートの歌を聴きたいのは、王女も同じだった。
二階の階段の手すりから身を乗り出した王女は青い、大きな双眸を細め、微笑んだ。
胸が切なくなるほどの、美しい笑顔だった。
「まあ、無事に帰ってこられなかったら、そのときはそのときね。でも忘れないでちょうだい。私があなたを行かせるのは、あなたが至宝だからよ」
リトヴィス人の女官に不審がられないように、王女は早口で言った。
私の背後から、歌が聞こえた。
それは国王賛歌だった。
どんな気持ちで彼女が歌ったのかわからない。私への餞別だったのかもしれない。
この時点で、彼女は二度と会えないことを理解していたに違いない。リトヴィス兵から、彼女になんからの情報が言っていた可能性もある。
彼女は、ある種の覚悟を決めていた。
――アルトランディアのものを好きだなんて、言えるはずがないじゃない。
ただあのときは、その後に起きることなど知らなかった。
王女の意外なやさしさを不思議に思っていた。
アナイ・タートの歌は王女も聴きたかったはずだ。アナイ・タートの舞台を心待ちにしていたのは王女も同じだったはずなのに、なぜ譲ってくれたのだろう。
理由はわからなかった。わからなかったけれど、王宮に戻ったら、王女と話をしたいと思った。アナイ・タートの舞台の話だけじゃない。もっとたくさんの話を。
王女相手におこがましいのだけれど。きっと、私たちは何か、わかりあえるのではないか、最良の友達になれるのではないか――そう思った。
リトヴィス兵の護衛がついた馬車に乗り込み、私は王室劇場に向かった。
それからのルートは、アナスタシア王女を演じていたヴィーカが話したのと同じだ。
建物は王宮の内部にあるのに、馬車で行くのもおかしいけれど、式典の際には馬車で王宮の外壁を一周し、劇場の正面入口から入る慣習があった。
私は馬車の中で息を潜めた。リトヴィス兵には幸い、身代わりは気づかれなかった。
突如、何かの爆発音のようなものが聞こえ、馬車が止まった。王室劇場の方向から煙が上がり、暴徒が押し寄せてくるのが見えた。
御者が逃げ惑う人を呼び止めて話を聞いた。
「王女殿下、反リトヴィス派の民衆によるクーデターです!」
扉を開けた憲兵は、理性を失った群集に頭を砕かれ、絶命した。
それからのことはほとんど覚えていない。
警備兵の一人が御者台に座り、剣と小銃を振りかざしながら活路を開いた。もう一人の兵は私を庇って死んだ。
王女の馬車にリトヴィスの旗が掲げられていたため、標的となったのだ。
リトヴィス大使館に逃げるか、あるいは一日馬車を駆ってリトヴィス国境に行くか、馬車を飛ばしながらリトヴィスの兵たちは話し合っていた。
だが、行ってどうなる?
私はアナスタシア王女ではない。何より王宮に残った本物の王女の安否が気がかりだった。
逃げるには王宮の馬車は目立ちすぎる。私たちは馬車を捨て、河畔沿いに走り続けた。
警備兵が別の馬車をさがしに行くと言い、私を木陰に残して去っていった。
私は警備兵を待たず、その場を離れた。
重い宝冠もドレスも脱ぎ捨て、ペチコート姿になった。逃げ惑う人の流れに逆らい、王宮に向かおうとしたが、無駄だった。
王宮は燃えていた。王宮だけではない。その火は飛び火し、千年の歴史を誇る、王都が炎上していた。王宮に近づくことなどできなかった。
――なにかあったら、叔父様――サルティコフ大公を頼りなさい。彼なら助けてくれるわ。
王女の言葉だけがたよりだった。サルティコフ大公は、ユヴェリルブルグの領主。
そうだ。ヤローキンとも約束していた。そこで再会すると。
あとは無我夢中だった。
どうやって逃げたのかわからない。気がついたときには、国境のユヴェリルブルグに来ていた。
→(次回)「青の緞帳が下りるまで #36」(第十一章 最後の歌 1)
ありがとうございます。いただいたサポートは活動費と猫たちの幸せのために使わせていただきます。♥、コメントいただけると励みになります🐱
