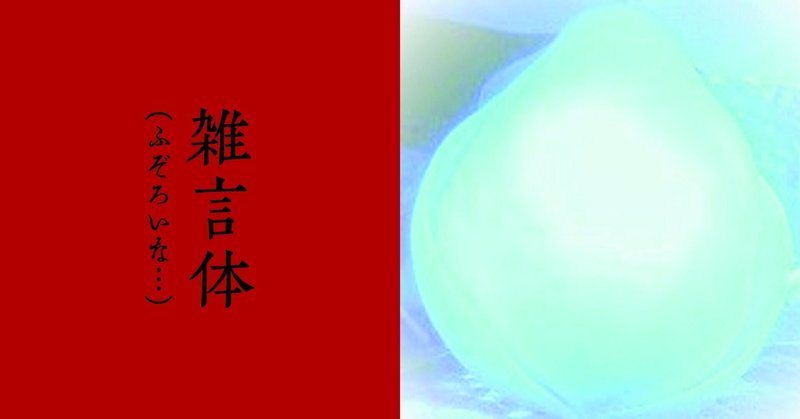
05|『同志社美学』第19号のこと
2023年3月1日/記
(敬称省略)
1973年、当時の私は工学部から転部して文学部文化学科の美学専攻の学生になっていた。ある日、専任講師の中村敬治から『同志社美学』の編集を頼まれた。美学専攻学生の公式の雑誌であり、なぜ転部した私が依頼を受けたのか、それにはあの時代独特の事情があったのである。
美学への転部
その数年前、たぶん1969年、工学部の事務所を占拠するということで、なぜか駆り出された。ヘルメットを被って事務所に突入した光景だけは憶えている。その直後に、美学の活動グループが集会を開いているというので、なぜか乗り込んで議論した。「なぜか」「なぜか」と続くが、50年も前の話なので、記憶がマダラなのである。ともかく、そこで初めて出会ったのが美学の学生たち、そして講師の中村敬治、車椅子の大学院生の木下長宏であった。(のちに中村は美術評論家、木下は美術史家として名をなしている)。
その後、私が参加したバリケード内の自主講座運動で中村とは接触する機会があった。私たち学生と進歩派教員たちが交流した会議や協力して開いたシンポジウムなどがあって、そうした場で時々会って親しくなったのである。
美学への転部はさらにのちである。工学部では卒業できないことが判明して、担当教授から転部を薦められ、少しは縁のある美学を希望した。美学の主任教授の面接を受け、「どんな作家が好きか?」と聞かれ、「ポロックとか」と答えると、教授は「ああいうのがダメなんだ」と言う。彼はシラーの専門家だった。けれども転部を許してくれた。
まるで『ゐまあごを』別冊
そんな訳?とそんな成り行きで、『同志社美学』の編集をまかされたのである。その結果、学生のものとはいえ、学術系としては異色の雑誌になってしまった。学術系雑誌は堅苦しいのが定番だから、表紙からしてすでに異例であろう。色っぽいポスターに本物の蜂がたかっているところを撮影した、私の写真作品である(図1)。内容は目次のとおり4人の執筆で、内3人が『ゐまあごを』(注1)メンバーだから、まるで『ゐまあごを』別冊である。塚本青史は例のイラストと文章の交差する作品、勝木雄二は「マゾヒズムの彼岸」という、きわどい論文。ん?、彼らが執筆しているということは、二人とも美学専攻だったのか。すっかり忘れていた。


私の執筆は、「メディア革命論の難問(アポリア)」であり、ベンヤミンやエンツェンスベルガーなどの理論を取り込んだ学術的論文(図2)である。ただ、タイトル表紙の半分に青柳祐介の漫画のどぎつい場面を引用するなど、やはり挑発的側面が出張っている。
私の転部を許可した主任教授はカンカンだったと思うが、私に何も言ってこなかった。中村講師に苦情が集中したと推測するが、盾になってくれたのではないか。彼には在学中はもちろん、卒業後もお世話になった。また、私には鈍感なところがあり、自分では気がつかないまま、ずいぶんと迷惑をかけたように思われる。本当に感謝と謝罪しかない。
(注1)『雑言体』03|ジャンル横断雑誌『ゐまあごを』を参照。
第19号「後記」
後記に編集方針を書いているが、当時の空気をよく表していると思うので再録しておこう。
※ この雑誌は三頭谷鷹史、勝木雄二、塚本青史の編集によるものである。
※ 一切の題材を自由とした。各自の論文の背後、その政治的・文化的運動はここではひとまず問うことを断念した。
※ 形式的には美学学生による美学科機関誌という規定をふんだ。
※ この雑誌への参加呼びかけは口コミ、掲示板への表示に限られた。
※ 郵送されてきた岡林洋君の論文「乞食の美学」は編集者によってかってに編集した。
※ 一切の費用は文化学科からおりて来る。すなわち同志社大学の制度に寄生するものである。
(文責 三頭谷)
たまたまだが
「制度に寄生」とか、今なら嫌みにしかならない言い方だが、自分の挫折や妥協に対する自責の念と抵抗感の表明だったと思う。岡林論文「乞食の美学」は、そのタイトルから『ゐまあごを』と同類のようにも見えるが、まったく無関係であり、郵送で来たから、本人とは会っていない。
数年前、ネットで同志社大学の美学教授に同姓同名の人物を発見した。その人は当時美学に在籍していたようだから、おそらく本人であろう。そうすると「同志社美学」19号の執筆者は、目次順に小説家、美術評論家、グラフィック・デザイナー、美学教授であり、全員が美学と関わりのある分野に生き残った?ということになる。たまたまそういう結果になったのだが、編集責任者としては、ちょっと嬉しい。(了)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
