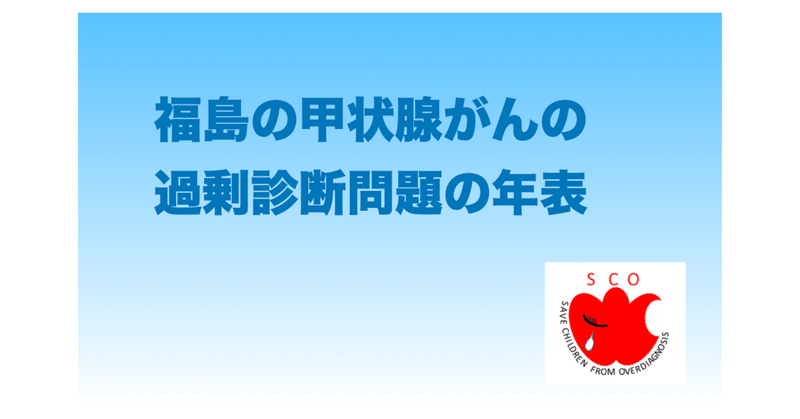
福島の甲状腺がんの過剰診断問題の年表
私たちが今まで作成したNoteや「福島の甲状腺検査と過剰診断」(あけび書房)「みちしるべ、福島県甲状腺検査の不安と疑問に応えるために」(POFF)に基づき、これまでの経緯を年表として簡単にまとめてみました(敬称略)。
2011年 甲状腺検査開始
・3月11日 東日本大震災
・10月9日 1000億円の予算をかけて福島県民健康調査が計画され、甲状腺超音波検査が始まる。
2012-13年 問題が発覚
・このころから当初の予想に反して甲状腺検査で多数の甲状腺がんがみつかるようになる。
2014年 専門家たちの見込み違いの発覚と過剰診断の議論
・検査に関わった専門家らは1巡目の甲状腺がんの多発見について、「スクリーニング効果」であると説明していたが、2巡目の検査でも多数の甲状腺がんが見つかったことにより矛盾が生じるようになる。
・甲状腺評価部会において渋谷健司・津金昌一郎が過剰診断が起こっている可能性について言及。
2015年 過剰診断への取り組みを開始
・菊池臣一福島医大学長の指示により、外科の鈴木眞一に代わり、大津留晶・緑川早苗が甲状腺検査の責任者となる。
・大津留晶・緑川早苗は過剰診断の被害を軽減できるように、検査そのものや住民への説明のやり方を改善する方法を模索する。
2016年 福島県の姿勢の変化
・8月、福島小児医会が甲状腺検査の見直しの要望書を県に提出。県の専門家会議では議論されず。
・9月の国際専門家会議において大津留晶・緑川早苗が福島県の甲状腺検査で過剰診断とスクリーニングの不利益があることに初めて言及。
2017年 過剰診断問題への取り組みに対する抵抗
・菊池臣一が(2017年3月)退任する 。
・4月、日本内分泌学会において大津留晶・緑川早苗が福島県の甲状腺検査で過剰診断と心理社会的影響について言及 。
・これ以降、福島県・福島医大・環境省から検査担当者に、住民に対する説明で「過剰診断」の文言を入れることや検査の被害を説明することを抑制するように指導が入るようになる。
・福島県・環境省が「甲状腺検査が開始されたことは正しい判断であり、これからも継続すべきである」とする文書を関係施設に配布。
2018年 海外の専門家たちの見解 県の専門家会議での最後の議論
・WHOのがん専門部会であるIARCから「原発事故後であっても甲状腺スクリーニング検査は推奨しない」とする提言が出される。
(https://www.env.go.jp/chemi/rhm/post_132.html)
・髙野徹・祖父江友孝が甲状腺検査の改善案(髙野―祖父江提案)を甲状腺評価部会に提出。 (https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/295104.pdf)
議論は紛糾し、改善は住民に対する説明文書の改訂のみにとどまった。
・改訂された説明文書では過剰診断という用語は使用されておらず、IARCの提言内容も紹介されていない。
(https://note.com/mkoujyo2/n/n740dfe34d227)
・これ以降、甲状腺評価部会では検査体制に対する議論は行わないとする方針が出される。
・日本甲状腺学会が専門医試験受験者に対する公式のテキストである「甲状腺専門医ガイドブック」で、福島県の甲状腺検査について、「甲状腺がんの患者が増えているのはスクリーニング効果またはハーベスト効果であり、過剰診断・過剰治療は発生していない」と明記。この内容は現在まで改訂されていない。
2019年 福島医大の体制の変化
・過剰診断への取り組みに積極的であった大津留晶・緑川早苗が甲状腺検査の担当から外される。
2020年 過剰診断問題を解決しようとする新たな動き
・国連UNSCEAR2020/2021の報告書が出され、「福島で甲状腺がんが増加しているのは過剰診断の可能性」と明記される。
(https://www.unscear.org/docs/publications/2020/UNSCEAR_2020_21_Report_Vol.II_JP.pdf)
・音喜多駿が参議院で福島の甲状腺検査にともなう過剰診断について質問。これに対して環境省は新たな対応は示さず。
・大津留晶・緑川早苗が過剰診断の被害者を救済するためのNPO法人、POFFを設立。(https://www.poff-jp.com)
・大津留晶・緑川早苗が福島医大を退職。
・大津留晶らが若年者の甲状腺がんの問題に取り組むための若年型甲状腺癌研究会(JCJTC)を設立。(https://www.med.osaka-u.ac.jp/pub/labo/JCJTC/index.html)
・渡辺康平が福島県議会において甲状腺検査にともなう過剰診断について質問。これに対して県は新たな対応は示さず。
2021年 専門家たちの強い抵抗
・IARCのメンバーであったジェリー・トーマスが福島医大に招待されてシンポジウムで講演し、IARCの提言を改竄して報告。
・同シンポジウムで福島医大の教授らが福島で実施されているのはスクリーニングではなくモニタリングであり、IARCの提言に沿っている、と主張。(https://note.com/mkoujyo2/n/n7a53db6186f8)
・緑川早苗が編集担当となり日本甲状腺学会雑誌「過剰診断を考える」が発行される。福島県の甲状腺検査に伴う健康被害を懸念する論文が複数掲載された。(https://note.com/mkoujyo2/n/na1399764d049)
・日本甲状腺学会が「過剰診断を考える」の内容は学会の一部の意見でしかなく、過剰診断に関しては既に取り組み済みで、学会としては検査を支援する、という旨の広報を出す。 (https://note.com/mkoujyo2/n/ncbcc9980b2d3)
・日本甲状腺学会理事会が福島県の甲状腺検査に関する特集号を緑川早苗らの雑誌編集委員会に諮らずに発行し、「過剰診断は対策済み」「福島において過剰診断と思われる例はほとんど無く、通常の臨床癌のみが治療されていた」とする論文が掲載された。 (https://note.com/mkoujyo2/n/n2f29557bdff9)
・髙野徹が日本甲状腺学会理事会に、福島の過剰診断問題に関する開かれた議論をすることを提案するが理事会は無回答。 (https://note.com/mkoujyo2/n/ne706ca944dac)
2022年 過剰診断問題に背を向ける行政と学会
・福島医大が主催した日本小児科学会でジェリー・トーマスが再び招待されてシンポジウムで講演し、前回と同様にIARCの提言を改竄して報告。 (https://note.com/mkoujyo2/n/n0e6a99c021c2)
・日本内分泌甲状腺外科学会雑誌に「福島の甲状腺検査に関して過剰診断であるという意見があるのは迷惑だ」「過剰診断、という言葉は誤診の意味で使うべきであり疫学者は用語の使い方を間違えている」とする福島県民健康調査に参加した専門家たちの論文が掲載される。(https://www.jstage.jst.go.jp/article/jaesjsts/38/4/38_265/_pdf)
・山口壯環境大臣が記者会見で過剰診断問題に対する姿勢を問われ、「過剰云々は自分の関知するところではない」と回答し、省としての関与を明確に拒否する。
2023年 深まる住民と専門家の間の溝
・SNSで過剰診断問題を無視する福島県・福島県立医大・学会の姿勢に対する批判が相次ぐようになる。
・福島の漫画家,端野洋子が講談社で「俺の初恋の人が兄とフラグを立てまくってつらい」の連載を開始。主人公は福島県民健康調査で甲状腺がんの診断を受けた高校生との設定。「(主人公は)過剰診断の被害者だ。」「検査を始めた医者がその害を認めるはずがない。」福島医大に対する批判的な発言が見られます。
・12月、日本甲状腺学会学術集会が開催される。この場で学会理事会は過剰診断問題についてのオープンな議論の場を求める学会員の声に応えることはなく、むしろ山下俊一、志村浩己ら検査を推進してきた専門家たちの講演がいくつも企画される。彼らが福島の甲状腺検査の正当性を会員に対して主張した。
こうやってまとめてみると、過剰診断問題の解決の足を引っ張っているのは、一般に言われているような「市民らの反対」ではなく、むしろ検査を計画した行政や専門家たちであることがわかります。この問題では、始めてしまったことは止められない、日本の医療行政の悪い一面が典型的に出ているように思えます。
