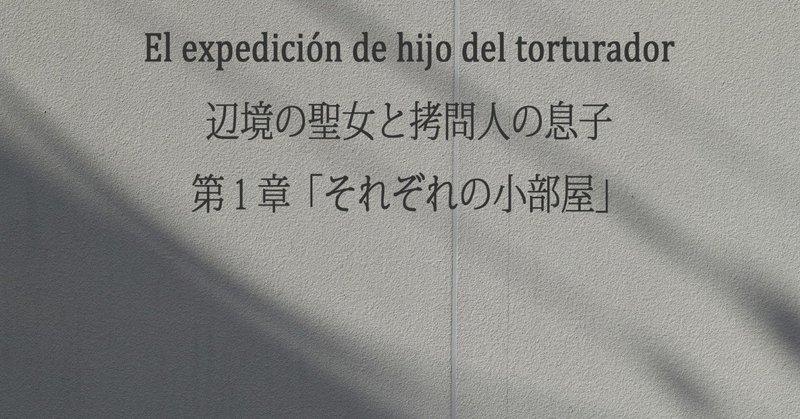
El expedición de hijo del torturador 辺境の聖女と拷問人の息子 第1章「それぞれの小部屋」
メルガールとヒメネスのブリキの小部屋
夜の手前、昼が終わるころ、空はゆるやかに明るさを失い、とらえどころのない暗闇がにじむように広がっていく。
川岸の船着き場にもやわれた、銀色の小屋のようにもグァグァ(乗り合い自動車)のようにもみえる物体を目指し歩きながら、メルガールはヒメネス枢機卿の新し物好きが加速していることに愚痴をこぼし、ぼやく聖職者たちを思い出していた。
なるほど、これほどまでとはな。
ただ、メルガール自身は特に目くじらを立てることのように思えなかったし、むしろ畏れにも似た奇妙な敬意すら感じていた。
桟橋で待っていたのは、革頭巾に風除けメガネという不思議ないでたちの聖職者で、彼が翼(アラ)と称する小屋から突き出した銀色の板に乗り、その先にある扉をくぐったところで猊下がお待ちだという。みると、物体は川面から突き出したやぐらに乗っかっており、細かいひだが施された銀色の板を少しのぼったところに、下を斜めにそぎ落とされたいびつな扉が開いている。
「翼というが、この板も鳥のそれと同じということか?」
「さようでございます。ただ、鳥の翼とは異なり、人間を乗せられます」
いささかいんぎんな口ぶりのように聞こえなくもなかったが、そんなささいなことを気にするほど肝を冷やしているのかと、自分ながら情けなくなる。いやいや、そこまで器の小さい人間ではないはずだと、仕方なくメルガールは踏み台をのぼって翼というか、銀色の板へ足を乗せた。
その瞬間、かすかではあるものの、全体がふわりと傾くような気がする。
「これは、川舟のようなものか?」
「そういうものと思っていただいて結構です。窓の下にも踏み台が続いていますから、そこへ足をかけてください」
いわれてみると、たしかに足がかりのような突起がいくつかあった。慎重に一歩、また一歩と進み、ようやく扉までたどり着くと、頭を低くして中へ滑り込む。薄暗い室内にはベンチのようなソファがあり、とりあえずそこへ腰をかける。すると、前からヒメネス枢機卿の声が聞こえた。
「座り心地はいかがかな? メルガール君」
「は……猊下……まだ腰かけたばかりですので」
ヒメネス枢機卿が『掃除』の話をするときは、決まって最初になにか突拍子もないことを言うし、メルガールも切り返しを考えてくる。だが、今回もまた当たり障りのない言葉を返すのが精一杯だった。
「はは、たしかにそうだ」
猊下との儀式めいた受け答えを済ませ、落ち着いてあたりをながめると、前にソファのような丸みを帯びた椅子がふたつならんでおり、メルガールの右側に枢機卿の後ろ姿がみえる。窓枠にはカーテンがあり、枢機卿が座る椅子の正面には、黄色い花を生けた花瓶まで飾られていた。
「お背中からお声をかけさせていただいておりますが、このままでよろしゅうございますか?」
儀式などの際、高位聖職者へ後ろから耳打ちすることが全くなかったかと言えば、決してそんなことはないのだが、それにしても気まずいというか、どうにもやりにくかった。とはいえ、馬車か客車のコンパルティメント(仕切り部屋)程度の広さでは、この位置関係でもやむを得まい。
「かまわぬ。そもそも、余が望んでおるのだ」
ただでさえ枢機卿の低い声が、背中越しに聞くことでくぐもったような調子まで帯びていた。
「承知いたしました。しかして、なに用でございましょうか?」
呼び出されたときから『掃除』の話であろうと予想していたが、余人を遠ざけるにしても場所が凝りすぎているし、表情も全く読み取れない。言葉が聞きとりにくいことも合わせ、メルガールはいつになく緊張を強いられていた。
「治安憲兵の将校だった、ホルヘ・コルトという男がおる」
「名前だけは聞いたことがあります。軍人だった地球人(テリンゴ)ですね。巡回審問の護衛でしたが、辺境遠征での不始末を恥じて逐電したかと」
「あの辺境遠征ではな、治安憲兵が二~三〇人ほど邪教徒に首をはねられておる。だが、その責めを負わされたのはコルト『ただひとり』だった」
相変わらず表情こそ読み取れないが、声の調子がかすかに変化したことは、メルガールの注意を引くのに十分だった。ひと呼吸おいて、枢機卿は再び話し始める。
「治安憲兵の査問を拒んだコルトは鋸歯魚の庭(ハルディン・デ・ピランハス)一帯へ逃げ込み、野盗の頭目におさまっていたらしい。だが、最近では辺境の聖女と行動を共にしているという」
「辺境の……聖女……」
言葉を押し殺してもなお、うめくような声が漏れてしまう。
「昨日、かの地を治める『大佐』からの使者が、付近の審問院へ急を知らせたらしい」
にわかには信じがたい話だったが、ここで疑義を口にしてもろくなことはない。情報の不足はこちらで補い、猊下の意図を先回りして実行、実現する。それが、枢機卿の手足となって働く者に求められる心得のひとつであった。
ともあれ、最も厄介ではないにしても、楽ではない『掃除』だ。問題は処分する相手がコルトか、辺境の聖女か、あるいは両方か?
正直なところ、ひとりで聖女を相手にするのは、いささか荷が重かった。
「猊下、掃除するのはテリンゴですか、それとも」
「コルト『ただひとり』でよい」
「御意」
「鋸歯魚の庭は、聖なる処女信仰が根強く生き残る土地ではある。だが、頭目のコルトを失えば、他は烏合の衆にすぎない。ただ、そのような土地柄ゆえに、辺境の聖女については手間をかけざるをえまい。かの地へはいずれ巡回審問も派遣するが、その下準備に軽く掃除しておきたいのだ」
「かしこまりました。もし、可能であればパレハ(相棒)をともなってことに当たりたいのですが、いかがでしょう?」
ごくわずかだが、枢機卿が肩をすくめたような気がした。メルガールはつまらんことを言ったかと、なかば叱責にそなえるかのごとく身を固くする。だが、この掃除は酔いどれ破戒司祭を処分するのとは、いささかわけが違う。やはり、パレハを求めるに足る難しさではないかと、思いなおした。
「わかっておる。エル・スプランタドール(なりすま師)。だが、こたびは相手が違う」
メルガールの顔が渋くなる。
仲間内、それもパレハを務めた相手ならともかく、まさか枢機卿からあのふたつ名で呼びかけられるとは!
そもそも、そのふたつ名が猊下のお耳に届いていたこと自体、メルガールには恥ずべきことだった。
「辺境の聖女が関わるゆえ、残念ながら非神子は君ひとりでなければならない。メルガール君は他の非神子をパレハとし、たとえば入れ替わるなどすることで相手を幻惑させているようだな。そこで、今回は辺境の聖女と入れ替わってもよいのではないかと思う」
まず、非神子とは旧帝国の失われた奇跡術を用いて創出された人造人間を素体とし、帝国世界で死亡した霊を転生させた不老難死の超越者である。伝説によれば、人として顕現した名づけられざるものの妻が、時に人間と交わって子供を産み落とすことがあり、それを模して創りだされたとされる。
ほぼすべての素体は少女で、男性は伝承の中にしか登場しない。また、すべての素体は基本的に同じ姿形なので、外見から個人を識別することは非常に困難である。そのため、非神子であるメルガールは、特に困難と思われる任務に際しては、他の非神子と組んでことに当たるようにしていた。また、非神子は身体こそ非力な子供程度だが、奇跡能力は極めて高く、さらに睡眠と食事、排泄が不要で疲労もしないため、結果として人間離れした活動が可能となる。いずれにせよ、メルガールは同じ顔や姿の者がふたりいることをうまく利用して、難しい仕事もそつなくこなしていた。
そして、黄印の兄弟団が深刻な脅威とみなす辺境の聖女もまた非神子であり、メルガールなど兄弟団によって転生されたものと表裏をなす、宿敵のような存在だった。
「かしこまりました。ただ、辺境の聖女になりすますとしても、彼奴に同行しております土曜男爵(バロン・サバド)はいかがしましょうか?」
「君ほどの力量であれば、従属させられるであろう。黒い仔山羊の亜種と考えられるからな。願訴人はエル・ディアブロの息子。エル・イーホを使うがよい」
その時、枢機卿が自分に背を向けている幸運を、メルガールは心の底からかみしめた。もし顔が見えていたら、怒りと恐怖で明滅する信号灯めいたメルガールの動揺ぶりに、痛烈な皮肉が飛んできていただろう。だが、わずかにメルガールが言いよどんだすきに、枢機卿は言葉を重ねてきた。
そして、それは極めてまれなことで、メルガールは『猊下が言葉を重ねた』ことそのものに、深く恐れ入ったのである。
「エル・イーホはまだ若く、頼りなく思うのも無理はなかろう。また、せんだっての掃除についても、働きぶりは芳しくなかったようだな。寄せられた報告によれば、だがね」
メルガールはエル・イーホの『逸材ぶり』について記した報告書の文面を、素早く思い返す。
大丈夫『盛って』いない……。猊下の勘気に触れる内容ではないはずだ。
「とはいえ、余がゆえなくエル・イーホを用いんとするわけではない。まず、彼の母親と秘書のメルセデス・イトゥルビデは問題の辺境遠征に加わっており、また鋸歯魚の庭についても土地勘がある。館にはその件に関する詳細な報告があり、あわせてセニョーラ・メルセデス・イトゥルビデから話を聞く必要があろう」
枢機卿の説明はエル・イーホを用いる理由になっていなかったが、それはさておき、さらなる言葉を待つ。
「そして、ここからが肝要なのだが、君が辺境の聖女になりすますからには、両者を区別できる人間が同行せねばならん」
「それがエル・イーホと?」
「さよう。こればかりは余人にゆだねられまい」
枢機卿が指摘したとおりだった。メルガールの素体を用意したのはエル・イーホの父、エル・ハポネスであり、蘇生前の測定値と写真はあの館にある。おそらくは出発前に再び身体を測定し、写真も撮ることとなろう。もし、なんらかの手違いでメルガールが『辺境の聖女として捕縛された』場合、それらの数値と写真のみが『機械化異端審問官(エル・インキシドール・メカニサド)の少佐』であることを証明する。
そして、それらの数値などを管理するのが、エル・イーホということなのだ。どう控え目にいっても不愉快な成り行きではあるが、いずれにしても外部には流出させたくない情報であり、メルガールに選択の余地はなかった。
審問院が辺境の聖女をどのように扱うか?
もちろんメルガールは深く理解している。
辺境の聖女の純潔を奪い、苦痛をもたらすためだけの『贖罪と反省を促す審問』を経て異端判決宣告式(アウト・デ・フェ)でさらしものとなった挙句、ようやく火刑に処されるまでのすべてに、メルガールは立ち会ったことがあるのだ。非神子は頭部を切断されるか心臓を破壊されるか、あるいは焼かれるなどして全身を破壊されない限り簡単には死なない。しかし、だからこそ『贖罪と反省を促す審問』は陰惨を極め、建前としては禁じられている、文字通り禁断の審問であった。
もちろん、自分の身にそのような運命が降りかかることなど、いかにメルガールといえども想像すらしたくなかった。
「ご説明をいただき、すべてを理解しました。猊下のお心に感謝いたします」
謝意を口にしつつ、メルガールは『つまるところ、俺は辺境の聖女へなりすまし、かつ聖女としてコルトを始末せねばならん』のだと、絶望的な覚悟を固めた。確かに、そういう小芝居をするなら始末するのはコルトだけで済むが、むしろ聖女とまとめて闇討ちするほうが楽かもしれなかった。
さて、ほぼ間違いなく猊下の考えを理解できたわけだが、ここでそれを口にするのはさかしらに過ぎないか?
あるいは、親の思いを先取りする子供のごとき無邪気さを装いつつ、あえて猊下の前へ出るように振る舞うか?
しかし、考えを巡らせるまでもなく、枢機卿が念を押した。
「よいか、こたびはいままでと異なり、闇に葬ってはならんぞ。その正反対に、人目につくよう公然と処するのだ。そのためであれば、君が自ら手を下さずともよい。いや、できれば信徒が私刑に処するよう、うまく立ち回ってほしいぐらいだ」
「みせしめ、ですね」
枢機卿はごく軽くうなずくと右手をあげ、会見の終わりを告げる。
「では……」
「着座のまま、手は高くかかげずともよい。他はいつもと同じように、余の後へ続け」
こんなところでも締めの儀はするのだなと、メルガールは妙な気持に襲われた。
「ディオス! レアルタド! イ コンパニェロス!」
「神! 忠誠! そして仲間たち!」
そして、メルガールは座ったまま「ありがとうございました」と一礼し、ブリキの奇妙な小部屋を後にした。
ここから先は
¥ 100
¡Muchas gracias por todo! みんな! ほんとにありがとう!
