
源氏物語 夕顔の巻 概略18(東山にて最後の対面~落馬する源氏 )
・ 同輩の誹りを恐れる右近
右近に「二条院に来ればよい」と言いますと、これからの身の振り方についての煩悶が噴き出したのか、
「私は乳母子で、幼い頃から片時も離れずお仕え申しておりましたのですから、こうして突然のお別れとなっては、私にはもう帰る場所などございませんのです」

「同輩たちにこのなりゆきをどう説明すればよいのか」「皆に何と言われるか考えるだけで辛うございます」
「荼毘の煙と一緒に私も消えてしまいたいと思っておりました」と泣き崩れます。

・ 道理を説くも、更に心細くなっていく源氏
「尤もではあるが、それが世の中というものである」「悲しくない別れなどないのだ」「だがしかし寿命のうちは生きていかなければならない定めだ」「気を取り直して私を頼みとして生きるがよい」と慰めます。

(惟光には泣き言を洩らしっぱなしの源氏ですが、なにがしの院で一夜保護者のようにして過ごしたせいか、右近にはいやに大人ぶって正論で諭す源氏です。女にはとにかく優しいのです。)
とはいえ「そう言っているこの私が生きながらえる気がしないでいる」と崩れていきます。
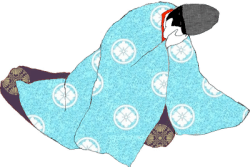
・ 帰途につく
惟光が「もはや明け近くになりましょう」「早くお帰りになられませ」と促します。
源氏は名残惜しく振り返り振り返り、胸の締め付けられる思いで帰途につきました。
道まで涙がちに、朝露にひどく濡れています。
朝霧が濃く、この世ならぬ道を彷徨っているような気がしてしまいます。

見すぼらしい板屋でただ眠っているようにしか見えなかった女の様子が思い出されます。
末期の閨で、鳥が羽を重ね合うような思いで掛けてやった自分の単衣がそのまま掛けられていました。
真っ白に閉ざされた霧の帳の道行に、艶やかな絹の紅色の幻が目に沁みるように浮かんでいます。

・ 落馬
乗馬も覚束ない有様なので、惟光が抱きかかえるように乗っていたのが、
鴨川の土手の辺りまで来ると、意識が遠のいたのか力が脱けて、惟光も支えきれず、鞍からずり落ちてしまいました。
ぼんやりして「こんな出先の路傍で野垂れ死んでしまうのか」「二条院に帰り着ける気がしないよ」などと言うので、惟光も途方に暮れてしまいます。
「いくらおっしゃられても、自分がしっかりして断じてお連れしなければよかったのだ」と後悔します。
惟光は焦燥に駆られて、鴨川の水で手を清め、清水観音の方に向き直って拝みます。

源氏も強いて我が心を励まし、御仏を念じ、惟光の必死の支えを受けながら何とか二条院に帰り着きました。
・ 嘆き合う女房たち
女房達も、若い主人の様子にただならぬものを感じています。
この頃にわかに続いている怪しげな夜の忍び歩きに、
「どうなさったのかしら」「このところ毎晩そわそわとお出掛けだったのが、昨日などは本当にお加減がお悪そうで」「どなたかにお通いなのかしら」「心配だわね」と嘆き合います。

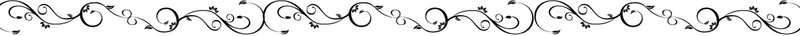
Cf.『夕顔の巻』落馬する源氏
眞斗通つぐ美
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
